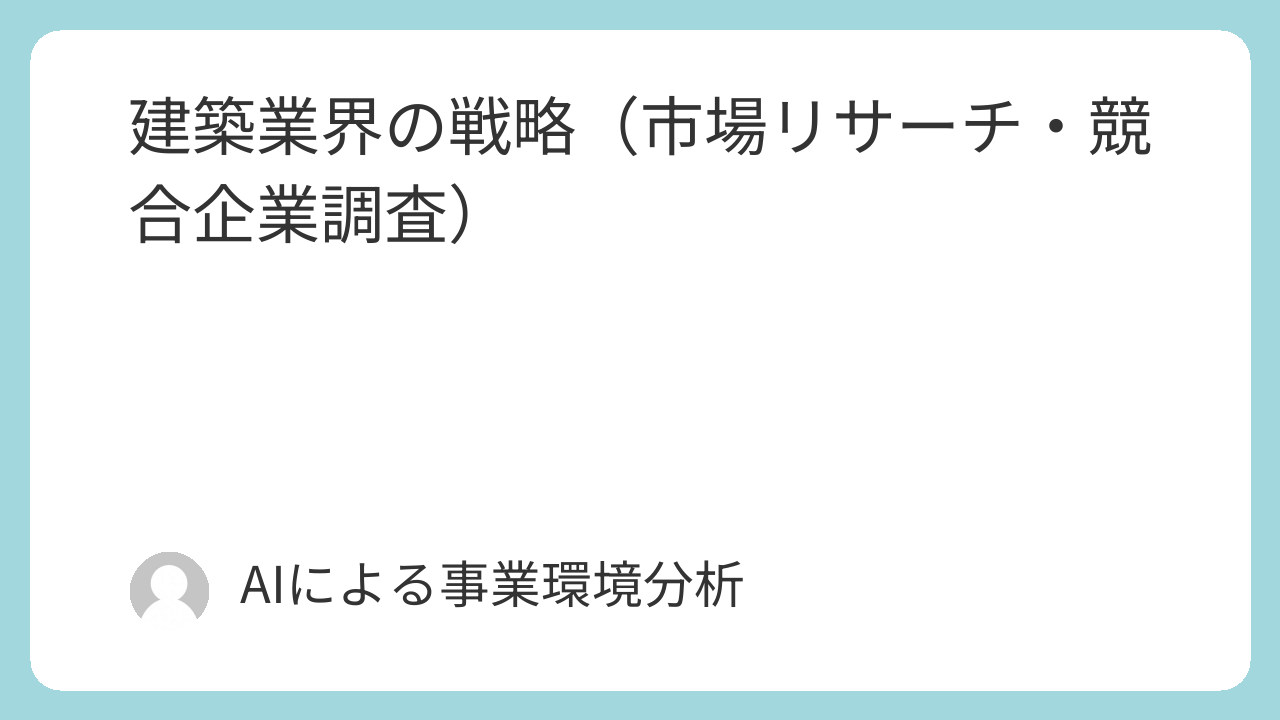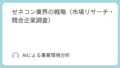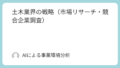デジタルと循環型経済で再構築する、次世代建築ビジネスの生存戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、日本の建築業界が直面する「深刻な労働力不足」「デジタル化の遅れ」「脱炭素社会への移行」という三重の構造的課題を乗り越え、持続可能な成長を実現するための事業戦略策定を目的とする。日本の建築業界は、岐路に立たされている。従来の成功モデルが通用しなくなりつつある中で、新たな価値創造の源泉を見出し、ビジネスモデルを根本から変革することが急務である。
本調査の対象は、ゼネコン、サブコン(専門工事業者)、設計事務所、ハウスメーカーといった伝統的なプレイヤーに留まらない。建材・建設機械メーカー、そして業界構造に変革をもたらす可能性を秘めた建設テック(ConTech)企業までを網羅し、建築ビジネスを取り巻くエコシステム全体を俯瞰的な視点から分析する。
最も重要な結論
分析の結果、日本の建築業界の未来は、従来の「安く、早く、作る」という規模と効率を追求する請負モデルから、「賢く、長く、活かす」というライフサイクル全体での価値提供モデルへと、いかに迅速に転換できるかにかかっているという結論に至った。
この変革を駆動する二つのエンジンが、「デジタル技術による生産性革命」と「サーキュラーエコノミー(循環型経済)を前提としたビジネスモデルの再構築」である。これらは単なる個別テーマではなく、相互に連携し、業界の競争原理そのものを書き換える不可逆的なメガトレンドである。今後5年から10年で、この二つの潮流に適応し、自社のコアコンピタンスとして昇華させた企業が次世代の勝者となり、旧来のモデルに固執する企業は市場からの退場を余儀なくされるだろう。
主要な推奨事項
以上の分析に基づき、持続的な競争優位性を確立するために、以下の4つの戦略的アクションを強く推奨する。
- バリューチェーンの再定義:「ライフサイクル・インテグレーター」への変革
単なる「施工」の請負業務から脱却し、BIM/CIM*データを核として、事業の企画・開発段階から設計、施工、そして完成後の維持管理・運営まで、建築物のライフサイクル全体を貫くデータプラットフォームを構築・主導する「ライフサイクル・インテグレーター」への変革を目指すべきである。これにより、断片的なサービス提供から脱し、顧客の事業価値最大化に貢献するパートナーとしての地位を確立する。- BIM/CIM (Building / Construction Information Modeling, Management): 3次元モデルを中核に、企画・設計・施工・維持管理の各段階の情報を一元化し、関係者間で共有することで業務効率化を図る仕組み。
- サプライチェーンの再構築:垂直統合と水平連携の同時推進
生産性向上の最大の足枷である重層下請け構造の弊害を克服するため、二つのアプローチを同時に推進する。第一に、工場で部材やユニットを生産し現場作業を最小化する「オフサイトコンストラクション」の比率を高め、品質と生産性を直接管理する「垂直統合」を強化する。第二に、信頼できる専門工事業者との間でBIM/CIMデータを共有するオープンなプラットフォームを構築し、透明性の高い「水平連携」を深化させる。 - 「グリーン・プレミアム」の事業化:サステナビリティを新たな収益源へ
ZEH/ZEBや既存ストックのリノベーションを、規制対応のコストとして捉えるのではなく、顧客にとっての「資産価値向上」「光熱費や修繕費を含めたLCC(ライフサイクルコスト)の最適化」「従業員のウェルビーイング向上」といった具体的な経済価値に転換する提案力を強化する。これにより、環境性能を価格競争からの脱却と高付加価値化を実現する「グリーン・プレミアム」として事業化し、新たな収益源を確立する。- ZEH (Net Zero Energy House) / ZEB (Net Zero Energy Building): 年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅・建築物。
- 人材ポートフォリオの抜本的改革:異能人材の獲得と組織能力の再設計
従来の施工管理者や設計者といった専門人材に加え、データサイエンティスト、AIエンジニア、BIMマネージャー、さらにはサーキュラーエコノミーの専門家といった「異能人材」を積極的に採用・育成する。多様な専門性を持つ人材が協働できる組織体制と評価制度を構築し、デジタルとサステナビリティを前提とした新たな組織能力を根本から再設計する。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本の建設投資額の推移と今後の予測
日本の建設市場は、名目上は拡大基調にある。国土交通省や建設経済研究所の予測によれば、2024年度の建設投資額は73兆円台に達し、過去10年で最も高い水準となっている 1。さらに、2025年度には75兆円台、2026年度には79兆円台へと、名目ベースでの成長が続くと予測されている 3。
この成長を牽引しているのは、主に二つの要因である。第一に、政府による「国土強靭化計画」を背景とした安定的かつ大規模な公共事業投資であり、特に2026年度以降の予算拡大が市場に強い追い風となる 3。第二に、企業の旺盛な設備投資意欲に支えられた民間非住宅投資(工場、倉庫、都市再開発など)の堅調な推移である 1。
しかし、この名目上の成長には注意が必要である。建設資材価格や労務費の歴史的な高騰が投資額を押し上げており、実質的な工事量(物量)の伸びは限定的である。建設経済研究所の分析でも、実質値ベースの投資額は横ばい、もしくは微増に留まると予測されており 5、市場は「利益なき繁忙」に陥るリスクを内包している。
表2.1: 建設投資額の見通し(名目値)
| 年度 | 総額(兆円) | 前年度比 | 政府投資(兆円) | 民間非住宅投資(兆円) | 民間住宅投資(兆円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度(予測) | 74.0 | +4.0% | 23.7 | 17.8 | 17.0 |
| 2025年度(予測) | 75.5 | +2.5% | 24.5 | 18.6 | 16.8 |
| 2026年度(予測) | 79.2 | +5.0% | 26.8 | 19.3 | 17.3 |
出典: 建設経済研究所のデータを基に作成 1
セグメント別動向の分析
市場を詳細に見ると、セグメントごとに異なる動向が確認できる。
- 政府投資 vs. 民間投資: 政府投資は、国土強靭化計画(2026年から5ヵ年で大規模予算)に後押しされ、2026年度には前年度比9.2%増と大幅な伸びが予測されるなど、市場全体の強力な下支え役となっている 3。一方で民間投資は、非住宅分野が企業の設備投資意欲に支えられ堅調に推移するものの、住宅分野は資材高や金利上昇への懸念から伸び悩む可能性がある 1。
- 建築 vs. 土木: 国土強靭化計画の恩恵を直接受ける土木分野は安定した需要が見込まれる。建築分野では、非住宅(特に工場やデータセンター、物流倉庫など)の需要が旺盛である一方、住宅は新設着工戸数の長期的な減少トレンドに直面している。
- 新設 vs. 維持・修繕: 人口減少社会を背景に、新設住宅着工戸数の頭打ちが避けられない中、ビジネスの主戦場は既存ストックへとシフトしつつある。老朽化したインフラの維持・更新や、空き家・既存建物のリノベーション、コンバージョン(用途転換)といった維持・修繕市場の重要性が今後ますます高まることは確実である 4。長期的に見れば、この維持・修繕市場が新たな成長領域となる可能性が高い 6。
市場成長ドライバーと阻害要因
今後の市場の方向性を決定づける主要なドライバーと阻害要因は以下の通りである。
- 主要な市場成長ドライバー
- 国土強靭化計画: 災害対策やインフラ老朽化対策を目的とした、中長期的で安定した公共投資 8。
- 都市部の大型再開発: 東京や大阪などの大都市圏で進行中の、オフィス、商業施設、ホテルなどを含む複合的な再開発プロジェクト。
- 企業の設備投資意欲: サプライチェーン再編に伴う国内工場の新設・増設、データセンターや物流施設の需要拡大、企業の脱炭素化・省力化に向けた投資。
- 主要な市場阻害要因
- 深刻な労働力不足: 技能労働者の高齢化と若年層の入職者減少による、供給能力そのものの制約 12。
- 建設資材・労務費の高騰: グローバルな需給変動や円安を背景とした資材価格の高止まりと、人手不足に起因する労務費の上昇が、企業の収益を直接的に圧迫する 14。
- 2024年問題: 働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が、工期の長期化と労務コストのさらなる上昇を招き、企業の競争力に直接的な影響を与える 18。
業界の収益性と主要KPIのベンチマーク
市場が名目上拡大する一方で、業界の収益性は悪化傾向にある。スーパーゼネコン5社の財務データを見ると、その厳しい実態が浮き彫りになる。2023年度決算では、建築事業の完成工事総利益率(粗利益率)は、かつて10%を超えていた水準から大きく低下し、トップの鹿島建設でも9.2%に留まった。特に清水建設は、大型案件での採算悪化が響き、赤字に転落している 22。
この背景には、資材価格や労務費の高騰というコスト増を、発注者への価格転嫁によって十分に吸収しきれていないという構造的な問題がある。受注高自体は各社とも堅調に推移しており、選別受注を進める「売り手市場」の様相を呈しているものの 22、過去に受注した低採算案件の消化が利益を圧迫している。この状況は、単なる売上規模の拡大が必ずしも企業価値の向上に繋がらないことを示しており、厳格なコスト管理と付加価値の高い提案による利益率の確保が、これまで以上に重要な経営課題となっている。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
建築業界を取り巻くマクロ環境は、政治、経済、社会、技術、法規制、環境の各側面から、構造的かつ不可逆的な変化の圧力を受けている。これらの要因は個別に作用するだけでなく、相互に影響し合い、業界の前提条件を根本から覆そうとしている。
政治(Politics)
- 国土強靭化計画と公共事業予算: 政府は、激甚化する自然災害やインフラの老朽化に対応するため、「国土強靭化計画」を推進している。今後5年間で20兆円規模の事業規模が計画されており、公共事業関連予算は安定的かつ継続的に確保される見通しである 9。これは、特に土木・インフラ事業を手掛ける企業にとって、強力な需要の下支えとなる。
- 働き方改革関連法(2024年問題): 2024年4月から建設業にも罰則付きの時間外労働上限規制が適用された。これは、長時間労働が常態化していた業界にとって、ビジネスモデルの変革を迫る最大の規制変更である 19。違反した場合には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるため、遵守は絶対である 19。結果として、労務費の上昇、工期の長期化は避けられず、生産性の抜本的な向上ができなければ企業の収益と競争力は著しく低下する 20。
- ZEH/ZEB補助金制度と標準化政策: 政府は2050年カーボンニュートラル実現に向け、2030年までに新築される住宅・建築物についてZEH/ZEB水準の省エネ性能確保を目指す方針を明確にしている 23。これを後押しするため、国や地方自治体は多様な補助金制度を設けており 25、省エネ建築への移行を強力に推進している。これは、高付加価値な環境配慮型建築の市場を創出する一方で、技術開発やサプライチェーンの変革に対応できない企業にとっては参入障壁となる。
- 空き家対策特別措置法: 2023年に改正された本法は、管理が不十分な「管理不全空き家」に対する行政の指導・勧告権限を強化し、固定資産税の優遇措置を解除できるようにした。これにより、所有者が空き家を放置するインセンティブが薄れ、解体、リノベーション、売却といった市場の流動化が促進される。これは、建設業界にとって新たなビジネスチャンス(リフォーム、解体、不動産活用提案など)の拡大を意味する 29。
経済(Economy)
- 建設資材・エネルギー価格の高騰: 2021年頃からのウッドショックやアイアンショックに加え、ウクライナ情勢によるエネルギーコストの上昇、そして長期的な円安傾向が輸入資材の価格を押し上げている 17。建設資材物価指数は高止まりしており 15、このコストプッシュ圧力は工事採算を継続的に圧迫する最大の経済的リスクである。
- 金利政策の正常化: 長期にわたる金融緩和政策からの転換、すなわち金利の上昇は、二つの経路で建設市場に影響を及ぼす。第一に、住宅ローン金利の上昇は個人の住宅取得意欲を減退させる。第二に、企業の借入コストが増加することで、設備投資計画の見直しや延期に繋がり、民間非住宅投資を冷却化させるリスクがある。
社会(Society)
- 建設技能労働者の高齢化と若年層の入職者減少: これは業界が直面する最も深刻な社会課題である。2024年時点で、建設業就業者のうち55歳以上が約37%を占める一方、29歳以下は約12%に過ぎず、全産業平均(55歳以上31.5%、29歳以下16.4%)と比較して高齢化が際立っている 13。今後10年間で、約4分の1を占める60歳以上の技能者が大量に退職することが見込まれており 12、業界全体の供給能力が根底から揺らぐ「サプライサイド・クライシス」が現実味を帯びている。
- ライフスタイルの変化と新たな建築ニーズ: 新型コロナウイルス禍を経て定着したリモートワークは、オフィスと住宅のあり方を大きく変えた。JLLの調査によれば、ワーカーが最も望む働き方はハイブリッド型であり、経営層も週3日程度の出社を求める傾向にある 34。これにより、オフィスには単なる執務スペースではなく、コミュニケーションやコラボレーションを促進する機能が求められるようになっている 35。CBREの調査では、東京23区の約8割の企業がハイブリッドワークを導入予定であり、余剰スペースを新たな価値創造の場に転換する動きが主流となる 36。住宅においても、仕事部屋や快適な通信環境といった新たなニーズが高まっている。
- 空き家問題の深刻化: 全国の空き家数は過去最高の900万戸に達し、空き家率は13.8%と深刻な社会問題となっている 29。これは、防犯や景観の悪化といった負の側面を持つ一方で、リノベーションによる再生、解体後の土地活用、空き家管理サービスといった、既存ストックを対象とする巨大な潜在市場の存在を示唆している。
技術(Technology)
- BIM/CIM、i-Constructionの浸透: 国土交通省は、2025年度までに公共工事でBIM/CIMの原則適用を目指すなど、建設プロセス全体のデジタル化を強力に推進している 10。3次元モデルを核としたデータ連携は、設計・施工の手戻りを削減し、維持管理段階でのデータ活用を可能にする 39。さらに、2040年までに生産性1.5倍向上を目指す「i-Construction 2.0」では、建設機械の自動化・遠隔操作といった施工のオートメーション化が重点項目となっており 41、生産性、安全性、品質を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めている。
- 建設ロボット、ドローン、IoT、3Dプリンター: 人手不足を補い、危険な作業を代替するため、鉄筋結束ロボットや塗装ロボットなどの実用化が進んでいる。ドローンは測量や進捗管理、インフラ点検に不可欠なツールとなりつつある。IoTセンサーは建物の状態をリアルタイムで監視し、予知保全を可能にする。3Dプリンターは、複雑な形状の部材製造や、将来的には建築物そのものの建設に応用される可能性もある。これらの技術は、従来の労働集約的な建設プロセスを、データ駆動型の工業プロセスへと変革する力を持つ。
法規制(Legal)
- 建築基準法・省エネ法の改正: ZEH/ZEBの標準化に向け、省エネルギー基準が段階的に引き上げられ、2025年度からは全ての新築住宅・建築物への適合が義務化される 23。これに適合しない建築物は建設できなくなるため、設計・施工の両面で高度な環境技術への対応が不可欠となる。
- 建設業法・建設リサイクル法の改正: 建設業法では、働き方改革の観点から著しく短い工期の契約を禁止するなどの改正が行われている。建設リサイクル法も、フロン類やアスベストといった有害物質の有無に関する記載が義務付けられるなど、環境コンプライアンスへの要求が年々厳格化している 42。目標達成に向けた再資源化率のモニタリングも行われており、適正な廃棄物処理プロセスが強く求められる 44。
環境(Environment)
- 脱炭素社会への移行: 2050年カーボンニュートラルという国家目標は、建設業界に二つの大きな変革を迫る。一つは、建物の運用段階でのエネルギー消費をゼロに近づけるZEH/ZEBの実現である。もう一つは、建設(Embodied Carbon)から解体・廃棄に至るまでのライフサイクル全体でのCO2排出量を評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)の視点である。これにより、使用する建材の選定(例:木材の活用)、施工方法、解体後のリサイクル性までが企業の環境性能として問われることになる。
- 循環型経済(サーキュラーエコノミー)への要請: 「作って壊す」リニアエコノミーから、「長く使い、再利用する」サーキュラーエコノミーへの移行は、建設業界のビジネスモデルを根底から変える。建設廃棄物の削減や再生材利用の要請は、設計段階から解体・再利用を考慮する「サーキュラーデザイン」の導入を促す 45。これは、単なる廃棄物処理の問題ではなく、建物を将来の「資源バンク」として捉える新たな価値観への転換を意味する。
これらの外部環境の変化は、業界に対して「統合」と「淘汰」という二重の圧力をかけている。働き方改革関連法は「時間」を制約し、改正省エネ法は「性能」を規定し、そしてBIM/CIMは「情報」の共有を強制する。これらの圧力はすべて、これまで分断されていた企画・設計・施工・維持管理というバリューチェーンの各プロセスを、データを介して統合せよという同じ方向を指し示している。この変化に対応し、プロセスを統合する能力を獲得できた企業のみが生き残り、旧来の縦割り・分業モデルに固執する企業は、コスト増と競争力低下の末に淘汰されることになるだろう。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
建築業界の収益構造と競争環境は、マイケル・ポーターのFive Forcesフレームワークを用いて分析することで、その複雑な力学を解き明かすことができる。特に、労働力不足とデジタル化の波が、従来のパワーバランスを大きく変動させている。
供給者の交渉力(Bargaining Power of Suppliers):強い
供給者の交渉力は、近年著しく強まっている。これは主に二つの要因による。
- 専門工事業者(サブコン)・建設技能者(職人): 業界全体の深刻な人手不足、特に高度な専門技術を持つ技能者の不足は、サブコンの交渉力を飛躍的に高めている 46。元請であるゼネコンは、必要な技能者を確保するために、より高い労務費を支払わざるを得ない状況にある。これにより、サブコン側が利益率の高い案件を選ぶ「選別受注」の傾向が強まり、ゼネコンのコスト管理を困難にしている 48。全国建設業協会の調査では、元請企業の約9割が賃上げを実施した一方、下請企業への労務単価引き上げに応じたのは約7割に留まるというデータもあり、元請と下請の間で価格転嫁を巡る厳しい交渉が行われている実態がうかがえる 49。
- 建材・設備メーカー: ウッドショックやアイアンショックに代表されるように、主要な建設資材はグローバルな需給バランスや為替レートに大きく影響される 17。特定の高性能建材や最新の省エネ設備など、代替が難しい製品を供給するメーカーは、価格決定において強い立場にある。資材価格の高騰分を工事価格に完全に転嫁することが難しい場合、建設会社の利益は直接的に圧迫される。
買い手の交渉力(Bargaining Power of Buyers):強い
買い手、すなわち発注者(デベロッパー、官公庁、個人施主)の交渉力も依然として強い。
- コスト・工期への圧力: 特に民間工事においては、発注者からの厳しいコストダウン要求や工期短縮の圧力が常態化している。複数の建設会社を競わせる入札制度は、価格競争を激化させる主要因である。
- 情報の非対称性の緩和: かつては建設会社が専門知識を独占していたが、インターネットの普及やコンサルタントの活用により、発注者側も情報を得やすくなった。BIM/CIMの導入は、発注者がプロジェクトの進捗や品質をより詳細に可視化・管理することを可能にし、発注者の力をさらに強める可能性がある。
- 官公庁の役割: 公共事業においては、発注者である官公庁が予定価格を設定し、入札参加者の価格競争を促す構造となっている。一方で、近年はダンピング防止や品質確保の観点から、適正な価格での契約を促す動きも見られる。
新規参入の脅威(Threat of New Entrants):中程度
建設業は、許認可制度、莫大な初期投資、実績や信用の必要性などから、伝統的な意味での新規参入障壁は高い。しかし、異業種からの新たな形での参入の脅威は増大している。
- 建設テック企業・IT企業: BIM/CIMプラットフォーム、プロジェクト管理ツール、AIを活用した積算・工程管理サービスなどを提供する建設テック企業が、バリューチェーンの一部を切り出してサービスを提供する形で参入している 50。これらの企業がデータとネットワークを独占した場合、既存の建設会社が単なる下請け的存在になる「プラットフォーマー化」のリスクがある。
- 海外企業: 日本市場の特殊な商慣習や品質要求の高さが障壁となり、海外ゼネコンの本格的な参入は限定的である。しかし、特定の技術(例:環境技術、モジュール建築)に強みを持つ企業が、国内企業との提携などを通じて参入する可能性は否定できない。
代替品の脅威(Threat of Substitute Products or Services):中程度
「建物を新築する」という行為そのものに対する代替品の脅威も、徐々に顕在化している。
- 既存ストックの活用(リノベーション・コンバージョン): 人口減少と空き家の増加を背景に、新築するのではなく、既存の建物をリノベーション(改修)やコンバージョン(用途転換)して活用する動きが活発化している。これは、新築中心のビジネスモデルにとっては直接的な脅威となる。
- 新たな工法(3Dプリンター建築など): 3Dプリンターを用いて建築物を建設する技術は、まだ発展途上ではあるが、将来的には小規模な建築物や特定の部材製造において、従来の工法を代替する可能性がある。コストや工期、設計の自由度といった面で優位性を示せば、脅威度は増すだろう。
業界内の競争(Rivalry Among Existing Competitors):非常に強い
業界内の競争は極めて激しい。
- スーパーゼネコン間の競争: スーパーゼネコン5社は、大規模プロジェクトや技術的に難易度の高い案件を巡って激しい受注競争を繰り広げている。近年は、国内市場の成熟化を受け、不動産開発や海外事業、再生可能エネルギー事業など、非建設分野での競争も激化している。
- 地域建設会社間の競争: 各地域では、地場の建設会社が公共事業や民間の中小規模案件を巡って熾烈な価格競争を続けている。
- 価格競争からの脱却の難しさ: 多くの企業が技術力や提案力での差別化を謳うものの、特に汎用的な建築物においては、依然として価格が発注の決め手となるケースが多い。資材高騰と人手不足というコスト増圧力を背景に、利益を確保しながら競争に打ち勝つことは、ますます困難になっている。
総じて、建築業界は「供給者」と「買い手」の両方から強い圧力を受け、業界内の激しい競争によって利益が削られるという、収益性の低い構造に置かれている。この厳しい環境から抜け出すためには、新規参入者であるテック企業と協業し、代替品である既存ストック活用を新たなビジネスチャンスと捉え、単なる価格競争ではない付加価値(技術力、環境性能、ライフサイクル提案)で差別化を図る戦略が不可欠である。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
建築業界の生産性問題を理解するためには、その複雑で旧態依然としたサプライチェーンと、価値の源泉が変化しつつあるバリューチェーンを深く分析する必要がある。
サプライチェーン分析:分断と脆弱性
建築プロジェクトのサプライチェーンは、多岐にわたる資材の調達と、数多くの専門工事業者の手配が複雑に絡み合う構造を持つ。
- サプライチェーンの構造: プロジェクトは、元請であるゼネコンが全体を統括し、資材(セメント、鉄骨、木材、ガラス、設備機器等)をメーカーや商社から調達する。同時に、基礎工事、鉄骨工事、内装工事、電気設備工事といった各専門工事を一次下請けであるサブコンに発注する。サブコンはさらに二次、三次下請けへと業務を再委託し、最終的に現場で作業する技能者(職人)へと繋がる、長く重層的な構造を形成している。
- グローバルな需給変動と地政学リスクへの脆弱性: 近年のウッドショックや鋼材価格の高騰が示したように、日本の建設資材の多くは海外からの輸入や原料に依存しており、サプライチェーンは極めて脆弱である 17。為替の変動、産出国の政策変更、国際紛争といった地政学リスクは、資材の安定供給と価格を直接的に脅かし、工期の遅延や工事コストの急騰を引き起こす。
- 重層下請け構造がもたらす問題点: 業界の生産性を著しく阻害している最大の要因が、この重層下請け構造である。国土交通省のレポートでも、その弊害が厳しく指摘されている 53。
- 品質管理の問題: 下請けの階層が深くなるほど、元請の管理や指示が末端の作業者にまで行き届きにくくなる。これにより、施工に関する責任の所在が曖昧になり、品質の低下や施工ミスのリスクが高まる 53。
- コストの問題: 各階層の企業が中間マージンを抜くため、末端の作業者に支払われる賃金が抑制され、全体のコスト構造が不透明かつ非効率になる。この構造が、技能者の待遇悪化と若者離れの遠因ともなっている 53。
- 生産性の問題: 各専門工事業者がサイロ化(縦割り化)し、情報伝達が口頭や紙ベースで行われるため、プロセス全体での情報共有が著しく困難になる。BIM/CIMのようなデジタルツールを導入しても、この構造自体が情報の流れを分断し、手戻りや非効率を生む温床となっている 53。
- 労働環境の問題: 元請からの短い工期や厳しいコスト要求のしわ寄せが、最も立場の弱い下位の下請業者に及び、長時間労働や安全管理の不徹底といった問題を引き起こしやすい 49。
バリューチェーン分析:価値の源泉のシフト
建築ビジネスのバリューチェーンは、伝統的に「企画・開発 → 設計 → 調達 → 施工 → 販売 → 維持管理・運営」という線形のプロセスで構成されてきた。しかし、デジタル化とサステナビリティの潮流は、このバリューチェーンにおける価値の源泉を大きくシフトさせている。
- 従来の価値の源泉: かつて、建設会社の競争力の源泉は、主に「施工」段階にあった。すなわち、いかに高品質な建物を、コストを抑え、定められた工期内に完成させるかというQCD(Quality, Cost, Delivery)の達成能力が最も重要視された。
- 新たな価値の源泉へのシフト:
- フロントローディングと設計・施工連携: BIM/CIMの活用により、価値の源泉は「施工」から、より上流の「設計」段階へと移行している。設計段階で施工や維持管理までを見越した詳細なシミュレーション(フロントローディング)を行い、関係者間で3Dモデルを共有することで、施工段階での手戻りを劇的に削減し、プロジェクト全体の最適化を図ることが可能になる。価値は、物理的な建設能力そのものから、BIMを活用した設計と施工を連携させるデータマネジメント能力へとシフトしている。
- ライフサイクル全体を見据えた提案: 建物の価値は、完成した瞬間が最大なのではなく、その建物が利用される全期間(ライフサイクル)を通じて生み出されるという認識が広がっている。そのため、顧客が求める価値も、初期建設コスト(イニシャルコスト)の低さから、光熱費や修繕費を含めたLCC(ライフサイクルコスト)の最適化へと変化している。ZEH/ZEBによるエネルギー効率の向上や、IoTセンサーを活用した予知保全サービスの提供など、建物のライフサイクル全体での価値を最大化する提案能力が、新たな競争力の核となりつつある。
- 「作る」から「活かす」へ: 人口減少社会において、新築市場が縮小する一方で、既存ストックの価値をいかに最大化するかが重要になる。リノベーションやコンバージョンによって既存の建物に新たな命を吹き込む事業や、建物の運営・管理サービスといった下流工程のビジネスの重要性が増している。バリューチェーンは、もはや「作って終わり」ではなく、維持管理・運営まで含めた循環型のモデルへと再構築されつつある。
この価値の源泉のシフトは、建設会社に対して、単なる「請負業者(Contractor)」から、顧客の事業全体を理解し、建築物のライフサイクル全体にわたって価値を提供する「ソリューションプロバイダー」への変革を要求している。
第6章:顧客需要の特性分析
建築市場における競争優位を確立するためには、主要な発注者セグメントのニーズと、その変化を深く理解することが不可欠である。伝統的なQCD(品質、コスト、納期)の重要性は依然として高いものの、それに加えて新たな価値基準が購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)として台頭している。
主要な発注者セグメントとそれぞれのニーズ・課題
- 官公庁(国、地方自治体)
- ニーズ・課題: 国土強靭化計画に基づくインフラの防災・減災機能の強化、老朽化した公共施設(学校、庁舎、公営住宅など)の長寿命化と更新、公共事業のコスト縮減と透明性の確保。
- KBF:
- コストパフォーマンス: 予定価格内での応札と、LCC(ライフサイクルコスト)の低減提案。
- 法令・基準遵守: BIM/CIM原則適用など、国が定める技術基準への完全な対応能力。
- 事業の継続性・信頼性: 災害時にも対応可能な企業の財務健全性と事業継続計画(BCP)。
- 地域貢献: 地元企業の活用や地域雇用の創出。
- 民間デベロッパー(総合不動産会社など)
- ニーズ・課題: オフィス、商業施設、マンション等の開発プロジェクトにおける事業採算性の最大化、テナントや購入者にとって魅力的な付加価値の創出、環境不動産(CASBEE、LEED認証など)としてのブランド価値向上。
- KBF:
- 事業性向上への貢献: 単なる施工に留まらず、企画段階からのコスト最適化や工期短縮に繋がるVE(バリューエンジニアリング)提案。
- 環境性能・ブランド価値: ZEB認証の取得支援や、ESG投資を呼び込むための高い環境性能の実現。
- テナントニーズへの対応: ハイブリッドワークに対応した柔軟なオフィスレイアウトや、先進的なICTインフラの導入提案。
- スピード: 市場機会を逃さないための迅速な意思決定と工期遵守。
- メーカー(工場・研究所)
- ニーズ・課題: サプライチェーン強靭化のための国内生産拠点の新設・増強、製造プロセスの高度化(自動化、クリーンルームなど)に対応した特殊な施設要件、生産活動を止めないための短工期での建設・改修。
- KBF:
- 特殊技術への対応力: 生産ラインの仕様や特殊な環境(例:精密機械、医薬品)に関する深い理解と、それを実現する高度な設計・施工能力。
- 工期遵守の徹底: 生産計画に直結するため、いかなる理由があっても工期を遵守するプロジェクトマネジメント能力。
- 安全性: 稼働中の工場での改修工事など、高いレベルの安全管理能力。
- 情報セキュリティ: 企業の機密情報(生産技術など)を保護する厳格な管理体制。
- 倉庫・物流事業者
- ニーズ・課題: Eコマース市場の拡大に伴う、大規模・高機能な物流施設の旺盛な需要への対応、自動化・省人化設備(マテリアルハンドリングなど)の導入を前提とした施設設計、24時間稼働を支える耐久性とBCP。
- KBF:
- 大規模・短工期施工能力: 広大な面積の施設を、市場投入のスピードを重視して短期間で建設する能力。
- コスト競争力: 開発競争が激しい分野であるため、高いコストパフォーマンスが求められる。
- 将来の拡張性・柔軟性: 将来の自動化設備の更新やレイアウト変更に対応できる柔軟な設計。
- 個人施主(戸建住宅、アパートオーナー)
- ニーズ・課題: 高い資産価値の維持、光熱費の削減(省エネ性能)、地震などの災害に対する安全性、健康で快適な居住空間、ライフスタイルの変化(在宅勤務、高齢化)への対応。
- KBF:
- 信頼性・ブランド: 長期にわたる安心を担保する企業の信頼性とブランドイメージ。
- 環境・省エネ性能: ZEH基準への適合による光熱費削減効果と、補助金活用を含めた経済的メリットの提案。
- デザイン・提案力: 個々のライフスタイルに合わせた、画一的でない設計提案能力。
- アフターサービス: 竣工後の長期的なメンテナンスやサポート体制の充実。
顧客が求める価値の変化:QCDから「E・D・B」へ
伝統的なQCD(Quality, Cost, Delivery)が顧客にとっての基本的な要求事項であることに変わりはない。しかし、それに加え、新たな価値軸として「E・D・B」、すなわち環境(Environment)、デジタル(Digital)、事業継続性(Business Continuity)の重要性が急速に高まっている。
- 環境性能(Environment): 脱炭素社会への移行は、もはや単なるCSR活動ではなく、不動産の資産価値を左右する決定的な要因となっている。ZEH/ZEB認証の取得は、光熱費の削減という直接的な経済的メリットに加え、ESG投資の対象となるか、将来的に売却・賃貸する際の競争力に直結する。顧客は、建設会社に対して、単に省エネ基準を満たすだけでなく、LCC最適化や資産価値向上に繋がるソリューションを求めている。
- デジタル対応(Digital): BIM/CIMの活用は、建設プロセスを可視化し、顧客が意思決定に参加しやすくする。完成後の建物においても、BIMデータは効率的な維持管理の基盤となる。また、スマートビルディング技術やIoTの導入は、利用者の利便性向上やエネルギー管理の高度化に繋がり、建物の付加価値を高める。顧客は、物理的な建物だけでなく、それを支えるデジタルインフラやデータ活用サービスまでを一体として求めるようになっている。
- 事業継続性(Business Continuity, BCP): 頻発する自然災害やパンデミックを経験し、企業や個人は事業や生活の継続性に対する意識を格段に高めている。耐震・免震構造はもちろんのこと、非常用電源の確保、サプライチェーンの寸断に備えた資材調達計画、感染症対策を考慮した空調・換気設計など、不測の事態においても機能不全に陥らないレジリエントな建物への需要が高まっている。
この価値観の変化は、建設会社に対して、単なる「モノづくり」から、顧客の事業や生活に深く寄り添い、長期的な課題解決に貢献する「コトづくり」への転換を迫るものである。
第7章:業界の内部環境分析
外部環境の激変に対し、建築業界の内部環境、すなわち経営資源や組織能力は、深刻な課題と構造的な脆弱性を抱えている。持続的な競争優位を築くためには、自社の強みを再認識すると同時に、弱みを直視し、抜本的な改革に着手する必要がある。
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
業界のリーディングカンパニーが持つ伝統的な強みは、VRIOフレームワーク(Value, Rarity, Inimitability, Organization)で分析すると、依然として有効な部分と、陳腐化しつつある部分が明らかになる。
- 価値(Valuable): 超高層ビル、長大橋梁、原子力発電所といった大規模かつ技術的に複雑なプロジェクトを完遂する総合的なエンジニアリング能力とプロジェクトマネジメント能力は、社会インフラを構築・維持する上で極めて高い価値を持つ。また、官公庁や大手デベロッパーといった主要顧客との長年にわたる信頼関係も、安定的な受注基盤となる貴重な経営資源である。
- 希少性(Rare): 上記のような高度な能力と実績を持つ企業は、スーパーゼネコンをはじめとする一握りの企業に限られており、希少性は高い。
- 模倣困難性(Inimitable): これらの能力は、一朝一夕に獲得できるものではない。数多くのプロジェクトを通じて蓄積された経験、暗黙知、そして「地図に残る仕事」を成し遂げてきたという企業文化やブランドは、新規参入者が資本力だけで模倣することは極めて困難である。
- 組織(Organized): ここに最大の課題が存在する。伝統的な強みを活かすための組織体制は確立されている一方で、その組織がDXやサステナビリティといった新たな価値創造に適応できているとは言い難い。部門間の壁が厚い縦割り組織 55 や、変化を好まない旧来の商慣習が、全社的な変革の足枷となっているケースが散見される。過去の成功体験に最適化された組織が、未来の競争に必要な能力の獲得を阻害しているのである。
この状況は、業界が「ケイパビリティ・トラップ」に陥っている可能性を示唆している。過去の成功を支えた強みが、未来の市場で求められる新たな能力(デジタル対応力、環境技術提案力など)への転換を妨げるというジレンマである。顧客が求める価値が「物理的な施工能力」から「デジタルと人材を統合した課題解決能力」へと質的に変化する中、業界の内部環境はこの変化に全く追いついていない。このギャップこそが、業界が直面する最も根深い問題である。
人材動向:崩壊の危機にある供給基盤
業界の持続可能性を根底から揺るがしているのが、人材問題である。
- 需給の絶望的なミスマッチ: 建設技能者はあらゆる職種で不足しており、有効求人倍率は高水準で推移している。特に、躯体工事を担う型枠工、左官、とび工、鉄筋工の不足は、工事の進捗に直接的な影響を及ぼすレベルに達している 13。
- 歪んだ年齢構成: 建設業就業者の年齢構成は、55歳以上が約37%を占める一方で、29歳以下の若年層は約12%に過ぎない 13。これは、今後10年で労働力の中核をなす熟練技能者が大量に退職し、技術承継が途絶える「2030年問題」が目前に迫っていることを意味する。
- 魅力に欠ける労働条件: 労務単価は近年上昇傾向にあるものの、建設業の男性生産労働者の賃金水準は、依然として製造業のそれを下回っている 13。加えて、全産業平均より年間約230時間も長い労働時間 13 や、週休2日制の未整備といった労働環境が、若年層から敬遠される大きな要因となっている。
- 新たな人材要件への対応遅れ: DXの推進には、BIMマネージャー、データサイエンティスト、AIエンジニアといったデジタル人材が不可欠であるが、これらの人材はIT業界をはじめとする他業界との激しい争奪戦の対象となっている。建設業界が提示できる処遇やキャリアパスは、他業界に見劣りしており、必要な人材の獲得・育成は極めて困難な状況にある。
労働生産性:国際的に低い水準
日本の建設業の労働生産性は、長年にわたり低い水準に留まっている。
- 国際比較・他産業比較: 公益財団法人日本生産性本部の調査によると、日本の建設業の労働生産性(就業者一人当たり付加価値)は、米国の約55%(2020年時点)という低い水準にある 56。時間あたり労働生産性で見ても、OECD加盟38カ国中29位(2023年時点)と、先進国の中で著しく低い 56。
- 生産性向上のボトルネック: この低生産性の構造的な要因は、以下の三点に集約される。
- 長時間労働の常態化: 長い労働時間は、労働者の疲弊を招き、集中力や作業効率の低下に直結する。
- アナログな業務プロセス: 依然として紙の図面や電話、FAXに依存した情報伝達が多く、非効率な手作業や手戻りが多発している。
- 重層下請け構造: サプライチェーン分析で指摘した通り、情報の分断、責任所在の曖昧化、中間マージンの発生といった重層下請け構造の弊害が、プロセス全体の生産性を著しく阻害している。
表7.1: 労働生産性と労働力人口のベンチマーク
| 項目 | 建設業(日本) | 製造業(日本) | 全産業(日本) | 建設業(米国) |
|---|---|---|---|---|
| 時間あたり労働生産性(ドル, 2023) | 56.8 | – | – | – |
| 年間総実労働時間(時間, 2024) | 1,900+ | 1,860 | 1,670 | – |
| 平均賃金(男性生産労働者) | 製造業より低い | 建設業より高い | – | – |
| 55歳以上の就業者割合(%, 2024) | ~37% | – | ~31.5% | – |
| 29歳以下の就業者割合(%, 2024) | ~12% | – | ~16.4% | – |
出典: 日本生産性本部、日本建設業連合会、総務省「労働力調査」のデータを基に作成 13
このテーブルが示すように、日本の建設業は、生産性、労働時間、賃金、年齢構成のすべての面で、国内の他産業や国際的な水準から大きく取り残されている。この内部環境の脆弱性を克服しない限り、外部環境の変化に対応することは不可能である。DXや働き方改革は、単なる効率化のためのツールではなく、企業の生存そのものを賭けた戦略的投資と位置づけ、断行する必要がある。
第8章:AIが建築業界にもたらす影響とインパクト
人工知能(AI)は、建築業界が抱える生産性の低さや人手不足といった根深い課題を解決し、ビジネスモデルそのものを変革するポテンシャルを秘めた破壊的技術である。AIのインパクトは、設計から施工、維持管理に至るバリューチェーンのあらゆる段階に及ぶ。
設計・計画プロセスへのインパクト
AIは、設計者の創造性を拡張し、計画業務の精度とスピードを飛躍的に向上させる。
- ジェネレーティブデザイン(生成AIによる設計): 設計者は、建物の目的、予算、敷地条件、法規制、エネルギー性能などの制約条件をAIに入力するだけで、AIがそれらの条件を満たす何百、何千ものデザイン案(意匠、構造、設備計画)を自動で生成・最適化する。これにより、設計者は従来の発想にとらわれない最適な解決策を短時間で探索できるようになり、その役割はゼロから創造する「デザイナー」から、AIが生成した多様な選択肢を評価し、最終的な意思決定を下す「キュレーター」へと変化する可能性がある。
- BIMデータの自動チェックと積算・見積もり業務の高度化: AIは、BIMモデルに内包された膨大なデータを瞬時に解析し、建築基準法や省エネ法といった法規制への適合性、あるいは部材間の干渉といった設計の整合性を自動でチェックすることができる。これにより、ヒューマンエラーを削減し、手戻りを防ぐことが可能になる。さらに、過去の類似プロジェクトのデータや最新の資材価格データを学習したAIは、BIMモデルから数量を拾い出し、極めて精度の高い工事費の積算や見積もりを自動で行う。これは、積算担当者の業務を大幅に効率化するだけでなく、事業の初期段階における採算性の判断精度を大きく向上させる。
施工プロセスへのインパクト
AIは、建設現場を「経験と勘」に頼る場から、「データに基づき最適化された工場」へと変貌させる。AIsmileyの調査によれば、建設業界では既に、人材不足解消を目的としたAI活用が加速している 52。
- 安全管理・進捗管理の高度化: 現場に設置されたカメラ映像をAIがリアルタイムで解析し、危険な行動(ヘルメット未着用、危険エリアへの侵入など)を検知して即座に警告を発することで、労働災害を未然に防ぐ。また、撮影された映像から建設の進捗状況を自動で判定し、計画との差異を可視化することで、施工管理者は問題の早期発見と対策に集中できる 52。
- 建設ロボット・建機の自律運転制御: AIは、建設ロボットや自動化された建設機械の「頭脳」として機能する。3次元の設計データと、センサーがリアルタイムで収集する現場状況データを基に、AIが最適な作業手順を判断し、複数のロボットや建機を協調させて自律的に作業を行わせる。これにより、24時間体制での無人施工も視野に入り、生産性と安全性が劇的に向上する。
- リソース配分の最適化: AIは、プロジェクト全体の進捗状況、各作業員のスキルと稼働状況、資機材の在庫と納期といった複雑な変数を統合的に分析し、最適な人員配置や資機材の発注計画を立案する。これにより、無駄な待機時間や資材の過不足をなくし、サプライチェーン全体を最適化することが可能になる 52。
維持管理・運営プロセスへのインパクト
建物のライフサイクルが重視される時代において、AIは維持管理業務を「事後対応型」から「予知保全型」へと進化させる。
- 劣化予測と最適な修繕計画の立案: ドローンが撮影した建物の外壁画像や、橋梁に設置されたIoTセンサーから得られる振動データをAIが継続的に分析する。これにより、人間の目では見逃してしまうような微細なひび割れや構造的な劣化の兆候を早期に発見し、将来の劣化進展を予測する。この予測に基づき、AIは最もコスト効率の良いタイミングと内容の修繕計画を自動で提案する。これは、インフラや建物の長寿命化に貢献するだけでなく、「予知保全サービス」という新たなビジネスモデルを創出する可能性を秘めている。
経営・事業開発へのインパクト
AIは、現場レベルの効率化に留まらず、経営層の意思決定をも支援する。
- 事業リスク予測と新たな開発機会の発見: AIが、過去の膨大なプロジェクトデータ(工期、コスト、発生した問題など)と、金利や資材価格、地域ごとの需要動向といったマクロ経済データを分析することで、新規プロジェクトに潜むリスク(例:コスト超過、工期遅延の確率)を定量的に予測する。これにより、経営層はデータに基づいた投資判断を下すことができる。さらに、人流データ、不動産取引データ、都市計画情報などを統合的に分析することで、これまで見過ごされていた新たな不動産開発の機会(例:将来的な人口増加が見込まれるエリア、特定のテナント需要が高まる地域)を発見し、事業開発の精度を高めることに貢献する。
第9章:主要トレンドと未来予測
建築業界は、複数の強力なトレンドが同時進行し、相互に影響を及ぼし合う中で、構造的な変革期を迎えている。今後10年間の業界の姿を形作る、四つの決定的なトレンドを以下に詳述する。
建設DXの深化:BIM/CIMを核としたプラットフォーム化
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや単なる業務効率化のツールではない。BIM/CIMを中核に据えたデータ連携プラットフォームは、業界のビジネスモデルそのものを変革する可能性を秘めている。国土交通省が推進するi-Constructionは、計画・調査・設計から施工、維持管理に至る全プロセスを3次元データで繋ぎ、一気通貫での全体最適を目指すものである 38。
将来的には、発注者、設計事務所、ゼネコン、サブコン、建材メーカーといったすべてのステークホルダーが、クラウド上の単一のプラットフォームでBIM/CIMデータを共有し、リアルタイムで協働する姿が想定される。これにより、情報の非対称性や伝達ロスが解消され、サプライチェーン全体が透明化される。このプラットフォームを制する企業が、業界の新たなエコシステムの中心となる可能性がある。これは、製造業における「製販一体」モデル、すなわち顧客のニーズをダイレクトに設計・生産に反映させるモデルが、建設業界でも実現可能になることを意味する。
オフサイトコンストラクションの加速
深刻な人手不足、働き方改革による現場作業時間の制約、そして品質の安定化という要請に応えるため、オフサイトコンストラクション、すなわち工場での部材生産(プレハブ、モジュール化)の比率を高め、現場での作業を最小限に抑える動きが加速している。
世界のオフサイトコンストラクション市場は、年率4.9%の成長が見込まれており 58、日本においても、労働力不足を背景にその重要性は増している 59。鉄骨の柱や梁、壁パネル、さらにはキッチンやバスルームといったユニットまでを天候に左右されない工場で精密に生産し、現場ではそれらを組み立てるだけ、という工法である。
この動きは、建設業を従来の「現場での一品生産」から、製造業に近い「工場での計画生産」へと転換させる。これにより、工期の大幅な短縮、品質の均質化、現場での廃棄物削減、そして労働安全性の向上といった多くのメリットがもたらされる。特に、都市部での再開発やホテル建設など、標準化されたユニットを多用するプロジェクトで普及が進むと予測される。
マス・ティンバー(大規模木造建築)の台頭
脱炭素社会の実現と国内林業の活性化という二つの要請が交差する点に、マス・ティンバー(CLT*や集成材を用いた大規模木造建築)の大きな可能性がある。木材は、製造時のCO2排出量が鉄やコンクリートに比べて少なく、さらに樹木が成長過程で吸収した炭素を建材として長期間固定する「炭素貯蔵効果」を持つ、カーボンニュートラル時代に最適な建材である 45。
- CLT (Cross Laminated Timber): 挽き板を繊維方向が直交するように積層接着した木質パネル。
技術の進歩により、木材でも高層・大規模な建築物の建設が可能になりつつあり、オフィスビルや商業施設といった非住宅分野での木造・木質化建築の市場が拡大すると予測される 60。政府もCLTの利用環境整備を支援しており 11、今後、建築基準法の改正などが進めば、その普及はさらに加速するだろう。これは、新たな設計・施工技術の需要を喚起すると同時に、国内の豊富な森林資源を有効活用する新たなサプライチェーンの構築を促す。
サーキュラーエコノミーへの移行:「作って壊す」から「長く使い、再利用する」へ
資源の枯渇と廃棄物問題への対応として、サーキュラーエコノミーへの移行は、建設業界にとって避けて通れない道である。これは、従来の「作って壊す(リニアエコノミー)」モデルからの根本的な転換を意味する。
- リノベーション・コンバージョン市場の成長: 新築需要が頭打ちになる中、900万戸を超える空き家 29 や老朽化したインフラといった膨大な既存ストックを、いかに有効活用するかがビジネスの主戦場となる。既存の建物の価値を向上させるリノベーションや、時代のニーズに合わせて用途を変更するコンバージョン市場は、今後、安定した成長が見込まれる。
- 建設リサイクルの高度化: 建設リサイクル法に基づき、建設廃棄物の再資源化率は高い水準を維持しているが 44、今後はさらに高度化が求められる。単に破砕して路盤材にするようなカスケードリサイクルから、元の建材として再利用するアップサイクルへの移行が重要となる。そのためには、設計段階から解体・再利用を考慮する「分解しやすい設計(Design for Disassembly)」 45 や、建材の履歴情報を追跡可能にする「マテリアルパスポート」 61 といった新たな概念の導入が不可欠となる。
これらのトレンドは、建設業界の競争軸を「いかに安く、早く作るか」から、「いかに環境負荷を少なく、ライフサイクル全体での価値を最大化し、資源を循環させるか」へと完全にシフトさせるものである。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
日本の建築業界を牽引する主要プレイヤーの戦略を比較分析することで、業界全体の動向と、各社が直面する課題への対応の違いが明らかになる。ここでは、スーパーゼネコン5社、大手ハウスメーカー、および建設テック企業を対象に、事業ポートフォリオ、DX、サステナビリティ、人材戦略の観点から分析する。
スーパーゼネコン5社(鹿島建設、大林組、大成建設、清水建設、竹中工務店)
- 事業ポートフォリオと収益構造: 5社ともに国内の建築・土木請負事業を収益の根幹としている。売上高は各社2兆円前後の規模を誇るが、近年は資材高騰の影響で利益率が低下傾向にある 22。このため、収益の安定化を目指し、リスクの低い不動産開発事業や、海外事業の比率を高める戦略が共通して見られる。
- DX戦略: 各社ともBIM/CIMの導入を積極的に進め、生産性向上を目指している。特に、大成建設は「デジタルツイン」「AI」「リモート技術」をコア技術と位置づけ、全社横断的なDX推進体制を構築している 62。清水建設は「超建設」をスローガンに、2030年までに定型業務の50%以上自動化という野心的な目標を掲げ、データ利活用基盤の整備とDX人材の育成に注力している 64。鹿島建設も異業種や大学との共創を通じてDXによる新たな価値創出を目指している 66。各社とも方向性は類似しているが、その実行レベルとビジネスモデル変革への本気度には差が見られる。
- サステナビリティへの取り組み: 2050年カーボンニュートラルは全社共通の目標であり、ZEB技術の開発や再生可能エネルギー事業への投資を加速させている 67。また、建設廃棄物の削減やリサイクル率向上といったサーキュラーエコノミーへの貢献も重要なテーマとなっている 71。大成建設は、サステナビリティへの対応が多くの施工現場を抱える中でも実効的であると評価されている 69。
- 人材戦略: 2024年問題への対応として、週休二日制の定着や長時間労働の是正は最優先課題である。女性技術者・技能者の活躍を推進する「けんせつ小町」の取り組みや、外国人材の活用も共通して進められている 13。大成建設は「企業風土改革」「人事制度改革」を明示的に掲げ、従業員のエンゲージメント向上を図るなど、組織文化の変革にまで踏み込んでいる 72。
大手ハウスメーカー(積水ハウス、大和ハウス工業)
- 事業ポートフォリオと収益構造: 戸建住宅事業で培った技術力とブランド力を基盤に、賃貸住宅、商業施設、事業施設(物流施設、医療・介護施設など)へと事業を多角化している。海外展開も積極的に進めており、特に米国や豪州市場でのシェア拡大を目指している 60。
- DX戦略: 設計から生産、施工、アフターサービスに至るまで、一貫した顧客データベースとBIMデータを活用し、業務効率化と顧客満足度向上を図っている。工場生産(オフサイトコンストラクション)の比率が高いため、製造業に近い形でのDXが進んでいる点がゼネコンとの違いである。
- サステナビリティへの取り組み: 環境性能を製品の競争力の中核と位置づけている。積水ハウスは、ZEHの普及をリードし、CDP(国際的な環境情報開示プラットフォーム)において気候変動、フォレスト、水セキュリティの全分野で最高評価の「Aリスト」に選定されるなど、世界的に高い評価を得ている 73。大和ハウス工業は、「サーキュラーエコノミー&カーボンニュートラル」をマテリアリティ(最重要課題)に特定し、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿った情報開示を行うなど、先進的な取り組みを推進している 74。
- 人材戦略: 多様な人材が活躍できる環境整備に注力しており、ダイバーシティ&インクルージョンの推進を経営戦略の重要な柱と位置づけている。
建設テック企業
- 事業モデル: 建設業界の特定領域における非効率を、SaaS(Software as a Service)などのITソリューションで解決することに特化している。カオスマップを見ると、プロジェクト管理、図面共有、積算、安全管理、人材マッチングなど、多岐にわたる分野で専門的なサービスが提供されている 50。
- 強みと弱み: 強みは、最新のIT技術とアジャイルな開発体制による、スピーディなサービス提供能力である。弱みは、建設業界特有の複雑な商慣習や現場オペレーションへの理解不足、そして大手ゼネコンなどが持つ顧客基盤や信用力に欠ける点である。
- 業界へのインパクト: 建設テック企業は、既存の建設会社と競合するだけでなく、協業するパートナーでもある。彼らが提供するツールは、建設会社のDXを加速させる一方、業界の情報をプラットフォーム上に集約することで、将来的には業界のパワーバランスを変化させる可能性を秘めている。
これらのプレイヤー分析から、主要企業の戦略がDXとサステナビリティという二大潮流に収斂しつつあり、一見すると「同質化」しているように見える。しかし、その実行レベル、特に既存の請負ビジネスモデルをいかに変革し、新たな収益モデル(サービス化、プラットフォーム化など)を構築するかに着手できているかという点において、戦略的な優劣が生まれ始めている。投資の配分や組織構造の変革が、各社の本気度を測るリトマス試験紙となるだろう。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、日本の建築業界が直面する構造的課題を乗り越え、持続可能な成長を遂げるための戦略的な意味合い(インプリケーション)と、具体的な推奨事項を提示する。
今後5~10年で、建築業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因
今後5~10年で業界の勝敗を分けるのは、もはや個別の施工技術の優劣や、受注高の規模ではない。以下の三つの変革への対応能力が、決定的な要因となる。
- データ・ドリブンな意思決定能力: 経験と勘に頼った経営から脱却し、BIM/CIM、IoT、AIから得られる膨大なデータを収集・分析し、設計の最適化、施工プロセスの効率化、維持管理の高度化、さらには経営判断に至るまで、あらゆる階層でデータに基づいた意思決定を徹底できるか。
- バリューチェーン統合能力: 分断された設計、調達、施工、維持管理の各プロセスを、デジタルプラットフォームを介してシームレスに統合し、顧客に対してライフサイクル全体での価値を提供できるか。重層下請け構造という旧来のサプライチェーンの軛(くびき)から脱し、オープンかつフラットなエコシステムを主導できるか。
- サステナビリティの事業化能力: 脱炭素やサーキュラーエコノミーを、規制対応のコストではなく、顧客の資産価値向上や新たな収益機会に転換するビジネスモデルを構築できるか。「環境性能」を技術的なスペックとして語るのではなく、顧客の経営課題を解決するソリューションとして提案できるか。
これらの能力を欠く企業は、コスト上昇と供給能力の低下という二重苦の中で収益性を悪化させ、市場での存在感を失っていく。一方で、これらの能力を獲得した企業は、生産性の飛躍的な向上と高付加価値なサービス提供により、新たな成長軌道を描くことができるだろう。
自社が捉えるべき機会(Opportunity)と備えるべき脅威(Threat)
- 捉えるべき機会(Opportunity)
- 既存ストック市場: 900万戸の空き家と老朽化するインフラは、リノベーション、コンバージョン、維持管理、解体という巨大な「ストック型ビジネス」市場を形成している。
- グリーン・トランスフォーメーション(GX)市場: ZEH/ZEB化への移行は、高断熱建材、高効率設備、エネルギーマネジメントシステム(BEMS)など、高付加価値な製品・サービスの需要を創出する。
- DXによる新サービス創出: 収集した建物データや施工データを活用し、予知保全サービス、エネルギー最適化コンサルティング、不動産価値評価サービスなど、従来の建設業の枠を超えた新たなサービス事業を展開する機会がある。
- オフサイトコンストラクションによる生産革命: 工場生産へのシフトは、品質の安定化と生産性向上だけでなく、労働環境の改善を通じて、これまで建設業を敬遠していた多様な人材(女性、若者など)を惹きつける機会となる。
- 備えるべき脅威(Threat)
- 労働力の枯渇: 技能労働者の大量退職による供給能力の崩壊は、事業継続そのものを脅かす最大の脅威である。
- コスト構造の激変: 資材価格と労務費の継続的な上昇は、従来のコスト構造を前提としたビジネスモデルを成り立たなくさせる。価格転嫁ができない企業は、赤字受注に陥り、淘汰される。
- 異業種からのディスラプション(破壊): 建設テック企業やITジャイアントが、データを活用したプラットフォームで業界の主導権を握り、既存の建設会社が単なる労働力提供者へと「下請け化」するリスクがある。
- 規制の強化: 省エネ基準やリサイクル法、労働時間規制など、環境・労働関連の規制は今後さらに強化される。コンプライアンス対応の遅れは、事業機会の損失に直結する。
戦略的オプションの提示と評価
以上の分析を踏まえ、考えられる戦略的オプションを複数提示し、それぞれのメリット・デメリットを評価する。
表11.1: 戦略的オプションの評価
| 戦略的オプション | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| A. 施工特化・効率追求モデル | ・既存のコアコンピタンス(施工能力)に集中できる ・徹底したコスト削減と効率化により、価格競争力を維持 | ・利益率の低い価格競争から脱却できない ・労働力不足や資材高騰の影響を直接受けやすい ・下請け化のリスクが高く、持続可能性が低い |
| B. 「エンジニアリング/コンサルティング」へのシフト | ・高付加価値な上流工程(企画、設計)に特化し、高い利益率を確保 ・物理的な施工リスクから解放される ・専門性の高い人材を惹きつけやすい | ・施工部門とのシナジーを失う ・設計事務所や専門コンサルとの厳しい競争に直面 ・大規模な組織変革と人材の再教育が必要 |
| C. M&Aによる事業領域拡大・垂直統合 | ・DXや環境技術を持つ企業を買収し、短期間で新たな能力を獲得 ・オフサイト工場や専門工事業者を傘下に収め、サプライチェーンを強化 | ・M&A後の組織文化の統合(PMI)が難しい ・高値掴みのリスクがある ・自社での内発的な変革力が育ちにくい |
| D. 「ライフサイクル・インテグレーター」への事業転換 | ・企画から維持管理まで一貫して関与し、顧客との長期的関係を構築 ・ストック型収益(維持管理、サービス料)により経営が安定 ・業界のプラットフォーマーとなるポテンシャルを持つ | ・最も野心的で、実現に向けた難易度が高い ・多岐にわたる専門性(金融、IT、不動産運営等)が必要 ・莫大な先行投資と長期的なコミットメントが不可欠 |
最終提言:事業戦略「ライフサイクル・インテグレーター」への転換
最終提言: 戦略オプションD「ライフサイクル・インテグレーター」への事業転換こそが、三重の構造的課題を乗り越え、持続可能な成長を実現するための最も説得力のある戦略である。これは、単なる事業の多角化ではなく、自社の存在意義(パーパス)を「建物を造る会社」から「建物を核とした価値創造プラットフォームを提供する会社」へと再定義する、根本的な変革である。
実行に向けたアクションプランの概要
- KPI(重要業績評価指標):
- 財務KPI:
- LCC関連事業(維持管理、コンサルティング等)の売上比率:現状5% → 5年後20%
- 全体の営業利益率:現状X% → 5年後X+3%
- 非財務KPI:
- BIM/CIM活用プロジェクト比率:現状30% → 3年後100%
- デジタル人材比率:現状1% → 5年後10%
- 顧客LTV(Life Time Value):5年後に30%向上
- 財務KPI:
- タイムライン:
- Phase 1 (Year 1-2): 基盤構築
- 全社DX戦略の策定と推進組織(CDO職の設置)の確立。
- 主要プロジェクトにおけるBIM/CIMの完全導入とデータ収集基盤の整備。
- 維持管理部門の強化と、IoT/AIを活用した予知保全サービスのパイロット導入。
- デジタル人材の中途採用と、全社員向けデジタルリテラシー教育の開始。
- Phase 2 (Year 3-5): 事業展開とエコシステム構築
- 企画・設計段階からLCC最適化を提案するコンサルティング事業の本格展開。
- 収集したデータを活用した新たなサービス(エネルギーマネジメント等)の商品化。
- 設計事務所、専門工事業者、テック企業を巻き込んだオープンなデータ連携プラットフォームの構築開始。
- オフサイトコンストラクション工場の新設または提携強化。
- Phase 1 (Year 1-2): 基盤構築
- 必要リソース:
- 人材: CDO(Chief Digital Officer)、データサイエンティスト、AIエンジニア、BIMマネージャー等の専門人材を今後5年でXX名採用。
- 投資: DXプラットフォーム構築、オフサイトコンストラクション関連、M&A(必要に応じて)のために、今後5年間でXXX億円の戦略的投資枠を設定。
- 組織: バリューチェーン横断型のプロジェクトチームを組成し、部門間の壁を撤廃。成果連動型の報酬制度を導入し、変革を推進する人材に報いる。
この変革の道は平坦ではない。しかし、未来の市場で求められる価値を提供し、業界のリーダーとして生き残るためには、この痛みを伴う自己変革こそが唯一の道である。
第12章:付録
引用文献
- 建設経済モデルによる建設投資の見通し(2025年4月), https://www.rice.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/250411_model.pdf
- 建設分野における物価等動向について(2/3) – みずほリサーチ&テクノロジーズ, https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2024/articles_0070.html
- 建設経済モデルによる建設投資の見通し( 2025 年 7 月 ), https://www.rice.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/250711_model.pdf
- 【建設業の基礎知識】2025【7】建設経済モデルによる「建設投資(見通し)」について | 新着記事一覧, https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=3966
- 2025・4月 – 経済調査会, https://www.zai-keicho.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/keizaiyosoku202504.pdf
- 1.2 建設投資の中長期予測(2035 年度までの見通し) – RICE 一般財団 …, https://www.rice.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/%E2%91%A31.2-%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%AE%E4%B8%AD%E9%95%B7%E6%9C%9F%E4%BA%88%E6%B8%AC%EF%BC%882035%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%EF%BC%89P21%EF%BD%9E59.pdf
- 【建設経済レポート】35年度は最大81兆円/建設投資の中長期予測示す, https://www.nikoukei.co.jp/news/detail/503652
- 国土強靭化の加速化に向けた意見, https://www.jcci.or.jp/chiiki/2024resilience-gaiyo.pdf
- 2025年度予算、国交省配分8.4兆円/全建が国土強靭化25兆円規模要望 他, https://kensetsu-data.co.jp/blog/blog_detail.php?id=612
- 国土交通大臣の新春インタビューからわかる今後の建設業界【2023年】, https://kensetsu-ict.com/column/6024/
- 令和7年度 国土強靱化関係予算案の概要 – 内閣官房, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/r07kankeiyosan.pdf
- 建設業における人材確保に 向けた取り組みについて 建設業における人材確保に 向けた取り組みについて – 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧, https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/4_060829ngtjinzaikakuho_seibikyoku.pdf
- 4. 建設労働 | 建設業の現状 | 日本建設業連合会, https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html
- 成長率8%超!2030年まで右肩上がりが続くベトナム建設市場の真実とは?, https://axconstdx.com/2025/06/08/%E6%88%90%E9%95%B7%E7%8E%878%E8%B6%85%EF%BC%812030%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%8F%B3%E8%82%A9%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%81%8C%E7%B6%9A%E3%81%8F%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%BB%BA/
- 最近の建設業を巡る状況について【報告】 – 国土交通省, https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001734007.pdf
- 【特集】主要資材の需給と市況動向(2023年10月末現在) – 建設物価調査会, https://www.kensetu-bukka.or.jp/article/12714/
- 【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説 …, https://lline-group.co.jp/magazine/building-materials-prices-soaring/
- 建設業界の最新動向2025 ~市場概況、制度改正、建設コストの値動きまで~ – 建設 IT NAVI, https://process.uchida-it.co.jp/itnavi/info/c20250317/
- 2024年問題の建設業への影響は?働き方改革の進め方も解説 | Think …, https://www.kddimatomete.com/magazine/240731100000/
- 働き方改革に伴う2024年問題の影響 – IFA Leading, https://ifa-leading.com/ifalt/hatarakikatakaikaku/
- 2024年の建設業はどう変わる?時間外労働の上限規制の適用に向けて取り組むべきこととは?, https://kensetsu-kaikei.com/lab/work/construction_industry_2024
- スーパーゼネコン5社の財務分析 2024年版 | 建設業を支援する経営 …, https://www.applibank.com/post/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%82%B3%E3%83%B35%E7%A4%BE%E3%81%AE%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%88%86%E6%9E%90%E3%80%802024%E5%B9%B4%E7%89%88/
- ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業 調査発表会2024, https://sii.or.jp/zeb06/uploads/ZEB_conference_2024_02.pdf
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 – 調査発表会 2024, https://sii.or.jp/zeh06/uploads/ZEH_conference_2024.pdf
- SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ|補助事業(令和6年度 …, https://sii.or.jp/zeb06/public.html
- ZEB・ZEH-M設計支援補助金 – 札幌市, https://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/hojo/zebzehm.html
- ZEH補助金サイトトップページ, https://zehweb.jp/
- 【令和6年度】ZEB(ゼブ)導入に活用できる9つの補助金 – トレンド&データ | 未来図(ミライズ), https://www.mirait-one.com/miraiz/whatsnew/trend-data_0014.html
- 空き家が過去最高の900万戸に 所有者の意識高まるなかビジネスチャンスが拡大, https://htonline.sohjusha.co.jp/683-026/
- 注目!空き家ビジネス | 情報誌「戦略経営者」 – TKCグループ, https://www.tkc.jp/cc/senkei/201504_special02
- 空き家再生ビジネスにどう挑むか? ―ポテンシャルと課題から取り組み方を考える, https://www.biz-lixil.com/column/business_library/article09_007/
- 建設業の人手不足の現状と理由を徹底解説!原因と対策も紹介 – Safie(セーフィー), https://safie.jp/article/post_18566/
- 最近の建設業を巡る状況について – 国土交通省, https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001493958.pdf
- 新しい働き方として社会に定着するハイブリッドワーク – JLL, https://www.jll.com/ja-jp/insights/hybrid-work-established-for-the-post-corona
- これからのオフィス需要と求められる要素 | JLL記事, https://www.jll.com/ja-jp/insights/the-future-of-office-demand-and-key-factors
- ジャパンレポート-コロナ禍を経たオフィス戦略 2022年3月 – CBRE, https://www.cbre.co.jp/insights/reports/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8D%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D%E3%82%92%E7%B5%8C%E3%81%9F%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%88%A6%E7%95%A5-2022%E5%B9%B43%E6%9C%88
- ジャパンレポート-ポストコロナの東京オフィスマーケット 2022年 …, https://www.cbre.co.jp/insights/reports/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8D%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-2022%E5%B9%B44%E6%9C%88
- 国土交通省のi-Construction推進最新動向 – 建設 IT NAVI, https://process.uchida-it.co.jp/itnavi/column/20200905/
- 国土交通省における BIM/CIMの取組と今後の展開 – 一般社団法人 OCF, https://ocf.or.jp/pdf/cim/seminar2019/OCFseminar2019_1_MLIT.pdf
- 国交省i-Construction 2.0対応:BIM/CIMの最新動向 | お役立ちコラム – 株式会社リビック, https://livic-eng.com/media/i-con/i-con2
- 国交省発表「i-Construction 2.0」2025年度の取組予定を解説 …, https://digital-construction.jp/column/1895
- 建設リサイクル法 – 新潟県ホームページ, https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1200589236715.html
- 建設リサイクル法 改正情報 – 一般社団法人 産業環境管理協会(JEMAI CLUB), https://www.e-jemai.jp/jemai_club/act_amendment/lex_3/act8/
- 建設リサイクルを取り巻く近年の 社会情勢の変化と … – 国土交通省, https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/05shiryou2.pdf
- 未来を築く!サーキュラーエコノミー×建築の最前線 – KOTORA …, https://www.kotora.jp/c/106389-2/
- 建設業界での人手不足(技術者不足)が与える影響と対策を徹底解説 – 建設システム, https://www.kentem.jp/blog/construction-labor-shortage-engineer/
- 建設業の職人不足の原因と影響について”きちんと”データと事例に基づいてまとめました, https://souken.craft-bank.com/analisys/shokunin-husoku/
- ゼネコン(総合建設業者)とサブコン(専門工事業者)の景気予測 …, https://note.com/harusan_1002/n/n6e58953a1c9f
- 建設業に忍び寄る「人手不足格差」 68%が仕事を断るという現実の裏で何が起きているのか, https://mkensetu.jp/news/labor-shortage-gap/
- LBMA Japan、「位置情報ビジネス&マーケティングカオスマップ2025年版」を発表! – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000055226.html
- 建設・不動産業界AI導入事例カオスマップ 2025を公開!用途やAIカテゴリ別に全82事例を掲載, https://www.atpress.ne.jp/news/1924009
- 建設・不動産業界AI導入事例カオスマップ 2025を公開!用途やAI …, https://aismiley.co.jp/ai_news/construction-realestate-chaosmap-2025/
- 重層下請構造の問題点, https://www.mlit.go.jp/common/001132804.pdf
- 【アンケートを終了しました】国土交通省 「重層下請構造の実態調査」へのご協力のお願い – PwC, https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/2025/mlit-research.html
- 製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/pdf/016_04_00.pdf
- 産業別労働生産性水準の国際比較2024 概 要 – 公益財団法人日本生産 …, https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/Productivity_report_vol20_summary.pdf
- 日本生産性本部、「労働生産性の国際比較2024」を公表 – 共同通信PRワイヤー, https://kyodonewsprwire.jp/release/202412121594
- オフサイト建設市場の動向|レポート[2033] – Business Research Insights, https://www.businessresearchinsights.com/jp/market-reports/offsite-construction-market-120810
- 日本の橋梁建設市場の規模と2033年までの予測 – IMARC Group, https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bridge-construction-market
- 米ダラス近郊にマスティンバー建築の木造 7 階建てオフィス – 住友林業, https://sfc.jp/information/news/pdf/2022-12-26-02.pdf
- サーキュラーエコノミーが示す未来への道 ~建設業界とジャストの取り組み – note, https://note.com/just_50/n/n3bfac9857b98
- デジタルトランスフォーメーション(DX) – 大成建設サステナビリティ, https://www.taisei-sx.jp/social/consumer/dx.html
- DX戦略|大成建設 DXサイト, https://www.taisei-dx.jp/strategy/
- シミズのDX 「超建設」によるデジタルゼネコンの進化|清水建設, https://www.shimz.co.jp/digital-strategy/
- 【レポート解説】 清水建設株式会社 シミズコーポレートレポート2024 ダイジェスト – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=EVyGoOV6SY4
- 鹿島 統合報告書 2024, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250217/20250213573362.pdf
- 鹿島 統合報告書 2023, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240207/20240202525723.pdf
- OBAYASHI コーポレートレポート 2025 – 株主・投資家情報 – 大林組, https://ir.obayashi.co.jp/ja/ir/data/report/main/05/teaserItems2/02/linkList/0/link/CR2025_all.pdf
- 統合レポート2023(和文) – in-Report, https://in-report.com/library/pdf/1801_2023.pdf
- Corporate Report 2025 – 竹中土木コーポレートレポート, https://www.takenaka-doboku.co.jp/wp-content/themes/ill/img/page/company/pdf/report2025.pdf
- サーキュラーエコノミーとは?必要な3つの理由と建設業界の取り組み事例を紹介, https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_0601/
- 「大成建設グループ統合報告書2025」を公開 | 大成建設株式会社, https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2025/250925_10645.html
- VALUE REPORT 2024 – 積水ハウス, https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/sustainable/download/2024/value_report/all.pdf
- 「サステナビリティレポート2024」発行(ニュースレター …, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002144.000002296.html
- 国土交通省発表、2025年度建設投資75.6兆円見通し 民間が4.5%増で牽引, https://news.build-app.jp/article/37253/
- 脱炭素社会の実現に向けて~基礎編 – 環境省, https://www.env.go.jp/earth/zeb/news/files/20220125_document4.pdf
- アフターコロナの働き方・オフィスのあり方に関するレポート – CBRE, https://www.cbre-propertysearch.jp/with-corona/with-corona_1/
- 建設業で人材不足が起こっている理由は?その対策も詳しくご紹介!|JAC, https://jac-skill.or.jp/columns/story/reason-shortage.php
- 建築業における人手不足|原因や解決策など詳しく解説 | 働き方改革ラボ – リコージャパン, https://www.ricoh.co.jp/magazines/workstyle/download/architecture-shorthanded/
- 建設業の長期ビジョン2.0 – 日本建設業連合会, https://www.nikkenren.com/sougou/vision2025/
- 再生と進化に向けて, https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001441267.pdf
- 建設業界総本山のトップが大胆提唱!人手不足の解消は週休2日とDX、そして「切り札」とは?, https://diamond.jp/articles/-/355744
- 知っておくべき!建設業 労務単価の実際と2026年度予測【業界情報】, https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=3753
- 「労働生産性の国際比較2021」からの考察 – 三菱UFJ信託銀行, https://www.tr.mufg.jp/shisan-ken/pdf/shisan_keisei_12.pdf
- モジュラー建設市場調査レポート、規模とシェア、成長機会、およびトレンド洞察分析, https://www.sdki.jp/reports/modular-construction-market/110091
- 鹿島 統合報告書 2021 – 名古屋証券取引所, https://www.nse.or.jp/listing/search/files/140120211125441115.pdf
- 【CSR図書館.net】CSRレポート、環境報告書、統合報告書の検索 …, https://csr-toshokan.net/index.php?page=csr_view.pdf_viewer&csr_id=7559&
- 統合報告書 2024 – 積水化学工業, https://www.sekisui.co.jp/ir/document/annual/pdf/SC_IR2024_ALL_J.pdf
- 統合報告書2024 – 積水化学工業, https://www.sekisui.co.jp/ir/document/annual/pdf/SC_IR2024_J_01.pdf