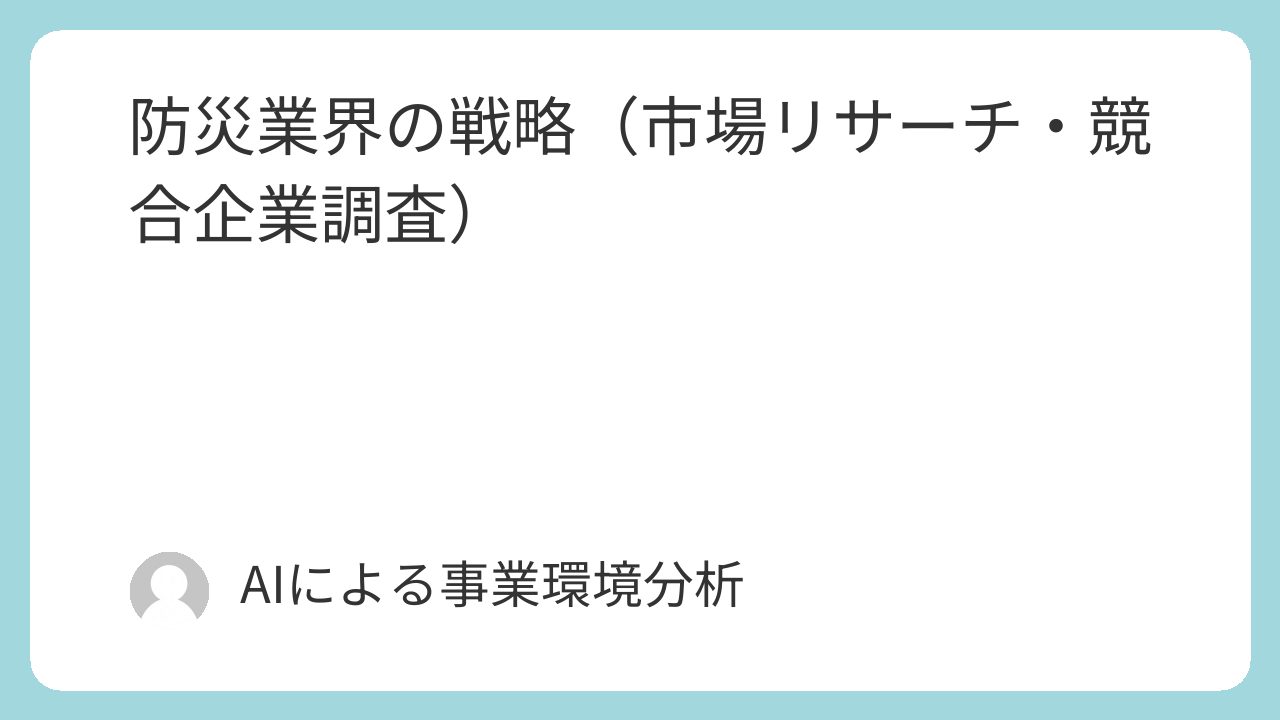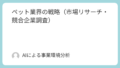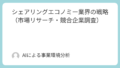フェーズフリーとAIが拓く「パーソナライズド防災」:個人向け防災市場の次世代戦略
第1章:エグゼゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、気候変動による自然災害の激甚化・頻発化、パンデミック等の新たな脅威、そして高齢化・単身世帯化といった深刻な社会構造の変化に直面する日本の「個人向け防災業界」において、持続的な成長を実現するための新たな事業戦略を提言することを目的とする。気候変動は、1時間降水量80mm以上の豪雨の発生頻度を過去約40年で約1.7倍に増加させており 1、首都直下地震では最大約2.3万人の死者と約95.3兆円の経済被害 3、南海トラフ巨大地震では最大約33.2万人の死者と約224.9兆円の経済被害が想定されるなど 4、事業環境のリスクはかつてないほど高まっている。
本調査の対象は、個人・家庭向けの防災関連商品(備蓄食品、飲料水、衛生用品、非常用電源、パーソナルシェルター等)、および防災関連サービス(情報提供アプリ、備蓄管理・定期配送サービス、防災コンサルティング・教育)市場とする。
最も重要な結論:市場の根源的課題と成長への道筋
個人向け防災市場は、「増大し続ける災害リスク」と「一向に改善しない低い備蓄実践率」という深刻なギャップが存在する未成熟な市場である。防災食の備蓄率は約59.0% 6 に留まり、特に簡易トイレの備蓄率は30.6% 6 と極めて低い。このギャップの根源には、消費者が防災を「もしもの時だけの特別なコスト」と捉え、「何を、どれだけ、どのように備えれば良いか分からない」という知識不足と「管理が面倒」という心理的・物理的負担が存在する。
この根源的課題を解決し、市場を本格的な成長軌道に乗せる鍵は、従来の「恐怖(Fear)」を起点としたアプローチからの脱却にある。そして、以下の3つの価値転換を事業の中核に据えることである。
- フェーズフリー(Phase-Free): 「非常時」のためだけの製品から、「日常時」でも便利で価値のある製品・サービスへの転換。
- パーソナライズ(Personalize): 画一的な防災セットから、AIを活用し個々の世帯状況やリスクに最適化されたソリューションへの転換。
- サブスクリプション(Subscription): 一度きりの「売り切り」モデルから、継続的な関係を通じて安心を提供するサービスモデルへの転換。
特に、人工知能(AI)技術はこれらの価値転換を飛躍的に加速させ、需要予測、顧客体験、サプライチェーンの全てを革新し、市場のゲームチェンジャーとなる決定的なポテンシャルを秘めている。
主要な戦略的推奨事項
本分析に基づき、本市場で持続的な競争優位を確立するために、以下の4つの戦略的アクションを提言する。
- 事業ポートフォリオの抜本的「フェーズフリー」化: 開発リソースを、アウトドアでも活用できるポータブル電源や、インテリアに溶け込むデザインの備蓄食など、日常生活における利便性とデザイン性を重視した製品群へ集中投下する。これにより、「コスト」と認識されていた防災支出を、ライフスタイルへの「投資」へと転換させる。
- AIを活用した「パーソナライズド防災プラットフォーム」の構築: 顧客の家族構成、居住地のハザード情報、健康状態(アレルギー等)といったデータを基に、AIが最適な備蓄品と行動計画を提案するサブスクリプション・サービスを事業の中核に据える。これにより、顧客の「分からない」「面倒」という最大の障壁を解消し、継続的な収益基盤を確立する。
- 「共助」のデジタル化支援によるエコシステム形成: 地域コミュニティ(マンション管理組合、自治会等)を対象に、備蓄品のシェアリングや安否確認を容易にするアプリやプラットフォームを提供する。自治体やNPOとの連携を通じて、防災エコシステムのハブとしての地位を確立し、新たな事業機会を創出する。
- 異業種との戦略的アライアンスの推進: 自社に不足するケイパビリティを迅速に補完するため、IT企業(AI技術)、保険会社(リスクファイナンス)、住宅メーカー(住宅設備)等との積極的なアライアンスを締結し、新たな顧客価値を共創する。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本の個人向け防災関連市場規模の推移と今後の予測(2020年~2030年)
個人向け防災市場は、単一の統計が存在しない複合市場であり、その全体像を把握するには関連市場を統合的に分析する必要がある。
- 防災食品市場: 市場規模は大規模災害の発生に大きく左右される。矢野経済研究所によると、2021年度の市場規模は東日本大震災から10年の節目による買い替え需要で313億円に達した 7。一方で富士経済は、2024年の市場を能登半島地震などの影響で前年比21.4%増の261億円と予測しており 8、市場がイベントドリブンで変動する特性を示している。
- 防災用品市場(広義): 防災関連ビジネス全体では8兆円超 10、防災用品市場単体でも3,500億~4,000億円規模 11 との推計もあるが、これらは公共インフラや法人向けを含むため、個人向け市場はこれより小さい規模と推定される。
- 防災情報システム・サービス市場: シード・プランニングの調査では、2024年度の国内市場を約2,150億円、2030年度には約2,360億円に達すると予測している 12。しかし、この市場の大半は自治体向けの総合防災システムなどの官公需要であり 13、個人向けの防災アプリや情報サービスが占める割合は限定的である。
- 急成長する特定カテゴリー: 中でもポータブル電源市場は、防災需要とアウトドアブームという2つの追い風を受け、顕著な成長を遂げている。日本の市場規模は2022年の1億5,834万米ドルから、年平均成長率(CAGR)8.0%で成長し、2032年には3億4,371万米ドルに達すると予測されている 14。この成長は、市場が単なる「災害への備え」から、日常の利便性も追求する「ライフスタイル統合型」へとシフトしていることを象徴している。
これらのデータを統合すると、個人向け防災市場は、災害発生をトリガーとする短期的なスパイクと、フェーズフリーのような新たな価値観に牽引される長期的な構造変化が混在する、過渡期の市場であると評価できる。
市場セグメンテーション分析
| セグメント | 主要製品・サービス | 市場特性・動向 |
|---|---|---|
| 製品カテゴリー別 | 備蓄食品・飲料水 | アルファ米、缶詰パン、長期保存水。近年は味や栄養バランス、アレルギー対応など品質の高度化が進む。 |
| 衛生用品 | 簡易トイレ、からだ拭きシート、口腔ケア用品。特に簡易トイレの家庭備蓄率は約30%と極めて低く、大きな潜在需要が存在 6。 | |
| 生活用品 | LEDライト、ラジオ、電池、軍手。多機能化(ラジオ付きライトなど)やデザイン性の向上が進む。 | |
| 非常用電源 | ポータブル電源、発電機、ソーラーパネル。アウトドア需要と在宅避難ニーズの高まりを背景に市場が急拡大 14。 | |
| 耐震・家具固定具 | 突っ張り棒、転倒防止マット。補助金制度などが需要を後押しするが、設置の手間が普及の障壁。 | |
| 防災セット | 一人用の基本的なアイテムをまとめたセット。エントリーユーザー向けに需要があるが、中身の画一性が課題。 | |
| サービス別 | 防災情報アプリ | Yahoo!防災速報、特務機関NERVなど。プッシュ通知によるリアルタイム情報提供が主流。マネタイズが課題。 |
| 備蓄管理・定期配送 | 備蓄品の賞味期限管理と定期的な入れ替えを代行するサブスクリプションモデル。新たなビジネスモデルとして注目。 | |
| 防災教育・訓練 | 防災士によるセミナーや、VRを活用した災害体験など。法人向けが中心だが、個人・家庭向けの需要も増加。 | |
| 販売チャネル別 | ホームセンター | カインズ、コーナンなど。PB商品の開発に注力し、価格競争力を持つ。防災コーナーの常設で顧客接点を確保。 |
| EC | Amazon, 楽天など。圧倒的な品揃えとレビュー機能により、商品比較が容易なため、特に若年層やエントリーユーザーの主要購入チャネルとなっている 16。 | |
| 専門EC | 防災用品専門のオンラインストア。専門知識に基づく品揃えとコンサルティングで差別化。 | |
| GMS・スーパー | イオンなど。ローリングストックを意識した日常食品との併売や、PB防災セットの展開 17。 |
主要な市場成長ドライバーと阻害要因
- 成長ドライバー
- 大規模災害の発生: 能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発令後、防災食品や簡易トイレの需要が急増し、一部メーカーでは欠品や納期遅延が発生した 16。これは、需要が潜在的には存在するものの、具体的な脅威によって初めて顕在化することを示している。
- 気候変動による災害の激甚化: 気象庁の報告によれば、短時間強雨の発生頻度は年々増加傾向にあり 1、風水害への備えの重要性が増している。
- 政府・自治体の啓発活動: 首都直下地震や南海トラフ巨大地震の被害想定の公表 3 や、防災白書を通じた継続的な呼びかけが、国民の防災意識を喚起する。
- 阻害要因
- 防災意識の風化: 災害への関心は時間とともに薄れる傾向がある。災害直後に急増した需要は、平時には急速に冷え込み、安定的な市場成長を妨げている 19。
- コスト負担感: ミドリ安全の調査では、防災食を備蓄しない最大の理由として「お金がかかる」が28.1%を占めている 6。
- 物理的・心理的障壁: 「置き場所がない」20、「何を備えれば良いか分からない」6、「賞味期限の管理が面倒」21 といった物理的・心理的負担が、備蓄行動への高いハードルとなっている。
業界の主要KPIベンチマーク分析
個人向け防災市場の成熟度を測る上で、以下のKPIは極めて重要である。
- 主要品目の備蓄実施率(世帯ベース):
- 防災食: 「少しでも備えている」世帯は約59.0% 6。しかし、「家族全員が3日以上対応できる量」を備えているのは12.0%に過ぎない 23。
- 飲料水: 食料品と合わせた備蓄率は約60% 24。
- 簡易トイレ: 備蓄率は約30.6% 6。能登半島地震でその重要性が再認識されたものの、備蓄は依然として進んでいない。
- 平均備蓄日数と政府推奨とのギャップ:
- 政府は大規模災害に備え「最低3日分、推奨1週間分」の家庭備蓄を呼びかけている 25。しかし、多くの家庭では3日分すら確保できておらず、特に大都市圏でのライフラインの長期停止リスクを考慮すると、このギャップは深刻な脆弱性を示している。
- 世帯当たりの年間防災関連支出額:
- 現実: 実際の年間支出額は平均で数千円から1万円程度に留まる(インテージ調査:2,892円 19、住友生命調査:10,292円 27)。
- 理想: 一方で、十分な対策に必要だと考える費用(理想)は、平均で39,662円(住友生命調査)27 にも上り、理想と現実の間に約3万円もの巨大なギャップが存在する。このギャップは、単なる価格の問題ではなく、現在の防災用品が提供する価値が、消費者の支出意欲を喚起できていない「価値提案の失敗」を示唆している。消費者は、年に一度使うかどうかわからない「死に金」ではなく、日常的にも便益をもたらす「生きた投資」を求めている。このギャップこそが、フェーズフリー戦略が狙うべき最大の市場機会である。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
個人向け防災業界は、政治、経済、社会、技術、法規制、環境といった多岐にわたるマクロ環境要因から強い影響を受ける。PESTLEフレームワークを用いてこれらの要因を分析し、事業戦略上の機会と脅威を特定する。
政治(Politics)
- 大規模災害の被害想定と対策: 政府の中央防災会議が公表する首都直下地震 3 や南海トラフ巨大地震 5 の被害想定は、国民の危機意識を直接的に刺激し、防災用品への関心を高める最大の政治的ドライバーである。特に、首都直下地震ではライフライン(電力、水道、通信)が1週間停止するシナリオが示されており 3、在宅避難に必要な製品(ポータブル電源、簡易トイレ、備蓄水)の重要性を浮き彫りにしている。
- 防災ガイドラインと推奨品目: 内閣府や各自治体が発行する防災ガイドラインは、消費者が「何を備えるべきか」を判断する際の基準となる。これらのガイドラインで推奨される品目は、市場におけるデファクトスタンダードとなりやすく、メーカーの商品開発戦略に大きな影響を与える。
- 補助金・助成金制度: 自治体が実施する家具転倒防止器具や感震ブレーカーの設置に対する補助金は、特定の製品カテゴリーの需要を直接的に創出する。これらの制度と連携したマーケティングは有効な販売戦略となり得る。
経済(Economy)
- 景気変動と可処分所得: 景気後退やインフレによる可処分所得の減少は、防災用品への支出、特にポータブル電源やパーソナルシェルターといった高額商品の購入意欲を減退させる。実際に、防災食を備えない最大の理由として「お金がかかる」ことが挙げられており 6、市場はマクロ経済の動向に敏感である。
- 災害による経済損失と復興需要: 大規模災害はサプライチェーンの寸断や生産活動の停止を通じて甚大な経済損失をもたらす 3。一方で、被災後の復旧・復興プロセスでは、住宅再建やインフラ整備に関連する特需が発生する。
社会(Society)
- 人口動態の変化: 日本社会が直面する高齢化、単身世帯・核家族化の進展は、防災ニーズの多様化と個別化を加速させている。2019年時点で65歳以上の一人暮らし世帯は736万世帯を超え 28、これらの世帯では、少量で調理が簡単な備蓄食、軽量で操作が容易な防災グッズ、そして社会的孤立を防ぐための安否確認や見守りサービスへの需要が高まっている 29。
- 防災意識の波と価値観のシフト: 災害直後に急上昇し、平時には急速に低下する「防災意識の波」は、業界が乗り越えるべき最大の課題である 19。この課題を解決する鍵が、「フェーズフリー」という新しい価値観の浸透にある。アスクルの調査では、フェーズフリーの認知度はまだ7.4%と低いものの 31、コンセプト認知後の商品購入意向は54.3%に達しており 32、そのポテンシャルの高さを示している。また、日常の食料品を備蓄に回す「ローリングストック法」の実践率も24.6%と過去最高を記録しており 6、消費者が「特別な備え」から「日常の延長線上にある備え」へと意識を転換しつつあることがうかがえる。
- コミュニティの変容: 従来、地域の消防団や自治会が担ってきた「共助」の機能は、地域コミュニティの希薄化により低下している。その一方で、SNSや専用アプリを通じたデジタルコミュニティが、安否確認や情報共有の新たな担い手として台頭しており、ここに新たなサービス機会が生まれている。
技術(Technology)
- 予測技術の高度化: AIやスーパーコンピュータの活用により、地震動や津波、洪水などの災害予測精度は飛躍的に向上している 33。これにより、より精緻なハザードマップの作成や、個人レベルでのリスク評価が可能になりつつある。
- 情報伝達の進化とリスク: 緊急地震速報やJアラート、そして多様な防災アプリが、リアルタイムでの情報伝達を可能にした。しかし、SNSの普及は、デマや誤情報が瞬時に拡散するリスクも増大させており、信頼性の高い情報を選別・提供するサービスの重要性が高まっている。
- 製品技術の革新:
- 食品: フリーズドライ(アルファ米)やレトルト技術の進化により、5年以上の長期保存が可能で、かつ美味しい備蓄食が実現している 35。
- 電源: リチウムイオン電池技術の進歩は、ポータブル電源の大容量化・小型化・低価格化を牽引し、在宅避難の可能性を大きく広げた。
- IoT: スマートメーターやスマートホーム機器と連携し、電力使用状況から在宅状況や安否を推定するサービスや、河川やため池に設置したIoTセンサーで水位を遠隔監視するシステム 36 など、新たな防災ソリューションが生まれている。
法規制(Legal)
- 関連法規: 食品衛生法(賞味期限やアレルギー表示)、消防法(住宅用火災警報器の設置義務)、建築基準法(耐震基準)などが、製品の安全性や品質を担保する上で重要な役割を果たしている。これらの法規制の変更は、製品仕様の見直しを企業に要求する可能性がある。
環境(Environment)
- 気候変動の影響: 地球温暖化に伴う気候変動は、極端な気象現象の頻度と強度を増大させている。気象庁のデータによると、1時間降水量50mm以上の短時間強雨の年間発生回数は、1976-1985年の平均約226回に対し、2015-2024年には約334回と約1.5倍に増加している 1。この傾向は今後も続くと予測されており 2、台風や豪雨による洪水・土砂災害リスクの増大は、水害対策関連商品への恒常的な需要を生み出す。
- サステナビリティへの要請: 防災備蓄の推進は、一方で賞味期限切れによるフードロスという環境問題を引き起こす。年間数千万食にのぼるとされる備蓄食の廃棄は、SDGsの観点からも看過できない課題である。この問題への対応として、ローリングストックの推奨や、期限が近づいた備蓄食をフードバンクへ寄付する取り組み 39 が企業に求められており、環境配慮の姿勢が企業価値を左右する要因となりつつある。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
個人向け防災業界の収益性と競争の力学をマイケル・ポーターの五力分析フレームワークを用いて分析する。結論として、本業界は新規参入の脅威と代替品の脅威が高く、競争が激しい「魅力度の低い」構造にあるが、競争のルール自体が変化する過渡期にあり、新たな戦略的ポジショニングの機会が存在する。
供給者の交渉力:中程度
供給者の交渉力は、部品や原材料によって大きく異なる。
- 交渉力が弱い領域: 備蓄食品の原材料(米、小麦粉など)や飲料水の採水元、防災グッズの多くを構成するプラスチックや繊維素材は、供給元が多数存在するコモディティであり、供給者の交渉力は限定的である。
- 交渉力が強い領域: 一方で、ポータブル電源の性能を決定づけるリチウムイオン電池は、CATL(中国)、LG Energy Solution(韓国)、Samsung SDI(韓国)といった特定のアジア企業が世界市場で高いシェアを握っている 41。これらの大手電池メーカーは、技術力と生産規模を背景に、ポータブル電源メーカーに対して比較的強い交渉力を持つ。サプライチェーンにおけるこのボトルネックは、価格や供給安定性におけるリスク要因となる。
買い手の交渉力:平時は高く、災害時は低い
買い手である個人消費者の交渉力は、状況によって劇的に変化する。
- 平時(交渉力:高): 平時において、消費者は多数の選択肢(ブランド、製品、販売チャネル)の中から比較検討できるため、価格感度が高い。スイッチングコストもほぼ存在せず、小売業者のPB商品との価格競争も激しいため、買い手の交渉力は強い。しかし、「何をどれだけ備えれば良いか分からない」という情報格差も大きく、専門家や信頼できるブランドの推奨に影響されやすい側面も持つ。
- 災害時(交渉力:低): 大規模災害が発生すると、状況は一変する。需要が供給を爆発的に上回り、特定の商品(水、簡易トイレ、電池など)に買い注文が殺到する。このパニックバイ状況下では、消費者の価格感度は著しく低下し、入手できること自体が最優先されるため、買い手の交渉力は一時的に無力化される。
新規参入の脅威:高い
本業界は、異業種からの参入障壁が比較的低く、常に新たな脅威に晒されている。特に、既存の競争ルールを根本から変える力を持つプレイヤーの参入が相次いでいる。
- ライフスタイル提案型企業: 無印良品が展開する「いつものもしも」シリーズ 43 は、その代表例である。彼らは「防災用品」を売るのではなく、「万が一の時にも役立つ、いつもの暮らしの品」というコンセプトを提案する。これにより、機能や価格といった従来の競争軸を無効化し、自社の強力なブランドイメージと世界観で顧客を惹きつけている。同様に、ニトリなどのホームファニシング企業も、その流通網と商品開発力を活かして容易に参入可能である。
- アウトドアブランド: スノーピーク 45 やモンベル 47 といったアウトドアブランドは、高品質・高機能・高デザイン性を兼ね備えた製品群をすでに保有している。彼らの製品は、過酷な自然環境での使用を前提としているため、本質的に防災用途との親和性が高い。「野遊びが防災になる」というスノーピークのコンセプト 46 に見られるように、彼らは防災をライフスタイルの一部として捉え、高価格帯であっても熱心なファン層に支えられた高付加価値市場を形成している。
- IT企業: ヤフー(Yahoo!防災速報)や特務機関NERVのようなIT企業は、防災アプリや情報サービスという「非モノ」の領域で市場に参入し、数百万~数千万規模のユーザーベースを確立している。彼らはモノの製造・販売は行わないが、顧客との最大の接点を押さえることで、将来的に防災市場全体のプラットフォーマーとなる可能性を秘めている。
代替品の脅威:中程度から高い
専用の防災用品を購入するのではなく、他の手段でリスクに備えるという「代替」の動きは、市場の根幹を揺るがす脅威である。
- ローリングストックの実践: 消費者が日常的に購入する食品(缶詰、レトルト食品、パスタ等)や日用品(カセットコンロ、トイレットペーパー、乾電池)を少し多めにストックする「ローリングストック」は、最も強力な代替品である。この習慣が広く普及すれば、「長期保存専用の防災食」や「防災セット」の必要性は相対的に低下する。ローリングストックの実践率は年々高まっており 6、この脅威は看過できない。
- 防災保険や共済への加入: これは「モノの備え」を直接代替するものではないが、「災害リスクへの対処法」という広い視点で見れば代替の選択肢となり得る。物理的な備えを最小限にし、経済的な損失の補填に重点を置くという考え方である。ただし、生命や安全を直接守ることはできないため、補完的な役割に留まることが多い。
業界内の競争:高い
業界内には多様なプレイヤーがひしめき合い、競争は激化している。
- 専門メーカー間の競争: 尾西食品(アルファ米)やカゴメ(長期保存野菜飲料)35 のように、特定分野で高い技術力とブランドを持つ専門メーカーが存在し、品質や機能で競争している。
- 総合型メーカーの価格攻勢: アイリスオーヤマや山善といった総合メーカーは、家電から生活用品まで多岐にわたる製品開発力と、国内外の生産拠点を活用したコスト競争力を武器に、特に防災セットなどのエントリー市場で大きなシェアを占めている。
- 小売チャネルの台頭: カインズ 50 やイオン 17 といった大手小売業者は、PB(プライベートブランド)商品の開発を強化している。これにより、メーカーから商品を仕入れて販売するだけでなく、自らがメーカーとして競争に参加し、価格競争をさらに激化させている。
この分析から導かれる戦略的示唆は明確である。伝統的な「防災用品」のスペック競争に留まっていては、価格競争と異業種からの侵食によって収益性は低下する一方である。競争の主戦場が「製品のスペック」から「ライフスタイルへの提案力」へと移行している現実を直視し、自社の提供価値を再定義することが、この厳しい競争環境を生き抜くための唯一の道である。
第5章:バリューチェーンとエコシステム分析
バリューチェーン分析:価値の源泉は「モノ」から「コト」へ
個人向け防災業界のバリューチェーンは、顧客が求める価値の変化に伴い、大きな変革期を迎えている。
伝統的なバリューチェーン
従来の業界の価値連鎖は、製品(モノ)を製造し、顧客に届けるまでの一方向的なプロセスであった。
商品企画・開発(長期保存性、機能性重視) → 原材料調達 → 製造 → 在庫管理・物流(長期保管・賞味期限管理) → 販売・マーケティング(啓発活動含む) → アフターサービス(限定的)
このモデルにおける価値の源泉は、主に「製造」段階における食品の長期保存技術や、製品の機能性にあった。しかし、このモデルは災害発生後の特需に依存し、平時の需要喚起力が弱いという構造的課題を抱えていた。
価値の源泉のシフト
現在、価値の源泉は、製品そのもの(モノ)から、それを利用することで得られる体験や便益(コト)へと明確にシフトしている。消費者は単に「5年保存できる水」を求めているのではなく、「水がなくなるかもしれないという不安からの解放」や「備蓄を管理する煩わしさからの解放」を求めている。
このシフトを象徴するのが、防災テック・スタートアップであるLaspyが提供するサブスクリプション型サービス「あんしんストック」である 53。このサービスは、備蓄品そのものを販売するのではなく、「備蓄品の選定・調達・保管・賞味期限管理・入れ替え」という一連のプロセスを月額料金で代行する 55。顧客は、自宅の収納スペースを圧迫することなく、常に最適な備えを維持できる「安心」という価値(コト)を購入している。これは、バリューチェーンの「在庫管理」や「アフターサービス」といった部分を収益化する、全く新しいビジネスモデルである。
この変化は、業界のあらゆる企業にバリューチェーンの再構築を迫っている。価値はもはや「モノ」に宿るのではなく、顧客との継続的な関係性の中に生まれる。
エコシステム分析:単独から連携へ
個人向け防災は、一社単独で完結できる事業ではない。その実効性を高めるためには、多様なプレイヤーが連携するエコシステムの構築が不可欠である。
エコシステムの構成プレイヤー
このエコシステムは、以下のような官民の多様な主体によって構成されている。
- 民間企業: メーカー、卸売、小売(実店舗/EC)、IT企業(アプリ開発、AI)、保険会社、物流会社、警備会社
- 公的機関: 国(内閣府、気象庁等)、地方自治体(都道府県、市区町村)
- 専門家・団体: 防災士、危機管理アドバイザー、大学・研究機関、NPO/NGO、地域コミュニティ(自治会、マンション管理組合)
- メディア: テレビ、新聞、ウェブメディア
エコシステムの現状と災害時の機能不全
平時において、これらのプレイヤー間の連携は限定的であり、それぞれが独立して活動していることが多い。しかし、ひとたび大規模災害が発生すると、このエコシステムは深刻な機能不全に陥る。
- サプライチェーンの寸断: 道路や港湾の損壊により、物流網は麻痺する 57。メーカーが製品を製造できても、それを被災地の小売店や避難所に届けることができなくなる。東日本大震災では、サプライチェーンの寸断が広範囲に及び、被災地以外でも商品の供給が滞る事態が発生した 57。
- 情報の錯綜: 通信インフラの途絶や輻輳により、正確な被害状況や避難者ニーズの把握が困難になる。SNSではデマが拡散し、行政からの公式情報も届きにくくなる。
- ラストワンマイル問題: プッシュ型で避難所に送られた支援物資が、仕分けや配送の人員不足により、本当に必要としている人々の手元に届かないという問題が頻発する。
官民連携によるエコシステムの進化
こうした課題を克服するため、近年、デジタル技術を核とした官民連携(防災DX)の動きが加速している。2024年1月の能登半島地震では、防災DX官民共創協議会(BDX)などの民間デジタル人材が発災直後から被災地入りし、石川県のニーズに応じて活動した 59。具体的には、通信が途絶した地域に衛星インターネット「スターリンク」を設置して通信環境を確保したり 60、避難者情報を一元管理するデータベースや、Suicaを活用した避難者状況把握の仕組みを迅速に構築したりするなど、災害対応の高度化に大きく貢献した 59。
これらの動きは、将来の防災ビジネスが、単一企業のバリューチェーン効率化競争ではなく、多様なプレイヤーを巻き込み、データを連携させながら社会課題を解決する「エコシステムの設計・運営能力」によって勝敗が決まることを示唆している。自社をハブとして、いかに効果的なエコシステムを構築し、主導できるかが、次世代の競争優位性の源泉となるだろう。
第6章:顧客需要の特性分析
防災行動の背景にある顧客の深層心理と行動特性を理解することは、効果的な事業戦略を策定する上で不可欠である。本章では、消費者セグメンテーション、行動障壁、需要の変動性について分析する。
消費者セグメント分析
防災への意識と行動、そしてライフステージによって、顧客は複数のセグメントに分類できる。それぞれが抱える固有のニーズとKBF(Key Buying Factor:購買決定要因)を理解することが重要である。
| セグメント分類 | セグメント名 | 主な不安・ニーズ | KBF(購買決定要因) |
|---|---|---|---|
| 防災意識・行動別 | 無関心層 | 災害リスクは認識しているが、切迫感がなく行動に移さない。「まだ大丈夫」という正常性バイアスが強い。 | きっかけ(災害報道、キャンペーン)、手軽さ、低価格 |
| 潜在的不安層 | 漠然とした不安はあるが、「何を揃えればいいか分からない」という知識不足が行動を阻害している 6。 | 分かりやすさ(専門家推奨のセット)、信頼性、網羅性 | |
| 積極的備蓄層 | 災害リスクへの意識が高く、情報収集や備蓄を能動的に行う。より高度で専門的な製品・情報を求める。 | 機能性、専門性、最新技術、カスタマイズ性 | |
| ライフステージ・世帯構成別 | 単身世帯(若年/高齢) | 備蓄スペースが限られる。災害時の孤立や、助けを求められないことへの不安 30。 | コンパクトさ、省スペース、デザイン性、簡便さ、共助サービス |
| ファミリー(乳幼児/学齢期) | 子どもの安全と健康が最優先。アレルギー対応食、粉ミルク、おむつ、衛生用品へのニーズが高い 63。 | 安全性(アレルギー対応)、子どもの嗜好、栄養バランス、知育要素 | |
| 高齢者のみ世帯 | 体力的な問題から避難行動に不安。持病の薬の確保、調理が不要な食事、安否確認の仕組みが重要 29。 | 少量、柔らかさ、健康配慮(減塩等)、操作の容易さ、見守り機能 | |
| ペット飼育世帯 | ペットとの同行避難、ペットフードや水の備蓄、避難所での受け入れ体制に強い不安。92.7%が不安を感じている 64。 | ペットフードの長期保存、携帯用トイレ、同行避難情報サービス |
防災行動の障壁(ボトルネック)分析
多くの人々が「防災は必要だ」と認識しているにもかかわらず、なぜ実際の備蓄行動に繋がらないのか。複数の消費者調査から、共通する5つの強力な障壁(ボトルネック)が浮かび上がってくる。
- コストの壁:「お金がかかる」
ミドリ安全の調査をはじめ、多くの調査で備蓄をしない最大の理由として挙げられている 6。年に一度使うかどうかわからないものに数万円を投資することへの抵抗感は根強い。 - 知識の壁:「何を揃えればいいか分からない」
情報が氾濫する中で、自分の家族構成や住環境に本当に必要なものを、適切な量だけ選ぶことは専門知識を要するタスクであり、多くの消費者がこの段階で挫折する 6。 - スペースの壁:「置き場所がない」
特に都市部のマンションなど、限られた居住スペースの中で、数日分の水や食料、かさばる防災用品の保管場所を確保することは物理的に困難である 20。 - 手間の壁:「面倒くさい」
防災用品を選び、購入し、保管場所を整理し、さらに定期的に賞味期限をチェックして入れ替えるという一連の作業は、多忙な現代人にとって大きな心理的負担(手間)となる 22。 - 心理の壁:「まだ大丈夫」
災害が起きていない平時においては、「自分は大丈夫」「まだ時間がある」という正常性バイアスが働き、行動が先延ばしにされがちである 22。
これらの障壁を分析すると、消費者が直面している真の課題は、個別の製品や価格にあるのではなく、「防災について考え、判断し、管理し続けることの全体的な負荷」そのものであることがわかる。したがって、この市場で成功する製品・サービスとは、これらの障壁、特に「意思決定と管理の負荷」を劇的に低減させるソリューションでなければならない。
需要の変動性:災害特需の波をどう乗り越えるか
個人向け防災市場の需要は、平時は低位で推移し、大規模災害の発生やメディアでの報道をきっかけに急増(パニックバイ)、その後急速に沈静化するという、極めて変動性の高いパターンを示す 16。この「需要の波」は、メーカーや小売業者にとって深刻な経営課題となる。
- サプライチェーンへの影響: 需要急増時には欠品や納期遅延が発生し、販売機会を損失する。一方、需要沈静化後には過剰在庫を抱えるリスクがある。
- マーケティングへの影響: 災害への恐怖心を煽るだけのマーケティングは、平時には響かず、需要の波を助長するだけである。
この需要の波をマネジメントし、事業を安定させるためには、需要を平準化する戦略が不可欠である。具体的には、防災の日(9月1日)や東日本大震災の発生月(3月)に合わせた計画的な販促キャンペーンや、季節性のあるリスク(夏場の台風・水害、冬場の停電・寒さ対策)に合わせた提案、そして何よりも「フェーズフリー」のコンセプトを通じて、防災を日常の購買行動に組み込むアプローチが求められる。
第7章:業界の内部環境分析
企業の持続的な競争優位の源泉を特定するため、VRIOフレームワークを用いて業界の経営資源とケイパビリティを分析する。また、事業成長の鍵となる人材や生産性の動向についても考察する。
VRIO分析:持続的競争優位の源泉は何か?
VRIOフレームワークは、経営資源やケイパビリティが持つ価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability)、そしてそれを活用する組織(Organization)の4つの観点から競争優位性を評価する。
| 経営資源/ケイパビリティ | 価値 (V) | 希少性 (R) | 模倣困難性 (I) | 組織 (O) | 競争優位性への示唆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品の長期保存技術 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 持続的競争優位 尾西食品のアルファ米技術やカゴメの長期保存野菜加工技術 68 など、特許に裏付けられた独自技術は、他社が容易に模倣できない価値の源泉となる。 |
| 全国規模の流通・在庫管理網 | ◎ | ○ | △ | ○ | 一時的競争優位 イオン 17 や大手ホームセンターが持つ物流網は価値があり希少だが、Amazonなど他の巨大プレイヤーも同様の能力を持つため、模倣困難性は中程度。 |
| 高いブランド信頼性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 持続的競争優位 無印良品 43 やスノーピーク 46 が長年かけて築き上げたブランドイメージと顧客との信頼関係は、一朝一夕には模倣できず、極めて強力な競争優位となる。 |
| 防災士等の専門家ネットワーク | ○ | △ | △ | △ | 競争均衡 専門家との連携は価値があるが、排他的な関係を築くことは難しく、多くの企業が同様のネットワークを構築可能。 |
| 大規模な顧客データ(EC会員等) | ◎ | ◎ | ○ | △ | 潜在的な競争優位 Amazonや楽天が保有する購買履歴や個人属性データは極めて価値が高く希少。これを防災分野で活用する組織と戦略が伴えば、他を圧倒するパーソナライズサービスが可能になる。 |
この分析から、本業界における持続的な競争優位の源泉は、単なる製造技術や物流網といったハードな経営資源から、ブランド信頼性や顧客データといったソフトな経営資源へとシフトしていることがわかる。特に、将来の競争では、収集した顧客データを活用し、パーソナライズされた価値提案へと転換できる組織能力が決定的な差を生むだろう。
人材動向:デジタル人材の獲得競争がボトルネックに
個人向け防災業界で求められる人材ポートフォリオは、市場の変化を反映して大きく変わりつつある。
- 需要が急増する専門人材:
- データサイエンティスト/AIエンジニア: 災害リスク予測、パーソナライズド・レコメンデーション、需要予測モデルを構築・運用する人材。
- UI/UXデザイナー: 防災アプリやWebサービスにおいて、複雑な情報を分かりやすく伝え、顧客が直感的に使える体験を設計する人材。
- デジタルマーケター: 顧客データを分析し、セグメントごとに最適化されたコミュニケーション戦略を実行する人材。
- 従来から求められる専門人材:
- 防災士、危機管理アドバイザー
- 食品開発技術者(特に長期保存、栄養学)
- 気象予報士
人材獲得における課題:
特に需要が急増しているデータサイエンティストやUI/UXデザイナーといったデジタル人材は、IT業界、コンサルティング業界、金融業界など、あらゆる産業で引く手あまたである。伝統的な製造業が中心であった防災業界の給与水準や企業文化では、これらのトップタレントを惹きつけることは極めて困難であり、人材の確保と定着が事業成長の最大のボトルネックとなる可能性が高い。外部の専門企業とのアライアンスや、優秀なスタートアップのM&Aも、人材獲得の有効な選択肢として検討すべきである。
労働生産性/開発効率
- 製造リードタイムとコスト構造: 備蓄食のような長期保存品は、計画生産が基本となるが、災害特需による需要の急変動に対応するため、サプライチェーンの柔軟性が求められる。リードタイムの短縮と、平時の稼働率を維持しながら特需に対応できる生産体制の構築が課題である。
- 賞味期限管理と在庫最適化: 長期にわたる在庫保管は、倉庫コストや管理コストを増大させる。また、賞味期限切れによる廃棄ロスは直接的な損失となる。AIによる需要予測を活用した在庫の最適化や、サブスクリプションモデルによる計画的な出荷は、これらの非効率性を改善し、生産性を向上させる上で極めて有効である。
第8章:AIの影響とインパクト(重点分析章)
人工知能(AI)、特に生成AIの進化は、個人向け防災業界のバリューチェーン全体に破壊的な変化をもたらし、これまでにない新たな事業機会を創出する。AIは単なる業務効率化ツールではなく、業界のビジネスモデルそのものを顧客中心へと再定義する中核技術である。
需要予測とマーケティングの革新
- 超高解像度なリスク予測とピンポイント・マーケティング:
AIは、気象データ、過去の災害履歴、地形データ、さらにはSNS上のリアルタイム情報を統合的に分析し、災害リスクを極めて高い解像度で予測する 33。従来の「〇〇市は水害リスクが高い」というレベルから、「〇〇市△△町3丁目の来週の浸水確率は85%」といったピンポイントでの予測が可能になる。この予測に基づき、「浸水対策セットのご準備はできていますか?」といった、個々の世帯に最適化されたプッシュ型のマーケティングが実現する。これにより、防災無関心層に対しても、自分事としてリスクを認識させ、行動を喚起することが可能になる。 - 災害時のリアルタイム需要検知とサプライチェーン連携:
災害発生時、Twitter(X)などのSNS上には「水が足りない」「おむつが欲しい」「〇〇地区が孤立している」といった被災者の生の声が溢れる。AIの自然言語処理技術は、これらの膨大なテキストデータをリアルタイムで解析し、どの地域で何が不足しているかを瞬時に特定する 33。この需要情報は即座にサプライチェーンにフィードバックされ、支援物資のミスマッチを防ぎ、最も必要とされる場所に、最も必要とされる物資を届けることが可能になる。
パーソナライズド・レコメンデーションの実現
- 「あなただけの最適備蓄リスト」の自動生成:
AIは、顧客がアプリなどを通じて入力した情報(家族構成、年齢、性別、アレルギーの有無、持病、ペットの種類)と、外部データ(居住地のハザードマップ、住宅種別(戸建て/マンション))を統合分析する。これにより、「4人家族(夫40代、妻30代、長男5歳(小麦アレルギー)、長女2歳)、木造戸建て、海抜5m地域」といった具体的な世帯に対し、「あなただけの最適備蓄リスト」と、それに紐づく「あなただけの避難計画」を自動で生成・提案する。これは、消費者の「何を揃えればいいか分からない」という最大の障壁を根本から解消する画期的なサービスとなる。 - 生成AIによる24時間365日対応の「防災相談チャットボット」:
生成AIを活用した対話型チャットボットは、ユーザーからの自由形式の質問に対して、24時間365日、即座に、かつ個別具体的に回答する 34。例えば、「このポータブル電源で、うちの冷蔵庫はどのくらい動かせますか?」や「生後6ヶ月の赤ちゃんの離乳食備蓄で気をつけることは?」といった専門的な質問にも、データベースと連携して的確なアドバイスを提供する。これにより、顧客満足度を飛躍的に向上させると同時に、コールセンターの負荷を大幅に軽減できる。
製品開発の高度化
- AIによる製品仕様の最適化シミュレーション:
備蓄食品の開発において、AIは「栄養バランス」「味」「コスト」「5年以上の保存性」といった複数の制約条件を満たす最適な原材料の組み合わせと配合比率を、膨大なシミュレーションを通じて導き出す。これにより、従来は開発者の経験と勘に頼っていた開発プロセスをデータドリブン化し、開発期間の短縮と製品品質の向上を両立させる。 - 生成AIによるフェーズフリー製品のデザイン:
インテリアに溶け込むフェーズフリー製品のデザインは、今後の重要な差別化要因となる。生成AIは、SNSやインテリア雑誌から最新のデザイントレンドを学習し、「北欧風デザインの備蓄食パッケージ」や「ミニマルデザインの防災ツール」といったデザイン案を数秒で数百パターン生成する。これにより、デザイナーは創造的な作業に集中でき、市場のニーズに迅速に対応した製品開発が可能になる。
サプライチェーン・ロジスティクスの最適化
- AIによる平時の在庫最適化と賞味期限管理:
AIは、過去の販売データ、季節変動、メディア露出、そして将来の災害リスク予測を統合的に分析し、全国の物流拠点における最適な在庫量を品目ごとに算出する。これにより、欠品による機会損失と過剰在庫による廃棄ロスの双方を最小化する。また、賞味期限管理を自動化し、期限が近づいた製品をローリングストック用としてECサイトで割引販売したり、フードバンクに自動で寄付手続きを行ったりするシステムも構築可能である。 - 災害時のダイナミック・ロジスティクス:
災害発生時、AIは刻々と変化する被災状況(道路の寸断、橋の崩落、インフラの停止)をリアルタイムで把握し、支援物資を目的地まで届けるための最適な物流ルートを動的に再計算する。ドローン配送など、新たな輸送手段との連携も視野に入れ、人命救助の「72時間の壁」の中で、最も効率的なロジスティクスを実現する。
情報サービスの信頼性向上
- AIによるデマ・フェイクニュースの自動フィルタリング:
災害時には、人々の不安を煽るデマやフェイクニュースがSNS上で急速に拡散される。AIは、情報の発信源、拡散パターン、内容の信憑性を瞬時に分析し、信頼性の低い情報を自動でフィルタリングする。これにより、ユーザーは混乱することなく、自治体や公的機関が発信する信頼できる避難情報や救援情報に集中することができる。
これらのインパクトを統合すると、AIは「商品を売る」という従来のビジネスモデルを、「顧客一人ひとりの安全を継続的に守り続ける」というリカーリング・レベニュー(継続収益)型のサービスモデルへと転換させる、まさに中核的な駆動力となる。企業はAIを活用することで、顧客との関係を深め、LTV(顧客生涯価値)を最大化し、災害特需の波に左右されない安定した事業基盤を構築することが可能になるのである。
第9章:主要トレンドと未来予測
これまでの分析を踏まえ、今後3~5年で個人向け防災市場を形成するであろう6つの主要なトレンドと、その先の未来像を予測する。
1. フェーズフリーの主流化:防災が日常に溶け込む未来
「防災用品」という特別なカテゴリーは徐々にその輪郭を失い、多くの日常品が「もしも」の時の機能を当たり前に備えるようになるだろう。「有事のため」という非日常的な訴求ではなく、「普段も便利で、いざという時も頼りになる」という二重の価値提案が、製品選択のスタンダードとなる。
- 予測される変化:
- インテリア化: 備蓄食や水は、キッチンやリビングに置いても景観を損なわない、洗練されたパッケージデザインが一般化する。
- 多機能化: アウトドア用品と防災用品の境界はさらに曖昧になる。ポータブル電源はキャンプ、車中泊、DIY、そして停電対策という複数の顔を持つことが常識となる。
- KBFの変化: 「保存期間」や「カロリー」といった機能的スペックに加え、「デザイン性」「日常での使いやすさ」「省スペース」が重要な購買決定要因となる。
2. サブスクリプション・モデルの普及:「所有」から「利用」へ
備蓄品を一度購入して「所有」するモデルから、必要なサービスを月額で「利用」するサブスクリプション・モデルへの移行が加速する。これは、消費者の「管理が面倒」「何を買えばいいか分からない」という根源的な課題に対する最も合理的な解決策である。
- 予測されるサービス:
- 備蓄品の定期配送・自動入替: AIが各家庭に最適な備蓄品を選定し、賞味期限が切れる前に新しいものを届け、古いものを回収する(フードバンク等へ寄付)サービスが普及する 53。
- 防災コンシェルジュ・サービス: 月額料金で、AIによる最新のリスク分析、パーソナライズされた避難計画の更新、家族の安否確認機能などを包括的に提供するサービスが登場する。
3. 防災テック(Bosai-Tech)の隆盛:スタートアップが市場を革新
AI、IoT、ドローン、ビッグデータといった先進技術を活用し、防災・減災領域の課題解決を目指す「防災テック」スタートアップが次々と登場し、市場に新たなダイナミズムをもたらす。
- 注目される領域:
- 超個別リスク予測: Arithmer社が開発する「浸水AI」のように、特定の地点の浸水リスクを高精度で予測するサービス 69。
- 備蓄管理・シェアリング: Laspy社のように、備蓄のアウトソーシングやコミュニティ内でのシェアリングを可能にするプラットフォーム 53。
- 災害状況のリアルタイム把握: ドローンや衛星画像をAIで解析し、被害状況を即座に可視化するサービス 69。
4. 「食」の高度化:「生存」から「QOL(生活の質)の維持」へ
災害時の食事は、「生き延びるためのカロリー摂取」という最低限の役割から、「困難な状況下でも、心身の健康とQOLを維持するための重要な要素」へとその位置づけを変える。
- ニーズの高度化:
- 美味しさと日常性: 「非常食だから味が落ちるのは仕方ない」という妥協は許されなくなり、日常食と遜色ない美味しさが求められる。
- 多様な食への対応: アレルギー対応はもちろんのこと、ヴィーガン、ベジタリアン、ハラル、あるいは介護食や離乳食など、個々の食のニーズに対応した製品ラインナップが不可欠となる。
- 栄養バランス: 災害時の野菜不足を補うためのビタミンや食物繊維が豊富なスープ 35 など、健康維持を目的とした栄養設計が重要視される。
5. 「共助」のプラットフォーム化:デジタルの力で地域の繋がりを再構築
地域コミュニティの希薄化という社会課題に対し、デジタル技術が新たな「共助」の形を創出する。
- 予測されるプラットフォーム:
- 備蓄品シェアリング: マンションの居住者間や近隣住民同士で、ポータブル電源や工具、簡易トイレといった高価またはかさばる備蓄品を共同で備蓄・シェアするためのアプリが登場する。
- デジタル安否確認: 災害発生時に、地域の住民が互いの安否を迅速に確認し、助けが必要な世帯(特に高齢者や障害者)の情報を共有するための地域限定SNSやプラットフォームが普及する。
6. パーソナルシェルター市場の顕在化:究極の「自助」への投資
自然災害だけでなく、国際紛争や新たなパンデミックなど、多様化する脅威への備えとして、富裕層を中心に自宅の安全性を極限まで高める需要が顕在化する。
- 市場の萌芽:
- 自宅設置型シェルター: 地震の揺れや飛来物から身を守るための、室内設置型の簡易シェルターや、庭に設置する地下シェルターへの関心が高まる。
- 耐災リフォーム: 既存住宅に対し、耐震補強だけでなく、洪水対策の防水壁や、停電・断水に備えた蓄電池、井戸、ろ過装置などを設置する「耐災リフォーム」市場が形成される。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
個人向け防災市場における主要なプレイヤーをカテゴリー別に分類し、各社の戦略、強み・弱み、そして市場のメガトレンド(フェーズフリー、AI/デジタル化)への対応状況を比較分析する。
| プレイヤー名 | カテゴリー | 強み (VRIO) | 弱み | 製品/サービスポートフォリオ | ターゲット顧客 | フェーズフリー/AI戦略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | 総合型 | ・多岐にわたる製品開発力 ・強力な製造・物流網 ・価格競争力 | ・ブランドイメージのコモディティ化 ・デジタル戦略の遅れ | 防災セット、家具固定具、家電(LEDライト等)、保存水、アルファ米など幅広いラインナップ。 | 価格に敏感なマス層、エントリーユーザー。 | フェーズフリー: 家電や収納用品など日常品との連携を強化。 AI/デジタル: 現時点では限定的。ECサイトでの販売が中心。 |
| カゴメ | 食品・飲料 | ・「健康」を軸とした高いブランド信頼性 49 ・野菜加工に関する独自技術と研究開発力 68 | ・製品ラインナップが野菜関連に特化 | 「野菜一日これ一本 長期保存用」35、「野菜たっぷりスープ」73 など、栄養バランスを訴求した備蓄食。 | 健康志向の高い層、ファミリー層。 | フェーズフリー: 日常的な健康飲料・食品の延長線上に備蓄を位置づける戦略。 AI/デジタル: ビッグデータを活用した農業研究 49 を進めているが、顧客向けサービスへの応用はこれからの課題。 |
| Anker / Jackery / EcoFlow | 電源 | ・先進的なバッテリー技術 ・高いデザイン性とユーザービリティ ・強力なデジタルマーケティング力 | ・高価格帯 ・リチウムイオン電池の供給リスク | 大容量ポータブル電源、ソーラーパネル。アウトドアと防災の両シーンを訴求 74。 | アウトドア愛好家、ガジェット好き、在宅避難を想定する層。 | フェーズフリー: 防災を主目的としないアウトドア需要を開拓し、市場を創造。Ankerはデータドリブンな組織文化を持つ 76。EcoFlowはAIを活用した家庭用エネルギー管理システムを発表 77。 |
| 無印良品 | 異業種参入 | ・圧倒的なブランド世界観と顧客ロイヤリティ 43 ・全国規模の店舗網とEC | ・専門メーカーに比べた製品機能の限定性 | 「いつものもしも」をコンセプトに、日常に溶け込むデザインの防災セット、備蓄品、ツールを展開 44。 | 既存の無印良品ファン、ライフスタイルにこだわる層。 | フェーズフリー: コンセプトそのものがフェーズフリー戦略の最先端。防災を「暮らしの知恵」として提案。 AI/デジタル: Webサイトやアプリでの情報発信に留まる。 |
| カインズ | 小売チャネル | ・強力なPB商品開発力 ・広大な店舗網による顧客接点 ・DIY文化の醸成 | ・ECにおけるAmazon等との競争 | 「Kumimoku」などのPBで、収納用品から防災グッズまでトータルで提案。「自分らしい防災」を訴求 50。 | DIY層、ファミリー層、郊外の戸建て居住者。 | フェーズフリー: 収納やアウトドアといった日常の「コト」と防災を繋げた売り場作りと提案力が強み。 AI/デジタル: デジタル会員基盤を活用した顧客分析を進めている段階。 |
| Amazon | 小売チャネル | ・世界最大級の顧客基盤とデータ ・高度なレコメンドエンジン ・圧倒的な物流網 | ・PBのブランド力が限定的 ・専門的な提案力の欠如 | あらゆるメーカーの防災関連商品を網羅。定期的な「防災特集」ページで需要を喚起。 | 全ての消費者セグメント。 | フェーズフリー: 購買履歴からアウトドア用品と防災用品を関連付けて推奨。 AI/デジタル: AIによるレコメンデーションが最大の武器。顧客データを活用したパーソナライズ提案のポテンシャルは最も高い。 |
| Laspy | 防災テック | ・革新的なサブスクリプション・ビジネスモデル ・管理の手間を解消する明確な価値提案 | ・ブランド認知度の低さ ・事業規模の小ささ | 防災備蓄のアウトソーシングサービス「あんしんストック」を提供 53。 | BtoB(企業のBCP対策)やBtoBtoC(マンション管理組合)が中心。 | フェーズフリー: 該当せず(BtoB中心のため)。 AI/デジタル: 備蓄管理システムをクラウドで提供。ビジネスモデル自体がDXを体現している。 |
戦略的示唆
この比較分析から、いくつかの重要な示唆が浮かび上がる。
- 競争軸の多様化: もはや「価格」や「機能」だけで戦う時代ではない。「ライフスタイル提案力」(無印良品、カインズ)、「ブランド・コミュニティ」(アウトドアブランド)、「デジタル体験」(Anker、Amazon)、「サービスモデル革新」(Laspy)など、各社が異なる土俵で競争を繰り広げている。
- 「フェーズフリー」の重要性: 成功しているプレイヤーの多くは、意識的か無意識的かにかかわらず、フェーズフリーの考え方を取り入れている。防災を特別なイベントではなく、日常の延長と捉えることで、新たな顧客層の開拓に成功している。
- デジタル・ケイパビリティの格差: Ankerのようなデジタルネイティブな企業と、伝統的なメーカーとの間には、データ活用や顧客との直接的な関係構築(D2C)において大きな差が存在する。この格差は、AI時代においてさらに拡大する可能性が高い。
- プラットフォーマーの脅威: Amazonは、その圧倒的な顧客データとAI技術を背景に、将来的には防災市場における最強のプラットフォーマーとなるポテンシャルを持つ。メーカーは、単なる製品供給者として下請け化しないための戦略が急務である。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、個人向け防災市場における事業機会を最大化するための具体的な戦略的提言を行う。
今後3~5年で勝者と敗者を分ける決定的要因
個人向け防災業界の勝敗を分けるのは、もはや製品の機能的優位性ではない。以下の3つの能力こそが、未来の市場リーダーを決定づける要因となる。
- 顧客エンゲージメントの深化: 災害特需に依存する「一見さん」ビジネスから脱却し、顧客との継続的な関係を構築できるか。平時から顧客に寄り添い、ライフステージの変化やリスクの変化に応じて価値を提供し続けることで、LTV(顧客生涯価値)を最大化できる企業が勝者となる。
- データとAIの活用能力: 勘と経験に頼った製品開発やマーケティングから、データとAIを駆使したパーソナライズ戦略へと転換できるか。顧客一人ひとりの「分からない」「面倒くさい」を解消し、「あなただけの安心」をサービスとして提供できる企業が、圧倒的な競争優位を築く。
- エコシステムの主導権: 自社単独のバリューチェーンに固執せず、IT企業、保険会社、自治体、地域コミュニティといった多様なプレイヤーを巻き込み、新たな価値を共創するプラットフォームを構築・主導できるか。エコシステムのハブとなる企業が、業界のルールメーカーとなる。
これらに対応できない企業、すなわち、依然として「モノ」の売り切りモデルに依存し、顧客との関係が希薄で、データ活用に乏しい企業は、異業種からの参入者やデジタルネイティブな競合との価格競争に巻き込まれ、市場から淘汰される「敗者」となるだろう。
事業機会(Opportunity)と脅威(Threat)の特定
| 機会 (Opportunity) | 脅威 (Threat) | |
|---|---|---|
| 市場・顧客 | O-1: フェーズフリー市場の創造 防災無関心層を「ライフスタイル」を切り口に新規顧客として開拓する巨大な機会。 | T-1: 異業種からのディスラプション 無印良品やアウトドアブランドが、既存の競争ルールを無効化する脅威。 |
| 製品・サービス | O-2: パーソナライズド・サブスクリプション AIを活用し、「意思決定の負荷」という最大の顧客ペインを解消する高付加価値サービス市場。 | T-2: ローリングストックの一般化 専用防災用品の市場そのものが縮小し、日用品との境界がなくなるリスク。 |
| 競争環境 | O-3: セグメント特化によるニッチ市場開拓 高齢者、乳幼児ファミリー、ペット飼育世帯など、特定の深いニーズに応えることで高い収益性を確保。 | T-3: プラットフォーマーによる顧客接点の独占 AmazonやYahoo!が顧客データと接点を掌握し、メーカーが単なる製品供給者(下請け)となるリスク。 |
戦略的オプションの評価
上記の分析に基づき、取りうる戦略的オプションを4つ提示し、それぞれのメリット・デメリットを評価する。
| A: フェーズフリー製品による事業拡大 | B: AI防災テック・スタートアップの買収 | C: 異業種(保険・住宅)との提携 | D: 提言戦略(A+B+Cの統合) | |
|---|---|---|---|---|
| 戦略概要 | 自社の開発・製造能力を活かし、デザイン性の高いフェーズフリー製品群を拡充する。 | 先進的なAI技術とデジタル人材を持つスタートアップを買収し、一気に技術的優位を確立する。 | 保険会社や住宅メーカーと提携し、新たな販路と補完的なサービス(保険割引等)を提供する。 | AIを中核に、パーソナライズされたフェーズフリー製品とサービスをサブスクリプションで提供するプラットフォームを構築する。 |
| メリット | ・自社のコアコンピタンスを活かせる ・ブランドイメージ向上に直結 | ・開発時間の劇的な短縮 ・優秀なデジタル人材の獲得 | ・低リスクで新規顧客層へアクセス可能 ・新たな価値提案(安心のワンストップ提供) | ・持続的な競争優位の源泉を構築 ・安定した継続収益モデルへの転換 ・エコシステムの主導権獲得 |
| デメリット | ・開発・マーケティングへの大規模投資 ・強力な競合(無印良品等)との直接対決 | ・高額な買収費用と財務的負担 ・PMI(買収後の統合)の失敗リスク | ・提携先との主導権争い ・レベニューシェアによる利益率の低下 | ・最も複雑で実行難易度が高い ・多額の初期投資と長期的なコミットメントが必要 |
| 成功確率 | 中 | 中~高(対象企業による) | 中 | 高(実行できれば) |
最終提言:AI防災コンシェルジュを中核とした「パーソナライズド防災プラットフォーム」戦略
戦略概要
上記のオプション評価に基づき、最も持続的な成長と高い収益性をもたらす戦略として、オプションDの「AI防災コンシェルジュを中核としたパーソナライズド防災プラットフォーム戦略」を提言する。
これは、顧客一人ひとりのリスクとニーズをAIで継続的に分析し、最適な「フェーズフリー製品」のレコメンデーションと「備蓄管理サービス」を、サブスクリプションモデルで包括的に提供するものである。この戦略は、単なる製品販売から脱却し、顧客の「安心な暮らし」に寄り添うライフタイムパートナーへと自社を変革する試みである。
実行に向けた具体的なアクションプラン(概要)
| フェーズ | 期間 | 主要アクション | 主要KPI | 必要リソース |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1: 基盤構築 | 1年目 | ・AI/データサイエンスチームの組成(必要に応じて外部パートナー/M&Aも検討) ・無料の防災診断アプリをリリースし、顧客データ(パーミッションベース)の収集を開始 ・第一弾となるフラッグシップのフェーズフリーPB商品を市場投入 | ・アプリダウンロード数: 100万 ・アクティブユーザー数: 30万 ・データ収集同意率: 70% | ・AI/アプリ開発チーム(10-15名) ・プロダクト開発・マーケティング予算 ・データ基盤(DMP/CDP)構築 |
| Phase 2: サービス収益化 | 2-3年目 | ・備蓄品の定期配送と管理代行を含む、3段階のサブスクリプションプランを開始(例:ベーシック、ファミリー、プレミアム) ・大手損害保険会社と提携し、サービス加入者向けの地震保険料割引プログラムを共同開発 | ・有料会員数: 5万 ・月次経常収益(MRR): 1.5億円 ・顧客解約率(Churn Rate): 5%未満 | ・物流・フルフィルメントパートナーとの連携強化 ・カスタマーサクセス部門の設立 ・アライアンス担当チーム |
| Phase 3: エコシステム拡大 | 4-5年目 | ・プラットフォームのAPIを公開し、他社メーカーの優れた防災製品やサービスも販売可能にする(マーケットプレイス化) ・自治体と連携し、地域の「共助」支援機能(安否確認、備蓄シェアリング)を実装し、社会インフラ化を目指す | ・プラットフォーム流通総額(GMV): 50億円 ・提携パートナー企業数: 50社 ・連携自治体数: 10自治体 | ・API開発・パートナーサポートチーム ・公共政策・渉外担当 ・エコシステム拡大に向けた投資ファンド |
この戦略を実行することにより、需要の波に左右される脆弱な収益構造から脱却し、データと顧客との信頼関係を基盤とした、21世紀型の強靭な防災リーディングカンパニーへと飛躍することが可能となる。
第12章:付録
参考文献・引用データリスト
- 内閣府防災情報のページ「令和6年版防災白書」79
- 内閣府「防災に関する世論調査(令和4年9月調査)」80
- 内閣府「首都直下地震等による被害想定」3
- 内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について」4
- 気象庁「気候変動監視レポート」1
- 消防庁「製品火災等調査結果」86
- 株式会社矢野経済研究所「防災DX市場に関する調査」87
- 株式会社矢野経済研究所「国内防災食品市場に関する調査」7
- 株式会社富士経済「防災食品の国内市場調査」8
- 株式会社シード・プランニング「防災情報システム・サービス市場の実態調査」12
- ミドリ安全株式会社「家庭の防災対策実態調査」6
- 株式会社インテージ「防災に関する調査」19
- 住友生命保険相互会社「防災に関する調査」27
- Spherical Insights「日本のポータブル電源市場洞察予測」14
- アスクル株式会社「事業所における防災意識と対策に関する実態調査」31
- コクヨ株式会社「企業防災担当者の『フェーズフリー』期待度調査」95
- 株式会社ロイヤリティマーケティング「ローリングストックに関する調査」96
- ユニ・チャーム株式会社「ペットの防災対策に関するアンケート調査」64
- アイペット損害保険株式会社「ペットのための防災対策に関する調査」97
- 株式会社アントロット「防災セットに関する意識調査」20
- 株式会社mitoriz「防災備蓄に関するアンケート」66
- 日本トイレ研究所「災害用トイレに関する実態調査」18
- その他、本レポート内で引用した各企業・団体のウェブサイトおよびプレスリリース。
引用文献
- 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化 – 気象庁, https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html
- 気象庁|日本の気候変動2025 —大気と陸・海洋に関する観測・予測 …, https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/2025/html_honpen/cc2025_honpen_5.html
- 首都直下地震の被害想定等について, https://www.soumu.go.jp/main_content/001007208.pdf
- 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 概要, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/dai4/sankou1-1.pdf
- 防災・減災、国土強靱化 – 国土交通省, https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001471690.pdf
- -2025年度 家庭の防災対策実態調査- 防災食備蓄率は59.0%、コスト要因で備蓄断念 約3割に増加 ローリングストックの活用 24.6%で過去最高を記録 | ミドリ安全株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000011153.html
- 防災食品市場に関する調査を実施(2021年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press/press.php/002942
- 【速報】防災食品市場規模、24年は前年比21.4%増の261億円 富士経済調べ, https://news.nissyoku.co.jp/flash/1116807
- 防災食品市場、24年は2割増へ 地震頻発で需要高まる – 日本食糧新聞, https://news.nissyoku.co.jp/news/sato20241122101320685
- 災害大国ニッポンの防災ビジネス – 伊藤忠商事, https://www.itochu.co.jp/ja/business/textile/geppo/202003/geppo_vol719.pdf
- Overview – 【公式・メイン】防災事業者100社会, https://center.bosai100.net/overview
- 防災情報システム・サービス市場の実態を調査/2024年度の国内市場は2150億円に, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000109717.html
- 防災・減災サービス市場の市場規模と数値予測(2025-2050) – エネがえる, https://www.enegaeru.com/disasterpreventionandmitigation-servicesmarket
- 日本ポータブル電源市場 規模、分析、成長 2032 – Spherical Insights, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/japan-portable-power-station-market
- 3日分携帯トイレ、家庭備蓄27% 飲料水は半数超、政府世論調査 – nippon.com, https://www.nippon.com/ja/news/kd1351835220088751090/
- 令和6年 防災食品市場、前年比+21.4%の261億円を見込む、富士経済調べ, https://gohansaisai.news/news/article-10902/
- イオンの防災用品 被害を最小限におさえる「減災」 – イオンスタイルオンライン, https://aeonretail.com/Page/p-bousai-reduction.aspx
- 携帯トイレの市場動向および生産、普及活動に関する アンケート調査結果, https://www.toilet.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/keitaitoilet_survey2024.pdf
- 防災費用「理想と現実」で依然2倍の差 – 市場調査・マーケティングリサーチなら株式会社インテージ, https://www.intage.co.jp/news/6447/
- 防災セットを持たない理由、1位は「置き場所がないから」-アントロット調べ | 新建ハウジング, https://www.s-housing.jp/archives/222805
- 準備してそのままになっていませんか?】73.8%の総務が「非常食の備蓄管理」に悩み『賞味期限が切れた非常食の処理が大変…』〜7割強が、ローリングストックが可能な「置き社食」に興味 – 心幸 SHINKO, https://www.shinko-jp.com/column/chousa-bitiku/
- 防災に対する意識調査を実施, https://news-ins-saison.dga.jp/topics/down2.php?id=9002558&attach_id=1443
- ~2024年度 家庭の防災対策実態調査~ 防災食(非常食)の備蓄率 54.6%で昨年より5.3ポイント減少 備えていない理由、最多は「お金がかかるから」 | ミドリ安全株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000011153.html
- 家庭備蓄、トイレは3割届かず=能登地震で不足指摘―内閣府調査 | 防災・危機管理ニュース, https://www.risktaisaku.com/articles/-/106610
- 特集 災害の備え、何をしていますか : 防災情報のページ – 内閣府, https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h22/09/special_01.html
- 防災にも物価高の波が…家庭の防災費1人当たり年間2892円も「かけたい費用」が初減少「理想と現実」で2倍の差(放送局のニュース ) – tenki.jp, https://tenki.jp/news/fnn/e0931d53-c01d-4551-9f01-cf6d6889ac06.html
- スミセイ「わが家の防災」アンケート 2024 – 住友生命, https://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2023/240215.pdf
- 高齢者・障害者の防災施策に関する調査研究, http://www.boukakiki.or.jp/crisis_management/library/report/R4chousa_houkoku.pdf
- 【2025年版】シニア層の防災意識実態調査レポート – コスモラボ, https://cosmolab.jp/report/disaster_prevention_awareness_250312/
- これまでの調査の総括と今後の検討の方向性 – 防災情報のページ, https://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/shiryo02_dai4kai.pdf
- ASKUL事業・リサーチ専門チーム、全国の仕事場におけるニーズを探る「職場の災害対策と新たな防災概念〈フェーズフリー〉」に関する実態調査 | アスクル株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000021550.html
- フェーズフリーに関する調査を実施 – アスクル, https://www.askul.co.jp/f/special/survey/for_each_job_16/
- 2025年最新動向:災害予測と早期警戒システムにおけるAI活用最前線と地震・津波・洪水予測モデル精度向上データ – note, https://note.com/umibenoheya/n/ne97367280a9a
- AI技術の防災・減災への活用 – 防災の動き : 防災情報のページ – 内閣府, https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/r01/98/news_05.html
- 【楽天市場】カゴメ 野菜の保存食セット YH-A カゴメ野菜たっぷりスープ3種各2 カゴメ野菜一日これ一本長期保存用6本 : あんしんの殿堂防災館, https://item.rakuten.co.jp/bousaikan/421123/
- IoTと防災の未来|リアルタイムモニタリングやデータ分析の重要性 – 株式会社ASTINA, https://www.astina.co/media/8633/
- IoT技術を利用した災害(防災)対策の可能性・実例について 2022.06.20 通信 – SONY, https://iot.sonynetwork.co.jp/column/column035/
- 地球温暖化がさらに進行した場合、線状降水帯を含む極端降水は増加することが想定されます – 気象研究所, https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R05/050919/press_release050919.pdf
- 地方公共団体の食品ロス削減の取組事例 – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/case/local.html
- 食品ロス削減の取組事例集 – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/case/assets/case_200319_0002.pdf
- リチウムイオン電池メーカーの世界ランキング!市場規模と日本企業3選 – プルーヴ株式会社, https://www.provej.jp/column/ar/lithium-ion-battery/
- リチウムイオン電池の技術を牽引するメーカーや企業|市場規模や世界シェアについて|coevo, https://aconnect.stockmark.co.jp/coevo/lithium-ion-battery-manufacturer/
- 無印良品のおすすめ防災グッズがセットに! 『いつものもしも持ち出しセット』を開封レビュー, https://update.grapee.jp/1616041
- くらしの備え。いつものもしも。 | 無印良品 – Muji, https://www.muji.com/jp/ja/special-feature/other/itsumomoshimo/
- トランクルームに入れておきたい防災グッズ スノーピークのアウトドアアイテムを活用! – kurasul, https://kurasul.hello-storage.com/disaster-prevention-goods/
- ワクワクする野遊びBOUSAI賃貸住宅。 – 大東建託, https://www.kentaku.co.jp/sw/snowpeak_nonoka/
- 愛される【モンベル】の防災グッズ、開発のきっかけは阪神淡路大震災。広報いちおしグッズを聞いた! – HugKum, https://hugkum.sho.jp/408767
- 買ってよかった「モンベルで手に入る防災アイテム」4選 | ROOMIE(ルーミー), https://www.roomie.jp/2024/09/1315288/
- 食を通じて社会問題の解決に取り組み、 持続的に成長できる「強い企業」を目指して – カゴメ, https://www.kagome.co.jp/library/company/ir/data/integratedreport/2017/pdf/2017_3.pdf
- カインズで買える ときめく防災グッズ 片づけコンサルタントが選んだ意外な商品とは, https://www.ms-ins.com/tokimekubousai/article8.html
- 防災もDIYで日常化しよう | 株式会社カインズのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000008255.html
- 災害時の備えに「イオンディライトの防災用品(備蓄品)」|お役立ち情報, https://service.aeondelight.co.jp/blog/disaster-prevention/
- スタートアップが語る防災テック 株式会社Laspy, https://resilience-tech.net/interview/vol2
- 株式会社Laspyの防災備蓄サービス「あんしんストック」、賃貸マンション『コスモグラシア内神田』に初導入 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000092071.html
- 防災備蓄のワンストップサービス – あんしんストック, https://laspy.net/anshinstock/
- あんしんストックの特徴や注目ポイント・料金などについて徹底リサーチ, https://www.shopowner-support.net/attracting_customers/target-marketing/btob/laspy/
- 首都直下地震時における 流通・物流の維持、燃料供給の確保について – 防災情報のページ, https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/6/pdf/siryo1.pdf
- 【自然災害と物流】供給網のリスクをどう克服する?~DX時代のサプライチェーン変革~, https://service.shippio.io/glossary/disaster
- デジタル庁における防災DXの取組, https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f7339476-4afc-42d8-a574-a06bb8843fb5/826edcd0/20250620_policies_disaster-prevention_outline_01.pdf
- ICTソリューション紹介 -防災DX官民共創協議会- 官民が連携した防災DXに期待される新しい防災スタイルとビジネスモデル, https://www.jtua.or.jp/ict/solution/cloud/bousai-dx/202508_01/
- 防災DXの活用事例|デジタル技術が革新する災害対策の最前線, https://dxlabo.oce.co.jp/posts/bousai02
- ひとり暮らしの防災意識調査2025 | 株式会社エイブル&パートナーズのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000016136.html
- ホームセンター「カインズ」の防災意識が高すぎる!マネしたい防災のヒント&おすすめグッズ, https://kufura.jp/life/security/390322
- 災害時の『ペットの防災対策に関するアンケート調査』を実施 – ユニ・チャーム, https://www.unicharm.co.jp/ja/company/news/2025/0822-01.html
- 意識調査 FromプラネットVol.221 <防災対策に関する意識調査>約半数が防災対策で備蓄を実施|知る・役立つ・参加する | 株式会社プラネット, https://www.planet-van.co.jp/shiru/from_planet/vol221.html
- 防災に関するアンケート調査≪2024年≫-高まる意識・食料備蓄は約6割が取り組むも持ち出し袋常備は4割 | 株式会社mitoriz, https://service.mitoriz.co.jp/blog/96
- 東日本大震災から間もなく13年。 非常用持ち出し袋、簡易トイレ、非常食など3大ECモールの防災グッズ動向を調査! – Nint, https://www.nint.jp/blog/bousai-goods/
- 2025年の ありたい姿 持続的な成長を実現するカゴメの力, https://www.kagome.co.jp/library/company/ir/data/integratedreport/2019/pdf/2019_2.pdf
- 防災テックを行っている企業の事例は?気候テックとの違いもご紹介 – 日本BCPコラム, https://jp-bcp.co.jp/column/041/
- 防災DXとは?必要性や国・自治体の取り組み事例を解説 – TOPPAN, https://www.toppan.com/ja/joho/social/column/column17.html
- Arithmerの浸水AIシステムについて – ArithmerBlog, https://arithmer.blog/about-arithmers-inundation-ai-system
- 【防災特集】激甚化する自然災害。防災テックでソフト面の安心・安全対策を推進 – モーニングピッチ, https://morningpitch.com/innovation_trend/27585/
- 【楽天市場】非常食 保存食 備蓄食 野菜たっぷり3日分 セット 5年保存 カゴメ野菜一日これ一本、野菜たっぷりスープが入った長期保存食 KAGOME 震災・有事への備え防災用品 避難グッズ レジャー キャンプ 登山 アウトドア, https://item.rakuten.co.jp/at-rescue/10000934/
- 防災にポータブル電源は本当にいらない?災害時に役立つ場面や容量の選び方をご紹介 – Anker, https://www.ankerjapan.com/blogs/magazine/power-bousai
- 業界初!日々の電気代が減らせる「市場連動型」充放電サービスと連携したポータブル電源の実証販売開始 | EcoFlow Technology Japan株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000050601.html
- スピード 合理性。販路急拡大を支えるアンカー・ジャパンの組織文化とは | Anker Japan, https://corp.ankerjapan.com/careers/interview/0007
- EcoFlow、AI搭載の「EcoFlow OASIS」を「CES 2025」にて発表 省エネ効果の最大化と異常気象への備えを同時に実現, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000050601.html
- 「いつものもしも」パンフレット(PDF:2.1MB) – 無印良品, https://www.muji.net/pdf/store/campaign/itsumo_moshimo.pdf
- 防災白書(令和6年版), https://www.gov-online.go.jp/data_room/publication/202408/cao-10409.html
- [内閣府]防災に関する世論調査結果公表 – 障害保健福祉研究情報システム, https://www.dinf.ne.jp/d/6/528.html
- 防災に関する世論調査(令和4年9月調査) | 世論調査 | 内閣府, https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-bousai/
- 内閣府の「防災に関する世論調査」 身を守る意識に高まり – WEB防災情報新聞, https://www.bosaijoho.net/2022/12/15/gov-bosai-survey/
- 首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日公表) – 東京都防災ホームページ, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000902/1021571.html
- 首都直下地震等による東京の被害想定 報告書, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/571/20220525/n/002n.pdf
- 南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ – 気象庁, https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/assumption.html
- 令和5年中に発生した製品火災に関する調査結果について, https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/060701_yobou_1.pdf
- 24年の防災情報システム市場規模は184億円、矢野経済研究所が調査 – 週刊BCN+, https://www.weeklybcn.com/journal/news/detail/20250910_211819.html
- 防災DX市場に関する調査を実施(2025年) – Yano ICT, https://www.yanoict.com/summary/show/id/782
- 2025年版 防災DX市場の実態と展望 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C67107900
- 防災DX市場に関する調査を実施(2025年)【概要】~2024年の防災情報システム市場規模を184億円と推計。防災ソリューションでは平常時からリスクを可視化する仕組みの整備が進む【矢野経済研究所】 – 経済レポート, http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/637086/
- 防災情報システム・サービス市場 2026年に約1352億円市場に発展 – Seed Planning, https://www.seedplanning.co.jp/global/news/%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%80%80%E3%80%802026%E5%B9%B4%E3%81%AB%E7%B4%841352%E5%84%84/
- シード・プランニング、防災情報システム・サービス市場は、2025年に約1160億円に発展すると推計, https://www.digital-gyosei.com/post/research-seedplanning/
- 防災情報システム・サービス市場 2026年に約1,352億円市場に発展[調査データ] | デジタル行政, https://www.digital-gyosei.com/post/2022-01-31-ressearch-spi-report/
- 防災情報システム・サービス市場の最新動向と市場展望 – CiNii 図書, https://ci.nii.ac.jp/ncid/BC12470994
- 企業防災担当者への調査:オフィスにおける「フェーズフリー」の可能性 – コクヨ, https://www.kokuyo-furniture.co.jp/phasefree/article/001.html
- 備蓄食品に関する調査 – 株式会社ロイヤリティ マーケティング, https://biz.loyalty.co.jp/report/139/
- 2023年ペットのための防災対策に関する調査 | ペット保険のアイペット損保, https://www.ipet-ins.com/info/33483/
- 災害用携帯・簡易トイレ備蓄実態アンケート調査を実施 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000106356.html