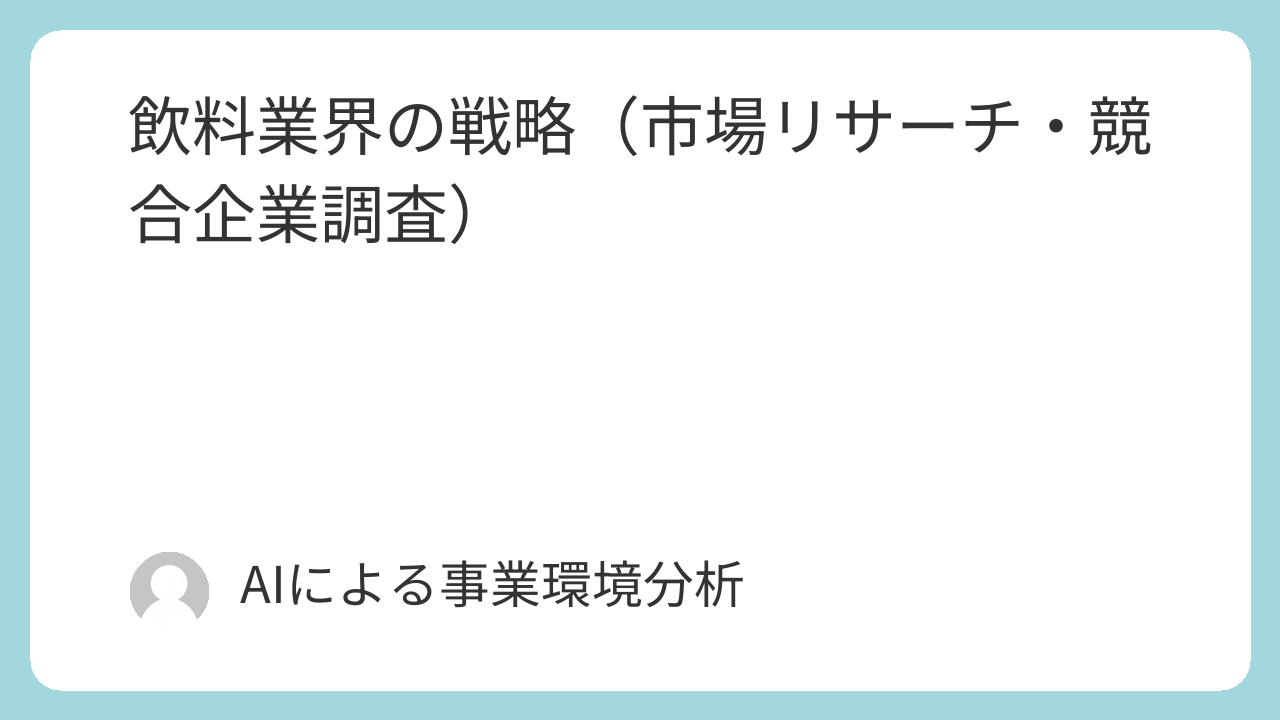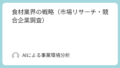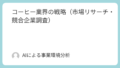パーソナライズと循環の未来:AIが駆動する飲料業界の次世代ウェルネス戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートは、日本の飲料業界が直面する不可逆的な構造変化、すなわち①「ウェルネス価値の再定義」、②「サーキュラーエコノミーへの移行」、そして③「AIによるバリューチェーン革新」という3つのメガトレンドを深く分析し、持続可能な成長戦略を策定するための戦略的洞察を提供することを目的とする。調査対象は、清涼飲料、アルコール飲料、機能性・ウェルネス飲料、およびそれらに関連するパッケージ、ロジスティクス、販売チャネルを包括的に網羅する。
最重要結論(Key Findings)
飲料市場は、原材料価格の高騰を背景とした価格改定により、出荷金額ベースでは成長を維持しているように見える。しかし、その内実を精査すると、販売数量は横ばいであり、市場は実質的な需要拡大ではなく、インフレとコストプッシュによって名目上拡大しているに過ぎない。真の成長機会は、消費者の高度な要求に応える高付加価値な「ウェルネス」領域と、バリューチェーン全体の効率性を極限まで高める「AI活用」にのみ存在する。
ESG(環境・社会・ガバナンス)への対応は、もはや単なる規制対応コストではない。特に、使用済みペットボトルを新たなペットボトルへと再生する「Bottle to Bottle」リサイクルや水資源の持続可能な利用は、企業のブランド価値と収益性を左右する競争戦略の中核要素へと昇華した。消費者は企業の環境姿勢を厳しく評価しており、これが購買決定の重要な一因となっている。
そして、AI(人工知能)は単なる効率化ツールではなく、業界のゲームチェンジャーである。製品開発の初期段階から、超精密な需要予測、サプライチェーンの自動最適化に至るまで、バリューチェーンのあらゆる段階を再定義する。この変革に適応し、AIを戦略的に活用する能力こそが、未来の勝者と敗者を分ける決定的なケイパビリティとなるであろう。
主要な推奨事項(Key Recommendations)
本分析に基づき、飲料業界における持続可能な成長を実現するため、以下の4つの戦略的アクションを提言する。
- ポートフォリオの抜本的再構築: 伝統的な炭酸飲料や有糖コーヒー飲料への経営資源依存から脱却する。そして、高い成長性を示す機能性表示食品(特に睡眠改善、脂肪対策)、プラントベース飲料、NoLo(ノンアルコール/ローアルコール)といったウェルネス領域へ、M&Aや研究開発投資を含む経営資源を重点的に再配分する。
- サーキュラーエコノミーの事業化: ラベルレス製品の標準化と、再生PET樹脂100%利用(Bottle to Bottle)を業界に先駆けて達成し、これをブランドの核となる価値として消費者へ積極的に訴求する。同時に、リフィルモデル(詰め替え)や新たな容器回収プラットフォームの構築といった、収益化を伴う新ビジネスモデルを試験的に導入する。
- AIドリブン・サプライチェーンの確立: 天候、地域イベント、POSデータ、SNSトレンドを統合したAI需要予測モデルを構築する。これにより、特に非効率性が深刻な自動販売機チャネルの補充・在庫管理を抜本的に改革し、「ドリンクロス(飲料の廃棄ロス)」の削減を主要KPI(重要業績評価指標)として設定する。
- D2Cによる顧客接点の深化: ニッチなウェルネスブランドのM&Aまたは自社開発を通じてD2C(Direct to Consumer)チャネルを確保する。これにより、従来は小売業者が握っていた顧客データを直接収集・分析する体制を構築し、将来のパーソナライズド飲料開発の強固な基盤とする。
第2章:市場概観(Market Overview)
市場規模の推移と予測
日本の飲料市場は、成熟期にあるものの、近年は価格改定が市場規模を押し上げる構造となっている。2024年度の国内飲料市場規模は、メーカー出荷金額ベースで前年度比102.3%の5兆2,800億円に達し、4年連続の成長を記録した 1。しかし、この成長は主に製品価格の上昇に起因するものであり、販売数量自体は前年度並みで推移している 1。これは、市場が実質的な需要増ではなく、インフレとコストプッシュによって名目上拡大していることを示唆しており、「見せかけの成長」に安住することは長期的なブランドエクイティと市場シェアの毀損リスクを内包する。
清涼飲料市場に絞ると、現在の国内市場規模約3.8兆円が、今後5年間で6.86%成長し、4兆円を超えると予測されている 4。この微増トレンドは、人口減少社会において大きな数量増が見込めない中、単価の高い高付加価値製品へのシフトが進むことを前提としたものと考えられる。
グローバル市場に目を向けると、同様の傾向が見られる。特に北米や西欧では、金額ベースの売上は堅調に推移しているものの、数量ベースの成長は歴史的平均を大きく下回っている 5。市場の成長は中国やインドといった新興国市場が牽引する構図が続くと予測されるが 6、地政学的リスクや世界的な所得圧力の高まりを受け、2025年にかけて成長ペースは鈍化する見込みである 7。
市場セグメンテーション分析
市場全体が停滞する一方で、特定のセグメントでは力強い成長が見られ、市場が多様な価値観を持つクラスターが併存する「まだら模様」の様相を呈している。
- 製品カテゴリー別:
- 清涼飲料: 国内ではコーヒー飲料(構成比21.0%)、茶系飲料(19.2%)、炭酸飲料(17.9%)が依然として主要カテゴリーを形成している 8。中でも、消費者の健康志向と記録的な猛暑による止渇需要を背景に、ミネラルウォーターと無糖茶系飲料が堅調に推移している 1。2013年から2022年にかけて、ミネラルウォーターの売上は67%、緑茶は20%増加した 10。対照的に、果汁飲料や有糖コーヒーの売上は減少傾向にある 10。
- 機能性・ウェルネス飲料: このセグメントは市場の成長エンジンとなっている。機能性表示食品市場は急成長を遂げ、2023年には前年比19.3%増の6,865億円に達する見込みである 11。特に「脂肪・コレステロール値改善」や「睡眠サポート」といった明確なベネフィットを訴求する商品が市場を牽引している 11。また、プラントベースフード市場も年平均22.5%という高い成長率を記録しており、中でもオーツミルクなどに代表されるプラントベースミルクへの注目度が高い 13。NoLo(ノンアルコール/ローアルコール)市場も7年連続で成長し、2022年には4,170万ケースに達すると予測されるなど、新たなライフスタイルとして定着しつつある 10。
- 販売チャネル別: スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった小売チャネルが依然として販売の主軸を担っている。これに加え、日本市場に特有のチャネルとして自動販売機が重要な役割を果たしている 9。近年では、特にパーソナライズ飲料やニッチなウェルネス飲料の領域において、EC(電子商取引)やD2Cチャネルが急速に存在感を増している 16。
市場成長ドライバーと阻害要因
- 成長ドライバー:
- 高度化する健康・ウェルネス志向: 機能性、プラントベース、NoLoなど、消費者の求める価値の多様化が、高付加価値製品市場を創出している。
- 気候変動: 猛暑の常態化による止渇需要の増加が、水やお茶などの基盤的カテゴリーを支えている。
- ライフスタイルの変化: イエナカ需要の定着や単身世帯の増加が、大型ペットボトルや個食対応製品の需要を後押ししている。
- 阻害要因:
- コスト構造の悪化: 砂糖、コーヒー豆、原油(PET樹脂の原料)といった原材料価格の高騰と、物流費の上昇が常態化しており、企業の利益率を直接的に圧迫している 18。
- 国内市場の構造的縮小: 人口減少と高齢化は、市場全体のパイを中長期的に縮小させる最大の要因である。
- 競争激化: 小売業者が展開する低価格なPB(プライベートブランド)商品との競争が激しさを増している。
業界の主要KPIベンチマーク分析
- 売上構成比: サントリー、アサヒ、キリンといった国内大手メーカーは、依然として伝統的なアルコール飲料と清涼飲料が収益の柱である。しかし、各社ともに将来の成長を見据え、ヘルスサイエンス事業や機能性飲料への戦略的シフトを加速させている 21。
- チャネル別利益率: 自動販売機チャネルは、運営形態によっては高い利益率(フルオペレーションで約20%、セミオペレーションで最大70%)が見込めるが、これは売上に対する比率であり、補充コストや人件費、設置場所の確保といった運用コストを考慮すると、その収益性は大きく変動する 24。一方、大手小売チェーン向けの卸売は、買い手の強い交渉力により、利益率が圧迫される傾向にある。
| カテゴリー | 市場規模(2024年予測、億円) | 年平均成長率(CAGR, 2020-2024年) | 将来性評価 |
|---|---|---|---|
| 無糖茶 | N/A | 堅調 | 中 |
| ミネラルウォーター | N/A | 成長 | 中 |
| コーヒー | N/A | 微減/横ばい | 低 |
| 炭酸飲料 | N/A | 微減/横ばい | 低 |
| 果汁飲料 | N/A | 減少 | 低 |
| 機能性表示食品(脂肪対策) | 約3,669億円 (2023年) 11 | 高成長 | 高 |
| 機能性表示食品(睡眠サポート) | 急伸 11 | 高成長 | 高 |
| プラントベースミルク | N/A | 高成長 (市場全体) 14 | 高 |
| NoLo飲料 | 約1,400億円 (2030年予測) 26 | 高成長 | 高 |
(注: 一部の市場規模データは完全には利用できず、関連データからの推定を含む)
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
飲料業界を取り巻くマクロ環境は、複数の要因が複雑に絡み合い、事業の前提を揺るがす大きな変化の渦中にある。
政治(Politics)
健康増進政策と環境規制が、業界に対する二大政治的圧力となっている。海外では英国やメキシコで「砂糖税」が導入され、対象となるソーダ類の売上を6%から12%減少させる効果が報告されている 27。日本でも導入の議論は潜在的なリスクとして常に存在し、特に有糖飲料カテゴリーにとって直接的な脅威となる。環境面では、「容器包装リサイクル法」がメーカーにリサイクルの責任とコストを課しており 29、将来的には再生材利用率の義務化など、規制がさらに強化される可能性が高い。
経済(Economy)
コストプッシュ型のインフレが常態化している。砂糖、コーヒー豆、アルミ、そしてPET樹脂の原料となる原油といった原材料価格の高騰に加え、物流費の上昇が企業の利益率を直接圧迫している 18。これにより、各社は製品価格への転嫁を余儀なくされているが、これは消費者の購買意欲を減退させ、販売数量の減少につながる悪循環のリスクをはらむ。また、原材料の多くを輸入に頼るため、円安は直接的なコスト増要因として経営に影響を与える。
社会(Society)
消費者の価値観の変容が、市場の需要構造を根底から変えている。
- 健康・ウェルネス志向の再定義: 消費者が求める「健康」は、単なるカロリーオフから、免疫サポート、ストレス軽減、睡眠改善といった、より具体的でパーソナルな機能性へとシフトしている 10。さらに、オーガニック、ナチュラル、プラントベースといった、より包括的なウェルネスへの関心が高まっている 13。
- NoLoトレンドの定着: 「ソバーキュリアス(Sober Curious)」に代表される、あえてアルコールを飲まない、あるいは低アルコールを選択するライフスタイルが若年層を中心に拡大している 10。これは伝統的なアルコール市場を代替するだけでなく、独自の飲用シーンを持つ新たな市場を創出している。
- エシカル消費とサステナビリティ: 企業の環境への姿勢が、消費者の購買決定要因(KBF)としての重要性を増している。脱プラスチックへの意識は高く、ラベルレス製品への支持が集まっている 31。また、フードロス(飲料の場合は「ドリンクロス」)削減や水資源保護といった企業の取り組みが、ブランドイメージを大きく左右する。
技術(Technology)
技術革新は、業界の課題解決と新たな価値創造の両面で鍵となっている。パッケージング技術では、PETボトルの軽量化、再生PET利用技術(Bottle to Bottle)、紙ボトルなどの代替素材、ラベルレス技術の進化が、環境負荷低減とコスト削減の両立を可能にしつつある。デジタル技術の領域では、キャッシュレス決済やパーソナライズ機能を備えた「スマート自販機」市場が年率18%以上で急成長しており、2032年には368億ドル規模に達すると予測されている 33。この進化は、伝統的な自販機チャネルの概念を覆す可能性を秘めている。
法規制(Legal)
食品表示法、特に「機能性表示食品制度」は、製品開発の方向性を大きく左右する。科学的根拠に基づいた健康効果を訴求できるようになったことで、高付加価値製品の開発が活発化している 11。一方で、表示の正確性と科学的根拠の信頼性が厳しく問われ、不適切な表示は景品表示法違反などの法的リスクを伴う。
環境(Environment)
プラスチック廃棄物問題と水資源、そしてカーボンニュートラルが三大環境課題である。海洋プラスチック問題への社会の関心は極めて高く、PETボトルを大量に使用する飲料業界は、その責任を厳しく問われている 9。リサイクル率の向上やプラスチック使用量の削減は、もはや企業の社会的責任(CSR)の範疇を超え、事業継続のための必須条件となっている。同様に、製品のライフサイクル全体で消費される水の総量を示すウォーターフットプリントの削減や、製造・物流過程でのCO2排出量削減(カーボンニュートラル)への取り組みが、企業のESG評価、ひいては企業価値そのものに直結する時代となっている。これらの環境課題への対応は、従来コスト増と捉えられてきたが、技術革新により環境負荷を下げながらコストも下げる「デカップリング」が可能になりつつあり、これを実現できるかが新たな競争優位の源泉となる。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
飲料業界の収益構造は、バリューチェーン上の各プレイヤー間の力関係と、激しい内部競争によって規定されている。
買い手の交渉力:極めて強い
飲料業界における買い手の交渉力は極めて強い。主要な買い手であるコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの大手小売チェーンは、その強大な販売網を背景に、メーカーに対して強い影響力を持つ。彼らは、①マージン確保のための価格引き下げ圧力、②限られた棚スペースを巡るメーカー間の競争を誘発する「棚割り」の決定権、③そして販売実績に基づくPB(プライベートブランド)商品の開発力という3つの強力な武器を持っている 37。消費者視点では、ブランド間のスイッチングコストはほぼゼロに等しく、価格やプロモーション、その時の気分で容易に他社製品やPB商品に乗り換えるため、最終消費者も間接的に強い交渉力を持っていると言える。
売り手の交渉力:中程度~強い
原材料や包装資材を供給する売り手の交渉力は、品目によって異なるものの、総じて中程度から強い。特にアルミ缶や砂糖などの供給業者は寡占的な市場構造にあり、価格交渉において優位な立場にある 37。また、コーヒー豆や特定の果実といった農産物は、天候不順や地政学リスクによって供給が不安定になりやすく、価格が高騰する局面では売り手の交渉力が一時的に著しく強まる。
新規参入の脅威:中程度
伝統的に、飲料業界への新規参入には、①大規模な製造設備への投資、②全国を網羅する物流網の構築、③小売りの棚を確保するための強力な営業力、という3つの高い障壁が存在した。しかし、デジタル技術の進化がこの構図を変えつつある。D2C(Direct to Consumer)やサブスクリプションといったビジネスモデルは、これらの障壁の一部を迂回することを可能にした 16。特定の健康志向やライフスタイルを持つニッチな顧客層をターゲットにしたスタートアップが、SNSを活用して直接顧客と関係を構築し、市場に参入する事例が増加している 38。また、製薬会社や他分野の食品メーカーが、自社の研究開発力を武器に機能性飲料市場へ参入する動きも活発化しており、新規参入の脅威は中程度と評価できる。
代替品の脅威:中程度~強い
消費者が「喉の渇きを潤す」「気分転換する」といった根源的なニーズを満たすための選択肢は、パッケージ飲料に限定されない。浄水器の普及による水道水の品質向上、ネスプレッソに代表される家庭用コーヒーメーカーの高性能化、自宅で手軽に作れるスムージーなどは、強力な代替品である。さらに、菓子やスナックといった他の嗜好品も、消費者の可処分所得と時間を奪い合う代替品と見なすことができる。
業界内の競争:極めて激しい
日本の飲料市場は、サントリー、アサヒ、キリン、コカ・コーラといったメガプレイヤーによる寡占市場であり、その競争環境は極めて激しい 8。製品カテゴリーによっては差別化が難しく、結果として大規模なマーケティング投資合戦や、小売店での価格プロモーション競争が常態化している。また、日本市場に特徴的な競争要因として、駅やオフィスビルなどの優良な立地における自動販売機の設置場所を巡る、物理的なスペースの熾烈な陣取り合戦が挙げられる。これらの要因が複雑に絡み合い、業界全体の収益性を圧迫する構造となっている。競争の主戦場は、従来の「小売りの棚」や「自販機の設置場所」といった物理的スペースから、D2Cの台頭により消費者の「スマートフォン画面」へとシフトしつつあり、大手企業が不得手とする領域での非対称な競争が激化している。
第5章:サプライチェーン分析
飲料業界のサプライチェーンは、「原材料調達 → 濃縮・加工 → ボトリング(製造)→ 一次物流(工場→倉庫)→ 二次物流(倉庫→小売・自販機)→ 販売 → 容器回収・リサイクル」という長く複雑な連鎖で構成されている。このチェーンの各段階には、特有の課題とリスクが内在している。
原材料調達のリスク
サプライチェーンの起点である原材料調達は、天候不順や地政学リスクといった外部環境の変動に極めて脆弱である。特に、コーヒー豆、果実、茶葉などの農産物は、異常気象や産地の政情不安によって供給が不安定になりやすく、価格の急騰を引き起こすリスクを常に抱えている。サプライチェーンのレジリエンス(回復力)を高めるためには、調達先の多様化や、リジェネラティブ農業(環境再生型農業)への投資を通じた生産者との関係強化が不可欠となる 39。
自動販売機チャネルの物流非効率性
業界の生命線とも言える自動販売機チャネルは、物流・補充オペレーションの非効率性という構造的な課題を抱えている。全国に点在する多数の自販機に対し、人手によるルート巡回で補充を行う現行のモデルは、労働集約的であり、人手不足が深刻化する中で持続可能性が問われている。各機体の在庫状況をリアルタイムで把握できず、経験と勘に頼った補充計画は、販売機会の損失(品切れ)と過剰在庫(補充したのに売れない)の両方を生み出す原因となっている。
リサイクルチェーンのボトルネック
サプライチェーンの終点であり、サーキュラーエコノミーの起点でもある容器回収・リサイクルチェーンには、複数のボトルネックが存在する。日本のPETボトルリサイクル率は高い水準にあるが、その品質には課題が残る。特に自動販売機横のリサイクルボックスでは、飲み残しやタバコの吸い殻といった異物の混入が後を絶たず、これがリサイクルの品質と効率を著しく低下させている 29。また、回収されたペットボトルのうち、国内で再びペットボトルに再生される「Bottle to Bottle」の比率はまだ十分ではなく、多くが海外へ輸出されたり、他のプラスチック製品にダウンサイクルされたりしているのが現状である 29。リサイクルプロセス自体にも、収集、分別、再生処理、輸送といった各段階で多大なコストとエネルギーが必要であり、経済合理性の確保が大きな課題となっている 41。
第6章:バリューチェーン分析
飲料業界において付加価値が創出される源泉は、バリューチェーンの複数の活動に分散している。これらの活動がどのように連鎖し、競争優位を構築しているかを分析する。
価値の源泉
飲料業界の競争優位性は、主に以下の4つの活動によって生み出されている。
- 強力なブランド・マーケティング力: 製品の機能的価値が同質化しやすい市場において、ブランドイメージや世界観といった情緒的価値が極めて重要となる。大規模な広告宣伝活動を通じて築き上げられたブランドへの信頼と愛着が、消費者の購買決定に大きな影響を与える。
- 広範な販売チャネル網: スーパーやコンビニの棚を確保する営業力と、全国津々浦々に張り巡らされた自動販売機ネットワークは、消費者が「いつでも、どこでも」製品にアクセスできる環境を提供する。これは、特に衝動買いが多い飲料製品において、売上を左右する決定的な要素である。
- 製品開発力: 消費者の味覚の嗜好や健康ニーズの変化を的確に捉え、ヒット商品を生み出す能力。これには、伝統的な「味づくり」の技術だけでなく、機能性成分に関する科学的知見や研究開発能力も含まれる。
- 大規模製造によるコスト効率: 大規模な生産設備によるスケールメリットを活かし、製品1単位あたりの製造コストを低減する能力。これにより、価格競争力を維持し、マーケティング活動への投資原資を確保する。
D2Cモデルがもたらす変革
D2C(Direct to Consumer)モデルの台頭は、従来の「製造→卸→小売」という線形的なバリューチェーンの構造を根本から揺るがしている。D2Cは、卸売業者や小売業者を介さずにメーカーが直接顧客に製品を販売することで、これまで中間業者に支払われていた「中間マージン」を自社の利益として確保することを可能にする。
しかし、それ以上に重要な変革は「顧客データ」の所有権の移転である。従来のモデルでは、誰が、いつ、どこで、なぜ商品を購入したかという貴重な顧客データは小売業者が独占していた。D2Cモデルでは、メーカーが自社のECサイトやアプリを通じてこれらのファーストパーティデータを直接収集・分析できる 43。このデータは、顧客理解を深め、パーソナライズされたマーケティング施策や新製品開発に活用することができ、顧客ロイヤルティの向上とLTV(顧客生涯価値)の最大化に直結する、極めて価値の高い経営資源となる 43。
サステナビリティ(ESG)と付加価値
サステナビリティへの取り組みは、バリューチェーンの各段階においてコスト要因と付加価値要因の両側面を持つ。
- コスト増要因:
- 調達: 持続可能性が認証された原材料(例:レインフォレスト・アライアンス認証の茶葉)は、一般的にコストが高い。
- 製造: 省エネ設備や再生可能エネルギーの導入には、初期投資が必要となる。
- パッケージ: 再生PET樹脂は、市場の需給バランスによってはバージン樹脂よりも高価になる場合がある 45。代替素材の開発にも研究開発費がかかる。
- 物流: CO2排出量の少ない輸送手段への切り替えは、コスト増につながる可能性がある。
- 付加価値(ブランドイメージ向上)要因:
- 環境配慮型のパッケージ(ラベルレス、再生材100%ボトルなど)や、水資源保護活動(水源涵養)といった具体的な取り組みは、企業の環境に対する真摯な姿勢を消費者に伝え、ブランドイメージと信頼性を大幅に向上させる。エシカル消費を重視する層にとっては、これが製品を選択する際の決定的な要因(KBF)となり、価格以外の付加価値を生み出す。
第7章:顧客需要の特性分析
飲料市場の成熟化は、消費者のニーズが画一的なマスから、多様な価値観を持つ複数のセグメントへと細分化・高度化していることを意味する。これらのセグメントを理解し、変化する購買決定要因(KBF)を捉えることが戦略策定の鍵となる。
主要な顧客セグメント
現代の飲料市場は、主に以下の5つの顧客セグメントに分類できる。
- 伝統的価値重視層: 主に40代以上の男性が中心。長年親しんできたブランドへの信頼性、慣れ親しんだ味、そして価格を手堅く評価する。缶コーヒー、定番の茶系飲料、ビール類などを習慣的に飲用する傾向が強い。
- 健康・機能性追求層: 30代から50代の男女が中心で、体脂肪、睡眠の質、ストレスといった具体的な健康課題を解決する手段として飲料を選択する。機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)を積極的に購入する。特に、20代から30代の若年男性においても健康意識は高く、トクホ製品の摂取率が高いというデータもある 10。
- ウェルネス・ライフスタイル層: 20代から30代の女性が中心的な層を形成。オーガニック、プラントベース、ナチュラルといった製品背景にある世界観や思想に共感し、自身のライフスタイルを表現する一部として商品を選択する。価格が高くても、自らの価値観に合致するものであれば購入を厭わない。
- NoLo/ソバーキュリアス層: 20代を中心に拡大しているセグメント。アルコールが飲める場面であっても、あえてノンアルコールやローアルコール飲料を積極的に選択する。彼らにとってNoLo飲料は単なるアルコールの代替品ではなく、洗練された味やブランドの世界観を楽しむための独立したカテゴリーである。
- エシカル消費層: 年齢や性別を問わず、その規模は拡大し続けている。ラベルレスボトル、リサイクル素材の使用、企業の環境保護活動といったサステナビリティへの取り組みを重要な購入の判断基準とする 31。
KBF(Key Buying Factor)の変化
購買決定要因(KBF)は、伝統的な要素に新たな価値軸が加わり、より複雑で階層的な構造へと変化している。
- 伝統的KBF: 「味」「価格」「ブランドの知名度」。これらは依然として購買の基礎となる重要な要素である。
- 現代的KBF: 上記に加え、「健康・機能性」(どのような具体的なベネフィットを提供してくれるか)、「環境配慮」(ラベルレスか、リサイクル素材を使用しているか)、「共感性」(ブランドの思想やストーリーに共感できるか)、そして「パーソナライズ」(自分に合っているか)といった要素の重要性が急上昇している。特に「健康」というKBFは、「体によいから」という漠然としたものから、「水分補給」「気分転換」「好きだから」といった、より多様で個人的な理由へと細分化されている 46。
この変化は、消費者が飲料を単なる「モノ」としてではなく、自身のライフスタイルや価値観を表現するための「コト」として捉え始めていることを示唆している。
チャネル別の購買行動とニーズ
- コンビニエンスストア: 「利便性」と「即時性」が最優先される。新商品や話題の商品を試す場としての役割が大きく、小型ペットボトルが中心となる。
- スーパーマーケット: 「計画購買」と「価格」が重視される。家族用の大型ペットボトルやケース単位でのまとめ買いが多く、PB商品の選択率も高い。
- 自動販売機: 「場所の利便性」がすべてを決定する。定価販売が基本であり、緊急の止渇需要に応える役割を担う。
- EC/D2C: 「目的買い」が中心。重い商品を自宅まで届けてもらう物理的な利便性に加え、特定のブランドのファンや、スーパーなどでは手に入らないニッチな商品、パーソナライズされた商品を求める層が利用する。
パーソナライズド飲料への潜在的ニーズ
個人の体質やライフスタイル、嗜好に合わせて最適化されたパーソナライズド飲料は、次世代のウェルネス市場における大きな潜在需要を秘めている。アンケートや尿検査といった診断を通じて顧客の健康状態や栄養バランスを把握し、最適な商品を提案するビジネスモデルは、すでにヘルスケア分野で注目を集めている 47。このアプローチは、顧客が自らの意思で情報を提供する「ゼロパーティデータ」の獲得に繋がり、極めて質の高い顧客理解を可能にする 48。特に、明確な健康課題を持つ層や、自分だけの特別感を求めるウェルネス・ライフスタイル層において、この潜在的ニーズは高いと推察される。これは、消費者の志向が「メーカーが提供する画一的な健康価値」を受動的に受け入れる段階から、「自分自身のデータに基づき、能動的にウェルネスを管理する」段階へと進化していることの表れである。
第8章:業界の内部環境分析
企業の持続的な競争優位は、外部環境への適応能力だけでなく、内部に保有する独自の経営資源やケイパビリティによっても規定される。
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
VRIOフレームワーク(Value: 経済価値, Rarity: 希少性, Imitability: 模倣困難性, Organization: 組織)を用いて、飲料業界における持続的な競争優位の源泉を分析する。
- 歴史ある強力なブランドポートフォリオ:
- V/R/I/O: 全て満たす(持続的競争優位)。長年にわたるマーケティング投資によって築き上げられたブランドへの信頼と認知度は、高い経済価値(Value)を持ち、新規参入者が短期間で獲得することは困難(Rarity, Imitability)である。大手企業は、このブランド価値を維持・向上させるためのマーケティング組織(Organization)を有している。
- 全国を網羅する自販機ネットワークと営業網:
- V/R/I/O: 全て満たす(持続的競争優位)。優良な設置場所を物理的に確保している自販機ネットワークは、安定した収益源であり(Value)、その規模と密度は他社が容易に模倣できない(Rarity, Imitability)。この広範なネットワークを維持・管理するための営業・補充部隊という組織(Organization)も強固な参入障壁となっている。
- 大規模な製造・物流インフラ:
- V/R/I: 満たすが、Oは部分的に留まる(一時的競争優位)。スケールメリットによるコスト効率(Value)は競争の基盤であるが、他社も同様の投資が可能であり、希少性(Rarity)や模倣困難性(Imitability)は相対的に低い。また、物流の「2024年問題」など、外部環境の変化に対して既存の組織(Organization)が十分に対応しきれていない課題も存在する。
- 特定分野の研究開発能力(例:発酵技術、機能性成分):
- V/R/I/O: 全て満たす(持続的競争優位)。キリンホールディングスの「プラズマ乳酸菌」のように、長年の研究開発によって生み出された独自の機能性素材は、高い付加価値(Value)と明確な差別化(Rarity, Imitability)をもたらす。これを製品化し、市場に展開する組織能力(Organization)と組み合わせることで、極めて強力な競争優位となる。
人材動向
業界の構造変化は、求められる人材像にも大きな変革を迫っている。
- 求められる人材像のシフト:
- 従来の主力であった、小売店や自販機ロケーションオーナーと関係を構築するルートセールス型営業や、マス広告を主導するマーケターの重要性は相対的に低下している。
- 一方で、以下の専門人材への需要が急増している。
- データサイエンティスト: AIを活用した需要予測モデルの構築や、SCM(サプライチェーン・マネジメント)の最適化を担う。
- サステナビリティ専門家: ESG戦略の策定、カーボンフットプリントの算定、サーキュラーエコノミー関連の法規制対応などを担当する。
- デジタルマーケティング担当者: D2Cチャネルの運営、SNSを通じた顧客エンゲージメント、パーソナライズ施策の実行を担う。
- 食品科学者/研究者: プラントベース素材や新たな機能性成分の研究開発を推進する。
- 専門人材の獲得競争:
- 特にデータサイエンティストなどのデジタル人材は、IT業界や金融業界など、あらゆる産業で需要が高く、業界を越えた激しい獲得競争に直面している。飲料業界が提示する賃金相場やキャリアパスは、これらの業界と比較して必ずしも魅力的とは言えず、優秀な人材の確保は喫緊の経営課題である。サステナビリティ専門家も同様に需要が高まっており、コンサルティングファームなどではマネージャークラスで年収1,000万円を超えるオファーも珍しくない 49。
労働生産性
- 製造ラインの自動化: 多くの工場で生産ラインの自動化やスマートファクトリー化が進められており、労働生産性の向上に寄与している 51。サントリーの京都ビール工場では、搬送工程の自動化により作業効率を30%向上させた事例もある 53。政府も「みどりの食料システム戦略」において、2030年までに食品製造業の労働生産性を3割以上向上させる目標を掲げている 54。
- 物流・自販機補充オペレーションの課題: 製造現場とは対照的に、物流、特に自販機の補充オペレーションは依然として労働集約的であり、生産性の向上が大きな課題となっている。ドライバー不足や「2024年問題」による労働時間規制は、この課題をさらに深刻化させている 55。この領域の生産性改革こそが、業界全体の収益性を改善する上で最もインパクトの大きいレバーの一つである。
第9章:AIの影響とインパクト
AI、特に予測AIと生成AIは、飲料業界のバリューチェーン全体に破壊的なインパクトをもたらし、競争のルールを根底から書き換える可能性を秘めている。
製品開発 (R&D)
AIは、製品開発のスピードと成功確率を飛躍的に向上させる。
- トレンド分析とアイデア創出: AIが膨大な量のSNS投稿、学術論文、POSデータをリアルタイムで解析し、消費者の潜在的なニーズや新たなフレーバーの組み合わせ、注目すべき機能性成分を抽出・提案する。キリンホールディングスは、生成AIを用いて仮想的な顧客像である「AIペルソナ」を構築し、RTD(Ready-to-Drink)商品の開発プロセスにおいて顧客インサイトを効率的に抽出する試みを開始している 57。また、サッポロビールは日本IBMと共同開発したAIシステムを活用し、市場データから導き出されたコンセプトに基づき「男梅サワー 通のしょっぱ梅」を開発した 58。
- パッケージデザインの高速生成: 生成AIは、製品コンセプトやターゲット層といったキーワードを入力するだけで、無数のパッケージデザイン案を瞬時に生成する。伊藤園は、業界に先駆けて「お~いお茶 カテキン緑茶」のパッケージ開発に商品デザイン用の画像生成AIを活用し、開発期間の大幅な短縮と、従来の発想にとらわれないデザインの創出を実現した 60。これは、これまで人間の感性に依存してきた創造的プロセスに、AIが協業者として参加する新たな時代の到来を告げている。
製造 (Manufacturing)
スマートファクトリー化の中核技術として、AIは製造プロセスの最適化と自律化を推進する。
- 生産プロセスの最適化: AIが生産ラインのセンサーデータをリアルタイムで監視・分析し、設備の故障を事前に予測する「予知保全」を実現し、ダウンタイムを最小化する。また、原材料の配合比率や生産ラインの稼働速度、工場全体のエネルギー消費を常に最適化し、コスト削減とCO2排出量削減を両立させる。サントリーは「天然水 北アルプス信濃の森工場」を次世代ファクトリーモデルと位置づけ、IoT基盤とデジタル技術を活用した高度なトレーサビリティと工場経営の変革を推進している 63。
サプライチェーン・ロジスティクス (SCM)
AIは、サプライチェーンにおける「予測」の精度を極限まで高め、非効率性を抜本的に解消する。
- 需要予測の革命: AIは、過去のPOSデータに加え、天候、地域のイベント情報、販促計画、SNSのトレンドといった、従来は人間の経験と勘に頼っていた複雑な変数を統合的に分析し、SKU(最小管理単位)別・チャネル別・地域別に超高精度な需要予測を行う 65。NECとアサヒ飲料は共同で、AIによる新商品需要予測の実証実験を行い、予測精度マネジメントによる戦略立案の高度化を目指している 66。
- 自販機オペレーションの自動運転化: AIは、飲料業界の長年の課題であった自販機オペレーションを劇的に変革する。各機体の販売実績とリアルタイム在庫、周辺のイベント情報、天候予報などから、最適な補充タイミングと商品構成を機体ごとに予測。同時に、複数の補充車両の積載量と移動時間を考慮した上で、最も効率的な補充ルートをリアルタイムで算出し、ドライバーにナビゲートする。これにより、補充効率の最大化と販売機会損失の最小化が同時に実現される。
- 在庫最適化と「ドリンクロス」削減: 高精度な需要予測は、工場から倉庫、店舗、自販機に至るサプライチェーン全体の過剰在庫を劇的に削減する。これは、保管コストの削減に直結するだけでなく、賞味期限切れによる製品廃棄、すなわち「ドリンクロス」を抜本的に削減し、サステナビリティ目標の達成にも大きく貢献する。
マーケティング・販売
AIは、マスマーケティングからパーソナライズされた顧客体験への移行を加速させる。
- パーソナライズド・レコメンデーション: ECやD2Cサイトにおいて、AIが顧客一人ひとりの購買履歴、閲覧履歴、さらには顧客が任意で提供した健康データに基づき、その顧客に最も適した商品を推薦する。
- 新たな顧客エンゲージメントの創出: AIは、単なる分析ツールに留まらず、新たなマーケティングコンテンツを生み出す。アサヒビールは画像生成AI「Stable Diffusion」を活用し、ユーザーが自分だけのオリジナル画像を生成できる体験型プロモーションを展開 57。また、伊藤園は生成AIで作成したAIタレントをテレビCMに起用するなど 60、AIは顧客との新たな関係構築の手法を提供している。
| バリューチェーンの段階 | 現状の課題 | AIによる変革(具体的な活用例) | 戦略的インパクト(So What?) |
|---|---|---|---|
| 製品開発 | 長い開発期間、消費者ニーズの把握の困難さ | ・SNS/論文データ分析による新フレーバー・機能性成分の提案 57 ・生成AIによるパッケージデザイン案の高速生成 61 | ・開発リードタイムの劇的な短縮 ・ヒット商品創出の確度向上 |
| 製造 | 熟練作業員への依存、エネルギーコスト、品質のばらつき | ・AIによる生産ラインの予知保全 ・原材料配合とエネルギー消費の最適化 63 ・画像認識によるリアルタイム品質検査 | ・生産性の向上とダウンタイムの削減 ・製造コストとCO2排出量の同時削減 |
| SCM・ロジスティクス | 不正確な需要予測、過剰在庫と品切れ、自販機補充の非効率性 | ・天候・イベント等を統合した超高精度な需要予測 65 ・AIによる自販機補充の最適ルート算出 | ・「ドリンクロス」の抜本的削減 ・物流コストの最適化と販売機会損失の最小化 |
| マーケティング・販売 | マス広告への依存、顧客理解の不足 | ・個人の嗜好・健康状態に基づくパーソナライズド・レコメンデーション ・生成AIによる広告クリエイティブの自動最適化 57 | ・顧客エンゲージメントとLTVの向上 ・マーケティングROIの最大化 |
第10章:主要トレンドと未来予測
飲料業界は、本レポートで分析したメガトレンドの複合的な影響を受け、今後5年から10年でその姿を大きく変えることが予測される。
- ウェルネス飲料の進化:「機能性」から「超パーソナライズ」へ
現在主流の「機能性表示食品」は、特定の健康課題を持つ不特定多数のマス層に向けたソリューションである。しかし今後は、個人の生体データ(DNA、腸内フローラ、ウェアラブルデバイスから得られる活動量や睡眠データなど)に基づき、一人ひとりの体質やライフスタイルに最適化された「超パーソナライズド飲料」やサプリメントが主流となる。これは、飲料が「製品」から「個人の健康ソリューション・サービス」へと進化することを意味する。 - サステナビリティの主流化:「コスト」から「KBF」へ
現在、移行期にあるサステナビリティへの取り組みは、将来的には業界の標準となる。「ラベルレス」が当たり前になり、リサイクル素材100%のボトル(Bottle to Bottle)が普及する。さらに、企業の評価軸は、水使用量を実質ゼロにする「ウォーターニュートラル」や、CO2排出量を吸収量が上回る「カーボンネガティブ」といった、より高いレベルの環境貢献へとシフトする。これらの取り組みは、企業の社会的責任(CSR)活動ではなく、消費者がブランドを選択する際の重要な購買決定要因(KBF)となる。 - チャネル・トランスフォーメーション:「設置」から「接続」へ
従来型の自動販売機の設置台数は、人口減少や採算性の問題から減少傾向が続くと予測される。その一方で、キャッシュレス決済、多言語対応、そしてAIによるパーソナライズド・レコメンデーション機能を備えた「スマート自販機」への置き換えが加速する 33。自販機は単なる「飲料を売る箱」から、顧客データと接続し、最適な体験を提供する「無人のマイクロ店舗」へと進化する。同時に、EC/D2Cチャネルはさらに拡大し、リアルとデジタルの垣根を越えたオムニチャネル戦略が必須となる。 - NoLo(ノンアル/ローアル)市場の確立:「代替品」から「独自の文化」へ
現在、アルコール飲料の代替品として語られることが多いNoLo市場は、独自の価値と飲用シーンを持つ独立した市場として確立される。洗練された味わいや健康価値、ブランドの世界観を訴求することで、アルコールを飲む・飲まないに関わらず、すべての人が楽しめる新たな嗜好品としての地位を築き、独自の文化を形成していく 26。 - M&A動向:大手によるスタートアップ買収の加速
変化のスピードに対応するため、大手飲料メーカーによる、プラントベース、機能性素材、D2Cプラットフォームといった特定領域に強みを持つスタートアップの買収がさらに加速する。これにより、大手は自社に不足する技術、ブランド、顧客接点、そしてアジャイルな企業文化を短期間で獲得しようと試みるだろう。
第11章:主要プレイヤーの戦略分析
飲料業界の競争環境は、グローバルなメガプレイヤーと日本の大手企業、そして特定のカテゴリーで強みを発揮する新興勢力によって形成されている。
グローバル・メガプレイヤー
- The Coca-Cola Company:
- 戦略: 「Total Beverage Company」を掲げ、中核の炭酸飲料ブランドを守りつつ、水(smartwater)、スポーツドリンク(Powerade)、コーヒー(Costa Coffee買収)、エナジードリンク(Monsterとの提携)など、非炭酸領域へのポートフォリオ多角化を積極的に推進。健康志向の高まりに対応し、「Zero Sugar」製品群をグローバルで強化している。
- 強み: 世界最高峰のブランドエクイティと、他社の追随を許さないグローバルなボトラーシステムおよび流通網。
- サステナビリティ戦略: 2030年までに販売した製品と同等量の容器を回収・リサイクルするというグローバル目標「World Without Waste」を掲げ、各国で取り組みを進めている。
- PepsiCo:
- 戦略: 飲料事業(Pepsi, Gatorade)とスナック食品事業(Lay’s, Quaker)の両輪で成長を目指すシナジー戦略を採る。健康・ウェルネス領域への注力を鮮明にしており、機能性飲料(Propel)の強化やスナックのヘルシー化を推進。近年では、機能性ソーダのスタートアップ「Poppi」の買収を検討するなど、M&Aにも積極的である 7。
- 強み: 飲料と食品の事業ポートフォリオがもたらす販売チャネルやマーケティングにおけるシナジー。Gatoradeブランドで培ったスポーツ科学分野での深い知見。
- サステナビリティ戦略: 「pep+ (PepsiCo Positive)」という包括的なサステナビリティ戦略を掲げ、リジェネラティブ農業(環境再生型農業)の推進、プラスチック使用量の削減、水使用量の削減など、野心的な目標を設定している。
日系大手プレイヤー
- サントリーホールディングス:
- 戦略: 「水と生きる」という企業理念を根幹に、「サントリー天然水」「BOSS」「伊右衛門」といった高品質な製品で強力なブランドを構築。酒類事業と飲料・食品事業を両輪としつつ、健康食品事業を第三の柱として育成中。海外事業、特に欧州・アジアでの展開を加速している。
- 強み: 「天然水」に代表される水源開発力と、徹底した品質へのこだわり。ウイスキー事業で培った、時間をかけてブランド価値を育む長期的な視点。
- サステナビリティ戦略: 2030年までにグローバルで使用する全ペットボトルを100%サステナブル素材(リサイクルまたは植物由来)に切り替えるという、業界でも特に野心的な目標を掲げている 68。水源涵養活動「天然水の森」は、同社のサステナビリティ活動の象徴である 70。
- アサヒグループホールディングス:
- 戦略: 中核ブランド「スーパードライ」を擁する酒類事業で圧倒的な基盤を築き、近年は欧州や豪州のビール事業買収など、積極的な海外M&Aによってグローバル化を加速。飲料事業では「三ツ矢」「カルピス」といったロングセラーブランドを強化しつつ、健康・機能性分野へも注力している。
- 強み: 「スーパードライ」という極めて強力なキャッシュカウ(収益の柱)と、M&Aによって獲得したグローバルな事業基盤。
- サステナビリティ戦略: 2030年までにPETボトルを100%リサイクル素材などに切り替える目標を設定。ラベルレス商品の展開にも積極的である。
- キリンホールディングス:
- 戦略: 長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」に基づき、「食領域(ビール・飲料)」から「医領域(協和キリン)」、そして「ヘルスサイエンス領域」へと事業ポートフォリオを大きく変革させる戦略を推進 71。ビール事業で培った発酵・バイオテクノロジーを強みとし、「プラズマ乳酸菌」による免疫ケアなど、科学的根拠に基づいた独自性の高い健康価値の創出に注力している。
- 強み: グループ内に医薬品事業を持つことによる科学的知見と、それに基づく製品への信頼性。「プラズマ乳酸菌」に代表される、他社が容易に模倣できない独自の機能性素材。
- サステナビリティ戦略: 2027年までにペットボトルのリサイクル樹脂使用率50%を目標とするなど、具体的なCSV(Creating Shared Value)コミットメントを掲げ、事業と社会課題解決の統合を目指している。
カテゴリーキラー/新興勢力
- モンスタービバレッジ / レッドブル: エナジードリンクという単一カテゴリーに特化し、独自のブランドイメージとマーケティング手法で巨大市場を築き上げた。大手メーカーとは異なるルールで戦うカテゴリーキラーの代表例。
- 新興D2Cブランド: PostCoffee(パーソナライズコーヒー)やGREEN SPOON(パーソナルフード)など、特定のニーズに特化し、D2Cモデルとサブスクリプションを駆使して顧客と直接的な関係を構築。大手にはないスピード感と顧客理解で、新たな市場を切り拓いている 38。
| プレイヤー | ポートフォリオ戦略 | ウェルネス戦略 | サステナビリティ戦略(PETボトル) |
|---|---|---|---|
| サントリーHD | 酒類・飲料の両輪+健康食品育成 | 水源開発力と品質を基盤としたブランド構築 | 2030年までに100%サステナブル化 68 |
| アサヒGHD | 酒類中心、M&Aでグローバル化 | 既存ブランド強化+機能性分野への注力 | 2030年までに100%リサイクル素材等へ |
| キリンHD | 「食」から「医・ヘルス」へシフト | 独自技術(発酵・バイオ)による機能性素材開発 | 2027年までにリサイクル樹脂使用率50% |
第12章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、飲料業界で持続的な成長を遂げるための戦略的意味合いを導出し、具体的な推奨事項を提言する。
勝者と敗者を分ける決定的要因
今後5年から10年の飲料業界において、企業の盛衰を分ける決定的な要因は、以下の3つの能力に集約される。
- データ活用能力: 顧客データ、サプライチェーンデータ、市場データを統合・分析し、意思決定のスピードと精度を飛躍的に高める能力が不可欠となる。特に、D2Cチャネルなどを通じて得られるゼロパーティ/ファーストパーティデータを、製品開発やパーソナライズされた顧客体験の提供に直接活かせるかどうかが、競争優位の源泉となる。
- ポートフォリオ変革の断行力: 過去の成功体験や既存の巨大ブランド(キャッシュカウ)に固執することなく、縮小する市場から成長市場へと、大胆に経営資源をシフトできるかどうかが問われる。この変革は、短期的な収益悪化や既存事業とのカニバリゼーションを許容する、経営陣の強い覚悟とリーダーシップを必要とする。
- サステナビリティの収益化能力: ESG対応を単なるコストやリスク管理として捉えるのではなく、ブランド価値向上や新ビジネスモデル創出の機会と捉え、消費者が「より高い価格を支払ってでも選びたい」と感じるような付加価値に転換できる能力。
機会(Opportunity)と脅威(Threat)
- 機会(Opportunities):
- 超パーソナライズド・ウェルネス市場の創出: 個人の生体データ(DNA、腸内環境など)とAIを組み合わせ、究極のパーソナライズド飲料/サプリメントを提供するサービス事業を創出する。
- サーキュラーエコノミー・プラットフォームの主導: 自社だけでなく業界全体が利用可能な、効率的な容器回収・再生プラットフォームを構築・運営し、業界標準を確立することで新たな収益源とする。
- AIによる自販機チャネルの再発明: スマート自販機とAIによる補充・在庫最適化を組み合わせ、単なる飲料販売機から、パーソナライズされた商品を24時間提供する「無人マイクロ店舗」へと進化させ、新たな顧客体験と収益機会を創出する。
- 脅威(Threats):
- コスト構造の崩壊: 原材料価格の高騰と、物流の「2024年問題」に端を発する輸送コストの上昇が継続し、従来の薄利多売ビジネスモデルが完全に成り立たなくなるリスク。
- ブランドのコモディティ化: D2Cブランドや小売PBが顧客接点とデータを掌握し、大手メーカーが差別化された価値を提供できなくなり、単なる製造委託先(下請け)へと転落するシナリオ。
- 規制の激変: 砂糖税の本格導入や、プラスチック容器への課徴金・使用禁止といった、事業の前提を覆すような、より厳しい環境・健康関連規制が導入されるリスク。
戦略的オプションの提示と評価
上記の分析に基づき、考えられる戦略的オプションを3つ提示し、評価する。
- オプションA:コア事業強化・効率化戦略
- 内容: 既存の主力ブランド(炭酸、コーヒー等)のマーケティングを強化し、AI活用によるSCM効率化で徹底的にコストを削減し、収益性を最大化する。
- 評価: 短期的な収益確保には繋がるが、市場の構造変化に対応できず、長期的には衰退が避けられない。成功確率は低い。
- オプションB:M&Aによる成長領域獲得戦略
- 内容: プラントベース、機能性、D2C分野で成功しているスタートアップを積極的に買収し、成長領域へ迅速に参入する。
- 評価: 開発時間を短縮し、新たな知見や人材を獲得できるメリットは大きい。しかし、高値掴みのリスクや、買収後の組織文化の統合(PMI)の難易度が高い。自社のイノベーション能力が育たないという根本的な課題も残る。成功確率は中程度。
- オプションC:自社変革によるウェルネス・サービス企業への転換戦略
- 内容: 自社のR&D能力を核とし、独自の機能性素材やパーソナライズ技術を開発。D2Cチャネルを自ら構築し、単なる「飲料」というモノを売る企業から、「健康ソリューション」というサービスを提供する企業へとビジネスモデル自体を変革する。
- 評価: 多大な先行投資と時間を要し、実行難易度は極めて高い。しかし、市場の不可逆的な変化に適応し、持続的な競争優位を築く唯一の道である。成功確率は高い(ただし、強力な実行力が前提)。
最終提言とアクションプラン
最終提言:オプションC「自社変革によるウェルネス・サービス企業への転換戦略」の推進
市場の構造変化は不可逆的であり、小手先の改善(オプションA)や他社の力を借りる戦略(オプションB)だけでは、長期的な成長は望めない。自社のビジネスモデルそのものを未来の市場構造に適応させることこそが、唯一の持続可能な成長戦略である。
実行に向けたアクションプラン概要:
- Phase 1 (1~2年): 基盤構築
- 主要KPI: D2C売上比率5%達成、パーソナライズド飲料のテスト販売開始、AI需要予測モデルのPoC(概念実証)完了。
- アクション: ①ウェルネス分野のD2Cスタートアップを1~2社買収し、顧客データ分析チームを組成。②R&D部門に「パーソナライズ研究」チームを新設。③SCM部門とIT部門の合同で「AI需要予測プロジェクト」を立ち上げ。
- 必要リソース: M&A資金、データサイエンティストおよびデジタルマーケターの採用。
- Phase 2 (3~5年): 事業拡大
- 主要KPI: D2C売上比率15%達成、パーソナライズド飲料事業の黒字化、AIによる自販機補充ルートの全面最適化。
- アクション: ①買収したD2Cブランドのノウハウを自社主力ブランドのD2C展開に活用。②パーソナライズド飲料のサブスクリプションモデルを本格展開。③AI需要予測を全社に展開し、SCMを全面的に最適化。
- 必要リソース: 大規模なデジタルマーケティング投資、スマート自販機への設備投資。
- Phase 3 (6~10年): サービス企業への転換
- 主要KPI: 飲料事業に占めるサービス(パーソナライズ、健康ソリューション)売上比率20%達成。
- アクション: ①個人の生体データと連携した「超パーソナライズド・ウェルネスプログラム」を提供開始。②飲料の提供に留まらず、食事や運動に関するアドバイスも含めた総合的な健康ソリューション事業へと進化。
- 必要リソース: ヘルスケア関連企業との戦略的アライアンス、医療・栄養分野の専門家人材の確保。
第13章:付録
引用文献
- 飲料市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース・トピックス …, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3894
- 矢野経済研究所「飲料市場に関する調査結果」発表 – フードボイス, https://fv1.jp/99830/
- 矢野経済研究所/飲料市場に関する調査を実施2025(食品OEMコム), https://www.food-oem.com/h-topics-2025247.html
- service.xenobrain.jp, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/soft-drink#:~:text=%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89-,%E6%B8%85%E6%B6%BC%E9%A3%B2%E6%96%99%E6%B0%B4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%202030%E5%B9%B4%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%20%2B6.86%25%E5%A2%97,4.02%E5%85%86%E5%86%86%E3%81%A8%E4%BA%88%E6%B8%AC&text=%E6%B8%85%E6%B6%BC%E9%A3%B2%E6%96%99%E6%B0%B4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AF%E3%80%81%E7%8F%BE%E5%9C%A8,%E3%81%AB%E9%81%94%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
- Soft Drinks: Half-Year Update H1 2023 | Market Research Report – Euromonitor International, https://www.euromonitor.com/soft-drinks-half-year-update-h1-2023/report
- Food, Beverages and Tobacco Global Industry Overview | Market Research Report, https://www.euromonitor.com/food-beverages-and-tobacco-global-industry-overview/report
- Soft Drinks: Half-Year Update | Market Research Report | Euromonitor, https://www.euromonitor.com/soft-drinks-half-year-update/report
- 飲料 – TDB REPORT ONLINE | 株式会社帝国データバンク, https://www.tdb-publish.com/trends/E06/
- 飲料業界の動向と展望 – 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/industry/xat0i8yb7/
- Report Name:Non-Alcohol Beverage Market Update 2023, https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Non-Alcohol%20Beverage%20Market%20Update%202023_Osaka%20ATO_Japan_JA2023-0121
- 機能性表示食品、特定保健用食品などの国内市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24019&la=ja
- 機能性表示食品の今後について – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/movie_004/assets/food_labeling_cms206_20250106_04.pdf
- プラントベースフード市場の可能性|急成長の要因と今後の展望 – グリーングロワーズ, https://mygreengrowers.com/blog/potential-of-the-plant-based-food-market/
- 第109回 世界で拡大を続けるプラントベースとプラントベースミルクについて – 日本乳業協会, https://nyukyou.jp/effort/council/20230719.html
- 参考資料2 – 食品安全委員会, https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20221207te1&fileId=410
- 丸紅ベンチャーズ、会話型コマースによる飲料販売を手がけるIris Nova社に出資 ~テキストメッセージを利用したD2Cプラットフォームを展開~【丸紅ベンチャーズ】 – Marubeni Corporation, https://www.marubeni.com/jp/news/2020/group/00002.html
- 食品D2Cサービス市場は340億円、58%増の見込み【2020年度】, https://netshop.impress.co.jp/node/8659
- 一部商品の価格改定に関するお知らせ|ニュースリリース 2024年 – アサヒ飲料, https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2024/pick_0613.html
- 飲料、10月1日から約1000品が価格改定 20円アップは540品以上 – 食品新聞, https://shokuhin.net/106677/2024/10/01/inryou/inryou-inryou/
- 10月1日から飲料・食料品3000品目以上が値上げ “マイボトル給茶”で節約の動きも=静岡, https://www.at-s.com/snews/article/ats/1816615.html
- IRライブラリー | 株主・投資家情報 | サントリー食品 …, https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/library/
- IRライブラリー|IR・投資家情報|アサヒグループホールディングス, https://www.asahigroup-holdings.com/ir/library/
- IRライブラリ | IR情報 | KIRIN – キリンホールディングス株式会社, https://www.kirinholdings.com/jp/investors/library/
- 清涼飲料業界の現状と課題, https://sb90c5f8e9e2d7755.jimcontent.com/download/version/1328202089/module/5683413715/name/5%E6%9C%9F4%E7%8F%AD%E9%A3%B2%E6%96%99%E6%B0%B4.pdf
- 自動販売機導入ガイド|導入方法、費用、設置条件を解説, https://jidohanbaiki.jp/column/install-vendingmachine/
- サントリー“ヒット請負人”起用で「ノンアル市場」覇権狙う。若者訴求へ学生サークルとも交流, https://www.businessinsider.jp/article/2502-suntory-establishes-a-new-specialized-department-non-alcoholic-drinks/?page=2
- 生産割当廃止後のEUにおける砂糖および異性化糖産業の動向, https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002302.html
- Vol.021「砂糖税」は日本でも導入が検討!? 本当に肥満対策になる?, http://medg.jp/mt/?p=6448
- 事業系飲料容器回収における課題と対応の最新動向, https://www.3r-suishinkyogikai.jp/data/event/R04_3rce-002.pdf
- 清涼飲料業界 プラスチック資源循環宣言 および 取組み説明, https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/577/shiryo2-5.pdf
- 「ペットボトル飲料」に関する調査結果 – datacolle | 株式会社エクスクリエ(excrie), https://www.excrie.co.jp/datacolle/page/b6u511l-9ry8
- ペットボトル飲料に関する調査(2024年) – クロス・マーケティング, https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20240710plasticbottle
- スマート自動販売機の世界市場は2030年まで年平均成長率18.12%で成長すると予想される, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005192.000067400.html
- 世界のスマート自動販売機市場規模、シェア、トレンド分析レポート – 業界概要と2032年までの予測 – Data Bridge Market Research, https://www.databridgemarketresearch.com/jp/reports/global-smart-vending-machine-market
- インテリジェント自動販売機市場規模|分析レポート[2032年] – Fortune Business Insights, https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A9%9F%E5%B8%82%E5%A0%B4-107360
- 機能性表示食品、特定保健用食品などの国内市場を調査 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=23025&view_type=2&la=en
- 競争に勝ち抜くための頼れる分析手法!5フォース分析の基本と活用術, https://d-cam.jp/blog/5forces/
- 【2024年版】日本で人気のD2Cブランド一覧。マーケティング手法も解説 – 事業内容, https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/d2c_brand
- 食品・飲料業界のサステナビリティ目標達成にいま必要な5つのこと, https://www.sustainablebrands.jp/news/1222851/
- ペットボトルリサイクルの課題とその解決方法であるボトルtoボトルを解説|日本の回収率や各メーカーの工夫は? | 株式会社利根川産業, https://www.tonegawa-s.co.jp/blog/industry/horizontal-recycle/
- 【2025】日本のリサイクルの現状がヤバい!プラスチックの問題点「ペットボトルは燃やしてもリサイクル!?」 | ドクターエコ, https://dr-eco.jp/environment/japan-3type-recycling/
- マテリアルリサイクルとは|日本における普及の課題と解決策 – DNP, https://www.dnp.co.jp/biz/column/detail/20173521_4969.html
- D2Cとは?マーケティング戦略が重要な理由、顧客接点・戦略を設計するポイント | DX BLOG, https://www.ever-rise.co.jp/dx-blog/d2c-marketing/
- 食品D2Cの成功事例20選!競争で勝ち残るための7つのポイントを解説, https://corekara.co.jp/contents/sales-up/food_d2c/
- 【コラム】巡り廻るPETボトルのリサイクルコスト | プラジャーナル PJ, https://plasticjournal.net/column/4500.html
- 飲料についての調査 – 日本リサーチセンター, https://www.nrc.co.jp/report/pdf/NRCrep_inryo2013.pdf
- 急成長するパーソナライズフードビジネス|具体事例と重要ポイントを解説 – ヨミトル, https://shindancloud.com/trend/1777/
- D2C事業で得た顧客の嗜好性データをマスマーケティングに生かす! UCC上島珈琲のデータ戦略, https://www.advertimes.com/20200602/article313516/
- サステナビリティコンサルタントとは?年収やSDGsコンサルとの違い – みらいワークス, https://mirai-works.co.jp/consulnext/column/2244/
- サステナビリティコンサルタントとは?企業・年収・仕事内容をわかりやすく解説 – サスキャリ, https://sus-career.com/media/sustainability-consulting
- 食品工場での「改善事例」4選!自動化や生産性向上の取り組みとは – tebiki, https://tebiki.jp/genba/useful/food-improvementexamples/
- 生産性向上等の取組における優良事例 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/seisansei-134.pdf
- サントリー 京都工場で進む搬送の自動化、缶ラインの作業効率を30%改善 – MONOist, https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2302/08/news007.html
- 2030年までに食品製造業の自動化等を, https://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/pdf/kobo/2022/project_2022-5.pdf
- 飲料5社/物流2024年問題改善へ待機時間40%削減、荷役作業30%削減 – LNEWS, https://www.lnews.jp/2025/05/r0529501.html
- 2024年問題とは?物流業界の課題と企業が今すぐできる対策 – SBSリコーロジスティクス, https://www.sbs-ricohlogistics.co.jp/sbsrlsc/logistics/guide/logi2024/
- 食品・飲料メーカー業界におけるChatGPT・生成AIの活用事例5選紹介と導入ポイントについて解説, https://www.c-and-inc.co.jp/ai/business-manufacturer1/
- 食品業界で進む「味のデジタル化」 AIで開発した商品も話題に, https://www.jtua.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/tf202406_ict_feature.pdf
- AIを使って商品開発はできる。具体的な使い方と事例も紹介, https://corp.automagica.ai/topics/post-5
- 生成AI活用事例 製造業界編(消費財・食品) – インターセクト株式会社, https://intersect.inc/scW0fnId/A9Tjn98G
- 伊藤園、「お~いお茶」に生成AIパッケージ – Impress Watch, https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1526837.html
- 業界初!『商品デザイン用画像生成AI』を活用したデザインで伊藤園「お~いお茶 カテキン緑茶」リニューアル発売 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000062916.html
- OTとITの融合により、サントリー次世代ファクトリーがめざすものとは|Lumada – 日立製作所, https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/stories/20221025_suntory/index.html
- スマートファクトリー|事例紹介|デジタルへの取り組み|サントリー食品インターナショナル, https://www.suntory.co.jp/softdrink/company/digital/factory.html
- T3 SmartSCM – 導入事例 – 飲料メーカー – ザイオネックス株式会社, https://zionex.co.jp/t3smartscm/cases/case01/index.html
- NEC、AIによる新商品需要予測と予測精度マネジメントによる収益拡大に向けた戦略立案高度化の実証実験をアサヒ飲料と実施, https://jpn.nec.com/press/202312/20231220_01.html
- NEC、AIを活用してお客様の戦略的な意思決定を支援する「NEC Advanced-S&OP ソリューション」を販売開始, https://jpn.nec.com/press/202406/20240617_01.html
- サントリーグループ「プラスチック基本方針」策定 | ニュースリリース, https://www.suntory.co.jp/news/article/13473.html
- 資源循環 サントリーグループのサステナビリティ サントリー, https://www.suntory.co.jp/company/csr/env_circular/
- サントリーグループのサステナビリティ サステナビリティに関する7つのテーマ「01:水」, https://www.suntory.co.jp/company/csr/themes/water/
- 「キリングループ2022年-2024年中期経営計画」スタート – グルメプレス, https://gourmetpress.net/834601/
- 長期経営構想「キリングループ・ビジョン 2027」及び 「キリングループ 2019 年-2021 年中期経営計画」の策定 再生から成長へ, https://www2.jpx.co.jp/disc/25030/140120190214477095.pdf
- 「清涼飲料水統計2024」(PDF), https://www.j-sda.or.jp/statistically-information/pdf/2024jsda_databook.pdf
- 全国清涼飲料連合会、「清涼飲料水統計2024」が発刊 – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/news/hasegawak20240612104221077
- 8. Focus sector: Food and beverage, https://vm.ee/sites/default/files/documents/2024-05/Focus%20Sector_Food%20and%20Beverages_0.pdf
- JAPAN: Soft drinks market shrinking – Just Drinks, https://www.just-drinks.com/news/japan-soft-drinks-market-shrinking-2/
- 食品ECの成功事例&トレンドに学ぶ|D2Cブランドが売れる仕組みを築く方法 – BiNDec, https://bindec.jp/media/555953147543/
- 日本の食品・飲料D2Cブランド12選!成功事例から共通項を読み解く – SMMLab, https://smmlab.jp/article/d2c-food-beverage-brands/