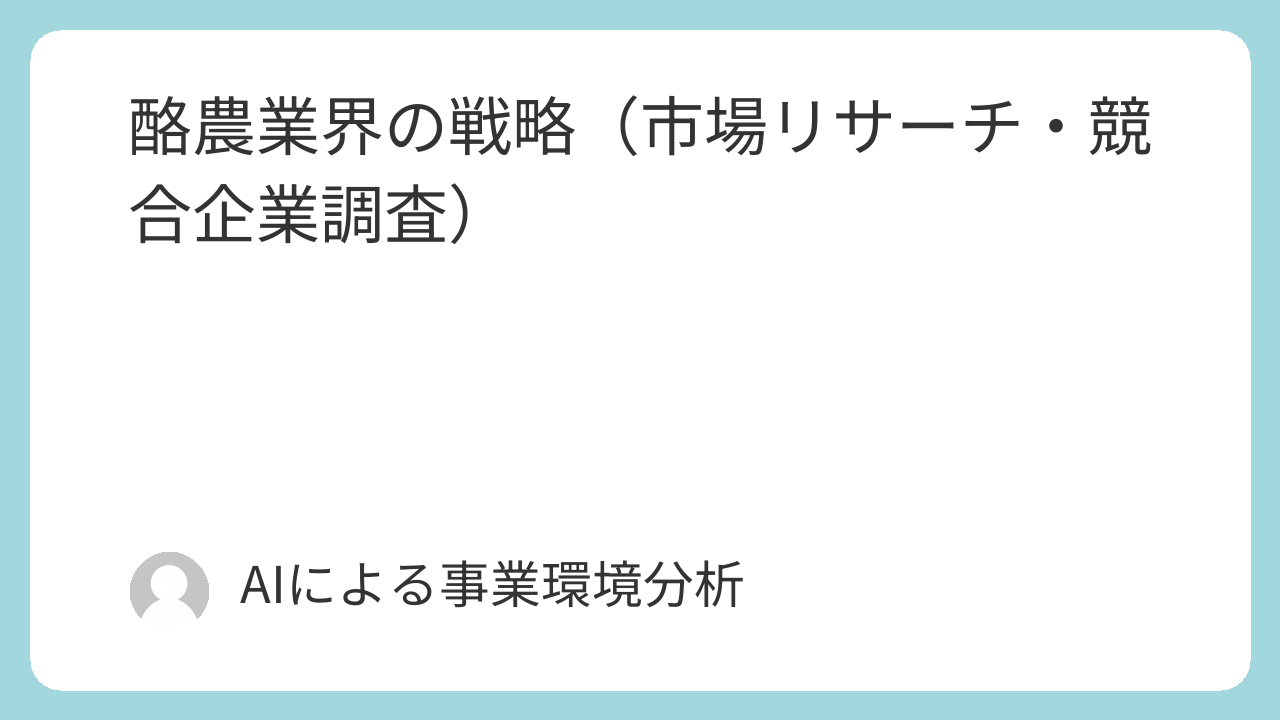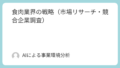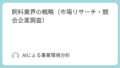生存と進化の岐路:AIと持続可能性が再定義する酪農業界の次世代戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートは、日本の酪農業界が直面する多重的な構造変化を深く分析し、持続可能な成長を実現するための次世代戦略を提言することを目的とする。調査範囲は、生乳生産(酪農家)から乳業(加工・製造)、関連資材(飼料、機械)、流通・小売に至るバリューチェーン全体を網羅する。
日本の酪農業界は、深刻な後継者不足、飼料・エネルギーコストの高騰、環境負荷への社会的要請、そして「代替乳」という破壊的イノベーションの台頭という、複合的な危機に直面している。規模と効率を追求する従来の成長モデルは限界を迎え、業界は生存と進化の岐路に立たされている。しかし、この構造変化は、新たな価値創造の機会をもたらすものでもある。本分析の結論として、今後の勝敗を分けるのは、従来の「生乳」というモノ(商品)の生産・販売から脱却し、AIと精密酪農技術を駆使して「データ」「乳質」「環境価値」という無形の資産を収益化できるか否かにある。代替乳との競争を脅威としてのみ捉えるのではなく、プロテイン・栄養市場全体における自社のポジショニングを再定義する好機と捉える視点が不可欠である。
本分析に基づき、経営層に対して以下の5つの戦略的推奨事項を提言する。
- データアセット経営への転換: 「精密酪農(Precision Dairy Farming)」への投資を単なるコスト削減手段ではなく、高付加価値な生乳(例:チーズ製造最適乳、特定栄養強化乳)の生産や、環境価値(例:カーボンクレジット)を定量化・収益化するためのコア資産と位置づける。
- 競争領域の再定義:「牛乳 vs. 代替乳」から「プロテイン・栄養ソリューション」へ: 牛乳・乳製品が持つ独自の栄養的価値や風味を科学的根拠に基づき再訴求すると同時に、成長市場である代替乳事業へ戦略的に参入し、ポートフォリオを多様化する。
- 環境負荷の資産化(Liability to Asset): 糞尿処理やメタンガス排出といった長年の課題を、バイオガス発電によるエネルギー事業、環境再生型農業による土壌炭素貯留(カーボンファーミング)といった新たな収益源へと転換するビジネスモデルを構築する。
- 次世代型人材・オペレーションモデルの構築: 搾乳ロボット等の自動化を積極的に推進し、省人化を実現する一方で、データアナリストやIT技術者といった新たな専門人材の育成・確保に注力し、データ駆動型の経営体制を確立する。
- レジリエントなサプライチェーンの再構築: 輸入飼料への過度な依存という最大のリスクを低減するため、国産飼料(飼料用米、エコフィード等)の生産・利用拡大や、地域内での耕畜連携を強化し、持続可能で安定した生産基盤を確立する。
第2章:市場概観(Market Overview)
世界の市場動向
世界の生乳生産量は、アジア、特にインドやパキスタン、中国における効率的な大規模酪農の増加と乳牛頭数の増加を背景に、持続的な成長が見込まれている 1。国連食糧農業機関(FAO)は、2024年の世界の生乳生産量を前年比1.4%増の約9億7900万トンと予測している 1。中長期的には、2030年には10億2000万トン 3、2034年には11億4600万トンに達すると予測されており、他の主要農産物を上回る成長率が期待される 4。この成長は、飼料効率の改善や育種改良による1頭当たり乳量の増加が牽引する 4。一方で、欧州連合(EU)では環境規制の強化などを背景に生産量が微減すると予測されており、成熟市場と新興市場での成長ダイナミクスの違いが鮮明になっている 4。
日本の市場動向
日本の酪農市場は、世界的な成長トレンドとは対照的に、構造的な課題に直面し、縮小と再編の過程にある。
生産量・酪農家戸数・飼養頭数の推移
日本の生乳生産量は、近年減少傾向にある。令和5年度(2023年度)の全国生産量は732万トンと、前年度比で2.8%減少した 6。これは生産者団体による生産抑制や猛暑の影響が要因である 6。ただし、令和6年度(2024年度)には前年比1.2%増の741万トンと、3年ぶりの増産に転じる見通しが示されている 7。
この生産動向の背景には、深刻な担い手不足がある。酪農家戸数は年々3~5%のペースで減少し続けており、令和4年(2022年)には1万3300戸 8、令和6年(2024年)には1万1900戸まで減少した 6。一方で、1戸あたりの飼養頭数は増加傾向にあり、令和4年には初めて100頭を突破するなど、大規模化・集約化が急速に進んでいる 8。
地域別に見ると、この構造変化は一様ではない。北海道では生産量が維持・増加傾向にあるのに対し、都府県では大幅な減少が続いており、国内酪農の生産基盤が北海道へ集中する傾向が強まっている 10。
市場セグメンテーション分析
用途別:
国産生乳(2022年度)の約52%が飲用乳等向け、約47%がチーズ、バター、脱脂粉乳などの乳製品向けに仕向けられている 6。飲用乳向けは乳価が高い一方、需給バランスが崩れて生乳が余剰になると、保存が効くバター・脱脂粉乳向けに仕向けられる。この用途別構成比の変動が、業界全体の収益性に大きな影響を与える。
代替乳市場:
代替乳市場は、伝統的な牛乳市場の停滞を尻目に、急成長を遂げている。富士経済によると、代替乳を含む日本の代替タンパク食品市場は、2024年の1,239億円から2030年には1,473億円に成長すると予測されている 12。この市場の8割以上を占めるのが代替乳であり、市場の牽引役となっている 12。
特にオーツミルクの成長は著しく、ある調査では日本の市場規模が2024年に5,170万ドル、2033年には1億6,310万ドルに達し、年平均成長率(CAGR)12.6%で成長すると予測されている 13。また、直近3年間で市場規模が9倍に成長したとのデータもあり、消費者の急速な受容を示している 15。豆乳が確立された市場を形成する中、アーモンドミルクも健康・美容効果への期待から人気を博している 16。
以下の表は、伝統的な酪農市場と代替乳市場の対照的な成長ダイナミクスを明確に示している。
| 指標 | 2022年 | 2024年(予測/実績) | 2030年(予測) | 成長トレンドと戦略的意味合い |
|---|---|---|---|---|
| 国内生乳生産量 | 753万トン 10 | 741万トン 7 | 横ばい~微減 | 供給基盤の脆弱化が進行。規模拡大によるコスト競争力強化(北海道)と、高付加価値化による差別化(都府県)の二極化が必須。 |
| 代替タンパク食品市場規模 | – | 1,239億円 12 | 1,473億円 12 | 市場全体の成長を牽引。乳業メーカーにとって、この成長市場への参入は脅威への対応であると同時に、新たな収益機会となる。 |
| うち代替乳市場規模 | – | 約1,000億円以上 (推定) 12 | 約1,200億円以上 (推定) 12 | 代替タンパク市場の主要セグメント。牛乳との直接的な競合関係が最も激しい。 |
| うちオーツミルク市場規模 | – | 5,170万ドル (約77億円) 13 | 1億6,310万ドル (約244億円, 2033年予測) 13 | 代替乳の中でも特に高い成長率を誇る。消費者の健康・環境意識の高まりを象徴するセグメント。 |
市場成長ドライバーと阻害要因
- 成長ドライバー: 消費者の健康志向の高まり(高タンパク、プロバイオティクス製品への需要増)18、機能性表示食品市場の拡大、政府による食料安全保障政策。
- 阻害要因: 深刻な後継者不足と生産者の高齢化 19、飼料・エネルギー価格の高騰による生産コストの急増 21、円安による輸入飼料コストの上昇 23、そして代替乳の急速な普及による牛乳需要の侵食。
業界の主要KPIベンチマーク分析
- 1戸あたり飼養頭数: 103.1頭(令和4年)と、規模拡大が継続 8。
- 1頭あたり乳量: 8,809 kg(令和5年度)6。生産性の向上は続いているものの、コスト上昇を吸収するには至っていない。
- 生乳生産コストと乳価: 令和4年の搾乳牛1頭当たり生産費は100万8,902円(前年比14.1%増)、生乳100kg当たりでは9,669円(同9.8%増)と、コストが急騰している 21。乳価の上昇がコスト増に追いつかず、酪農経営の収益性を著しく圧迫している。
- 乳業メーカーの収益性: 大手乳業メーカー(明治、森永、雪印メグミルク)は、原材料コストの上昇と小売からの価格圧力の板挟みとなり、利益率の確保に苦慮している。
この市場概観から浮かび上がるのは、日本の酪農市場が二極化しつつあるという構造的な変化である。一方は、北海道を中心とした規模拡大と効率化を追求するモデル。もう一方は、コスト高と後継者難に喘ぐ都府県の小規模経営体である。この二極化は、それぞれに異なる戦略的アプローチを要求する。さらに、市場全体の成長が代替乳セグメントによってのみ牽引されているという事実は、乳業メーカーが自らの事業領域を「牛乳」から「プロテイン・栄養」へと再定義する必要性を強く示唆している。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
酪農業界を取り巻くマクロ環境は、複雑かつ急速に変化しており、事業戦略の策定にあたってはこれらの外部要因を深く理解することが不可欠である。PESTLEフレームワーク(政治、経済、社会、技術、法規制、環境)を用いて分析する。
政治(Politics)
- 食料安全保障政策と補助金制度: 政府は、国内の食料自給率の観点から酪農を重要産業と位置づけ、様々な補助金や交付金制度(例:配合飼料価格安定制度の特例措置)を通じて経営を支援している 25。これらの政策は経営の下支えとなる一方、市場原理から乖離した生産構造を温存する側面もある。
- 生乳の価格決定メカニズム: 「指定生乳生産者団体制度」は、農協などが酪農家から生乳販売を一体的に受託し、乳業メーカーと交渉することで、個々の農家では持ち得ない価格交渉力を確保する仕組みである 26。これは価格の安定に寄与するが、硬直的で市場の需給動向を迅速に反映しにくいという課題も抱えている 28。近年、より高い乳価を求めて指定団体を離脱し、独自に販売する「アウトサイダー」の動きも見られる 29。
- 国際貿易協定(TPP, 日欧EPAなど): TPPや日欧EPAなどの貿易協定により、チーズやホエイを中心に輸入乳製品の関税が削減・撤廃され、市場アクセスが拡大した 30。これにより、国産乳製品は安価な輸入品との厳しい価格競争に晒されており、特に加工用乳製品の分野で大きな影響を受けている 30。
経済(Economy)
- 穀物・原油相場と為替レート: 酪農経営は、生産コストの大部分を占める飼料とエネルギーの価格変動に極めて脆弱である。飼料原料の多くを輸入に依存しているため、国際的な穀物相場(トウモロコシ、大豆粕など)の変動と、円安がコストを直接的に押し上げる 23。特に近年の急激な円安は、酪農経営の収益性を著しく悪化させている。
- 金利政策: スマート酪農化に向けた自動搾乳ロボットや最新鋭の牛舎建設には、数億円規模の設備投資が必要となる。今後の金利政策の動向は、これらの大規模投資の意思決定に直接的な影響を与え、業界の生産性向上スピードを左右する可能性がある。
社会(Society)
- 消費者の価値観の多様化:
- 健康志向: 高タンパク質、プロバイオティクス、低脂肪といった付加価値を持つ乳製品への需要が高まっている 18。
- エシカル消費: アニマルウェルフェア(動物福祉)や環境配慮への関心が高まり、購買決定における重要な要素となりつつある。アニマルウェルフェアに配慮した製品に対しては、価格が高くても購入意向を示す消費者が一定層存在する 34。
- 代替乳の受容: アレルギーや乳糖不耐症といった身体的な理由に加え、健康的なイメージ、環境負荷の低さ、味の好みなど、多様な動機から代替乳を選択する消費者が急増している 36。
- 人口動態と後継者問題: 農業従事者全体の高齢化と減少が深刻であり、特に酪農は労働集約的であるため、後継者不足が事業継続の最大の障壁となっている 19。都府県の経営主の平均年齢は59.2歳に達し、60歳以上が半数以上を占めるなど、事業承継は喫緊の課題である 20。
技術(Technology)
- スマート酪農(精密酪農)の進化: 自動搾乳ロボット、IoTセンサー(個体行動モニタリング)、ドローン、AIによるデータ解析といった技術が急速に進化・普及している 38。これらの技術は、単なる省力化に留まらず、疾病の早期発見、繁殖管理の最適化、乳質の向上など、経営の質そのものを変革するポテンシャルを秘めている。
- 糞尿処理・バイオガス技術: 糞尿をメタン発酵させ、発電や熱利用を行うバイオガスプラント技術が進化している。これは環境負荷を低減すると同時に、エネルギーコストの削減や売電による新たな収益源となり得る。
- 育種改良技術: ゲノム情報を活用した育種改良(ゲノミック選抜)により、乳量や乳質、疾病耐性といった能力を効率的に高めることが可能になっている。
法規制(Legal)
- 食品安全基準: HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化など、食品安全に関する基準は年々厳格化しており、遵守は事業継続の前提条件である。
- アニマルウェルフェア(動物福祉): EUなどではアニマルウェルフェアに関する法規制が強化されており、日本でもJGAP(農業生産工程管理)認証などでその考え方が導入されている 41。今後、国際基準に準拠した国内法の整備が進む可能性があり、つなぎ飼いからフリーストールや放牧への移行など、飼養方法の変更を迫られるリスクがある 43。
- 表示規制: 「牛乳」「乳製品」といった表示は法律で厳密に定義されており、植物性ミルクとの明確な区別がなされている。これは牛乳の価値を守る一方で、消費者の混乱を招かないようなマーケティング戦略が求められる。
環境(Environment)
- 温室効果ガス(GHG)排出: 牛のゲップ(腸内発酵)由来のメタンガスは、二酸化炭素の約25~30倍の温室効果を持つとされ、酪農はGHGの主要な排出源の一つと認識されている 45。これは業界全体のレピュテーションリスクであり、政府の削減目標達成に向けた圧力が高まっている。
- 糞尿による環境汚染: 糞尿の不適切な管理は、水質汚染や土壌汚染、悪臭の原因となる 47。持続可能な経営のためには、適切な処理と資源としての利活用(堆肥化、バイオガス化)が不可欠である。
- 気候変動の影響: 夏場の猛暑は乳牛に深刻な熱ストレスを与え、乳量の低下や繁殖成績の悪化を招く 48。また、気候変動は飼料作物の生育にも影響を及ぼし、生産基盤を不安定化させる要因となっている 47。
これらの外部環境要因を総合すると、酪農業界は「コスト上昇」と「コンプライアンス要求の高まり」という二重の圧力に晒されていることがわかる。経済要因がコストを押し上げる一方で、社会・環境・法規制の各側面からの要求(アニマルウェルフェア、GHG削減など)は、直接的な収益に結びつきにくい追加投資を強いる。この「コスト・コンプライアンス・スクイーズ」から脱却するためには、技術革新をテコに、コンプライアンス対応を新たな付加価値や収益源へと転換する戦略的思考が不可欠である。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
マイケル・ポーターのFive Forcesモデルを用いて、酪農業界の収益性に影響を与える競争環境を構造的に分析する。
売り手の交渉力:強い
酪農家にとって、主要な資材を供給する売り手の交渉力は極めて強い。
- 配合飼料メーカー: フィード・ワン、中部飼料、日清丸紅飼料といった少数の大手企業による寡占市場が形成されている 49。飼料は酪農経営における最大のコスト項目であり、その価格は国際穀物相場に連動するため、個々の酪農家が価格交渉を行う余地はほとんどない。
- 農業機械・アグリテック企業: 特に自動搾乳ロボットなどの先進技術分野では、DeLaval(スウェーデン)、Lely(オランダ)といったグローバル企業が市場を支配している 52。これらの企業が提供する製品は、高い技術力と特許に裏打ちされており、スイッチングコストも高いため、非常に強い価格決定権を持つ。
- 動物用医薬品・精液企業: これらの分野も専門性が高く、グローバルな寡占化が進んでおり、売り手の交渉力は強い。
買い手の交渉力:強い
生乳を買い取る側の交渉力も同様に強い。
- 乳業メーカー: 明治、森永乳業、雪印メグミルクの大手3社が市場の過半を占める寡占状態にある 54。数千戸の酪農家に対して買い手が数社に集約されているため、構造的に買い手優位となっている。指定生乳生産者団体が交渉を一本化しているものの、最終的な価格決定においては乳業メーカー側の意向が強く反映される傾向にある。
- 小売業者: イオンやセブン&アイ・ホールディングスなどの大手小売チェーンは、その巨大な販売網を背景に強い交渉力を持つ。特に、低価格なプライベートブランド(PB)牛乳は、ナショナルブランド(NB)製品に対する強力な価格引き下げ圧力となっている 57。PB商品の開発力は、乳業メーカー、ひいては酪農家が受け取る乳価にまで影響を及ぼす。
新規参入の脅威:低い~中程度
- 伝統的な酪農経営: 新規参入の障壁は非常に高い。広大な土地の確保、牛舎や搾乳施設への莫大な初期投資、家畜の導入、そして何よりも飼養管理に関する専門的なノウハウの蓄積が必要であり、異業種からの参入は極めて困難である。
- 異業種による大規模スマート酪農: IT企業や電力会社などが、資本力を活かして最先端技術を導入した大規模農場を建設する可能性は存在する。しかし、土地の確保や、確立された集荷・流通システムへのアクセス、動物を扱うノウハウの欠如などが依然として高い参入障壁となる。直接的な生産者としての参入よりも、アグリテック分野での技術提供という形での参入が現実的である。
代替品の脅威:非常に強い(かつ増大中)
これは、業界構造を根底から揺るがす最も強力な圧力である。
- 植物性ミルク(オーツ、アーモンド、豆乳など): 健康志向、環境意識、アニマルウェルフェアへの関心の高まりを背景に、市場シェアを急速に拡大している 12。これらはもはやニッチな代替品ではなく、牛乳の直接的な競合製品として消費者の選択肢に定着している。
- 培養乳(精密発酵): これは将来的な、しかし破壊的な脅威である。微生物(酵母など)を遺伝子的にプログラムし、牛を介さずに牛乳と同一のタンパク質(カゼイン、ホエイ)を生成する技術である 59。Perfect Day(米国)などのスタートアップが先行しており、日本でもKinishなどの企業が研究開発を進めている 60。この技術がコスト面で牛乳と同等になり、規制当局の承認を得た場合、酪農という農業形態そのものを不要にする可能性を秘めている。
業界内の競争:激しい
- 酪農家間の競争: 経営の持続性をかけて、規模拡大によるコスト削減競争が繰り広げられている。また、乳質(乳脂肪率、無脂乳固形分、細菌数など)を改善し、品質プレミアムを得るための競争も存在する。この競争の結果、体力の劣る経営体が淘汰され、業界の集約化が進行している。
- 乳業メーカー間の競争: 製品開発(特にヨーグルトなどの高付加価値製品)、ブランド構築、マーケティング活動において熾烈な競争が展開されている。近年では、大手3社がほぼ同時に植物性ミルク市場に参入するなど、新たな競争領域が生まれている 62。
このFive Forces分析から明らかになるのは、酪農業界が「砂時計」のような収益構造に陥っている点である。上部には強力な供給業者(飼料、機械)、下部には強力な買い手(乳業メーカー、小売)が存在し、その両サイドから強い圧力に晒されている。その結果、中間で分断された多数の酪農家は、バリューチェーンの中で最も利益を確保しにくいポジションに置かれている。この構造的な収益性の低さが、後継者不足や離農を加速させる根本的な要因となっている。さらに、代替品の脅威は、従来の「模倣品(植物性ミルク)」から、将来的には「代替品(培養乳)」へと質的に変化しつつあり、業界の前提そのものを覆しかねない。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析
日本の酪農サプライチェーンは、以下の構造で成り立っている。
「海外飼料生産/輸入 → 配合飼料メーカー → 酪農家(生乳生産) → 集荷(農協・指定団体) → 乳業メーカー(加工) → 物流 → 小売 → 消費者」
このチェーンには、いくつかの構造的なボトルネックと脆弱性が存在する。
- ボトルネック①:海外飼料への極端な依存:
日本の飼料自給率は全体で27%程度に過ぎず、特に乳牛の主食である濃厚飼料(トウモロコシ、大豆粕など)の自給率はわずか13%である 63。これは、サプライチェーン全体のコストと安定性が、海外の生産状況、国際市況、地政学リスク、為替レートに完全に依存していることを意味する。ウクライナ情勢の緊迫化は、穀物価格を急騰させ、日本の配合飼料価格に直接的な打撃を与えた 23。この脆弱性は、日本の酪農経営における最大のリスク要因である。 - ボトルネック②:硬直的な集荷・流通システム:
指定生乳生産者団体による一元的な集荷・販売システムは、全量を確実に販売できるという安定性をもたらす一方で、いくつかの非効率性を生んでいる 26。例えば、「合乳」(複数の農家の生乳を混ぜること)は、個々の農家が高品質な生乳を生産しても、それが最終製品の価格に反映されにくい構造を生み出す 26。また、生産者が直接、特徴ある生乳を特定の乳業メーカーや加工業者に販売するような、柔軟な取引を阻害する側面もある 29。 - ボトルネック③:生乳の価格決定プロセス:
乳価は、指定団体と乳業メーカーとの間の交渉によって決定されるが、そのプロセスは複雑で透明性が高いとは言えない。需給バランスが崩れ生乳が余剰となった場合、価格の安い乳製品向け(バター、脱脂粉乳)に仕向けざるを得ず、これが全体の乳価を下げる圧力となる 28。
バリューチェーン分析
酪農業の価値(バリュー)の源泉は、時代とともに大きく変化している。
- 伝統的な価値の源泉:「規模と効率」
かつては、より多くの牛を、より少ないコストで飼育し、1頭あたりの乳量を最大化することが価値創造の主たる源泉であった。これは、生乳をコモディティ(汎用品)と捉え、生産量を追求するモデルである。 - シフトする価値の源泉:「乳質」「データ」「環境価値」
コモディティ化からの脱却を図る上で、新たな価値の源泉が重要性を増している。- 乳質(高付加価値): 単なる乳脂肪率や無脂乳固形分率といった指標だけでなく、特定の機能性成分(例:オメガ3脂肪酸)を豊富に含む牛乳 65 や、特定のチーズ製造に最適なタンパク質組成を持つ牛乳など、用途に特化した「オーダーメイド型」の生乳生産が新たな価値を生む。
- データ(精密酪農): 自動搾乳ロボットや個体管理センサーが収集する膨大なデータは、それ自体が新たな経営資源となる。個体ごとの健康状態、乳量・乳質、行動パターンなどのデータを解析することで、生産効率を極限まで高めるだけでなく、そのデータを活用して「24時間体制で健康管理された牛から搾った、安全・安心な牛乳」といった、トレーサビリティと信頼性を裏付ける強力なマーケティングツールとなり得る。
- 環境価値(サステナビリティ): これが最も注目すべき価値のシフトである。従来はコスト要因であった環境負荷(メタンガス排出、糞尿処理)を、技術を用いて価値に転換する。例えば、メタン排出量を削減する飼料給与や、糞尿を利用したバイオガス発電は、カーボンクレジットの創出やエネルギー販売といった直接的な収益機会につながる。また、放牧や不耕起栽培などを通じて土壌に炭素を貯留する「環境再生型農業(リジェネラティブ農業)」は、環境貢献をブランド価値として消費者に訴求する源泉となる 66。ダノンやネスレといったグローバル企業は、サプライチェーン全体のGHG排出量削減(Scope 3)を目標に掲げており、環境価値を創出する酪農家は、将来的にこれらの企業からプレミアム価格で選ばれるサプライヤーとなる可能性がある 67。
この分析が示すのは、酪農業界の未来が、物理的な「モノ」の生産から、データと信頼性に基づいた「コト」の提供へと移行しつつあるという事実である。サプライチェーン上の最大のリスクである飼料依存からの脱却を図りつつ、バリューチェーン上で「環境価値」という新たな収益の柱をいかに構築できるかが、今後の持続的成長の鍵を握る。
第6章:顧客需要の特性分析
BtoB顧客(乳業メーカー)
乳業メーカーが生乳を調達する際のKBF(Key Buying Factor:主要購買決定要因)は、多岐にわたる。
- 乳価: 最も重要な要素であり、調達コストに直結する。指定団体との交渉で決定されるが、常にコスト削減圧力がかかっている。
- 乳質: 乳脂肪率、無脂乳固形分、体細胞数、細菌数が基本的な品質指標となる。これらの指標は製品の歩留まりや風味、保存性に直接影響するため、極めて重要視される。高品質な生乳にはプレミアムが支払われることもある。
- 供給の安定性: 乳業メーカーの工場は24時間365日稼働しており、計画通りに安定した量の生乳が供給されることが事業の前提となる。指定団体制度は、この安定供給を保証する上で重要な役割を果たしている。
- トレーサビリティ: 食品安全への要求が高まる中、生産された農場まで遡ることができるトレーサビリティの確保は必須条件である。
近年では、これらに加えてサステナビリティ要素(アニマルウェルフェアへの配慮、環境負荷の低減など)が新たなKBFとして浮上しつつある。これは、最終製品のブランド価値向上や、企業のCSR(企業の社会的責任)活動の一環として、サプライチェーン全体での取り組みが求められているためである。
BtoC顧客(消費者)
消費者の乳製品購買行動は多様化しており、複数のセグメントに分類できる。
- 価格重視層: PB商品などを中心に、最も安価な製品を選択する層。特売などの価格変動に敏感に反応する。
- 健康志向層: 高タンパク、低脂肪、カルシウム強化、プロバイオティクス(善玉菌)入りなど、特定の健康機能を持つ製品を積極的に選択する層。価格が多少高くても、健康への便益を重視する。
- エシカル消費層: アニマルウェルフェア認証、放牧酪農、環境再生型農業で生産された製品など、生産背景にある倫理的・環境的価値を重視する層。まだ少数派ではあるが、意識の高い消費者を中心に影響力を増している。
- ファミリー層: 子供の成長に必要な栄養源として、安全性や鮮度、ブランドの信頼性を重視する。消費量が多く、家計への影響も考慮する。
- 嗜好・風味重視層: 特定のブランドの味やコク、風味を好み、指名買いする層。
消費者が牛乳・乳製品に求める価値(KBF)は、これらのセグメントによって異なるが、共通して「価格」「鮮度」「味」「安全性」が基盤となる。その上で、「機能性」や「ブランドイメージ」「生産背景のストーリー」が付加価値として機能する。
消費者が「代替乳」を選ぶ動機
消費者が牛乳の代わりに代替乳を選ぶ動機は、複合的である。
- 身体的理由: 乳糖不耐症や牛乳アレルギーを持つ消費者にとっては、代替乳は必要不可欠な選択肢である。
- 健康イメージ: 代替乳は「低カロリー」「低脂肪」「コレステロールゼロ」といった健康的なイメージが強い 17。特にアーモンドミルクはビタミンEの豊富さなどが、オーツミルクは食物繊維などが訴求されている 16。
- 環境負荷への懸念: 牛乳生産に伴う温室効果ガス排出や水資源の使用量に対し、植物由来の代替乳は環境負荷が低いという認識が広がっている 69。サステナビリティを重視する消費者にとって、これは重要な選択理由となる。
- アニマルウェルフェアへの配慮: 工業的な畜産システムに倫理的な懸念を抱く消費者が、動物を利用しない代替乳を選択するケースがある。動物飼育に抵抗感を持つ消費者は、代替タンパク製品を試す意向が高いという調査結果もある 70。
- 味の好みと多様性: 豆乳の独特の風味や、オーツミルクのクリーミーさ、アーモンドミルクの香ばしさなど、牛乳とは異なる風味を好み、コーヒーや料理に合わせて使い分ける消費者も増えている。
これらの分析から、乳業メーカーや酪農家は、もはや「牛乳」という単一の製品カテゴリーの中だけで競争しているのではないことがわかる。消費者は「白い飲み物」という大きな枠の中で、その日の気分や目的、価値観に応じて牛乳、豆乳、オーツミルクなどを自由に選択している。したがって、牛乳が提供できる独自の価値(例:動物性タンパク質としての品質、カルシウムの吸収率、自然な風味)を再定義し、代替乳にはない魅力を明確に伝えるコミュニケーション戦略が不可欠である。
第7章:業界の内部環境分析
VRIO分析
VRIOフレームワーク(Value: 経済的価値、Rarity: 希少性、Imitability: 模倣困難性、Organization: 組織)を用いて、酪農業界が持つ持続的な競争優位の源泉となりうる経営資源やケイパビリティを評価する。
| 経営資源/ケイパビリティ | 価値 (V) | 希少性 (R) | 模倣困難性 (I) | 組織 (O) | 競争優位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広大な土地(特に北海道) | 有 | 有 | 高 | 有 | 持続的競争優位 |
| 優良な牛群(血統・ゲノム情報) | 有 | 中 | 中 | 有 | 一時的競争優位 |
| 長年の飼育ノウハウ | 有 | 中 | 中 | 否 | 競争均衡 |
| 最新のスマート酪農設備 | 有 | 低 | 低 | 有 | 一時的競争優位 |
| 地域コミュニティとの関係 | 有 | 有 | 高 | 有 | 持続的競争優位 |
| 強力な乳業ブランド | 有 | 有 | 高 | 有 | 持続的競争優位 |
- 広大な土地: 特に北海道の広大な草地は、低コストな放牧や自給飼料生産を可能にし、都府県酪農に対して明確なコスト優位性をもたらす。土地という資源は物理的に模倣不可能であり、持続的な競争優位の源泉となる。
- 優良な牛群: 優れた血統やゲノム情報を持つ牛群は高い生産性を実現するが、精液や受精卵の市場を通じて他者もアクセス可能であるため、希少性や模倣困難性は中程度であり、一時的な優位に留まる。
- 長年の飼育ノウハウ: 経験に基づくノウハウは価値があるが、属人的で形式知化が難しく、組織全体で活用(O)できていない場合が多い。また、技術の進化により陳腐化する可能性もある。
- 最新のスマート酪農設備: 設備自体は資金があれば誰でも導入可能であり、希少性・模倣困難性は低い。競争優位を生むのは設備そのものではなく、そこから得られるデータを活用し、経営を改善する組織能力である。
- 地域コミュニティとの関係: 耕種農家との連携による堆肥の供給や飼料の確保、地域住民の理解と協力といった関係資本は、長年にわたって構築されるものであり、模倣が極めて困難な持続的競争優位の源泉となり得る。
- 強力な乳業ブランド: 明治「おいしい牛乳」や森永乳業、雪印メグミルクといったブランドは、消費者の信頼とロイヤルティの源泉であり、高いブランド価値は模倣困難な資産である。
人材動向
- 需要と供給のギャップ: 酪農従事者、特に後継者の供給不足は業界の存続を脅かす最大の課題である 19。基幹的農業従事者の平均年齢は68.7歳(2023年)に達し、高齢化が著しい 19。新規就農者は存在するものの、離農者の数を補うには全く足りていない。
- 求められる人材像の変化: スマート酪農の普及に伴い、従来型の「家畜の世話をする労働者」から、新たなスキルセットを持つ人材が求められている。具体的には、センサーから得られるデータを分析して経営判断に活かすデータサイエンティスト型経営者や、搾乳ロボットや各種センサーのメンテナンスを行うIT/機械技術者である。このような人材の育成と確保は、業界全体の課題となっている 72。
- 賃金水準と労働環境: 酪農は、早朝から深夜までの長時間労働と、365日休みがないという過酷な労働環境が常態化しやすい。他産業と比較して賃金水準が高いとは言えず、若者にとって魅力的な就職先とはなっていないのが実情である 75。人材を確保するためには、賃金の上昇だけでなく、自動化による労働時間の短縮や休暇制度の整備といった労働環境の抜本的な改善が不可欠である。
労働生産性
- 現状: 労働生産性は、従業員1人あたり、あるいは1頭あたりの生乳生産量で測られる。日本の酪農は、欧米の大規模酪農と比較すると、労働生産性の面で見劣りする部分がある。
- 自動化・スマート化による向上ポテンシャル: 自動搾乳ロボット、自動給餌機、自動糞尿処理装置などの導入は、労働生産性を飛躍的に向上させるポテンシャルを持つ 40。例えば、搾乳作業は1日の労働時間の中で最も大きな割合を占めるが、これを自動化することで、従業員は個体管理や繁殖管理といった、より付加価値の高い業務に時間を割くことが可能になる。ある試算では、AIとロボットの活用により労働時間が40%削減される可能性も示唆されている 76。
VRIO分析が示すように、持続的な競争優位は、もはや購入可能な物理的資産(機械や牛)からは生まれにくい。模倣困難なのは、データ活用能力、地域との関係資本、そして強力なブランドといった無形資産である。人材面での深刻な危機は、裏を返せば、テクノロジーを活用して労働生産性を劇的に改善し、より魅力的で知的な産業へと転換する強力な動機付けとなり得る。
第8章:AIと精密酪農がもたらす破壊的イノベーション
精密酪農(Precision Dairy Farming)とAIの融合は、単なる生産性の向上(コスト削減)という次元を超え、酪農経営のあり方そのものを根底から変革する破壊的イノベーションである。データが新たな経営資源となり、品質、環境価値、そして収益モデルを再定義する。
AIが生産プロセスに与える影響
AIは、センサーが収集する膨大なデータをリアルタイムで解析し、人間では不可能なレベルの精密な個体管理とプロセスの最適化を実現する。
- 個体管理の超精密化:
- 疾病の超早期予兆検知: 牛の首、胃、脚などに取り付けられたIoTセンサーが、活動量、反芻時間、体温、歩行パターンといったデータを24時間収集する 38。AIはこれらのデータを学習し、個体ごとの正常なパターンを把握する。乳房炎や代謝疾患などの疾病発症前に現れる微細な行動変化をAIが検知し、管理者にアラートを発することで、重症化する前の超早期介入が可能となる 77。
- 繁殖管理の最適化: 活動量の急増や特徴的な行動パターンから、AIが発情の兆候を極めて高い精度で検知する 78。これにより、最適な授精タイミングを逃さず、受胎率の向上と空胎期間の短縮に貢献する。DeLaval社のReProシステムなどは、乳汁中のプロゲステロン濃度を自動分析し、繁殖サイクルを正確に把握する 79。
- 搾乳プロセスの自動化とデータ化:
- リアルタイム乳質分析: Lely社やDeLaval社の自動搾乳ロボットは、搾乳のたびに個体ごとの乳量、乳脂肪率、乳タンパク率、体細胞数、電気伝導度などをリアルタイムで測定・記録する 40。
- 個体別フィードバック: AIはこれらのデータを分析し、乳房炎の疑いがある牛の乳を自動的に分離廃棄したり、乳量や乳成分に応じて給与する濃厚飼料の量を自動調整したりするなど、即時的なフィードバックループを形成する 81。
- 飼料給与の最適化:
- 個体別栄養リコメンデーション: AIが個体ごとの泌乳ステージ、乳量、乳成分、活動量、体重などのデータを統合的に分析し、その牛にとって最適な栄養要求量を算出する。これに基づき、濃厚飼料の配合や給与量を自動でリコメンデーションし、飼料の無駄をなくし、生産性を最大化する。これにより、飼料コストを5~10%削減しつつ、乳量を8~12%増加させることも可能との試算もある 76。
AIが経営・意思決定に与える影響
AIは、生産現場のオペレーションだけでなく、経営者の意思決定の質をも向上させる。
- 生産性・収益性予測: 過去の生産データ、乳価の市場動向、飼料価格の変動などを学習したAIが、将来の乳量や収益性を予測する。これにより、経営者はデータに基づいたシミュレーションを行い、より精度の高い経営計画を立案できる 78。
- リソース配分の最適化: 労働力の配置、エネルギー消費量、設備投資のタイミングなど、経営リソースの配分をAIが最適化する提案を行う。これにより、経営全体の効率性が向上する。
AIが生み出す新たな価値
AIと精密酪農が生み出す価値は、コスト削減や効率化に留まらない。新たなビジネスモデルを創出する可能性を秘めている。
- 品質(乳質)の価値化:
AIによる精密な乳質管理は、生乳をコモディティから「スペシャリティ製品」へと昇華させる。例えば、搾乳ロボットが収集したデータに基づき、「カゼインミセル(チーズの主成分)の粒子径が小さく、チーズ製造に最適な生乳」や、「オメガ3脂肪酸の含有率が高い生乳」といった特定の価値を持つ生乳だけを選別し、付加価値をつけて販売することが可能になる。これは、従来の「合乳」システムでは実現できなかった、品質による差別化とブランディングを可能にする。 - 環境価値の定量化と収益化:
AIとセンサー技術は、個体ごとのメタン排出量や糞尿の排出量を正確にモニタリング・分析することを可能にする。これに基づき、メタン排出量を削減する飼料(例:カギケノリ)の効果を個体レベルで実証したり、糞尿処理プロセスにおけるGHG排出量を定量化したりできる。この「見える化」された環境貢献度は、カーボンクレジットとして市場で売買したり、サステナビリティ・ブランドとして製品の付加価値に転換したりする際の、信頼性の高い根拠となる。飼料の最適化によりメタン排出量を平均25%削減できるという予測もある 76。
導入の障壁と課題
この革新的な技術の普及には、いくつかの大きな障壁が存在する。
- 高額な初期投資: 自動搾乳ロボット1台で数千万円、牛舎全体のスマート化には億単位の投資が必要となる。これは特に中小規模の農家にとって大きな負担である 82。
- データ活用のリテラシー不足: 多くの生産者は、高度なデータ分析やITシステムの運用に関する専門知識を持っていない。技術を導入しても、それを使いこなす人材が不足している 82。
- データ規格の非標準化: DeLaval、Lely、ファームノートなど、異なるメーカーの機器やシステム間でのデータ連携が容易ではない。データ形式が標準化されていないため、データを一元的に管理・分析することが困難な場合がある 76。
- データ所有権とセキュリティ: 収集された膨大なデータの所有権は誰にあるのか(農家か、メーカーか)、また、そのデータをいかにサイバー攻撃などから守るかといった、法務・セキュリティ上の課題も存在する 84。
これらの課題を克服するためには、機器の共同購入やリース、成果連動型の課金モデルといった導入支援策、データ規格のオープン化、そして何よりもデータリテラシー向上のための教育・研修プログラムが不可欠である 76。
第9章:主要トレンドと未来予測
酪農業界の未来を形作るいくつかの重要なメガトレンドが存在する。これらは単独で、あるいは複合的に作用し、業界の競争ルールを書き換えていく。
アニマルウェルフェアの主流化
アニマルウェルフェア(AW)は、もはや一部の倫理意識の高い消費者の関心事ではなく、社会全体の要請となりつつある。伝統的な「つなぎ飼い」から、牛が自由に動ける「フリーストール」や「放牧」への移行が求められている 43。欧米では、子牛用ストールの禁止など、AWに関する法規制が既に導入されている 44。日本でも、JGAP認証などでAWが評価項目に含まれており 41、将来的にはAW認証が、高付加価値製品の証となるだけでなく、取引の必須条件(デファクトスタンダード)となる可能性がある。消費者のAWへの関心は高まっており、特に若年層を中心に購買行動に影響を与え始めている 34。
環境再生型農業(リジェネラティブ農業)との融合
従来の農業が環境から資源を収奪する(degenerative)のに対し、環境再生型農業は、土壌の健康を回復させ、生物多様性を高め、生態系全体を豊かにすることを目指す。酪農においては、放牧がその中核をなす。牛の糞尿が自然な肥料となって土壌を肥沃にし、牧草の根が土壌中に炭素を貯留(カーボンファーミング)することで、温室効果ガスの吸収源となり得る 66。北海道のユートピアアグリカルチャーのように、放牧酪農を通じて土壌の炭素吸収率を科学的に測定し、環境価値を可視化しようとする先進的な事例も登場している 66。これは、酪農を環境負荷産業から「環境再生産業」へと転換させる可能性を秘めている。
代替乳の進化と多様化
植物性ミルク(オーツ、アーモンド、豆乳など)の市場が成熟期に向かう中、次なるイノベーションの波が訪れようとしている。
- 植物性ミルクの多様化: 大豆やオーツ麦に加え、エンドウ豆、ひよこ豆など、新たな原料を用いた製品が次々と開発されている。森永乳業の「Plants & Me」は5種類の植物素材をブレンドするなど、栄養価や風味の改良が進んでいる 69。
- 精密発酵(培養)ミルクの登場: これがゲームチェンジャーとなりうる。微生物を利用して牛乳と全く同じタンパク質(カゼイン、ホエイ)を生産する技術であり、「動物由来でない本物の乳製品」を可能にする 59。この技術が商業化されれば、アレルギー対応やヴィーガン向けといった従来の代替乳の枠を超え、牛乳市場そのものを直接的に代替する可能性がある。規制環境の整備が課題だが、技術開発は着実に進んでいる 88。
エネルギーの地産地消と自給
エネルギーコストの高騰は、酪農経営を圧迫する大きな要因である。これに対し、農場内でエネルギーを自給する動きが加速する。糞尿を利用したバイオガス発電は、メタンガスを回収して発電し、農場内の電力を賄うだけでなく、余剰電力を売電することで新たな収益源となる 89。また、広大な牛舎の屋根に太陽光パネルを設置することも有効な手段である。エネルギーの地産地消は、コスト削減と環境負荷低減を同時に実現する、レジリエントな経営モデルの鍵となる。
D2C(Direct to Consumer)モデルの広がり
伝統的な「生産→農協→乳業メーカー→小売」というサプライチェーンから脱却し、酪農家自身が加工(6次産業化)まで手掛け、ECサイトや直売所を通じて消費者に直接製品を販売するD2Cモデルが広がりを見せている。北海道の十勝しんむら牧場のように、放牧牛乳を使ったミルクジャムやカフェ運営で成功を収める事例も出てきている 90。D2Cモデルは、中間マージンを排除して収益性を高めると同時に、生産者の顔が見えるストーリーを消費者に直接伝えることで、強力なブランドロイヤルティを構築できるという利点がある。
これらのトレンドは、酪農業界が直面する課題への解決策であると同時に、新たなビジネスチャンスの源泉でもある。これらの変化にいかに迅速かつ戦略的に対応できるかが、未来の競争優位を決定づけるだろう。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
酪農業界のバリューチェーンには、それぞれ異なる戦略を持つ多様なプレイヤーが存在する。ここでは主要なプレイヤーグループの動向を比較分析する。
国内大手乳業メーカー
明治ホールディングス、森永乳業、雪印メグミルクの3社は、市場の大部分を占める寡占プレイヤーである 55。
- 共通戦略: 3社ともに、中核事業である牛乳・乳製品のブランド価値向上と、ヨーグルトなどの高付加価値・機能性製品の開発に注力している。また、サステナビリティ経営を中期経営計画の柱に据え、環境負荷低減(GHG排出量削減など)や持続可能な原材料調達を推進している 91。
- 代替乳戦略の分岐: 3社は2024年春、奇しくも同時に代替乳市場へ本格参入したが、そのアプローチには違いが見られる 62。
- 明治: 「明治まるごとオーツ オーツミルク」を発売し、急成長するオーツミルク市場に焦点を当てている 15。既存の牛乳ブランドで培った製造技術とブランド力を活かす戦略と見られる。
- 森永乳業: 大豆、オーツ、アーモンドなど5種類の植物素材をブレンドした「Plants & Me」を発売 87。ブレンドによる風味や栄養バランスの良さを訴求し、差別化を図る戦略。
- 雪印メグミルク: エンドウ豆を主原料とする新ブランド「Plant Label」を立ち上げ、ヨーグルトや飲料、さらには植物性チーズへと製品ラインを拡大する計画 96。プラントベースフード事業を成長の柱の一つと明確に位置づけ、積極的な投資を行っている 99。
主要酪農協同組合
- ホクレン農業協同組合連合会: 北海道の生乳の大部分を取り扱う指定生乳生産者団体であり、生産者と乳業メーカーをつなぐ巨大なプラットフォーマーである 101。生産者への飼養技術指導、良質な飼料の安定供給、生乳の集荷・販売を通じて、北海道酪農の生産基盤を支える役割を担う 101。近年は、牛の消化管由来メタン低減に資する飼料開発など、環境負荷軽減への取り組みも強化している 102。
- よつ葉乳業: ホクレンを母体とする乳業メーカーであり、生産者団体としての側面とメーカーとしての側面を併せ持つ。北海道産生乳100%にこだわった「よつ葉ブランド」は、消費者から高い支持を得ている。中期経営計画では、CO2排出量削減や自然冷媒機器の導入など、具体的な数値目標を掲げて環境経営を推進している 103。また、海外、特にアジア市場への輸出拡大にも積極的に取り組んでいる 105。
グローバル乳業メジャー
Nestlé(スイス)、Danone(フランス)などのグローバル企業は、日本市場に製品を供給するだけでなく、世界のサステナビリティ潮流をリードする存在として間接的に大きな影響を与えている。
- Nestlé: サプライチェーン全体でのGHG排出量削減を目標に掲げ、契約酪農家が持続可能な農法を実践するための支援を行っている。例えば、ニュージーランドのFonterraと提携し、低排出な酪農を実践する農家に追加支払いを行うプログラムを実施している 68。リジェネラティブ農業(環境再生型農業)の実証にも投資している 106。
- Danone: 同様にリジェネラティブ農業の推進をグローバル戦略の柱としており、日本法人であるダノンジャパンもその方針に沿った計画を策定中である 108。
これらのグローバル企業の動向は、日本の乳業メーカーや酪農家に対し、サステナビリティへの取り組みが将来の取引条件となりうることを示唆している。
代替乳プレイヤー
- 海外勢: Oatly(スウェーデン)は、巧みなブランディングとマーケティングで世界のオーツミルク市場を創出したパイオニアである。日本では、カフェチャネルへの導入や大手テーマパークとの提携などを通じて、ブランド認知度を高める戦略をとっている 110。
- 国内勢: キッコーマンやマルサンアイは、長年にわたり豆乳市場をリードしてきた。これらの企業は、既存の製造基盤と販売網を活かし、オーツミルクなど新たな植物性ミルクのラインナップを拡充している。
アグリテック(酪農DX)企業
- グローバル企業: DeLaval(スウェーデン)とLely(オランダ)は、自動搾乳ロボット市場の二大巨頭である 52。彼らは単なるハードウェアの提供に留まらず、「DelPro」(DeLaval)や「Horizon」(Lely)といったデータ管理プラットフォームを提供し、収集したデータを活用した経営改善ソリューションを販売している 79。彼らのビジネスモデルは、ハードウェア販売からSaaS(Software as a Service)へと移行しつつある。
- 国内スタートアップ: ファームノート(日本)は、牛群管理システム「Farmnote Cloud」やセンサー「Farmnote Color」を提供し、国内の酪農DXをリードする存在である。自社でもスマート技術を駆使した牧場を運営し、生産現場でのデータ活用ノウハウを蓄積・提供している 114。今後は、LLM(大規模言語モデル)などを活用し、経営判断までを自動化するプラットフォームへの進化を目指している 116。
各プレイヤーの戦略は、業界の構造変化に対応する形で進化している。乳業メーカーは代替乳市場への参入を急ぎ、農協は生産基盤の維持と環境対応を強化、そしてアグリテック企業はデータプラットフォームの覇権を争っている。この多層的な競争環境を理解することが、自社の戦略を位置づける上で不可欠である。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、日本の酪農業界が取るべき次世代戦略を導出する。
勝者と敗者を分ける決定的要因
今後5~10年で、酪農業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因は、以下の3点に集約される。
- データ資本の蓄積と活用能力: 精密酪農技術を導入するだけでなく、そこから得られる膨大なデータを経営資源として活用し、生産性の向上、高付加価値製品の開発、環境価値の証明といった具体的な経済価値に転換できるか。データを制する者が、次世代の酪農を制する。
- 環境価値の収益化モデル構築: 環境負荷低減を単なるコストとして捉えるか、新たな収益源(カーボンクレジット、エネルギー販売、サステナブルブランド)として事業モデルに組み込めるか。この転換に成功したプレイヤーは、規制強化を追い風に変え、競争優位を確立する。
- 「牛乳」の呪縛からの脱却: 代替乳の台頭を脅威とのみ捉え、防戦一方に陥るのではなく、自らを「プロテイン・栄養ソリューションを提供する企業」と再定義し、牛乳と代替乳の両市場で価値を提供できるか。市場の変化に柔軟に対応できる事業ポートフォリオを構築した者が生き残る。
機会(Opportunity)と脅威(Threat)
この市場で成長するためには、以下の機会を捉え、脅威に備える必要がある。
- 機会(Opportunities):
- 精密酪農による高付加価値化: AIとセンサーを活用し、特定の用途に特化した「機能性生乳」を生産・ブランディングする機会。
- 環境再生型農業による新市場創出: カーボンファーミングやバイオガス発電を通じて、カーボンクレジット市場やエネルギー市場に参入する機会。
- 健康志向の高まり: 科学的根拠に基づいた牛乳・乳製品の健康価値を再訴求し、機能性表示食品市場などでシェアを拡大する機会。
- D2C/6次産業化: 中間流通を排し、独自のブランドストーリーと共に消費者に直接製品を届けることで、高い収益性と顧客ロイヤルティを確保する機会 65。
- 脅威(Threats):
- 生産コストの構造的高騰: 輸入飼料価格とエネルギー価格の高止まり、および円安基調による収益性の継続的な圧迫。
- 代替乳の市場浸透: 特に若年層を中心に、牛乳からの恒久的な需要シフトが加速する脅威。
- 精密発酵(培養乳)の技術的ブレークスルー: 牛乳と同一成分の製品が低コストで生産可能になった場合、酪農生産の基盤そのものを破壊する脅威。
- 人材基盤の崩壊: 後継者・労働力不足が限界点に達し、地域の生産基盤が維持できなくなる脅威。
戦略的オプションの評価
考えられる主要な戦略的オプションは以下の通りである。
| 戦略オプション | 概要 | メリット | デメリット | 成功確率 |
|---|---|---|---|---|
| A: 「超効率・大規模化」によるコストリーダーシップ | 北海道などで、スマート酪農への巨額投資により徹底的な省人化と規模の経済を追求し、コスト競争力で優位に立つ。 | 生産量あたりのコストを最小化できる。コモディティ市場での生き残りに有効。 | 莫大な初期投資が必要。国際的なコモディティ価格変動に脆弱。差別化が困難。 | 中(資本力のある大規模経営体に限る) |
| B: 「高付加価値・環境価値」による差別化 | 精密酪農と環境再生型農業を組み合わせ、品質・サステナビリティで他と一線を画すプレミアム製品を開発。 | 高い利益率が期待できる。価格競争から脱却できる。ブランド価値を構築できる。 | 市場規模が限定的。価値を消費者に伝え、価格に転嫁するためのマーケティング力が必須。 | 高(実行できれば持続的優位を築ける) |
| C: 「代替乳事業への参入」による多角化 | 自社の製造・開発ノウハウを活かし、成長市場である代替乳製品を開発・販売。既存の牛乳事業とのシナジーを追求。 | 成長市場の機会を捉えられる。事業ポートフォリオのリスク分散。 | 牛乳事業とのカニバリゼーション(共食い)のリスク。既存の代替乳プレイヤーとの厳しい競争。 | 中(乳業メーカーにとって現実的だが、成功には明確な戦略が必要) |
| D: 事業売却/撤退 | 将来性が見込めない、あるいは後継者不在の中小規模経営体が、事業を他社に売却するか、計画的に撤退する。 | 経営資源を他の有望な分野に再配分できる。損失の拡大を防ぐ。 | 地域の生産基盤や雇用の喪失。 | – |
最終提言:ハイブリッド戦略「データ駆動型・高付加価値酪農」の実行
これまでの分析に基づき、最も持続可能かつ収益性の高い成長を実現する戦略として、オプションB「高付加価値・環境価値による差別化」を中核に据え、オプションA「超効率・大規模化」の要素(データ活用による効率化)とオプションC「代替乳事業への参入」の視点(市場の俯瞰)を取り入れたハイブリッド戦略を提言する。
戦略の核心
生乳を単なる「量」で測るコモディティ生産から脱却し、AIと精密酪農技術を駆使して「質」「データ」「環境価値」を最大化し、それを収益に転換するビジネスモデルを構築する。
実行に向けたアクションプラン概要
- 第1フェーズ:基盤構築(1~2年)
- KPI: データ収集基盤の整備率、主要プロセスの自動化率。
- アクション:
- 自動搾乳ロボット、個体管理センサー、統合管理プラットフォーム(Farmnote, DelPro, Horizon等)への戦略的投資。
- データアナリスト、IT技術者の採用・育成プログラムの開始。
- バイオガスプラント導入や土壌分析を通じた、環境価値(GHG排出量、炭素貯留量)のベースライン測定。
- 必要リソース: 設備投資資金、人材採用・育成予算。
- 第2フェーズ:価値創造と実証(3~5年)
- KPI: 高付加価値生乳の生産比率、カーボンクレジット創出量、D2Cチャネル売上高。
- アクション:
- 収集データを活用し、「チーズ向け」「高栄養価」など特定の価値を持つ生乳の生産・選別プロセスを確立。特定の乳業メーカーとの実証プロジェクトを開始。
- メタン削減飼料の導入や放牧管理の最適化により、GHG削減を実証し、カーボンクレジットの認証取得を目指す。
- 小規模な6次産業化(ヨーグルト、チーズ等)を開始し、D2Cチャネルでのテストマーケティングを実施。
- 必要リソース: 研究開発費、マーケティング費用、認証取得コンサルティング費用。
- 第3フェーズ:事業拡大とエコシステム構築(5年~)
- KPI: プレミアム製品の市場シェア、環境価値事業の収益額、アライアンス数。
- アクション:
- 高付加価値製品の本格的な市場投入とブランディング強化。
- 創出したカーボンクレジットを国内外の企業に販売。バイオガス発電による余剰電力を地域に供給。
- 地域の耕種農家、食品加工業者、大学、IT企業などを巻き込み、データと資源が循環する「サステナブル酪農エコシステム」を構築。
- 必要リソース: ブランド投資、アライアンス構築のための専門チーム。
この戦略は、短期的なコスト増を伴う挑戦的なものである。しかし、業界が直面する構造的な危機を乗り越え、単に生き残るだけでなく、社会から必要とされ、高い収益性を誇る未来の酪農・乳業の姿を実現するための、最も確実な道筋であると確信する。
第12章:付録
引用文献
- 2024年の世界の生乳生産量を1.4%増、乳製品貿易量を0.8%増と予測 – Jミルクは, https://www.j-milk.jp/report/international/intelligence202407_1.html
- 2024 年の世界の生乳生産量を 1.4%増、乳製品貿易量を 0.8%増と予測 – Jミルクは, https://www.j-milk.jp/report/international/h4ogb4000000fo2y-att/h4ogb4000000fo54.pdf
- 2030年までの国際乳製品市場の動向, https://www.dairy.co.jp/dairydata/jdc_news/kulbvq000000te3m-att/kulbvq000000te66.pdf
- OECD/FAO、2034年までの世界の乳製品需給見通しを公表 – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_004180.html
- OECD/FAO、2033年までの世界の乳製品需給見通しを公表 – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003879.html
- 牛乳・乳製品 – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/content/001264423.pdf
- 生乳生産量、24年度は増産の見込み・Jミルク – 酪農乳業速報, https://dailydairynews.jp/post/5310
- 酪農経営の早期改善に向けて, https://www.zennoh.or.jp/press/release/2022/12/02/%EF%BC%88%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%89%E9%85%AA%E8%BE%B2%E6%83%85%E5%8B%A2%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E4%B8%AD%E9%85%AA%E4%BD%9C%E6%88%90%EF%BC%89.pdf
- 乳用牛をめぐる情勢 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_katiku/attach/pdf/r6_nyuuyougyuu-5.pdf
- 日本の生乳生産量と消費量 | findNew 牛乳乳製品の知識 – Jミルクは, https://www.j-milk.jp/findnew/chapter1/0202.html
- 1 酪農をめぐる情勢(生産), https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/nogyo/20161013/161013nogyo08-2.pdf
- 代替乳や微細藻類、代替肉などの代替タンパク食品をはじめとした
サスティナブルフードと関連装置・サービス市場を調査 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25040 - 日本オートミルク市場規模、シェア、トレンド、成長レポート 2025-2033 | NEWSCAST, https://newscast.jp/news/9541782
- 日本オートミルク市場規模、シェア、トレンド、成長レポート 2025-2033 | IMARC Group, https://www.atpress.ne.jp/news/454186
- オーツミルク市場に本格参入!「明治まるごとオーツ オーツミルク」10月1日 販売エリア拡大, https://kyodonewsprwire.jp/release/202409186606
- アーモンドミルクとは – 意識調査, https://www.almondm-labo.jp/survey.php
- アーモンドミルクとは – アーモンドミルクの特長, https://www.almondm-labo.jp/feature.php
- 日本の乳製品原料市場規模は2033年までに41億 … – NEWSCAST, https://newscast.jp/news/1536248
- 日本の農業人口はどう推移している? 農業現場へ与える影響とは – minorasu(ミノラス, https://minorasu.basf.co.jp/80076
- 「酪農全国基礎調査」からみる 日本酪農の現状, https://www.dairy.co.jp/news/kulbvq000000mybw-img/kulbvq000000myd8.pdf
- 令和4年牛乳生産費 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukei/tiku_seisanhi/r4/gyunyu/index.html
- 令和4年「肥育豚生産費」「肉用牛生産費」「牛乳生産費」 – みんなの農業広場, https://www.jeinou.com/topics/2023/12/08/173000.html
- 配合飼料価格高騰特別対策の継続実施について | ホクレン農業協同組合連合会, https://www.hokuren.or.jp/news/detail.php?id=891
- 飼料高騰特集 – マイナビ農業, https://agri.mynavi.jp/feedinflation/
- 飼料価格高騰緊急対策について(令和5年3月) – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/siryo_r5_3.html
- 日本の生乳流通を支える「指定団体制度」とその課題 – ミルクデザイン, https://www.milkdesign.jp/post/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%94%9F%E4%B9%B3%E6%B5%81%E9%80%9A%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%AA%B2%E9%A1%8C
- 第91回 昨今の農政課題 ~改正畜安法、日EU・EPAを中心に – 日本乳業協会, https://www.nyukyou.jp/effort/council/20180110.html
- 酪農・乳業の現状と課題の整理 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/tikusan/attach/pdf/bukai1004-3.pdf
- 牛乳・乳製品の安定供給に指定団体制度は欠かせません。 – アグリポート, https://agriport.jp/dairy-livestock/ap-11112/
- 日本・欧州連合経済連携協定が 日本酪農に及ぼす影響とその意味, https://www.snowseed.co.jp/wp/wp-content/uploads/grass/2018_02.pdf
- 第83回 TPP農林水産物市場アクセス交渉の結果 – 一般社団法人日本乳業協会, https://www.nyukyou.jp/effort/council/20151126.html
- 博士論文(要約) 我が国における生乳・乳製品市場の数量経済分析 佐藤 秀保 – 東京大学学術機関リポジトリ, https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/52310/files/A34120_summary.pdf
- 飼料価格高騰と気候変動 – 新着情報 株式会社エス・ディー・エス バイオテック, https://www.sdsbio.co.jp/products/anim/cnsl_lp/news_details28.html
- アニマルウェルフェアや人権に配慮した食品の購入意向に 関する国際比較, https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/07/seiken_230711_01.pdf
- アニマルウェルフェアや人権に配慮した食品の購入意向に関する国際比較, https://www.murc.jp/library/report/seiken_230711/
- 牛乳・乳製品は代替ミルクの時代へ, https://www.hopeforanimals.org/meat-free-monday/562/
- 牛乳購買に関する主婦の意識・行動調査レポート, https://www.dairy.co.jp/dairydata/kulbvq0000006r3l-att/kulbvq0000006rdv.pdf
- 酪農の未来:2025年に自動化、AI、持続可能性を取り入れる – The Bullvine, https://www.thebullvine.com/ja/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC/2025%E5%B9%B4%E3%81%AE%E9%85%AA%E8%BE%B2%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%EF%BC%9A%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E3%80%81AI%E3%80%81%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%9F%E9%85%AA%E8%BE%B2%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5/
- スマート酪農・畜産に関する調査を実施(2023年) | ニュース …, https://www.yano.co.jp/press/press.php/003308
- スマート畜産の現状と展開 – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002309.html
- 私たちのこだわり – 石田牧場グループ公式サイト|JGAP/HACCP認証牧場, https://ishidafarmgroup.jp/approach/
- 畜産における生産工程管理(GAP) – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/attach/pdf/chikusan_gap-119.pdf
- 酪農におけるアニマルウェルフェアと現状 – 酪農ジャーナル電子版【酪農PLUS+】, https://rp.rakuno.ac.jp/archives/feature/2148.html
- 米国畜産業における アニマルウェルフェアへの対応について, https://www.alic.go.jp/content/001211925.pdf
- 酪農乳業と気候変動対策 ~海外の酪農大国にみる生乳生産での温室効果ガス削減対策, https://www.nochuri.co.jp/genba/pdf/otr20250123.pdf
- 牛のゲップと温暖化? ~酪農経営の環境対策とは~ | 夢ナビ講義, https://yumenavi.info/vue/lecture.html?gnkcd=g011643
- 酪農における温室効果ガス排出と削減に向けて – 酪農ジャーナル電子版【酪農PLUS+】, https://rp.rakuno.ac.jp/archives/feature/4081.html
- 地球温暖化が日本における家畜の生産性に及ぼす 影響評価の現状と課題, https://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f31342d326a706e/save/0/0/14_2-12.pdf
- AIが予測する飼料メーカー 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/feed
- FEED ONEの強み | 個人投資家の皆様へ | フィード・ワン株式会社, https://www.feed-one.co.jp/ir/investors/investment_strength.html
- 国内一般企業トップの配合飼料メーカー 売上高連続過去最高更新見込む | フィード・ワン, https://www.kabutecho.com/interview/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%B3/
- エサ寄せロボ「ジュノ」導入台数1000台到達 – 酪農乳業速報, https://dailydairynews.jp/post/1499
- 農水省もオススメする搾乳ロボット、省人化だけでない価値に脱帽した話。|安藤 健 – note, https://note.com/takecando/n/na9d8e519f463
- AIが予測する乳製品(飲料)メーカー 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/dairy-drinks
- 乳製品業界の業界研究|市場規模や現状など就活に役立つ情報をご紹介 – JobQ Town, https://job-q.me/articles/13147
- 【調査レポート】 日本の乳製品市場:規模とシェア分析 – 成長傾向と2030年までの予測, https://www.marketresearch.co.jp/insights/japan-dairy-market-mord/
- インフレ下の米国でPBが進化(後編)先行PBビジネスにみる戦略 | 地域・分析レポート – ジェトロ, https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/9ac6d5a0a131255c.html
- 急成長するオーツミルク市場② 日本の最新トレンド, https://tsukagoshisan.com/shop/information/oat-milk-trend-2
- 精密発酵でつくる「牛のいない」乳製品 オイシックスCVCも出資するFormo – TECHBLITZ, https://techblitz.com/startup-interview/formo/
- 植物分子農業によりイネからミルクをつくるフードテックスタートアップ「Kinish」が1.2億円調達, https://sogyotecho.jp/news/20250219kinish/
- イネで乳タンパク質を開発する日本発のKinish、1.2億円のシード資金を調達 | Foovo, https://foodtech-japan.com/2025/02/17/kinish-2/
- 大手乳業3社がプラントベースで三つ巴の戦い – 酪農乳業速報, https://dailydairynews.jp/post/5151
- 飼料生産・利用の現状と飼料政策について, https://agri.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/01/02nosuisyo_ueki.pdf
- 飼料自給率とは?現状と目標、取り組み、農家が向上に貢献するメリット – 自然電力, https://shizenenergy.net/re-plus/column/dairy/livestock_feed_self_sufficiency_ratio/
- 6次産業化 アワード 事例集 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/attach/pdf/yuryo-5.pdf
- リジェネラティブ(環境再生)とは?農業や酪農・漁業での取り組みと事例を紹介, https://www.publicweek.jp/ja-jp/blog/article_68.html
- 農業の脱炭素化を目指して――再生型農業に挑む先進企業の最前線|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan, https://www.sustainablebrands.jp/news/1301948/
- Nestlé partnership sees extra payment offered to Fonterra farmers this season, https://www.fonterra.com/jp/ja/our-stories/media/nestle-partnership-sees-extra-payment-offered-to-Fonterra-farmers-this-season.html
- 【日本初】森永乳業が5種ブレンド植物性ミルク 温室効果ガスは牛乳の3分の1 プラントベースフード新展開にも期待 – FNNプライムオンライン, https://www.fnn.jp/articles/-/674638?display=full
- 消費者価値観とアニマルウェルフェア意識を考慮した 畜産物購買意欲の解明 ~多様化する消費, https://www.alic.go.jp/content/001219745.pdf
- 消費者価値観とアニマルウェルフェア意識を考慮した畜産物購買意欲の解明~多様化する消費者ニーズに向けた代替タンパク普及の可能性 – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002589.html
- スマート農業 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/
- 【スマート農業普及加速化のカギ】スマート農業技術を使いこなす人材の育成は地域行政・生産者団体・メーカー一体で取り組むべき – 日本総研, https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/15573/
- スマート農林水産業における人材育成に向けて, https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/wgkaisai/nougyou_dai4/siryou7.pdf
- 深刻化する酪農業の人手不足の解決策とは?労働力確保に役立つ外国人採用戦略, https://tokuty.jp/blog/dairy_farming_labor_shortage/
- 【2035年予測】AIが拓く日本の酪農の未来 ~生産性向上・省力化のインパクト~|川上哲也 – note, https://note.com/kawakamifarm/n/nff0025bf8199
- 畜産業でのAI活用方法は?生産性向上への活用事例・導入事例徹底解説! – AI Market, https://ai-market.jp/industry/stockraising/
- 事例1:搾乳ロボットを活用した飼養管理技術の高度化, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_katiku/attach/pdf/index-25.pdf
- Key features – DeLaval, https://www.delaval.com/en-us/explore-our-farm-solutions/milking/delaval-vms-series/key-features/
- 搾乳ロボットと搾乳機を「ハイブリッド活用」 – 県立広島大学, https://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/life/44840_108956_misc.pdf
- 【事例あり】スマート畜産とは?|導入効果と課題を徹底解説 – Hakky Handbook, https://book.st-hakky.com/industry/smart-livestock-case-studies-iot-sensor-data-analysis-efficiency
- 「農業用トラクターの日本市場:エンジン出力別(30HP以下、30HP~100HP、100HP~200HP、200HP以上)、市場規模(~2029年)」調査資料を販売開始|PressWalker, https://presswalker.jp/press/73719
- Wi-Fi HaLowを活用した畜産/酪農の一 元的な見える化サービスの実証 – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/001004686.pdf
- Farm Management Software | Data Driven Solutions – Lely, https://www.lelyna.com/us/solutions/farm-management-software/
- 米国畜産業におけるアニマルウェルフェアへの対応について, https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002306.html
- 生乳生産ではどのくらい 温室効果ガスが発生する? – アグリポートWeb, https://agriport.jp/dairy-livestock/ap-20026/
- 【日本初】森永乳業が5種ブレンド植物性ミルク 温室効果ガスは牛乳の3分の1 プラントベースフード新展開にも期待 – FNNプライムオンライン, https://www.fnn.jp/articles/-/674638
- 細胞培養ミルクを開発するカナダのOpalia、大手乳業サプライヤーHoogwegtから購入注文を受注, https://foodtech-japan.com/2025/08/05/opalia-2/
- サステナブルファイナンス | 森永乳業のサステナビリティ, https://www.morinagamilk.co.jp/sustainability/susbond/
- 野村アグリプランニング&アドバイザリー 6次産業化 優良事例30選 (PDF) – Nomura, https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/services/fabc/publications/publications20160401103085/main/0/teaserItems1/0/linkList/0/link/20160401_a.pdf
- 健康にアイデアを – meiji, https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/r6/attach/pdf/r6_3_haifu-2.pdf
- 2030経営計画・2024中期経営計画 | 経営方針 | IR情報 | 森永製菓株式会社, https://www.morinaga.co.jp/company/ir/policy/strategy.html
- 創刊80周年記念特集:雪印メグミルク 現代の健土健民へ体制整備, https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20220614123721786
- 雪印メグミルクグループ 調達方針|サステナビリティ, https://www.meg-snow.com/csr/procurement/
- 「Plants&Me オリジナル」「Plants&Me 砂糖不使用」4月2日(火)より全国にて新発売 – 森永乳業, https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4368.html
- 代替食・プラントベースフード特集:雪印メグミルク プラントラベル展開 – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20241004012707008
- 雪印メグミルク 植物性食市場で成長加速 新たな“おつまみ”提案 – 食品新聞, https://shokuhin.net/104852/2024/08/26/topnews/
- 雪メグ、植物性ブランド「プラントラベル」立ち上げ – 酪農乳業速報, https://dailydairynews.jp/post/4518
- ヨシダコーポレーションを子会社化 プラントベースフード開発を推進 雪印メグミルク – JAcom, https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2024/05/240515-74116.php
- 雪印メグミルク、成長3分野に新商品投入 需要創造と領域拡大を – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20240801015741997
- HOKUREN Group Report 事業本部紹介, https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/nogyo/140424/item1_9.pdf
- 酪農畜産事業本部|ホクレン農業協同組合連合会, https://www.hokuren.or.jp/about/guide/office/rakunou/
- 環境活動 – サステナビリティ|北海道のおいしさを、まっすぐ。よつ葉, https://www.yotsuba.co.jp/company/sustainability/environment.html
- 環境マネジメント|北海道のおいしさを – よつ葉乳業, https://www.yotsuba.co.jp/company/csr/management/
- 飲用乳(LL牛乳・チルド牛乳)輸出への取り組み~よつ葉乳業株式会社におけるアジア諸国への輸出策 – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003654.html
- 【詳説】ネスレのSDGs戦略 ~ヘルスケア、リサイクル、酪農関連のイノベーション事例を紹介, https://www.techno-producer.com/column/nestle_sdgs_innovation_strategy/
- 【国際】ネスレ、リジェネラティブ農業促進に1400億投資。低炭素認証のラベル表示も, https://sustainablejapan.jp/2021/09/22/nestle-regenerative-food-system/66359
- 【メンバー紹介】ダノンジャパン株式会社 – ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム – 群馬県ホームページ, https://www.pref.gunma.jp/site/naturepositive/708094.html
- 【徹底解説】ダノンのSDGs達成に向けた経営戦略 ~環境再生型農業への転換と、特許から読み解くイノベーション事例の紹介 – TechnoProducer, https://www.techno-producer.com/column/danone-sdgs-strategy/
- オートミルク市場Benchmark:主要企業比較と競争優位性の検証 – イノベーションズアイ, https://www.innovations-i.com/release/1761287.html
- 「ポスト・ミルク世代」——スウェーデン発、植物性ミルクブランド「オートリー」が新たな市場へ踏み出した – パケトラ | 世界各国で暮らすライターがお届けする、ビジネスアイデア情報。ビジネスのヒントや閃きのきっかけに。, https://pake-tra.com/package/8788/
- Better farm performance – DeLaval, https://www.delaval.com/en-us/explore-our-farm-solutions/farm-management/delaval-delpro/better-decisions/better-farm-performance/
- Farm Management Software | Data Driven Solutions – Lely, https://www.lely.com/solutions/farm-management-software/
- ファームノートDP 代表取締役交代のお知らせ – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000039111.html
- ファームノート、IoT・AI・自動化技術を活用した牧場にて酪農生産を開始 | IoTNEWS, https://iotnews.jp/agriculture/158235/
- AIエンジニア|株式会社ファームノート, https://corp.farmnote.com/job/20250627/68/
- DeepResearch追加指示.txt
- グローバルにおける乳製品市場(2024-2031):製品タイプ別(牛乳、脱脂粉乳(SMP)、ホエイミルクパウダー(WMP)、ホエイプロテイン、バター、チーズ、ヨーグルト、その他)、流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、地域別(北米、中南米、欧州、アジア太平洋、, https://www.globalresearch.co.jp/reports/dairy-market-pred/
- 牛乳乳製品統計(令和7年8月分) – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/gyunyu_tyosa/gyunyu_m/r7/m8.html
- 第8回生乳の需給等に係る情報交換会 説明資料 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/attach/pdf/seinyujukyu-40.pdf
- 第10回生乳の需給等に係る情報交換会 説明資料 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/attach/pdf/seinyujukyu-55.pdf
- スマート畜産とは? – 産総研, https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20240313.html
- 持続可能性に配慮した調達コード(第3版) 解説 <個別基準:畜産物>, https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2023/assets/pdf/sustainability/sus_code_docs_12.pdf
- 米国における持続可能な酪農・肉用牛生産に向けた取り組みについて, https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002627.html
- 指定団体(制度)の重要性と指定団体制度を巡る情勢, https://www.dairy.co.jp/kulbvq000000f7jc-att/kulbvq000000h4fq.pdf
- TPP「大筋合意」内容にもとづく関税障壁の変化が 日本の酪農乳業に及ぼす影響に関する研究 – researchmap, https://researchmap.jp/smzike/misc/33455450/attachment_file.pdf
- TPPに関する疑問にお答えします – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tpp/pdf/tpp_leaflet.pdf
- TPP交渉における乳製品をめぐる状況 – 国際農業・食料レター, https://www.zenchu-ja.or.jp/wp_zenchu/wp-content/uploads/2022/09/up182.pdf
- サステナブルフードに関する消費者アンケート調査を実施(2024年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press/press.php/003524
- アニマルウェルフェアを意識した賢い食品選びとは – あしたメディア by BIGLOBE, https://ashita.biglobe.co.jp/entry/news/animal-welfare-food
- 日本の乳製品市場規模とシェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド – Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/japan-dairy-market
- 相互利益を徹底追求した「戦略提携」で、信頼関係と価値あるPB商品が生まれる – MD NEXT, https://md-next.jp/6657
- 飼料の現状と課題の整理 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/tikusan/attach/pdf/241113-42.pdf
- 飼料, https://www.alic.go.jp/content/001205824.pdf
- 6次産業化 優良事例集 – Nomura, https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/fabc/data/20170228_ap.pdf
- 酪農経営の労働力減少に対応した多角的な取り組みと地域主体間の連携 ~北海道大樹町を事例として – 農畜産業振興機構, https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000460.html
- ~未来を創る 『酪農のなかま』~ 優良事例を共有 | ちくさんクラブ21, https://www.chikusan-club21.jp/article/5931
- 持続可能な畜産物生産の取組事例集について – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_tiku_manage/zizoku_jirei.html
- 牛乳乳製品に関する食生活動向調査2022 『牛乳の購買・飲用の状況に関する緊急調査報告(牛乳消費低迷と物価高との関係を探る調査 – Jミルクは, https://www.j-milk.jp/report/trends/h4ogb40000009z9h.html
- 令和4年度データを活用した産地と消費者をつなぐプロジェクト 牛乳・乳製品の分析報告書 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/attach/pdf/syouhisyatosannchi-52.pdf
- 乳業業界の動向~需給構造の変化に対する乳業メーカーの戦略の方向性, https://www.smbc.co.jp/hojin/report/investigationlecture/resources/pdf/3_00_CRSDReport028.pdf
- 購買データから見る 牛乳類・植物性ミルクの消費動向, https://www.j-milk.jp/report/marketing/h4ogb4000000c6lm-att/h4ogb4000000c6o5.pdf
- “第3のミルク”として注目される「アーモンドミルク」 | ナッツの情報サイト Ton’s Cafe(トンカフェ), https://www.tons-cafe.jp/about/almonds/nuts-entry-1867.html
- アーモンドミルク売上急上昇!人気の決め手は「手軽さ」 | 消費インサイド, https://diamond.jp/articles/-/130131
- 農業労働力に関する統計 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html
- 農業における雇用の動向と今後 – 労働政策研究・研修機構, https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2016/10/pdf/004-015.pdf
- 畜産への新規就農及び経営離脱に関する調査 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_hosin/attach/pdf/tikusan_shunou_ridatu-6.pdf
- 畜産への新規就農及び経営離脱に関する調査 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_hosin/attach/pdf/tikusan_shunou_ridatu-3.pdf
- 農業デジタル人材育成プロジェクト – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=wDIzE82HDn4
- 飼料の生産性向上(スマート農業技術の現場普及) – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/tikusan/attach/pdf/241113-44.pdf
- ビッグデータを活用した 酪農経営の最適化への取り組み, https://www.alic.go.jp/content/001272053.pdf
- 2026中期経営計画 | 明治ホールディングス株式会社, https://www.meiji.com/investor/vision/mid-term-plan/
- 明治グループサステナビリティ2026ビジョン – 明治飼糧株式会社, https://www.meijifeed.co.jp/sustainability/
- 雪印メグミルクグループ経営計画「Next Design 2030」の策定について, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250514/20250424522205.pdf
- 事業方針 | ホクレンくみあい飼料株式会社, https://kumiai-siryo.jp/company-policy/
- 100 万ヘクタールの農地で再生型農業を実施 | Unilever – ユニリーバ・ジャパン, https://www.unilever.co.jp/news/2024/how-unilevers-implementing-regenerative-agriculture-practices-across-1-million-hectares/
- How to analyse your milking performance in DelPro™ FarmManager – DeLaval, https://www.delaval.com/en-gb/learn/inspired-by-delpro/milking/analyse-your-milking-performance/
- Lely Horizon – Apps on Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lely.mobile.assistantNext
- 明治グループの成長戦略, https://www.meiji.com/pdf/investor/individual/presentation-meiji_growthstrategy_2021_01.pdf
- 環境と健康にアイデアを。食品容器包装における明治のサステナビリティ戦略 – 三井化学, https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/soso/archive/column/common/2025-1003-01
- 代用乳 – 明治飼糧株式会社, https://www.meijifeed.co.jp/business/products/milkreplacer/
- 森永乳業、健康ケアへ植物性飲料「Plants&Me」発売 素材5種ブレンド – 日本食糧新聞, https://news.nissyoku.co.jp/news/ozawa20240321054229217
- 森永乳業から5種の植物素材をブレンドしたドリンク『Plants & Me』が新発売! – ベジタイム, https://vegetime.net/plantsandme_morinaga/
- 雪印メグミルクグループはなぜ、 「食の持続性」の実現に向け, https://www.meg-snow.com/csr/report/pdf/2024/9_14.pdf
- 食品企業向け人権尊重の取組のための セミナー 明治グループの取り組み, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kokusaihan/attach/pdf/jinken-seminear-8.pdf
- 明治ホールディングス株式会社, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240329/20240301546521.pdf
- 持続可能な原材料調達の推進 | 森永製菓グループのサステナビリティ, https://www.morinaga.co.jp/company/sustainability/valuechain/procurement.html
- 雪印メグミルクレポート2023(統合報告書), https://www.sse.or.jp/wp-content/uploads/2023/10/20231003_2270_ESG.pdf
- 雪印メグミルクレポート(統合報告書)|サステナビリティ, https://www.meg-snow.com/csr/report/
- 「雪印メグミルクレポート 2025(統合報告書)」 発行のお知らせ – アットプレス, https://www.atpress.ne.jp/news/5224651
- 米Brown Foodsが培養全乳「UnReal Milk」を発表|研究室での生成に成功 | Foovo, https://foodtech-japan.com/2025/03/04/brown-foods-2/
- 次世代の食料生産技術「精密発酵」とは ―業界団結で加速する市場開発― – Mitsui, https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2024/02/15/2402t_sawano.pdf
- 精密発酵フードと食の科学 ― 商品レビュー連載 第1弾:Perfect Day社 の Tech & Product ① – 日本細胞農業協会, https://cellagri.org/articles/2023-03-30-22-48_%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%99%BA%E9%85%B5%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E9%A3%9F%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E2%80%95-%E5%95%86%E5%93%81%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E9%80%A3%E8%BC%89-%E7%AC%AC1%E5%BC%BE%EF%BC%9Aperfect-day%E7%A4%BE-%E3%81%AE-tech-product-%E2%80%95