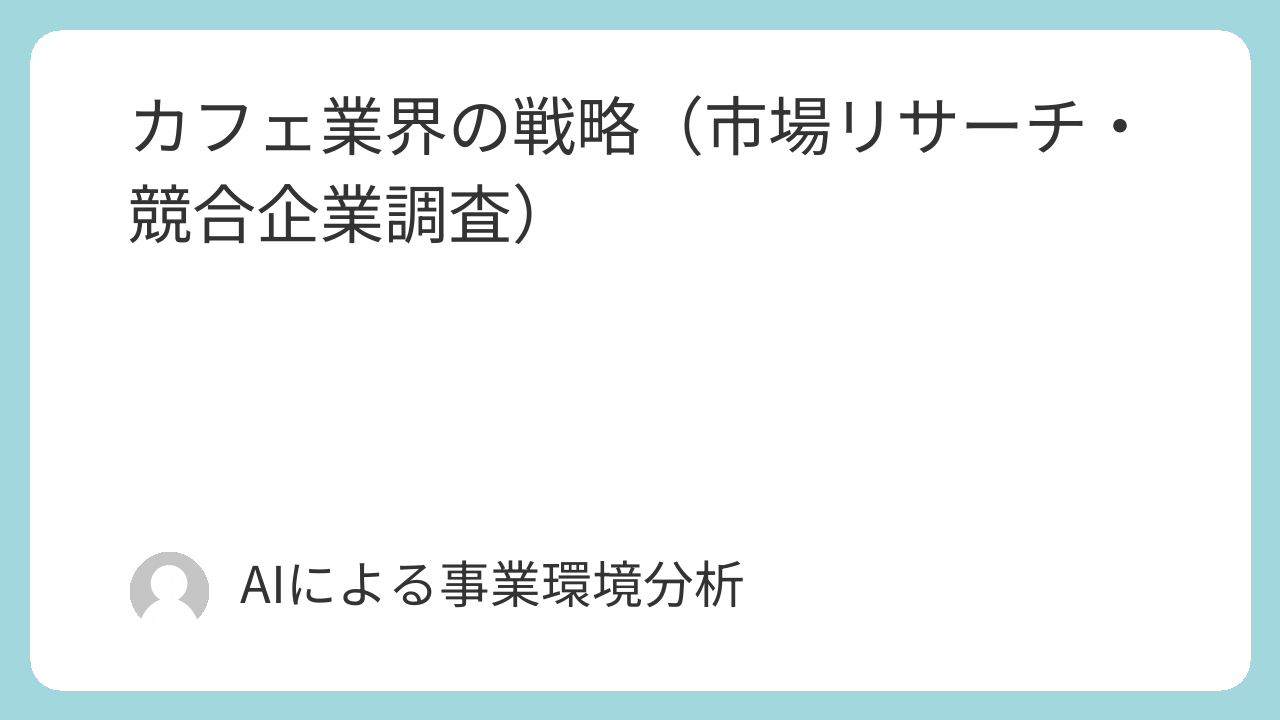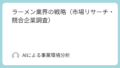体験と効率の岐路:デジタルとサステナビリティで再構築するカフェ業界の次世代戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートは、日本のカフェ業界が直面する構造的変化を多角的に分析し、持続可能な成長を達成するための事業戦略を提言することを目的としています。調査対象は、大手カフェチェーン(スターバックス、ドトール・日レスホールディングス、コメダホールディングス等)、スペシャルティコーヒー専門店(ブルーボトルコーヒー等)、およびコンビニコーヒーや異業種参入者(蔦屋書店等)を含む広範な競合領域を網羅します。
カフェ業界は、単なるコーヒー提供業から、「体験価値」を追求する高付加価値モデルと「利便性」を徹底する効率モデルへと、不可逆的な二極化の渦中にあります。市場は成熟期を迎え飽和状態に近づく一方、原材料費、エネルギーコスト、人件費の「トリプルコスト高騰」という深刻な収益圧迫要因に直面しています。さらに、コンビニコーヒーという強力な代替品の存在と、書店やアパレルといった異業種からの参入が競争環境を一層複雑化させています。この厳しい事業環境下で生き残り、成長を遂げるためには、旧来のビジネスモデルからの脱却と、明確な戦略的ポジショニングの確立が不可欠です。
本分析から導き出された最も重要な結論は、今後の業界における勝者と敗者を分ける決定的な要因が、①明確な価値提案(「体験」特化か「効率」特化か)、②デジタル技術を駆使した顧客エンゲージメントとオペレーション最適化能力、③サプライチェーン全体を俯瞰したサステナビリティとコスト管理能力、という3つの要素に集約されるという点です。
以上の分析に基づき、取るべき主要な戦略的推奨事項を以下に提示します。
- 価値提案の選択と集中: 自社の経営資源とブランド特性を鑑み、「体験価値(サ-ドプレイス2.0)」を追求する高付加価値路線か、「利便性(ファスト・カフェ)」を追求する効率路線のいずれかに戦略的ポジショニングを明確化し、経営資源を集中投下すべきです。両者を追う「中途半端」な戦略は、競争優位を築けず淘汰されるリスクが最も高いと考えられます。
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速: モバイルオーダー&ペイ、AIを活用したパーソナライズドCRM、ロイヤルティプログラムを標準装備とし、顧客生涯価値(LTV)の最大化を図ります。同時に、AIによる需要予測、自動発注、最適人員配置を導入し、徹底したオペレーション効率化と食品ロス削減を実現します。デジタルはもはや選択肢ではなく、事業存続の必須条件です。
- サステナビリティの戦略的事業化: 「Farm to Cup(農園からカップまで)」のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保し、そのストーリーをブランド価値の中核に据えることで、エシカル消費を重視する顧客層の獲得を目指します。これは、企業の社会的責任を果たすと同時に、気候変動に起因する将来の原材料調達リスクに対応する、強靭なサプライチェーンを構築するための戦略的投資と位置づけるべきです。
- 「サードプレイス」の再定義と価値向上: リモートワークの定着やコミュニティ需要の高まりを受け、単なる座席提供から、コワーキング機能、イベントスペース、ブランド体験のハブといった多機能な空間へと進化させます。時間課金制やサブスクリプションモデルの導入も視野に入れ、「滞在価値」を収益化する新たなビジネスモデルを構築します。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本のカフェ市場規模の推移と今後の予測
日本のカフェ・喫茶店市場は、新型コロナウイルス感染症の流行による一時的な落ち込みから回復基調にあります。矢野経済研究所の調査によれば、2023年の国内珈琲喫茶店市場規模は約1兆円と推定されています 1。また、株式会社xenoBrainのAI予測では、現在の市場規模を8,613億円とし、今後5年間で6.33%成長、2030年には9,158億円に達するとの見通しが示されています 2。
しかし、これらの回復・成長予測は慎重に解釈する必要があります。過去の長期的な統計データを見ると、喫茶店施設数や市場規模は減少傾向にあった時期も存在します 3。現在の市場規模の回復は、コロナ禍からの反動的な需要回復に加え、インフレに伴う商品単価の上昇が売上高を押し上げている側面が強いと考えられます。ドトール・日レスホールディングスが増収にもかかわらず営業減益に陥っている事実は、コスト上昇分を価格転嫁しきれず、利益構造が悪化している可能性を示唆しており 5、市場が必ずしも健全な成長軌道にあるとは断定できません。市場は成熟期にあり、限られた需要をめぐるプレイヤー間のシェア争奪戦が本質であると認識すべきです。
市場セグメンテーション分析
カフェ市場は、顧客ニーズの多様化を反映し、複数の軸で細分化されています。
- 業態別: 顧客が席で注文し、商品が提供されるフルサービス型(例:コメダ珈琲店)と、カウンターで注文・会計し、顧客自身が商品を運ぶセルフサービス型(例:スターバックス、ドトール)に大別されます。コメダ珈琲店は、ゆったりとした座席と豊富なフードメニューで「滞在型」の価値を提供し、独自の地位を確立しています 7。
- 価格帯・品質別: コーヒーの品質によって、スペシャルティコーヒーとコモディティコーヒー(汎用的な豆)の市場に分けられます。近年、スペシャルティコーヒー市場の成長は著しく、その背景には消費者の「プレミアムな体験」への欲求があります 8。日本スペシャルティコーヒー協会の調査によると、スペシャルティコーヒーの生豆輸入量シェアは2018年の11.0%から2022年には13.4%へと着実に増加しており、品質へのこだわりが市場の重要なトレンドであることを裏付けています 9。
- チャネル別: 店舗内で飲食するイートインに加え、コロナ禍を経てテイクアウトとデリバリーの重要性が恒久的に高まりました。ある調査では、飲食店全体の売上に占めるデリバリー比率が9%、テイクアウト比率が20%に達したとのデータもあり 11、カフェ業態においても売上の10~20%を占める重要なチャネルとなっています 12。これにより、事業者は「空間価値」と「利便性」の両面での戦略構築を迫られています。
- 立地別: 駅前、ロードサイド、商業施設内、オフィス街、住宅街など、立地によって主要顧客層、利用動機、競合環境が大きく異なります。特定のエリアに集中出店するドミナント戦略(コメダ珈琲店)や、ブランドイメージを象徴する一等地への出店戦略(スターバックス)など、立地戦略そのものが企業の競争優位性を左右する重要な要素です。
主要な市場成長ドライバーと阻害要因
市場成長ドライバー
- スペシャルティコーヒー需要の拡大: 高品質なコーヒー体験を求める消費者の増加が、市場の質的成長を牽引しています 8。
- リモートワークの普及: 平日の日中、自宅やオフィス以外の「第三の場所(サードプレイス)」で仕事をする需要が拡大し、新たな市場機会を創出しています 1。
- SNS文化と体験価値の重視: InstagramなどのSNS上で「カフェ巡り」が一種のライフスタイルとして定着し、写真映えする空間やメニュー、そこでしか得られない体験への需要が高まっています 15。
市場阻害要因
- 国内人口の減少: 長期的に見て、国内の総消費人口の減少は市場全体のパイを縮小させる最大の構造的要因です。
- 異業種間競争の激化: 特にコンビニコーヒーは、低価格と圧倒的な利便性を武器に、カフェ市場の大きな脅威となっています 16。
- 構造的なコスト高騰: コーヒー豆、乳製品などの原材料費、光熱費、物流費、そして人件費の上昇が、業界全体の収益性を著しく圧迫しています 5。
- 「イエナカ」需要の高度化: 高性能な家庭用コーヒーメーカーや高品質なコーヒー豆のEC販売が普及し、自宅で楽しむコーヒーの質が向上したことも、外食需要に対する競合要因となっています 19。
業界の主要KPIベンチマーク分析
業界の健全性と各社の競争力を評価するため、主要なKPI(重要業績評価指標)を分析します。
| 企業名 | 2025年2月期 連結売上収益 | 2025年2月期 営業利益 | 2025年2月期 営業利益率 | 店舗数(2025年2月末時点) |
|---|---|---|---|---|
| コメダホールディングス | 470億5,700万円 (+8.8%) | 88億2,000万円 (+1.2%) | 18.7% | 1,015店舗 |
| ドトール・日レスHD | 1,488億2,200万円 (+5.8%) | 95億9,700万円 (+177.9%) | 6.4% | 2,065店舗 |
| スターバックス | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 1,986店舗 (2024年9月末) |
出典: 各社決算短信 6, 報道資料 22 を基に作成。ドトール・日レスHDは2025年2月期通期実績。コメダHDは2025年2月期実績。スターバックスは2015年に上場廃止のため公開財務データは限定的。
上表から、いくつかの戦略的示唆が読み取れます。コメダホールディングスは、高い営業利益率を維持しつつ安定成長を続けています。これは、フルサービスによる高い客単価と、ロイヤリティ収入が安定するフランチャイズ中心のビジネスモデルが、コスト高騰環境下で強みを発揮していることを示しています 17。一方、ドトール・日レスホールディングスは、売上規模では業界トップクラスですが、営業利益率はコメダに比べて低い水準にあります。これは、低価格帯セグメントでの競争の激しさと、コスト圧力の影響を受けやすい事業構造を示唆しています 6。
また、店舗あたりの売上高は、価格帯によって大きく異なります。ある分析によれば、客単価400円以上の高価格帯セルフサービス型カフェの1店舗あたり平均売上高が8,340万円であるのに対し、400円未満の低価格帯では4,320万円と、約2倍の開きがあります 24。この事実は、ブランド力と価格設定が収益性にいかに直結するかを明確に物語っています。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
カフェ業界を取り巻くマクロ環境は、政治、経済、社会、技術、法規制、環境の各側面から大きな影響を受けています。これらの要因をPESTLEフレームワークを用いて体系的に分析します。
政治(Politics)
- 受動喫煙防止条例の全国的な影響: 2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、屋内での原則禁煙が義務化されました。これにより、かつて喫煙席をセールスポイントとしていた一部の喫茶店やカフェチェーンは、顧客層の転換や店舗改装を余儀なくされました。小規模な既存店には経過措置が設けられていますが 25、新規出店においては完全禁煙が標準となり、クリーンな環境が業界のスタンダードとして定着しました。ある研究では、条例施行が飲食店の数に統計的に有意な悪影響を与えなかったと結論付けており 26、市場は既にこの変化に適応したと考えられます。
- 最低賃金政策: 政府主導による継続的な最低賃金の引き上げは、アルバイト・パート労働力への依存度が高いカフェ業界にとって、直接的な人件費増加要因となり、収益構造を圧迫し続けています。
経済(Economy)
- コストプッシュ・インフレ: 現在、業界が直面する最大の経済的脅威です。
- 原材料費の高騰: 主要な原材料であるコーヒー豆の国際相場は、生産国の天候不順や需要増を背景に歴史的な高値水準で推移しています 18。
- 為替レートの影響: 日本はコーヒー豆のほぼ全量を輸入に依存しているため、2022年以降の円安傾向は仕入れコストを大幅に押し上げています 29。
- エネルギー・物流費の上昇: 電気・ガス料金の高騰は店舗運営コストを、燃料価格の上昇はサプライチェーン全体の物流コストを増加させ、利益を侵食しています 5。
- 個人消費動向: 実質賃金の伸び悩みが続く中、消費者の価格に対する感度は依然として高く、可処分所得の動向はカフェの利用頻度や選択に影響を与えます。特に価格重視の顧客層は、より安価なコンビニコーヒーへと流れる可能性があります。
社会(Society)
- ライフスタイルの変化:
- リモートワークの定着: 働き方改革とコロナ禍を経てリモートワークが社会に定着したことは、カフェの役割を大きく変えました。平日の日中に、オフィスでも自宅でもない「第三の場所(サードプレイス)」として、集中して仕事をするためのワークスペース需要が生まれました 14。ある調査では、仕事場所としてカフェを利用したいと考える人が48.9%に上ることが示されています 33。この変化は、従来の回転率を重視するビジネスモデルから、滞在価値を収益化するモデルへの転換を促しています。
- 健康志向の高まり: カフェインの摂取を控えたい層向けのデカフェ(カフェインレス)コーヒーや、乳製品アレルギーやヴィーガンに対応する植物性ミルク(オーツミルク、アーモンドミルク等)、糖質を抑えたフードメニューへの需要が顕著に増加しています。
- 消費者意識の変化:
- エシカル消費とサステナビリティ: 環境や社会に配慮した商品・サービスを選ぶ「エシカル消費」への関心が高まっています。特に若年層を中心に、コーヒー豆の生産者の労働環境や、環境負荷の少ない調達方法(フェアトレード、ダイレクトトレード等)を重視する傾向が強まっています 15。企業のサステナビリティへの取り組みが、ブランド選択の重要な基準となりつつあります。
- 体験価値とSNS文化: カフェは単に喉の渇きを潤す場所ではなく、自己表現や他者との交流の場としての意味合いを強めています。「カフェ巡り」という言葉に代表されるように、空間のデザイン性、メニューの独創性、写真映え(インスタ映え)するビジュアルなどが、特にZ世代の来店動機に大きく影響しています 15。
技術(Technology)
- 店舗運営・顧客接点のデジタル化:
- モバイルオーダー&ペイ: スマートフォンで事前に注文・決済を済ませ、店舗では商品を受け取るだけというシステムが急速に普及しています。テイクアウト利用時の経験率は48.8%に達し、「待ち時間のストレスが減る」点が大きなメリットとして認識されています 36。
- キャッシュレス決済・セルフレジ: 多様な決済手段への対応と、レジ業務の省力化は、顧客利便性の向上と店舗オペレーションの効率化に不可欠な要素となっています。
- バックヤードの高度化:
- AIによる需要予測・在庫管理: 天候や過去の販売データなどをAIが分析し、需要を予測することで、発注業務の自動化や食品ロスの削減が可能になります(詳細は第8章で後述)。
- 進化するコーヒー関連技術: 焙煎技術や抽出マシンの性能向上は、スペシャルティコーヒーの繊細な風味を引き出すことを可能にし、業界全体の品質向上に貢献しています。
法規制(Legal)
- 労働関連法規: 「同一労働同一賃金」の原則や、パート・アルバイト従業員の有給休暇取得義務化など、労働関連法規の遵守は、人件費管理の複雑性を増大させ、労務管理体制の強化を企業に求めています。
- 食品リサイクル法: 年間の食品廃棄物排出量が100トンを超える事業者は、国への定期報告が義務付けられています。多くの大手カフェチェーンはこの対象となり、食品ロス削減への取り組みは法的な要請でもあります 38。
環境(Environment)
- 脱プラスチックへの対応: プラスチック資源循環促進法が施行され、使い捨てプラスチック製品の削減が社会全体で求められています。カフェ業界では、プラスチック製ストローやカトラリー、カップ、蓋の使用量を削減し、紙や木、植物由来のバイオマスプラスチックといった代替素材への切り替えが急務となっています 40。ある推計では、国内主要カフェチェーン9社だけで年間3億6950万個もの使い捨てカップが使用されているとされ、対応の遅れは企業イメージを大きく損なうリスクがあります 42。
- 気候変動リスクとサプライチェーン: コーヒー豆の主要生産国は、気候変動による干ばつ、豪雨、気温上昇といった影響を深刻に受けています。これにより、コーヒーの木の病気(さび病など)が蔓延し、収穫量の減少や品質の低下が懸念されています 43。将来的には、コーヒー豆の栽培に適した土地が2050年までに半減するという「コーヒーの2050年問題」も指摘されており 45、これは業界の存続基盤を揺るがしかねない長期的なリスクです。
このPESTLE分析から浮かび上がるのは、カフェ業界が単一の課題ではなく、コスト高騰、消費者意識の変化、技術革新、環境問題といった複数の強力な外部要因に同時に対応しなければならない、極めて複雑な経営環境にあるという事実です。特に、経済的な圧力である「コスト高騰」と、社会的・環境的な要請である「サステナビリティ」への対応は、一見するとトレードオフの関係にありますが、これを統合的に解決するサプライチェーン改革こそが、将来の競争優位を築くための鍵となります。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
カフェ業界の収益構造と競争の激しさを、マイケル・ポーターの「Five Forces(5つの力)」フレームワークを用いて分析します。この分析により、業界の魅力度と、持続的な収益性を確保する上での課題が明らかになります。
供給者の交渉力:【強い】
業界の収益性は、複数の強力な供給者によって圧迫されています。
- コーヒー豆農園・商社: コーヒー豆は天候や生産国の政情に左右される農産物であり、供給と価格が不安定です。特に、気候変動リスク(「コーヒーの2050年問題」)は、長期的な供給不安と価格上昇圧力をもたらします 45。高品質なスペシャルティコーヒーにおいては、生産者が限定されるため、その交渉力はさらに強まります。ダイレクトトレード(直接取引)は、品質とトレーサビリティを確保できる一方で、特定の生産者への依存度を高めるという側面も持ちます 46。加えて、円安は輸入調達コストを構造的に押し上げ、供給者側の価格交渉力を事実上強化しています 29。
- 店舗不動産オーナー: 特に駅前や一等地の商業施設など、集客力の高い立地の不動産オーナーは極めて強い交渉力を持ちます。賃料はカフェ事業の固定費の大部分を占めるため、その動向は収益性に直接的な影響を与えます。
- 乳製品・食材メーカー: 牛乳や小麦粉といった主要食材のメーカーも、インフレ局面においてはコスト上昇を理由に価格交渉力を強める傾向にあります。
買い手の交渉力:【極めて強い】
消費者は非常に多くの選択肢を持ち、その交渉力は極めて強い状況にあります。
- 多数の選択肢と低いスイッチングコスト: 消費者は、大手カフェチェーン、独立系カフェ、コンビニコーヒー、家庭用コーヒーなど、その時々の気分や状況に応じて自由に選択できます 16。特定のブランドへの強いロイヤルティがない限り、別の選択肢へ乗り換える際の心理的・金銭的コストはほぼゼロです。
- 多様化・高度化する要求: 買い手がカフェに求める価値は、単なる「コーヒーの味」に留まりません。価格の手頃さ、空間の雰囲気や快適さ(電源・Wi-Fiの有無)、立地の利便性、ブランドイメージ、接客の質、フードメニューの充実度など、要求は多岐にわたります。これらの多様なニーズをすべて満たすことは困難であり、企業はどの価値で顧客に訴求するかの選択を迫られます。
新規参入の脅威:【中程度】
業界への参入障壁は、参入形態によって異なります。
- 独立系カフェの開業: 個人が小規模なカフェを開業すること自体の許認可や初期投資のハードルは、他の業種と比較して著しく高いわけではありません。
- 大手チェーンとの競争: しかし、新規参入者が大手チェーンの牙城を崩すのは容易ではありません。大手は、強力なブランド認知度、全国規模の店舗網、スケールメリットを活かした原材料の一括調達によるコスト競争力、そして優良物件を確保する交渉力といった、高い参入障壁を築いています。
- 異業種からの参入: 近年、脅威として増しているのが異業種からの参入です。書店(蔦屋書店)、アパレルブランド、家電量販店などが、既存事業との相乗効果を狙い、カフェを併設するケースが目立ちます 48。これらの企業は、既に確立されたブランド力と顧客基盤を活用できるため、カフェ専業の新規参入者よりも有利な立場で市場に参入してきます。
代替品の脅威:【極めて強い】
カフェ事業は、機能面・価格面で多数の強力な代替品に晒されています。
- コンビニコーヒー: 1杯100円台という圧倒的な価格競争力と、全国5万店を超える店舗網がもたらす利便性により、カフェ業界にとって最大の代替脅威となっています。その市場規模は数千億円規模と推定され 49、カフェ市場から「手軽な一杯」の需要を確実に奪っています。当初は安価な代替品と見なされていましたが、品質向上に伴い、今や消費者の頭の中に「コーヒーの基準価格」を形成する「価格アンカー」としての役割を担うようになりました。
- 家庭用コーヒー(イエナカ需要): 高性能なコーヒーメーカーやカプセル式マシンの普及、オンラインでの高品質なコーヒー豆の入手容易化により、「イエナカ」で楽しむコーヒーの質は飛躍的に向上しました 19。リモートワークの普及もこのトレンドを後押しし、カフェで過ごす時間を代替しています。
- その他の代替品: 飲料としては、紅茶専門店やティースタンド、エナジードリンクなど。場所としては、コワーキングスペース、ファストフード店、ファミリーレストランのドリンクバー、さらには公園のベンチに至るまで、多様な代替品が存在します。
業界内の競争:【極めて激しい】
既存企業間の競争は、熾烈を極めています。
- 大手チェーン間のポジショニング競争: スターバックスが「体験価値(サードプレイス)」、ドトールが「価格と利便性」、コメダ珈琲店が「くつろぎのフルサービス空間」といったように、大手プレイヤーはそれぞれ異なるポジショニングを築きながら、激しいシェア争いを繰り広げています 2。
- 独立系・スペシャルティコーヒー店との差別化競争: 独自のコンセプトやストーリー、バリスタとの人間的な繋がり、希少なコーヒー豆の提供など、大手チェーンにはない価値を武器に、特定のこだわりを持つ顧客層を惹きつけています。
結論として、カフェ業界の収益性は5つの力すべてから強い圧迫を受けており、構造的に利益を上げにくい業界であると言えます。 この厳しい環境下で持続的な収益を確保するためには、徹底したコストリーダーシップ戦略を追求するか、他社には模倣困難な強力な差別化によって価格決定権を握るか、いずれかの明確な戦略的選択が不可欠です。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
カフェビジネスの競争優位性は、一杯のコーヒーが顧客に届くまでの全プロセス、すなわちサプライチェーンとバリューチェーンの設計と管理能力に大きく依存します。本章では、これらの連鎖を分析し、コスト構造、リスク要因、そして価値創出の源泉を明らかにします。
サプライチェーン分析(Farm to Cup)
コーヒーのサプライチェーンは、赤道を挟んだ「コーヒーベルト」地帯の農園から、日本の消費者のカップに至るまでの長く複雑な旅路です。
- 調達 (Sourcing):
- ルート: 主に、総合商社や専門商社を経由して生豆を買い付ける方法と、カフェ事業者自身が生産者から直接買い付けるダイレクトトレードがあります。
- コストとリスク: 商社経由は安定供給のメリットがある一方、中間マージンが発生します。ダイレクトトレードは、中間コストを削減し、生産者との直接コミュニケーションを通じて品質向上を図れるメリットがありますが、天候不順などによる生産量の変動リスクを直接負うことになります 46。為替レートの変動(特に円安)と、燃料価格高騰による輸送コストの上昇は、調達段階における二大リスク要因です 29。
- 焙煎 (Roasting):
- 形態: 大手チェーンでは、品質の均一化と効率化のため、大規模な焙煎工場で集中焙煎し、各店舗に配送する方式が主流です。一方、スペシャルティコーヒー店では、店舗ごとに小型の焙煎機を設置し、豆の個性を最大限に引き出す焙煎を追求するケースも多く見られます。外部の専門業者に焙煎を委託する形態もあります。
- 物流 (Logistics):
- 焙煎されたコーヒー豆や、牛乳、パン、ケーキなどの食材を、焙煎工場やセントラルキッチンから全国の店舗網へ効率的に配送するプロセスです。リードタイムの短縮(鮮度の維持)と、物流コストの最適化が重要な課題となります。
- 店舗での提供 (Serving):
- 最終的に、店舗のバリスタが豆を挽き、抽出し、一杯のコーヒーとして顧客に提供します。
サプライチェーンにおける変革の要請
- 価格変動リスクへの対応: 多くの事業者は、先物取引などを利用してコーヒー豆の価格変動リスクをヘッジしていますが、近年の歴史的な価格高騰と円安は、その効果を限定的にしています 18。リスク分散のため、複数の生産国や多様な調達ルートを確保するポートフォリオ戦略がますます重要になっています。
- サステナビティとトレーサビリティ: 消費者のエシカル消費への関心の高まりは、サプライチェーン全体の変革を迫っています。
- トレーサビリティの確保: 「どの農園で、誰が、どのように栽培した豆なのか」を追跡できる透明性の確保が求められています。ブロックチェーン技術などを活用し、生産から消費までの情報を追跡可能にする取り組みも始まっています。
- 環境負荷の低減: 生産地における森林破壊の防止、水資源の保全、農薬使用の削減といった環境配慮型の農法で栽培された豆(例:レインフォレスト・アライアンス認証)の調達が、企業の社会的責任として重視されています。
- 生産者の生活支援: フェアトレード認証のように、生産者に対して公正な価格を保証し、その生活水準の向上を支援する取り組みも、ブランドイメージを構成する重要な要素です。
バリューチェーン分析
カフェビジネスの価値は、事業活動の連鎖(バリューチェーン)の中で生み出されます。価値の源泉がどこにあるかを分析し、競争優位を構築するための示唆を得ます。
主活動 (Primary Activities)
- 原材料調達: 高品質でストーリー性のあるコーヒー豆を、いかに安定的に、かつ持続可能な方法で調達できるか。ダイレクトトレードによる生産者との強固な関係構築は、模倣困難な価値の源泉となり得ます(例:ブルーボトルコーヒー)。
- 商品開発: 顧客を惹きつける定番商品、季節限定ドリンク、フードメニューを開発する能力。特にスターバックスは、巧みな商品開発とマーケティングで常に話題を創出し、高い付加価値を生み出しています 52。
- 店舗開発: ブランドコンセプトを体現し、顧客が魅力を感じる立地を選定し、出店する能力。ドトールの駅前一等地への展開力や、コメダの郊外ロードサイドでのドミナント戦略は、それぞれの強力な価値基盤です。
- オペレーション: 注文受付から商品提供までの一連のプロセスを、効率的かつ高品質に実行する能力。モバイルオーダーの導入による待ち時間短縮や、マニュアル化された安定的なサービス提供が含まれます。
- マーケティング・販売: ブランドイメージを構築・維持し、顧客との関係を深化させる活動。スターバックスの「サードプレイス」というコンセプトの訴求は、単なるコーヒー販売を超えた価値提案の成功例です 51。
- 接客サービス: バリスタの専門知識、抽出技術、そして顧客一人ひとりに合わせたホスピタリティ溢れる接客。顧客満足度とロイヤルティを決定づける最後の、そして最も重要な価値創出の場です。
支援活動 (Support Activities)
- 人材育成・管理: 高度なスキルを持つバリスタや、店舗を統括するマネージャーを育成し、定着させる仕組み。スターバックスは、マニュアルに頼らない主体的な接客を促す人材育成に定評があります 53。
- 技術開発: 焙煎・抽出技術の研究、モバイルアプリの開発、データ分析基盤の構築など、ビジネスモデルを支える技術力。
価値の源泉とデジタルの役割
カフェビジネスにおける価値の源泉は、単一ではありません。①高品質なコーヒーと焙煎技術、②快適な空間デザインとブランド体験、③効率的なオペレーションと利便性、④バリスタの接客スキルという4つの要素が複雑に絡み合っています。
デジタル技術、特にモバイルアプリは、これらの価値を飛躍的に高めるポテンシャルを秘めています。
- マーケティング・販売の強化: モバイルアプリを通じて顧客データを収集・分析し、パーソナライズされたクーポンや新商品情報を配信することで、顧客エンゲージメントを高め、再来店を促進します。
- オペレーションの効率化: モバイルオーダー&ペイは、レジでの待ち時間を解消し、店舗スタッフの業務負荷を軽減します。これにより、スタッフはより付加価値の高い接客に集中できるようになります。
- 顧客体験の向上: デジタルとリアルを融合させ、オンラインでの事前注文から店舗でのスムーズな受け取り、アプリを通じたロイヤルティプログラムへの参加まで、一貫したシームレスな顧客体験を提供することが可能になります。
第6章:顧客需要の特性分析
カフェ市場の成長戦略を策定する上で、顧客を深く理解することは不可欠です。本章では、多様化する顧客をセグメントに分類し、それぞれの利用動機や購買決定要因(KBF)を分析します。特に、現代のカフェ需要を象徴する「サードプレイス」の概念について深掘りします。
顧客セグメント分析
カフェの利用者は、利用動機、利用頻度、世代といった複数の軸でセグメント化できます。
- 利用動機別セグメント:
- ワーク/スタディ層: リモートワーカーや学生など、仕事や勉強に集中する環境を求めて来店する層。静かな環境、快適な座席、電源・Wi-Fiの有無がKBFとなります。
- リフレッシュ/休憩層: ショッピングの合間や仕事の休憩時間に、一息つくために立ち寄る層。手軽さ、立地の良さ、スピーディーな商品提供が重視されます。
- ソーシャル/会合層: 友人や同僚との会話、打ち合わせの場として利用する層。複数人で利用しやすい座席配置、適度に活気のある雰囲気、長居のしやすさが求められます。
- ミール(食事)層: ランチやモーニングなど、食事目的で来店する層。フードメニューの魅力、セットメニューのお得感がKBFとなります。
- テイクアウト/利便性重視層: 店内では過ごさず、コーヒーや軽食を持ち帰ることを主目的とする層。モバイルオーダーの利便性、立地、提供スピードが最重要視されます。
- 利用頻度/こだわり別セグメント:
- ヘビーユーザー: ほぼ毎日、習慣としてカフェを利用する層。利便性や価格、あるいはロイヤルティプログラムのお得感を重視する傾向があります。
- ライトユーザー: 週に1回程度、あるいはそれ以下の頻度で利用する層。非日常的な体験や特別なメニューを求める傾向が強いです。
- スペシャルティコーヒー愛好家: コーヒー豆の産地や品種、焙煎度合い、抽出方法に強いこだわりを持つ層。バリスタの専門知識や、希少な豆の品揃えがKBFとなります。
- 価格・利便性重視層: コーヒーの品質よりも、価格の安さやアクセスの良さを最優先する層。コンビニコーヒーの主要顧客層と重なります。
- 世代別セグメント:
- Z世代(~20代半ば): SNSでの「映え」を意識した店舗の雰囲気やメニューのビジュアルを重視します。また、ブランドの社会的な姿勢(エシカル、サステナビリティ)に敏感で、共感を基にした「界隈消費」を行う傾向があります 15。友人と同じカフェを訪れ、その体験をSNSで共有すること自体が価値となります。
- ミレニアル世代(20代後半~40代前半): リモートワークの主要な担い手であり、「サードプレイス」としてのカフェのワークスペース機能を積極的に活用します。品質とブランドイメージ、空間の快適性のバランスを重視します。
- シニア層(60代以上): 地域のコミュニティの場、友人との交流の場としてカフェを利用します。フルサービスでゆったりと過ごせる空間(例:コメダ珈琲店)を好み、一度気に入ると繰り返し通うリピーターになりやすい特性があります 55。
KBF(主要購買決定要因)の分析
顧客が数ある選択肢の中から特定のカフェを選ぶ決め手(KBF)は、セグメントによって優先順位が異なります。
| KBF(主要購買決定要因) | ワーク/スタディ層 | ソーシャル層 | テイクアウト層 | スペシャルティ愛好家 | Z世代 | シニア層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒーの味・品質 | 中 | 中 | 中 | 高 | 中 | 中 |
| 価格 | 中 | 中 | 高 | 低 | 中 | 中 |
| 空間の雰囲気・快適さ | 高 | 高 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 座席(電源/Wi-Fi) | 高 | 中 | 低 | 低 | 中 | 低 |
| 立地の利便性 | 中 | 中 | 高 | 低 | 中 | 中 |
| ブランドイメージ | 中 | 中 | 低 | 中 | 高 | 低 |
| 接客の質 | 中 | 中 | 低 | 高 | 中 | 高 |
| メニューの多様性 | 中 | 高 | 中 | 中 | 高 | 高 |
出典: 各種調査データ 15 等を基に戦略的洞察を加え作成。
このマトリクスが示すように、すべての顧客を満足させる「万能なカフェ」は存在しません。例えば、「ワーク/スタディ層」に最高の環境を提供しようとすれば、静かで集中できる空間作りが求められますが、これは「ソーシャル層」が求める活気ある雰囲気とは相反する可能性があります。したがって、自社がどの顧客セグメントを主要ターゲットとし、どのKBFで他社を凌駕するのかを明確に定義することが、戦略の出発点となります。
「サードプレイス」需要の深掘り
社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した「サードプレイス」は、カフェ業界の価値を語る上で中心的な概念です。これは「第一の場所(自宅)」でも「第二の場所(職場・学校)」でもない、心安らぐ「第三の場所」を指します。現代の顧客がサードプレイスに求めるものは、より多様で深層的なものになっています。
- 集中と生産性の場: リモートワーカーにとって、サードプレイスは自宅の生活感から離れ、仕事に集中するための空間です。適度な雑音(アンビエントノイズ)が逆に集中力を高めるとも言われます。
- 孤独を感じない繋がり(”Alone Together”): 一人で過ごしながらも、周囲に他者の気配を感じることで、社会的な孤立感を和らげ、緩やかな繋がりを感じられる場です。
- リラックスと自己回復の場: 日常の役割(親、従業員など)から解放され、自分だけの時間を過ごし、精神的なエネルギーを充電するための空間です。
- 新しい発見とインスピレーションの場: いつもと違う環境に身を置くことで、新しい本や音楽、人々との出会いからインスピレーションを得る機会を提供します。
これらの需要に応えるためには、単に座席とWi-Fiを提供するだけでは不十分です。座席のレイアウト(一人席、ソファ席、大テーブルの多様性)、照明の明るさ、BGMの選曲、スタッフとの適度な距離感といった、空間全体の緻密な設計が求められます。成功しているカフェは、物理的な空間だけでなく、こうした心理的なニーズを満たす「雰囲気」や「文化」を巧みに創り出しているのです。
第7章:業界の内部環境分析
外部環境と顧客需要の変化に対応し、持続的な競争優位を築くためには、自社および競合が保有する経営資源や能力(ケイパビリティ)を客観的に評価することが不可欠です。本章では、VRIOフレームワークを用いて主要プレイヤーの競争優位の源泉を分析するとともに、業界全体の人材動向と労働生産性について考察します。
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
VRIO分析は、企業の経営資源が経済的価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(In-imitability)、組織(Organization)の4つの観点から持続的な競争優位を生み出すかを評価するフレームワークです 59。
- スターバックス コーヒー ジャパン
- 経営資源/ケイパビリティ: 強力なグローバルブランド、一等地を確保する店舗開発力、独自の「サードプレイス」体験を創出する空間デザイン能力、マニュアルに依存しない従業員育成システム。
- VRIO評価:
- 価値 (V): 高い。洗練されたブランドイメージと快適な空間は、顧客に高い付加価値を提供している 51。
- 希少性 (R): 高い。世界レベルで一貫したブランド体験を提供できる企業は稀である 53。
- 模倣困難性 (I): 非常に高い。ブランドイメージや企業文化は長年の投資の賜物であり、単に内装を真似るだけでは模倣できない。グローバルな調達網やデジタルプラットフォームも追随を困難にしている 53。
- 組織 (O): 高い。従業員に主体性を促す組織文化が、質の高い顧客体験を支えている 54。
- 結論: 持続的な競争優位を確立している。ブランド力とそれを支える組織文化が中核的な強み。
- 株式会社コメダホールディングス(コメダ珈琲店)
- 経営資源/ケイパビリティ: 「くつろぎ」を提供する独自の空間コンセプト(フルサービス、ソファ席)、FC加盟店との強固なパートナーシップに基づく独自のフランチャイズモデル、モーニングサービスに代表されるユニークな商品。
- VRIO評価:
- 価値 (V): 高い。特に郊外のファミリー層やシニア層に対し、「自宅のリビングの延長」のような価値を提供している 61。
- 希少性 (R): 高い。大手チェーンでフルサービスを徹底し、独自の「くつろぎ」文化を築いている点はユニーク。
- 模倣困難性 (I): 高い。FCオーナーの利益を重視し、本部が食材供給や経営指導で支えるというビジネスモデルは、長年の信頼関係の上に成り立っており、模倣が難しい。店舗設計のノウハウも蓄積されている。
- 組織 (O): 非常に高い。FC本部としての店舗支援体制、物流網、研修制度が、全国規模での品質の均一化とFCオーナーの高いロイヤルティを実現している。
- 結論: 持続的な競争優位を確立している。独自のFCモデルと、それを支える組織能力が競争力の源泉。
- ドトール・日レスホールディングス(ドトールコーヒーショップ)
- 経営資源/ケイパビリティ: 圧倒的な店舗網と駅前一等地を中心とした立地戦略、効率的なオペレーションによるコスト競争力、長年培われたブランドの知名度。
- VRIO評価:
- 価値 (V): 高い。「手頃な価格で、手軽に一杯」という価値を、利便性を求める顧客層に提供している 51。
- 希少性 (R): 中程度。1,000店舗を超える規模の店舗網は希少だが、低価格・利便性という価値提案自体は、コンビニコーヒーなど競合が多い。
- 模倣困難性 (I): 中程度。優良立地の確保は他社にとって容易ではないが、オペレーションの効率化や低価格戦略は、資本力のある競合(特にコンビニ)に模倣されやすい。
- 組織 (O): 中程度。効率的な店舗運営を支える組織体制は整備されているが、スターバックスやコメダのような、独自の文化に根差した模倣困難な組織能力とまでは言えない 63。
- 結論: 一時的な競争優位に留まる可能性がある。コスト競争力と立地優位性が強みだが、代替品の脅威に常に晒されており、持続性には課題が残る。
人材動向
- 求められる人材像: カフェ業界では、店舗で働くバリスタや店舗マネージャー(店長)、本部で働く商品開発、マーケティング、スーパーバイザー(SV)など多様な職種が存在します。特にスペシャルティコーヒー市場の拡大に伴い、コーヒー豆の知識、高度な抽出技術、ラテアートのスキルを持つ専門人材の市場価値は高まっています。
- 人材の定着と課題: 業界全体の課題として、特にアルバイト・パート従業員の離職率の高さが挙げられます。これは、比較的低い賃金水準、ピークタイムの過酷な労働環境、キャリアパスの不透明さなどが要因と考えられます。人材の定着率の低さは、採用・教育コストの増大、サービス品質の不安定化を招き、経営上の大きな課題となっています。
従業員の賃金相場とトレンド
- 賃金水準: バリスタの平均年収は、勤務先や経験によって大きく異なります。大手チェーンの正社員で年収350~420万円、個人経営のカフェで280~350万円程度が相場とされています 64。アルバイト・パートの平均時給は約1,096円というデータもあり 65、これはコンビニやファストフードといった他業種と比較して、必ずしも高い水準とは言えません。
- トレンド: 経験年数やスキルに応じて年収は上昇する傾向にあり、店長などの管理職になれば年収400万円以上も可能です 64。しかし、業界全体としては、最低賃金の上昇に対応するためのベースアップが中心であり、労働生産性の向上を伴わない賃金上昇は、企業の収益をさらに圧迫する要因となります。
労働生産性
- 人時売上高: 飲食店の生産性を測る代表的な指標として人時売上高(売上高 ÷ 総労働時間)があります。これは、従業員1人が1時間あたりにどれだけの売上を生み出したかを示す指標です 66。
- 業界水準と課題: 一般的な飲食店では3,000円~4,000円が平均値とされ、5,000円を超えると優良店と評価されます 67。カフェ業態は、比較的客単価が低く、顧客の滞在時間が長い傾向があるため、人時売上高は3,500円程度が一つの目安となります 68。
- 生産性向上の障壁: カフェ業界の労働生産性を高める上での障壁としては、①ランチタイムなど特定の時間帯に来客が集中すること、②ドリンクやフードの調理、接客、会計などオペレーションが複雑であること、③高い離職率による従業員のスキル習熟度の低さなどが挙げられます。これらの課題を克服し、人時売上高をいかに向上させるかが、収益性改善の鍵となります。
第8章:AIの影響とインパクト
人工知能(AI)は、もはや単なる業務効率化ツールではありません。それは顧客体験を根底から覆し、新たな収益機会を創出し、ビジネスモデルそのものを再定義する、カフェ業界にとって最も重要な戦略的基盤です。本章では、AIがバリューチェーンの各段階で具体的にどのような変革をもたらすのか、そのユースケースと戦略的意味合いを詳細に分析します。
店舗オペレーションの革新
AIは、店舗運営における無駄、無理、ムラを排除し、生産性を飛躍的に向上させます。
- 需要予測と自動発注: AIが天候、曜日、過去のPOSデータ、近隣のイベント情報、さらにはSNS上のトレンドまでを統合的に分析し、サンドイッチやケーキといった賞味期限の短い商品の需要を高い精度で予測します。
- ユースケース: ある弁当チェーンではAI導入により廃棄率を40%削減し、カフェ業態でもパン類の廃棄が多いという課題に対し予測精度を向上させた成功事例があります 69。
- 戦略的意味合い: これは、食品ロス削減による直接的なコスト削減と、欠品による販売機会損失の最小化という二つの大きなメリットを同時にもたらします。さらに、店舗スタッフを発注や在庫管理といった煩雑なノンコア業務から解放し、より付加価値の高い接客業務へとリソースを再配分することを可能にします。
- 人員配置の最適化: 来店客数の時間帯別予測に基づき、AIが最適な人員配置とアルバイトのシフトを自動で生成します。
- ユースケース: サイゼリヤでは来店予測AIの導入により、売上予測誤差を25%改善したと報告されています 70。
- 戦略的意味合い: ピークタイムの人員不足によるサービス品質の低下や、アイドルタイムの過剰人員による人件費の無駄を徹底的に排除します。これにより、顧客満足度を維持しつつ、労働生産性(人時売上高)を最大化することが可能になります。
- 自動化・省人化:
- ロボットバリスタ: アーム型ロボットがドリップコーヒーやエスプレッソを安定した品質で抽出し続けます。これにより、品質の標準化、24時間営業の実現、深夜早朝時間帯の省人化に貢献します。
- 画像認識AIレジ: ベーカリーチェーン「アンデルセン」で導入された「BakeryScan」のように、トレーに載せられた商品をAIカメラが瞬時に識別し、会計を自動で完了させます 70。これにより、レジ待ちの行列が劇的に解消され、顧客体験が向上します。
- 戦略的意味合い: 単純作業や反復作業をAIやロボットに任せることで、人間は「おもてなし」や顧客とのコミュニケーション、予期せぬトラブルへの対応といった、人間にしかできない創造的・感情的な業務に集中できます。ただし、ブランドのポジショニングによっては、過度な自動化が「温かみ」や「人間らしさ」といった価値を損なうリスクもあるため、戦略的な導入判断が求められます。
顧客体験のハイパー・パーソナライゼーション
AIは、画一的なマスマーケティングを終焉させ、顧客一人ひとりに最適化された「N=1」の体験を提供します。
- AIレコメンデーション: 顧客の過去の購買履歴、アプリの利用状況、来店時間帯、さらにはその日の天候などをAIがリアルタイムで分析し、モバイルアプリや店内のデジタルサイネージを通じて「あなたへのおすすめ」を提案します。
- ユースケース: スターバックスは既にAIを活用し、顧客データに基づいたパーソナライズされた商品推奨を行っています 71。この背景には、類似ユーザーの行動から推薦する「協調フィルタリング」や、商品の属性から推薦する「コンテンツベース」といった技術が用いられています 72。
- 戦略的意味合い: 顧客に「いつもの一杯」だけでなく、新たな発見や驚きを提供することで、アップセルやクロスセルを自然に促し、客単価の向上に繋げます。顧客は「自分の好みを深く理解してくれている」と感じ、ブランドへのエンゲージメントとロイヤルティが飛躍的に高まります。
- ダイナミック・プライシング: 店舗の混雑状況や需要に応じて、AIがリアルタイムで価格を変動させます。例えば、比較的空いている平日の午後にはドリンクを割引価格で提供して来店を促し、席の稼働率を平準化させるといった活用が考えられます。
- 戦略的意味合い: 収益機会を最大化するポテンシャルを秘める一方で、価格の公平性に対する顧客の不信感を招くリスクも伴います。導入には、透明性の高いルール設定と丁寧なコミュニケーション戦略が不可欠です。
マーケティングとCRMの高度化
AIはCRM(顧客関係管理)を、単なるデータ管理ツールから、未来を予測し、次の一手を導き出す戦略的意思決定システムへと進化させます。
- AIによる顧客データ分析: CRMシステムに蓄積された膨大な顧客データ(POS、アプリ利用履歴、位置情報など)をAIが多角的に分析し、人間では見つけ出すことが困難なインサイトを抽出します。
- ユースケース: 優良顧客となる可能性の高い顧客セグメントの特定、サービスからの離反予兆の検知、実施するキャンペーンの効果予測などが可能になります 74。
- 戦略的意味合い: 経験と勘に頼った旧来のマーケティングから、データに基づいた科学的なアプローチへと完全に移行します。これにより、マーケティング投資のROIを最大化し、LTV(顧客生涯価値)の向上に直接的に貢献します。
- SNSトレンド分析と商品開発: AIがTwitterやInstagram上の投稿をリアルタイムで分析し、次に流行する可能性のあるフレーバー、色、食感、あるいは「写真映え」するビジュアルの組み合わせを特定します。
- 戦略的意味合い: このインサイトを季節限定ドリンクなどの商品開発に活用することで、開発サイクルの短縮とヒット確率の向上を両立させることができます。消費者の潜在的なニーズをデータに基づいて捉え、市場に先駆けて投入することが可能になります。
サプライチェーンの最適化
AIは「Farm to Cup」の全工程に介在し、品質向上、コスト削減、トレーサビリティ確保を実現します。
- AIによる品質検査: コーヒーの生豆を撮影した高解像度画像をAIが解析し、カビ豆、虫食い豆、未熟豆といった欠点豆を瞬時に、かつ自動で検知・選別します。
- ユースケース: 既に「サクッとAI」や「ProfilePrint」といった、AI画像認識を活用したコーヒー豆の品質評価・不良検知システムが開発され、導入が進んでいます 76。
- 戦略的意味合い: 熟練した人間の目視による選別作業よりも高速かつ高精度な品質管理を24時間体制で実現します。品質の安定化は、顧客満足度とブランドの信頼性を支える根幹です。
- 焙煎プロファイルの最適化と物流ルートの最適化: AIが豆の種類、水分含有量、その日の気温・湿度といった変数を考慮し、最適な焙煎プロファイル(温度と時間のカーブ)を自動生成・制御します。また、各店舗への配送においては、交通状況や納品時間指定を考慮した最適な物流ルートを算出し、配送コストとCO2排出量を削減します。
| バリューチェーン段階 | 具体的なAIユースケース | 期待される効果(効率化/体験向上) | 戦略的意味合い(コスト削減/売上向上/LTV向上) |
|---|---|---|---|
| 商品開発 | SNSトレンド分析による新商品コンセプトの発見 | 体験向上 | 売上向上 |
| 原材料調達 | AI画像認識によるコーヒー豆の品質検査 | 効率化 | コスト削減(品質安定) |
| 焙煎・物流 | 最適な焙煎プロファイルの自動生成、配送ルート最適化 | 効率化 | コスト削減 |
| 店舗オペレーション | 需要予測と自動発注、最適人員配置、ロボットバリスタ | 効率化 | コスト削減、売上向上(機会損失防止) |
| マーケティング | CRMデータ分析による離反予測、キャンペーン最適化 | 効率化 | LTV向上 |
| 接客サービス | AIレコメンデーションによるパーソナライズされた提案 | 体験向上 | 売上向上(客単価UP)、LTV向上 |
この分析が示すように、AIは「体験」と「効率」という二極化する市場の方向性を、それぞれ極限まで推し進める強力な触媒として機能します。AIを駆使して徹底的な効率化を追求する「ファスト・カフェ」と、AIが提供する深い顧客理解を基に、人間が最高のパーソナルな「体験」を提供する高付加価値カフェ。どちらの戦略を選択するかが、企業の未来を決定づけることになるでしょう。
第9章:主要トレンドと未来予測
これまでの分析を踏まえ、今後3~5年のカフェ業界を形成する主要なトレンドと、その帰結として予測される未来像を提示します。これらのトレンドは個別に進行するのではなく、相互に影響し合いながら業界の構造変革を加速させます。
二極化の進展:「体験」と「効率」の棲み分け
市場は、高付加価値・体験重視の「スペシャルティ/サードプレイス型」と、低価格・利便性重視の「コモディティ/ファスト型」へと、より明確に二極化が進行します。
- スペシャルティ/サードプレイス型: スターバックスやブルーボトルコーヒーに代表されるこのセグメントは、単価が高くとも、そこでしか得られない高品質なコーヒー、洗練された空間、バリスタとのコミュニケーションといった「体験価値」を求める顧客層をターゲットとします。リモートワーク需要の取り込みによるコワーキング機能の強化や、特定の趣味・関心を持つ人々が集うコミュニティハブ化など、「場所」としての価値をさらに高めていく方向へ進化します。
- コモディティ/ファスト型: ドトールやコンビニコーヒーが属するこのセグメントは、時間のないビジネスパーソンや価格に敏感な学生などを主なターゲットとし、「速さ」「安さ」「手軽さ」を追求します。モバイルオーダーによる事前決済と店舗でのピックアップ、ドライブスルーの拡充、AIやロボティクスを活用した徹底的な省人化・効率化が競争の焦点となります。
この二極化の進展は、両者の中間に位置する特徴の曖昧なカフェにとって、淘汰の圧力を強めることを意味します。
サステナビビリティの主流化と競争優位の源泉化
サステナビリティ(持続可能性)は、もはや一部の意識の高い企業が取り組むCSR活動ではなく、事業の根幹に関わる必須要件、すなわち「守りのコンプライアンス」から「攻めの競争優位」へとその意味合いを変えます。
- エシカル調達の証明: フェアトレードやダイレクトトレードといった倫理的な調達を行っていることが、単なる美談ではなく、商品の品質とブランドの信頼性を保証する重要な要素となります。トレーサビリティ情報をQRコードなどで消費者に開示することが一般化するでしょう。
- 環境配慮型店舗と循環型ビジネス: 店舗設計におけるリサイクル素材の活用や省エネ設備の導入、コーヒーかすを再利用した商品の開発(アップサイクル)、リユーザブルカップの普及などが加速します。これらの取り組みは、環境負荷を低減すると同時に、エシカル消費を重視する顧客を引きつける強力なマーケティングツールとなります。
- 気候変動への適応: 「コーヒーの2050年問題」 45 への対応として、気候変動に強い品種の開発や、生産地の農家と連携した持続可能な農法の導入支援が、企業の長期的な安定調達を左右する重要な戦略課題となります。
デジタル・トランスフォーメーションの深化
デジタル技術は、顧客との接点からバックヤード業務まで、カフェビジネスのあらゆる側面を再構築します。
- モバイルオーダーの一般化: モバイルオーダー&ペイは、テイクアウトやクイック利用の標準的なインターフェースとなります 36。これにより、店舗はレジ業務から解放され、よりスムーズな商品提供と顧客対応に集中できます。
- サブスクリプションモデルの普及: 「月額〇〇円でコーヒー飲み放題」といった定額制サービスが、ヘビーユーザーを囲い込むための有力なモデルとして普及します。顧客の来店頻度を高め、安定的な収益基盤を構築することに貢献します。
- データ活用による経営の高度化: POSデータ、アプリ利用履歴、顧客属性データなどを統合的に分析し、顧客一人ひとりにパーソナライズされたマーケティングを展開することが可能になります。勘と経験に頼る経営から、データに基づいた科学的な意思決定へと移行します。
「体験」の多様化と異業種連携
「サードプレイス」の概念は、より多機能でダイナミックなものへと進化します。
- 異業種コラボレーション: 書店(蔦屋書店)、アパレル、アートギャラリー、音楽など、異業種との連携によって、カフェは多様な文化が交差するプラットフォームとなります。これにより、新たな顧客層の開拓と、ブランドイメージの向上が期待できます 48。
- コワーキング機能の強化: 単なる電源・Wi-Fiの提供に留まらず、オンライン会議に適した個室ブースの設置や、時間単位での課金システムの導入など、本格的なワークスペースとしての機能が強化されます。
- コミュニティハブ化: 特定の趣味(読書、写真など)や学び(英会話、プログラミング教室など)をテーマにしたイベントを定期的に開催し、共通の関心を持つ人々が集うコミュニティの拠点としての役割を担います。
健康志向への本格的対応
消費者の健康への関心はますます高まり、カフェのメニュー構成に大きな影響を与えます。
- ラインナップの拡充: デカフェ(カフェインレス)や、オーツミルク、アーモンドミルクといった植物性ミルクの選択肢が標準装備となります。
- 機能性・栄養価の訴求: 低糖質・低カロリーのスイーツやパン、プロテインやスーパーフードを加えた機能性ドリンクなど、健康や美容に貢献する付加価値を持った商品への需要が高まります。カフェインの過剰摂取への懸念 79 に対応し、健康的な選択肢を提供することが、顧客の信頼を得る上で重要になります。
これらのトレンドは、カフェ業界に大きな挑戦を突きつけると同時に、新たな成長機会をもたらします。変化の潮流を的確に捉え、自社の強みを活かした戦略を迅速に実行できる企業のみが、次世代の勝者となるでしょう。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
日本のカフェ市場における競争環境を深く理解するため、主要なプレイヤーの戦略、強み・弱み、そしてメガトレンド(デジタル、サステナビリティ)への対応状況を比較分析します。
国内大手チェーン(セルフサービス)
- スターバックス コーヒー ジャパン
- 戦略: 「サードプレイス」というコンセプトを軸に、高品質なコーヒーと洗練された空間による体験価値の最大化を追求。季節限定のフラペチーノ®に代表される巧みな商品開発とプロモーションで常に市場の話題をリード。
- 強み・弱み:
- 強み: 圧倒的なブランド力、主要都市の一等地を抑える店舗開発力、独自の企業文化に根差した高いレベルの接客サービス、強力なデジタルプラットフォーム(公式アプリ、Starbucks® Rewards)。
- 弱み: 比較的高価格帯であるため、景気変動や低価格競争の影響を受けやすい。店舗の標準化が進む一方で、画一的との批判も一部に存在する。
- デジタル戦略: 業界をリード。モバイルオーダー&ペイを早期に導入し、会員プログラム「Starbucks® Rewards」は1,000万人以上の会員を擁し、収集したデータを活用したパーソナライズマーケティングに強みを持つ 71。
- サステナビリティ: 「GRENER STORES」の展開、倫理的な調達(C.A.F.E.プラクティス)の推進、リユーザブルカップの割引やタンブラー貸し出しプログラムなど、業界のサステナビリティを牽引する取り組みを積極的に行っている 40。
- ドトール・日レスホールディングス(ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ)
- 戦略: 駅前やビジネス街といった好立地を基盤に、手頃な価格とスピーディーな提供による利便性の追求を基本戦略とする。モーニングセットやミラノサンドなど、フードメニューにも強みを持つ。
- 強み・弱み:
- 強み: 全国に広がる圧倒的な店舗網と立地優位性、効率化されたオペレーションによるコスト競争力、幅広い層に受け入れられる知名度。
- 弱み: ブランドイメージの陳腐化、体験価値の側面でのスターバックスとの差。コンビニコーヒーとの直接的な価格競争に晒されやすく、収益性が圧迫されやすい 5。
- デジタル戦略: 公式アプリやdポイント・Pontaポイントとの連携を進めているが、スターバックスほどの強力な顧客囲い込みプラットフォームには至っていない。DXは今後の重要課題と認識されている。
- サステナビリティ: グループ行動規範の中で環境活動を推進しており、廃棄物削減や持続可能な商品調達を掲げているが、スターバックスほど先進的な取り組みは目立たない。
- タリーズコーヒージャパン
- 戦略: スターバックスと同様のシアトル系カフェとして、コーヒーの品質にこだわりつつ、パスタなどの食事メニューを充実させることで差別化。伊藤園グループの一員として、紅茶メニューにも力を入れている。
- 強み・弱み:
- 強み: スペシャルティコーヒーへのこだわり、フードメニューの多様性、落ち着いた内装による一定のファン層の獲得。
- 弱み: スターバックスとドトールの中間に位置し、ポジショニングがやや曖昧。ブランドの独自性をいかに打ち出すかが課題。
- デジタル戦略: 公式アプリ、タリーズカード、クラブタリーズといったロイヤルティプログラムを展開。モバイルオーダーも導入している。
- サステナビリティ: コーヒー産地との共生(接ぎ木プロジェクト等)、マイタンブラー割引、絵本アワードの開催など、環境・福祉・地域貢献の3軸で独自のCSR活動を展開している。
国内大手チェーン(フルサービス)
- コメダホールディングス(コメダ珈琲店)
- 戦略: 「街のリビングルーム」をコンセプトに、郊外のロードサイドを中心に展開。フルサービス、ゆったりとしたソファ席、豊富なフードメニュー(シロノワール等)で「くつろぎ」という独自の体験価値を提供。
- 強み・弱み:
- 強み: 独自のポジショニングによる高い顧客ロイヤルティ、FCオーナーの利益を重視した強固なフランチャイズモデル、高い収益性 23。
- 弱み: 主に郊外・地方が中心であり、都心部での競争力は限定的。伝統的な喫茶店モデルであり、若年層への訴求力やデジタル化の面では課題も。
- デジタル戦略: プリペイドカード「コメカ」や公式アプリを展開しているが、決済や店舗検索が中心。顧客データ活用によるパーソナライゼーションはこれからの領域。
- サステナビリティ: 「コメダの森」活動や子ども職場体験など、地域社会との共生を重視した活動に注力している。
グローバル・スペシャルティ
- ブルーボトルコーヒー
- 戦略: 「デリシャスネス(美味しさ)」を徹底的に追求。サードウェーブコーヒーの旗手として、豆の品質、焙煎、抽出方法にこだわり、最高品質のコーヒー体験を提供。ミニマルで洗練された店舗デザインも特徴。
- 強み・弱み:
- 強み: スペシャルティコーヒー市場における強力なブランドイメージ、品質への妥協なき姿勢、熱狂的なファン層の存在。
- 弱み: 店舗数が限定的で、マスマーケットへのリーチは小さい。高価格帯であり、顧客層が限られる。
- デジタル戦略: オンラインストアでのコーヒー豆販売や定期便(サブスクリプション)に注力し、eコマースで全国のファンと繋がっている。
- サステナビリティ: 創業以来、生産者とのダイレクトトレードを基本とし、持続可能な調達を重視。廃棄物ゼロや温室効果ガス排出削減を目標に掲げている。
最大の競合(コンビニ)
- セブン‐イレブン(セブンカフェ)、ローソン(マチカフェ)、ファミリーマート(ファミマカフェ)
- 戦略: 全国津々浦々の店舗網という圧倒的な利便性と、1杯100円台という低価格を武器に、日常的なコーヒー需要を取り込む。近年は豆の品質向上や高機能マシンの導入にも注力。
- 強み・弱み:
- 強み: 他の追随を許さない店舗数とアクセスの良さ、価格競争力、24時間営業。
- 弱み: あくまでコンビニの一機能であり、カフェのような滞在価値や専門性は提供できない。ブランド体験の構築は困難。
- デジタル戦略: 各社の公式アプリ(セブン-イレブンアプリ、ファミペイ等)と連携し、コーヒーの割引クーポンを頻繁に配布することで、来店頻度を高める強力なツールとして活用している。
- サステナビリティ: 各社ともグループ全体で環境目標(GREEN CHALLENGE 2050等)を掲げ、持続可能な調達やプラスチック削減に取り組んでいる。
異業種参入
- 蔦屋書店(CCC)、無印良品(Café&Meal MUJI)など
- 戦略: 本業である書籍や雑貨の販売とカフェを融合させ、ライフスタイル提案型の空間を創出。カフェ機能は、顧客の滞在時間を延ばし、ブランドへのエンゲージメントを高めるための重要な要素と位置づけられている。
- 強み・弱み:
- 強み: 既存の強力なブランド力と顧客基盤、本業とシナジーを生み出すユニークな体験価値の提供。
- 弱み: カフェ事業単体での収益性やオペレーション効率は、専業チェーンに劣る可能性がある。
- デジタル戦略: Tポイント(CCC)やMUJI passport(無印良品)といった、本業で構築した強力な会員基盤とアプリを活用し、顧客データを横断的に分析・活用できるポテンシャルを持つ。
- サステナビリティ: ブランド全体の思想としてサステナビリティを重視。特に無印良品は、「素材の選択」を理念に掲げ、Café&Meal MUJIでも旬の素材や環境配慮型の食材を積極的に使用している。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、日本のカフェ業界で勝ち抜くための戦略的意味合い(インプリケーション)を導き出し、実行すべき具体的な事業戦略を提言します。
今後3~5年で、勝者と敗者を分ける決定的な要因
カフェ業界は、構造的なコスト圧力と激しい競争に晒され、もはや全ての顧客を満足させる総花的な戦略では生き残れない時代に突入しています。今後、業界の勝者と敗者を分けるのは、以下の4つの能力です。
- ブランド力と明確な価値提案: 「なぜ、コンビニではなく、あなたのカフェを選ぶのか?」という問いに、顧客が即答できるだけの明確な理由を提供できるか。それはスターバックスのような「最高のサードプレイス体験」か、コメダのような「心からくつろげる空間」か、あるいはドトールやコンビニのような「圧倒的な利便性」か。曖昧なポジショニングは、価格競争と体験価値競争の板挟みとなり、淘汰される運命にあります。
- デジタル対応力: デジタルは、もはや単なるツールではなく、事業の神経網です。モバイルアプリを基盤とした顧客とのダイレクトな関係構築、収集したデータをAIで分析し、一人ひとりに最適化された体験を提供する能力(パーソナライゼーション)、そして需要予測や自動化による徹底したオペレーション効率化。このデジタル神経網の洗練度が、LTV(顧客生涯価値)と収益性を直接的に左右します。
- コスト管理能力: 原材料費、エネルギー費、人件費の構造的な上昇は今後も続くと予想されます。これに対応するには、サプライチェーン全体の最適化、AI活用による食品ロス削減、省人化技術の導入など、テクノロジーを駆使した科学的なコスト管理能力が不可欠です。従来の経験と勘に頼った管理では、利益を確保し続けることは困難です。
- 体験価値の創出と進化: 「体験」を強みとするプレイヤーにとっては、その価値を常に進化させ続ける能力が問われます。リモートワーク、コミュニティ需要、異業種連携といった外部環境の変化を捉え、「サードプレイス」の概念を再定義し、新たな収益モデル(例:時間課金制、サブスクリプション)を構築できるかが、持続的成長の鍵となります。
捉えるべき機会と備えるべき脅威
- 機会 (Opportunities):
- サードプレイス2.0需要: リモートワーク定着による、単なる休憩場所ではない「集中できるワークスペース」「緩やかな繋がりを感じるコミュニティハブ」としての新たな需要。
- エシカル・サステナブル消費市場の拡大: 環境や社会に配慮したブランドを積極的に選ぶ消費者層、特にZ世代の増加。これをブランドストーリーの中核に据えることで、新たなファンを獲得できる。
- 健康志向の高まり: デカフェ、植物性ミルク、低糖質フードなど、健康を切り口とした高付加価値商品の開発機会。
- インバウンド需要の回復: 訪日外国人観光客に対し、日本の喫茶文化や高品質なスペシャルティコーヒーといったユニークな体験を提供できる機会。
- 脅威 (Threats):
- コスト構造の悪化: コーヒー豆の国際価格高騰、円安、エネルギー・人件費の上昇という「トリプルパンチ」による継続的な収益圧迫。
- コンビニコーヒーの進化: さらなる品質向上や、カフェラテ・スイーツなど商品ラインナップの拡充による、カフェ市場への侵食拡大。
- 労働力不足の深刻化: 国内の生産年齢人口の減少に伴う、店舗運営に必要な人材(特にアルバイト・パート)の採用難と、それに伴う人件費のさらなる上昇。
- 「イエナカ」需要の質的向上: 家庭用コーヒー機器の高性能化と、高品質な豆のD2C(Direct to Consumer)販売の拡大により、カフェを利用する動機そのものが相対的に低下するリスク。
戦略的オプションの提示と評価
上記の分析に基づき、取りうる3つの戦略的オプションを提示します。
- オプションA:「体験価値」特化戦略(プレミアム・エクスペリエンス・プロバイダー)
- 概要: 高品質なスペシャルティコーヒー、洗練された空間デザイン、高度な専門性を持つバリスタによる接客を武器に、高価格帯でも顧客が満足する最高の体験価値を追求する。
- メリット: 高い利益率を確保でき、価格競争から脱却できる。強力なブランドロイヤルティを構築可能。
- デメリット: ターゲット市場が限定される。高い初期投資(内装、設備)と継続的な人材育成コストが必要。
- 成功確率: 中~高。実行には、強力なブランドコンセプト、卓越した品質管理能力、そして人材への投資が不可欠。
- オプションB:「利便性」特化戦略(ファスト・カフェ・オペレーター)
- 概要: モバイルオーダー、ドライブスルー、小型店舗の多店舗展開を軸に、圧倒的な利便性とスピードを追求する。AIやロボティクスを最大限活用し、徹底したローコストオペレーションを構築する。
- メリット: 広範な市場にリーチできる。規模の経済を活かしやすい。
- デメリット: コンビニコーヒーとの熾烈な競争に常に晒される。低い利益率を、高い回転率と販売量でカバーする必要がある。
- 成功確率: 中。成功には、巨額のシステム投資と、コンビニに匹敵するレベルの立地確保能力、そして徹底したコスト管理文化が求められる。
- オプションC:両利きの経営戦略(ハイブリッド・モデル)
- 概要: 主要ブランドは「体験価値」を追求しつつ、テイクアウト専門の小型サテライト店や、デジタルチャネル限定の利便性重視ブランドを別途展開する。
- メリット: 異なる顧客セグメントを同時に捉え、市場全体でのシェアを最大化できる可能性がある。
- デメリット: 経営資源が分散し、どちらの戦略も中途半端になるリスクが最も高い。ブランド管理が複雑化し、組織内でコンフリクトが生じる可能性。
- 成功確率: 低~中。実行には、極めて高度な経営管理能力と、明確なブランドポートフォリオ戦略が必要。
最終提言:『体験価値』特化戦略への集中
データと論理に基づき、取るべき最も説得力のある事業戦略は、オプションA:「体験価値」特化戦略であると提言します。
その理由は以下の通りです。
- 収益性の確保: Five Forces分析が示す通り、カフェ業界は構造的に収益性が低い。コスト高騰が続く環境下で持続的に利益を成長させるには、価格競争から脱却し、価格決定権を握ることが不可欠です。体験価値への投資は、これを可能にする唯一の道です。
- 代替品との差別化: 利便性でコンビニに対抗するのは、資本力と店舗網の観点から極めて困難です。「なぜコンビニの2倍、3倍の価格を払うのか」という問いに対し、「最高の空間とサービス」という明確な答えを提供することが、最も合理的な差別化戦略です。
- メガトレンドとの合致: サステナビリティ、健康志向、コミュニティ需要といった社会的なメガトレンドは、すべて「安さ」や「速さ」よりも、「質」や「意味」を重視する価値観に基づいています。体験価値特化戦略は、これらの追い風を最大限に活用できます。
実行に向けたアクションプランの概要
- KPI(重要業績評価指標):
- 財務指標:顧客単価、客当たり利益、既存店売上高成長率
- 顧客指標:NPS®(ネット・プロモーター・スコア)、顧客ロイヤルティプログラム会員数・利用率、再来店率
- オペレーション指標:バリスタのスキル認定レベル、従業員満足度・定着率
- タイムライン(最初の1年間):
- 第1四半期: ブランドコンセプトの再定義とターゲット顧客セグメントの明確化。フラッグシップ店舗のコンセプト設計開始。
- 第2四半期: サプライチェーンの見直し(ダイレクトトレード先の探索)。バリスタの新たな育成・評価プログラムの策定。
- 第3四半期: 公式アプリのリニューアル(パーソナライゼーション機能強化)。フラッグシップ店舗の改装着手。
- 第4四半期: 新ブランドコンセプトに基づくマーケティングキャンペーンの開始。リニューアルしたフラッグシップ店舗のオープン。
- 必要リソース:
- 人材: CBO(チーフ・ブランド・オフィサー)の任命、データサイエンティスト、UX/UIデザイナーの採用・育成。
- 投資: 店舗改装投資、デジタルプラットフォーム開発投資、人材育成プログラムへの投資。
- パートナーシップ: ユニークな体験を提供できる異業種(アート、音楽、出版など)との戦略的提携。
この戦略は、短期的なコスト増を伴う困難な道ですが、長期的に見て模倣困難な競争優位を築き、変化の激しい市場で持続的に成長するための、最も確実な道筋であると確信します。
第12章:付録
引用文献
- 外部環境分析_ 珈琲喫茶店, https://sanzaka.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/pachira_sample_cafe.pdf
- AIが予測するカフェ業界 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング – xenoBrain, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/cafe
- 喫茶店営業の 実態と経営改善の方策 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000171261.pdf
- 喫茶店営業の実態と – 経営改善の方策 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001547735.pdf
- (株)ドトール・日レスホールディングス【3087】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3087.T/financials
- ドトール・日レスホールディングス (3087) : 決算情報・業績 [DNHC] – みんかぶ, https://minkabu.jp/stock/3087/settlement
- 【ポジショニングマップとは】スタバ/ドトールなどカフェ市場で分析 – Marketing101 -, https://marketing101.jp/positioning_map/
- 【調査資料】 日本のコーヒー市場予測2025-2033:ホールビーン、挽き豆、インスタントコーヒー, https://www.marketresearch.jp/reports/japan-coffee-market-renub/
- スペシャルティコーヒー市場調査2022 要約, https://scaj.org/wp-content/uploads/2023/04/%EF%BD%BD%EF%BE%8D%EF%BE%9F%EF%BD%BC%EF%BD%AC%EF%BE%99%EF%BE%83%EF%BD%A8%EF%BD%BA%EF%BD%B0%EF%BE%8B%EF%BD%B0%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%BB2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A6%81%E7%B4%84.pdf
- スペシャルティコーヒー 市場調査2024 要約, https://scaj.org/wp-content/uploads/2025/05/2024%E5%B9%B4%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8-1.pdf
- 数字で読み解くフードサービストレンド:飲食店の売上げ比率、デリバリーは9%、テイクアウトは20%に – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/restaurant/hamada20220325013422652
- フードデリバリー売上比率の適正値は?|飲食店が損をしない導入バランス完全ガイド, https://inshokuai.jp/delivery-sales-ratio/
- スペシャルティコーヒーの意味・定義とは?評価基準・市場規模・割合 – DRIP POD, https://drip-pod.jp/Page/Feature/specialty-coffee-definition.aspx
- サードプレイスとは?意味や必要性をわかりやすく解説! – Beacapp Here, https://jp.beacapp-here.com/blog/what-is-third-place/
- 界隈消費とは?Z世代の消費傾向と企業がマーケティングに活かす方法を解説 – 株式会社FinT, https://fint.co.jp/blog/kaiwai-consumption
- カフェ業界コラム | 新規事業ドットコム, http://www.sinkijigyou.com/column/cafe/
- 2025年2月期 決算短信〔IFRS〕(連結), https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250409/20250408510776.pdf
- コーヒー価格2倍の危機、業界の企業努力と消費者への影響 | 食品産業新聞社ニュースWEB, https://www.ssnp.co.jp/beverage/605345/
- 日本のコーヒーポッド市場 規模、成長、2032年までの予測, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/japan-coffee-pods-market
- 日本のコーヒーメーカー市場規模(~2035年), https://www.globalresearch.co.jp/reports/japan-coffee-machines-market-mrf/
- 日本コーヒーマシン市場規模、株式、成長、予測, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/japan-coffee-machine-market
- スタバ2024業績 物価高でも順調に成長 2025年度、直営2000店達成へ, https://coffee.ism.fun/article/fd5a72ce-b0e5-496a-bcc5-035ce116312f
- コメダホールディングス (3543) : 決算情報・業績 [KHCL] – みんかぶ, https://minkabu.jp/stock/3543/settlement
- 日本の喫茶店およびカフェ市場の展開と 主要企業の戦略(1), https://manage.chukyo-u.ac.jp/research/bulletin/pdf/109010330101matsubara-chukyo.pdf
- 飲食店・職場等の原則屋内禁煙が義務化されました! – 千葉県, https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/tabako/jyudoukitsuen.html
- 受動喫煙を厳しくすると飲食店の売上は減るのか – ダイヤモンド・オンライン, https://diamond.jp/articles/-/120300
- コーヒーの統計について – SOMA COFFEE KYOTO, https://somacoffee.net/coffee-statistics/
- 2025年 世界のコーヒー価格の現状とその要因 – ILMIIO ROASTERY Lab., https://ilmiioroastery.com/blogs/stats/2025-coffee-price
- 2025年、米国発の「コーヒー関税ショック」:世界と日本はどう動く? そしてサステナブルな未来とは – 2050 coffee by Kurasu, https://2050.coffee/blogs/news/trump-coffee-effect
- 【円安】スタバやモスも… コーヒー”仕入れ価格上昇”で値上げの動き 福島 NNNセレクション, https://www.youtube.com/watch?v=uLdgKDz9AbY
- コーヒーのサプライチェーンにおける構造的課題, https://toyoeiwa.repo.nii.ac.jp/record/1722/files/JSKR-N40_P95-114.pdf
- サードプレイスオフィスとは? 最適なテレワーク環境を見つける検索サービス5選 | Worker’s Resort, https://www.workersresort.com/articles/third-place-office/
- コロナ流行後、自宅でも職場でもない「第三の場所」を求める人が増加 | 株式会社ブイキューブ, https://jp.vcube.com/news/release/20220324-1530.html
- 電通、「エシカル消費 意識調査2022」を実施 – News(ニュース) – 電通ウェブサイト, https://www.dentsu.co.jp/news/release/2022/0620-010527.html
- Z世代における界隈消費の傾向と価値観の変化 | 株式会社一創, https://www.issoh.co.jp/column/details/4535/
- 外食店での利用経験率、セルフオーダー(自身のスマホ利用)57.1%、テイクアウト時のモバイルオーダー(事前注文や決済)48.8%。セルフオーダーが2021年調査(26.0%)と比べて急増 | 株式会社リクルート, https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/0722_14591.html
- 「モバイルオーダーがある店をよく利用するようになった」は48.0%。デメリット1位は「登録の手間」【消費者意識調査】 | ネットショップ担当者フォーラム, https://netshop.impress.co.jp/node/13754
- 食品リサイクル法とは?施行された背景や具体的な取り組みを分かりやすく解説, https://toukatsuseisou.com/3077/
- 食品リサイクル法とは?食品を扱う飲食店、食品メーカーが必ず知っておくべき法律をわかりやすく解説します – ごみ.Tokyo, https://gomi.tokyo.jp/category/industrial-waste-law/food-recycling-law
- 飲食店にも迫る「脱プラスチック」の波!導入事例や取り入れ方とは? – canaeru(カナエル), https://canaeru.usen.com/diy/trend/p1010/
- 【脱プラスチック】飲食店向けのプラスチック削減策をご紹介!導入事例や取り入れ方は?, https://sawanna.jp/blogs/blog/restaurant-plastic-reduction
- 【使い捨てカップ】カフェチェーン9社で年間3.7億個、スタバが突出大半が焼却処理で, https://plasticjournal.net/backnumber/topics/3742.html
- コーヒーを気候変動に適応させ、農家の未来も守る――不足するイノベーションに新品種の開発・普及で巻き返し|サステナブル・ブランド ジャパン | Sustainable Brands Japan, https://www.sustainablebrands.jp/news/1228126/
- Action1:コーヒーの課題を語ろう|コーヒーから始める、私のSDGs – My COFFEE STYLE, https://mystyle.ucc.co.jp/magazine/a_30989/
- コーヒーの2050年問題って知ってますか?|マンスリーレポート – 株式会社日本統計センター, https://www.nihon-toukei.co.jp/monthly_report/archives/6
- ダイレクトトレードコーヒーとは?フェアトレードとの違いや購入できるお店も紹介 – Life Hugger, https://lifehugger.jp/column/direct-trade-coffee/
- フェアトレードとダイレクトトレードの違いとは?, https://coffee-a-gogo.net/2018/05/01/what-is-the-difference-between-fair-trade-and-direct-trade/
- 急増中のミクストランとは? 飲食店×異業種の新たなカタチ, https://owner-blog.tabelog.com/kaigyo/post-85.html
- コンビニコーヒーのマーケティング戦略とは?急拡大するコーヒー市場でのシェア争いから目が離せない – ゆいマーケ, https://yui-marke.com/article/2426/
- カフェ業界動向および現状 | M&A・事業承継なら経営承継支援, https://jms-support.jp/column/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%EF%BD%8D%EF%BC%86a%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- カフェのポジショニングマップ事例。軸の決め方の参考に! – 集客・広告戦略メディア「キャククル」, https://www.shopowner-support.net/glossary/position/mapcafe/
- 「バリュー・チェーン分析」の4つのステップ!事業のムダをなくして圧倒的な成長スピードを実現するフレームワーク – MarTechLab(マーテックラボ)|マーケティング×テクノロジー, https://martechlab.gaprise.jp/archives/mlt/value-chain-analytics/
- VRIO分析とは?4つの要素と目的・他社事例(ユニクロ・トヨタ)を紹介 – キャリアマート, https://www.careermart.co.jp/blog/blog/archives/22012
- VRIO分析とは?4つの要素と分析手順、大手企業の事例を解説 – 口コミアカデミー, https://academy.kutikomi.com/news/marketing_vrioanalysis/
- シニア向け喫茶店・カフェ事業 | 高齢者とともに明るい未来を, https://koureisya-to-akaruimirai.com/hobby/cafe/
- vol.2シニア×カフェ|「アクティブシニア」ホントのところ|シルバーラボシルバーラボブログ, https://fujiplus.jp/silverlab/blog/vol2_blog.html
- コーヒーショップ(カフェ)利用に関するアンケート調査 – アスマーク, https://www.asmarq.co.jp/data/ex1610/
- [16510] コーヒーチェーン店の利用に関するアンケート調査(第3回), https://myel.myvoice.jp/products/detail/16510
- VRIO分析とは?VRIO分析の考え方や具体的な事例をわかりやすく解説 – bizboost, https://blog.bizboost.co.jp/what-is-vrio-analysis-and-how-it-works
- 3C分析とは?目的・事例からSWOT分析との違い、一緒に使いたいフレームワークまで徹底解説, https://my-vision.co.jp/articles/3c-analysis
- バリューチェーン分析|幸成 – note, https://note.com/wisearrowltd/n/n020395c0e34d
- VRIO分析|幸成 – note, https://note.com/wisearrowltd/n/n21f66e86d1f5
- VRIOフレームワーク – やさしいビジネススクール, https://yasabi.co.jp/vrio/
- バリスタの年収はいくら?仕事内容・初任給・年収アップの方法・将来性まで徹底解説, https://pairing-job.jp/content/barista-nensyu/
- xn--pckua2a7gp15o89zb.com, https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6#:~:text=%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7,%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E5%B0%82%E9%96%80%E8%81%B7%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
- 飲食店スタッフの生産性に関する基礎知識。正しく数値を把握して業務効率化を!, https://www.inshokuten.com/foodist/article/5434/
- 飲食店経営者が意識すべき人時売上高の目安・労働分配率とは?人件費率を30%に抑えるだけじゃダメ!? – 店舗物件探し, https://www.inshokuten.com/foodist/article/4468/
- 飲食店の生産性【人時売上高・人時生産性・人時入客数・労働分配率】詳しく解説します。 | AtoZコンサルタント, https://atoz-consultant.com/restaurant-productivity/
- 売上予測AIの活用で仕込み量を最適化する|飲食店の食品ロス削減と業務効率UPの実践法, https://inshokuai.jp/ai-sales-forecasting/
- 飲食店におけるAIの活用事例15選!売上UPやロス・人件費削減など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/restaurant-ai-cases/
- 飲食店×AI活用事例10選!前年比120%に売上向上した理由は? | AI Front Trend, https://ai-front-trend.jp/ai-restaurants/
- 【AIレコメンドメニューとは?】ビジプリ飲食・飲食用語辞典, https://visipri.com/foodservice-dictionary/0001-AIRecommendMenu.php
- AIレコメンドとは? 顧客満足度を高める仕組みと企業の活用事例 | 大塚商会のERPナビ, https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/category/apparel/sp/solving-problems/archive/250625-01.html
- AIを活用したCRMとは?従来型との違いや導入ポイントを解説 – Salesforceブログ, https://www.salesforce.com/jp/blog/jp-ai-crm/
- サービス業の顧客管理をAIで効率化!飲食・小売・ホテルの事例と導入法を解説, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/service-industry-ai-crm/
- 「サクッとAI」でコーヒー豆の不良検知と品質保証を簡単に!デモ機の稼働テストを開始しました。, https://www.rosso-tokyo.co.jp/%E3%80%8C%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%83%E3%81%A8ai%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E8%B1%86%E3%81%AE%E4%B8%8D%E8%89%AF%E6%A4%9C%E7%9F%A5%E3%81%A8%E5%93%81%E8%B3%AA%E4%BF%9D%E8%A8%BC/
- コーヒー豆の不良検知による品質保証 – サクッとAI・クラウド, https://www.rosso-solution.com/ai-1/
- ProfilePrint – AI Ingredient Quality Platform, https://nomjim.co.jp/files/libs/2732/202505200958144134.pdf
- カフェインの過剰摂取について – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem/caffeine.html
- 喫茶店・カフェ経営業者1180社の経営実態調査 – 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/industry/mezp1lba5k/
- 喫茶店(カフェ・コーヒーショップ)(2024年版) | 市場調査データ – J-Net21, https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/restaurant/cons-kissaten2.html
- Ⅱ.喫茶店の「いま」 – 総務省統計局, https://www.stat.go.jp/data/e-census/topics/pdf/topics95_2.pdf
- 観光地カフェ経営者必見!STP分析から読み解く、集客力を高める戦略 – note, https://note.com/eyar/n/n92a4623de19d
- 日本のインスタントコーヒー市場規模、動向、2033年予測, https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-instant-coffee-market
- 日本のコーヒー豆市場規模は2033年までに34億米ドルに達すると予測|年平均成長率5.73%, https://newscast.jp/news/1559937
- 日本のコーヒー市場調査、規模、シェア、傾向、予測2037年, https://www.researchnester.jp/industry-reports/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E5%B8%82%E5%A0%B4/85
- IR情報 | スターバックス コーヒー ジャパン, https://www.starbucks.co.jp/ir/
- 業績・財務ハイライト | スターバックス コーヒー ジャパン, https://www.starbucks.co.jp/ir/highlight/
- (株)ドトール・日レスホールディングス【3087】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3087.T
- IR情報 | 当社について|株式会社ドトールコーヒー, https://www.doutor.co.jp/about_us/ir/
- 株式会社ドトールコーヒー, https://www.doutor.co.jp/
- 株式会社ドトール・日レスホールディングス|IR情報, https://www.dnh.co.jp/html/ir01.html
- 株式会社ドトール・日レスホールディングス, https://www.dnh.co.jp/
- (株)コメダホールディングス【3543】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3543.T
- コメダホールディングス(コメダ)【3543】株の基本情報 – 株探(かぶたん), https://kabutan.jp/stock/?code=3543
- コメダホールディングス【3543】のIR資料 – キタイシホン, https://kitaishihon.com/company/3543/ir-library
- 統計資料 – 全日本コーヒー協会, https://coffee.ajca.or.jp/data/
- 全日本コーヒー協会, https://coffee.ajca.or.jp/
- 全協海外情報488号 2021年2月18日 全日本コーヒー協会, https://ajcra.org/news/member/202102/210218.pdf
- 世界のコーヒー市場の動向 – 名古屋文理大学, https://www.nagoya-bunri.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/2006_05.pdf
- 世界のコーヒーの生産量|コーヒー大辞典 | 味の素AGF株式会社, https://agf.ajinomoto.co.jp/enjoy/cyclopedia/zatugaku/
- コーヒー消費0.4%減、ホット需要減と生豆高騰で – 食品産業新聞社, https://www.ssnp.co.jp/beverage/604275/
- コーヒー統計資料, https://www.coffee-jiten.com/category/knowledge/statistics/
- 料飲店、喫茶などの国内外食市場を調査 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25069
- カフェ業界 最新事情 2025年版|Sota Pro – note, https://note.com/sotapro/n/n7309f125d8b2
- 漫画喫茶・インターネットカフェのマーケティング戦略とは?新たな時代の勝ち筋を見つける, https://yui-marke.com/article/2284/
- 月次情報 – 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES, https://www.food-and-life.co.jp/investor/monthly-information/
- ドトール・日レスHD 決算/2月期売上高10.8%増でコロナ前超え | 流通ニュース, https://www.ryutsuu.biz/accounts/q041278.html
- 「コメダ珈琲」のコメダHD、既存店売上高の成長は続くも成長率が鈍化(2019年10月) 注目小売店月次実績シリーズ | LIMO | くらしとお金の経済メディア, https://limo.media/articles/-/14396?page=1
- 既存店売上高は対前年同月比112.9%と高い伸び(2020年2月) 注目小売店月次実績シリーズ | LIMO | くらしとお金の経済メディア, https://limo.media/articles/-/16416?page=1
- 2020年の飲食店売上に占めるデリバリー比率は倍増の6.5%に【NPD Japan調べ】, https://foodfun.jp/archives/12671
- 卵だけじゃない… 2025年は「朝のコーヒー」もますます高くなる見込み | Business Insider Japan, https://www.businessinsider.jp/article/2502-coffee-prices-food-inflation-climate-change-eggs/
- 飲料・カフェの「エシカル通信簿」発表 企業の消費者教育に期待, https://www.jc-press.com/?p=4615
- 2022年のエシカル消費は 約8兆円, https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202412_03.pdf
- モバイルオーダーの普及率はどれくらい?自店舗で導入すべきか判断する3つのポイント – Bizcan, https://bizcan.jp/column/mobileorder-fukyuritsu/
- バリスタの年収について解説!仕事の形態による給料の差とは? – 神戸製菓専門学校, https://www.kobeseika.ac.jp/contents/cafe-staff/varistor-income/
- カフェ満足度調査、スターバックスが首位 「楽しさ」等の付加価値でファン化をけん引, https://life.oricon.co.jp/news/2165865/
- カフェ, https://www.jpc-net.jp/research/jcsi/resultlist/assets/pdf/72a29fb688ac0c2d6a15d567f8e0f489.pdf
- 顧客満足度が最も高いカフェ 2年ぶりに1位を獲得したのは?:約2万5000人に聞く – ITmedia, https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2207/29/news070.html
- 喫茶店営業のみなさまへ – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/000841306.pdf
- 【2024年 購買行動調査】Z世代約1,500人に聞いた!「計画購買」は日用品・スキンケア化粧品・本で多い? | CCCMKホールディングス株式会社, https://www.cccbiz.jp/columns/research4
- よくわかる! 地域が広がる 認知症カフェ, https://www.mhlw.go.jp/content/001241168.pdf
- 飲食店でAIを活用するとどう変わる?具体例やツールの導入方法を解説 | マネーフォワード クラウド, https://biz.moneyforward.com/restaurant/basic/2006/
- コメダホールディングス, https://www.komeda-holdings.co.jp/
- 株式会社良品計画, https://ryohin-keikaku.jp/
- コメダ珈琲店, https://www.komeda.co.jp/
- タリーズコーヒー: Taste The Difference | TULLY’S COFFEE, https://www.tullys.co.jp/
- BLUE BOTTLE COFFEE: ブルーボトルコーヒー オンラインストア …, https://store.bluebottlecoffee.jp/
- セブン‐イレブン, https://www.sej.co.jp/
- LAWSON|ローソン公式サイト, https://www.lawson.co.jp/
- ファミリーマート公式ウェブサイト, https://www.family.co.jp/
- CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社, https://www.ccc.co.jp/