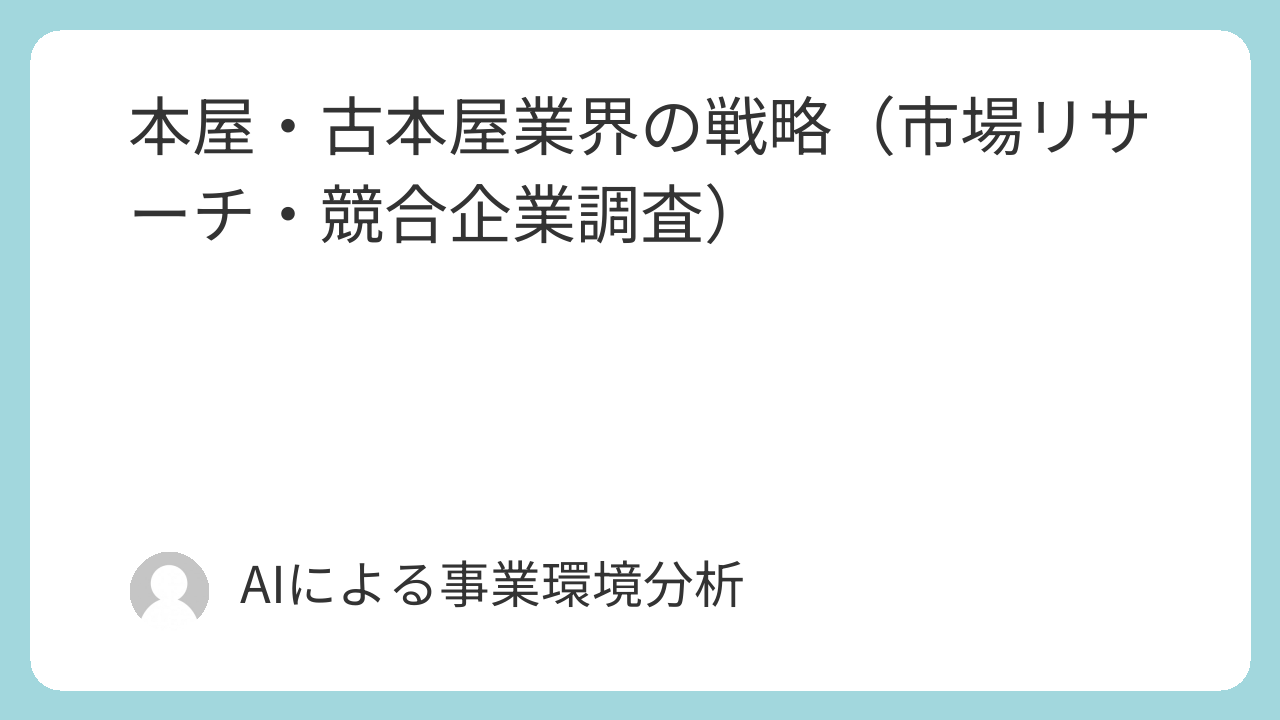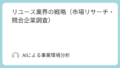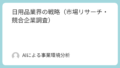知の再定義:デジタル・C2C時代を生き抜く書店ビジネスの生存・成長戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートは、日本の本屋・古本屋業界が直面する構造的課題を多角的に分析し、持続的な成長を実現するための事業戦略を提言することを目的とする。調査対象は、新刊書店(大型チェーン、独立系)、古本屋(店舗型、EC型)、および主要な競合となる電子書籍プラットフォーム、ECサイト(Amazon等)、C2Cフリマアプリ(メルカリ等)市場である。当業界は、①電子書籍やECプラットフォームの圧倒的な利便性、②C2Cフリマアプリの急速な浸透、③動画サービス等との可処分時間の奪い合いという三重の逆風にさらされ、単なる「書籍の小売」という旧来のビジネスモデルでは存続が困難な岐路に立たされている。
分析の結果、業界の将来は、以下の3つの転換を遂行できるか否かにかかっているという結論に至った。第一に、事業の核を「モノ(書籍)」の販売から「コト(体験・コミュニティ)」の提供へとシフトすること。第二に、リアル店舗という物理的空間の価値を再定義し、デジタル技術と融合させた独自の顧客体験を創出すること。第三に、高い返本率や画一的な配本といった課題を抱える伝統的なサプライチェーンから部分的に脱却し、収益構造を改善することである。今後の勝敗を分けるのは、もはや「何を売るか」ではなく、「顧客とどのように関わり、どのような場を提供できるか」という点に集約される。
以上の分析に基づき、取るべき事業戦略として、以下の4点を主要な推奨事項として提言する。
- 超・体験特化型への転換: 店舗を「本を売る場所」から「知的好奇心を満たす体験空間」へと再定義する。カフェや雑貨、イベントスペースを併設し、専門性の高い選書や独自の企画を通じて滞在価値を高め、書籍販売以外の収益源を組み合わせた複合的な収益モデルを構築する。
- OMO(Online Merges with Offline)戦略の推進: リアル店舗の強みである「発見性(セレンディピティ)」と、デジタル(自社アプリ、AIレコメンデーション)の強みである「利便性・パーソナライズ」を融合させる。オンラインでの在庫確認・取置サービスや、店舗と連動した顧客ロイヤルティプログラムを通じて、顧客エンゲージメントを最大化する。
- ニッチ・コミュニティ戦略の採用: 特定のジャンル(例:ビジネス、アート、フェミニズム)や特定の価値観に特化する。熱量の高い顧客コミュニティのハブ(拠点)としての機能を担い、イベントやワークショップを定期開催することで、価格競争から脱却し、代替不可能なブランド価値を確立する。
- サプライチェーン改革への参画: 出版社との「直取引」や、リスクを取った「買切」モデルを限定的に導入する。これにより、約22%という低い粗利益率の改善を図るとともに、取次の配本に依存しない主体的かつ魅力的な棚作りを実現する自由度を確保する。
第2章:市場概観(Market Overview)
市場規模の全体像と構造変化
本屋・古本屋業界を理解する上で、まず書籍に関連する各市場の規模と構造変化を俯瞰することが不可欠である。全国出版協会・出版科学研究所の調査によると、紙と電子を合算した日本の出版市場全体は、2023年に1兆5,963億円(前年比2.1%減)となり、減少傾向が続いている 1。2024年も1兆5,716億円(前年比1.5%減)と3年連続のマイナス成長となった 3。
この市場縮小の内実を見ると、劇的な構造変化が進行していることがわかる。2024年において、書籍・雑誌を合わせた「紙」の出版市場は1兆56億円(前年比5.2%減)と大幅な縮小が続く一方、「電子」出版市場は5,660億円(前年比5.8%増)と成長を維持している 4。市場全体に占める電子出版のシェアは36%に達し、10年連続で拡大している 6。
特筆すべきは、電子出版市場の成長を牽引しているのが「電子コミック」である点だ。2023年時点で電子出版市場5,351億円のうち、電子コミックが4,830億円と全体の90.3%を占めている 1。これは、読書市場が単一ではなく、「マンガ読者のデジタルシフト」と「その他書籍(文字もの)の緩やかなデジタルシフト」という全く異なる様相を呈していることを示唆している。
一方で、古本(リユース)市場も重要な構成要素である。環境省の調査によれば、消費者需要をベースとした書籍・雑誌カテゴリのリユース市場規模は2024年推計で約787億円となっている 7。この数値には、ブックオフのようなBtoC(Business-to-Consumer)事業者と、メルカリに代表されるC2C(Consumer-to-Consumer)プラットフォームの両方が含まれる。経済産業省の調査では、C2C-EC市場全体が2022年時点で2兆3,630億円(前年比6.8%増)という巨大市場を形成しており 8、書籍もその中で活発に取引されている。これは、古本事業者が消費者を「顧客」としてだけでなく、仕入先としてもC2Cプラットフォームと直接競合している厳しい現実を浮き彫りにしている。
| 市場セグメント | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2029年 (予測) | CAGR (2019-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙の出版物 (書籍・雑誌) | 12,360 | 12,237 | 12,080 | 11,292 | 10,612 | 10,056 | – | 約 -4.1% |
| 電子出版物 | 3,072 | 3,931 | 4,662 | 5,013 | 5,351 | 5,660 | 約 8,000 (※1) | 約 +13.0% |
| (内) 電子コミック | 2,593 | 3,420 | 4,114 | 4,479 | 4,830 | 5,122 | – | 約 +14.6% |
| (内) 電子書籍・雑誌 | 479 | 511 | 548 | 534 | 521 | 538 | – | 約 +2.3% |
| リユース市場 (書籍・雑誌) | – | – | 807 (※2) | – | – | 787 (※3) | – | – |
| C2C-EC市場 (全体参考値) | 17,407 | 19,586 | 22,121 | 23,630 | – | – | – | 約 +10.8% (※4) |
表2.1: 主要市場規模の推移と予測(単位:億円)
出典: 出版科学研究所 1, インプレス総合研究所 9, 環境省 7, 経済産業省 8 のデータを基に作成。
※1: インプレス総合研究所の2028年度予測値8,000億円、2029年度予測値8,000億円弱を参考値として記載 9。
※2: 令和3年度推計値。※3: 令和6年度推計値。※4: 2019-2022年のCAGR。
書店数の減少トレンドと店舗面積の推移
市場の構造変化は、リアル書店の経営環境を直撃している。書店調査会社アルメディアによると、全国の書店数は2012年5月時点で14,696店だったが 13、2020年5月には11,024店にまで減少 14。日本出版インフラセンター書店マスタ管理センターの調査では、2025年8月時点で10,250店(売場面積ありは7,550店)となっており、前年同月比で459店減少するなど、減少トレンドに歯止めはかかっていない 16。この20年間で書店数はほぼ半減しており 17、これは単なる店舗数の減少ではなく、地域社会における「知のインフラ」そのものの喪失を意味する深刻な事態である。
一方で、書店一店舗あたりの平均売場面積は増加傾向にある 17。これは、地域に根差した小規模な個人書店の廃業が相次ぐ一方で、郊外型の大型チェーン店や、蔦屋書店に代表される複合型書店が新規出店・改装を進めていることを示している。業界内での「大型化・複合化」と「小規模店の淘汰」という二極化が進行している。
業界の主要KPIベンチマーク分析
書店ビジネスの収益構造は、他の小売業と比較して構造的な脆弱性を抱えている。主要な経営指標(KPI)を分析すると、その実態が明らかになる。
| KPI項目 | ベンチマーク数値/傾向 | 経営上の課題(So What?) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 粗利益率 (新刊) | 約 22% | 一般小売業の平均(約30%超)を大幅に下回り、利益創出が極めて困難な構造。再販制度による硬直的な価格体系が主因。 | 18 |
| 返本率 (新刊) | 書籍: 約 35%超 雑誌: 約 40%超 | 高水準で推移。委託販売制度の下で非効率な配本が行われ、機会損失と返送コストの二重の負担が発生。経営を直接的に圧迫。 | 21 |
| 在庫回転日数 | 4ヶ月~10ヶ月 (年間回転率 1.2~3.0回) | 他の小売業に比べ極めて長い。キャッシュフローを悪化させ、限られた店舗スペースを非効率に占有。多品種少量販売の宿命でもある。 | 24 |
| 坪当たり売上高 (月商) | 長期的に低下傾向 (例: 2009年 18.5万円 → 2019年 13.7万円) | 「薄利多売」のビジネスモデルが崩壊し、「薄利少売」状態に陥っている。店舗維持コストを売上でカバーすることが年々困難に。 | 26 |
| 古本買取マージン | ブックオフ: 買取平均70円/冊 メルカリ: ブックオフの約2.5倍で売却可能 | C2Cプラットフォームとの仕入れ(買取)競争が激化。安価な買取価格は顧客満足度を低下させ、仕入れ機会の損失に繋がる。 | 28 |
表2.2: 業界KPIベンチマーク分析
これらのKPIは、書店業界が抱える問題の根深さを示している。特に、低い粗利益率と高い返本率は、個々の書店の経営努力だけでは解決が困難な、業界全体の構造的問題である。この低収益構造こそが、書店が書籍販売以外の付加価値(体験、コミュニティなど)を模索し、新たな収益源を創出しなければならない根源的な理由である。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
本屋・古本屋業界は、社会や技術の大きな潮流から多大な影響を受けている。PESTLEフレームワークを用いてマクロ環境を分析することで、事業戦略が対応すべき外部要因を体系的に整理する。
政治(Politics)
- 再販売価格維持制度(再販制度)の見直し議論: 書籍・雑誌の定価販売を義務付けるこの制度は、独占禁止法の例外として長年維持されてきた。文化の多様性を守るという大義がある一方、価格競争を阻害し、書店の低い粗利率(約22%)に繋がる構造的要因となっている 18。公正取引委員会では定期的に見直しの議論がなされており 31、万が一制度が変更(一部または全部廃止)されれば、体力のある大手チェーンやECプラットフォームによる価格競争が激化し、中小書店は壊滅的な打撃を受けるリスクがある。
- 軽減税率: 現在、書籍・雑誌は消費税の軽減税率(8%)の対象外である。出版業界は「心の糧」として適用を求めているが、実現には至っていない 32。これにより、消費増税の局面では、食料品などと比較して消費者の価格負担感が増し、買い控えに繋がる可能性がある。
- 図書館との関係性: 図書館によるベストセラーの大量購入が書店の売上を圧迫しているとの指摘は根強い。一方で、著作者や出版社への経済的還元を目的とした「公共貸与権」の制度導入に関する議論は、日本では停滞している 33。図書館政策の動向は、書店の売上に間接的な影響を与え続ける。
経済(Economy)
- 個人消費の動向と可処分所得: 日本の個人消費は、物価上昇の影響もあり、総じて横ばい圏での推移が続いている 35。書籍は嗜好品の側面が強く、可処分所得が伸び悩む状況では、購入の優先順位が下がりやすい。
- インフレとコスト上昇: 製紙、印刷、輸送にかかるコストの上昇は、書籍の定価上昇圧力となる 37。再販制度下では書店が価格を柔軟に調整できないため、コスト上昇分は消費者に転嫁されやすく、これが需要減退を招くリスクをはらむ。
- 最低賃金の上昇: 全国的な最低賃金の引き上げは、アルバイト・パート労働力への依存度が高い書店経営にとって、人件費の増加という形で直接的なコスト圧力となる 38。低い利益率の中でこのコストを吸収する必要があり、店舗の省人化(セルフレジ導入など)や、採算の悪い店舗の閉鎖を加速させる要因となる。
社会(Society)
- 「本離れ」と可処分時間の奪い合い: 若年層を中心に、1か月の読書冊数が減少傾向にある 40。これは単に活字への関心が薄れたのではなく、YouTube、Netflix、TikTokといった動画サービス、SNS、スマートフォンゲームなど、より手軽で没入感の高いエンターテイメントとの「可処分時間」をめぐる熾烈な競争に敗れていることが本質的な原因である。
- タイパ(タイムパフォーマンス)重視の消費行動: Z世代を中心に、かけた時間に対する満足度や効果を最大化したいという「タイパ」意識が消費行動の基軸となっている 42。動画の倍速視聴、ショート動画の流行、結論を先に知る「ネタバレ消費」といった行動は、一定の時間を要する読書とは対極の価値観である。このトレンドは、ビジネス書の内容を10分で把握できる「flier」のような書籍要約サービスの需要を喚起している 44。
- SNSによるヒット創出: TikTokの書籍紹介コミュニティ「#BookTok」からベストセラーが生まれるなど、SNSでの個人の発信がヒットの起点となる現象が定着している 46。これは、出版社や書店主導のマーケティングの影響力が相対的に低下し、消費者の口コミや共感が購買を動かす大きな力となっていることを示している 49。
- 「推し活」消費の拡大: アイドル、アニメ、漫画のキャラクターなどを応援する「推し活」に関連する消費は巨大な市場を形成している 51。関連書籍や雑誌、写真集などは、ファンにとってコレクションの対象であり、熱心な消費が見込める分野となっている。
技術(Technology)
- デジタルデバイスの普及と高性能化: スマートフォンやタブレット端末の画面が高精細化・大型化したことで、専用リーダーがなくとも快適な電子書籍体験が可能になった 53。これが、特にフルカラーで表現される電子コミック市場の急拡大を支える技術的基盤となっている。
- 代替フォーマットの台頭: 「聴く読書」であるオーディオブック市場は、スマートフォンの普及とワイヤレスイヤホンの一般化を背景に、通勤中や家事をしながらの「ながら聴き」需要を取り込み、成長を続けている(2024年に260億円規模との予測) 54。これは、従来の読書とは異なる新たな需要層を開拓している。
- C2Cプラットフォームの利便性向上: メルカリなどのフリマアプリは、AIによる価格提案、匿名配送システムの整備、シンプルな出品プロセスなど、個人間取引のハードルを劇的に下げる技術革新を続けている 56。これにより、誰もが容易に古本の売り手となれる環境が整い、既存の古本屋の仕入れ・販売両面におけるビジネスモデルを根底から揺るがしている。
- レコメンデーションエンジンの進化: AmazonなどのECサイトでは、AIを活用し、個々のユーザーの購買履歴や閲覧行動を分析してパーソナライズされた商品を提案するレコメンデーションエンジンが高度化している 57。これは、リアル書店が提供する「偶然の出会い(セレンディピティ)」とは異なる、データ駆動型の新たな「本との出会い」の形を提示している。
法規制(Legal)
- 著作権法: 令和3年の法改正により、違法にアップロードされたと知りながら漫画や書籍などをダウンロードする行為が私的利用であっても違法となるなど、デジタルコンテンツの著作権保護が強化されている 59。これは、正規の電子書籍プラットフォームにとっては追い風となる。
- 古物営業法: 古本の買取・販売は古物営業法に基づき、公安委員会の許可が必要であり、取引時の本人確認が義務付けられている。近年の法改正で「主たる営業所」の届出が義務化されるなど、コンプライアンス遵守の重要性が高まっている 60。
環境(Environment)
- サステナビリティへの意識の高まり: 紙の生産や輸送、廃棄に伴う環境負荷(カーボンフットプリント)に対する社会的な関心が高まっている 61。適切に管理された森林からの木材を使用したFSC認証紙の採用など 63、環境に配慮した出版活動は、企業の社会的責任(CSR)として、またブランドイメージ向上の観点から重要性を増している。
- リユース・リサイクルの価値再評価: 古本事業は、不要になった資源を再利用する循環型経済の一翼を担うビジネスとして、サステナビリティの文脈で再評価される可能性がある。消費者の間での環境意識の高まりは、新品の購入から中古品の選択へと行動を促す一因となりうる。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
書店業界、特に新刊書店の収益性の低さは、業界を取り巻く厳しい競争環境に起因する。マイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いることで、その構造を解明する。
売り手の交渉力(出版社・取次):強い
伝統的に、出版業界のサプライチェーンは「出版社 → 取次 → 書店」という構造で成り立っており、売り手である出版社と、流通を寡占する大手取次(日本出版販売、トーハン)が強い力を持ってきた 65。再販売価格維持制度(書店が定価で販売する義務)と委託販売制度(書店が売れ残った本を返品できる制度)の組み合わせにより、書店は仕入れ価格(正味)や配本される書籍の種類・冊数に対してほとんど交渉力を持たない。しかし、出版不況は取次自身の経営をも圧迫しており 66、一部の先進的な出版社や書店は、取次を介さない「直取引」を模索している 68。この動きが拡大すれば、将来的には書店の交渉力が向上する可能性がある。
買い手の交渉力(消費者):非常に強い
書籍という商品は、基本的にどこで購入しても内容が同じ「コモディティ」である。そのため、買い手である消費者は、自身の価値基準に基づき購入チャネルを自由に選択できる極めて強い交渉力を持つ。価格を重視するなら中古品やC2Cフリマアプリ、利便性を求めるならAmazon、新たな発見や体験を求めるならリアル書店、といった具合である。あるチャネルから別のチャネルへ乗り換える際のスイッチングコストは実質的にゼロであり、書店は常に他チャネルとの厳しい比較と競争にさらされている。
新規参入の脅威:チャネルにより強弱が混在
リアル店舗への新規参入の脅威は「中程度」である。店舗物件の確保や在庫投資、取次との取引口座開設には一定の資本とノウハウが必要となる。しかし、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が「蔦屋書店」で展開したように、異業種の資本が「ライフスタイル提案」という新たなコンセプトを武器に市場に参入し、既存の業界地図を塗り替える事例は存在する 70。
一方、オンラインチャネルへの新規参入の脅威は「非常に高い」。ECサイトの構築や、メルカリのようなC2Cプラットフォームへの出品は個人でも容易に行えるため、参入障壁は極めて低い。事実上、無数のプレイヤーがオンライン上で書籍を販売しており、競争は飽和状態にある。
代替品の脅威:非常に高い
書店ビジネスにとっての代替品の脅威は、二つのレベルで存在する。第一に、読書体験そのものを代替する「直接的な代替品」である。これには電子書籍、オーディオブック、そして「flier」に代表される書籍要約サービスが含まれる 44。特に、月額定額制の読み放題サービス(例:Kindle Unlimited)は、書籍を「所有」するモデルから「利用(アクセス)」するモデルへと消費者の意識を転換させ、都度購入を基本とする書店のビジネスモデルを根底から脅かす。
第二に、より広範な「間接的な代替品」の存在である。これは、消費者の「可処分時間」を奪い合う、あらゆるエンターテイメントコンテンツを指す。NetflixやYouTubeの動画、SNS、スマートフォンゲームなどは、読書よりも手軽で即時的な満足感を提供する強力な競合である。書店は、本を売るだけでなく、これらの魅力的な代替品と顧客の時間獲得競争を繰り広げている。
業界内の競争:非常に激しい
業界内の競争は、複数の次元で激化している。
- チャネル間競争: 「リアル書店 vs EC(Amazon) vs C2C(メルカリ)」の三つ巴の戦いが最も熾烈である。利便性と品揃えで圧倒するAmazon 71、価格の安さと「売る」楽しみを提供するメルカリ 72 に対し、リアル書店は「体験価値」や「セレンディピティ(偶然の出会い)」といった独自の価値で差別化を図るほかない。
- 業態間競争: リアル書店内でも、ナショナルチェーン(紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店など)が持つ規模と総合力、独立系書店が持つ専門性やコミュニティ機能、ブックオフのような古本チェーンが持つ価格訴求力といった、異なる強みを持つ業態が顧客を奪い合っている。
- 価格競争: 「新品(定価)」「中古(変動価格)」「C2C(個人設定価格)」の間で、常に価格が比較される環境にある。特にC2Cプラットフォームの普及は、中古市場全体の価格形成に大きな影響を与え、古本事業者の収益性を圧迫している。
| 競争要因 | 圧力の強さ | 主な要因と戦略的示唆(So What?) |
|---|---|---|
| 売り手の交渉力 | 強い | ・再販制度・委託販売制度と寡占的な流通構造。 ・書店の利益率が構造的に低く抑えられている。 → 直取引など、伝統的流通からの部分的脱却が収益改善の鍵。 |
| 買い手の交渉力 | 非常に強い | ・書籍のコモディティ化とチャネル選択の自由度。 ・スイッチングコストがゼロ。 → 価格や利便性以外の「体験価値」「専門性」での差別化が必須。 |
| 新規参入の脅威 | 高い | ・オンラインでの参入障壁は皆無。 ・異業種が新たなコンセプトでリアル店舗市場に参入。 → 既存の枠組みにとらわれない独自のポジショニング確立が急務。 |
| 代替品の脅威 | 非常に高い | ・電子書籍、オーディオブック、要約サービスなど直接的代替品が多数。 ・動画、SNSなど「可処分時間」を奪うあらゆるエンタメが競合。 → 「本を読む」行為自体の価値を再提案する必要がある。 |
| 業界内の競争 | 非常に激しい | ・チャネル間、業態間、価格の各次元で競争が激化。 ・特にAmazon、メルカリはビジネスモデルが異なり、非対称な競争を強いられる。 → 競合が提供できない独自の価値(空間、コミュニティ、選書)に集中すべき。 |
表4.1: ファイブフォース分析サマリー
この分析から導き出される戦略的結論は明確である。書店業界は、5つの競争要因すべてが収益性を下げる方向に強く作用する、極めて魅力度の低い市場構造にある。価格や利便性といった土俵で戦う限り、巨大なプラットフォーマーに勝つことは不可能である。したがって、生き残りのための戦略は、これらの競争圧力が比較的及びにくい「体験価値」「専門性」「コミュニティ」といった領域に活路を見出すことに他ならない。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析(新刊)
日本の新刊書籍のサプライチェーンは、「出版社 → 取次 → 書店 → 消費者」という伝統的な流通構造によって特徴づけられる。この構造の中核をなすのが、委託販売制度と再販売価格維持制度(再販制度)である。
- 委託販売制度: 出版社が取次を通じて書店に書籍の販売を「委託」する制度。書店は売れ残った書籍を一定期間内であれば出版社に返品できる。
- 再販制度: 出版社が書籍の定価を決定し、書店など小売業者がその定価で販売することを義務付ける制度。
これらの制度は、表裏一体の関係にあり、業界に以下のメリットとデメリットをもたらしてきた。
メリット:
- 文化的多様性の維持: 書店は在庫リスクを負わずに多種多様な書籍を店頭に並べることができる。これにより、発行部数の少ない専門書や学術書なども消費者の目に触れる機会が確保され、文化の多様性が維持される 73。
- 全国均一の価格とアクセス: 消費者は日本全国どこでも同じ価格で書籍を購入できる 30。
デメリット:
- 高い返本率と経営圧迫: 返品が前提となっているため、出版社は需要予測以上に多くの書籍を印刷・出荷する傾向がある。結果として、書籍で約35%、雑誌で約40%という高い返本率が常態化している 21。返品にかかる物流コストや再断裁のコストは、出版社、取次、そして(返送料を負担する場合がある)書店の経営を圧迫する大きな要因となっている。
- 画一的な配本と機会損失: 大手取次が各書店の過去の販売実績などに基づいて自動的に書籍を配本する「見計らい配本」が主流である。これにより、各書店の特色や地域性が反映されにくく、画一的な品揃えになりがちである。また、「売りたい本が入荷しない」「売れるはずのない本が送られてくる」といった機会損失や非効率が発生する。
- 書店の主体性の欠如: 書店は自らの意思で品揃えを決定する自由度が低く、棚作りの専門性や独自性を発揮しにくい。これにより、書店員のモチベーション低下や、他店との差別化困難といった問題が生じている。
この伝統的サプライチェーンの限界に対し、近年、新たな流通形態が模索されている。
- 出版社との「直取引」: トランスビューやミシマ社といった出版社が先駆的に行ってきたモデル 68。取次を介さず、出版社と書店が直接取引を行う。書店はより高い利益率(マージン)を確保できる一方、返品不可の「買切」が条件となることが多く、在庫リスクを負うことになる。BookCellarのような受発注プラットフォームも登場し、直取引を支援するインフラが整いつつある 76。
- 書店の「買切」モデル: 紀伊國屋書店とCCC、日販が設立した新会社「ブックセラーズ&カンパニー」は、書店と出版社の直取引を促進し、買切を基本とすることで、書店の利益率向上と出版社の返品率低減を目指している 69。これは、業界構造の変革に向けた大きな動きとして注目される。
- 出版社の小売参入: 日本出版販売(日販)が運営する「文喫」のように、出版流通業者が自ら小売に乗り出し、入場料モデルといった新たなビジネスモデルを実験するケースも現れている 77。
サプライチェーン分析(古本)
古本ビジネスのサプライチェーンは、新刊とは大きく異なる。
- 伝統的な古本屋: 「消費者(売却)→ 古本屋(買取・査定)→ 古本屋(商品化・陳列)→ 消費者(購入)」という流れ。ビジネスの根幹は「仕入れ(買取)」であり、査定能力と、いかに多くの良質な古本を消費者から買い取れるかが競争力の源泉となる。
- C2Cフリマアプリ: 「消費者(出品)→(プラットフォーム)→ 消費者(購入)」という流れで、個人間で直接売買が行われる。これにより、従来は古本屋の仕入れ対象であった書籍が、直接C2C市場に流出するようになった。
C2Cフリマの台頭は、古本屋にとって深刻な「仕入れ競争」を引き起こしている。消費者は、手間を惜しまなければ古本屋の買取価格よりも高く売却できるメルカリを選ぶ傾向がある 29。これに対し、古本屋は「持ち込むだけ」という手軽さや、一度に大量に処分できる利便性で対抗しているが、仕入れ競争はますます激化している。
バリューチェーン分析
書店ビジネスの価値創造プロセス(バリューチェーン)を分析すると、価値の源泉がどこにシフトしているかが明確になる。
書店ビジネスのバリューチェーン:
- 仕入/買取・査定: (新刊)取次からの配本、(古本)消費者からの買取と価格査定。
- 配本/在庫管理: 店舗への書籍の割り振り、在庫の管理、返本作業。
- 選書・棚作り・陳列: 書籍を選び、テーマに沿って棚を構成し、顧客にアピールする形で陳列する。
- 接客・販売: 顧客へのレコメンド、問い合わせ対応、レジ業務。
- 空間プロデュース・イベント企画: カフェや雑貨の併設、居心地の良い空間の設計、著者トークショーや読書会などのイベント企画・運営。
かつて書店の価値は、主に「④接客・販売」、すなわち「本を売る」という機能にあった。しかし、ECサイトが利便性と品揃えでこの機能を凌駕した現在、価値の源泉は明らかに他のプロセスへとシフトしている。
価値の源泉のシフト:
- 「③選書・棚作り・陳列」へ: どのような本を選び、どのような文脈で顧客に提示するかという「編集能力」が、書店の最も重要な競争優位の源泉となっている。特定のテーマに沿った棚作りや、書店員の個性的なPOPは、アルゴリズムによるレコメンデーションでは代替できない「思いがけない発見(セレンディピティ)」を生み出す。
- 「⑤空間プロデュース・イベント企画」へ: 蔦屋書店が示すように、書店は単なる販売の場から、人々が時間を過ごし、文化的な刺激を受け、交流する「場」へと進化している。居心地の良い空間、魅力的なカフェ、知的好奇心を刺激するイベントは、それ自体が顧客を惹きつける強力な価値となる。書籍販売は、この「体験」の一部として位置づけられる。
So What?: このバリューチェーンの変化は、書店がリソースをどこに重点的に投下すべきかを示唆している。レジ業務や単純な在庫管理といったオペレーション(④、②の一部)は、ITやAIを活用して徹底的に効率化・省人化すべき領域である。一方で、人間ならではの創造性や専門性が求められる「選書・棚作り(③)」と「空間プロデュース・イベント企画(⑤)」にこそ、人材と資本を集中投下し、他社が模倣できない独自の価値を創造していく必要がある。
第6章:顧客需要の特性分析
デジタル化とC2Cの浸透により、消費者の書籍購入行動は多様化・複雑化している。効果的な戦略を策定するためには、主要な顧客セグメントを特定し、それぞれのニーズと購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)を深く理解する必要がある。
主要な顧客セグメント分析
現代の書籍購入者は、そのニーズと利用チャネルによって、大きく4つのセグメントに分類できる。
- 価格・利便性重視層:
- 特徴: 書籍を最も安く、または最も手軽に入手することを最優先する層。
- 主要チャネル: Amazon、楽天ブックス(新品・中古)、メルカリ、ラクマ(C2C)、電子書籍ストアのセールや読み放題サービス。
- ニーズ/課題: 欲しい本が明確で、探索コストや移動時間をかけたくない。少しでも安く購入したい。物理的な保管スペースを節約したい(電子書籍)。
- KBF: 価格の安さ、配送スピード、ワンクリックで購入できる手軽さ、品揃えの豊富さ。
- 体験・空間重視層:
- 特徴: 書店で過ごす時間そのものに価値を感じ、知的な刺激や居心地の良さを求める層。
- 主要チャネル: 蔦屋書店などの大型複合書店、カフェ併設の書店、デザイン性の高い書店。
- ニーズ/課題: 目的の本を探すだけでなく、リラックスできる空間で時間を過ごしたい。コーヒーを飲みながら本を選びたい。本以外の雑貨やカルチャーにも触れたい。
- KBF: 空間のデザイン性・快適さ、カフェやラウンジの質、書籍以外のライフスタイル商品の品揃え、イベントの魅力。
- 専門性・発見重視層:
- 特徴: 特定のジャンルへの深い知見を求める、あるいは自分の知らない本との偶然の出会い(セレンディピティ)を期待する層。
- 主要チャネル: 特定のジャンルに特化した専門書店、店主の個性が光る独立系書店。
- ニーズ/課題: 大手書店やオンラインでは見つけられない専門書やニッチな本を探している。信頼できるキュレーター(書店員)によるレコメンデーションを求めている。自分の興味の幅を広げたい。
- KBF: 書店員(店主)の専門的な選書能力、独自の棚作り、ニッチな品揃え、著者トークショーや読書会などのコミュニティ活動。
- 売却目的層:
- 特徴: 読み終えた本を売却し、金銭的対価や次の本の購入資金を得ることを主目的とする層。
- 主要チャネル: ブックオフなどの古本屋(店舗・宅配買取)、メルカリ、ラクマ(C2C)。
- ニーズ/課題: できるだけ高く売りたい。手間をかけずに売りたい。すぐに現金化したい。
- KBF: 買取価格の高さ(メルカリ)、処分の手軽さ・即時性(ブックオフ)。この二つのKBFはトレードオフの関係にあることが多い。
リアル書店への来店動機
価格と利便性でAmazonやメルカリが圧倒的優位に立つ中で、顧客はなぜわざわざリアル書店(新刊・古本)に足を運ぶのか。その動機は、オンラインでは満たされない特定の価値への希求にある。
- セレンディピティ(偶然の出会い)の価値: リアル書店の最大の価値は、目的の本を探している過程や、何気なく棚を眺めている時に、予期せぬ本と出会う「セレンディピティ」にある 79。これは、自分の興味関心に基づいて最適化されたECサイトのレコメンデーションとは異なり、自分の認知の範囲外にある未知の領域へと知的好奇心を広げてくれる体験である 81。棚に並んだ背表紙を一覧する行為そのものが、現在のトレンドや世の中の関心事を俯瞰的に把握する機会を提供する 82。
- 「モノ」としての本の魅力: 装丁の美しさ、紙の手触り、インクの匂いなど、物理的な「モノ」としての本が持つ五感に訴える魅力は、リアル書店でしか体験できない 82。特にデザイン書や写真集、絵本などは、実際に手に取ってその質感を確かめたいというニーズが強い。「ジャケ買い」という衝動的な購買行動は、この物理的魅力とセレンディピティが組み合わさって生まれる。
- 空間体験と時間の消費: 顧客は単に本を買いに来るのではなく、書店という空間で「時間を過ごす」ことを目的としている 83。静かで知的な雰囲気に浸りながら本を選ぶ行為は、一種の娯楽やリフレッシュとなっている。特にカフェ併設の書店では、購入前の本を試し読みしながらくつろぐといった、デジタルにはない豊かな時間体験を提供している。
- 信頼できるキュレーターとしての書店員: 専門知識を持つ書店員からの推薦や、熱意のこもった手書きのPOPは、アルゴリズムにはない「人の温かみ」と「信頼性」を持つ。顧客は、書店員を自分の知らない世界へ導いてくれる水先案内人として信頼し、その提案に価値を見出している 84。
So What?: リアル書店が生き残るためには、「価格・利便性重視層」を追いかけるべきではない。彼らはECとC2Cの顧客である。リアル書店がターゲットとすべきは、「体験・空間重視層」と「専門性・発見重視層」である。戦略の全ての要素は、「セレンディピティの最大化」「空間価値の向上」「キュレーション能力の強化」という3つの方向に収斂されなければならない。リアル店舗の家賃や人件費は、単なるコストではなく、これらの価値を提供するための「投資」として再定義される必要がある。
第7章:業界の内部環境分析
外部環境の厳しさに加え、書店業界は内部にも構造的な課題を抱えている。企業の競争優位の源泉を分析するVRIOフレームワーク、人材動向、そして低い生産性という観点から内部環境を評価する。
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉は何か?
VRIO分析は、企業の経営資源やケイパビリティが「Value(価値)」「Rarity(希少性)」「Inimitability(模倣困難性)」「Organization(組織)」の4つの観点から持続的な競争優位の源泉となりうるかを評価するフレームワークである 85。
| 経営資源/ケイパビリティ | V (価値) | R (希少性) | I (模倣困難性) | O (組織) | 競争優位性 | 戦略的示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一等地の「立地」 | Yes | Yes | No | Yes | 一時的競争優位 | 駅前などの好立地は集客に価値があるが、家賃負担が重く、競合も同様の立地を狙うため模倣は可能。立地だけでは持続的優位には繋がらない。 |
| 大手チェーンの「ブランド・信頼」 | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 | 長年培ったブランドは顧客の安心感に繋がる。しかし、ブランドイメージが画一的だと、個性を求める顧客層には響かない可能性がある。 |
| 書店員の「専門的な選書能力」 | Yes | Yes | Yes | No/Yes | 宝の持ち腐れ or 持続的競争優位 | 特定ジャンルの専門知識を持つ書店員の選書は極めて価値が高く、模倣困難。しかし、その能力を評価し、権限を与え、組織として活かす仕組みがなければ「個人のスキル」で終わり、競争優位にならない。 |
| 熱心なファンとの「顧客コミュニティ」 | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 | 独立系書店などが築く顧客との強い絆やコミュニティは、時間と信頼の蓄積が必要であり、他社が容易に模倣できない強力な参入障壁となる。 |
| 独自の「仕入れルート」(希少古書など) | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 | 古書市場における独自の仕入れネットワークや鑑定眼は、他にはない品揃えを実現し、価格競争から脱却できる源泉となる。 |
分析の要点:
デジタル時代において、単なる「立地」や「規模」といった物理的な経営資源の価値は相対的に低下している。一方で、「書店員の専門性」や「顧客コミュニティ」といった、模倣が困難な無形のケイパビリティこそが、持続的な競争優位の源泉となりうる。しかし、VRIO分析が示す最も重要な点は、「O(組織)」の要素である。優れた選書能力を持つ人材がいても、組織がその能力を正当に評価し、裁量権を与え、顧客に価値として届けられる仕組み(イベント企画、SNS発信など)を構築していなければ、その能力は「宝の持ち腐れ」となる。多くの従来型書店がこの課題に直面している。
人材動向
- 求められるスキルセットの変化: 書店員に求められるスキルは、大きく変化している。かつては、レジ打ち、返品作業、棚の整理といったオペレーション能力が中心であった。しかし現在では、以下のような専門的・創造的なスキルが強く求められている。
- 選書・棚作り能力: 顧客の潜在的なニーズを読み取り、知的好奇心を刺激するテーマで棚を編集するキュレーション能力 84。
- イベント企画力: 著者トークショー、読書会、ワークショップなどを企画・運営し、店舗をコミュニティハブへと変えるプロデュース能力 87。
- デジタルマーケティング知識: SNS(X, Instagramなど)を活用して店の魅力や入荷情報を発信し、オンラインの顧客をリアル店舗へ誘導する能力。
- コミュニケーション能力: 顧客との対話を通じて信頼関係を築き、ファンを育てる能力 84。
- 賃金水準と労働環境: 書店業界の従業員の賃金は、小売・サービス業の中でも決して高い水準ではない 88。正社員の平均年収は地域や企業規模によるが、専門性が求められる一方で、それに見合った待遇が提供されにくい構造がある。これが、優秀な人材の獲得・定着を困難にする一因となっている。また、大量の本を扱うため、立ち仕事や力仕事も多く、一定の体力が求められる 89。
労働生産性・収益性
- 低い利益率の構造的要因: 第2章で示した通り、約22%という低い粗利益率が業界全体の収益性を根本的に規定している 91。この低いマージンの中から、店舗賃料、人件費、水道光熱費、さらにはキャッシュレス決済手数料といった販管費を捻出しなければならず、営業利益を確保することが極めて困難なビジネスモデルである。
- 生産性向上の可能性と限界:
- 可能性: セルフレジの導入、ICタグを活用した在庫管理・棚卸作業の効率化、AIによる需要予測に基づいた発注・返本業務の自動化など、店舗オペレーションの生産性を向上させるための技術的手段は存在する 92。これらは、単純作業にかかる人件費を削減し、スタッフがより付加価値の高い業務(選書、接客、イベント企画など)に集中するための時間を生み出す上で有効である。
- 限界: しかし、これらのオペレーション改善は、あくまで「コスト削減」の域を出ない。根本的な低収益構造、すなわち低い粗利益率そのものを改善するものではない。したがって、生産性向上努力には限界があり、それだけで事業の持続可能性を確保することは難しい。
So What?: 内部環境分析は、書店ビジネスが「人で勝つ」ビジネスモデルへの転換を迫られていることを示している。VRIO分析で明らかになった競争優位の源泉は、いずれも「人」に依存するケイパビリティである。しかし、現状の労働環境や待遇では、そうした高度なスキルを持つ人材を惹きつけ、育成し、定着させることは容易ではない。生産性向上のためのテクノロジー導入は、単なるコスト削減策としてではなく、スタッフを単純作業から解放し、創造的な業務に集中させるための戦略的投資として位置づけられるべきである。
第8章:AIの影響とインパクト
人工知能(AI)は、書店・古本屋業界のあらゆる側面に変革をもたらす潜在力を持つ。その影響は、顧客体験の向上、業務プロセスの効率化から、市場構造そのものの変化、そして書店員の役割の再定義にまで及ぶ。
顧客体験へのインパクト
- 高度な「選書レコメンデーション」とリアル店舗の融合:
AIは、顧客の過去の購買履歴、閲覧履歴、さらにはアプリ上での評価などを分析し、極めて精度の高いパーソナライズされた書籍推薦を可能にする。このデジタルの強みをリアル店舗の体験と融合させることで、新たな価値が生まれる。- パーソナライズ棚: 書店アプリと連携し、顧客が来店すると、その顧客の好みに合わせた「あなただけのおすすめ棚」がアプリ上に表示され、店内での位置が示される。
- AIアバター・チャットボットによる接客: 店頭に設置されたサイネージや顧客のスマートフォンを通じて、AI書店員が対話形式で本を推薦する。KADOKAWAが展開する「AI書店員ダ・ヴィンチさん」は、利用者の感情や興味に基づいて本を推薦する実証実験を行っている 93。また、freeeが運営する「透明書店」では、ChatGPTを活用したAI副店長「くらげ」が接客を行う 95。これにより、書店員が多忙な時間帯でも、顧客は気軽に本の相談ができるようになる。
- AR(拡張現実)との連携: スマートフォンのカメラを棚にかざすと、AR技術によってAIが推薦する本のレビューや関連情報、紹介動画が浮かび上がる。これにより、静的な棚がダイナミックな情報空間へと変化する 96。
業務プロセスへのインパクト
- 在庫管理・発注の最適化:
AIは、書店経営における長年の課題であった非効率な在庫管理と発注業務を劇的に改善する。- AI需要予測: 過去の販売データ(POSデータ)だけでなく、天候、地域のイベント情報、SNSでのトレンド、近刊情報などを統合的に分析し、書籍ごとの将来の需要を高い精度で予測する 97。TSUTAYAでは、AIによる需要予測を導入し、在庫の最適化を実現した事例がある 97。
- 発注・返本の自動最適化: AIの需要予測に基づき、最適な発注量と返本すべき書籍を自動的にリストアップする。これにより、書店員の勘と経験に頼っていた発注業務の負担を大幅に軽減し、欠品による機会損失と過剰在庫による返品コストを同時に削減する 99。
- 古本査定の自動化と高度化:
古本事業の根幹である査定業務は、AIによって大きく変わる。- AI自動査定システム: スマートフォンのカメラで本の表紙や状態を撮影すると、AIが画像認識技術で書籍を特定し、市場の取引データ(ECサイトやオークションの相場)をリアルタイムで分析して、瞬時に買取価格を提示する。大黒屋がブランド品買取で導入したAI査定システムは、このモデルの先進事例である 100。
- 影響: これにより、査定業務の属人性が排除され、アルバイトスタッフでも迅速かつ公正な査定が可能になる。査定時間の短縮は顧客満足度を向上させ、仕入れ競争において優位に立つ要因となる。
- 店舗運営の効率化:
AIカメラなどの技術は、店舗運営の最適化にも貢献する。- 顧客動線分析: 店内に設置したAIカメラが顧客の動きを分析し、どの棚の前で立ち止まる時間が長いか、どのエリアが混雑しているかといった「ヒートマップ」を作成する。このデータを基に、棚の配置や商品の陳列を最適化し、売上向上に繋げることができる 102。
市場構造へのインパクト
- 「読書」需要の代替または補完:
AIは、書籍コンテンツの消費形態そのものを変える可能性がある。- AIによる書籍要約サービス: ChatGPTのような生成AIは、長文の書籍を瞬時に要約できる 103。これにより、タイパを重視する層が「本を読まずに内容だけを知る」という新たな需要が拡大し、従来の読書需要を一部代替する可能性がある。
- AIによるオーディオブック自動生成: テキストデータを自然な音声で読み上げるAI技術の進化により、低コストかつ短期間でオーディオブックを制作することが可能になる。これによりオーディオブックのコンテンツ数が飛躍的に増加し、市場のさらなる拡大を後押しする。
書店員の役割の変化
AIの導入は、書店員の仕事を奪うのではなく、その役割をより高度で創造的なものへと進化させる。AIが得意な業務と、人間にしかできない価値を明確に切り分けることが重要である。
- AIが代替可能な業務(効率化・自動化の対象):
- レジ業務(セルフレジ、無人決済)
- 在庫検索、単純な問い合わせ対応(AIチャットボット)
- データに基づく需要予測、発注・返本リストの作成(AIシステム)
- 古本の簡易査定(AI査定システム)
- 棚卸し、在庫データの入力(ICタグ、AIカメラ)
- AIには代替困難な、人間ならではの価値(注力すべき領域):
- 文脈を読んだ選書と共感を呼ぶ棚作り: 顧客との対話の中から潜在的なニーズを汲み取り、思いがけない一冊を提案する能力。社会の空気や季節感を捉え、物語性のある棚を編集する創造性。
- コミュニティ運営とファシリテーション: 読書会やイベントを主催し、参加者同士の交流を促し、知的なハブとしての場を創造する能力。
- 空間の雰囲気作りとホスピタリティ: 居心地の良い空間を維持し、温かみのある接客を通じて、顧客に「また来たい」と思わせる人間的な魅力。
- 複雑で高度な古書査定: 希少性、歴史的価値、署名の有無など、データベース化が困難な要素を総合的に判断する専門的な鑑定眼。
So What?: AIは書店業界にとって脅威であると同時に、長年の課題であった低生産性や非効率な業務を解決し、新たな顧客体験を創造するための強力なツールである。AIを戦略的に活用できる書店は、コストを削減し、顧客満足度を高め、競争優位を築くことができる。一方で、AIに代替される業務に固執する書店は淘汰されるだろう。未来の書店員の価値は、「本のオペレーター」から、AIを使いこなし、人間ならではの創造性と共感力で顧客と繋がる「知のキュレーター」「コミュニティ・プロデューサー」へとシフトしていく。
第9章:主要トレンドと未来予測
書店・古本屋業界は、生き残りをかけて様々な変革を試みている。ここでは、現在進行中の主要なトレンドを分析し、そこから導き出される業界の未来像を予測する。
「体験型」書店の進化と多角化
単に本を売るだけでは顧客を惹きつけられない時代、書店は「体験」を提供する場へと進化している。このトレンドは今後さらに加速し、多様な業態との融合が進むだろう。
- 複合化の深化: 蔦屋書店が先鞭をつけたカフェや雑貨の併設は、もはやスタンダードとなりつつある。今後は、アパレル、コスメ、食品、さらにはコワーキングスペースや小規模なギャラリーなど、より多様なライフスタイル提案機能が書店に組み込まれていく。
- 滞在型コンテンツの登場: 「泊まれる本屋」をコンセプトにした「Book and Bed Tokyo」のように、書店が宿泊施設と融合するモデルも登場している。これは、書店を「本と出会う場所」から「本の世界に浸る場所」へと進化させる試みであり、究極の体験価値提供と言える。今後、同様のコンセプトを持つ小規模な施設が各地に生まれる可能性がある。
- 収益モデルの多角化: これらの動きは、書籍販売の低い利益率を補うための必然的な戦略である。入場料モデル(例:文喫) 77、カフェや物販の売上、イベント参加費、スペースのレンタル料など、収益源を多角化することで、ビジネスの安定性を高めることが不可欠となる。
専門・ニッチ特化によるサバイバル
大型チェーン店やAmazonが「広さ」と「量」で競争する一方、独立系書店は「深さ」と「熱量」で独自のポジションを築いている。このニッチ特化の流れは、小規模事業者の主要な生存戦略となる。
- ジャンル特化: ビジネス書、アート、ミステリー、SF、絵本など、特定のジャンルに特化することで、深い知識を持つ書店員による専門的な選書と、熱心なファンが集まるコミュニティを形成する。
- 価値観・テーマ特化: フェミニズム、環境問題、社会科学、あるいは特定のライフスタイル(例:ミニマリズム、アウトドア)といった、特定の価値観やテーマで書籍をセレクトする書店が増加している。これらの書店は、単に本を売るだけでなく、同じ価値観を共有する人々のためのサロンや活動拠点としての役割を担う。
- コミュニティ形成: これらのニッチな書店は、読書会、勉強会、作家との交流会などを頻繁に開催し、顧客同士の繋がりを創出する。このコミュニ-ティこそが、ECサイトにはない強力な顧客吸引力となり、持続的な経営の基盤となる。
新刊・中古・C2Cの境界溶解
消費者は、新品、中古、個人間売買を意識することなく、自身のニーズに合わせて最適なチャネルをシームレスに使い分けている。この現実に対応するため、事業者側でもチャネルの境界を越える動きが加速する。
- 新刊と古本の併売: 新刊書店が一部で古本を取り扱う、あるいは古本屋が話題の新刊を仕入れて販売するモデルが一般化するだろう。丸善ジュンク堂書店がリユース事業に参入し、ホビー商材などを扱う「駿河屋」のFC展開を始めたのはその一例である 106。これにより、顧客はワンストップで多様な選択肢を得られるようになり、店舗の魅力向上に繋がる。これは、C2Cフリマアプリへの対抗策としても有効である。
- リアル店舗のC2Cハブ化: 書店がC2Cフリマアプリの発送・受取拠点となる、あるいは出品代行サービスを提供するなど、オンラインの個人間取引をサポートする役割を担う可能性がある。これにより、店舗への来店動機を創出し、新たな顧客層との接点を生み出す。
流通革命の加速
高い返本率や低い利益率といった構造問題の根源である、伝統的な取次システムからの脱却を目指す動きは、今後ますます加速する。
- 直取引の拡大: 出版社と書店が直接取引するモデルは、双方にメリットがあるため、今後さらに拡大する可能性が高い。紀伊國屋書店などが主導する「ブックセラーズ&カンパニー」のような取り組み 69 や、「BookCellar」のようなプラットフォーム 76 が、その動きを後押しする。
- 取次の機能変化: 大手取次自身も、単なる物流業者からの脱却を迫られている。AIを活用した需要予測サービスの提供 98、無人書店ソリューションの開発支援 107 など、書店経営を支援するコンサルティングやソリューションプロバイダーとしての役割を強化していくだろう。
- 出版社の小売参入: 出版社が自ら書店を経営し、読者との直接的な接点を持ち、自社ブランドの世界観を表現する動きは今後も続くと考えられる。これは、マーケティングの場として、また新たなビジネスモデルの実験場として機能する。
サブスクリプションモデルの多様化
「所有から利用へ」という消費トレンドは、書籍の世界にも及んでいる。
- 読み放題サービスの定着: Kindle Unlimitedのような電子書籍の読み放題サービスは、特に多読家の間で一定の地位を確立している。
- 「選書」サービスのサブスクリプション: 単に本を読み放題にするだけでなく、「専門家があなたのために選んだ本を毎月届ける」という「選書」サービスが新たな市場を形成する可能性がある 108。これは、情報過多の時代に「何を読むべきか」という選択の負担を軽減したいというニーズに応えるものであり、独立系書店や専門家個人のキュレーション能力を収益化する新たなモデルとなりうる。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
本屋・古本屋業界を取り巻く競争環境を理解するため、各業態の主要プレイヤーの戦略、強み・弱み、そしてデジタル時代への対応を比較分析する。
新刊・大型チェーン
- 紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店:
- 戦略: 全国主要都市の一等地に大型店舗を構え、圧倒的な品揃えとブランド力を武器に、幅広い顧客層にアプローチする。学術書や専門書に強みを持ち、大学や研究機関への外商も重要な収益源である。
- 強み: 豊富な在庫量による「探している本が見つかる」という信頼感。長年培ってきたブランドイメージ。専門性の高いスタッフ。
- 弱み: 高い賃料や人件費による重いコスト構造。ECサイトと比較した場合の利便性の劣後。画一的な店舗運営になりがちで、個性を出しにくい。
- 動向: 丸善ジュンク堂書店は、リユース事業(駿河屋FC)への参入で収益源の多角化を図る 106。紀伊國屋書店は、CCCや日販と共同で直取引を推進する新会社を設立し、流通改革に乗り出すなど 69、業界の構造問題に積極的に取り組む姿勢を見せている。両社とも、オンラインストアとリアル店舗の連携(OMO)強化が共通の課題である。
体験型モデル
- 蔦屋書店(カルチュア・コンビニエンス・クラブ):
- 戦略: 「本を売る」のではなく、「ライフスタイルを提案する」ことをコンセプトに、書籍、音楽、映画、文具、雑貨、カフェなどを融合させた大規模な複合文化空間をプロデュースする。
- 強み: 高い企画力とデザイン性による、唯一無二の空間体験の創出。書籍販売以外の多様な収益源(テナント料、カフェ売上など)を持つビジネスモデル 110。Tポイント(現Vポイント)による強力な顧客データベース。
- 弱み: 高い初期投資と運営コスト。コンセプトが陳腐化するリスク。一部では、FC展開するトップカルチャーの業績不振も報告されている 111。
- 動向: CCCは非上場であり詳細な経営分析は困難だが 113、代官山T-SITEの成功以降、そのモデルを全国に展開。書店業界における「体験価値」の重要性を決定づけたプレイヤーであり、業界全体のベンチマークとなっている。
古本チェーン
- ブックオフグループホールディングス:
- 戦略: 「本だけじゃないブックオフ」を掲げ、書籍・ソフトメディアからアパレル、ホビー、家電、ブランド品まで取り扱い商材を拡大する総合リユース企業へと変貌。大型複合店「BOOKOFF SUPER BAZAAR」の展開を加速 114。
- 強み: 全国に広がる店舗網と圧倒的な知名度。多様な商材を一度に売買できる利便性。海外事業(マレーシア、米国など)も成長軌道に乗っている 115。
- 弱み: C2Cフリマアプリとの仕入れ(買取)競争の激化。特に書籍においては、メルカリ等に比べて買取価格が安いというイメージが定着しており、優良な在庫の確保が課題 29。
- 動向: 2025年5月期決算では売上高1,192億円、経常利益は過去最高を更新するなど業績は好調 116。書籍事業の利益率を維持しつつ、成長分野であるトレカ・ホビーやブランド品、海外事業へ積極的に投資するポートフォリオ経営を推進している 115。
ECプラットフォーム
- Amazon:
- 戦略: 「地球上で最も豊富な品揃え」を掲げ、ロングテール戦略によりニッチな書籍も含めて網羅的に取り扱う。Prime会員向けの迅速な配送サービスと、Kindleによる電子書籍エコシステムで市場を支配。
- 強み: 圧倒的な利便性(検索、注文、配送)、豊富な品揃え、強力なレコメンデーションエンジン、価格競争力。紙、電子、中古(マーケットプレイス)をシームレスに提供するプラットフォーム。
- 弱み: リアル店舗が持つ「セレンディピティ」や「空間体験」の欠如。過去にリアル書店「Amazon Books」を展開したが、全店閉店しており、リアルでの成功体験は乏しい 119。
- 動向: 書籍販売はAmazonにとって数ある商材の一つに過ぎず、顧客接点を確保し、他の高利益商材へ誘導するためのツールという側面も持つ。リアル書店とはビジネスモデルの土俵が根本的に異なる非対称な競合である。
C2Cプラットフォーム
- メルカリ、ラクマ:
- 戦略: 個人がスマートフォンで簡単に出品・購入できるマーケットプレイスを提供。出品手数料を主な収益源とする。
- 強み: 出品の手軽さ、匿名配送による安全性、ユーザー間の価格交渉によるダイナミックな価格設定。古本屋よりも高く売れる可能性が高い 29。
- 弱み: 商品の状態や出品者の信頼性が不均一。梱包・発送の手間がかかる。欲しい本が常に出品されているとは限らない。
- 動向: 巨大なユーザーベースを背景に、リユース市場における存在感を増し続けている。古本屋にとっては、仕入れと販売の両面で競合する最大の脅威となっている。
独立系書店の代表例
- 本屋B&B(東京・下北沢):
- 戦略: “Book & Beer”をコンセプトに、ビールを飲みながら本を選べるユニークな体験を提供。ブックコーディネーターの内沼晋太郎氏らが共同経営 121。
- ユニークな点: 収益の柱は書籍販売だけでなく、毎日開催される著者トークショーなどのイベント参加費である 123。イベントを通じて著者や編集者と読者が直接交流する場を創出し、強力なコミュニティを形成。書籍の利益率が約20%と低い中、イベント収益でビジネスモデルを成立させている 123。
- Title(東京・荻窪):
- 戦略: 元リブロ書店員であった店主の辻山良雄氏による、独自の審美眼でセレクトされた書籍と、カフェ、ギャラリーを併設した店舗。
- ユニークな点: 大量生産・大量消費の出版業界とは一線を画し、一冊一冊の本を丁寧に顧客に届ける姿勢を貫く。店の世界観に共感する顧客との強い信頼関係を構築している。オンラインでの発信にも力を入れ、店の哲学や思想を伝えることでファンを増やしている 124。
これらの独立系書店は、規模では大手チェーンやECに劣るものの、「体験」「コミュニティ」「専門性」という独自の価値を創造することで、熱心なファンに支えられ、持続可能な経営を実現している。彼らの戦略は、業界全体が向かうべき方向性を示唆している。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、本屋・古本屋業界が直面する本質的な課題を再確認した上で、この厳しい市場で生き残り、成長を遂げるための具体的な戦略を提言する。
今後5~10年で勝者と敗者を分ける決定的要因
今後、業界の勝敗を分けるのは、以下の3つの能力の有無に集約される。
- 「空間」を収益化する能力: リアル店舗を単なる「在庫置き場」ではなく、顧客が時間とお金を費やす価値のある「体験の場」へと転換し、書籍販売以外の収益源(飲食、イベント、雑貨販売、スペース利用料など)を確立できるか。店舗の家賃をコストではなく、体験価値を生み出すための投資と捉えられるかどうかが分岐点となる。
- 「コミュニティ」を形成・運営する能力: 特定のテーマや価値観に共感する人々を集め、彼らの知的好奇心を満たし、交流を促進するハブとなれるか。価格や利便性を超えた顧客との強いエンゲージメントを構築し、熱量の高いファンベースを築けるかが、C2Cを含む価格競争から脱却する鍵となる。
- 「デジタル」を味方につける能力: デジタルをリアル店舗の脅威と見なすのではなく、顧客体験を補完・強化するツールとして戦略的に活用できるか。OMO(Online Merges with Offline)の発想で、オンラインの利便性とオフラインの発見性をシームレスに繋ぎ、顧客データを活用してパーソナライズされたサービスを提供できるかが問われる。
これらの能力を持たず、旧来の「本を仕入れて売るだけ」のビジネスモデルに固執するプレイヤーは、ECとC2Cプラットフォームとの消耗戦の末、淘汰される可能性が極めて高い。
取るべき戦略的方向性
目指すべきは、Amazonやメルカリと同じ土俵で戦うことではない。彼らが提供できない独自の価値を提供することで、特定の顧客セグメントから熱烈に支持される存在になることである。
- ターゲット顧客: 主なターゲットは、第6章で定義した「体験・空間重視層」と「専門性・発見重視層」である。彼らは価格や利便性以上に、知的な刺激、居心地の良さ、信頼できるキュレーション、そして偶然の出会いを求めている。
- 提供価値: 提供すべき価値は、「セレンディピティ(発見性)」「キュレーション(専門性)」「エクスペリエンス(体験)」「コミュニティ(繋がり)」の4つに集約される。これらの価値を最大化するために、リアル店舗とデジタルの両方を活用する。
具体的な施策とアクションプラン
上記の戦略的方向性を実現するため、「超・体験特化型コミュニティハブへの転換」を最終的な事業戦略として提言する。以下に、その実行に向けた具体的なアクションプランの概要を示す。
提言戦略:超・体験特化型コミュニティハブへの転換
この戦略の核心は、店舗を「本を売る小売店」から「特定のテーマに関心を持つ人々が集い、学び、交流する文化施設」へと再定義することにある。
1. 店舗の再構築:空間価値の最大化
- アクション:
- 店舗面積の一定割合(例:30%以上)を、カフェ、イベントスペース、ギャラリー、コワーキング機能を持つエリアに割り当てる。
- 居心地の良さを追求し、照明、什器、BGM、香りなど、五感に訴える空間デザインに投資する。
- 特定のテーマ(例:「旅と文学」「食と暮らし」「テクノロジーと未来」など)を設定し、書籍だけでなく、関連する雑貨、食品、アートなどを融合させた編集的な売り場を構築する。
- KPI: 顧客平均滞在時間、書籍以外の売上比率、坪当たり売上高。
- タイムライン: 1年目(コンセプト設計、パイロット店舗の改装)、2年目以降(効果検証と他店舗への展開)。
2. デジタルの活用:OMOによる顧客エンゲージメント強化
- アクション:
- 自社アプリを開発・導入し、会員証、ポイントプログラム、イベント予約、オンラインでの在庫確認・取置機能を統合する。
- AIを活用し、アプリ上で顧客の購買・閲覧履歴に基づいたパーソナライズド・レコメンデーションを提供する。
- 店舗でのイベントをオンラインで配信し、リアルとオンラインのハイブリッドなコミュニティを形成する。SNSでの情報発信を強化し、各店舗の書店員が主体的に「中の人」として顧客と交流する。
- KPI: アプリのアクティブユーザー数、オンライン経由の店舗送客数、イベントのオンライン参加者数。
- タイムライン: 1年目(アプリ開発・導入)、2年目以降(機能拡充、データ分析に基づく施策改善)。
3. 人材への投資:キュレーターの育成
- アクション:
- 書店員の評価制度を見直し、オペレーション能力だけでなく、選書能力、企画力、情報発信力を重視する。
- 特定のジャンルに深い知見を持つスタッフを「専門キュレーター」として認定し、棚作りの裁量権とインセンティブを与える。
- 社内研修を強化し、イベント企画・運営スキルやデジタルマーケティングに関する知識習得を支援する 84。
- KPI: 専門キュレーターによる企画イベント数、担当棚の売上・利益率、スタッフの定着率。
- タイムライン: 即時開始、継続的に実施。
4. サプライチェーンへの挑戦:収益構造の改善
- アクション:
- 専門性の高いジャンルや、自社で販売予測が立てやすい書籍について、出版社との「直取引」や「買切」を試験的に導入する。
- 買切による在庫リスクを管理するため、AIによる需要予測システムの導入を検討する。
- 新刊と古本を併売するモデルを導入し、顧客の多様なニーズに応えるとともに、利益率の高い商材を確保する。
- KPI: 粗利益率、返本率、買切商品の売上比率・消化率。
- タイムライン: 1年目(一部出版社・店舗での試験導入)、2年目以降(対象範囲の拡大)。
必要リソース:
- 資金: 店舗改装投資、システム開発投資(アプリ、AI)、人材育成投資。
- 人材: 空間デザイナー、イベントプロデューサー、デジタルマーケティング担当、データサイエンティストなど、従来の書店業界には少なかった専門人材の採用・育成。
- パートナーシップ: 独自の価値を持つ出版社、地域のクリエイター、イベント事業者、カフェ運営業者などとの連携。
最終的に、この戦略が目指すのは、単なる書店の生き残りではない。デジタルとリアルの境界が溶け合う時代において、「知」との出会いを再定義し、地域社会に不可欠な文化的拠点としての新たな存在意義を確立することである。それは困難な道のりであるが、業界が未来を切り拓くための唯一の道であると確信する。
第12章:付録
引用文献
- 2023年出版市場(紙+電子) 前年比2.1%減の1兆5963億円、2年連続マイナス 電子コミックのみ7.8%増 – BookLink, https://book-link.jp/media/archives/11624
- 2023 年度 事業報告 – 全国出版協会, https://www.ajpea.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/%E2%97%8F2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6-%E5%85%A8%E5%8D%94%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf
- 24年の出版市場規模、1兆5716億円に 3年連続マイナス – 新文化 – WEB本の雑誌, https://www.webdoku.jp/shinbunka/2025/01/31/163416.html
- 2024年出版市場(紙+電子)は1兆5716億円で前年比1.5%減、コロナ前の2019年比では1.8%増 ~ 出版科学研究所調べ【追記有】 | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/53725
- 全国出版協会・出版科学研究所 2024 年出版市場・紙+電子は1.5%減で1 兆5,716 億円、電子出版は5,660億円で全ジャンルプラスに 『季刊出版指標』2025年冬号で2024年出版市場規模を発表 | 【印刷業界ニュース】ニュープリ, https://www.newprinet.co.jp/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%87%BA%E7%89%88%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%83%BB%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E3%80%802024-%E5%B9%B4%E5%87%BA%E7%89%88%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%83%BB
- 2024年の出版市場規模、3年連続前年割れ 電子コミックのシェアは5年で倍増, https://book.asahi.com/article/15615142
- 令和6年度 リユース市場規模調査 報告書 – 環境省, https://www.env.go.jp/content/000321556.pdf
- 令和4年度 電子商取引に関する市場調査 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf
- 2023年度の電子書籍市場規模は6449億円、2028年度には8000億円市場に成長, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/697
- 2026年には8000億円市場に『電子書籍ビジネス調査報告書2022』8月10日発売, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004709.000005875.html
- 2024年度の国内市場規模は前年比3.9%増の6703億円 『電子書籍ビジネス調査報告書2025』7月24日発売 飛躍への転換期に入ったWebtoon、IP戦略、海外展開 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/715
- 電子書籍ビジネス調査報告書2025 | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/report/list/ebook/502255
- アルメディア、書店数は1万4696店に – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/112566/
- 【アルメディア調査】2020年 日本の書店数1万1024店に、売場面積は122万坪 – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/219153/
- 第8回 出版不況の出口 – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/archives/875
- 書店マスタ管理センター 8月の書店数は1万250店 売場面積ありは7550店に – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/434902/
- 【データから読み解く】国内出版・書籍EC・書店市場 – ビジネス・ブレークスルー大学大学院, https://www.ohmae.ac.jp/mbaswitch/e-books/
- 関係者から指摘された書店活性化のための課題(案)に対する パブリックコメントの結果について, https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000286288
- 「本を届けるために、 本だけを売らない。」箱根本箱 – ひらく, https://hiraku.info/works/41/?c=business
- 関係者から指摘された 書店活性化のための課題(案) 令和6年10月4日 経済産業省 書店振興プロジェクトチーム, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/syoten_kadai.pdf
- 出版関連用語集[は行] | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/knowledge/glossary06/
- 業界の現状及びアクションプラン(案)について 【書店】 (事務局資料④), https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/003_04_04.pdf
- 2-5.返本率 – | 企業出版で本を出したい。, https://kigyoshuppan.jp/2-5%EF%BC%8E%E8%BF%94%E6%9C%AC%E7%8E%87/
- 「書店業界のM&Aの特徴や留意点」とは? ~在庫の金額は?在庫の積み増しによる不正会計は?, https://links.zeiken.co.jp/mauseful/6413
- ビジネス書の在庫回転率はどれくらいか?|アップル – note, https://note.com/apple_ringo/n/n99c21b057974
- 書店の利益率は減っていますか? – 出版流通学院, https://ryutsu-gakuin.nippan.co.jp/n-column-cat2-3/
- 出版市場統計/書店の経営統計|日販 ストアソリューション課 – 出版流通学院, https://ryutsu-gakuin.nippan.co.jp/statistics/
- ブックオフの買取はひどい?【安いって口コミは本当?ジャンル別の買取価格も紹介】, https://kaitori2.xsrv.jp/bookoff-kaitori-price/
- 【本の断捨離】メルカリならブックオフの2.5倍値がつく 予想外な査定結果に売却をやめた大ヒット漫画とは? | マネーの達人, https://manetatsu.com/article/2024/03/31/459441.html
- 書店の役割〔再販売価格維持制度と委託制度〕 – 超書店員, https://bookseller.work/distribution-01-3/
- 再販適用除外制度の見直し – 公正取引委員会, https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h09/02120000.html
- 「なぜ出版物に軽減税率が必要か?」Q&A – 出版広報センター, https://shuppankoho.jp/faq/taxrate_qa.html
- 公共貸与権 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9
- CA2011 – 動向レビュー:電子書籍を中心とした公貸権制度の2005年以降の国際動向 / 稲垣行子, https://current.ndl.go.jp/ca2011
- 2025年4月消費統計 – 大和総研, https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20250606_025142.html
- 2024年11月消費統計 2025年01月10日 | 大和総研 | 菊池 慈陽, https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20250110_024857.html
- 梶 善 登 諸外国の書籍再販制度, https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999613_po_069903.pdf?contentNo=1
- 【2025年】最低賃金の引上げによる影響は?中小企業がとるべき対策も解説 – ネオキャリア, https://www.neo-career.co.jp/humanresource/knowhow/a-contents-parttime-saiteichingin2022_220824/
- 最低賃金引き上げによって何が起こる?正社員に影響はある?経営者に必要な対策を徹底解説, https://www.yscorpo.co.jp/content/%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%E3%81%8C%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8B%EF%BC%9F%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AB/
- 「学校読書調査」の結果 – 全国学校図書館協議会, https://www.j-sla.or.jp/material/research/dokusyotyousa.html
- 資料3.「国民の読書推進に関する協力者会議」報告書素案 – 文部科学省, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/024/shiryo/attach/1310794.htm
- Z世代の新しい価値観「タイパ」とは?代表的な行動7つ – Cotra, https://www.transcosmos-cotra.jp/typer
- タイパ消費とは?Z世代が重視する背景や事例について紹介 – sellwell(セルウェル), https://marketing.sellwell.jp/column/time-performance/
- 「本の要約サービス」利用者が急増、時短読書は出版不況を救うか – ダイヤモンド・オンライン, https://diamond.jp/articles/-/268267
- 本の要約サービス「flier」 要約配信4000冊突破!累計会員数は125万人超に ~タイパ時代にマッチした読書体験を提供~ | 株式会社フライヤー – ドリームニュース, https://www.dreamnews.jp/press/0000320504/
- 「TikTok売れ」を牽引する2022年の「新成人」が読んだ本を発表!「20歳」は『呪術廻戦』、「18歳」は学習参考書がトップ3を独占 | hontoPR事務局のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000009424.html
- 10代向け小説が3ヶ月間売れ続けたきっかけはTikTok。従来のプロモーション手法と異なるTikTokで本が売れるメカニズムとは<集英社さんインタビュー – note, https://note.com/tiktok/n/n9845a4cb6ef5
- SNSでバズって注目!令和の新ベストセラー – シティリビングWeb, https://city.living.jp/tokyo/f-tokyo/1498437/
- なぜTikTok売れが起きるの?仕組みや成功させるコツを事例も挙げて解説 – 株式会社NOKID, https://nokid.jp/blog/8774/
- 3ヶ月で7.5万部増刷!なぜ4年前に発売された小説がTikTokきっかけで爆発的に売れたのか <スターツ出版さんインタビュー – note, https://note.com/tiktok/n/ne56c59b26c94
- 節約志向でも旺盛な推し活消費、「推しがいる」人の約7割が「推しにお金を使う」と回答 市場規模は約3.9兆円と推計 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000993.000012048.html
- 推し活の経済効果はどれくらい?市場規模と推し活マーケティングのメリットとは, https://www.cross-m.co.jp/column/marketing/mkc20241025
- タブレット端末」での利用が45.5%とトップ。次いで「スマートフォン」(35.8%)、「電子書籍専用リーダー」(26.0%) [価格.comリサーチ]No.065, https://kakaku.com/research/report/065/p03.html
- 【デジタルトレンド】急成長するオーディオブック市場 オーディブルが「聴き放題」サービス参入(堀鉄彦) – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/254333/
- オーディオブック市場 2024年に260億円規模に – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000035568.html
- CtoCとは?市場規模、メリット・デメリットから中国最新トレンドまで徹底解説 – zero-one, https://zeroone-totyudxss.com/media/3gjVmtNl
- 【2025年】レコメンドエンジンのおすすめ比較15選!機能やツールの選び方をご紹介, https://www.bsearchtech.com/blog/e-commerce-marketing/recommendation-engine-recommendations/
- レコメンドエンジン 5製品をまとめて比較! – ITトレンド, https://it-trend.jp/recommendation_engine
- 漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。 | 政府広報オンライン, https://www.gov-online.go.jp/article/202012/entry-8917.html
- 【古物営業法改正】どう変わる?「主たる営業所」未届出は、今までの許可が失効します!, https://office-aoyagi.com/syutarueigyosyo/
- サプライチェーン全体のCO2排出量と 主要再生紙製品のカーボンフットプリント(CFP)を初公開, https://www.sanyo-paper.co.jp/information/6797.html
- 紙・板紙のライフサイクルにおけるCO2排出量 – 日本製紙連合会, https://www.jpa.gr.jp/file/release/20110318021915-1.pdf
- FSC認証の広がり | Forest Stewardship Council, https://jp.fsc.org/jp-ja/FSC_growth
- FSC認証製品の種類と表示, https://shitte-erabo.net/aboutfsc/fscproducts/
- 出版不況下における出版流通構造と流通制度の変革の必要性, https://econ.meijigakuin.ac.jp/econ_wp/wp-content/uploads/159-5.pdf
- 出版取次・書店経営業者の経営実態調査|株式会社 帝国データバンク[TDB], https://www.tdb.co.jp/report/industry/xjigm6pi2rl3/
- 止まらない出版不況 出版取次5年連続の減収、書店では「変革」の波が…… – J-CAST ニュース, https://www.j-cast.com/kaisha/2019/09/28368635.html?p=all
- 「独立系出版でメシ食えます?」17年続けるミシマ社に訊いた一冊の価値 – イーアイデム「ジモコロ」, https://www.e-aidem.com/ch/jimocoro/entry/kakijiro58
- 出版社との直取引で利益率アップを目指す新書店 紀伊國屋書店主導で誕生 永江朗, https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20231031/se1/00m/020/015000c
- 全国書店ヒアリングでの声 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/syoten_koe.pdf
- 令和のリアル書店はAmazonに潰される?各社の生存戦略を調べてみた(ちざ散歩Vol.03), https://toreru.jp/media/trademark/6765/
- 古本を売りたい!ブックオフとメルカリだとどっちが良い? | 買取のコツ, https://www.recommerce.co.jp/column/kaitori-technique/entry-239.html
- 改めて考察する委託販売制度下の発注と返品 – 日本出版学会, https://www.shuppan.jp/wp-content/uploads/2010/05/happyo0801.pdf
- 返本率とは?出版業界が抱える返本率の課題とは? | 自費出版の書籍づくり本舗, https://shoseki.net/glossary/henponritsu/
- 取次を通さないで書店と直取引している出版社一覧, http://www.1book.co.jp/004028.html
- BookCellar 累計流通総額が22億円、注文冊数は100万冊を突破! – 株式会社とうこう・あい, https://www.toko-ai.com/469/
- 「文喫 六本木」、多角的経営の書店 入場料やイベントで収益押し上げ – AdverTimes, https://www.advertimes.com/20231211/article442754/
- smiles, https://creative.smiles.co.jp/projects/bunkitsu/
- リアル書店と利便性の功罪|瀬迫 貴士 – note, https://note.com/takashi_sesako/n/n42fe4c330bb4
- 本屋さんぶらぶらを習慣にする〜セレンディピティを意図的に増やす|sy – note, https://note.com/nice_mango691/n/n980a93d36858
- セレンディピティ~偶然が生む多様性の出会い~ | AKARI, https://akari-media.com/2020/04/28/member-783/
- ネットでは得られないこともある。「リアル書店」の活用メリット | リクナビNEXTジャーナル, https://next.rikunabi.com/journal/20160310_1/
- デジタル時代における「リアル店舗の存在価値」, https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/26945/files/017071020003.pdf
- 書店員の仕事内容と目指し方。業務で求められる資質・能力も – スタンバイplus(プラス), https://jp.stanby.com/magazine/entry/241106
- VRIO分析とは 4つ視点から強みを明らかにする分析フレームワークを解説 – 大和総研, https://www.dir.co.jp/world/entry/vrio
- 経営資源の分析方法とは|VRIO分析の特徴・手順と事例を解説 – 金融ナビ, https://financenavi.jp/basic-knowledge/management_resource_analysis/
- リアル書店を復活させる!出版社の新戦略 – マーケティングゼミ, https://marketingzemi.jp/trend/435/
- 書店の仕事の年収・時給・給料(求人統計データ) – 求人ボックス, https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/%E6%9B%B8%E5%BA%97%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6
- 書店員 – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag) – 厚生労働省, https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/68
- 書店員になるには?仕事内容や求められる資質・能力などを紹介, https://www.gyakubiki.net/readings/employment/503/
- 「街の書店」は本当に不要なのか…電車に乗る人がみんなスマホを見ている光景に私が思うこと 新規店ができる4倍のペースで書店が閉店している (2ページ目) – プレジデントオンライン, https://president.jp/articles/-/83402?page=2
- 需要予測AIによる在庫予測!活用の手法やメリットも紹介 – ノーコードAI予測分析・意思決定支援サービス「Deep Predictor」, https://aicross.co.jp/deep-predictor/blog/blog-407/
- ワントゥーテン、 KADOKAWAが推進する書店DXサービスの「AI書店員」に、ChatGPTと連携した独自AIを提供 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000016942.html
- KADOKAWA、生成AI技術活用の体験型コンテンツ「AI書店員ダ・ヴィンチさん」を期間限定で展開, https://aismiley.co.jp/ai_news/kadokawa-ai-davinci-bookstoreclerk/
- ChatGPTが本をおすすめ、AIで経営支援も? 「透明書店」は書店経営を変えるか – 好書好日, https://book.asahi.com/article/14892655
- ITやIoTを導入して活気ある書店に – 三菱電機デジタルイノベーション株式会社, https://www.mdsol.co.jp/column/column_123_772.html
- AIによる在庫管理のメリット・デメリットは?導入事例を解説 | Koto Online, https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/archives/268
- AIを活用したフレキシブルな製造と物流で書籍の販売機会を拡大 | ニュース – DNP 大日本印刷, https://www.dnp.co.jp/news/detail/1187769_1587.html
- 出版業界における生成AI活用事例|生産性向上・流通最適化・アクセシビリティ強化, https://dx-consultant.co.jp/publishing_industry_ai_case/
- 大黒屋が先進 AIで叶える経済活性化 – 最新ニュース – 大黒屋ホールディングス株式会社 | DAIKOKUYA HOLDINGS, https://www.daikokuyajp.com/news/dk-line-ai-nikkei-business/
- ブランド品買取の大黒屋、外部ECサイトからの買い付け業務を自動化するAIシステムを導入, https://dcross.impress.co.jp/docs/usecase/004113.html
- 小売業における生成AIの導入事例|メリットや注意点、活用事例を紹介, https://officebot.jp/columns/use-cases/retail-generation-ai/
- 【2025】要約ができるAIツールおすすめ14選!カテゴリ別・注意点やコツも解説 | スマート書記, https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/summary-with-ai/
- AI要約ツール5選|ビジネスに役立つおすすめツールを紹介 – Kaizen Penguin, https://kaizen-penguin.com/ai-summary/
- 入場料1500円の書店「文喫」は、 本の未来にイノベーションを起こせるか – LEXUS, https://lexus.jp/magazine/post/?id=m2a_mb4-o-j
- 丸善ジュンク堂書店、駿河屋フランチャイズ事業が急拡大 — 3年で売上50億円超えを目指す, https://brandreusenews.jp/posts/katHDl10
- トーハングループと協業し無人書店の実証実験をスタート | 株式会社Nebraskaのプレスリリース, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000117071.html
- 【人文・アート・社会をめぐる、あたらしい読書体験】独立書店kamos、第一線の専門家による選書サブスクリプションサービスを開始, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000141803.html
- チャプターズの選書が毎月の楽しみ。同世代の運営にも共感し応援したいサービスとして継続中。 ~ミレイさん(24)の場合~ | Chapters Blog, https://chapters.jp/blogs/?p=844
- 斜陽産業の逆張り戦略か?『蔦屋書店』の雄、トップカルチャー(7640)の生存戦略と未来価値を徹底解剖 – note, https://note.com/tatsuya_sabato/n/n51381e322428
- 「蔦屋書店」を展開するトップカルチャーの中間決算は赤字幅が拡大 業績予想は精査中として公表を控える – Yahoo! JAPAN, https://article.yahoo.co.jp/detail/fc1f40d1f823dfa556ca0172ee647cf13db6973f
- 「蔦屋書店」を展開するトップカルチャーの中間決算は赤字幅が拡大 業績予想は精査中として公表を控える | セブツーは, https://www.seventietwo.com/ja/business/TopCulture_Tsutaya_20250612
- ビジネスケース: カルチュア・コンビニエンス・クラブの業態転換 – researchmap, https://researchmap.jp/hajime_oda/misc/43754908/attachment_file.pdf
- ブックオフの価値創造MAP | BOOK-OFF Group 新卒採用サイト, https://freshers.bookoff.co.jp/value/
- 26/5期~28/5期 中期経営方針のアップデート – ブックオフグループ …, https://www.bookoffgroup.co.jp/management/wp-content/uploads/2025/08/%E6%88%90%E9%95%B7%E6%88%A6%E7%95%A5_20250815.pdf
- ブックオフグループホールディングス[9278] 2025年5月期 決算説明会 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=F6igXNVULG0
- ブックオフグループホールディングス(株)【9278】:決算説明会書き起こし – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/9278.T/financials?styl=presentation
- =企業価値の最大化, https://www.bookoffgroup.co.jp/management/wp-content/uploads/2025/05/%E6%88%90%E9%95%B7%E6%88%A6%E7%95%A5_20250424.pdf
- シリコンバレー101(916) 閉店もやむなし、Amazonの実店舗書店に私が行かなくなった理由, https://news.mynavi.jp/techplus/article/svalley-916/
- Amazon実店舗展開の3つの狙いと日本市場の課題とは? – ebisumart, https://ebisumart.com/blog/amazon-real/
- 住む場所が自分の幅を広げる。都心派だった内沼晋太郎さんが長野移住を経て思うキャリアのつくり方 #地方で働く, https://meetscareer.tenshoku.mynavi.jp/entry/20210624-uchinuma
- ブック・コーディネーター、内沼晋太郎が案内する、ゼロ年代「本屋」の歴史 – BRUTUS.jp, https://brutus.jp/rethinking_culture_00s_07/
- ビールが飲める本屋「B&B」大盛況の秘密 アマゾンには絶対まねできない体験を提供する, https://toyokeizai.net/articles/-/42074?display=b
- 中年の危機に刺さった。『本屋、はじめました 新刊書店 Title の冒険』(辻山良雄)読書記録, https://note.com/atsukute_yurui/n/n397e60e60371
- 独立系書店は「好き」やワクワクの宝庫。個性強めの発信が若者に刺さる, https://journal.meti.go.jp/p/37025/
- 店舗スタッフの教育を徹底解説!階層別<新人・中堅・店長>の教育方法とは? – shouin+ブログ, https://media.shouin.io/staff-training-new-mid-manager
- DeepResearch追加指示.txt
- 2025年上半期出版市場(紙+電子)は7737億円で前年同期比2.1%減、電子は2811億円で4.2%増 ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/56108
- 2024年の紙と電子を合算した出版市場(推定販売金額) – カレントアウェアネス – 国立国会図書館, https://current.ndl.go.jp/car/238836
- 古本の世界市場レポート2025年 – グローバルインフォメーション, https://www.gii.co.jp/report/tbrc1813772-second-hand-books-global-market-report.html
- 中古本の世界市場動向:エンドユーザー別、価格帯別、地域別分析&予測(2024年~2034年), https://www.marketresearch.co.jp/insights/second-hand-book-market-factmr/
- 令和3年度 リユース市場規模調査 報告書 – 環境省, https://www.env.go.jp/content/000064651.pdf
- 古本店 | 市場調査データ | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト], https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/productsales/cons-usedbookstore.html
- インプレス総合研究所、2023年度の電子書籍市場規模は6449億円と発表:前年比7.0%増, https://current.ndl.go.jp/car/223242
- インプレス総合研究所、2024年度の電子書籍市場規模は6703億円と発表:前年比3.9%増, https://current.ndl.go.jp/car/255891
- 書籍業界の市場傾向とECサイトの動向, https://www.ecsite-cx.com/tendency/book.html
- 書店数の推移 1999年~2017年:【 FAX DM、FAX送信の日本著者販促センター 】, http://www.1book.co.jp/001166.html
- デジタル社会経済のもとでの書店生き残り戦略 | 経営研レポート 2015, https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/reports/archives/2015/1119/index.html
- 在庫回転日数の計算式を解説!店舗における重要性と管理方法, https://usen.com/column/pos/Inventory-turnover-days-formula.html
- 在庫回転率とは?計算方法やメリット、適正在庫を把握するポイントを徹底解説, https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/blog/article-04.html
- DATA SOLUTION コラム 在庫日数とは|適正な在庫日数は?計算式も紹介 – 東芝テック, https://www.toshibatec.co.jp/datasolution/column/20221201_03.html
- ブックオフの店頭買取はひどい?130名に聞いて判明した利用者の本音, https://mangauru.com/bookoff-reputation/
- ブックオフの古本買取方法は4つ!高価買取リストや相場価格の調べ方も解説, https://uridoki.net/book/kiji_44949/
- 出版社の業績動向調査(2023年度) – 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250123-publisher23nendo/
- 電子書籍ビジネス調査報告書 2018 / インプレス総合研究所【著・編】 – 紀伊國屋書店, https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784295004585
- 2027年度には8000億円市場に成長Webtoonが電子コミック市場の1割の規模に『電子書籍ビジネス調査報告書2023』8月10日発売 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005378.000005875.html
- リユース経済新聞のリユース市場データブック, https://www.recycle-tsushin.com/databook/
- 令和6年度リユース市場規模調査報告書 (概要版) – 環境省, https://www.env.go.jp/content/000321557.pdf
- 【そうだ、リハロに相談だ】BOOKOFF総合買取窓口を「Rehello」にリネーム。モノを売ることに慣れていない方へリユースのきっかけと安心を提供 | ブックオフグループホールディングス株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000123523.html
- 「出版物販売額の実態 2024」「書店経営指標 2024年版」発行のご案内, https://www.nippan.co.jp/news/data2024_20241213/
- 2024年5月期決算説明資料, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20241015/20241015598366.pdf
- ブックオフグループホールディングス(9278) 2025年5月期第2四半期決算説明 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=gSBpztdEfE0
- IR資料一括ダウンロード – ブックオフグループホールディングス株式会社, https://www.bookoffgroup.co.jp/ir/top/
- 2024年5月期第2四半期決算説明資料, https://www2.jpx.co.jp/disc/92780/140120240112514202.pdf
- 矢野経済研究所、電子書籍市場に関する調査結果を発表——コンテンツ不足が解消され市場成長へ – MdN Design Interactive, https://www.mdn.co.jp/di/newstopics/22917/
- 市場調査資料 | マーケットレポート購入方法 – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/
- 販売商品 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/data/
- [ニュース]オンラインアシスタントサービス市場に関する調査を実施(202… | 『日本の人事部』, https://jinjibu.jp/news/detl/25641/
- 書店経営の先行き予想「下降」が6割以上 大手取次2社より発表 – The Bunka News デジタル, https://www.bunkanews.jp/article/103823/
- 第2回 書店人の覚書帳|草彅主税 – note, https://note.com/kusanagi_9379/n/n6e3dbac971b8
- 書店の売上が推定できる方法 – 出版流通学院, https://ryutsu-gakuin.nippan.co.jp/n-column-cat2-2/
- 書店情報の 管理・更新(書店マスタ管理センター) – JPO 一般社団法人日本出版インフラセンター, https://jpo.or.jp/business/business03.html
- 書店マスタ管理センター 7月の書店数は1万275店 売場面積ありは7571店に – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/433422/
- 出版業界ニュースまとめ#2025/04/04, https://furuhata.theletter.jp/posts/9739fb60-10c7-11f0-888b-8964286d4105
- 食料品等に対する軽減税率の導入問題 髙 田 具 視 – 国税庁, https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/46/takada/ronsou.pdf
- 時間効率にお金を払うタイパ消費。Z世代が課金するグルメ、エンタメ、ECの特徴とは, https://tomoruba.eiicon.net/articles/4609
- 電子書籍リーダーとは?メリットや種類を紹介! – デジタルアーカイブ教育, https://digitalarchive-edu.sei-syou.co.jp/blog/2019-05-15/
- 日本とアメリカのオーディオブック市場の違い – AJEC-日本編集制作協会, https://www.ajec.or.jp/interview_width_ueda1/
- 拡大し続けるCtoCの市場規模とは?国内外の事例を比較 | お役立ち情報, https://www.nck-tky.co.jp/itblog/869
- 著作権法の一部を改正する法律について, https://www.forum8.co.jp/topic/soumu142.htm
- 行政の動き-著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)について, https://www.dinf.ne.jp/d/3/006.html
- 古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行) – 警視庁ホームページ, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_sekoukisoku.html
- 国際認証ラベルに関する調査 FSC®ジャパン版報告書2020, https://jp.fsc.org/sites/default/files/2021-09/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%83%A9%E3%83%98%E3%82%99%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BBFSC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%A3%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%B3%E7%89%88%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B82020.pdf
- 【書籍の再販制度|H13公正取引委員会の見解→現在では合理性なし】 | 企業法務, https://www.mc-law.jp/kigyohomu/11025/
- 本の要約サービスを提供するメディアドゥの子会社フライヤーが新規上場【メディア企業徹底考察 #197】 – Media Innovation, https://media-innovation.jp/article/2025/01/31/142161.html
- 本の要約サービス「flier」が6億円調達‐法人事業を強化 – マイナビニュース, https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220527-2352850/
- 10代向け小説が3カ月間売れ続けたきっかけは「TikTok」 本が売れる新しいメカニズムとは, https://www.excite.co.jp/news/article/E1608520629565/
- 出会いと共感のコミュニティ、TikTokからベストセラーが生まれる – 好書好日, https://book.asahi.com/article/14360040
- TikTok売れとは?バズを活かして売上を高める仕組みと成功のコツを解説, https://atom-story.com/media/tiktok-sales
- 【2025年最新版】出版業界M&Aの最新動向|倒産増加と成功事例から見る今後の展望, https://www.tasuki.pro/ma/ma-3611/
- 「自分の本屋を開きたい!でもわからない!」「一冊!取引所って知ってる?」 – ライツ社, https://note.wrl.co.jp/n/n31b75a1267ea
- 消えゆく書店を救いたい!M&Aで業界に新たな風を, https://www.manda-pass.com/column/1596/
- ホテル等の書店開業を支援するサービスを開始 | ニュース | DNP 大日本印刷, https://www.dnp.co.jp/news/detail/20175690_1587.html
- 書店 | 業種別開業ガイド | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト], https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/retail/05.html
- 出版業界のM&A動向 昨今の事業買収・売却の事情やM&A事例を紹介, https://www.ma-cp.com/about-ma/industry/printing-advertising/2/
- 電子書籍サービスで見るべき重要なKPIや要素とは? | DataLab by FLYWHEEL, https://datalab.flywheel.jp/posts/KPI_for_ebook_service
- サブスクリプションビジネスとは?市場規模とBtoB収益モデルの成功事例 – wikiPaid(ウィキペイド), https://blog.paid.jp/3218/
- 出版およびサブスクリプションソフトウェア市場レポート:2025年から2032年までの予測 – Pando, https://pando.life/article/1537284
- 日本のサブスクビジネスの市場規模は?最新情報を紹介 – Stripe, https://stripe.com/jp/resources/more/subscription-business-market-japan
- サブスクリプションのビジネスモデルとは?市場規模やメリット、成功のポイント, https://www.tsuhan-marketing.com/blog/subscription/subscription_meaning
- 「本が読者に届かない」Amazon商法に公取委が突入で炙り出される出版業界の予後不良, https://stoica.jp/yamamoto_blogs/917
- 日本の書店の実態と経営課題 : アマゾンの 成功が示唆するもの, https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00007328/cd05_togawa.pdf
- なぜAmazonは、マイナーな書籍を仕入れることからビジネスをスタートしたのか?, https://diamond.jp/articles/-/339353
- 【古本】競争の番人 / 新川帆立 – メルカリ, https://jp.mercari.com/shops/product/SDgHLPw2TbjkUaBGgqvL4D
- 本売るために愚直に。知のインフラ守る… 大手チェーンが探る書店の進路 | 経済産業省 METI Journal ONLINE, https://journal.meti.go.jp/p/38382/
- I. 2023年8月期 業績ハイライト II. 各事業部門概況 III. 会社基盤と中長期成長戦略 – 株式会社 紀伊國屋書店, https://corp.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2023/11/fh6sbkt.pdf
- 丸善の書店営業利益率が「たったの0.1%」でも経営は安泰の理由 – ダイヤモンド・チェーンストア, https://diamond-rm.net/management/83630/
- 中期経営計画 – 丸善 CHIホールディングス, https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/ir/philosophy/main/03/teaserItems1/0/link/strategy20240314.pdf
- 異業種とのコラボで再発見した「書店の価値」 OMOで読書体験を広げる丸善ジュンク堂のユニファイドコマース戦略【前編】 – デジタラトリエ, https://digitalatelier.jp/column/special/post-102/
- Amazonが、日本企業の越境ECをサポートするためにアメリカとイギリスで開設している JAPAN … – About Amazon Japan, https://www.aboutamazon.jp/news/smb/supporting-sellers-on-japan-store
- ロングテール戦略とは? Amazonが売上げをアップしている方法 – ディーエスブランド, https://ds-b.jp/dsmagazine/pages/104/
- GFA(8783)、株主優待を新設!「泊まれる本屋」がコンセプトのホステル「BOOK AND BED TOKYO」などで使えるポイントを保有株数や期間に応じて贈呈 – ダイヤモンド・オンライン, https://diamond.jp/zai/articles/-/247795
- ニッチビジネスのマーケティングのポイントとは?成功例もご紹介!, https://forway.co.jp/post_column/niche-marketing/
- 誠品書店の成功の要因に関する考察 ―ジョブの3つの側面から, https://www.u-hyogo.ac.jp/mba/pdf/SBR/9-4/029.pdf
- 競争しないから儲かる! ニッチな新規事業の教科書|熊谷亮二|独自市場で成功するための実践書|空色書店 – note, https://note.com/books703/n/n1e0b2f6a2b90
- 本だけ売ってメシが食えるか|第8回|本に価値がある場所|小国貴司 | [Edit-us], https://www.editus.jp/archives/13326
- 小規模新刊書店の7つの経営手段|瀬迫 貴士 – note, https://note.com/takashi_sesako/n/nb83e80100b65
- 日本のサブスク成功事例 8 選と失敗事例 3 選を紹介 – Stripe, https://stripe.com/jp/resources/more/subscription-case-studies-japan
- AIスマホ自動買取機 – 愛回収ジャパン株式会社 AHS DEVICE JAPAN, https://ahsdevicejp.com/business/rereatm/
- バーチャル査定士「DAI」誕生 !大黒屋が挑むAI時代のブランド品買取 – ARCHETYP Staffing, https://staffing.archetyp.jp/magazine/daikokuya-dai/
- 小売業におけるAI活用事例12選!スーパーやコンビニ、量販店の成功例 | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/retail-ai-cases/
- COLUMNS | 日本の小売・EC業界における生成AI活用事例 – Neo Edgeは, https://neoedge.co.jp/columns/posts/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%A3%B2%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%94%9F%E6%88%90AI%E6%B4%BB%E7%94%A8%E4%BA%8B%E4%BE%8B
- 分で鍵アイデアをマスター:読書に革命を起こすAIブック要約ソフト10選 – ClickUp, https://clickup.com/ja/blog/241095/ai-book-summarizers
- 書籍要約サービスを比較してみた【2024.02.18現在】|float2024 – note, https://note.com/_floating/n/n2b675b5b748e
- 本の背表紙画像をAIで解析し、図書館の蔵書点検を効率化 – スマートIoT推進フォーラム, https://smartiot-forum.jp/iot-val-team/iot-case/kccs
- 来店者の表情を読み取り、お薦めの1冊を提案するAI書店員 – トーハン, https://news.mynavi.jp/techplus/article/20171106-a123/
- 書店へ足を運ぶ機会を与える新プロジェクト!在庫情報活用の実証実験開始, https://kowa-com.jp/news/20241023/
- 株式会社トーハンと、顔認識AIソフトウェアによる 書店向けマーケティング・プロモーション施策 “AI書店員” を共同開発 – sMedio, https://www.smedio.co.jp/news/2017/11/2017110601.html
- Books&Company, https://books-company.jp/
- 出版取次とは?本が流通する仕組みと2023年最新業界動向 – 神楽坂編集室, https://kagurazaka-editors.jp/publishing-industry-market-trends/
- 再販制度とは?再販制度のメリット・デメリット – 自費出版の書籍づくり本舗, https://shoseki.net/glossary/saihanseido/
- 本に魅せられて:書店・読者発の新たな価値創造の取り組み | 研究員コラム, https://rp.kddi-research.jp/atelier/column/archives/4953
- Amazonバリューチェーン分析(2025年) – Business Model Analyst, https://businessmodelanalyst.com/ja/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%88%86%E6%9E%90/
- リアルとデジタルの融合で変わる顧客体験について解説 ! – Digital Business Sherpa, https://www.dx-digital-business-sherpa.jp/blog/customer-experience-with-digital
- 書籍の関連性を持たせた陳列が及ぼす効果 -セレンディピティが消費者の購買意図と 再来店, https://www.komazawa-u.ac.jp/~knakano/NakanoSeminar/wp-content/uploads/2020/03/%E9%95%B7%E9%87%8E%E6%97%A5%E5%90%91%E5%AD%90%E3%80%8C%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%80%A7%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%9F%E3%81%9B%E3%81%9F%E9%99%B3%E5%88%97%E3%81%8C%E5%8F%8A%E3%81%BC%E3%81%99%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E6%84%8F%E5%9B%B3%E3%81%A8%E5%86%8D%E6%9D%A5%E5%BA%97%E6%84%8F%E5%90%91%E3%81%AB%E5%8F%8A%E3%81%BC%E3%81%99%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%83%BC%E3%80%8D.pdf
- セレンディピティ – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%94%E3%83%86%E3%82%A3
- 成功者の絶対法則 セレンディピティ “偶然のひらめき”は、失敗のあとにやってくる, https://www.toppoint.jp/library/20061108
- 「文喫」「箱根本箱」を手がけたチームの次なる挑戦。遊休施設を活用して – 公共R不動産, https://www.realpublicestate.jp/post/hiraku/
- 書店店員のお仕事とは?業務内容や身につくスキル、どんな資格や経験がいかせるの?[パコラ職種図鑑] – 【公式】福岡の求人広告は株式会社パコラ, https://www.pacola.co.jp/occupation-encyclopedia0187/
- オペレーション科学(柴田書店) – 実用 電子書籍無料試し読み・まとめ買いならBOOK WALKER, https://bookwalker.jp/series/354927/
- オペレーション科学 – 丸善ジュンク堂書店ネットストア, https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784388154524
- 生産性の向上が組織を変える!ブックエースの取り組み – ほんのひきだし, https://hon-hikidashi.jp/bookstore/6576/
- オペレーション科学 – 柴田書店, https://www.shibatashoten.co.jp/detail.php?bid=01545200
- バリューチェーン分析の活用法(VRIO分析) – 誰でもコンサルタント, http://www.darecon.com/tool/valuechain3.html
- VRIO分析のやり方は4ステップで覚えよう!活用事例と合わせて解説 – マップマーケティング, https://www.mapmarketing.co.jp/mm-blog/bunseki/vrio-bunnseki-yarikata/
- VRIO分析とは?創業・起業したい人必見! – 創業羅針盤Blog, https://startup-station.jp/tn/blog/vrio-bunseki/
- 中期経営計画の策定に関するお知らせ – トップカルチャー, https://www.topculture.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/20210715%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E7%AD%96%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf
- 本屋B&B店主 内沼晋太郎が語る。「活字離れ世代」だった私が、街の本屋を始めた理由 – American Express, https://www.americanexpress.com/ja-jp/business/trends-and-insights/articles/why-bookstore-b-and-b-owner-shintaro-uchinuma-founded-the-bookstore-in-town/
- 内沼晋太郎さんが長野に移住して考えた「暮らし」の最適解 – HOOK, https://fukushima-hook.jp/column-uchinuma/
- 経営者が語る、逆境の書店経営に必要な「3つ」の視点とは – オルタナ, https://www.alterna.co.jp/153873/
- 【イベント予告!】6/12(木) 「ビールとともに考える、まちづくり/ローカルの最前線」@本屋B&B, https://note.com/bibibidaikanyama/n/n8541f9e754e8
- TSUTAYA、書籍すべてで返品率制限買い切りを提案 – The Bunka News デジタル, https://www.bunkanews.jp/article/205627/
- 【決算】CCC 単体純利益51億円超 特益で120億円弱 連結最終損益は一転赤字に – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/428021/
- 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ – トップカルチャー, https://www.topculture.co.jp/wp-content/uploads/2024/07/20240702%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf
- 決算特集:カルチュア・コンビニエンス・クラブ(〜2021年) – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/kakokessan/kessan-ccc
- 「【リユース店 モデル分析 Vol.10】書肆スーベニア、「気の利いたブックオフ」意識」, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_8345.php
- 40 YEARS of CCC HISTORY|CCC40周年サイト|CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社, https://www.ccc.co.jp/40th/history/
- AI需要予測でビジネスを加速!ローソンやイトーヨーカドーの成功事例に学ぶ, https://bdlab.or.jp/lab/%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BA%88%E6%B8%AC-ai
- 太田出版単行本でARを活用光和コンピューター「ミライルーペ」, https://kowa-com.jp/case/oota-syutupan/
- ARを新聞・雑誌の広告枠に活用する事例 | AR(拡張現実)コンテンツが簡単に制作できる「COCOAR (ココアル)」, https://www.coco-ar.jp/activation/publisher/advertisement/
- ニュージーランド発「飛び出す小説」! 子どもに、豊かな読書経験を与えてくれるAR児童小説とは?, https://www.shinga-farm.com/study/ar-kids-novels/
- 体験型コミュニケーションの最前線。ARを使った集客&広告事例まとめ | PR EDGE, https://predge.jp/303075/
- 紙媒体を拡張するAR技術やアクリルスタンドを用いた販促の可能性 – note, https://note.com/komatsugeneral/n/n28d637d42269
- 書店員研修:出版社新入社員の書店研修|あかりbooks – note, https://note.com/akari77/n/n55e62cad08e6
- ROIとは?計算式やROASとの違い、ROI改善・向上のポイントを解説 | CXin(シーエックスイン), https://coorum.jp/cxin/column/roi-tips/
- 現代の小売業をマスターする:ROI重視のコンポーザブルコマースへの道 | Ecommerce Fastlane, https://ecommercefastlane.com/ja/mastering-modern-retail-the-roi-driven-journey-to-composable-commerce/