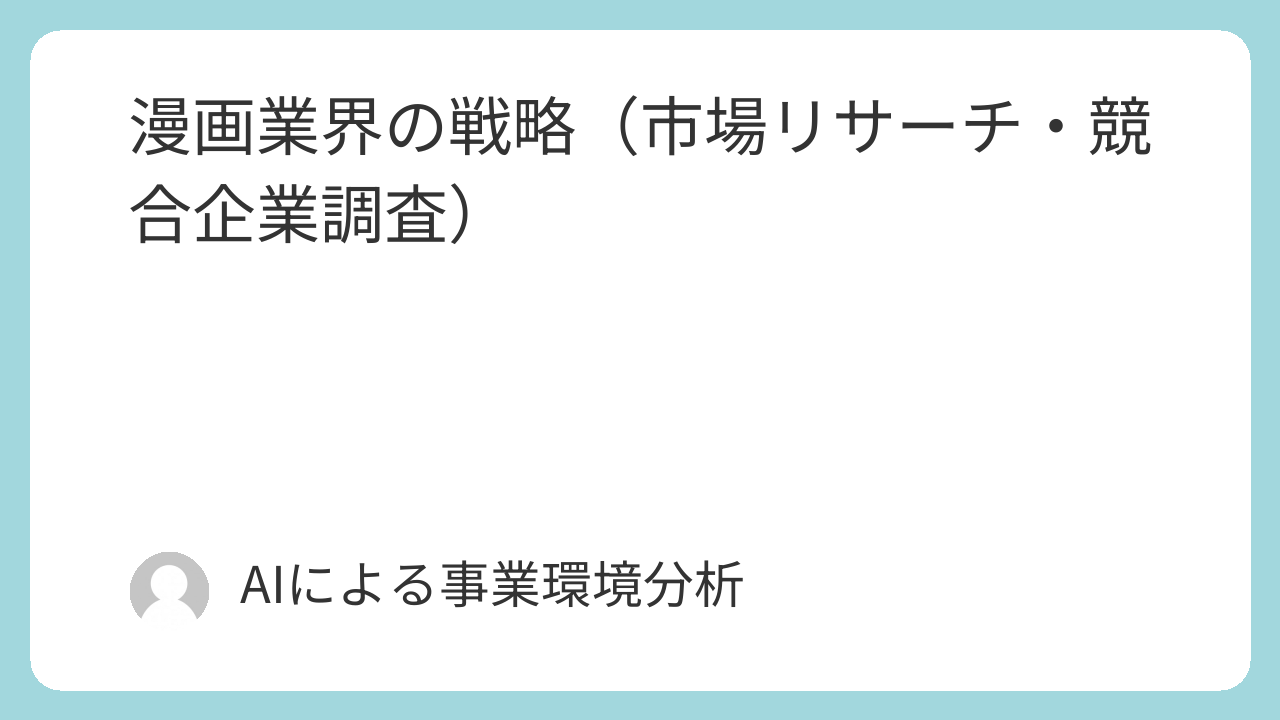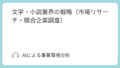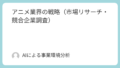IP新大陸の航海図:AIとWebtoonが再定義する漫画ビジネスの未来戦略
- 第1章:エグゼクティブサマリー
- 第2章:市場概観(Market Overview)
- 第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
- 第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
- 第5章:バリューチェーンとエコシステム分析
- 第6章:顧客需要の特性分析
- 第7章:業界の内部環境分析
- 第8章:AIの影響とインパクト(特別章)
- 第9章:主要トレンドと未来予測
- 第10章:主要プレイヤーの戦略分析
- 第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
- 第12章:付録
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、日本の漫画業界が直面する複合的かつ不可逆的な地殻変動を多角的に分析し、この変革期において持続可能な成長を達成するための事業戦略を提言することを目的とする。業界は今、①紙媒体からデジタルプラットフォーム(マンガアプリ、Webtoon)への移行、②国境を越えたリアルタイムでのグローバル競争の激化、③深刻な収益機会の損失をもたらす海賊版の蔓延、そして④生成AIによる制作・流通プロセスの根底からの変革という、四つの巨大な波に同時に晒されている。
本調査の範囲は、伝統的な紙媒体の漫画雑誌・単行本の出版事業から、電子コミック配信、マンガアプリおよびWebtoonプラットフォームの運営、さらにはそれらから派生するライセンス許諾、アニメ化、ゲーム化といったメディアミックス事業まで、漫画IP(知的財産)に関連するバリューチェーン全体を包括する。
最も重要な結論
日本の漫画市場は、電子コミック市場の拡大に牽引され、2023年には約7,000億円規模に達し、過去最高を更新し続けている 1。しかし、その成長率は年々鈍化しており、市場は単純な「量的拡大」フェーズから、ユーザーエンゲージメントとIPの価値を最大化する「質的競争」フェーズへと明確に移行している。
この新たな競争環境において、将来の勝者と敗者を分ける決定的な要因は、以下の三つの経営能力(ケイパビリティ)に集約される。
- グローバル・トランスメディアIP開発力: 企画初期段階からグローバル市場でのヒットと、アニメ、ゲーム、実写化など多角的なメディア展開(トランスメディア)を前提としたIPを戦略的にプロデュースする能力。
- プラットフォーム運営能力: 顧客接点を押さえ、膨大なユーザーデータを分析・活用することで、コンテンツのパーソナライゼーション、効果的なマーケティング、中毒性の高い課金モデルの設計を行い、ユーザーエンゲージメントとLTV(顧客生涯価値)を最大化する能力。
- テクノロジー適応力: 生成AIに代表される破壊的技術を、単なる効率化ツールとしてではなく、事業モデルを変革する戦略的アセットとして捉え、制作・翻訳・マーケティングの各プロセスへ迅速かつ的確に導入・活用する能力。
主要な推奨事項
上記の分析に基づき、取るべき事業戦略上の主要な推奨事項を以下に提示する。
- IP開発モデルの変革:「IPプロデュース・ユニット」の設立
企画初期段階からグローバル市場の需要とトランスメディア展開の可能性を評価する、事業横断的な専門組織を設立する。データアナリスト、海外マーケティング担当、編集者、ライセンス担当者で構成され、データに基づいたIP創出と価値最大化のブループリント策定を主導する。これにより、国内市場の経験則に依存したIP開発から脱却する。 - Webtoon事業への戦略的投資:二兎を追う「ハイブリッド戦略」
既存の強力なIPをWebtoonフォーマットへ展開し、短期的な収益化を図ると同時に、WebtoonネイティブのオリジナルIPを開発するスタジオを設立またはM&Aにより獲得する。スマートフォンに最適化されたUI/UXと課金モデルの研究開発に投資し、次世代のグローバルスタンダードフォーマットにおける主導権獲得を目指す。 - AI技術の戦略的導入とリスク管理体制の構築
制作工程(背景作画、着彩、多言語翻訳)の効率化と、マーケティング(パーソナライズド・レコメンデーション、広告クリエイティブ自動生成)の高度化を目的としたAIツールの全社的な導入を本格化する。同時に、AI生成物の著作権侵害リスクに対応するため、法務・知財部門を中心とした専門チームを組織し、明確な「AI利用ガイドライン」を策定・運用する。 - クリエイターエコノミーの構築による才能の確保
クリエイターが直接読者に作品を届け、収益化するD2C(Direct to Creator)モデルの潮流に対応する。クリエイターへの収益分配率の改善、詳細な実売データの提供、創作活動に集中できる環境支援などをパッケージ化した新たなパートナーシッププログラムを構築し、才能あるクリエイターの流出を防ぎ、新たな才能を引きつける魅力的なエコシステムを構築する。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本および世界の漫画市場規模と今後の予測(2018年~2028年)
日本の漫画市場は、構造的な変革期にありながらも、デジタル領域の力強い成長に支えられ、拡大を続けている。しかし、その内実と将来展望は、媒体によって大きく異なる様相を呈している。
日本の市場動向:デジタル主導の成長と紙媒体の急減速
出版科学研究所の調査によると、紙と電子を合算した日本のコミック市場は7年連続で成長し、2024年には推定販売金額7,043億円(前年比1.5%増)に達し、初めて7,000億円の大台を突破した 1。この成長は、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う巣ごもり需要を契機に加速し、市場は過去最高規模を更新し続けている 4。
しかし、この成長は完全に電子コミック市場によってもたらされている。2024年の電子コミック市場は5,122億円(同6.0%増)と堅調に推移し、コミック市場全体に占める割合は72.7%に達した 1。これは、5年前の2019年からほぼ倍増した規模であり、デジタルへのシフトがいかに急激であったかを示している 3。インプレス総合研究所の調査でも同様の傾向が確認されており、2024年度の電子コミック市場は5,878億円と推計されている 7。
一方で、紙媒体の市場は深刻な縮小局面に直面している。2024年の紙のコミック市場(単行本と雑誌の合計)は1,921億円(同8.8%減)と大幅に落ち込んだ 3。特にコミックス(単行本)は3年連続の大幅減、コミック誌は休刊が相次ぎ、長期的な減少トレンドに歯止めがかかっていない 1。これは、読者のコンテンツ消費の主戦場が、物理的な書店や雑誌から、スマートフォン上のアプリへと不可逆的に移行したことを明確に物語っている。
重要な点は、市場全体の成長率が鈍化していることである。2020年の前年比23.0%増という驚異的な成長 5 から、2022年には0.2%増 9、2023年には2.5%増 2、そして2024年には1.5%増 1 と、成長の勢いは明らかに落ち着きを見せている。これは、コロナ特需の終焉と国内市場の飽和を示唆しており、今後の成長は新たな付加価値の創出や海外市場の開拓にかかっていることを示している。
世界の市場動向:Webtoonが牽引するグローバルな拡大
世界の漫画・コミック市場は2021年時点で約1兆1,800億円規模と推定されており、安定した成長を続けている 11。このグローバル市場の成長を強力に牽引しているのが、スマートフォンでの閲覧に最適化された縦スクロール・フルカラー形式の「Webtoon(ウェブトゥーン)」である。
世界のWebtoon市場規模は、2023年の40億9,300万米ドルから、2030年には54億8,420万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)5.58%で成長すると予測されている 12。また、より広範なウェブコミック市場全体では、2024年の76億3,000万米ドルから2032年には130億4,000万米ドルへと、CAGR 6.89%での成長が見込まれている 13。特にアジア太平洋地域が最大の市場であり、人口の多さとインターネット普及率の高さが成長を後押ししている 13。
このWebtoonフォーマットの台頭は、日本の漫画業界にとって大きな機会であると同時に、韓国のプラットフォーマー(NAVER、カカオ)が市場を席巻しているという脅威でもある。日本の漫画コンテンツがグローバルでさらなる成長を遂げるためには、この新しいフォーマットへの適応が不可欠である。
以下の表は、日本および世界の漫画市場規模の推移と将来予測をまとめたものである。日本の電子市場におけるWebtoon/アプリ課金の正確な内訳は統計データとして存在しないが、インプレス総合研究所の推定(2022年度時点で電子コミック市場の約1割がWebtoon)などを参考に、その重要性を認識する必要がある 14。
表1: 日本および世界の漫画市場規模の推移と予測(2018年~2028年, 単位:億円)
| 年 | 日本 紙媒体 | 日本 電子 | 日本 合計 | 世界 合計 (漫画/コミック) | 世界 Webtoon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2,412 15 | 2,002 15 | 4,414 15 | N/A | N/A |
| 2019 | 2,387 16 | 2,593 16 | 4,980 16 | N/A | N/A |
| 2020 | 2,706 8 | 3,420 8 | 6,126 8 | N/A | N/A |
| 2021 | 2,645 17 | 4,114 17 | 6,759 17 | 11,800 11 | N/A |
| 2022 | 2,291 9 | 4,479 9 | 6,770 9 | N/A | N/A |
| 2023 | 2,107 2 | 4,830 2 | 6,937 2 | N/A | 6,140 12 |
| 2024E | 1,921 3 | 5,122 3 | 7,043 3 | N/A | 6,480 |
| 2028E | (1,500) | (6,500) | (8,000) | (14,000) | (7,700) |
注: 2024E以降の数値は、過去のトレンドと調査会社の予測に基づく推計値。世界市場の円換算は1ドル=150円で計算。
出典: 出版科学研究所 1, 経済産業省 11, GII 12
このデータが示す戦略的意味合いは明確である。国内市場はデジタルへの完全移行を前提とし、既存ユーザーからのARPU(ユーザー一人当たり売上)向上を狙う施策が中心となる。一方で、業界全体の持続的な成長を実現するためには、Webtoonを主戦場とするグローバル市場での成功が絶対条件となる。
市場セグメンテーション分析
媒体・フォーマット別
市場は「紙(雑誌・単行本)」と「電子(電子単行本、マンガアプリ、Webtoon)」に大別される。前述の通り、紙市場は構造的な縮小が続く。電子市場内では、従来の単行本をデジタル化したフォーマットに加え、スマートフォンでの「隙間時間」消費に特化したマンガアプリとWebtoonが主流となっている。特に「待てば無料」や「都度課金」といったビジネスモデルを組み合わせたマンガアプリが市場を牽引している。インプレス総合研究所の調査によれば、2022年度の電子コミック市場の約1割がWebtoon作品によるものと推定されており、その存在感は急速に増している 14。
地域別
- 日本: 世界有数の巨大市場であるが、成長は成熟期に入りつつある。
- 北米・欧州: 伝統的に日本の漫画(Manga)が強い市場であり、特にフランスでは2021年にフィジカル漫画市場の55%を日本漫画が占めるなど、高いブランド力を維持している 18。しかし、デジタル化比率は北米で約10%、フランスでは2%と極めて低く、これはWebtoonプラットフォームがデジタルネイティブな読者層を開拓する大きな潜在市場が存在することを意味する 18。
- 韓国・中国: Webtoonの発祥地および巨大市場であり、強力なプラットフォーマー(NAVER、カカオ、Tencent)が存在する。これらの地域への進出は、彼らとの提携または競争を意味する。
ジャンル別
少年漫画(『ONE PIECE』など)が発行部数・売上において依然として市場の中核を成している 19。しかし、デジタルプラットフォームの普及により、読者の嗜好は細分化している。『異世界転生』『悪役令嬢』『BL(ボーイズラブ)』など、特定のニッチなジャンルに特化した作品やアプリが大きな人気を集める傾向が強まっている。これは、マス市場を狙うだけでなく、特定ジャンルの熱狂的なファンコミュニティをターゲットにした戦略の有効性が高まっていることを示唆している。
主要な市場成長ドライバーと阻害要因
市場成長ドライバー
- マンガアプリの普及: 「ピッコマ」「LINEマンガ」に代表されるマンガアプリが、無料話の提供を通じて新たな読者層を開拓し、市場全体のパイを拡大した 11。
- Webtoonの急成長: グローバルでスマートフォンネイティブ世代の支持を集め、新たな市場を創出している。
- メディアミックスの成功: 『【推しの子】』『葬送のフリーレン』など、アニメ化の成功が原作コミックの売上を爆発的に押し上げる好循環が確立されている 2。
- 電子書店・アプリの販売促進: 独占・先行配信や大規模な割引キャンペーン、完結済み作品の掘り起こしなどが電子コミックの売上を押し上げている 2。
市場阻害要因
- 海賊版サイトの蔓延: 最大の阻害要因。ABJ(正規版マーク推進協議会)の推計によれば、2021年における海賊版による「タダ読み」被害額は1兆19億円に達し、同年の正規市場規模(約6,759億円)を遥かに上回る甚大な被害をもたらしている 20。これは、業界全体の収益機会を根こそぎ奪う深刻な問題である。
- 国内市場の縮小: 少子高齢化による人口減少は、長期的に国内市場のパイを縮小させる構造的な課題である。
- 可処分時間の奪い合い: 動画配信サービス、ゲーム、SNSなど、他のエンターテインメントコンテンツとの間で、消費者の限られた可処分時間を奪い合う競争が激化している。
業界の主要KPIベンチマーク分析
主要マンガアプリのMAU(月間アクティブユーザー数)
- 2022年11月時点の調査では、「LINEマンガ」(1,380万人)が1位、「ピッコマ」(1,060万人)が2位となっており、この二大プラットフォームが市場を寡占している状況が続いている 23。3位の「マガポケ」(541万人)以下を大きく引き離しており、プラットフォーマーとしての圧倒的な集客力を示している 23。
主要作品の累計発行部数(紙+電子)
- 『ONE PIECE』が5億1,000万部、『ドラゴンボール』が3億部超など、世界的に認知されたIPは依然として業界の収益基盤として絶大な力を持つ 24。これらのIPは、新規読者の獲得だけでなく、ライセンスやメディアミックスを通じて長期的に安定した収益を生み出す。
電子コミックの課金率(PUR)、ARPU(ユーザー一人当たり売上)
- インプレス総合研究所の調査では、2024年度の有料電子書籍利用率(PURに相当)は17.8%であり、コロナ禍の2021年をピークに4年連続で低下している 7。また、別の調査では利用者の61.5%が無料での利用に留まっているとのデータもあり 26、「待てば無料」モデルが定着する一方で、有料課金へのハードルが高いことがうかがえる。
- ARPU(ユーザー一人当たり売上)を向上させるためには、単にユーザー数を増やすだけでなく、課金率(PUR)を高めること、そして課金ユーザー一人当たりの単価(ARPPU)を高めることが重要となる 27。魅力的な独占コンテンツや、まとめ買いを促すキャンペーン設計がARPU向上の鍵となる。
海外売上高比率(主要出版社別)
- KADOKAWAは、出版事業における海外売上比率が16.5%に達しており、グローバル展開で先行している 30。これは、他の国内出版社が目指すべきベンチマークとなる。多くの出版社にとって海外売上はまだ限定的であり、ここに大きな成長の余地が残されている。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
政治(Politics)
海賊版サイトへの対策と国際連携
漫画業界が直面する最も深刻な政治的課題は、国境を越えて運営される海賊版サイトへの対策である。これらのサイトによる被害額は年間1兆円から2兆円規模と推定され、正規市場の規模を上回る壊滅的な影響を及ぼしている 20。各国政府は著作権法を改正し、違法サイトへのブロッキング措置を導入しているが、運営者が海外のサーバーを利用するため、国内法だけでの取締りには限界がある。
この課題に対し、官民連携による国際的な法執行が重要な戦略となっている。一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は、中国のアリババグループとのMOU締結や、韓国の著作権保護団体との連携など、国際的な協力体制を構築している 33。具体的な成果として、出版社が米国での情報開示手続(DMCAサピーナ)を通じて運営者情報を入手し、それを警察に提供することで摘発に至ったケースや、中国当局との連携により日本向け海賊版サイトを初めて摘発した「漫画BANK」の事例が挙げられる 34。さらに、文化庁は令和6年度予算でAIを活用した海賊版サイトの自動検知・分析システムの実証事業に乗り出しており、技術的な対策も強化されている 35。これらの動きは、海賊版対策が個社の努力だけでは不可能であり、国際的な法的枠組みと技術的手段を組み合わせた包括的なアプローチが不可欠であることを示している。
表現の自由に関する規制
表現の自由は漫画文化の根幹を成すが、国内外で常に規制の圧力に晒されている。国内では、東京都の青少年保護育成条例改正案を巡り、非実在青少年に関する描写が規制対象となる可能性が浮上し、漫画家や出版社から強い反発が起きた歴史がある 37。このような規制は、クリエイターの創作活動を萎縮させ、文化の多様性を損なうリスクをはらむ。
海外展開においては、この問題はさらに複雑化する。特に中国市場では、政治的・社会的なテーマに対する表現規制が極めて厳しく、コンテンツの大幅な改変が求められるか、そもそも展開が不可能となるケースが多い 40。また、国連人権理事会の特別報告者などを通じて、日本の漫画表現が「児童の性的搾取を助長する」といった批判がなされ、それが「外圧」として国内の規制強化に利用される動きも存在する 41。グローバル展開を推進する上で、各国の文化的・政治的背景を理解し、ゾーニング(年齢制限など)を適切に行うローカライズ戦略が不可欠となる。
インボイス制度の影響
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、これまで免税事業者であった多くの個人の漫画家やアシスタントの活動に直接的な影響を与えている。出版社などの課税事業者は、仕入税額控除を受けるために取引相手から適格請求書の発行を求める。そのため、インボイス登録を行わない免税事業者は、取引の継続が困難になったり、消費税分の値下げを要求されたりする可能性がある 42。
日本漫画家協会は、この制度がクリエイターの事務負担を増大させ、出版社との関係を悪化させる可能性があるとして反対を表明している 42。また、適格請求書発行事業者になると、国税庁の公表サイトで本名が公開されるため、ペンネームで活動するクリエイターのプライバシー問題も指摘されている 42。この制度は、漫画制作のサプライチェーンを支える個々のクリエイターの経済的基盤を揺るがし、長期的には人材確保や業界全体の活力に影響を及ぼすリスクを内包している。
経済(Economy)
可処分所得とエンターテインメント支出
漫画を含むエンターテインメントへの支出は、家計の可処分所得の動向に大きく左右される。景気後退期や物価上昇局面で可処分所得が減少すれば、消費者は娯楽費を削減する傾向にある 44。このような経済環境下では、高価な紙の単行本よりも、無料で楽しめる範囲が広い、あるいは少額課金で楽しめるマンガアプリやWebtoonが選好されやすくなる。特に「待てば無料」モデルは、可処分所得が低い若年層や景気に敏感な消費者層にとって魅力的な選択肢となり、経済状況の変化に対する耐性が比較的高いビジネスモデルと言える。
為替レートの変動
グローバル展開を加速する漫画業界にとって、為替レートの変動は収益とコストの両面に影響を及ぼす。円安局面では、海外でのライセンス収入や電子配信の売上を円換算した際の手取り額が増加し、収益を押し上げる効果がある。大手出版社にとって、これは大きな追い風となる。一方で、Webtoon制作を韓国などの海外スタジオに委託している場合、円安は制作コストの上昇に直結する。また、AppleやGoogleなどの海外プラットフォームに支払う手数料も、円ベースでは増加することになる。為替リスクをヘッジするための財務戦略や、制作拠点の多角化などが今後の経営課題となる可能性がある。
社会(Society)
「推し活」文化とSNSによるヒットプロセスの変容
現代のヒット創出において、SNSと「推し活」文化は切り離せない要素となっている。矢野経済研究所の調査によれば、「オタク」市場の中でも「アニメ」は最大のボリュームゾーンであり、その経済効果は3,000億円規模に達する 45。ファンが特定のキャラクターや作品(=推し)を応援するために時間やお金を費やす「推し活」は、単なるコンテンツ消費に留まらず、グッズ購入、イベント参加、聖地巡礼といった多岐にわたる消費行動を誘発する 46。この市場全体の規模は年間3.5兆円に達するとの試算もある 47。
この「推し活」を加速させるのがSNSである。X(旧Twitter)やTikTok、Instagramなどでファンが作品の感想やファンアートを共有することで「バズ」(バイラルヒット)が生まれ、それが新たなファンを獲得し、マンガアプリでの閲覧や単行本の購入に繋がるというプロセスが常態化している 49。これは、かつて漫画雑誌が担っていた「話題の創出」と「コミュニティ形成」の機能が、SNSへと移行したことを意味する。したがって、現代のマーケティング戦略は、SNS上での拡散性やファンコミュニティの熱量をいかに設計・醸成するかが成功の鍵となる。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)との共存
二次創作やファンアートといったUGC(ユーザー生成コンテンツ)は、ファンコミュニティを活性化させ、IPのエンゲージメントを深める上で重要な役割を果たしている。ファンによる自発的な創作活動は、IPの世界観を豊かにし、その寿命を延ばす効果がある。しかし、これらの活動は著作権法上「グレーゾーン」に位置づけられることが多く、無秩序な展開は公式のビジネス(特にグッズ販売など)と競合したり、作品のブランドイメージを損なったりするリスクも伴う 51。
この課題に対し、近年では権利者側が公式に「二次創作ガイドライン」を策定し、ファン活動として許容される範囲を明示する動きが広がっている 52。これにより、ファンは安心して創作活動を行えるようになり、権利者側はUGCのポジティブな効果を享受しつつ、ブランドイメージをコントロールすることが可能になる。ファンコミュニティとの建設的な関係構築は、IPを長期的に育成する上で不可欠な戦略である。
多様性(D&I)とポリティカル・コレクトネスへの要請
グローバル市場でコンテンツを展開する上で、多様性(ダイバーシティ)や包括性(インクルージョン)への配慮は、もはや倫理的な要請であるだけでなく、ビジネス上の必須要件となっている。人種、ジェンダー、性的指向、障がいの有無など、様々な背景を持つキャラクターを肯定的に描くことは、幅広い読者からの共感を獲得し、社会的な受容性を高める上で重要である 55。
しかし、この動きは「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」への過剰な配慮という形で、創作活動に負の影響を与える側面も持つ。原作の文脈を無視したキャラクター設定の変更や、特定の価値観を押し付けるような表現は、既存のファンからの反発を招き、「ポリコレ疲れ」といった批判を生むことがある 56。特に、歴史的背景や文化的な機微に関わる表現は、炎上のリスクを常に伴う。クリエイターと出版社は、社会的な要請に応えつつも、物語の本質的な面白さや表現の自由を損なわない、絶妙なバランス感覚を求められている。
技術(Technology)
Webtoonプラットフォームの優位性
Webtoonの成功は、その技術的な基盤であるプラットフォームの優位性に起因する。第一に、上から下へスクロールするだけのUI/UXは、スマートフォンでの片手操作に最適化されており、ユーザーの閲覧体験を極めてスムーズにしている 59。日本の伝統的な見開き・コマ割り漫画をスマートフォンで読む際に生じる、拡大・縮小・移動といった煩雑な操作を不要にした。第二に、「待てば無料」というビジネスモデルは、無料でコンテンツを楽しみたいユーザーを大量に引きつけ、習慣的なアプリ起動を促す。そして、待ち時間を短縮したい、あるいは最新話をすぐに読みたいという欲求を喚起し、少額課金へと巧みに誘導する。この中毒性の高いUXと課金モデルの組み合わせが、Webtoonプラットフォームの競争力の源泉である。
ブロックチェーン/NFTの可能性
ブロックチェーン技術と、それを用いたNFT(非代替性トークン)は、デジタルコンテンツの所有と流通に新たな可能性をもたらす。現状の電子書籍は、ユーザーが購入しているのはコンテンツの「利用権」であり、プラットフォームのサービスが終了すれば読めなくなるリスクがある。これに対し、NFTはデジタルデータに唯一無二の所有権を証明するしるしを付与することができる。
これを活用し、集英社は「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」プロジェクトで、漫画の1ページをアート作品としてNFT化し、販売する試みを開始した 60。他にも、『北斗の拳』や『鉄腕アトム』といった著名なIPでもNFTが活用されている 61。将来的には、限定カバー付きのNFT電子単行本の発行や、二次流通市場でのロイヤリティ収益の確保、さらには海賊版対策として正規版であることを証明する手段としての活用も期待される。まだ実験的な段階ではあるが、デジタルコンテンツに「所有」という新たな価値を付与する技術として、その動向を注視する必要がある。
AI翻訳によるグローバル同時展開
AI技術の進化、特に機械翻訳の精度向上は、グローバル展開のスピードとコスト構造を劇的に変える可能性を秘めている 62。従来、漫画の海外展開は、各国の出版社とライセンス契約を結び、現地の翻訳者やデザイナーが数ヶ月から1年以上かけてローカライズを行うのが一般的であった。このタイムラグが、ファンによる違法な翻訳版(スキャンレーション)が流通する原因となっていた。
しかし、AI翻訳の精度が向上し、漫画特有のオノマトペや文脈に応じた訳し分けが可能になれば、翻訳プロセスは大幅に短縮・低コスト化される。これにより、日本での公開とほぼ同時に、多言語でグローバルにサイマル配信(同時展開)することが現実的な戦略となる 64。これは、海外の海賊版サイトに先行して正規版を届けることを可能にし、海賊版対策として極めて有効な手段となりうる。
法規制(Legal)
著作権法:AIと二次創作
技術革新は、著作権法の解釈に新たな課題を突きつけている。最大の論点は、生成AIと著作権の関係である。日本の著作権法第30条の4では、著作物に表現された思想・感情の享受を目的としない場合、情報解析のために著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められている 65。これにより、AIが学習データとして大量の既存漫画を読み込む行為は、原則として適法と解釈されている。
しかし、問題はAIが生成した成果物である。文化庁の見解によれば、AI生成物が既存の著作物との「類似性」(表現が似ていること)と「依拠性」(元にして創作したこと)の両方を満たす場合、通常の著作権侵害と同様に扱われる 67。特定の作家の画風を模倣するよう指示して生成した場合などは、依拠性が認められやすく、法的リスクが高い。また、AI生成物自体の著作権は、AIが自動で生成しただけでは発生せず、人間の「創作的寄与」が認められる場合に限り、その人間に著作権が発生すると考えられている 66。この領域は判例の蓄積が乏しく、企業がAIを利用する際には、法務・知財部門による慎重なリスク評価が不可欠である。
独占禁止法:プラットフォーマーによる優越的地位の濫用
マンガアプリ市場が「ピッコマ」「LINEマンガ」などの巨大プラットフォーマーに寡占される中で、独占禁止法上の懸念が浮上している。公正取引委員会は、AppleやGoogleなどのアプリストア運営事業者が、アプリ内での決済システムの利用を強制し、高額な手数料(通常30%)を徴収する行為が、「優越的地位の濫用」に該当する可能性があると指摘している 71。同様の懸念は、マンガアプリプラットフォーマーと出版社・クリエイターとの間の取引にも当てはまる可能性がある。プラットフォーマーが不当に低い料率を強いたり、不利な取引条件を一方的に課したりする場合、独禁法違反と判断されるリスクがある 73。
環境(Environment)
紙媒体の環境負荷と社会的要請
持続可能性(サステナビリティ)への関心が世界的に高まる中、紙媒体を扱う出版業界も環境負荷への配慮を求められている。紙の生産には大量の木材、水、エネルギーが必要であり、製造・流通・廃棄の各段階でCO2を排出する。これに対し、適切に管理された森林からの木材を使用した製品であることを示すFSC(森林管理協議会)認証紙の利用が、環境配慮の重要な指標となっている 74。日本の製紙業界でもFSC認証材の利用は進んでおり、その割合は20%強で推移している 75。
電子書籍は、物理的な製造・流通が不要なため環境に優しいというイメージがあるが、一方でリーダー端末の製造やデータセンターの電力消費といった環境負荷も存在する。ライフサイクルアセスメント(LCA)による比較では、端末1台の製造・廃棄に伴うCO2排出量は大きいものの、年間にある一定冊数(例えば10冊)以上を読む場合は、紙の本よりも電子書籍の方が総CO2排出量は少なくなるとの試算もある 76。企業のCSR(企業の社会的責任)活動として、環境負荷の低減に向けた取り組み(FSC認証紙の積極利用、サプライチェーンの効率化など)は、企業イメージの向上と投資家からの評価に繋がる可能性がある。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
漫画業界の収益性と競争の力学を理解するため、マイケル・ポーターのFive Forcesフレームワークを用いて業界構造を分析する。結論から言えば、漫画業界は「買い手の交渉力」と「代替品の脅威」が極めて強く、業界内の競争も熾烈であるため、収益性が圧迫されやすい構造にある。
供給者の交渉力:中〜高
供給者とは、コンテンツの源泉であるクリエイターや制作スタジオを指す。彼らの交渉力は、その代替可能性によって大きく異なる。
- カリスマ的な人気漫画家: 『ONE PIECE』の尾田栄一郎氏や『ドラゴンボール』の鳥山明氏(故人)のような、世界的な知名度と巨大なファンダムを持つ作家は、代替不可能な存在である。彼らが創出するIPは出版社の収益の根幹を成すため、出版社に対する交渉力は極めて強い。印税率は通常、単行本の定価の8%〜10%が標準とされるが 78、トップクラスの作家はアニメ化や商品化に関する契約条件においても優位な立場を確保できる。
- 有力なWebtoonスタジオ: Webtoonの制作は、原作、ネーム、線画、着彩、背景といった工程を分業するスタジオモデルが主流である。このモデルにおいて、ヒット作品を安定的に生み出すためのクリエイターネットワークと制作管理ノウハウを持つ有力スタジオ(例:ソラジマ)は、プラットフォームにとって重要な供給者となる。プラットフォーム間の競争が激化する中で、有力スタジオはより良い条件(収益分配率など)を求めて交渉する力を持ちつつある 80。
買い手の交渉力:高
買い手には、最終消費者である「読者」と、流通を担う「書店・プラットフォーマー」が存在する。いずれの交渉力も非常に強い。
- 読者: 現代の消費者は、漫画だけでなく、動画配信サービス(Netflix、YouTube)、モバイルゲーム、SNS、VTuberなど、無数のエンターテインメントコンテンツにアクセス可能である 81。これらの代替品へのスイッチングコストは実質的にゼロであり、一つのコンテンツが面白くなければ、すぐに別のコンテンツへと移行してしまう。このため、読者(買い手)の交渉力は極めて高い。
- 書店(リアル/電子): リアル書店の店舗数は1999年の22,296店から2017年には12,526店へと激減しており 83、その影響力は著しく低下している。電子書店は多数存在するが、市場は少数の大手プラットフォームに集約されつつある。
- プラットフォーマー: 「ピッコマ」「LINEマンガ」のようなマンガアプリ運営企業は、数百万から一千万を超えるユーザーベースと、彼らの閲覧・購買データを独占している。この顧客接点とデータが、出版社に対する圧倒的な交渉力の源泉となっている。プラットフォーマーは、どの作品をトップページで推薦するか、どのようなキャンペーンを実施するかを決定する権限を持ち、それが作品のヒットを大きく左右する。出版社はプラットフォームへのコンテンツ提供を拒否することが困難であり、収益分配(手数料)に関してもプラットフォーマーが優位な立場にある 84。
新規参入の脅威:高
漫画業界、特にデジタル領域への参入障壁は比較的低く、新規参入の脅威は常に高いレベルにある。
- IT企業の参入: DMM、Cygames、and factoryなど、豊富な資金力、技術力、そして既存のユーザーベースを持つIT企業が、マンガアプリ市場へ次々と参入している 86。彼らはデータ分析やデジタルマーケティングに長けており、従来の出版社のビジネスモデルを脅かす存在となっている。
- 韓国系Webtoonスタジオ・プラットフォーマー: NAVER(LINEマンガの親会社)やカカオ(ピッコマの親会社)といった韓国の巨大IT企業は、Webtoonというグローバルスタンダードとなりつつあるフォーマットを武器に、日本市場での支配力を強めている 89。彼らはコンテンツ制作からプラットフォーム運営までを垂直統合しており、強力な競争相手である。
- SNS発の個人クリエイター: X(旧Twitter)やpixivといったSNSプラットフォームで人気を得たクリエイターが、出版社を介さずに直接ファンに作品を届け、クラウドファンディングやD2Cプラットフォーム(例:コミチ)を通じてマネタイズする事例が増えている 91。これは、才能の発掘と育成という出版社の伝統的な役割(ゲートキーパー機能)をバイパスする動きであり、長期的に業界構造を変化させる脅威となりうる。
代替品の脅威:非常に高い
漫画業界にとって最大の脅威は、他の漫画作品ではなく、消費者の「可処分時間(アテンション)」を奪うあらゆるエンターテインメントである。
- 動画配信サービス: NetflixやAmazon Prime Videoなどの定額制動画配信サービスは、アニメ、ドラマ、映画など膨大なコンテンツを提供しており、特に若年層のアニメ視聴の主要な手段となっている 93。
- ゲーム: 日本のモバイルゲーム市場は2022年に約1.5兆円規模に達し 95、世界的に見ても収益性の高い巨大市場である 96。没入感の高いゲーム体験は、ユーザーの時間を長時間にわたって拘束する。
- SNS、ショート動画: TikTokやYouTubeショートに代表されるショート動画プラットフォームは、短い時間で次々と新しい刺激を提供するUXで、特にZ世代の可処分時間を占有している。
これらの代替品は、いずれも巨額の投資によって高品質なコンテンツを大量に供給しており、漫画は常にこれらのコンテンツとユーザーの時間を奪い合う厳しい競争に晒されている。この競争環境は、漫画が単に「面白い物語」であるだけでは不十分であり、いかにユーザーの生活に食い込み、習慣化させるかという「体験設計」が重要であることを示唆している。
業界内の競争:非常に高い
業界内の既存企業間の競争も極めて激しい。
- 大手出版社間の競争: 集英社、講談社、小学館、KADOKAWAといった大手出版社は、常に新しいヒットIPを創出するための競争を繰り広げている。各社は自社の看板作品を抱えるマンガアプリ(少年ジャンプ+、マガジンポケットなど)を運営し、ユーザーの囲い込みを図っている 97。
- マンガアプリプラットフォーマー間の競争: 「ピッコマ」と「LINEマンガ」の二強が、大規模な広告宣伝、独占配信コンテンツの獲得、お得なキャンペーンの実施などを通じて、熾烈なユーザー獲得競争を展開している 99。
- Webtoonスタジオ間の競争: Webtoon市場の拡大に伴い、制作を担うスタジオ間の競争も激化している。ヒット作を生み出すためには、優秀な原作作家、線画担当、着彩担当といった専門クリエイターの確保が不可欠であり、スタジオは待遇改善や働きやすい環境の提供を通じて、クリエイターの獲得・囲い込みに注力している 101。
第5章:バリューチェーンとエコシステム分析
漫画業界の競争優位の源泉と、デジタル化によってそれがどう変化しているかを理解するため、バリューチェーン(価値連鎖)とエコシステムの構造を分析する。
バリューチェーン分析
漫画ビジネスのバリューチェーンは、伝統的な紙媒体モデルからデジタル/Webtoonモデルへと移行する中で、価値が創出されるポイントが劇的に変化している。
伝統的バリューチェーン
伝統的なモデルは、直線的で物理的な制約の多いプロセスであった。
企画 → 制作(作家・アシスタント) → 編集 → 印刷・製本 → 取次 → 書店 → 販売 → ライセンス
このチェーンにおける価値の源泉は、以下の点に集中していた。
- 個人の才能: 漫画家の独創的なアイデアと画力、そしてそれを支えるアシスタントの技術。
- 強力な編集部: 才能ある新人作家を発掘し、伴走しながら作品の質を高め、ヒットへと導く編集者の目利きと育成能力。
- 流通網の支配: 印刷会社、取次、全国の書店網という物理的な流通チャネルを確保していることが、参入障壁として機能していた。
このモデルでは、読者の反応は単行本の売上やファンレターといった限定的な情報でしか把握できず、データに基づいた迅速な意思決定は困難であった。
デジタル/Webtoonのバリューチェーン
デジタル化、特にWebtoonの台頭は、バリューチェーンを根本から再構築した。
企画(データ分析) → 制作(スタジオ分業) → プラットフォーム配信 → データ分析・マーケティング → グローバル展開 → トランスメディア
この新しいチェーンでは、価値の源泉が大きくシフトしている。
- データ分析能力: どのジャンルが読まれているか、何話目で読者が離脱するか、どのキャラクターが人気かといった膨大なプラットフォーム上のデータを分析し、ヒットの確度を高める企画立案能力 102。
- プラットフォームの集客力: 数百万、数千万のユーザーを抱えるプラットフォーム自体が、コンテンツの価値を増幅させる最大の装置となる。レコメンデーションエンジンやプロモーション機能がヒットを左右する。
- スタジオ分業による制作効率: 原作、ネーム、線画、背景、着彩といった工程を専門のクリエイターが分業する「スタジオモデル」により、品質を維持しながら週刊連載を安定的に、かつ高速で制作する能力 103。
- グローバルな展開力: デジタル配信により、国境を越えたコンテンツ提供が容易になり、企画段階からグローバル市場を視野に入れた展開が可能になった。AI翻訳などの技術がこれをさらに加速させる。
この変化は、ビジネスの成功要因が、かつての「個の才能と勘」への依存から、「データとシステム、そしてグローバルな展開スピード」へと移行していることを示している。
エコシステム分析
漫画業界は、多様なプレイヤーが相互に依存し合う複雑なエコシステムを形成している。デジタル化はこのエコシステムの力学を大きく変えた。
エコシステムの構成要素
- クリエイター層: 漫画家、アシスタント、Webtoonスタジオの専門クリエイター(原作、作画、着彩など)。
- 出版・プロデュース層: 出版社、編集者、IPプロデューサー。
- 製造・流通層(旧): 印刷会社、取次、リアル書店。
- プラットフォーム層(新): マンガアプリ運営会社、電子書店、Webtoonプラットフォーマー。
- パートナー層: アニメ制作会社、ゲーム開発会社、広告代理店、グッズメーカーなどメディアミックスパートナー。
- 消費者層: 読者、ファンコミュニティ。
日本型「作家と編集者の二人三脚」モデルとWebtoon「スタジオモデル」の比較
- 日本型モデル: 漫画家という一人のクリエイターがストーリーと作画の両方を担当し、編集者がマンツーマンで伴走する徒弟制度的な側面が強い。このモデルは、作家の強い個性が反映された独創的な作品を生み出す源泉となってきた。しかし、その一方で、週刊連載という過酷な労働環境を生み、作家個人の才能と体力に大きく依存するため、サステナビリティやスケーラビリティに課題を抱えている。
- Webtoonスタジオモデル: 映画制作のように、各工程を専門家が分業するシステマティックな制作体制 103。このモデルは、①制作スピードの向上、②品質の安定化、③クリエイターの専門性を活かした分業による労働負荷の軽減、といったメリットをもたらす。これにより、グローバル市場の需要に応えるための大量かつ迅速なコンテンツ供給が可能となる。ただし、分業が進むことで、作品全体としての作家性や統一感が損なわれるリスクもある 104。
「編集者」の役割の変化:伴走者からIPプロデューサーへ
バリューチェーンの変化に伴い、「編集者」に求められる役割も大きく変化している。
- 従来の編集者(伴走者): 才能ある作家を発掘し、対話を通じてその才能を最大限に引き出し、作品のクオリティを高めることに主眼を置いていた。成功は、個々の編集者の経験、勘、そして作家との人間関係に大きく依存していた。
- 新しい編集者(IPプロデューサー): 上記の能力に加え、データ分析に基づいて市場のニーズを的確に捉え、ヒットの確率を高める企画を立案する能力が求められる。さらに、漫画を単体の作品としてではなく、アニメ、ゲーム、グッズなど、多角的な展開を前提とした「IP」として捉え、その価値を最大化するための事業開発やプロデュースを行う視点が必要不可欠となる。これは、クリエイティブな感性とビジネス的な視点を両立させる、より高度で複合的な役割への進化である。この変化に対応できる人材の育成が、出版社の将来を左右する重要な経営課題となっている。
第6章:顧客需要の特性分析
事業戦略を策定する上で、最終顧客である「読者」と、IPを活用するBtoB顧客である「ライセンシー」の需要特性を深く理解することが不可欠である。
読者セグメント分析
漫画読者の行動や嗜好は、フォーマット、課金行動、そして世代によって大きく異なる。
フォーマット別(紙派 vs 電子派)
- 紙派: 調査によれば、電子コミック利用者であっても、漫画は「紙」で読みたいと考える層が半数以上を占める 105。特に10代の若年層でこの傾向が強い 105。これは、単行本を所有することによる満足感、コレクションとしての価値、友人との貸し借りといった、紙媒体ならではの物理的な体験価値を重視しているためと考えられる 106。
- 電子派: 利便性(いつでもどこでも読める)、物理的な保管スペースが不要であること、セールやキャンペーンによる価格的なメリットを重視する層。複数のサービスを併用し、お得な情報を常に探している傾向がある。
課金行動別
- 都度課金・まとめ買い層: 特定の好きな作品に対して、単行本単位でまとめ買いをしたり、最新話をすぐに読むために都度課金を行ったりするロイヤリティの高い層。有料利用者は、利用するサービスを1つに絞る傾向がある 105。
- 毎日コツコツ課金層(待てば無料ユーザー): 複数のマンガアプリを併用し、「待てば無料」の仕組みを最大限に活用して多くの作品を無料で楽しむ層。無料利用者は、4つ以上のサービスを併用する割合が最も高い 105。彼らをいかにして少額でも課金するユーザーへと転換させるかが、アプリ運営の収益化における重要なポイントとなる。調査では、課金のきっかけとして「試し読みで続きが気になったとき」が74.8%と最も多く、無料話による引きが課金へのトリガーとして極めて有効であることを示している 26。
Z世代の消費行動特性
Z世代(1990年代半ばから2010年代生まれ)は、今後の市場を担う中心的な顧客層であり、その消費行動には特有の傾向が見られる。
- 情報収集と認知経路: 彼らにとっての主要な情報源は、テレビや雑誌ではなく、SNS(X, Instagram, TikTok)である 107。友人やインフルエンサーがシェアした情報や、アルゴリズムによってレコメンドされたコンテンツから作品を認知する。「TikTok売れ」に象徴されるように、SNSでのバイラルヒットが消費の大きなきっかけとなる 108。
- タイパ(タイムパフォーマンス)重視: コンテンツ過多の時代において、時間を無駄にしたくないという意識が非常に強い。「失敗したくない」という志向も相まって 109、面白いかどうかわからない作品を最初からじっくり読むことに抵抗を感じる。そのため、SNSで面白いと話題になっている作品や、あらすじやハイライトをまとめた動画を見てから読む作品を決める傾向がある。
- エモ消費と推し活: 機能的な価値だけでなく、「わかる」「楽しい」「悲しい」といった感情的な共感(エモ)を重視する「エモ消費」を行う 110。好きなキャラクターや作品を応援する「推し活」に時間とお金を費やすことを厭わず、それが自己表現の一部にもなっている 109。
- UI/UXへの要求: スマートフォンネイティブであるため、直感的でストレスのないUI/UXを好む。縦スクロール形式のWebtoonは、彼らのコンテンツ消費スタイルに極めて親和性が高い。
これらの特性から、Z世代にアプローチするためには、従来のマス広告ではなく、SNS上での口コミや共感を誘発するようなマーケティング戦略が不可欠である。作品の魅力を短い時間で伝え、感情に訴えかけ、「話題に乗り遅れたくない」という感覚を醸成することが、彼らの消費行動を喚起する鍵となる。
BtoB顧客(ライセンシー)のニーズ分析
漫画IPは、アニメ、ゲーム、映画、グッズなど、多様なメディアへ展開されることでその価値を最大化する。これらのメディアミックスを担うBtoB顧客(ライセンシー)が原作漫画に求める要素は明確である。
- 世界観とキャラクター: ライセンシーが最も重視するのは、多角的な展開が可能な、魅力的で深い世界観と、ファンが感情移入できる強力なキャラクターである。キャラクターの口癖や特徴的なデザインは、グッズ化やSNSでの拡散において重要なフックとなる 111。
- 既存ファンダムの熱量: アニメ化やゲーム化には多額の初期投資が必要となるため、ライセンシーは投資回収のリスクを最小限に抑えたいと考える。そのため、原作が既に一定数の熱狂的なファン(ファンダム)を抱えていることは、プロジェクトの成功確率を測る上で極めて重要な指標となる。発行部数やSNSでの言及数などが、その熱量を測る客観的なデータとして用いられる。
- グローバルな普遍性: 海外展開を視野に入れるライセンシーは、特定の国や文化に依存しすぎない、普遍的なテーマ性や設定を持つ作品を求める。ファンタジーやSFといったジャンルは、文化的な翻訳の障壁が低く、グローバルで受け入れられやすい傾向がある 111。
- アニメ化を意識した原作表現: アニメ制作会社は、映像化しやすい原作を好む。風景やキャラクターの動きが具体的に描写されていること、視覚的に印象的なシーンが盛り込まれていることなどが、アニメ化の企画を後押しする要因となる 111。
出版社やクリエイターは、これらのBtoB顧客のニーズを企画段階から意識することで、メディアミックスの可能性を高め、IP価値の最大化に繋げることができる。
第7章:業界の内部環境分析
外部環境の変化に対応し、持続的な競争優位を築くためには、自社の経営資源や組織能力(ケイパビリティ)を客観的に評価する必要がある。ここでは、VRIOフレームワークを用いて競争優位の源泉を分析し、人材と生産性の観点から業界の内部環境を評価する。
VRIO分析
VRIOは、経営資源やケイパビリティが「経済的価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Inimitability)」「組織(Organization)」の4つの観点から持続的な競争優位の源泉となりうるかを評価するフレームワークである。
- 強力なIPポートフォリオ(例:『ONE PIECE』『ドラゴンボール』)
- 価値 (Value): イエス。これらのIPは、単行本、電子書籍、アニメ、ゲーム、グッズなど多岐にわたる収益源を生み出し、企業のキャッシュフローに大きく貢献する 25。
- 希少性 (Rarity): イエス。世界中で数億部を発行し、数世代にわたって愛されるメガヒットIPは、極めて少数しか存在しない。
- 模倣困難性 (Inimitability): イエス。長年の連載を通じて築き上げられた複雑な世界観、キャラクター間の関係性、そしてファンとの絆は、他社が短期間で模倣することは不可能である。
- 組織 (Organization): イエス。大手出版社は、これらのIPの価値を最大化するために、ライセンス管理、メディアミックス展開、海賊版対策などを専門に行う部門を組織している。
- 結論: 既存の強力なIPポートフォリオは、持続的な競争優位の源泉である。
- 優秀な編集者によるクリエイター発掘・育成システム
- 価値 (Value): イエス。新たなヒットIPを生み出す源泉であり、事業の将来性を担保する上で不可欠な能力である 113。
- 希少性 (Rarity): イエス。長年の経験と実績に裏打ちされた、ヒットを生み出す編集ノウハウを持つ組織は限られている。
- 模倣困難性 (Inimitability): イエス。作家と編集者の信頼関係や、組織内に暗黙知として蓄積された「ヒットの法則」は、言語化やマニュアル化が難しく、模倣困難性が高い。
- 組織 (Organization): 課題あり。 このシステムは伝統的に、紙の雑誌連載を前提とした徒弟制度的な側面が強い。デジタル化、グローバル化、データ活用の時代に対応した組織的な変革(スキルセットの再定義、評価制度の見直しなど)が追いついていない場合、このケイパビリティは陳腐化し、競争優位を失うリスクがある。
- メディアミックスを主導するプロデュース能力
- 価値 (Value): イエス。IPの価値を漫画単体から、アニメ、ゲームなどへ展開し、収益を指数関数的に増大させる上で極めて重要である。
- 希少性 (Rarity): 課題あり。KADOKAWAのように、グループ内にアニメやゲーム事業を持ち、一気通貫でプロデュースできる企業はまだ少数である 115。多くの出版社は、外部のパートナー(製作委員会など)に依存している。
- 模倣困難性 (Inimitability): 課題あり。メディアミックスの成功には多くのステークホルダーとの複雑な交渉と調整が必要であり、成功事例の再現は容易ではないが、資本力のある他業種からの参入者(IT企業など)が優秀なプロデューサーを引き抜き、模倣する可能性はある。
- 組織 (Organization): 最大の課題。 多くの出版社は、編集部、ライツ部、デジタル部などが縦割り組織となっており、IPを軸にした全社横断的な戦略を迅速に実行する体制が整っていない。KADOKAWAが推進する「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略 116 のような、IP価値最大化を目的とした組織設計と権限移譲が行われているかが、持続的な競争優位を確立する上での分水嶺となる。
人材動向
業界の競争力を支える人材の確保と育成は、喫緊の課題である。
- 漫画家・アシスタント:
- 労働環境: 週刊連載を支える漫画家とアシスタントの労働環境は依然として過酷である 118。長時間労働が常態化しており、この労働集約的なモデルが持続可能かについては大きな疑問符がつく 119。
- 収入とキャリアパス: アシスタントの収入は、フリーランスで年収120〜300万円、常駐でも180〜360万円程度が相場であり、専門的なスキルを要する職種としては決して高くない 121。アシスタントから漫画家として独立するキャリアパスが一般的だが、その道は険しく、将来のキャリアに対する不安から人材が他業種へ流出するリスクがある。
- 編集者:
- 求められるスキルの変化: 前述の通り、従来の作品のクオリティ管理能力に加え、データ分析、デジタルマーケティング、SNS運用、海外ライセンス交渉、プロジェクトマネジメントなど、求められるスキルセットが多様化・高度化している。これらのスキルを持つ人材の育成と、外部からの採用が急務である。
- Webtoon制作者:
- 人材不足と育成の課題: Webtoon市場の急拡大に対し、制作を担う専門人材の供給が全く追いついていない 122。特に、フルカラー制作に不可欠な「着彩」や、制作効率を左右する「背景・3Dアセット」のスキルを持つクリエイターは深刻な人手不足にある。ソラジマなどのWebtoonスタジオは、クリエイター育成のためのトライアルプログラムなどを実施しているが 123、業界全体としての人材育成システムの構築が、市場の成長を左右するボトルネックとなっている。
労働生産性
- 伝統的モデルの限界: 漫画家の個人的なスキルと長時間労働に依存する週刊連載モデルは、生産性の観点からは限界に達している。一人の作家が生み出せる作品数には物理的な上限があり、スケールさせることが難しい。
- 生産性向上のドライバー:
- デジタル作画ツール: CLIP STUDIO PAINTなどのデジタル作画ツールの普及は、作画プロセスを大幅に効率化した 124。特に、修正の容易さ、素材の再利用、3Dデータの活用などは、生産性向上に大きく貢献している 124。
- Webtoonスタジオモデル: 分業制は、各クリエイターが自身の専門分野に特化することで、全体の生産性を向上させる。一人の漫画家が全工程を担うよりも、高品質な作品をより速く、安定的に供給することが可能になる。
日本の漫画業界がグローバルなコンテンツ供給競争で勝ち抜くためには、伝統的な職人技的アプローチに固執するのではなく、テクノロジーと新しい生産モデルを積極的に取り入れ、労働生産性を抜本的に向上させることが不可欠である。
第8章:AIの影響とインパクト(特別章)
生成AI(Generative AI)は、漫画業界のあらゆるプロセスを根底から覆す可能性を秘めた、今世紀最大級の技術革新である。その影響は、単なる作業の効率化に留まらず、クリエイティビティのあり方、グローバル展開のスピード、そして著作権の概念そのものに及ぶ。AIを戦略的に活用できるか否かが、今後の企業の競争力を決定づけると言っても過言ではない。
制作プロセスへの影響
作画支援:制作スピードとコストの革命
AIは、漫画制作において最も時間と労力を要する作画工程を劇的に効率化する。
- 背景・小物・モブキャラクター生成: 「東京の夜景」「教室の風景」といった指示(プロンプト)を与えるだけで、AIが高精細な背景画像を瞬時に生成する。これにより、従来アシスタントが数時間から数日かけていた作業が大幅に短縮される 126。これは制作コストの削減に直結し、特に人手不足が深刻なWebtoon制作において、生産性を飛躍的に向上させるゲームチェンジャーとなりうる。
- 着彩・線画抽出: AIによる自動着彩は、フルカラーが標準のWebtoon制作において極めて有効である。また、ラフスケッチから綺麗な線画を抽出する技術も進化しており、作画の負担を軽減する。
ストーリー・ネーム生成:アイデアの触媒
- プロットとアイデアの提案: ChatGPTやNovelAIといった大規模言語モデル(LLM)は、クリエイターが入力したテーマや設定に基づき、ストーリーのプロット、キャラクター設定、セリフのアイデアを複数提案することができる 126。これにより、クリエイターはゼロからアイデアを練る負担が軽減され、創作活動の初期段階で行き詰まることを防げる。
- キャラクターの一貫性維持: 「StoryDiffusion」のような新しい技術は、プロンプトを変えても同一のキャラクターデザインや絵柄を維持したまま、連続したシーンを生成することが可能になってきている 128。これは、AIが断片的なイラストだけでなく、一貫性のある「物語」を生成する能力を持ち始めたことを示唆している。
クリエイティビティへの影響:補助ツールか、脅威か?
現時点において、AIは人間のクリエイティビティを完全に代替する存在ではない。むしろ、面倒な作業を自動化し、人間がより創造的な作業(ストーリーの核心、キャラクターの感情表現など)に集中できるようにする強力な「補助ツール」である 127。AIが提示する予期せぬアイデアが、クリエイターの新たなインスピレーションを刺激する「触媒」としての役割も期待される。
しかし、長期的には、AIが人間のクリエイターの仕事を奪う「脅威」となる可能性も否定できない。特に、特定の画風を学習し、それを模倣した作品を大量に生成するAIは、イラストレーターなどの仕事を直接的に脅かす。企業は、AIを生産性向上のツールとして活用しつつも、クリエイターとの共存関係をいかに築くかという倫理的な課題にも向き合う必要がある。
流通・翻訳プロセスへの影響
AI自動翻訳:グローバル同時展開の実現
AI翻訳の精度向上は、グローバル展開のあり方を根本から変える 62。
- スピードとコストの劇的改善: 従来、数ヶ月を要していた翻訳・ローカライズのプロセスが、AIによって数日から数時間単位に短縮される。これにより、日本の最新話を世界中のファンにほぼ同時に届ける「グローバル・サイマル配信」が、低コストで実現可能になる。集英社は既に、AIスタートアップMantra社と連携し、公式プラットフォーム「MANGA Plus」での多言語サイマル配信を支援する取り組みを開始している 64。
- 海賊版への対抗策: グローバル・サイマル配信は、海外のファンが違法な翻訳版(スキャンレーション)に手を出す最大の理由である「タイムラグ」を解消する。正規版が最速で提供されることは、海賊版サイトの存在価値を低下させ、ユーザーを正規プラットフォームへ誘導する上で最も効果的な対策となる。
海賊版対策:検知・削除の自動化
AIは、広大なインターネット上に蔓延する海賊版サイトの対策においても強力な武器となる。文化庁は、海賊版サイトのレイアウト、広告の種類、掲載されている画像や文字情報などをAIに学習させ、違法サイトを自動的に検知・リストアップするシステムの構築を進めている 35。これにより、従来人手に頼っていた発見・監視作業が大幅に効率化され、権利者が削除申請などの法的措置を迅速に行えるようになることが期待される。
マーケティング・消費への影響
AIによるパーソナライズド・レコメンデーションの高度化
マンガアプリや電子書店は、ユーザーの膨大な閲覧履歴、購入履歴、検索キーワードといったデータを保有している。AIはこれらのデータを解析し、個々のユーザーの嗜好を極めて高い精度で予測する。これに基づき、一人ひとりに最適化された作品を推薦することで、ユーザーエンゲージメントを高め、新たな作品との出会いを創出する。集英社が開発したAI対話型マンガレコメンドサービス「DEAIBOOKS」は、ユーザーとの対話を通じて好みを学習し、最適な作品を提案する先進的な事例である 129。
AIによるプロモーション素材の自動生成
広告クリエイティブの制作においても、AIは大きな変革をもたらす。
- 広告クリエイティブの大量生成: ターゲットとする読者層(性別、年齢、興味など)に合わせて、AIが最適なキャッチコピー、広告バナー、さらにはプロモーション用のショート動画などを複数パターン、自動で生成する 130。
- PDCAサイクルの高速化: 大量に生成された広告クリエイティブを実際に配信し、その効果(クリック率、コンバージョン率など)をAIが分析。効果の高いパターンを学習し、さらに改善されたクリエイティブを生成するというPDCAサイクルを高速で回すことが可能になる。これにより、広告効果の最大化と制作コストの削減を両立できる 131。
法的・倫理的課題
AIの導入は、生産性の向上という大きなメリットをもたらす一方で、深刻な法的・倫理的リスクを伴う「諸刃の剣」である。
著作権の帰属と侵害リスク
- 著作権の所在: AIが自動生成した作品に著作権は発生するのか、発生するとすれば誰に帰属するのか、という問題は未だ法的に確立されていない。文化庁の見解では、プロンプトの入力など、人間の「創作的寄与」が認められる場合に、その人間に著作権が認められる可能性があるとしている 66。しかし、その判断基準は曖昧であり、多くのケースでAI生成物は著作権保護の対象外となる可能性がある。
- 著作権侵害のリスク: AIが学習データに含まれる既存の著作物の表現をそのまま、あるいは酷似した形で出力してしまった場合、その生成物を利用すると著作権侵害(複製権や翻案権の侵害)となる 65。特に、特定の作家の画風を模倣する目的でAIを利用した場合、「依拠性」が認められやすく、訴訟リスクは極めて高い。企業がAIを事業利用する際には、生成物が他者の権利を侵害していないかを確認するプロセスが不可欠となる。
AIによって生成された「絵柄」の類似性
著作権法は具体的な「表現」を保護するものであり、抽象的な「アイデア」や「作風(絵柄)」自体は保護の対象外とされている 67。しかし、AIがある作家の絵柄を極めて精巧に模倣し、誰が見てもその作家の作品と誤認するようなイラストを生成した場合、不正競争防止法や、場合によっては著作者人格権の侵害といった問題に発展する可能性がある。この問題はクリエイターのアイデンティティを脅かすものであり、業界全体で議論とルール作りが必要な領域である。
企業は、AI技術の導入によるメリットを追求すると同時に、これらの法的・倫理的リスクを管理するための体制を構築しなければならない。具体的には、①AIの利用目的と許容範囲を定めた社内ガイドラインの策定、②AI生成物を公開・商用利用する前のリーガルチェックプロセスの確立、③学習データに関する権利情報が明確なAIサービスの選定などが急務である。
第9章:主要トレンドと未来予測
これまでの分析を踏まえ、今後3~5年で漫画業界の事業環境を大きく左右する四つの主要トレンドと、その先の未来像を予測する。
Webtoonのさらなる浸透とフォーマットの融合
Webtoonは、単なる一過性のブームではなく、スマートフォンネイティブ世代にとっての漫画の「デフォルト・フォーマット」として定着する。現在、電子コミック市場の約1割を占めるとされるWebtoonのシェアは、今後さらに拡大を続けると予測される 14。この流れを受け、日本の出版社も既存の人気作品をWebtoonフォーマットで再編集して配信するだけでなく、企画段階からWebtoonとして制作するオリジナル作品の創出を本格化させるだろう。
将来的には、「日本型漫画」と「Webtoon」という二項対立的な構造は薄れ、クリエイターや作品の特性に応じて、見開き表現を活かした伝統的なフォーマットと、縦スクロールの没入感を活かしたフォーマットが柔軟に使い分けられ、相互に影響を与え合う「ハイブリッドな表現」が生まれる可能性もある。
D2C(Direct to Creator)の進展と出版社の役割変革
クリエイターがプラットフォームやSNSを活用し、出版社を介さずに読者に直接作品を届け、収益化するD2C(Direct to Creator)モデルがさらに加速する。pixiv Fanbox、Fantiaといったファンコミュニティプラットフォームや、漫画家自身が作品を販売できる「コミチ」のようなサービス 91 は、クリエイターに新たな収益源とファンとの直接的なエンゲージメントを提供している。
このトレンドは、出版社の伝統的な「ゲートキーパー」としての役割を相対的に低下させる。才能あるクリエイターが出版社に依存する必要性が薄れる中で、出版社は単なる出版・流通の代行者から、クリエイターの活動を多角的に支援する「エージェント」や「ビジネスパートナー」へとその役割を変革せざるを得なくなる。具体的には、複雑な契約管理、メディアミックスのプロデュース、海外展開のサポート、データ分析に基づいたマーケティング支援など、クリエイター個人では難しい付加価値を提供できるかが、出版社が選ばれるための条件となる。
トランスメディア戦略の常態化
「漫画がヒットしたらアニメ化を検討する」という段階的なアプローチは過去のものとなり、企画段階からグローバルでの多角的なメディア展開を前提としたIP開発が業界のスタンダードとなる。この分野で最も先進的なのがKADOKAWAであり、「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、出版、アニメ、ゲーム、教育といった事業部門が連携し、IPの価値を最大化するエコシステムを構築している 115。
このモデルでは、漫画は無数のメディア展開の起点となる「原作IP」であると同時に、アニメやゲームから派生したストーリーを漫画化するなど、エコシステム内の一つのメディア形態として柔軟に位置づけられる。IPの企画段階で、各メディアの特性を活かした展開シナリオや、グローバル市場でのターゲット層を明確に設定することが、ヒットの確率を高める上で不可欠となる。
「読む」から「体験する」へ:エンゲージメントの深化
テクノロジーの進化は、漫画の消費形態を、静的な「読む」行為から、より動的で没入感のある「体験する」行為へと進化させる。
- VR/AR技術の活用: VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を用いることで、読者は漫画の世界に入り込み、キャラクターと同じ空間を共有するような体験が可能になる。例えば、ARアプリを通じて、現実の風景にキャラクターを登場させて一緒に写真を撮ったり、VRヘッドセットを装着して物語の重要なシーンを360度の映像で体験したりといった応用が考えられる。
- メタバース空間でのファンイベント: メタバース(仮想空間)上に作品の世界観を再現し、ファンがアバターとなって集うイベントが開催されるようになる。そこでは、ファン同士の交流だけでなく、作家とのバーチャルサイン会や、作中に登場するアイテムのデジタルグッズ販売など、新たなエンゲージメントとマネタイズの機会が生まれる。
これらの「体験型」コンテンツは、熱量の高いファン(「推し活」層)との関係を深化させ、IPへのロイヤリティを高める上で極めて有効な手段となる。漫画はもはや紙や画面の上だけで完結するものではなく、ファンの生活空間や体験そのものに溶け込んでいくことで、その価値を拡張していく。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
漫画業界のエコシステムは、異なるビジネスモデルと強みを持つ多様なプレイヤーによって構成されている。ここでは、主要なプレイヤーを「伝統的大手出版社」「プラットフォーマー(Webtoon系)」「新興Webtoonスタジオ」「IT系プラットフォーマー」の4つのカテゴリーに分類し、その戦略、強み・弱みを比較分析する。
表2: 主要プレイヤーの戦略プロファイル比較
| プレイヤー | カテゴリー | 主要な強み | 主要な弱み | デジタル/Webtoon戦略 | グローバル戦略 | AIへの取り組み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集英社 | 伝統的大手出版社 | 『ONE PIECE』等、世界最強クラスのIPポートフォリオ。編集力とブランド力。 | 紙媒体への依存度が依然高い。組織の機動性。 | 『少年ジャンプ+』『ゼブラック』運営。デジタルネイティブヒット創出に成功。 | 『MANGA Plus』でサイマル配信を強化。IPの海外展開に積極的。 | 対話型レコメンド「DEAIBOOKS」開発。AI翻訳活用。 |
| 講談社 | 伝統的大手出版社 | 多様なジャンルのIPポートフォリオ。IPライセンスビジネスの実績。 | デジタルネイティブヒットの創出で競合に後れ。 | 『マガポケ』『コミックDAYS』運営。既存IPのデジタル化が中心。 | 欧米での現地法人を通じた出版・ライセンス事業。 | 比較的限定的。制作効率化などを模索。 |
| KADOKAWA | 伝統的大手出版社 | グループ内でのメディアミックス垂直統合。アニメ・ゲーム事業との連携。 | 出版事業単体でのメガヒットIPは競合より少ない。 | 複数アプリ運営。Webtoon事業にも積極投資。 | 「グローバル・メディアミックス」戦略を掲げ、海外売上比率が高い 30。 | 全社的にDXを推進。AI技術の活用を中期経営計画に明記。 |
| カカオピッコマ | プラットフォーマー | 「待てば¥0」モデルの確立。強力なマーケティングとUI/UX。 | コンテンツ創出力は出版社に依存。手数料ビジネスへの批判。 | Webtoonを軸としたプラットフォーム戦略。独占・先行配信でユーザーを囲い込み。 | 韓国カカオグループのグローバル網を活用。欧州等へ進出。 | データ分析に基づく高度なレコメンデーション。 |
| NAVER (LINEマンガ) | プラットフォーマー | LINEの巨大なユーザー基盤。国内トップクラスのMAU。 | ピッコマとの熾烈な競争によるマーケティングコスト増。 | Webtoonプラットフォームのパイオニア。オリジナル作品も多数。 | グローバルで「WEBTOON」ブランドを展開。世界最大のWebtoonプラットフォーム。 | データ分析、パーソナライゼーションに活用。 |
| ソラジマ | 新興Webtoonスタジオ | Webtoonに特化した効率的なスタジオ制作体制。クリエイターネットワーク。 | 資金力、IPの蓄積では大手出版社に劣る。プラットフォームへの依存。 | WebtoonネイティブIPの企画・制作に特化。 | グローバルプラットフォームへのコンテンツ供給が基本戦略。 | 制作プロセスの効率化にAI活用を模索。 |
| コミックシーモア | IT系プラットフォーマー | 20年近い運営実績と国内最大級の会員基盤。NTTグループの信頼性。 | Webtoonなど新フォーマットへの対応で後発。 | 老舗の総合電子書店。ポイント施策などで顧客ロイヤリティを維持 98。 | 限定的。主戦場は国内市場。 | ユーザーデータ分析、レコメンデーションに活用。 |
伝統的大手出版社
- 集英社: 『週刊少年ジャンプ』を核とした圧倒的なブランド力と、『ONE PIECE』『ドラゴンボール』『NARUTO』といった世界的に通用するIP群が最大の経営資源である 132。デジタルシフトにも早くから取り組み、『少年ジャンプ+』からは『SPY×FAMILY』『怪獣8号』といったデジタルネイティブのメガヒットを創出することに成功している。グローバル展開においても、多言語対応の自社プラットフォーム『MANGA Plus by SHUEISHA』を通じて、日本とほぼ同時のサイマル配信を実現し、海外の海賊版対策とファン獲得を両立させている。AI活用にも積極的で、対話型レコメンドサービス「DEAIBOOKS」をリリースするなど 129、テクノロジーへの適応力も高い。課題は、依然として収益構造が紙媒体と少数のメガヒットIPに依存している点であり、事業ポートフォリオの多角化が求められる。
- 講談社: 少年漫画から少女・女性漫画、青年漫画まで、幅広いジャンルに強力なIPポートフォリオを持つことが強み 134。特にIPライセンスビジネスに長年の実績があり、メディアミックス展開に長けている。デジタル領域では『マガジンポケット』などを運営するが、集英社ほどのデジタルネイティブヒットは生まれておらず、既存IPのデジタル化が中心となっている。
- KADOKAWA: 「出版社」という枠を超え、「IP創出企業」としてのポジショニングを明確にしている。出版、アニメ、ゲーム、教育事業をグループ内に持ち、これらを連携させた「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を推進 115。IPを企画段階から多角的に展開し、その価値を最大化するビジネスモデルは、他の出版社とは一線を画す。海外売上高比率が16.5%と高いことからも 30、その戦略の有効性がうかがえる。中期経営計画でも海外売上高とテクノロジー活用を重視しており 116、業界の変革を最も戦略的にリードしているプレイヤーと言える。
プラットフォーマー(Webtoon系)
- カカオピッコマ(ピッコマ): 「待てば¥0」という画期的なビジネスモデルを日本市場に定着させ、後発ながら一気にトッププレイヤーへと躍り出た。データに基づいた徹底的なUI/UXの改善と、大規模なマーケティング投資が成功の要因である。Webtoonと日本の漫画をバランス良く揃えた品揃えと、独占・先行配信作品でユーザーを強力に引きつけている。収益面でも国内アプリ市場で常にトップクラスを維持しており 99、高い収益性を誇る。
- NAVER(LINEマンガ): 無料通話アプリ「LINE」の巨大なユーザー基盤を活かした集客力が最大の武器であり、MAUでは国内トップクラスを維持している 23。グローバルでは「WEBTOON」のブランド名でサービスを展開し、世界最大のWebtoonプラットフォームとしての地位を確立している。日韓のNAVERグループ内でコンテンツやノウハウを共有できる点も大きな強みである。
新興Webtoonスタジオ
- ソラジマなど: Webtoon制作に特化した新興企業群。大手出版社のようなIPの蓄積はないが、分業制による効率的かつスピーディーな制作体制を構築している。クリエイターを正社員として雇用したり、柔軟な契約形態を用意したりすることで、人材の獲得・育成に注力している 101。プラットフォームにコンテンツを供給する「スタジオ」としての役割に徹することで、機動的な経営を実現している。彼らの成長は、Webtoon市場における人材と制作ノウハウの重要性を示している。
IT系プラットフォーマー
- コミックシーモア(NTTソルマーレ): 2004年からサービスを開始した電子書籍の老舗であり、長年の運営で培った巨大な会員基盤と信頼性が強み。豊富な品揃えと、きめ細やかなポイント施策、LINE公式アカウントを活用したマーケティングなどで、安定した顧客層を維持している 98。Webtoonなどの新しいフォーマットへの対応はやや後手に回ったが、総合電子書店としての地位は盤石である。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの市場概観、外部・内部環境分析、競争環境分析、そして主要プレイヤーの戦略分析を統合し、取るべき具体的な戦略を提言する。
今後3~5年で、漫画業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因は何か?
漫画業界は、デジタル化の完了と成長鈍化により、新たな淘汰の時代に突入する。この環境下で勝者と敗者を分けるのは、過去の成功モデルからいかに早く脱却し、未来の市場構造に適応できるかという変革能力である。
- 勝者の条件:
- グローバルIP創出力: 国内市場の経験則ではなく、グローバルなデータと市場インサイトに基づき、企画段階から世界で通用するIPを設計・プロデュースできる。
- データドリブンなプラットフォーム思考: 自社を単なる「出版社」ではなく、読者とのエンゲージメントを最大化する「プラットフォーム」と再定義し、データ分析をあらゆる意思決定の中心に据えることができる。
- フォーマットへの適応力: Webtoonを日本型漫画の「脅威」ではなく、新たな表現と収益機会をもたらす「フォーマット」として戦略的に取り込み、両方の強みを活かすことができる。
- テクノロジーへの戦略的投資: AIなどの新技術をコスト削減ツールとしてだけでなく、事業モデルを変革し、新たな競争優位を築くための戦略的アセットとして積極的に投資・活用できる。
- クリエイターとの新たな関係性: クリエイターを単なる「供給者」としてではなく、共にIPを育成する「パートナー」として捉え、収益分配やデータ共有、活動支援を通じて魅力的なエコシステムを構築できる。
- 敗者の特徴:
- 過去の成功体験への固執: 紙の雑誌と単行本を中心としたビジネスモデル、国内市場偏重の事業構造から脱却できず、意思決定が遅れる。
- プラットフォームへの従属: 顧客接点とデータをプラットフォーマーに握られ、自らはコンテンツを供給するだけの「下請け」的な存在に甘んじ、収益性を低下させる。
- 人材の流出: デジタル時代に対応したスキルを持つ編集者やプロデューサーを育成できず、また、D2Cモデルを選択する魅力的なクリエイターを引き留めることができずに、才能の源泉を失う。
捉えるべき機会(Opportunity)と備えるべき脅威(Threat)
- 機会 (Opportunities):
- 未開拓のグローバル市場: 北米・欧州における漫画のデジタル化比率は依然として低く、Webtoonフォーマットを武器に巨大な潜在市場を開拓できる 18。
- IP価値の指数関数的増大: トランスメディア戦略を前提としたIP開発により、一つのヒットから得られる収益を飛躍的に増大させることが可能。
- AIによる生産性革命: AIの活用により、制作・翻訳コストを劇的に削減し、グローバル・サイマル配信を標準化することで、新たな競争優位を確立できる。
- 体験型コンテンツ市場: VR/ARやメタバースを活用し、「読む」から「体験する」へと消費形態を進化させることで、新たなエンゲージメントと収益源を創出できる。
- 脅威 (Threats):
- プラットフォーマーによる支配: 「ピッコマ」「LINEマンガ」などの巨大プラットフォーマーがデータと顧客接点を独占し、出版社・クリエイターの収益分配率がさらに低下するリスク。
- 海賊版による収益機会の喪失: 正規市場を上回る規模の海賊版市場が、業界全体の利益を継続的に蝕む 20。
- 可処分時間獲得競争の激化: 動画、ゲーム、SNSといった代替エンターテインメントが、より強力な資本とデータ活用を武器に、ユーザーの時間を奪っていく。
- AIによる著作権侵害リスク: AIの安易な利用が、意図せぬ著作権侵害を引き起こし、大規模な訴訟やブランドイメージの毀損に繋がるリスク 68。
戦略的オプションの提示と評価
取りうる戦略的オプションは、大きく分けて以下の三つが考えられる。
- 戦略A:既存モデルの防衛・強化(低リスク・低リターン)
- 概要: 伝統的な日本型漫画の強みである、作家性の高い物語と見開きを活かした芸術的なコマ割りに注力。既存の強力なIPの深耕(続編、スピンオフ)と、アニメ化を中心としたメディアミックスで着実に収益を上げる。
- メリット: 自社のコアコンピタンスに集中でき、短期的には安定した収益が見込める。組織的な大変革を伴わないため、実行のハードルが低い。
- デメリット: 市場の構造変化(デジタル化、Webtoon化)から取り残され、長期的に市場シェアを失い、衰退するリスクが極めて高い。グローバルな成長機会を逸する。
- 成功確率: 低。
- 戦略B:Webtoonへの全面移行(高リスク・高リターン)
- 概要: 経営資源の大部分をWebtoonの制作・配信事業に集中投下。自社でWebtoonスタジオを設立、または積極的に買収し、グローバル市場向けのオリジナルWebtoonを大量に生産する。最終的には自社プラットフォームの構築も視野に入れる。
- メリット: 急成長するWebtoon市場で、先行する韓国勢に対抗するポジションを築ける可能性がある。成功すれば、新たな成長エンジンを確立できる。
- デメリット: 既存の紙媒体・電子単行本事業とのカニバリゼーション(共食い)が発生する。NAVERやカカオといった巨大IT企業との直接競合は、資本力やプラットフォーム運営ノウハウの点で著しく不利。失敗した場合の経営的ダメージが大きい。
- 成功確率: 中。
- 戦略C:ハイブリッド・トランスメディア戦略(中リスク・高リターン)
- 概要: 既存の強み(IP創出力、編集力)を核としながら、Webtoonを新たな表現フォーマットおよびグローバル市場への戦略的ツールとして積極的に取り込む。IPごとに最適なフォーマット(日本型漫画 or Webtoon)と展開戦略(メディアミックスの順序や組み合わせ)を設計する。
- メリット: 伝統的市場での収益基盤を維持しつつ、新たな成長市場の機会を捉えることができる。リスクを分散しながら、IP価値の最大化という本質的な目標を追求できる。
- デメリット: 組織内に異なる文化(職人的な漫画編集と、工業的なWebtoon制作)とビジネスモデルが混在し、経営の複雑性が増す。両利きの経営を実現するための高度なマネジメント能力が要求される。
- 成功確率: 高(ただし、実行には強力なリーダーシップと組織変革が必須)。
最終提言:ハイブリッド・トランスメディア戦略の実行
これまでの分析を総合的に判断し、本レポートは戦略C:ハイブリッド・トランスメディア戦略を、取るべき最も説得力のある事業戦略として提言する。この戦略は、業界の構造変化に柔軟に対応し、リスクを管理しながら持続的な成長を実現する上で、最も現実的かつ効果的なアプローチである。
戦略目標: 「世界市場でヒットするトランスメディアIPの創出を通じて、グローバルな総合エンターテインメント企業へと進化する」
実行に向けた具体的なアクションプラン(概要):
- 組織改革(最初の1年):
- 事業部を横断する「グローバルIPプロデュース本部」をCEO直下に新設。データアナリスト、海外マーケティング、編集、ライセンス、法務・知財の専門家で構成し、IP戦略の策定と実行に関する全権限を委譲する。
- 評価指標(KPI)を、従来の「単行本の売上」から、「IPごとの生涯収益(トランスメディア収益含む)」と「海外売上高比率」に転換する。
- IP開発プロセスの再構築(1〜2年目):
- 企画フェーズ: グローバル市場の需要データ、SNSトレンド分析を基にした企画立案を義務化。企画承認には、トランスメディア展開のポテンシャル評価と、ターゲット市場(国・地域)を明記したグローバルマーケティング計画の提出を必須とする。
- Webtoon展開: 既存の人気IPをWebtoon化し、海外市場へのエントリーポイントとする「IPブリッジ」チームを組成。並行して、Webtoonネイティブのオリジナル作品を開発する「ネイティブスタジオ」を外部パートナーとの提携またはM&Aにより確保する。
- テクノロジー基盤の強化(1〜3年目):
- AI翻訳: 全ての新規主要IPについて、グローバル・サイマル配信を可能にするため、高精度のAI翻訳ツールを全部門に導入する。
- AI作画支援: Webtoonスタジオを中心に、背景・着彩工程にAI作画支援ツールを試験導入。生産性向上効果と品質、著作権リスクを検証し、本格導入を判断する。
- データ分析基盤: 全てのプラットフォームからの販売・閲覧データを統合・分析するDMP(データマネジメントプラットフォーム)を構築する。
- 主要KPIとタイムライン:
- KPI:
- 海外売上高比率:現状 → 3年後に30%
- Webtoon事業売上高:3年後に全社売上の15%
- 新規IPのトランスメディア化率:3年後に50%
- タイムライン:
- 1年目: 組織改革の断行。データ分析基盤とAI翻訳の導入。Webtoonスタジオとの提携開始。
- 2年目: 1〜2本のパイロットIPで、新開発プロセスによるグローバル・トランスメディア展開を実行。成功・失敗要因を分析。
- 3年目以降: 成功モデルを全社に本格展開。Webtoonスタジオへの追加投資または自社設立を検討。
- KPI:
- 必要リソース:
- データサイエンティスト、グローバルマーケティング人材、IPプロデューサーなど専門人材の採用・育成。
- データ分析基盤、AIツール導入へのIT投資。
- Webtoonスタジオへの出資またはM&Aのための戦略的投資資金。
この戦略を実行することは、従来の出版社の枠組みを大きく超える挑戦である。しかし、この変革なくして、IP新大陸の航海を乗り切り、未来の成長を掴むことはできない。
第12章:付録
引用文献
- 2024年コミック市場は7043億円 前年比1.5%増と7年連続成長で過去最大を更新 ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/54727
- 2023年コミック市場6900億円のうち約7割は電子【出版科学研究所調べ】 – massnavi, https://www.massnavi.com/report/1260.html
- 【速報】2024 年コミック市場は 1.5%増の 7,043 億円 7 年連続のプラスで 7 千億円突破 – 出版科学研究所, https://shuppankagaku.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B92502-.pdf
- コミック販売額 | 出版科学研究所オンライン, https://shuppankagaku.com/statistics/comic/
- 2020年コミック市場は紙+電子で6126億円、前年比23.0%増と2年連続急成長で過去最大規模に ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/30684
- コミックは電子版が7割超え 24年のコミック市場規模は過去最高7000億円規模に – ITmedia, https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2502/25/news146.html
- 電子書籍ビジネス調査報告書2025 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/report/list/ebook/502255
- 統計開始以来史上最大 紙は 13.4%増、電子は 31.9%増 – 出版科学研究所, https://shuppankagaku.com/wp/wp-content/uploads/2021/03/20210225.pdf
- 2022年コミック市場は6770億円前年比0.2%増で微増ながら5年連続成長で過去最大を更新 ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/39314
- 2022年コミック市場は0.2%増の6770億円 出版科研調べ – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/318396/
- 業界の現状及びアクションプラン(案)について 【漫画・書籍】 (事務局資料③), https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/003_04_03.pdf
- ウェブトゥーンの世界市場:市場規模、現状、予測(2024年~2030年), https://www.gii.co.jp/report/qyr1555082-global-webtoons-market-size-status-forecast.html
- ウェブコミックの市場規模、シェア、成長、トレンド[2025-2032] – Fortune Business Insights, https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E5%B8%82%E5%A0%B4-105731
- 2022年度の市場規模は6026億円、2027年度には8000億円市場に成長 Webtoonが電子コミック市場の1割の規模に 『電子書籍ビジネス調査報告書2023』8月10日発売 | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/673
- 2018年コミック市場は紙+電子で前年比1.9%増の4414億円と成長基調へ ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/21536
- 2019年コミック市場は紙+電子で4980億円、前年比12.8%増と急成長 ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/28155
- 2021年コミック市場は紙+電子で6759億円、前年比10.3%増で過去最大を更新しシェア4割超に ~ 出版科学研究所調べ | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/32771
- 国際競争力強化に向けた漫画産業の基盤整備 – Policy makers lab, https://policymakerslab.gr.jp/wp-content/themes/policymakers/assets/pdf/vol2_2022-11-05.pdf
- 日本の漫画市場:売上ランキングに見る成功事例とファンを掴む戦略とは?世界を牽引する日本のコンテンツマーケティングに迫る!, https://yui-marke.com/article/2672/
- 海賊版サイトで「漫画タダ読み」1兆円超の損害 前年の約5倍…正規市場規模は約6000億円, https://www.fnn.jp/articles/-/304189
- 爆発的に拡大する海賊版サイト 現状の対策と問題点, https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kokusai/r03_04/pdf/93657001_04.pdf
- 出版物海賊版サイトの最新データと、対策の現状補足, https://www.soumu.go.jp/main_content/000789252.pdf
- 「業界別」アプリランキング - コミック編 - | [マナミナ]まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン, https://manamina.valuesccg.com/articles/2141
- 歴代マンガで最も面白い漫画は何か?発行部数と巻数と連載期間から抽出したマンガの「面白さ度」の指標を定義してランキング化してみた – note, https://note.com/whomor_studio/n/n609f4b67473f
- 【2024年最新】漫画売上ランキング! 累計発行部数の歴代TOP100を紹介 – ねこくまぶろぐ, https://nekokuma.com/113131/
- 『電子コミックサービス』利用実態データ NEWS RELEASE, https://life.oricon.co.jp/information/675/
- ARPUとは?計算方法、ARPPUやARPAとの違いを解説 – 東大IPC−東京大学協創プラットフォーム開発株式会社, https://www.utokyo-ipc.co.jp/column/arpu/
- ARPUとはどんな指標?計算法と改善策、ARPPU・ARPAとの違い|わかりやすく用語解説, https://repro.io/contents/arpu/
- 電子書籍サービスで見るべき重要なKPIや要素とは? | DataLab by FLYWHEEL, https://datalab.flywheel.jp/posts/KPI_for_ebook_service
- 「日本のコンテンツ産業のハブになる」 KADOKAWAのグローバル担当が描く世界戦略 | K-Insight, https://group.kadokawa.co.jp/k-insight/ki70990.html
- マンガやアニメの海賊版被害は約2兆円、コロナ禍で5倍に CODA推計 – ITmedia NEWS, https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2304/27/news186.html
- 日本コンテンツ被害総額はネット海賊版で年間約2兆円、CODAが算出, http://animationbusiness.info/archives/14335
- 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA): TOP, https://coda-cj.jp/
- 海賊版サイト対策で利用される米国での情報開示 手続の実務と対策の現状について, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kaizokuban_taisaku/gijisidai/dai2/siryou4.pdf
- 2025年1月総合コラム:「海賊版サイト」をAIで検知する新システム構築(文化庁)|お役立ち情報, https://braina.net/2025%E5%B9%B41%E6%9C%88%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%EF%BC%9A%E3%80%8C%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E7%89%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%8D%E3%82%92ai%E3%81%A7%E6%A4%9C%E7%9F%A5%E3%81%99/
- AIを活用した海賊版サイトの検知・分析実証事業 – 文化庁, https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/workingteam/r06_02/pdf/94150601_10.pdf
- 青少年健全育成条例 性描写漫画規制、都議会で質疑 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=rHbc19s3u64
- 「漫画から翼を奪う」と秋本治さん 都条例改正案に漫画家、出版社が反対会見 – ITmedia NEWS, https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1011/29/news099.html
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E3%81%AA%E8%82%B2%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B
- 日本のマンガがいま世界でどうなっているのか アニメイト@タイから見てみよう – note, https://note.com/thibiki/n/n5ae9f3d73928
- 外圧による表現規制との闘い – 参議院議員 山田太郎 公式webサイト, https://taroyamada.jp/cat-expression/post-46404/
- インボイス制度の漫画家への2つの影響とは?基本ルールや特例も紹介, https://media.invoice.ne.jp/column/invoices/invoice-manga.html
- インボイス制度が漫画家に与える影響は?【2024年版】 – 弥生, https://www.yayoi-kk.co.jp/invoice/oyakudachi/mangaka/
- 家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要, https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf
- 推し活の経済効果はどれくらい?市場規模と推し活マーケティングのメリットとは, https://www.cross-m.co.jp/column/marketing/mkc20241025
- 聖地巡礼がもたらす経済効果とは? 推し活で地域創生を後押ししよう – ポプスタ – POP STUDY -, https://tais.ac.jp/popstudy/hobby/%E8%81%96%E5%9C%B0%E5%B7%A1%E7%A4%BC%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%99%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F-%E6%8E%A8%E3%81%97%E6%B4%BB%E3%81%A7%E5%9C%B0%E5%9F%9F/
- 推し活人口と経済効果 – フォーライフ, https://forlife.yokohama/2025/09/22/%E6%8E%A8%E3%81%97%E6%B4%BB%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8A%B9%E6%9E%9C/
- 市場規模は3兆5千億円に!第2回 推し活実態アンケート調査結果を公式noteで公開。, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000025413.html
- 開始から終了まで-クリエイティブプロセス by chicharlotta – お絵かきのコツ | CLIP STUDIO TIPS, https://tips.clip-studio.com/ja-jp/articles/5485
- SNS広告のトレンド〜SNSでマンガ広告が好まれる理由とは? – 株式会社トレンド・プロ, https://ad-manga.com/blog/c156
- ファンアートに関する二次創作ガイドラインの在り方を考える -ネット上におけるファンアートと著作権法の関係を踏まえて- 田島佑規|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts, https://www.kottolaw.com/column/220331.html
- 二次創作と著作権(備忘録/2023.6.5更新)|憂那 – note, https://note.com/yuu719/n/na366c5780c0f
- 二次創作ガイドライン – 株式会社gumi, https://gu3.co.jp/derivativework-guideline/
- 二次創作ガイドライン | 『ヒューマンバグ大学_闇の漫画』公式サイト, https://humanbug.jp/guideline
- ポリティカル・コレクトネスとは?その意味と事例、問題点を解説 – あしたメディア by BIGLOBE, https://ashita.biglobe.co.jp/entry/2022/01/12/110000
- ポリコレ(ポリティカルコレクトネス)とは?具体例や問題点をわかりやすく解説 – gooddo(グッドゥ), https://gooddo.jp/magazine/sdgs_2030/reduced_inqualities_sdgs/30403/
- 主人公が美男美女は差別?エンタメの「面白さ」と「正しさ」をポリコレから考える, https://sdgsmagazine.jp/2023/03/09/9462/
- ポリコレとは? 具体例やメリット、起きている弊害を解説 | ELEMINIST(エレミニスト), https://eleminist.com/article/3449
- ほぼ漫画コラム14【WEBTOONの優位性】 – note, https://note.com/comic_room/n/n002f251f1cc9
- 【NFT特集vol.7】NFT×本・漫画・雑誌の国内外事例3選! – note, https://note.com/studio_entre/n/n4ff5a6b12e21
- 【NFT×漫画・アニメ】日本の漫画・アニメIPへのNFT活用事例19選 – NFT Media, https://nft-media.net/animation/manga-anime/292/
- AI翻訳は生成AIに負けるのか? | 株式会社 十印, https://to-in.com/blog/112972
- 生成AI vs 従来の翻訳ツール:生成AIが翻訳精度を徹底比較!あなたの最適な選択は?, https://japan.wipgroup.com/media/genai-translation-accuracy-comparison
- 集英社マンガ作品を生成AIで多言語化。海賊版の被害を減少へ – AIsmiley, https://aismiley.co.jp/ai_news/mantraengine-manga-plus-by-shueisha-vietnam/
- 文化庁による「AIと著作権の関係等について」 – イノベンティア, https://innoventier.com/archives/2023/07/15231
- AIが生成した文章やイラストの著作権はどうなる?著作権侵害にあたるか、弁護士が解説!, https://www.authense.jp/komon/blog/dx-legaltech/2838/
- 生成AIに関する著作権法上のリスクは?文化庁の「考え方」についても解説 – TD SYNNEX BLOG, https://jp.tdsynnex.com/blog/ai/generated-ai-copyright-risks/
- 自分の作品に似たAIイラストがあったときの対応方法 文化庁が解説 – アスキー, https://ascii.jp/elem/000/004/213/4213761/
- AIと著作権の関係等について – 内閣府, https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
- 生成AIで作った文章・画像は、著作権法に違反していないのか? – NTTドコモビジネス, https://www.ntt.com/bizon/copyright_ai.html
- 公取委、Apple・Googleの自社優遇に懸念 アプリ内課金の開放など指摘 – Impress Watch, https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1477385.html
- アップルは優越的地位を“濫用”している? 公取委が調査 アカウント停止、表現規制, https://www.businessinsider.jp/article/187542/
- 消費者取引にも独禁法の「優越的地位の濫用」適用へ――ECモールなどへの実態調査踏まえ考え方を整理 | 通販新聞ダイジェスト, https://netshop.impress.co.jp/node/6460
- FSC世界市場調査, https://jp.fsc.org/sites/default/files/assets/FSC_newsentry_1432892898_file.pdf
- 令和5年10月25日 – 環境省, https://www.env.go.jp/content/000167923.pdf
- 電子書籍と紙の本はどちらが環境に良い? – 明日のためのエコレシピ, https://re-cipe.re-tem.com/recipe/book/
- iPadやキンドル、電子ブックは本当にエコ?, https://www.nygreenfashion.com/html/news/20100722.html
- 漫画家の原稿料・印税はいくら? 【印税額ランキングも】 – キャリアガーデン, https://careergarden.jp/mangaka/inzei/
- マンガ家は印税だけで生活できる?具体的な仕組みやその他の収入もご紹介!, https://ha.athuman.com/humanstar/blog/manga/post_228.html
- 【Webtoon業界注目スタートアップ3選】 | New Venture Voice, https://www.nvv.genai.co.jp/2024/06/3-startups-in-webtoon/
- エンタメ領域では可処分時間の奪い合いがない?——生活者調査から見えたヒント、「競争」よりも「共存」 – Think with Google, https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ja-jp/consumer-insights/consumer-trends/entertainment-report/
- 343. 2020年一番学んだ考え方「可処分時間」|イナチャンネルnote – 稲本浩介⛩️, https://note.com/sevenina/n/n5056ec93eee0
- 書店の現状と今後の課題について, http://www.kosekizemi.net/ronbun/18Lyamamoto.pdf
- 電子書籍の取り分についてのお話|hiroyama – note, https://note.com/publishnote/n/n0a38d1fb024a
- 「電子書籍市場の動向について」 – 公正取引委員会, https://www.jftc.go.jp/cprc/koukai/seminar/h25/34_notice_files/34thop_1.pdf
- 【SKYFLAG導入事例】and factory社の運営するマンガアプリ6媒体が、SKYFLAGを利用して3ヶ月で売上を130%増加。ユーザーのサービス利用を促進する機能を評価していただきました。 | マネタイズ・マーケティングラボ, https://skyflag.info/labo/42-3/
- 【導入事例】and factory社が運営するマンガアプリ6媒体で『SKYFLAG』導入後、3ヶ月で売上130%アップ | 株式会社Skyfallのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000045762.html
- 開発事例 – Link-U Technologies, https://technologies.link-u.co.jp/products
- 韓国メディア25社がオフィスにやってきたので、ナンバーナインや日本のwebtoonに関する質問に答えてみた – note, https://note.com/no9media/n/nc6a21847d030
- アジア最大規模の「漫画・WEBTOON素材プラットフォームACON」、日本進出発表 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000135277.html
- マンガD2C『コミチ』の紹介, https://comici.co.jp/d2c/
- 株式会社コミチ | マンガのプラットフォーム「コミチ」, https://comici.co.jp/
- 20代の6割以上が有料動画配信サービスでアニメを視聴【クロス・マーケティング調査】, https://markezine.jp/article/detail/47213
- 2025年 有料動画配信サービス利用動向に関する調査 – ICT総研, https://ictr.co.jp/report/20250423.html/
- 拡大を続けるモバイルゲーム市場 注目のスタートアップ133社 – KEPPLE REPORT, https://kepple.co.jp/articles/qw5y9js0gq
- [レポートシェアリング] 「2023年日本のモバイルゲーム市場インサイト」 – Sensor Tower, https://sensortower.com/ja/blog/state-of-mobile-games-in-japan-2023-report-JP
- マンガアプリの最新状況、総合型1位は「BookLive!」ながら、集英社系が上位を占める【オリコン調べ】, https://webtan.impress.co.jp/n/2020/10/07/37713
- 成長を続ける電子コミック業界。各媒体の強み、集客戦略を分析 – マナミナ, https://manamina.valuesccg.com/articles/1963
- 2024年APAC地域における非ゲームモバイルアプリの収益は25%増加 – コマースピック, https://www.commercepick.com/archives/62607
- 画像5 / 5>2022年、人気の書籍&漫画各アプリの実績はどうだった?市場レポートから読み解く! – ウォーカープラス, https://www.walkerplus.com/article/1117201/image11377503.html
- 日本で一番クリエイターにフレンドリーなWebtoonスタジオによる「創作満足度No.1プロジェクト」始動! | SORAJIMA STORY, https://story.sorajima.jp/articles/n3245b4b29fe4
- Webtoon制作スタジオ – デジタル職人株式会社, https://digishoku.co.jp/webtoonstudio/
- 編集者が語る!Webtoon制作工程-前編-魅力的な企画づくりの秘訣 – SORAJIMA STORY, https://story.sorajima.jp/articles/n885000cc501e
- 日韓のwebtoon制作で感じた違い|フーモアコミックスタジオ – note, https://note.com/whomor_studio/n/nac15b07b85c1
- 約1万人の利用者が回答した『電子コミックサービス』利用実態レポート 「有料利用」は41.6% 昨年より課金利用者は微増傾向に(オリコン顧客満足度) – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000555.000034467.html
- 電子書籍と紙の本はどう使い分ける?記憶の定着に有利なのはどちら? – PFU, https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/digiup/article/learn/00119/
- マンガに関する調査【2020年版】 – TesTee Lab, https://lab.testee.co/comic_2020/
- Z世代とプレWeb3.0時代のマンガ消費 – note, https://note.com/daisakku/n/n15da1405ba90
- Z世代の消費行動の特徴は? コンテンツ作りで意識すべき特有の”価値観” | 【レポート】デジタルマーケターズサミット2022 Summer, https://webtan.impress.co.jp/e/2022/11/02/43482
- 今注目の「エモ消費」とは?Z世代に刺さるポイントも解説 – クロス・マーケティング, https://www.cross-m.co.jp/column/marketing/mkc20240216
- 原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説, https://nokid.jp/blog/10027/
- 歴代ジャンプ漫画人気作品ランキングベスト89!【500人にアンケート調査】 – eeo Today, https://eeo.today/media/2022/02/21/32015/
- プロフェッショナルメンバー限定!「講談社 編集者に聞く 絵本づくりの仕事」 | キッザニア, https://www.kidzania.jp/grand/13954
- マッチング型マンガ投稿サイト「DAYS NEO」に竹書房の4編集部が参入! – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005944.000001719.html
- 事業紹介 | KADOKAWAグループ ポータルサイト, https://group.kadokawa.co.jp/business/
- 中期経営計画 | IR情報 | KADOKAWAグループ ポータルサイト, https://group.kadokawa.co.jp/ir/plan.html
- 仕事を知る – KADOKAWA キャリア採用サイト, https://group.kadokawa.co.jp/recruit/kadokawa/career/business/
- 元アシスタントが、著名漫画家に残業代を請求!変形労働時間制とは? | コラム – CLOUZA, https://clouza.jp/column/modified-working-schedule-system2/
- 「こち亀」作者・秋本治さんが語るSDGs。休載なしの40年連載を可能にした”持続可能な”仕事術とは!?【BS-TBS「Style2030 賢者が映す未来」】 – BS-TBSの公式note, https://note.bs-tbs.co.jp/n/ne558bb9bcbbc
- 秋本治の仕事術 『こち亀』作者が40年間休まず週刊連載を続けられた理由 – よみタイ, https://yomitai.jp/book/akimotoosamu/
- 漫画家アシスタントの収入はどれくらい?年収の現実と稼ぐためのポイントを解説!, https://oekakimovie.com/manga-syunyu/
- WEBTOON業界の課題とは!?その背景と対策までを解説! – Confidence Creator, https://confidence-creator.jp/column/25044/
- ソラジマ「webtoonクリエイター」採用|トライアル評価のポイント解説 | SORAJIMA STORY, https://story.sorajima.jp/articles/n3c4f04dc584b
- 漫画家の約9割がデジタル制作。半数以上は3Dを活用 ―漫画家実態調査アンケート – マンナビ, https://mannavi.net/14929/
- 「2024年」最新のお絵描きソフト・イラストソフト10選まとめ:有料と無料 – XP-PEN, https://www.xp-pen.jp/blog/best-drawing-illustration-software.html
- AI漫画の現在と未来|創作はAIとどう共存するか?, https://www.osslicense.jp/ai-manga-genzai-mirai/
- AIを使った漫画制作:具体的な使用ツールにいて徹底解説, https://aoco.jp/ai-manga-production/
- ストーリー性のあるマンガを自動生成するAIモデル「StoryDiffusion」 – GIGAZINE, https://gigazine.net/news/20240501-ai-story-diffusion/
- AI対話型マンガレコメンドサービス「DEAIBOOKS」 コンセプト設計から開発、PRまでをトータルで支援 – 電通デジタル, https://www.dentsudigital.co.jp/cases/0905-shueisha
- 広告業界での生成AI活用事例11選!クリエイティブ&ツール紹介や導入のメリットも, https://shift-ai.co.jp/blog/2686/
- 画像生成AIを活用した広告制作は可能か?メリットとリスク面を解説 – malna株式会社, https://malna.co.jp/blog/ai_advertisement/
- 決算特集:集英社(〜2021年) – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/kakokessan/kessan-shueisha
- 集英社の企業研究 – iroots, https://iroots.jp/research/4044/
- 講談社 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE
- (株)KADOKAWA【9468】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/9468.T
- マンガ・電子書籍アプリの1日における利用時間は9.7分 フラーが「マンガ・電子書籍アプリ市場調査レポート2024」を公開, https://www.fuller-inc.com/news/202409-comic-e-book-app-report
- インプレス総合研究所、2023年度の電子書籍市場規模は6449億円と発表:前年比7.0%増, https://current.ndl.go.jp/car/223242
- 電子書籍の市場規模・業界動向レポート – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/ebook
- 2023年度の電子書籍市場規模は6449億円、2028年度には8000億円市場に成長, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/697
- インプレス総合研究所、2024年度の電子書籍市場規模は6703億円と発表:前年比3.9%増, https://current.ndl.go.jp/car/255891
- 2026年には8000億円市場に『電子書籍ビジネス調査報告書2022』8月10日発売, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004709.000005875.html
- キャラクタービジネスに関する調査を実施(2025年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3849
- Webtoon市場の驚異的成長:3.9兆円産業への躍進と日本のチャンス – note, https://note.com/yutsudo/n/ne44aef96621f
- ウェブトゥーン産業の現状および展望詳細を見る | 産業フォーカス – Invest Korea, https://www.investkorea.org/ik-jp/bbs/i-685/detail.do?ntt_sn=491281
- 出版業界の世界市場シェアの分析 | deallab, https://deallab.info/publishing/
- リッシャー年間収益ランキングで世界1位を獲得 – LY Corporation, https://www.lycorp.co.jp/news/archive/L/ja/ja20170117_A.pdf
- 2025年第1四半期日本のモバイルゲーム – Sensor Tower, https://sensortower.com/ja/blog/state-of-mobile-games-2025q1-JP
- ARPU(ユーザーあたりの平均収益)とは?ARPUの計算方法 | Adjust, https://www.adjust.com/ja/glossary/arpu-definition/
- マンガアプリの開発にかかる費用や成功のためのポイントは?詳しく解説 – 株式会社Pentagon, https://pentagon.tokyo/app/3967/
- 海賊版に関する 海外での被害の状況について, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kaizokuban_taisaku/gijisidai/dai1/siryou5.pdf
- 2019年度の市場規模は3473億円、2年連続の20%超の成長 ~電子書籍に関する調査結果2020, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/612
- 電子書籍市場、2019年度は3473億円に Kindleの後を追うサービスは?/インプレス総研調べ, https://markezine.jp/article/detail/34132
- 漫画本の市場規模、シェア、価値、トレンド|分析、2032 – Fortune Business Insights, https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-103903
- 米国のマンガ市場が急拡大している件 – note, https://note.com/daisakku/n/n5837ca418cc5
- 歴代マンガ発行部数ランキングtop301 2024年 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=GyMKzZekFws
- ゲームアプリの基本KPI!PUとPURを理解しよう|わかりやすく用語解説 – Repro(リプロ), https://repro.io/contents/pu/
- 中期経営計画 2025-2027 – 日テレホールディングス, https://www.ntvhd.co.jp/ir/library/management/pdf/2025_2027.pdf
- コミックは電子・紙とも好調で拡大 2019年出版市場が前年比増, http://animationbusiness.info/archives/9182
- 2021年国内コミック市場6759億円 過去最高更新、紙も堅調 出版科学研究所が公表, http://animationbusiness.info/archives/12747
- 2018年度の市場規模は2826億円、海賊版サイト閉鎖を受けて前年比126.1%の大幅増 ~電子書籍に関する調査結果2019~ | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/566
- 2018年度の市場規模は2826億円 拡大する電子書籍市場について明らかにするインプレス社の調査レポートが公表される – ECのミカタ, https://ecnomikata.com/ecnews/marketing/23187/
- インプレス総合研究所 18年度電子出版市場を発表 電子コミックは29%増 電子雑誌初のマイナスに – The Bunka News デジタル – 文化通信, https://www.bunkanews.jp/article/206788/
- 巣ごもり消費で2020年度の「電子書籍市場」は前年比28.6%増の4821億円に、インプレス調べ, https://www.bcnretail.com/market/detail/20210805_238004.html
- 2018年度電子出版市場は3122億円で前年度比12.2%増と推計 ~ インプレス総合研究所『電子書籍ビジネス調査報告書2019』 | HON[.]jp News Blog, https://hon.jp/news/1.0/0/25681
- 2020年度の市場規模は4821億円、巣ごもり消費で前年から1071億円の大幅増加!『電子書籍ビジネス調査報告書2021』 | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/630
- インプレス総合研究所、2020年度の日本の電子書籍市場規模は4821億円と発表:前年比28.6%増, https://current.ndl.go.jp/car/44602
- 2020年電子コミック市場が4000億円突破、マンガアプリ広告は260億円, http://animationbusiness.info/archives/11742
- 2021年度の市場規模は5510億円、2026年には8000億円市場に 『電子書籍ビジネス調査報告書2022』8月10日発売 | インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/topics/list/ebook/655
- 国内電子書籍市場14.3%増の5510億円、84%をマンガが占める, http://animationbusiness.info/archives/13522
- 電子書籍ビジネス調査報告書2022 – インプレス総合研究所, https://research.impress.co.jp/report/list/ebook/501508
- 決算特集:小学館(〜2021年) – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/kakokessan/kessan-shogakukan
- 小学館 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%A4%A8
- 世界の出版社 売上ランキング 寄稿:冬狐洞 隆也 氏, http://www.1book.co.jp/005470.html
- 紀伊國屋書店、「2024年出版社別売上げベスト300」を発表 – 新文化オンライン, https://www.shinbunka.co.jp/archives/9714
- 社会のDXが進む中、産業としての出版はこれからどう変化していくのか?【HON-CF2024レポート】, https://hon.jp/news/1.0/0/52960
- オタ活・推し活とは?広がるオタク市場の経済効果と企業の実例を解説, https://www.sungrove.co.jp/otaku/
- 【だる絡み背後霊】『ギャグマンガ日和』に強く影響されたド下ネタホラーコメディが本日(10/16)発売。制作者の事前検証で「収益化は問題なし」 | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com, https://www.famitsu.com/article/202510/55293
- 「それって違法?」文化庁がAIと著作権のガイダンスを発表 – note, https://note.com/masajiro999/n/n59e2041a9b8c
- 東京都青少年条例による表現規制に反対する声明 – 日本マンガ学会, https://www.jsscc.net/info/106
- 森について学び、森の大切さを実感できる森 〜三菱製紙グループ「エコシステムアカデミー」の白河甲子の森 – FSC応援プロジェクト, https://shitte-erabo.net/actfsc/fscforest/4311/
- 日本製紙グループの環境への取り組み 44% 100%を, https://www.nipponpapergroup.com/contents/200180354.pdf
- 紙と電子メディアの CO2 排出量の比較 – 人工知能学会, https://www.ai-gakkai.or.jp/jsai2011/webprogram/2011/pdf/121.pdf
- 出版業の確定申告(作家、漫画家、編集者、出版社など), http://soei-tax.jp/15323916162503
- デジタル社会経済のもとでの書店生き残り戦略 | 経営研レポート 2015, https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/reports/archives/2015/1119/index.html
- “鬼滅の刃”人気で特需 縮小続いた書店市場、4年ぶり拡大の可能性高まる – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000043465.html
- Youtube漫画広告のアドアフィ企業が判明、売上26億、営利8億超えの衝撃。元welq高木健作氏率いるアレテコグループが仕掛けたD2C広告 | Suan | スタートアップメディア, https://suan.tokyo/areteco_part3/
- モバイルゲーム業界を多角的に分析したデータ年鑑『ファミ通モバイルゲーム白書2025』発売。米Sensor Towerが監修し最新データが満載, https://www.famitsu.com/article/202503/37835
- Webtoonで漫画家デビューを目指そう! | イラスト・マンガ描き方ナビ – CLIP STUDIO PAINT, https://www.clipstudio.net/oekaki/archives/156251
- フードバリューチェーンが変える日本農業(最新刊) – コミックシーモア, https://www.cmoa.jp/title/1101273179/
- DNPが構築した生産・流通ソリューションーーデータ活用で書籍のバリューチェーンを最適化!, https://connect.panasonic.com/jp-ja/gemba/article/00177632
- AIでWebtoon制作を加速 – SotaTek, https://www.sotatek.com/jp/portfolio/accelerating-webtoon-creation-with-ai/
- 漫画家アシスタントを半年やって分かったメリット・デメリット – しまくま制作, https://shimakuma.com/art/manga/mangaka-assistant-review/
- アニメ製作委員会の現実, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2025/cs_wg/dai1/siryou8.pdf
- 「製作委員会方式」はもう古い?世界が注目する日本のアニメや製作形態の変化 – DIME, https://dime.jp/genre/1616524/2/
- アニメビジネスにおける製作委員会の役割と功罪に関して – note, https://note.com/yoluyo/n/n8c20a0e60e9b
- 若年層のマンガへの関心が低下傾向か?最新調査で判明、読書と創作の男女差も – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000145064.html
- 【フリーランス/制作会社どう選ぶ?】アニメーションの実績の見方と上手な依頼先の選び方, https://smarvee.com/column-tips/anime-achievement-points-of-view/
- 漫画家は、アニメ化するスタジオを自分で選ぶんですか?それとも、アニメスタジオが漫画を選んで、合意するんですか? : r/anime – Reddit, https://www.reddit.com/r/anime/comments/rj8h00/do_mangakas_choose_the_anime_studio_of_their/?tl=ja
- 分水嶺に立つモバイルゲーム業界 ゲーム展開を積極化するIPホルダーとの協業に活路 Web3やIPプロデュースを模索する動きも | gamebiz, https://gamebiz.jp/news/374671
- ブロックチェーンゲーム「My Crypto Heroes」を運営するMCH社とブロックチェーン事業での協業を開始 | 株式会社gumi, https://gu3.co.jp/news/archives/8953/
- SHIFT、DXコンサルティング事業、モバイルゲーム・アプリ開発支援を行う 株式会社1LDKと業務提携, https://www.shiftinc.jp/news/business-alliance_1ldk/
- 未経験から漫画家のアシスタントになれる?給料・年収や募集内容の注意点など, https://charaten.net/blog/detail.html&id=41
- 【開催報告】第2回日本企業向けWebtoon短期研修プログラム | Culture Weaver合同会社, https://culture-weaver.com/webtoon_studytour_202403report/
- 生成AIで漫画ができる!? おすすめのツールと具体的なやり方を解説 | HENSHIN Lab, https://team-henshin.com/media/ai/ai-manga/
- 【2025】生成AI漫画制作おすすめサイト・アプリ10選!著作権や作る手順についても解説, https://businesskouzamitsuketai.com/seiseiai-manga/
- 生成AIと著作権法〜生成AIによるイラスト等の著作物の利用と注意点〜 | コラム, https://legal-leon.jp/column/900/