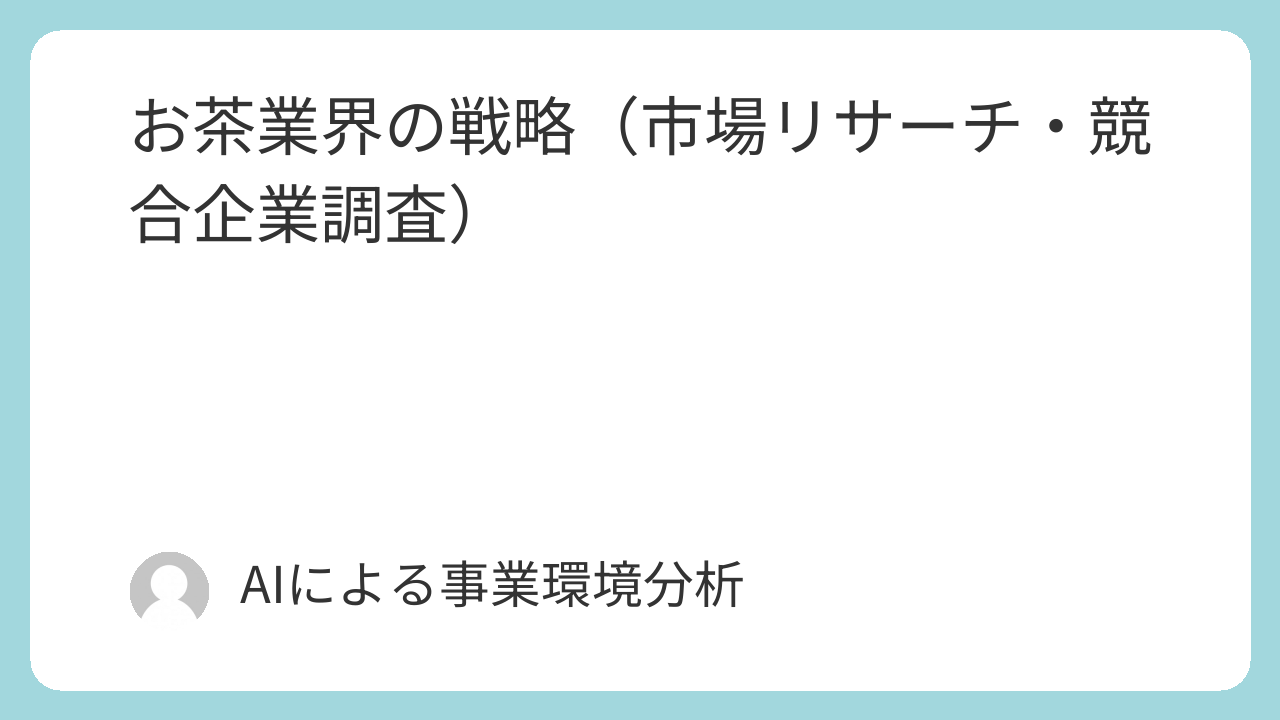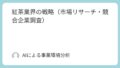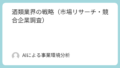伝統と革新の融合:健康・体験価値とAIが拓くお茶業界の持続可能な成長戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
1.1 本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、日本のお茶業界が直面する構造的課題と新たな成長機会を多角的に分析し、持続可能な成長を実現するための事業戦略を提言するものである。調査対象は、緑茶、紅茶、ウーロン茶等を含むお茶全般の生産、加工、流通、販売(リーフ、飲料、原料用途含む)ビジネスとする。業界は、国内リーフ茶市場の縮小、サプライチェーンの脆弱化、そしてグローバル市場での新たな機会という、複雑に絡み合う課題と好機に直面している。本分析は、これらの動向を解き明かし、具体的な戦略的選択肢を提示することを目的とする。
1.2 最も重要な結論
日本のお茶業界は、国内リーフ市場の構造的縮小とサプライチェーンの脆弱化という「守りの課題」と、健康・体験価値の再定義およびグローバル市場(特に抹茶)という「攻めの機会」が交差する、歴史的な転換点にある。この岐路において、将来の勝者と敗者を分ける決定的な要因は、伝統的な強み(品質、製茶技術、文化)を活かしつつ、テクノロジー(特にAIとスマート農業)を駆使してバリューチェーン全体を再構築し、パーソナライズされた顧客価値を創出できるか否かである。もはや、単に「美味しいお茶」を製造・販売するだけでは不十分であり、生産から消費に至るまでの全プロセスにおいて、データに基づいた意思決定と新たな価値提案が不可欠となっている。
1.3 主要な戦略的推奨事項
本分析に基づき、取るべき事業戦略上の主要な推奨事項を以下に3点提示する。
- 事業ポートフォリオの戦略的再構築: 国内リーフ市場では、画一的なマスプロダクトから脱却し、高付加価値な「体験型・パーソナライズド」モデルへ事業をシフトする。飲料市場では、「機能性表示食品」を核とした科学的根拠に基づく健康価値で明確な差別化を図る。そして、最大の成長エンジンとして、海外、特に北米・欧州におけるプレミアム抹茶市場への経営資源の重点的投下を最優先事項とする。
- サプライチェーンの垂直統合とデジタルトランスフォーメーション(DX): スマート農業技術を持つアグリテック企業との提携やM&Aを通じて、生産段階への関与を深め、品質と供給の安定性を確保する。同時に、ブロックチェーン技術などを活用したトレーサビリティシステムを確立し、「安全・安心・サステナブル」という無形の価値を可視化し、ブランド価値の源泉へと昇華させる。
- AIドリブンな顧客中心モデルへの転換: AIを活用した高精度な需要予測によってサプライチェーン全体の最適化とフードロス削減を実現する。それと並行して、個々の顧客の嗜好や健康データに基づいた「パーソナライズド・ティー」のD2Cサブスクリプション事業を新たに立ち上げ、顧客との直接的な関係を構築し、持続的な収益基盤を確立する。
第2章:市場概観(Market Overview)
2.1 世界のお茶市場規模と予測(2019-2030年)
世界のお茶市場は、堅調な成長軌道を維持している。複数の市場調査レポートを統合分析すると、市場は予測期間において年平均成長率(CAGR)4%~8%で拡大すると予測される 1。市場規模の推定値は調査機関の定義や範囲によって異なるものの(例:2024年時点で256億米ドルから495.3億米ドル 1)、その成長トレンドは一貫している。この成長の根底にあるのは、世界的な健康志向の高まりであり、特に緑茶やハーブティーに含まれる抗酸化物質などの健康機能性への関心が強力な原動力となっている 2。
茶種別に見ると、紅茶が依然として最大の市場シェアを占めているが、成長率の観点では緑茶、特にハーブティーが最も高いCAGRを示すと予測されている 3。これは、消費者がお茶を単なる嗜好品としてではなく、ウェルネスや特定の健康目的を達成するための機能性飲料として捉え始めていることの明確な証左である。
地域別では、アジア太平洋地域が生産・消費の両面で最大の市場であり続けている 2。しかし、市場成長の質と将来性を考慮すると、北米と欧州が極めて重要な市場である。これらの地域では、プレミアム、オーガニック、シングルオリジン(単一農園・単一品種)、そして明確な機能性を訴求する高付加価値製品への需要が市場全体を牽引しており、日本茶、特に抹茶の主要な輸出先となっている 2。
2.2 日本のお茶市場規模と構造変化
世界市場の成長とは対照的に、日本国内のお茶市場は深刻な構造変化に直面している。市場は大きく二つのセグメントに分断されており、それぞれが全く異なる様相を呈している。
第一に、リキッドタイプ(ペットボトルなどの茶飲料)の市場は、富士経済によると約5,253億円規模で比較的安定しており、微増傾向にある 7。これは、消費者の簡便性ニーズに応える形で市場が成熟したことを示している。
第二に、伝統的なリーフ茶(急須で淹れる茶葉)の市場は、構造的な縮小が続いている。総務省の家計調査データは、この変化を定量的に示している。1世帯当たりの緑茶(リーフ茶)への年間支出金額は、平成20年(2008年)の5,031円に対し、近年では約3,200円台まで減少し、平成20年比で64%の水準にまで落ち込んでいる [8]。一方で、茶飲料への支出は同期間に5,664円から約8,300円へと増加し、平成20年比で146%に達している 8。リーフ茶の購入数量自体も、平成20年の982gから約3割減少している 8。
このデータが示す本質は、単なる「簡便性へのシフト」や「お茶離れ」ではない。注目すべきは、リーフ茶と茶飲料を合わせた1世帯当たりの茶関連総支出額が、年間約11,000円で安定して推移している点である 8。これは、消費者が「お茶」というカテゴリーに支払う対価の総額は変わっていないが、その価値の配分先が劇的に変化したことを意味する。価値は「高品質な茶葉そのもの」や「淹れるという行為」から、「いつでもどこでも飲める利便性」「一貫した味を提供するブランド」「携帯可能な容器」といった周辺価値へと大きく移転したのである。この価値移転を理解することが、国内市場戦略を策定する上での第一歩となる。
2.3 日本茶(緑茶)の輸出市場分析
国内市場の停滞とは裏腹に、日本茶の輸出市場は目覚ましい成長を遂げており、業界にとって最大の成長機会となっている。緑茶の輸出額は過去最高を更新し続けており、政府が掲げる2025年の輸出額目標312億円に対し、令和5年(2023年)には292億円を達成した 11。直近の月次データを見ても、前年同月比で大幅な増加が続いており、この勢いは加速している 12。
この輸出拡大の主役は、圧倒的に抹茶を含む粉末状の緑茶である 11。輸出統計によれば、粉末状緑茶は数量・金額ともに大きく伸びており、輸出単価もリーフ茶より高い水準で推移している 8。これは、抹茶が海外市場で単なる緑茶の一形態としてではなく、健康効果の高い「スーパーフード」や、カフェ文化に溶け込む高付加価値な嗜好品として独自のポジションを確立したことを示している。
主要な輸出先国は米国であり、輸出額全体の約3割を占め、特に高い成長率を示している 12。次いで、健康志向の強いドイツを中心とした欧州市場が続く 2。これらの市場では、オーガニック認証やサステナビリティへの関心も高く、高価格帯のプレミアム製品が受け入れられる土壌がある。
2.4 業界の主要KPIベンチマーク分析
業界が直面する課題と機会は、いくつかの主要業績評価指標(KPI)の動向に集約される。
- 荒茶価格の低迷: *荒茶(あらちゃ)*とは、茶農家が収穫した生葉を蒸熱・揉み・乾燥といった一次加工を施したもので、製茶問屋などがブレンド(合組)や火入れを行う前の半製品を指す。この荒茶の国内取引価格は、国内リーフ茶需要の減少を直接的に反映し、長期的な低下傾向にある 17。特に、生産量の多い煎茶の一番茶価格の低下が顕著であり、ピーク時から1kgあたり約2,000円も下落している 17。これは生産者の収益性を直撃し、経営意欲の減退や後継者不足に拍車をかける最大の要因となっている。
- 消費の構造転換: 前述の通り、一人当たりのリーフ茶消費量・支出額の継続的な減少と、茶飲料への支出増加という二つのKPIの著しい乖離が、業界の構造問題を最も象徴している 8。
- 輸出単価の上昇: 輸出市場では、高付加価値な抹茶が全体を牽引することで、輸出単価は上昇傾向にある 8。これは、国内市場のデフレスパイラルとは対照的な動きであり、業界の収益性改善の活路が海外にあることを示唆している。
これらのKPIをまとめた以下の表は、業界の経済的ジレンマを明確に示している。
| 指標 | 2008年(平成20年)頃 | 近年(2022-2023年頃) | トレンド | 示唆 |
|---|---|---|---|---|
| 荒茶平均価格(煎茶) | 高水準(ピーク時) | 低下傾向 17 | ↓ 長期低迷 | 生産者サイドの収益性悪化 |
| 世帯年間支出(リーフ茶) | 5,031円 8 | 約3,200円台 8 | ↓↓ 大幅減少 | 国内リーフ市場の構造的縮小 |
| 世帯年間支出(茶飲料) | 5,664円 8 | 約8,300円台 8 | ↑↑ 大幅増加 | 簡便性・ブランド価値への支払い意欲 |
| 緑茶輸出額 | 約45億円(2006年)16 | 292億円(2023年)11 | ↑↑↑ 急成長 | 海外市場が最大の成長機会 |
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
3.1 政治(Politics)
- 輸出における非関税障壁: 輸出拡大を目指す上で、各国の食品安全基準、特に残留農薬基準が実質的な非関税障壁となっている。EUでは、使用が許可される農薬をリスト化し、食品ごとに最大残留基準値(MRL)を定めるポジティブリスト制を採用している 18。日本の国内基準とは異なる厳しいMRLが設定されている農薬もあり、これに適合しない茶葉は輸出できない。近年もクロチアニジンなどのMRL引き下げが提案されるなど、規制は常に変動しており、生産段階からの厳格な管理と継続的な情報収集が不可欠である 18。
- 地理的表示(GI)保護制度の活用: 「宇治茶」や「八女伝統本玉露」といったGI登録は、産地のブランド価値を法的に保護し、海外での模倣品対策にも有効な手段である。近年では「深蒸し菊川茶」が日EUEPAに基づきEU域内で保護されるなど、その活用が進んでいる 20。しかし、GIの戦略的な活用はまだ一部の有名産地に留まっており、国内外の消費者に対する認知度向上とブランド価値の訴求が今後の課題である。
- 農協(JA)の政策と影響力: JAは、茶葉の集荷・販売、生産資材の供給、営農指導などを通じて、特に個々の茶農家に対して大きな影響力を持つ。JAの販売戦略や政策が、地域全体の生産動向や茶価に影響を与える構造となっている。
3.2 経済(Economy)
- 生産・加工コストの高騰: 近年、世界的なインフレと地政学的リスクの高まりを受け、生産コストが急騰している。特に、肥料価格は約35%、荒茶製造に不可欠な燃料費(重油)は約60%も高騰しており(令和2年比)、生産者の利益を著しく圧迫している 21。これに加えて、物流コストやペット樹脂・アルミ缶といった包装資材の価格上昇も、最終製品の価格に転嫁されつつある。
- 為替レートの変動: 為替レートは、輸出入の両面で事業の採算性に大きな影響を与える。円安局面は、ドルやユーロ建てでの輸出価格競争力を高め、輸出採算性を向上させる大きな追い風となる 22。一方で、紅茶葉やコーヒー豆、包装資材など海外からの輸入原料に依存する事業にとっては、仕入れコストの上昇要因となる 23。したがって、為替変動の影響は、企業の事業ポートフォリオ(輸出比率、輸入原料依存度)によって大きく異なる。
3.3 社会(Society)
- 健康志向の深化と科学的根拠への要求: 消費者の健康志向は、単なる漠然としたイメージから、より科学的根拠(エビデンス)を求める段階へと深化している。カテキンの抗肥満作用や認知機能への影響、テアニンのリラックス効果など、学術的な研究成果がメディアで報じられることで、消費者の購買動機を直接的に刺激している 24。このトレンドは、健康効果を具体的に表示できる「機能性表示食品」市場の拡大に直結している 5。
- ライフスタイルの二極化: 消費者の価値観は、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視し、手間を省き簡便性を追求する層と、「プロパ(プロセスパフォーマンス)」を重視し、あえて手間や時間をかけてプロセスそのものを楽しむ「丁寧な暮らし」や「本物志向」を求める層へと二極化している 27。前者はペットボトル飲料市場を支え、後者は高級リーフ茶や体験型消費の潜在的なターゲットとなる。この両極端なニーズにどう応えるかが、戦略の鍵を握る。
- サステナビリティ・エシカル消費への関心: 環境問題や社会問題への意識が高い消費者、特に若年層を中心に、自身の消費行動が社会や環境に与える影響を考慮する「エシカル消費」が広がりつつある。消費者庁の調査では、約半数がエシカル消費に興味を持つと回答している 29。オーガニック製品やフェアトレード認証商品、生産者の顔が見えるストーリー性のある商品への共感が、新たな購買決定要因となっている 30。
- 可処分時間・支出の奪い合い: お茶は、サードウェーブコーヒーやクラフトビール、ワインなど、他の嗜好品と消費者の限られた可処分時間と支出を奪い合っている。特にコーヒー市場は日本でも成長を続けており、カフェ文化の浸透とともに、若者層の生活に深く根付いている 32。お茶が単なる日常の飲料ではなく、「特別な時間」を演出する嗜好品として選ばれるための価値提案が求められる。
これらの社会トレンドは、一見すると個別の事象に見えるが、その根底には共通する大きな価値観の潮流が存在する。それは、消費を単なるモノの獲得ではなく、自己の身体、生活、そして社会に対してより意識的で良い選択をしたいという「コンシャス・コンサンプション(意識的な消費)」へのシフトである。健康志向は自己の身体への投資、丁寧な暮らしは自己の時間と心の豊かさへの投資、エシカル消費は社会と環境への投資と捉えることができる。したがって、これからのマーケティングは、単に機能性や利便性を訴求するだけでなく、この「意識的な消費」に応えるブランドストーリーを構築することが、高付加価値化と顧客ロイヤルティ獲得の鍵となる。
3.4 技術(Technology)
- 生産:スマート農業の進展: 労働力不足と高齢化が深刻な生産現場において、テクノロジーが解決策として期待されている。ドローンによる上空からの生育状況のモニタリングや病害虫の早期発見、AI画像解析を用いた最適な摘採時期の予測といった精密農業技術の実証が進んでいる 34。これらは省力化と同時に、データに基づいた栽培管理による品質の安定化・向上をもたらすポテンシャルを持つ。
- 加工・R&D:技術革新: 鮮度保持技術や抽出技術、粉末化技術の進化は、製品の品質向上や新たな商品形態の開発に貢献している。研究開発分野では、DNA情報から機能性成分の含量を予測し、育種期間を大幅に短縮する「スマート育種」技術が開発されている 36。また、カテキンやテアニンといった機能性成分の効能に関する科学的研究が日々進展しており、新たな製品開発のシーズとなっている 24。
3.5 法規制(Legal)
- 機能性表示食品制度: 2015年に導入されたこの制度は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示できるもので、健康志向の消費者に対する強力なマーケティングツールとなっている。緑茶関連でも、メチル化カテキンによる「目や鼻の不快感軽減」37や、難消化性デキストリンを配合した製品の整腸作用 38 など、多様な届出が受理されている。
- 食品表示法(原料原産地表示): 消費者の食の安全・安心への関心の高まりを受け、加工食品の原料原産地表示が義務化されている。緑茶においては、「国産」または都道府県名の表示が求められ、消費者の信頼を得る上で重要な要素となっている 39。
- 国際的なオーガニック認証: 国内の「有機JAS認証」に加え、海外市場、特に欧米への輸出においては、米国の「USDA Organic」や欧州の「EU Organic」といった国際的な認証の取得が事実上必須となる。これらの認証基準は、化学合成農薬や化学肥料の不使用など厳格な要件を定めており 40、取得はサステナブルなブランドイメージの構築に不可欠である。
3.6 環境(Environment)
- 気候変動の深刻な影響: 気候変動は、お茶の生産に直接的かつ深刻な脅威をもたらしている。近年の猛暑、局地的な豪雨、春先の霜害の増加は、茶葉の生育を阻害し、収量減や品質低下の原因となっている 42。中長期的には、気温上昇により茶の栽培適地が北上する可能性も指摘されており、気候変動への適応(耐暑性品種の開発など)は喫緊の経営課題である。
- 生物多様性保全への貢献: 静岡県の一部で伝統的に行われている「茶草場農法」は、茶園の畝間にススキやササを敷くことで土壌を豊かにするだけでなく、周辺の草地の維持管理を通じて希少な動植物の生息地を保全する効果がある 43。この農法は2013年に国連食糧農業機関(FAO)から世界農業遺産に認定されており、環境保全への貢献をブランド価値として訴求する優れた事例となっている。
- プラスチック問題への対応: 環境問題への関心の高まりから、プラスチックごみに対する社会の目は厳しくなっている。特に、一部のティーバッグ(主にナイロンやPET製の三角ティーバッグ)から、熱湯を注ぐことで大量のマイクロプラスチックが溶出するとの研究報告があり 45、消費者の健康不安や環境負荷への懸念を招くリスクがある 46。また、ペットボトルのリサイクル率向上や、植物由来素材への転換も、企業の社会的責任として強く求められている。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
4.1 供給者の交渉力:中〜高
供給者の交渉力は、その供給する資源の希少性によって二極化している。
- 茶農家(二極化): 全体として茶農家は高齢化と後継者不足により減少し、個々の農家の交渉力は伝統的に弱い。しかし、特定の有名産地(宇治、静岡本山など)や、手間のかかる有機JAS認証を取得した高品質な茶葉を安定的に供給できる生産者は希少性が高い。大手飲料メーカーは、こうした優良な生産者を確保するため、「茶産地育成事業」(伊藤園)47や「源流調達」(サントリー)48といった形で契約栽培を進め、長期的な関係構築を図っている。これらの戦略的パートナーとしての生産者は、相対的に高い交渉力を持つ。
- その他供給者: 肥料、農薬、包装資材(ペット樹脂、アルミ)のメーカーは、原料価格の市況に影響されるものの、業界全体に対して安定した供給力を持っており、一定の交渉力を有する。
4.2 買い手の交渉力:高
お茶業界における買い手の交渉力は、チャネルと最終消費者の両面で非常に強い。
- 大手飲料メーカー・小売: 伊藤園、サントリー、日本コカ・コーラといった大手飲料メーカーは、その購買量の大きさから、荒茶の仕入れにおいて強い価格交渉力を持つ。同様に、セブン&アイやイオンなどの大手小売チェーンは、プライベートブランド(PB)商品の開発 49 や、ナショナルブランド製品の棚割(配荷)を通じて、メーカーに対して絶大な影響力を行使する。
- 最終消費者: 消費者にとって、お茶ブランド間のスイッチングコストはほぼゼロに等しい。価格、味、ブランドイメージ、健康機能、利便性、購入チャネルなど、多様な要因に基づいて購買を決定するため、最終消費者全体の交渉力は極めて高い。
4.3 新規参入の脅威:中
成熟市場と見られがちだが、特定のセグメントでは新規参入の脅威が存在する。
- 異業種からの参入: 花王が「ヘルシア緑茶」で特定保健用食品市場を創出したように 51、独自の技術や研究開発力を持つ製薬会社や食品メーカーが、健康機能性を切り口に高付加価値市場へ参入する可能性は常にある。
- 海外高級ティーブランド: 「TWG Tea」52や「マリアージュ フレール」53といった海外の高級ブランドが、百貨店などを拠点に「贅沢な体験」や「ギフト」といった文脈で独自のポジションを築いている。彼らは日本の伝統的な茶舗とは異なる価値観で市場に参入している。
- IT企業・D2Cブランド: ECプラットフォームとSNSマーケティングを駆使し、小資本で特定の顧客セグメント(例:オーガニック志向、特定の産地のファン)に直接アプローチするD2C(Direct to Consumer)ブランドの参入が相次いでいる。
4.4 代替品の脅威:高
お茶は、消費者の「喉の渇きを潤す」「気分転換をする」「健康を維持する」といった多様なニーズを満たすが、それぞれのニーズに対して強力な代替品が存在する。
- コーヒー: 最大かつ最強の代替品である。日本のコーヒー豆市場は2033年までに34億米ドル規模への成長が予測されており 32、スペシャルティコーヒーやカフェ文化の浸透により、特に若者層の可処分時間と支出を巡って激しい競争を繰り広げている。
- その他飲料・サプリメント: ミネラルウォーター、炭酸飲料、ジュースはもちろんのこと、健康維持という目的においては、ビタミン剤やプロテインといった健康サプリメントも代替品となりうる。
4.5 業界内の競争:非常に高い
業界内の競争は、市場セグメントによって様相が大きく異なる。
- 飲料市場: 伊藤園(2024年4月期決算時点でシェア36%)を筆頭に、日本コカ・コーラ(綾鷹)、サントリー(伊右衛門)、キリン(生茶)といった大手飲料メーカーによる寡占的な競争環境にある 54。各社が巨額のマーケティング費用を投下し、新製品開発やリニューアルを繰り返す熾烈なシェア争いが繰り広げられており、価格競争も激しい。
- リーフ市場: 飲料市場とは対照的に、市場は非常に断片化している。何世代も続く伝統的な老舗茶舗、スーパーマーケットで販売されるPB商品、百貨店を主戦場とする高級ティーブランド、EC専業の新興D2Cブランドなどが混在し、それぞれのニッチ市場で競争している。
この業界の収益構造を理解する上で重要なのは、競争が「飲料」と「リーフ」という全く異なる力学を持つ2つのアリーナで展開されている点である。飲料市場は、規模の経済、効率的なサプライチェーン、そして強力なマーケティング投資が勝敗を分ける「消耗戦」の様相を呈している。一方で、リーフ市場は、ブランドの信頼性、品質の独自性、顧客との深い関係性といった無形資産が差別化の源泉となる「価値提案戦」である。したがって、企業は両市場で同じ戦略をとることはできず、それぞれのアリーナのルールに最適化された、全く異なる戦略的アプローチが求められる。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
5.1 サプライチェーン分析
お茶業界の伝統的なサプライチェーンは、多段階の複雑な構造を持っている。
伝統的サプライチェーンの構造と課題:
「茶農家(生産)→ 荒茶工場(一次加工)→ 茶市場/農協(集荷・流通)→ 製茶問屋/茶商社(仕上げ加工・合組)→ 飲料メーカー/小売 → 消費者」
この長い連鎖の各段階には、構造的な課題が存在する。
- 中間マージンと情報の非対称性: 多くの仲介業者が介在するため、各段階で中間マージンが発生し、最終製品価格に上乗せされる。同時に、生産者から消費者までの情報の流れが分断されがちである。生産者は最終的に誰が自分のお茶を飲んでいるのかを知ることが難しく、消費者は生産者のこだわりやストーリーを知る機会が少ない。
- 在庫リスクと品質管理: 多段階の流通を経るため、在庫が各所に滞留するリスクがある。茶葉は生鮮品であり、時間経過とともに品質が劣化するため、在庫管理は収益性に直結する。
- サプライチェーンの持続可能性への脅威: 最大の課題は、起点となる生産者の高齢化(基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳 55)と後継者不足、それに伴う耕作放棄地の増加である。これは、高品質な茶葉の安定供給そのものを脅かす、業界の存続に関わる根本的なリスクである。農林水産省の統計によれば、茶の栽培面積と生産量は長期的に減少傾向にある 9。
新たなモデルの台頭:
この硬直化したサプライチェーンに対し、新たなモデルが変化をもたらしつつある。
- D2C(Direct to Consumer)モデル: 生産者や小規模ブランドが、ECサイトやSNSを活用して消費者に直接商品を販売するモデル。中間業者を排除することで、価格競争力を高めると同時に、利益率を改善できる。さらに重要なのは、顧客データを直接収集し、生産者のストーリーやこだわりをダイレクトに伝えることで、ファンコミュニティを形成し、顧客との強いエンゲージメントを構築できる点である 56。
- 産地直送モデル: 大手メーカーも、特定の産地や農家と直接契約する「茶産地育成事業」などを通じて、サプライチェーンの短縮化と品質の安定化を図っている 47。これにより、トレーサビリティを確保し、「顔の見えるお茶」として消費者に安心感を提供できる。
5.2 バリューチェーン分析
お茶業界における価値の源泉は、時代とともに変化し、多様化している。
価値の源泉:
価値は、バリューチェーンの様々な活動から生み出される。
- 素材と技術(伝統的価値): 「高品質な茶葉(品種、栽培方法)」「伝統的な製茶技術(蒸し、揉み)」「合組(ごうぐみ)」(複数の荒茶をブレンドし、味や香りを設計する専門技術)57は、製品の品質を決定づける根源的な価値である。
- 科学と研究開発(新たな価値): カテキンやテアニンといった「健康機能性」に関する科学的研究開発と、それに基づく特許取得は、新たな付加価値を生み出す重要な源泉となっている。
- ブランドと体験(無形の価値): 「ブランド・マーケティング力」は、特に競争の激しい飲料市場において、消費者の知覚価値を形成する上で決定的な役割を果たす。また、カフェ運営やECサイトでのコンテンツ提供、産地ツアーといった「顧客体験」の提供は、モノ消費からコト消費へのシフトに対応し、顧客エンゲージメントを高める上でますます重要になっている。
利益率の源泉:
バリューチェーンの各段階で、利益率が最も高いのはどの部分か。現状では、生産(茶農家)段階の利益率は、荒茶価格の低迷と生産コストの高騰により、極めて低い水準にある。一次加工、流通段階も比較的利益率は低い。
一方で、利益率が高いのは、以下の部分に集中していると考えられる。
- ブランド・マーケティング: 強力なブランドを構築し、マス広告や販促活動を通じて高い価格設定を維持できる大手飲料メーカー。
- 研究開発(機能性): 特許化された機能性成分を保有し、健康という付加価値で差別化できる企業。
- 顧客体験の提供: 高級ティーサロンの運営や、独自のストーリーを持つD2Cブランドなど、価格競争から脱却し、高い顧客ロイヤルティを確立している事業者。
結論として、業界の付加価値は、上流の「生産」から下流の「ブランディング」「R&D」「顧客接点」へと大きくシフトしている。この構造を認識し、自社のバリューチェーンの中でどこに注力し、どこで利益を生み出すかを再設計することが、今後の戦略の核心となる。
第6章:顧客需要の特性分析
6.1 顧客セグメント分析
お茶の消費者は決して一枚岩ではなく、多様なニーズを持つセグメントに分類できる。
| セグメント化の軸 | セグメント例 | 情報収集行動 | 購買チャネル | KBF(購買決定要因) |
|---|---|---|---|---|
| 年齢層別 | Z世代・ミレニアル世代 | SNS(Instagram, TikTok)、インフルエンサー、Webメディア | コンビニ、カフェ、EC、ドラッグストア | トレンド、見た目(映え)、簡便性、ストーリー性、健康(お茶なしでは生活できない層も 59) |
| シニア層 | TVCM、新聞、店頭(店員のおすすめ) | スーパー、百貨店、専門店 | 慣れ親しんだ味、産地、品質、健康効果(習慣として 60) | |
| 飲用シーン別 | 自宅での日常消費 | TVCM、店頭POP | スーパー、ドラッグストア | 価格、容量、味の安定性 |
| 職場・外出先 | 自販機、コンビニの棚 | コンビニ、自販機、駅売店 | 簡便性、携帯性、ブランドの信頼性 | |
| ギフト・贈答 | 百貨店のカタログ、ECサイトのレビュー | 百貨店、高級専門店、EC | パッケージデザイン、ブランドの格、希少性、ストーリー | |
| 購買動機別 | 健康維持層 | 健康情報サイト、TVの健康番組、学術論文 24 | ドラッグストア、スーパー、EC | 機能性表示、カテキン含有量、オーガニック認証 |
| リラックス・気分転換層 | ライフスタイル雑誌、SNS | カフェ、専門店、EC | 香り、特定の成分(テアニン)、ブランドの世界観 | |
| 簡便性追求層 | TVCM | コンビニ、スーパー、自販機 | すぐ飲めること、後片付け不要、価格 | |
| 嗜好・こだわり層 | 専門誌、生産者のSNS、専門店 | 専門店、産地直送EC、D2Cサイト | 産地、品種、製法、生産者の哲学、淹れるプロセス |
6.2 インサイト分析
セグメント分析から、さらに深い消費者インサイトを掘り下げる。
- なぜ消費者は「急須でお茶を淹れなくなった」のか?
これは単一の理由ではなく、複合的な要因によるものである。消費者調査からは、「淹れるのが面倒、時間がない」「急須を持っていない」「他に飲みたいものがある」といった直接的な理由が挙げられる 60。しかし、その背景には、ライフスタイルの変化(タイパ重視)、住環境の変化(単身世帯の増加)、そしてコーヒー文化の浸透といった、より大きな社会構造の変化が存在する。若者にとって、急須で淹れるお茶は「古い」「難しい」「面倒くさい」といったネガティブなイメージと結びついている一方で、ペットボトルのお茶は「手軽」「早い」「新しい」というポジティブなイメージを持たれている 61。 - 「健康に良い」という認識は、実際の購買行動にどの程度結びついているか?
「お茶は健康に良い」という認識は、全世代に広く浸透している 60。しかし、それが購買の決め手となるかは、セグメントによって異なる。シニア層にとっては、長年の習慣と健康維持への関心から、リーフ茶の購入を支える強い動機となっている。一方、若年層は、健康への関心は高いものの、それが必ずしもリーフ茶の購入には直結しない。彼らにとっては、ペットボトル飲料や他の健康食品・サプリメントも同列の選択肢となる。若年層の購買を促すには、「健康に良い」という一般的なメッセージに加え、彼らの価値観に響く別の要素(例:SNSでの話題性、サステナビリティ、エモーショナルな体験 28)との組み合わせが不可欠である。 - 海外(北米・欧州)の消費者が抹茶や日本茶に求める価値は何か?
海外での抹茶ブームは、日本国内の消費文脈とは全く異なる価値観に基づいている。- 健康(スーパーフード): 抹茶は豊富な抗酸化物質(カテキン)を含む「スーパーフード」として認識されている。コーヒーに代わる、より穏やかな覚醒効果(L-テアニンによるリラックス効果との両立)をもたらす「サステナブルな覚醒剤」として、健康志向の強い層に受け入れられている 62。
- 文化と体験(エキゾチシズムとマインドフルネス): 抹茶は、”ZEN”や”WABI-SABI”といった日本文化の象徴として捉えられている。茶筅で抹茶を点てる行為そのものが、マインドフルネスやセルフケアの儀式(”Self-care Ritual”)として、若者層を中心に体験価値として消費されている 63。
- カフェ文化の一部: スターバックスやDunkin’といった大手チェーンが抹茶ラテをメニューに加えたことで、抹茶は特別なものではなく、コーヒーやラテと並ぶ日常的なカフェの選択肢の一つとなった 63。
- 美的な魅力(SNS映え): 鮮やかな緑色は、InstagramやTikTokといったビジュアル中心のSNSで「映える」要素として非常に人気が高い 62。
これらのインサイトから、国内外の市場で求められる価値が全く異なることがわかる。国内では「日常の中の安らぎと健康」、海外では「健康、文化体験、そしてファッション性」という、異なる価値軸に沿った戦略が求められる。
第7章:業界の内部環境分析
7.1 VRIO分析
企業の持続的な競争優位の源泉となる経営資源(リソース)や組織能力(ケイパビリティ)を、価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability)、組織(Organization)の4つの観点から分析する。
| 経営資源・ケイパビリティ | 価値 (V) | 希少性 (R) | 模倣困難性 (I) | 組織 (O) | 持続的競争優位 | 戦略的示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定優良産地との強固な関係 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 可能性あり | 関係性を深化させ、スマート農業導入支援やサステナビリティ基準の共同策定を通じ、他社が模倣できない独自の原料調達網を構築する。 |
| 独自の「合組(ごうぐみ)」技術 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 課題あり | 熟練の茶師の暗黙知に依存。技術の形式知化(データ化)と、AIによる支援システムを導入し、組織的能力として継承・発展させる必要がある。 |
| 機能性に関する特許・研究開発能力 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 可能性あり | 継続的なR&D投資が不可欠。大学や研究機関との連携を強化し、次世代の機能性成分に関する研究で先行する。 |
| 強力な販売網(自販機、コンビニ棚) | ◎ | ○ | △ | ○ | 限定的 | 競争が激しく、棚の維持には莫大なコストがかかる。D2Cなど、自社でコントロール可能なチャネルの構築が重要性を増す。 |
| 高いブランド認知度 | ◎ | ○ | △ | ○ | 限定的 | 広告宣伝による維持コストが高い。SNSやコミュニティ形成を通じ、広告依存からエンゲージメント主導のブランド構築へと転換する必要がある。 |
分析の要点:
伝統的な強みであった「合組技術」や「販売網」は、それ単体では持続的な競争優位を保つことが難しくなりつつある。「合組」は属人性が高く継承が課題であり、「販売網」は維持コストと競争の激化に晒されている。
今後は、「優良産地との関係性」を基盤に、テクノロジー(スマート農業、トレーサビリティ)を掛け合わせることで「模倣困難なサプライチェーン」を構築すること、そして「R&D能力」を活かして「パーソナライズド・ヘルスケア」という新たな価値領域を切り拓くことが、持続的競争優位の鍵となる。
7.2 人材動向
- 生産現場:
- 高齢化と後継者不足: 日本の農業全体が抱える構造問題であり、茶業も例外ではない。基幹的農業従事者のうち65歳以上が7割を超え、平均年齢は69.2歳に達している 55。この状況は、長年培われてきた栽培技術や土壌管理のノウハウといった貴重な無形資産の継承を危うくしている。新規就農者数は年間4.5万人程度いるものの、減少傾向にある 67。
- 専門人材:
- 茶師(合組師): 製品の最終的な品質を決定づける極めて重要な専門職。全国に700人ほどしかおらず、最高位の十段は十数名という希少な存在である 57。彼らの五感と経験に頼る「暗黙知」をいかに次世代に継承するかが大きな課題である。
- 日本茶インストラクター/アドバイザー: 消費者への日本茶の魅力伝達や教育を担う人材。認定者数は増加傾向にあり、2021年時点でインストラクターが4,839名、アドバイザーが12,587名となっている 68。彼らは、コト消費や体験価値を創出する上で重要な役割を果たす。
- 新たな人材需要:
- 業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)とグローバル化に伴い、従来とは異なるスキルセットを持つ人材の需要が高まっている。具体的には、スマート農業を推進する農業技術者やデータサイエンティスト、海外市場を開拓するグローバルマーケター、D2Cビジネスを運営するEC運営・デジタルマーケティング専門家などが求められる。
7.3 従業員の賃金相場とトレンド
茶業従事者の賃金に関する直接的な統計データは限定的だが、農業全体や食品製造業のデータから類推すると、他産業と比較して高い水準にあるとは言えない。特に生産現場では、労働集約的でありながら収益性が低いため、賃金水準が低迷し、若手人材の確保を困難にする一因となっている。今後、スマート農業の導入による生産性向上が、賃金水準の改善に繋がるかが注目される。
7.4 労働生産性
- 茶葉生産の労働生産性: 日本の農業全体の労働生産性は、欧米の先進国と比較して低い水準にある。特に土地集約的な経営が難しい中山間地の茶園では、労働生産性の向上が大きな課題となっている。例えば、米国のコメ農家の経営規模は日本の約80倍であり、生産コストには約7倍の差がある 69。茶業においても同様の構造的課題が存在する。
- 生産性向上へのインパクト: スマート農業や茶工場の自動化は、労働生産性を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めている。
- スマート農業の導入効果(試算): 静岡県での実証実験では、スマート防除機の使用により、手作業の動力噴霧器に比べて防除作業時間を削減できた [70]。また、ドローンやリモートセンシングによる茶園巡回作業の削減効果も報告されている 34。これらの技術を組み合わせることで、管理作業全体の労働時間を20%~30%削減することも可能と試算される。
- インパクト: これは単なるコスト削減に留まらない。創出された時間を、土壌分析や新たな販路開拓といった、より付加価値の高い活動に振り向けることが可能となり、経営全体の質的向上に繋がる。
第8章:AIの影響とインパクト(特別章)
8.1 序論:バリューチェーンを再定義する触媒としてのAI
お茶業界における人工知能(AI)は、単なる業務効率化ツールではない。それは、生産の持続可能性を高め、熟練の技を形式知化し、未開拓の顧客ニーズを掘り起こすことで、業界が抱える構造的課題を根本から解決し、新たな価値創出を可能にする戦略的基盤である。本章では、生産からR&Dに至るバリューチェーンの各段階において、AIがもたらす破壊的なインパクトを詳細に分析する。
8.2 生産(スマート農業):経験と勘からデータドリブンへ
- 生育状況の監視と最適化: ドローンや茶園に設置された定点カメラで撮影した大量の画像をAIが解析し、新芽の生育ステージ(開葉数など)をリアルタイムで推定する技術が実用化されつつある 34。これにより、生産者は広大で点在する茶園を人手で巡回する膨大な労力から解放され、より的確な栽培管理に集中できる。
- 病害虫の早期発見と精密防除: ドローンで撮影した茶園の分光画像やRGB比率をAIが分析し、ナガチャコガネなどの病害虫による被害箇所やその兆候を早期に特定する実証が進んでいる 34。これにより、農薬を茶園全体に散布するのではなく、必要な場所にのみピンポイントで散布する「精密防除」が可能となり、農薬使用量の大幅な削減と環境負荷の低減、コスト削減を実現する。
- 最適な摘採時期の予測: 茶葉の品質と収量は、摘採のタイミングに大きく左右される。伊藤園と富士通が共同開発した技術は、この領域にブレークスルーをもたらした。生産者がスマートフォンで摘採前の茶葉を撮影するだけで、クラウド上のAIが画像を解析し、品質の指標となるアミノ酸量や繊維量を推定する 35。これは、これまで熟練生産者の長年の経験と勘という「暗黙知」に頼っていた判断を、データに基づいた「形式知」へと転換する画期的な取り組みである。これにより、若手生産者や新規就農者でも、ベテランに近い精度で最適な摘採時期を判断できるようになり、技術継承の課題解決に大きく貢献する。
生産現場へのAI導入がもたらす真の価値は、単なるコスト削減や省力化に留まらない。その本質は「品質の標準化」と「生産の計画可能性」の実現にある。AIによる摘採時期予測は、生産者ごとの経験の差から生じる品質のばらつきを抑制し、飲料メーカーなどの買い手に対して、より均質で安定した品質の原料を供給することを可能にする。さらに、「この品質の茶葉が、あと何日で、何トン収穫可能か」という高精度な予測は、工場の稼働計画、物流、在庫管理といったサプライチェーン全体の最適化に直結する。この生産データと後述する需要予測データを連携させることで、真の「マーケットイン」型、すなわち「売れるものを、売れるときに、売れるだけ作る」生産体制の構築が可能となり、フードロス削減と収益性向上に大きく貢献する。
8.3 加工・品質管理:匠の技のデジタルツイン
- 品質の客観的評価: AI画像解析は、荒茶の形状、色、サイズなどを分析し、その品質を客観的に評価・格付けする技術にも応用されている。これにより、人間による官能評価のばらつきを補完し、茶市場などでの取引の透明性と公平性を向上させることが期待される。
- 「合組(ブレンド)」技術の継承と支援: *合組(ごうぐみ)*は、複数の産地や品種の荒茶をブレンドし、ブランドとして安定した品質と独自の香味を創り出す、茶師の最も重要な技術である 57。このプロセスは、茶師の鋭敏な五感(味、香り、色、形状)と長年の経験に支えられた、まさに芸術的な暗黙知の領域であった。現在、味覚センサーや嗅覚センサー、色彩計といったデバイスを用いて官能評価をデータ化し、AIに学習させることで、この匠の技をデジタル化する研究が進んでいる 75。
AIは茶師に取って代わる存在ではなく、その能力を拡張し、創造性を解放する「協働パートナー」となりうる。茶師の仕事の本質は、単に毎年同じ味を再現することだけではない。その年の気候や茶葉の出来栄えといった無数の変動要因を読み解き、時には新たな香味を創造することにある 57。AIは、過去の膨大なブレンドデータと官能評価データを学習し、「この香味目標を達成するためには、A産地の茶葉をx%、B品種をy%配合する」といった形で、茶師に新たな発想の起点となる複数の選択肢を提示できる。これにより、茶師は定番商品の品質維持といったルーティンワークの一部をAIに任せ、より創造的な作業(新商品の開発、希少茶葉のポテンシャルを最大限に引き出すブレンドの探求など)に集中できるようになる。AIが「再現性」を担保し、人間が「創造性」を発揮するという、新たな協業モデルが実現する。
8.4 需要予測とマーケティング:マスからパーソナルへ
- 高精度な需要予測: 過去の販売実績、天候データ、曜日、プロモーション情報、SNSのトレンドといった膨大な変数をAIに学習させ、製品ごとの需要を高精度で予測するモデルが、多くの食品・飲料メーカーで導入されている 78。これにより、欠品による販売機会の損失と、過剰生産による廃棄ロスという二律背反の課題を同時に解決し、サプライチェーン全体の効率を最大化する。
- 消費シーンの可視化とパーソナライズド広告: 日本コカ・コーラの事例のように、SNSに投稿された製品画像をAIが解析することで、「どのようなシーンで(例:オフィスでの昼食時、週末のアウトドア)」「何と一緒に(例:お弁当、スイーツ)」自社製品が消費されているかを大規模に可視化できる 81。このインサイトに基づき、ターゲットセグメントごとに最適化された広告クリエイティブを生成・配信することで、マーケティングROIを大幅に向上させることが可能となる。
8.5 新サービス開発:パーソナライゼーションの究極形
- 「パーソナライズド・ティー」サブスクリプション: AIがもたらす最も破壊的なインパクトは、この新サービス領域にある。これは、顧客がウェブサイトやアプリ上で簡単な診断(味の好み、生活リズム、健康上の関心事、ストレスレベルなど)に答えるだけで、AIがその人に最適な茶葉のブレンドを提案し、定期的に自宅に届けるD2C(Direct to Consumer)ビジネスモデルである 82。
- 事業可能性: 日本酒業界では、既に味香り戦略研究所などが、個人の嗜好性診断と生成AIを組み合わせたレコメンドサービス「蔵酒Match」を実用化している 85。お茶は、産地、品種、蒸し時間、焙煎度合いといった要素の組み合わせによるフレーバーの多様性と、カテキン、テアニンなど健康機能性の豊富さから、パーソナライゼーションとの親和性が極めて高い。このモデルは、価格競争に陥っている国内リーフ市場から完全に脱却し、高い顧客ロイヤルティとLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を構築する、まさにゲームチェンジャーとなりうるポテンシャルを秘めている 56。
8.6 R&D:開発サイクルの飛躍的短縮
- AI育種(ゲノミックセレクション): 従来、十数年単位の時間を要した新品種の開発プロセスは、AIによって劇的に加速される。ドローンとAIを用いて、圃場にある数千の候補系統の生育特性(高さ、葉の数、病害耐性など)を非破壊で網羅的にデータ化し、それらのゲノム情報と組み合わせることで、優良な系統を高精度で予測・選抜する 88。これにより、特定の機能性成分(高カテキン、高テアニンなど)を多く含む新品種や、気候変動に適応した耐暑性・耐病性品種の開発サイクルが飛躍的に短縮される。
| バリューチェーン段階 | AIの応用例 | 現状 | 将来のポテンシャル | 成功の鍵 |
|---|---|---|---|---|
| 生産 | ドローン画像解析による生育監視・病害虫検知 34、AIによる最適摘採時期予測 73 | 実証段階~一部実用化 | 茶園管理の完全自動化、収量・品質の最大化 | 高解像度画像データ、気象データの蓄積 |
| 加工・品質管理 | AI画像解析による荒茶の品質評価、センサーとAIによる合組(ブレンド)支援 77 | 研究開発段階 | 熟練技術のデジタル化と継承、品質の完全な標準化 | 味覚・嗅覚センサーの精度向上、官能評価データのDB化 |
| 需要予測・マーケティング | AIによる需要予測モデル 78、SNS画像解析による消費シーン可視化 81 | 広く実用化 | リアルタイムでの需要変動への対応、超パーソナライズド広告 | POSデータ、気象データ、SNSデータの統合分析基盤 |
| 新サービス開発 | 生成AIによるパーソナライズド・ブレンド提案 87 | 一部業界で実用化 | 個人の健康データ(ウェアラブル等)と連携した究極のパーソナライゼーション | 嗜好性診断アルゴリズム、顧客との直接接点(D2C) |
| R&D | AI育種(ゲノミックセレクション)による新品種開発の高速化 88 | 研究開発段階 | 気候変動や新たなニーズに即応した品種開発、開発期間の1/2以下への短縮 | ゲノムデータと表現型データ(生育データ)の大量収集 |
第9章:主要トレンドと未来予測
これまでの分析を踏まえ、今後5~10年のお茶業界を形成する主要なメガトレンドと、その帰結として予測される未来像を以下に示す。
- 健康機能性の科学的探求: 「体に良い」という漠然としたイメージから、「どの成分が、どのようなメカニズムで、何の健康課題に貢献するのか」という科学的根拠に基づいた製品開発競争が激化する。「機能性表示食品」市場の拡大はその一端に過ぎず、将来的には個人の遺伝子情報や腸内環境に合わせた、よりパーソナライズされた健康茶へと進化する可能性がある。
- サステナビリティと完全な透明性: オーガニックやフェアトレードといった認証の取得は、もはや差別化要因ではなく、プレミアム市場における「入場券」となる。今後は、ブロックチェーン技術などを活用し、茶葉がどの畑で、誰によって、どのように栽培・加工されたかという生産履歴(トレーサビリティ)を消費者がスマートフォンで瞬時に確認できるような、完全な透明性が求められるようになる。
- グローバル市場の二極化: 海外市場は、二つの異なる方向に大きく分化していく。一つは、健康・ウェルネス志向の強い欧米市場を中心とした「高級抹茶・高品質煎茶」市場である。ここでは、品質、ストーリー、サステナビリティが重視され、高価格帯での競争が展開される。もう一つは、主にアジア市場向けの「安価な緑茶原料」としての需要である。これは、現地の飲料メーカーなどが使用するフレーバーティーやブレンドティーのベース原料としての市場であり、価格競争が中心となる。
- 「体験型」消費の本格化とリアル空間の再価値化: モノの所有からコトの体験へと消費者の価値観がシフトする中、お茶の楽しみ方も多様化する。高級ホテルや専門店が提供する洗練された「ティーサロン」、生産者と交流しながら茶摘みや製茶を体験できる「産地ツーリズム(茶畑体験)」、オンラインでの「淹れ方教室」など、お茶を五感で楽しむ体験型サービスが新たな収益源として本格化する。
- D2Cとコミュニティ形成によるマイクロブランドの勃興: ECプラットフォームとSNSの進化は、小規模な生産者や新興ブランドが、大手と同じ土俵で戦うことを可能にする。彼らは、独自の哲学やストーリーをSNSで直接発信し、共感する消費者と深い関係性を築くことで「ファンコミュニティ」を形成する。このコミュニティは、単なる顧客であるだけでなく、ブランドの共創者となり、マイクロブランドの持続的な成長を支える基盤となる。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
| プレイヤー分類 | 主要企業 | 戦略・特徴 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|---|
| 大手飲料メーカー | 伊藤園 | 「お~いお茶」を核とした圧倒的なブランド力。原料調達から販売までの一貫体制。「茶産地育成事業」によるサプライチェーン強化 47。AI活用にも積極的 35。 | 業界トップのブランド認知度と販売網、原料調達力。 | 主力事業が国内成熟市場にあり、新たな成長ドライバーの創出が課題。 |
| サントリーフーズ | 「伊右衛門」ブランドでの京都福寿園との協業による「本物感」の演出。「源流調達」による原料確保 48。巧みなマーケティングとリニューアル戦略。 | 高いマーケティング能力とブランド構築力。強力な流通網。 | 茶事業への専業度が低く、経営資源の配分が他事業に左右される可能性。 | |
| 日本コカ・コーラ | 「綾鷹」ブランドで「にごり」という新たな価値を市場に定着させた。急須で淹れたような味わいの再現を追求。 | 世界的なマーケティング知見と圧倒的な資本力、自販機網。 | 外資系企業であり、日本の伝統的な生産者との関係構築に課題を持つ可能性。 | |
| 大手茶葉メーカー/商社 | (国内の主要な老舗、大手問屋) | 伝統的な「合組」技術と、長年の取引で築いた産地との関係性が強み。百貨店や専門店など、特定のチャネルに強い。 | 高品質な茶葉の鑑定・ブレンド能力、特定の顧客層からの高い信頼。 | デジタルマーケティングやD2Cへの対応の遅れ。若者層へのアプローチが弱い。 |
| 新興・海外ブランド | TWG Tea 52, MATCHAFUL 90 | 「高級感」「体験」「グローバルな世界観」を武器に、新たな顧客層を開拓。ティーサロン併設によるブランド体験の提供。 | 既存の業界の常識にとらわれない斬新なコンセプトとマーケティング。 | サプライチェーンの脆弱性。生産基盤を持たないため、高品質な原料の安定確保が課題。 |
| 小売(PB) | セブン&アイ、イオン、ファミリーマート | 大手飲料メーカー(伊藤園など)との共同開発による高品質・低価格なPB商品を展開 49。圧倒的な販売チャネルが武器。 | 高い価格競争力と、全国を網羅する販売網による顧客接点の多さ。 | ブランドイメージの構築が難しい。利益率が低い価格競争に陥りやすい。 |
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
11.1 業界の勝敗を分ける決定的要因
これまでの分析を統合すると、今後5~10年でお茶業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因は、以下の3つの能力に集約される。
- 二極化する市場への対応能力: 国内の「簡便・健康志向の飲料市場」と「体験・こだわり志向のリーフ市場」、そして海外の「プレミアム抹茶市場」という、全く異なる価値観を持つ市場に対し、それぞれに最適化された事業ポートフォリオを構築・運営できるか。
- サプライチェーンの再構築能力: 生産者の高齢化という不可逆的な流れに対し、スマート農業などのテクノロジーを導入して生産性を向上させるとともに、トレーサビリティを確保することで「サステナビリティ」を競争力に変えられるか。
- データとAIの活用能力: 勘と経験に頼った経営から脱却し、生産からマーケティング、新サービス開発に至るまで、AIを活用してデータに基づいた意思決定を行い、顧客一人ひとりにパーソナライズされた価値を提供できるか。
11.2 機会(Opportunity)と脅威(Threat)
この市場で生き残り、成長するためには、以下の機会を捉え、脅威に備える必要がある。
- 捉えるべき機会:
- グローバルな抹茶市場の急成長: 最大の成長機会。特に北米・欧州の健康・ウェルネス市場への食い込みが鍵。
- 科学的根拠に基づく健康価値の追求: 機能性表示食品制度を最大限に活用し、他社との明確な差別化を図る。
- 体験型消費(コト消費)へのシフト: 産地ツアーやオンラインセミナー、サブスクリプションを通じたコミュニティ形成により、高付加価値なビジネスモデルを構築する。
- AIによるパーソナライゼーション: 個々の顧客ニーズに応えるD2Cモデルで、新たな収益源を確立する。
- 備えるべき脅威:
- 国内サプライチェーンの崩壊リスク: 生産者の高齢化・後継者不足は待ったなしの課題。放置すれば、高品質な国産茶葉の調達自体が困難になる。
- コーヒー市場との絶え間ない競争: 若者層の可処分時間と支出を巡る、コーヒーとの代替品競争は今後も続く。
- 気候変動による生産リスク: 異常気象による収量・品質の不安定化。
- 異業種からのディスラプション: ヘルスケアやITといった異業種が、新たなテクノロジーやビジネスモデルで市場の前提を覆す可能性。
11.3 事業ポートフォリオのジレンマと構築
「リーフ vs. 飲料」「国内 vs. 海外」「伝統 vs. 革新」というジレンマに対し、各事業を「金のなる木」「花形」「問題児」「負け犬」に分類し、最適な事業ポートフォリオを構築する必要がある。
| 相対的市場シェア:高 | 相対的市場シェア:低 | |
|---|---|---|
| 市場成長率:高 | 花形(Star) ・海外プレミアム抹茶事業 ・国内機能性表示飲料事業 | 問題児(Question Mark) ・AIパーソナライズドD2C事業 ・体験型サービス事業 |
| 市場成長率:低 | 金のなる木(Cash Cow) ・国内定番ペットボトル飲料事業 | 負け犬(Dog) ・国内汎用リーフ茶事業 |
ポートフォリオ戦略:
「金のなる木」(国内定番飲料)で得たキャッシュを、「花形」(海外抹茶、機能性飲料)に重点的に再投資し、市場シェアを確固たるものにする。同時に、将来の「花形」候補である「問題児」(AIパーソナライズドD2C、体験型サービス)へも戦略的投資を行い、新たな成長の芽を育てる。「負け犬」(国内汎用リーフ)事業は、不採算であれば縮小・撤退を検討し、経営資源を成長領域に集中させる。
11.4 戦略的オプションの提示と評価
| 戦略的オプション | メリット | デメリット・リスク | 成功確率(主観評価) |
|---|---|---|---|
| 1. スマート農業ベンチャーのM&A | 生産技術とデータ解析能力を迅速に獲得。サプライチェーンの垂直統合を実現。 | 企業文化の融合の難しさ。M&A後の統合作業(PMI)の負荷。 | 中 |
| 2. IT企業との戦略的アライアンス | AI開発やD2Cプラットフォーム構築のノウハウを低リスクで導入可能。 | パートナー企業への依存度が高まる。データ所有権や利益配分に関する交渉が複雑。 | 高 |
| 3. D2Cパーソナライズド事業の自社立ち上げ | 顧客データとブランドを完全に自社でコントロール。高い利益率が期待できる。 | 新規事業立ち上げに伴う多大な初期投資と人材確保。既存事業とのカニバリゼーションのリスク。 | 中 |
| 4. 海外有力ティーブランドの買収 | 海外市場でのブランド認知度と販売チャネルを即座に獲得。 | 高額な買収費用。ブランドイメージの維持・管理の難しさ。 | 低 |
11.5 最終提言:AIを活用した「パーソナライズド・ウェルネス・プラットフォーマー」への変革
提言:
従来の製茶・飲料メーカーから脱却し、AIを活用して個々の顧客に最適な「健康と安らぎ」を提供する「パーソナライズド・ウェルネス・プラットフォーマー」へと変革すべきである。
この戦略は、単一の製品を売るのではなく、顧客との長期的な関係性を基盤に、データに基づいたソリューション(製品とサービス)を提供し続けるビジネスモデルへの転換を意味する。
実行に向けたアクションプラン概要:
| フェーズ | 期間 | 主要アクション | KPI | 必要リソース |
|---|---|---|---|---|
| フェーズ1:基盤構築 | 1~2年 | ・スマート農業技術を持つベンチャーとの提携またはM&A ・D2Cパーソナライズド事業の専門部署設立 ・サプライチェーンのトレーサビリティシステム(ブロックチェーン)のパイロット導入 | ・契約農家におけるスマート農業導入率 ・D2Cサイトの会員登録者数 ・トレーサビリティ実証実験の完了 | ・M&A/提携資金 ・データサイエンティスト、DX人材の採用 ・ITシステム開発投資 |
| フェーズ2:事業展開 | 3~4年 | ・D2Cパーソナライズド・ティーのサブスクリプションサービス本格開始 ・機能性表示食品のラインナップ拡充(ストレス、睡眠、免疫など) ・海外(北米)でのプレミアム抹茶D2Cチャネル開設 | ・D2C事業の売上高、LTV、解約率 ・機能性表示食品の市場シェア ・海外EC売上高 | ・大規模マーケティング投資 ・海外現地法人設立または提携 ・顧客サポート体制の拡充 |
| フェーズ3:プラットフォーム化 | 5年~ | ・顧客の健康データ(ウェアラブルデバイス等)との連携によるレコメンド精度の向上 ・産地ツアーやオンラインコミュニティなど、体験型サービスの拡充 ・蓄積データを活用したBtoBソリューション(他社への需要予測提供など)の検討 | ・プラットフォーム経由の総売上高 ・顧客エンゲージメント指標(コミュニティ参加率など) ・新規事業(BtoB)の売上高 | ・データ連携基盤への追加投資 ・コミュニティマネージャーの配置 ・新規事業開発チームの組成 |
この変革は容易ではないが、業界の構造変化に対応し、新たな成長軌道を描くための最も確実な道筋であると結論付ける。
第12章:付録
引用文献
- お茶市場| 市場規模 成長性 産業動向 予測 2025-2033年 【市場調査 …, https://www.gii.co.jp/report/imarc1642555-tea-market-report-by-product-type-packaging.html
- 緑茶市場規模、業界シェア、世界需要、予測、2032年, https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E6%A5%AD%E7%95%8C-%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/%E7%B7%91%E8%8C%B6%E5%B8%82%E5%A0%B4-100790
- Tea Market Size, Share, Growth Trends & Global Industry Analysis …, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-tea-market
- 世界の茶市場の規模、シェア、2033年までの予測, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/tea-market
- 【調査レポート】 日本の茶市場2025年-2033年, https://www.globalresearch.co.jp/japan-tea-market/
- Tea Market Size, Share & Trends | Industry Report, 2030 – Grand View Research, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/tea-market
- 清涼飲料と嗜好品の市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=22012&view_type=2
- 茶業及びお茶の文化に係る現状と課題, https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/230929-7.pdf
- 【日本のお茶の現状】農林水産省「茶をめぐる情勢(令和5年2月時点)」公開, https://teabank.jp/column/column765/
- 第145回:『茶をめぐる情勢』をどう読み解くか? | 合同会社ティーメディアコーポレーション, https://www.teamedia.co.jp/blog_145/
- 茶業及びお茶の文化に係る現状と課題 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/230929-4.pdf
- お知らせ一覧 | 日本茶輸出促進協議会, https://nihon-cha.or.jp/export/exporting/
- 参考情報 | 日本茶輸出促進協議会, https://nihon-cha.or.jp/export/reference/
- 15.お茶の輸出入の動向 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-130.pdf
- 輸出品目別レポート(緑茶) – ジェトロ, https://www.jetro.go.jp/ext_images/industry/foods/item/10.pdf
- 【日本のお茶の現状】農林水産省「茶をめぐる情勢(令和5年2月時点)」公開, https://teabank.jp/column/column765/?lang=en
- 第2章 静岡市における茶業の現状と課題, https://www.ochanomachi-shizuokashi.jp/gcswp/wp-content/uploads/2021/01/7e9969caa3b404260d52b89d757c3f1b.pdf
- 茶の輸入規制、輸入手続き(EU、アイルランド、イタリア、オランダ、オーストリア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ルーマニア) | 日本からの輸出に関する制度 – 農林水産物・食品 – EU – 欧州 – 国・, https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/foods/exportguide/greentea.html
- 緑茶の輸出ヒント, http://nagamitsu1950.sakura.ne.jp/siryo-2-260925.pdf
- 海外における日本のGI保護 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/protection_abroad/index.html
- 荒茶製造における費用高騰調べ(令和2年と4年の比較) – 京都府茶協同組合, https://kyocha.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-19-1.pdf
- 円安が食品輸出に与える影響やメリットとは?販路拡大のポイントも紹介 – JFEX, https://www.jfex.jp/hub/ja-jp/blog/article10.html
- 為替レートの変動と原料輸入, https://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~imozuru/img/file10917.pdf
- 緑茶の抗肥満作用を柑橘由来成分が増強 | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY), https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/669/
- 緑茶に認知症予防効果?~65歳以上の日本人約9千人の脳を解析|CareNet.com, https://www.carenet.com/news/general/carenet/60004
- 令和 2 年度 研究概要 – 静岡県立大学 食品栄養科学部, https://dfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/labs/tsc/kenkyugaiyo/r2.pdf
- 2024年食市場のトレンド予測「HITキーワードBest10」 | 食品開発提案企業【清田産業株式会社】, https://www.kiyota-s.com/kiyota-diary/2154
- 若者の消費トレンドに関する調査 – ネオマーケティング, https://corp.neo-m.jp/report/investigation/life_031_youth-consumption-trend
- (調査結果) 令和5年度第3回消費生活意識調査 調査概要 1. 調査方法 インターネットを利用 – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/assets/consumer_research_cms201_231109_02.pdf
- Greenroom「サステナブルな商品・サービスの消費行動調査~食品編~2024」, https://green-note.life/8305/
- –買い物におけるサステナビリティの現実 – 2022-2024調査から見る意識と行動の進展と店舗戦略へのヒントを探る – スコープ販促創造研究所, https://sp-lab.scope-inc.co.jp/articles/ddp_report_2406-1/
- 日本のコーヒー豆市場規模は2033年までに34億米ドルに達すると予測|年平均成長率5.73%, https://www.atpress.ne.jp/news/1559937
- 日本のコーヒー市場規模とシェア分析 – 成長動向と予測レポート 2025-2033 – データリソース, https://www.dri.co.jp/auto/report/renub/250201-japan-coffee-market-size-and-share-analysis.html
- 茶におけるスマート農業技術の実証について – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/kanto/seisan/kankyo/smart/attach/pdf/2021smafo-10.pdf
- 伊藤園、AIでお茶の摘採期見極めるシステムに磨き 熟練の技や高額な成分分析機の代替として提案 農業DX化推進 – 食品新聞, https://shokuhin.net/130661/2025/09/14/nocategory/
- 【プレスリリース/記者説明会のご案内】日本茶の機能性成分含量を大量のDNAから予測し、新品種の開発へ ~品種改良の期間短縮と省力化、多様なニーズへの対応が可能に – 静岡大学, https://www.shizuoka.ac.jp/event/detail.html?CN=6666
- 10/6 機能性表示食品の届出情報(べにふうき緑茶ティーバッグ[森永製菓]等 追加2製品を公表)/消費者庁, https://news.e-expo.net/gyousei/2016/10/post-104-63.html/
- 緑茶(J409)の機能性表示食品届出情報【健康食品原料検索サイトバルバル(BALBAL)】, https://bal-bal.com/food/detail/8845
- 茶の表示の記載例 – 茶ガイド-全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会, https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/seisan03b.htm
- 有機JAS認証の仕組み, https://accis.jp/jas1/
- 有機栽培茶とオーガニック茶の違いと無農薬栽培茶について – IDLE MOMENT, https://idle-moment.com/dictionary/about-organic/
- 286 工芸作物 茶 (ア)現在の影響状況 本事業において実施した自治体へのアンケート結果による – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/report2018/attach/pdf/report-100.pdf
- 保全活動のコストの算出と効果の評価 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/c_bd/pr/attach/pdf/pr-32.pdf
- 茶草場の伝統的管理は生物多様性維持に貢献 – 農研機構, https://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result30/result30_08.html
- ティーバックのお茶が危険!?デメリットとプラスチックフリーで楽しむアイテム・方法をご紹介, https://www.qualselect.com/blogs/health-blog/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%8C%B6%E3%81%8C%E5%8D%B1%E9%99%BA-%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B
- ティーバッグにもマイクロプラスチックが潜んでいる?エコなお茶の淹れ方 – ELLE, https://www.elle.com/jp/gourmet/a39184724/plastic-free-teabags-220228-hns/
- 地域における食品メーカーの戦略展開と競争優位:伊藤園の事例 – 酪農学園大学学術研究コレクション, https://rakuno.repo.nii.ac.jp/record/5550/files/J-43-1-25.pdf
- サントリー「伊右衛門」で「源流調達」の取り組み強化 一番茶から秋冬番までの全茶期を活用した商品設計 – 食品新聞, https://shokuhin.net/76952/2023/06/13/inryou/inryou-inryou/
- 「ファミマル」は環境にも“マル”! PB飲料6品の容器を100%リサイクルペットボトルに切り替え 年間約2,900トンのプラスチック削減効果 “地球色のコンビニ”として、環境保全のための取り組みを強化|ニュースリリース|ファミリーマート, https://www.family.co.jp/company/news_releases/2024/20240321_02.html
- 緑茶はファミマが一番ウマい?コンビニ3社のオリジナル製品を飲み比べ! – エキサイト, https://www.excite.co.jp/news/article/Bizjournal_202302_post_332310/
- 異業種へ参入し成功した商品に関する 特許出願分析, http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2015_08_1072.pdf
- 800種類以上の茶葉を展開|『TWG Tea』に学ぶグローバルニッチ戦略, https://global-biz.net/southeast-asia/singapore/luxuryteajourney_twgt-sg/
- 東京、銀座、新宿で買える海外ハイブランドの紅茶専門店8選。ここでしか買えないギフトも! | 三越伊勢丹の食メディア | FOODIE(フーディー), https://mi-journey.jp/foodie/73350/
- コンビニ飲料売り場で火花散らす「ペットボトルお茶戦争」…消費者トレンド変化で実績に明暗くっきり, https://www.businessinsider.jp/article/green-tea-market-share-battle/
- 第3節 担い手の育成・確保と多様な農業者による農業生産活動 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/r6_h/trend/part1/chap3/c3_3_00.html
- D2Cとは?従来のビジネスモデルとの違い、メリットとブランド事例を解説 | DATA INSIGHT, https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2023/021390/
- 日本茶における茶師の役割 | 静岡茶商工業協同組合, https://www.ocha.or.jp/column/745/
- 茶師がつくりだす、日本茶の“モノ消費”と“コト消費” | WORKERS TREND, https://wawawork.work/workerstrend/skills/1993/
- お茶に関する調査(2023年) | リサーチ・市場調査ならクロス・マーケティング, https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20231012tea
- 1.緑茶等の消費実態について 2.食文化の継承について, https://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1702.pdf
- 若者の緑茶消費に関するテキストマイニングを用いた調査 – 金沢星稜大学, https://www.seiryo-u.ac.jp/u/research/gakkai/ronbunlib/e_ronsyu_pdf/No141/09_makino_kishimoto141.pdf
- なぜ今、抹茶が世界で人気?海外市場でのトレンドと売れ筋商品を解説 | YUSHUTSU, https://yushutsu.jp/2025/07/matcha/
- 抹茶がアメリカでバズってる5つの理由 〜 北米560億円市場の波に乗るための実践ガイド 〜 – デザイン会社 ビートラックス: ブログ freshtrax, https://blog.btrax.com/jp/matcha-in-us/
- Articles | 海外で抹茶の需要が拡大中!人気の理由は?, https://yellowpage.tokyo/articles/matcha
- (1)基幹的農業従事者 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html
- 日本の農業人口はどう推移している? 農業現場へ与える影響とは – minorasu(ミノラス, https://minorasu.basf.co.jp/80076
- 令和4年新規就農者調査結果 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sinki/r4/index.html
- 日本茶インストラクター協会とは? – Re:leaf Record, https://releafrecord.com/article/229/
- 経営規模・生産コスト等の内外比較 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/attach/pdf/230731-67.pdf
- 茶における – スマート農業技術の – 静岡県, https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/271/sumanopanf.pdf
- 伊藤園と富士通 AI画像解析による茶葉の摘採時期判断技術を共同開発 – AIsmiley, https://aismiley.co.jp/ai_news/ai_tea_itoen/
- 伊藤園と富士通、AI画像解析による茶葉の摘採時期判断の試験運用を開始 – Biz/Zine(ビズジン), https://bizzine.jp/article/detail/7524
- 伊藤園、AI画像解析で茶葉の摘採時期を判断 富士通と共同で技術開発 | 財経新聞, https://www.zaikei.co.jp/article/20220511/671487.html
- 伊藤園×富士通、AI画像解析による茶葉の摘採時期判断をスマホで – マイナビニュース, https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220510-2342420/
- 沢井製薬、薬の「味」「食感」機械やAIで客観評価―食品向け技術を応用、目指す「良薬は口に良し」, https://answers.ten-navi.com/pharmanews/29919/
- “どんな匂いに感じるか”を定量評価する「官能評価AI」 人間頼りの作業を機械化 – ITmedia NEWS, https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/24/news159.html
- 味のデジタル化とは~新たな「おいしさ」の世界~|フードラボ – 懐刀 – 株式会社 三友, https://futokoro.san-yu.co.jp/media/2025/02/28/120
- Customer Driven Supply(サプライチェーン) | NTTデータ, https://www.nttdata.com/jp/ja/industries/food/customerdrivensupply/
- AI需要予測が拓く食品製造業のフードロス対策 – DATAFLUCT, https://datafluct.com/column/clm0012/
- 食品業界のAI活用方法を、事例8点を交えてご紹介 – MatrixFlow, https://www.matrixflow.net/case-study/78/
- コカ・コーラのAI解析プロジェクト、ブレインパッドが支援 飲料の消費シーンの把握目指す, https://markezine.jp/article/detail/27901
- D2Cサブスクの成功事例7選|失敗しないための共通点と始め方をプロが徹底解説, https://stock-sun.com/column/how-to-success-d2c-subscription/
- D2Cはサブスクモデルを採用すべきか?国内D2Cブランド事例から解説 – Shopi Lab(ショピラボ), https://shopi-lab.com/know-how/43568/
- パーソナライズ商品の成功事例15選|D2Cビジネスのポイントやツールも紹介 – ヨミトル, https://shindancloud.com/trend/1477
- 嗜好性診断×生成AIによるレコメンドプラットフォーム始動、第一弾は“日本酒” – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000097214.html
- 嗜好性診断×生成AIによるレコメンドプラットフォーム、第一弾は“日本酒”で始動 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000059888.html
- 嗜好性診断×生成AIによるレコメンドプラットフォーム始動、 第一弾は“日本酒”, https://mikaku.jp/wp-content/uploads/2025/04/press20250429.pdf
- ドローン×AIで進化する作物計測技術 ――ダイズのバイオマスを効率的に計測する―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部, https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20240903-1.html
- 次世代栽培システムを いたスマート育種技術開発の加速, https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/seika/ai_r3/ai3_2.pdf
- 健康志向がマッチ!注目を集める日本茶・緑茶の海外展開の現状 – プルーヴ株式会社, https://www.provej.jp/column/overseas-development-of-japanese-tea/
- DeepResearch追加指示.txt
- 【調査資料】 お茶の世界市場(2025-2030):紅茶、緑茶、その他 – (株)マーケットリサーチセンター, https://www.marketresearch.jp/reports/tea-market-mordor/
- お茶の世界市場規模、2032年に339億ドルへと増加予想【市場調査】 – NEWSCAST, https://newscast.jp/news/0295826
- 日本茶の輸出 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2204/pdf/aff2204-4.pdf
- 茶 を め ぐ る 情 勢 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-126.pdf
- 茶 を め ぐ る 情 勢 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/kanto/seisan/engei/tokusan/attach/pdf/index-6.pdf
- 令和7年度 アーカイブ – 一般社団法人 鹿児島県茶生産協会 – かごしま茶ナビ -, https://kagoshima-cha.or.jp/yearly/%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6/
- 茶業界の現状と課題 – 静岡県立大学 食品栄養科学部, https://dfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/labs/tsc/pdf/03/0403_chagyoukainogenjo.pdf
- 飲料への支出 – 総務省統計局, https://www.stat.go.jp/data/kakei/tsushin/pdf/18_8-1.pdf
- Global Market Report: Tea prices and sustainability, https://www.iisd.org/system/files/2024-01/2024-global-market-report-tea.pdf
- Global Market Report: Tea – International Institute for Sustainable Development, https://www.iisd.org/system/files/publications/ssi-global-market-report-tea.pdf
- Tea Market By Size, Share, Trends, Growth, and Forecast 2030 – TechSci Research, https://www.techsciresearch.com/report/tea-market/14741.html
- Tea Market Size, Competitors, Trends & Forecast to 2033 – Research and Markets, https://www.researchandmarkets.com/report/tea
- Ready To Drink Tea And Coffee Market Size Report, 2030, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ready-to-drink-tea-and-ready-to-drink-coffee-market
- RTD Tea Market Size & Share Analysis – Industry Research Report – Growth Trends, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-ready-to-drink-tea-market
- RTD Tea Market Size & Share, Growth Analysis Report 2025-2034, https://www.gminsights.com/industry-analysis/rtd-tea-market
- Global RTD Tea and Coffee Market Report | World Tea News, https://www.worldteanews.com/data-research/global-rtd-tea-and-coffee-market-report
- 令和7年一番茶情勢について – 静岡茶市場, https://chaichiba.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/eb99e8ae3fe11165e6572a559e7af646.pdf
- 家計調査 家計収支編 総世帯品目分類 001 品目分類(平成27年改定 …, https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003105162
- 家計調査 品目分類 010 品目分類(2025年改定)(総数:金額) | データベース | 統計データを探す, https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&layout=dataset&query=%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4&statdisp_id=0004023601
- 世界の茶の現状について – 京都府, https://www.pref.kyoto.jp/nosan/documents/shinko-keikaku-sanko-siryo.pdf
- 茶の種類と産地 – 茶ガイド-全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会, https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/dekiru03.htm
- e-Stat(政府統計の総合窓口)の使い方 入門編 – 東京大学附属図書館, https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/sites/default/files/database/manual/text/estatnyumon.pdf
- 1 ガイド「家計調査データベースを使う」 データベースは,政府統計の総合窓口(e-Stat)ホー, https://www.stat.go.jp/data/kakei/pdf/db.pdf
- ガイド「家計調査統計表を探す」, https://www.stat.go.jp/data/kakei/pdf/gaido.pdf
- 世界各国の貿易統計を品目コード別調査するには? – 関税削減.com【HSコード分類事例の解説】, https://www.customslegaloffice.com/fta/worldtradingstatistics/
- 何をどうすれば?HSコードの調べ方を徹底解説!, https://service.shippio.io/glossary/howto-searchscord/
- 静岡茶市場 “史上最速”の初取引 茶シーズンの消費喚起に – 食品新聞, https://shokuhin.net/96823/2024/04/19/inryou/inryou-inryou/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%8C%B6/
- ボトル入りお茶飲料の未来:2025年までに予想される年平均成長率7.5%の最新トレンドと – Pando, https://pando.life/article/2247660
- 消費者調査データ 無糖茶(2025年9月版) 王者「お~いお茶」に迫る「綾鷹」、「生茶」、「伊右衛門」 – J-marketing.net produced by JMR生活総合研究所, https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/02-drink/mranking431.html
- お茶 流行の最新トレンドと戦略を解説 – Accio, https://www.accio.com/business/ja/%E3%81%8A%E8%8C%B6%E6%B5%81%E8%A1%8C
- 世界で広がる日本茶ブーム――新たな消費風景, https://peoplemonthly.jp/n17145.html
- 日本の緑茶市場規模は2033年に12万6200トンに達し、2025年から4.1%の成長が見込まれる, https://newscast.jp/news/8238396
- 緑茶の美味しさと機能性を両立する「水出し緑茶」 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/new_tech_cultivar/2021/2021seika-19.html
- 花王健康科学研究会 | 「緑茶飲用と健康:疫学研究からのエビデンスの現状」, https://www.kao.com/jp/healthscience/report/report070/report070_01/
- 緑茶[ハーブ – 医療者] – 厚生労働省eJIM, https://www.ejim.mhlw.go.jp/pro/overseas/c04/28.html
- – 1 – (別紙) 食品表示基準Q&A(新旧対照表) 改正後(新) 改正前(旧) 食品表示基準Q – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190301_0014.pdf
- キーワードは「コスパ・タイパ」と「丁寧な暮らし」~新生活トレンド2024 | JP – Criteo.com, https://www.criteo.com/jp/blog/new-lifestyle-trends-2024/
- 果樹茶の分析結果 | スマート農業実証プロジェクト – 農研機構, https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/seika_portal/keieibunnseki_kajyucha.html
- 茶の機能性に関する 研究成果集 – 静岡県, https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/276/kennkyuuseika.pdf
- ファミマルの「ペットボトルお茶 600ml」は、環境に“二重マル”! お茶と紅茶7商品で100%リサイクルペットボトルに切り替え完了。 年間販売数量 1億6000万本のボトルがプラ削減の環境配慮に。|ファミリーマート, https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2024/s20240724.html
- 日本コーヒーマシン市場規模、株式、成長、予測, https://www.sphericalinsights.com/jp/reports/japan-coffee-machine-market
- 紅茶・緑茶業界の世界市場シェアの分析 | deallab, https://deallab.info/tea/
- D2Cブランドの成功事例20選をD2Cマーケターが解説 – 株式会社Venture Ocean, https://venture-ocean.com/blog/d2c-successful-case/
- 【カンタン解説】D2Cとは?従来モデルと比べたメリットや成功ポイントをわかりやすく説明 – 事業内容, https://service.aainc.co.jp/product/letro/article/what-is-d2c
- この報告書は、農林水産省補助事業「平成25年度産地活性化総合対策事 – 公益社団法人日本茶業中央会, https://www.nihon-cha.or.jp/pdf/h25-enquete.pdf
- 変化する茶業と茶消費の 創造・確保のために – 静岡県立大学 食品栄養科学部, https://dfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/labs/tsc/pdf/2611_henka.pdf
- 若者の緑茶に対する意識と消費行動について – 金沢星稜大学, https://www.seiryo-u.ac.jp/u/research/gakkai/ronbunlib/e_ronsyu_pdf/No139/01_kishimoto139.pdf
- 日本茶・緑茶の海外進出!現行と成功のための販売戦略 – グローハイ, https://glohai.com/blog/6841
- 特集「日本茶を世界に届ける」 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2402/spe1_04.html
- 抹茶ブームは世界でどう広がる?日本・韓国・アメリカ市場を検索データで比較 – ListeningMind, https://jp.listeningmind.com/tutorial/matcha-search-trend/
- Ⅱ 農 業 構 造 農業就業人口・農家戸数 – 岐阜県, https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/9874.pdf
- 都道府県別農業就業人口 – とどラン, https://todo-ran.com/t/kiji/11541
- 人口構造の変化等が農業政策に与える影響と課題について – 総務省, https://www.soumu.go.jp/main_content/000578741.pdf
- 新規就農者の就農実態に関する調査結果 – 農業をはじめる.JP, https://www.be-farmer.jp/uploads/statistics/r6_zittai.pdf
- 日 本 茶 を 愉 し む – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2204/pdf/aff2204_all.pdf
- 市場の変化を読み、抹茶を米国へ/池田製茶(鹿児島県) | 中小企業の海外ビジネス – ジェトロ, https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/1002/61df5ba00c0664d7.html
- 茶師ってどんな仕事?必要スキルやこだわりについて解説!, https://www.ryuhoen.co.jp/apps/note/work_of_tea_master/
- 農業生産性の国際比較分析, https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/nosoken/attach/pdf/198907_nsk43_3_01.pdf
- 労働生産性の国際比較 | 調査研究・提言活動, https://www.jpc-net.jp/research/list/comparison.html
- 労働生産性の国際比較, https://www.jpc-net.jp/research/list/pdf/comparison_2018_trends.pdf
- スマート農業推進フォーラム2020(IoT技術・ロボット化技術を活用した大規模スマート茶業一貫体系) – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=xHmVlPTjC7Q
- おいしさを視覚化 官能評価センサーを活用 – 東京農業大学, https://www.nodai.ac.jp/research/teacher-column/22913/
- 食品業界DX事例:製造現場から物流までのデジタル変革 – 国際ソフトウェア株式会社, https://www.ksw.co.jp/media/column/a62
- 生成AI導入の成功事例:企業が得た具体的なメリットとは? – 株式会社GeNEE, https://genee.jp/contents/benefits-of-generative-ai/
- 飲食業界でのAIの活用方法とは? | Webアプリ・機械学習・生成AIメディア, https://exatech.dev/media/food_ai/
- 6つのD2C国内事例。ブランド成長のキーワードは「モノづくり×パーソナライズ」? – ecforce, https://ec-force.com/blog/d2c_no42
- 【事例紹介】D2Cとサブスクの違いから成功ブランドの3つの共通点を紹介 – ハンソクエスト, https://hansokuest.jp/article/detail/85