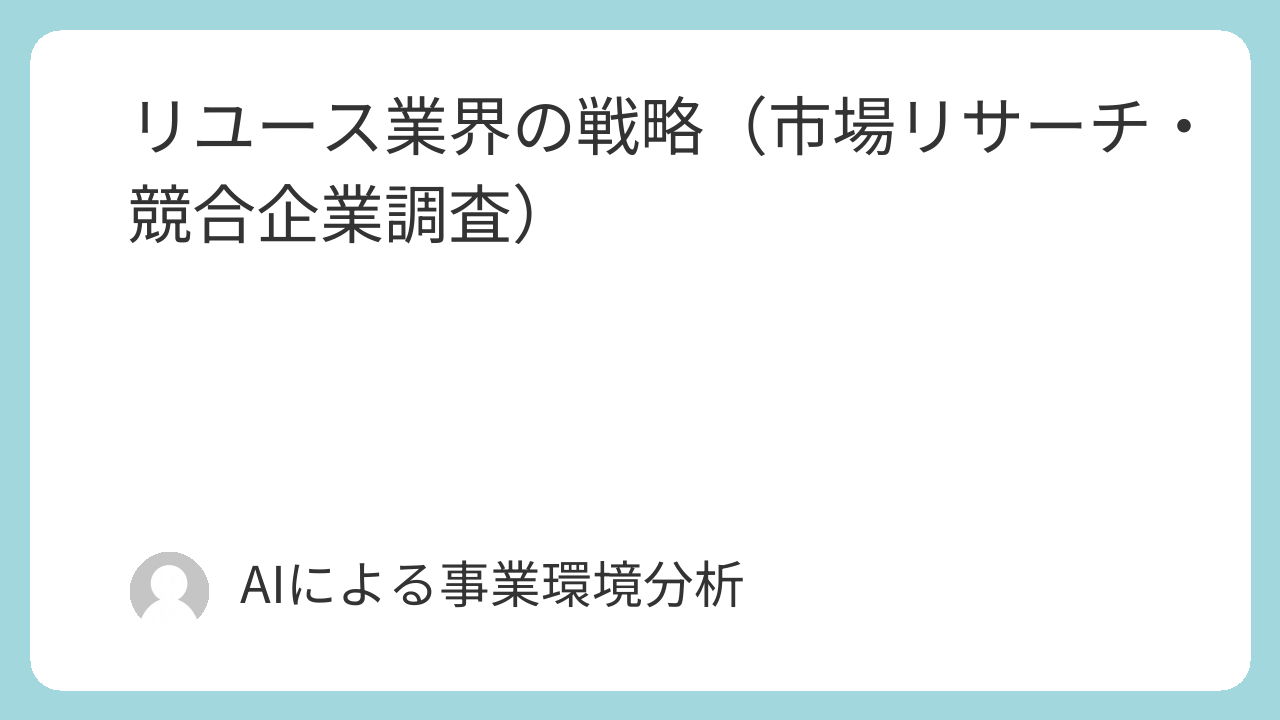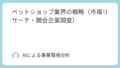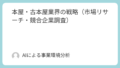「信頼」と「効率」の再定義:C2C時代を勝ち抜くリユース・リサイクル業界の次世代戦略
第1章:エグゼゼクティブサマリー
本レポートは、リユース・リサイクル業界が直面する構造変化、すなわちC2C(消費者間取引)プラットフォームの台頭とAI技術の進化という二つのメガトレンドを深く分析し、企業が持続的な競争優位を確立するための次世代事業戦略を提言するものである。調査範囲は、総合リユース、専門リユース(ブランド品、アパレル、ホビー等)、オンラインおよびオフラインチャネル、そして関連するC2Cプラットフォーム市場を網羅する。
当業界は現在、サステナビリティ意識の高まりと物価高騰を背景とした節約志向という二重の追い風を受け、市場規模は拡大を続けている。しかしその裏側では、C2Cプラットフォームへの個人在庫の流出により、事業の生命線である「仕入れ(買取)」における競争が熾烈を極めている。さらに、AIによる査定・真贋鑑定技術の進化は、従来価値の源泉であった属人的な「目利き」の優位性を根本から揺るがしている。
本分析を通じて導き出された結論は、今後の業界の勝敗を分ける決定要因が、もはや従来の「目利き」や「店舗網の規模」といった要素ではなく、以下の3点に集約されるということである。
- 優良在庫の安定確保能力: 多様なチャネルを駆使し、いかに効率的かつ継続的に良質な中古在庫を確保できるか。
- AI活用による圧倒的なオペレーション効率: 買取から販売までの全工程においてAIを実装し、属人性を排した上で抜本的なコスト削減と収益性向上を実現できるか。
- 「信頼性」のブランド化: C2Cプラットフォームが提供困難な「本物である保証」や「品質への安心感」を可視化し、高付加価値サービスとして確立できるか。
これらの結論に基づき、本レポートでは以下の主要な戦略的推奨事項を提言する。
- 仕入れチャネルのDXと多様化: 従来型の店舗買取への依存から脱却し、オンライン完結型(宅配・出張)のUI/UXを徹底的に改善する。同時に、一次流通企業との連携(リコマース)を強化し、安定的かつ質の高い仕入れ網を構築する。
- AIの全社的実装によるオペレーション革命: 査定・真贋鑑定から在庫最適配置、EC出品自動化まで、バリューチェーンの全工程にAIを導入する。これにより、属人性を排除し、コスト競争力と収益性を抜本的に改善する。
- 「信頼」のサービス化と高付加価値戦略へのシフト: C2Cが不得手とする高価格帯・専門商材に特化する。AIと専門家による真贋鑑定、品質保証、充実したアフターサービスを組み合わせた「信頼」をサービスとして提供し、価格競争から脱却する。
- OMO(Online Merges with Offline)戦略による顧客体験の再定義: 店舗を単なる販売・買取の場ではなく、EC商品の試着・受取拠点、そして信頼を醸成するための体験スペースとして再定義し、オンラインとオフラインをシームレスに連携させることで、顧客エンゲージメントを最大化する。
第2章:市場概観(Market Overview)
市場規模の推移と将来予測
日本のリユース市場は、持続的な成長軌道を描いている。リユース経済新聞の調査によれば、市場規模(小売金額ベース)は2022年に約2.9兆円、2023年には前年比7.8%増の3.1兆円を超え、調査が開始された2009年以降14年連続での拡大を記録した 1。この力強い成長は今後も継続する見通しであり、2025年には3.25兆円、さらに2030年には4兆円規模に達すると予測されている 3。
この成長の背景には、環境配慮を重視するサステナビリティ意識の浸透と、近年の物価高騰を起因とする消費者の節約志向という、二つの強力な社会的・経済的追い風が存在する 1。
| 年 | 市場規模(億円) | 前年比成長率 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,169 | +2.5% | リユース経済新聞 3 |
| 2021 | 26,988 | +11.7% | リユース経済新聞 3 |
| 2022 | 28,976 | +7.4% | リユース経済新聞 2 |
| 2023 | 31,227 | +7.8% | リユース経済新聞 1 |
| 2024 (推計) | 32,628 | +4.5% | リユース経済新聞 11 |
| 2025 (予測) | 32,500 | – | リユース経済新聞 3 |
| 2030 (予測) | 40,000 | – | リユース経済新聞 3 |
市場セグメンテーション分析
商材別
市場を商材別に見ると、ファッション関連が大きな割合を占めている。2023年時点で、「衣料・服飾品」が5,913億円、「ブランド・宝飾品」が3,656億円であり、合計すると約9,600億円規模に達する 1。次いで、トレーディングカードを含む「玩具・模型」が2,779億円、「家具・家電」が2,775億円と、それぞれ巨大な市場を形成している 11。
特に注目すべきは「携帯・スマホ」市場の急成長である。端末価格の高騰を背景に、2023年には865億円、2024年には1,059億円と1,000億円市場を突破し、前年比22.4%増という高い成長率を示している 1。一方で、伝統的なリユース商材である「書籍」は948億円規模を維持しているものの、市場全体の中では微減傾向にある 14。
チャネル別・ビジネスモデル別
2023年の市場3.1兆円の内訳を見ると、C2C(フリマアプリ等)が約1.3兆円(構成比約42%)と最大のチャネルとなっている。これにB2Cの店頭販売が約1兆円(同約32%)、B2Cのネット販売が約0.6兆円(同約19%)と続く 10。2022年のデータでも、C2Cが43%、B2C店頭が37%、B2Cネットが18%という構成比が示されている 2。
ここで見られる重要な変化は、チャネル間の成長率の逆転である。2015年以降、リユース市場の拡大を牽引してきたのはメルカリに代表されるC2Cプラットフォームであった 1。C2Cは中古品売買への心理的ハードルを下げ、市場参加者を爆発的に増加させる「市場教育」の役割を果たした。しかし、その成長率には鈍化の兆しが見える。2023年のC2C市場の成長率が前年比6.4%増であったのに対し、B2C市場は店舗販売が同7.5%増、ネット販売が同12.0%増と、いずれもC2Cを上回る成長を遂げた 1。
この現象は、市場の成熟を示唆している。C2Cを通じてリユースに慣れ親しんだ消費者の一部が、出品・梱包・発送・個人間交渉といったC2C特有の「手間」や「リスク」を回避するため、より利便性や信頼性の高いB2Cチャネルへと移行し始めていると考えられる。これはB2C事業者にとって、C2Cが育てた広大な顧客基盤を取り込む絶好の戦略的機会と言える。
市場成長ドライバーと阻害要因
ドライバー
- 経済合理性: 長引く物価高騰は、消費者の節約志向を強め、割安な中古品への需要を高めている。同時に、不要品を売却して収入を得たいという換金ニーズも刺激しており、需要と供給の両面から市場を押し上げている 1。実際に、物価高騰の影響で50%の消費者がリユース品の購入を、36%が不用品の売却を増やしたという調査結果もある 8。
- サステナビリティ意識: 特にZ世代を中心に、環境負荷の少ない消費を志向する「エシカル消費」が広まっている。製品を長く使い、再利用することは、この価値観に合致する行動として社会的に肯定されており、リユース市場の成長を後押ししている 17。
- リテラシー向上: フリマアプリの普及は、中古品の売買を日常的な行為へと変え、消費者の心理的抵抗感を大幅に低下させた。これにより、これまでリユース市場に参加してこなかった層が新たに取り込まれ、市場全体のパイが拡大した 16。
阻害要因
- 仕入れ競争激化: C2Cプラットフォームが個人が保有する膨大な「かくれ資産」の主要な出口となり、B2C事業者の仕入れ環境は厳しさを増している。優良な在庫をいかに安定的に確保するかは、業界全体の最重要課題である。
- 人口減少: 長期的な視点では、国内の総人口減少は市場全体の縮小圧力となる。
- 偽造品リスク: 特にブランド品などの高額商材において、精巧な偽造品の流通は消費者の信頼を損なうだけでなく、事業者側の真贋鑑定コストを増大させる要因となっている 22。
業界の主要KPIベンチマーク分析
業界の収益構造とオペレーション効率を把握するため、主要企業のKPIを分析する。
- 粗利率: 粗利率は取り扱い商材によって大きく異なる。一般的に、専門的な鑑定知識を要するブランド品などを扱う専門リユースは20%~30%と高く、幅広い商材を扱う総合リユースは10%~20%程度とされる 23。例えば、コメ兵ホールディングス(専門リユース)の2025年3月期連結粗利率は22.2%である 24。一方、ゲオホールディングス(総合リユース中心)の同連結粗利率は39.9%と高いが、これはリユース以外の事業(新品販売やレンタル)も含まれるため、商材構成が大きく影響している 26。
- 在庫回転日数: 在庫回転日数は、ビジネスモデルと商材単価に左右される。高単価な専門商材は長期化する傾向があり、コメ兵HDのブランド・ファッション事業では78.5日(2025年3月期)となっている 25。対照的に、オンラインに特化し、迅速な販売を強みとするマーケットエンタープライズは、業界最高水準とされる年間17.6回転(約21日)を実現している 28。
- オンライン販売比率: EC化は業界全体の潮流である。リユース事業者全体のネット売上比率は、2011年の10.5%から2022年には33.6%へと大幅に上昇した 2。個別企業では、ゲオHDのセカンドストリート国内事業におけるEC売上比率が約17.7%(2025年3月期)となっており、店舗網とECの連携を進めている 26。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
リユース業界を取り巻くマクロ環境を、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)、法規制(Legal)、環境(Environment)の6つの側面から分析する。
政治(Politics)
- 古物営業法: 買取時の本人確認義務は、リユース事業の根幹をなす規制である 29。近年、オンラインで本人確認を完結できるeKYC(electronic Know Your Customer)技術が普及したことで、宅配買取や出張買取といった非対面取引の利便性が向上し、この規制への対応が容易になった 30。
- 各種リサイクル法: 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)などは、対象品目を扱う事業者に対し、廃棄物としての適正な処理フローの構築を義務付けている。これはコスト要因であると同時に、社会的な責任を果たす企業としての信頼性にも繋がる 32。
- インボイス制度: 2023年10月に開始されたインボイス制度は、個人からの買取(C2B)においては「古物商特例」が設けられており、事業者は適格請求書(インボイス)がなくとも仕入税額控除が可能である 34。このため、個人からの仕入れが中心である多くのB2Cリユース事業者への直接的な財務インパクトは限定的である。
経済(Economy)
- 物価高騰・可処分所得の変動: 物価上昇は、消費者の生活防衛意識を高め、「より安く購入したい」という中古品購入ニーズと、「不要品を売って生活費の足しにしたい」という換金ニーズを同時に喚起する 8。これは市場にとって強力な追い風となるが、一方で売り手の価格期待値も上昇するため、買取価格へのプレッシャーが高まり、仕入れ競争をさらに激化させる側面も持つ。
- 不況耐性: 景気後退局面において、消費者は支出を抑える傾向が強まるため、新品よりも安価なリユース品の需要が高まる。このため、リユース業界は一般的に「不況に強い」ビジネスモデルとされている 18。
社会(Society)
- サステナビリティ意識の高まり: Z世代を中心に、大量生産・大量消費社会からの脱却を目指し、環境に配慮した消費行動(エシカル消費)を重視する価値観が浸透している 19。リユース品の利用は、資源の有効活用や廃棄物削減に直結するため、この価値観に合致するポジティブな行動として捉えられている 18。
- 「タイパ(タイムパフォーマンス)」重視の消費行動: 現代の消費者は、時間を効率的に使うことを重視する傾向が強い。フリマアプリでの出品作業(写真撮影、商品説明文作成、価格設定、購入者との交渉、梱包、発送)は、多くの時間と手間を要する。この一連のプロセスを「面倒」と感じる層にとって、専門業者に一括で売却できるB2Cの買取サービスが提供する「手軽さ」と「即時性」は、非常に魅力的な価値となる 37。
- シェアリングエコノミーの進展: 「所有から利用へ」という価値観のシフトを背景に、カーシェアリングやファッションレンタルなどのサブスクリプションサービスが拡大している。これは、自動車や高級ブランドバッグといった一部の耐久消費財カテゴリにおいて、そもそも中古品として市場に流通する「モノ」の総量を減少させる可能性があり、長期的な脅威となり得る。
技術(Technology)
- AI(人工知能): 査定・真贋鑑定、価格最適化、需要予測、EC出品の自動化など、リユース事業のバリューチェーン全体を根底から変革する、最もインパクトの大きい技術トレンドである(詳細は第8章で詳述)。
- C2Cプラットフォームの進化: メルカリなどのC2Cプラットフォームは、出品プロセスの簡略化や匿名配送サービスの導入など、UI/UXの改善を継続的に行っており、依然として高い利便性で多くのユーザーを惹きつけている 5。
- オンライン買取技術(eKYC): eKYCの普及は、オンラインでの本人確認プロセスを劇的に簡素化・高速化した 30。これにより、宅配買取や出張買取のハードルが下がり、店舗を持たない事業者でも全国を対象とした仕入れ活動が可能になった。
- トレーサビリティ技術: RFIDタグやブロックチェーンといった技術は、個々の商品の真贋情報や所有履歴を改ざん困難な形で記録・追跡することを可能にする。将来的には、特に高額なブランド品や美術品において、消費者がその商品の「正当性」を技術的に確認できる仕組みが普及し、「信頼」を担保する重要なインフラとなる可能性がある 41。
法規制(Legal)
- 模倣品(偽ブランド品)の流通規制: 税関での取り締まり強化など、模倣品の流通に対する規制は年々厳しくなっている 44。これは、事業者が負うべき真贋鑑定の責任を重くし、鑑定コストの増加に繋がる。一方で、高度な鑑定能力と体制を持つB2C事業者にとっては、個人間取引が中心で偽造品リスクが常に付きまとうC2Cプラットフォームとの明確な差別化要因となる。
- 個人情報保護法: 買取時に古物営業法に基づき取得する顧客の氏名、住所、生年月日といった個人情報は、個人情報保護法に則って厳格に管理する必要がある。
環境(Environment)
- サーキュラーエコノミー(循環型経済)推進政策: 政府や地方自治体が、廃棄物削減と資源の有効活用の観点からリユースを推進する政策を打ち出している 17。これは業界全体にとって強力な追い風となる。この大きな潮流は、新品を製造・販売するメーカー自身が、自社製品の下取りや認定中古品(CPO)販売といったリユース事業に参入する「リコマース」の動きを加速させている 46。これはリユース専業事業者にとって、仕入れにおける新たな競合の出現であると同時に、メーカーと提携し、その再販網を担うという新たな協業の機会も生み出している。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
リユース業界の収益構造と競争の力学を、マイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いて解明する。
供給者の交渉力(中古品を売る個人):極めて強い
- 分析: リユース業界における「供給者」とは、不要品を売却する個人である。彼らは、メルカリやヤフオクといったC2Cプラットフォームという、手数料が比較的安価で、場合によっては店舗買取よりも高値で売却できる強力な代替販売チャネルを保有している 16。これにより、B2C買取事業者に対する供給者の価格交渉力は極めて高い水準にある。供給者は常に、「より高い売却価格(C2Cの魅力)」と、「手間なく、早く、安心して売りたい(B2Cの魅力)」という価値を天秤にかけて売却先を決定している。
- So What?(戦略的意味合い): B2C事業者が仕入れ競争を勝ち抜くためには、単なる買取価格の競争ではC2Cプラットフォームに勝つことは困難である。したがって、C2Cが提供できない、あるいは苦手とする価値、すなわち「圧倒的な利便性(時間的コストの削減)」、「専門性に基づく査定への信頼」、そして「個人間取引のリスクからの解放」を明確に打ち出し、サービス価値で差別化することが不可欠となる。
買い手の交渉力(中古品を買う個人・業者):強い
- 分析: 「買い手」である中古品購入者は、他のリユース店の店舗やECサイト、C2Cプラットフォーム、さらには新品の低価格品(ファストファッションなど)まで、無数と言えるほどの購入選択肢を持っている。インターネットの普及により価格比較が容易になったことも、買い手の交渉力を強めている。
- ただし、 この力関係を一部相殺する要因が存在する。それは、特に高価格帯の商材において顕著な、偽造品リスクや商品の品質に対する懸念である。多くの消費者は「騙されたくない」「状態の悪いものを買いたくない」と考えており、「信頼できる事業者から安心して購入したい」という強いニーズを持つ 47。この「安心感」への対価が、B2C事業者の価格決定力(プライシングパワー)をある程度下支えしている。
- So What?: 激しい価格競争を回避し、収益性を確保するためには、「品質保証」「真贋鑑定証明」「購入後のアフターサービス」といった「信頼」を具体的な付加価値として商品に組み込み、価格以外の要素で顧客に選ばれる理由を構築することが極めて重要である。
新規参入の脅威:中~高
- 分析: 新規参入の脅威は、ビジネスモデルによって大きく異なる。
- オンライン特化・専門特化型(脅威:高): トレーディングカード、スニーカー、ヴィンテージ古着といった特定のカテゴリや、宅配買取サービスに特化する場合、大規模な店舗網や多額の初期投資を必要とせず、比較的容易に市場参入が可能である 48。Webマーケティングのノウハウがあれば、ニッチ市場で急速に存在感を高めることができる。
- 総合リユース型(脅威:低): 一方、セカンドストリートやブックオフのように、全国規模の店舗網を持ち、多種多様な商材を扱う総合リユース事業は、参入障壁が高い。店舗開発・運営、幅広い商材の査定ノウハウの蓄積、膨大なSKUを管理する在庫管理システムの構築には、莫大な資本と長年の運営ノウハウが不可欠であり、既存大手が持つ「規模の経済性」が強力な参入障壁として機能している。
- So What?: 大手総合リユース事業者は、自社の牙城が安泰であると考えるべきではない。オンラインを主戦場とする専門特化型の新規参入者が、収益性の高いニッチ市場を次々と侵食していく「デス・バイ・ア・サウザンド・カッツ(千の切り傷による死)」のリスクに常に注意を払う必要がある。M&Aによる有望な新規参入者の取り込みや、自社内での迅速なニッチサービス立ち上げが有効な対抗策となり得る。
代替品の脅威:非常に強い
- 分析: リユース業界は多様な代替品の脅威に晒されている。
- C2Cプラットフォーム: 最大かつ最も直接的な代替品(代替チャネル)である。リユース市場の4割以上を占め、B2C事業者とは仕入れ(買取)と販売の両面で顧客を奪い合う最大の競合関係にある 10。
- シェアリング/サブスクリプションサービス: 「所有」という概念そのものを代替するサービス。特に自動車、高級ブランドバッグ、家電などのカテゴリにおいて、リユース市場の潜在的な需要と供給を長期的に侵食する脅威となる。
- 新品の低価格品: ファストファッション、低価格なジェネリック家電など、新品であっても安価に購入できる商品は、中古品購入の主要動機である「経済合理性」を相殺する強力な代替品である。
- So What?: B2C事業者は、これらの代替品が提供できない独自の価値を明確に訴求する必要がある。C2Cに対しては「信頼と利便性」、シェアリングサービスに対しては「所有する喜びや資産価値」、新品の低価格品に対しては「一点物としての希少性(ヴィンテージ品など)や、かつての高級品が持つ高品質」が、それぞれ有効な差別化の軸となる。
業界内の競争:非常に激しい
- 分析: 業界内の競争は極めて激しい。特に、競争の主戦場は「いかに高く売るか(販売)」から「いかに優良な在庫を確保するか(仕入れ)」へと完全にシフトしている。
- 総合リユース vs 専門リユース: セカンドストリート(ゲオ)やハードオフのような総合リユースは、幅広い商材と顧客層をカバーし、規模の経済を追求する。対照的に、コメ兵のような専門リユースは、特定分野での深い専門知識と信頼性を武器に、高い利益率を追求する。
- オンライン専業 vs 店舗網: BuySell Technologiesのようなオンライン専業事業者は、店舗コストをかけずにWebマーケティングを駆使して全国から効率的に商品を仕入れる。一方、店舗網を持つ事業者は、地域社会に根差した仕入れ力と、顧客との対面による信頼関係の構築に強みを持つ。
- So What?: 競争が最も熾烈な領域は、C2Cとの競合が激しく、かつ利益率も確保しやすい「中~高価格帯のファッション・ブランド品」の仕入れである。この領域を制するための、他社にはないユニークで効率的な仕入れ戦略を構築できるかどうかが、企業の収益性を大きく左右する。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン(=買取チャネル)分析
リユース業界において、サプライチェーンはすなわち「買取チャネル」であり、その競争力の源泉は「いかに安く、安定的に、良質な商品を仕入れるか」という調達能力に集約される。この仕入れ網こそが、企業の持続的な成長を支える最も重要な経営資源である。
買取チャネル分析
主要な買取チャネルは「店頭」「出張」「宅配」の3つに大別され、それぞれに異なるコスト構造、メリット・デメリット、そして主要なターゲット層が存在する。
- 店頭買取
- メリット: 顧客にとっての最大のメリットは「即時換金性」である。査定後すぐに現金を受け取れるため、急な資金ニーズに応えることができる 22。また、査定士と対面でコミュニケーションを取ることで、査定内容への納得感や企業への信頼感が醸成されやすい。事業者側にとっては、来店客による「ついで買い」を誘発できるメリットもある。
- デメリット: 店舗の賃料や人件費といった固定費がかさむ。また、商圏が店舗周辺に限定されるため、広域からの集客が難しい。
- ターゲット層: 「すぐに現金が欲しい」と考える層、店舗の近隣住民、売りたい商品が少量である顧客。
- オペレーション: 顧客が持ち込んだ商品を査定ブースで専門スタッフが鑑定し、買取価格を提示。合意に至ればその場で本人確認書類を基に古物台帳を作成し、現金を支払う 50。
- 出張買取
- メリット: 家具、大型家電、あるいは大量の書籍や衣類など、店舗への持ち込みが困難な商品を扱える点が最大の強みである。顧客は在宅のまま不要品をまとめて売却できるため、利便性が非常に高い 51。特に高齢者層や、引越し・生前整理・遺品整理といったライフイベントに伴うニーズの受け皿となる。
- デメリット: 査定士の移動時間や車両コスト、人件費など、1件あたりのオペレーションコストが他のチャネルに比べて高くなる傾向がある。
- ターゲット層: 高齢者層、富裕層、引越しや遺品整理を控えた層、大型家具・家電の売却希望者。BuySell Technologiesはこの領域でシニア層を主要ターゲットとし、強みを築いている 5。
- 宅配買取
- メリット: 店舗網に依存せず、全国どこからでも商品を仕入れることが可能。店舗運営コストがかからないため、オンライン専業での事業展開もできる。顧客は時間や場所を選ばずに発送できるため、多忙な層にもリーチしやすい。
- デメリット: 商品の発送から査定、入金までに数日を要するリードタイムが発生する。輸送コスト(送料無料の場合、事業者負担)がかかる。また、顧客自身が商品を梱包する手間が発生する点が、利用のハードルとなる場合がある。
- ターゲット層: 近隣に適切な買取店がない層、日中多忙で店舗訪問が難しい層、カメラやオーディオ、楽器といった専門性の高い商品を、その分野に強い遠方の専門業者に査定してもらいたいと考える層 52。
C2Cプラットフォームに日々出品される膨大な「個人在庫」は、B2C事業者にとって潜在的な仕入れの宝庫である。これらの在庫をB2Cチャネルに取り込むには、各買取チャネルの特性を理解し、ターゲット顧客のニーズに応じて最適なサービスを提供することが鍵となる。特に、C2Cのプロセスを「面倒」と感じる層に対し、オンライン申込のUI/UXを極限まで簡素化し、ストレスフリーな買取体験を提供することが、オンライン買取(宅配・出張)の競争力を高める上で不可欠である。
バリューチェーン分析
リユース事業の価値創造プロセスをバリューチェーンのフレームワークで分析する 53。
リユース事業の価値連鎖
- 主活動:
- 仕入れ(買取): 上述の各チャネルを通じて、個人や業者から中古品を調達する。
- 査定・値付け: 商品の真贋、状態、市場相場を基に買取価格と販売価格を決定する。
- 商品化: クリーニング、簡易な修理、(PC等の)データ消去などを行い、再販可能な状態にする。
- 在庫管理・最適配置: 商品をデータ登録し、店舗やEC倉庫で管理。需要予測に基づき、最適な販売チャネル(店舗、自社EC、ECモール)へ商品を配置する。
- 販売: 店舗での接客販売、あるいはECサイトへの商品情報掲載(撮影、採寸、原稿作成)と販売。
- アフターサービス: 返品対応、品質保証、問い合わせ対応など。
- 支援活動:
- 人事管理: 査定士やEC運営スタッフの採用・育成。
- 技術開発: AI査定システム、在庫管理システム、ECプラットフォームの開発・保守。
- 調達活動: 店舗開発、備品調達、物流網の構築。
価値の源泉の変化
かつてリユース事業の価値の源泉は、個々の査定士が持つ経験と勘、すなわち「目利き能力(安く買う)」に大きく依存していた。しかし、この属人的な能力は、AIとデータベースの進化により、その重要性が相対的に低下しつつある。現代における価値の源泉は、以下の3つの能力へとシフトしている。
- データ活用能力(適正に値付けする): 膨大な過去の取引データ、C2C市場の相場、リアルタイムの需給動向を分析し、利益を最大化する買取・販売価格をシステムが導き出す能力。
- オペレーション能力(効率化する): 買取受付から査定、商品化、EC出品までの一連のプロセスを、テクノロジーを駆使していかに低コストかつ迅速に実行するかという能力 55。
- マーケティング能力(高く売る): データ分析に基づき、個々の商品を最も高く売れるチャネルとタイミングを判断し、販売を最適化する能力。
店舗の役割の変化:OMO(Online Merges with Offline)
デジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、実店舗の役割は単なる「販売・買取の場所」から、オンラインとオフラインを融合させた顧客体験を提供する「多機能ハブ」へと進化している 57。
- 仕入れ拠点: 地域社会に根差し、安定した商品供給を支える最重要機能。
- ECとの連携拠点: ECサイトで購入した商品の受け取りや試着を行う「クリック&コレクト」の拠点、あるいは店舗の在庫をECで販売する際の発送拠点としての役割。
- 信頼醸成・ブランド体験の場: 顧客が商品を直接手に取って品質を確かめたり、専門スタッフから商品説明を受けたりすることで、企業やブランドへの信頼感を醸成するショールームとしての機能。C2Cでは得られない「安心感」を提供する上で不可欠な接点となる 58。
第6章:顧客需要の特性分析
買取顧客(売り手)のセグメントとKBF分析
問い:なぜ顧客は、より高く売れる可能性があるC2C(フリマアプリ)ではなく、B2C(リユース店)に売るのか?
この問いに答える鍵は、売り手が売却先を決定する際の主要因(KBF: Key Buying Factor、この文脈ではKey Facto for Selling)を理解することにある。B2Cが提供する独自の価値は、C2Cの利便性を上回る明確なメリットとして顧客に認識されている。
KBF(売却先決定要因)分析
- 利便性(タイパ): 現代の消費者が重視する「タイムパフォーマンス」の観点から、B2Cの買取サービスは大きな魅力を持つ。フリマアプリにおける一連の作業、すなわち「商品の写真撮影」「詳細な説明文の作成」「購入希望者との価格交渉や質問対応」「梱包材の準備と発送手続き」といったプロセスは、多くの売り手にとって「面倒」で時間のかかる作業と認識されている 37。特に、引越しや大掃除などで多数の不要品を一度に処分したい場合、これらを一点ずつ出品する手間は計り知れない。B2Cの「まとめて」「すぐに」処分できる手軽さは、この「面倒さ」から解放されたいという強いニーズに応えるものである。消費者庁の調査でも、店舗買取で複数の業者を比較しない理由として「面倒だったから」が35.5%を占めている 59。
- 即時換金性: 「すぐに現金が必要」というニーズに対し、店舗買取はその場で現金化できるという他のどの手段にもない即時性を提供する 22。ゲオホールディングスが実施した調査では、買取サービスを利用する理由のトップに「現金化できる」(77.2%)が挙げられており、これが極めて重要な動機であることがわかる 60。
- 信頼性・安心感: C2C取引には、個人間取引特有のリスクが伴う。「商品状態に関するクレーム」「理不尽な返品要求」「輸送中のトラブル」といった購入者との直接的なやり取りは、精神的な負担となり得る。ある調査では、フリマアプリ利用者の72.2%が個人間取引に何らかの不安を感じていると回答している 38。特に、ブランド品や宝飾品、専門機材といった高額・専門商材の場合、「専門家による正当な価値評価を受けたい」「偽物と疑われるリスクを避けたい」という思いから、信頼できる事業者への売却を選択する傾向が強い。
顧客セグメント別KBF
これらのKBFは、売り手の状況や売却する商材によって重視される度合いが異なる。
- 高価格帯・専門品を売る層: 高級時計、ブランドバッグ、美術品などを売却する層。彼らが最も重視するのは「信頼性・安心感」である。自らの大切な資産の価値を正確に評価してくれる専門家の査定を求め、個人間取引のリスクを極めて嫌う。
- 低~中価格帯・大量品を売る層: 引越しや大掃除、衣替えなどで出た衣類、書籍、雑貨などをまとめて処分したい層。彼らにとって最も重要なのは「利便性(タイパ)」である。一点あたりの売却額の最大化よりも、手間をかけずに一括で片付けられることを優先する。
- 緊急現金化ニーズ層: 急な出費などで即座に現金を必要とする層。彼らは「即時換金性」を最優先し、査定額の多少の差よりも、その場で現金化できる店舗買取を選択する可能性が高い。
販売顧客(買い手)のセグメントとKBF分析
問い:なぜ顧客は、新品ではなくリユース品を買うのか?
買い手の動機もまた多様であり、リユース品ならではの価値に基づいている。
KBF(購入決定要因)分析
- 価格(経済合理性): リユース品を購入する最大の動機は、言うまでもなく「安さ」である。ある調査では、中古品を購入する理由として「安く買えるから」と回答した人が約8割に上る 61。ゲオの調査でも、ゲームソフトや家電、衣料品など多くのカテゴリで「価格が安い」ことが最重要視されている 60。
- 希少性: 新品市場ではもはや手に入らない「廃盤品」「限定品」「ヴィンテージ品」といった、一点物との出会いを求めるニーズ。これは、単なる節約目的とは異なる、趣味や収集といった側面が強い動機である 62。
- 信頼性(安心感): C2Cプラットフォームとの比較において、B2C事業者が提供する「信頼性」は重要な購入決定要因となる。中古品購入時に消費者が懸念する点として「ネットだと状態がよくわからない」「本物かどうかが心配」「クリーニングされているか気になる」といった項目が上位に挙がる 47。B2C事業者が提供する「品質保証」「真贋鑑定」「メンテナンス済み」といった付加価値は、これらの不安を解消し、安心して購入できる環境を提供する。
- 環境配慮(サステナビリティ): 環境問題への関心が高い層にとって、リユース品の購入は廃棄物を削減し、資源を有効活用する「エシカルな消費行動」として認識されている 18。
顧客セグメント別チャネル選好
これらのKBFに基づき、買い手は好む購入チャネルを選択する。
- 価格重視層: とにかく安さを追求する層。C2Cプラットフォームとリユース店の両方を駆使し、価格比較を徹底する。商品の状態や真贋リスクに対してはある程度許容する傾向がある。
- 品質・信頼性重視層: 特にブランド品や家電など、品質や機能が重要な商品を購入する層。状態を直接確認できる「店舗」や、企業が品質を保証する「自社ECサイト」を好む。C2Cでの購入には慎重である。
- 希少性重視層: 特定のアイテムを探し求めるコレクターや愛好家。品揃えが豊富な大型店舗や、専門性の高いECサイトを探索的に利用し、情報収集を積極的に行う。
第7章:業界の内部環境分析
企業の内部に存在する経営資源(リソース)と組織能力(ケイパビリティ)が、いかにして持続的な競争優位の源泉となり得るかを分析する。
VRIO分析
VRIO分析は、企業の経営資源やケイパビリティが持つ競争上のポテンシャルを、価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability)、組織(Organization)の4つの観点から評価するフレームワークである 63。
| 経営資源/ケイパビリティ | V | R | I | O | 競争優位の段階 | 戦略的示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国規模の店舗網 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 持続的競争優位 | OMO戦略の中核拠点。仕入れ、EC連携、顧客との信頼醸成のハブとして、その価値を最大化すべき。 |
| 優秀な査定士チーム | 〇 | 〇 | × | 〇 | 一時的競争優位 | AI査定の普及により、一般的な商材における希少性と模倣困難性は急速に低下。AIでは判断困難な超高額品や特殊商材の専門家として再定義し、価値を維持する必要がある。 |
| 膨大な真贋・相場データベース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 持続的競争優位 | AIモデルの学習データとして極めて重要。データの質と量がAIの精度を決定し、後発企業が決して模倣できない強力な参入障壁となる。最も戦略的な資産である。 |
| 確立されたブランドと信頼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 持続的競争優位 | C2Cプラットフォームとの最大の差別化要因。長年の事業活動を通じて築かれた消費者からの信頼は、一朝一夕には模倣できない。 |
| 効率化されたオペレーション | 〇 | × | × | △ | 競争均衡 | 多くの企業が効率化に取り組んでおり、それ自体で長期的な差別化は困難。AI導入で一時的な優位は築けるが、競合も追随するため、継続的な改善が不可欠。 |
この分析から浮かび上がるのは、将来の競争環境において最も重要かつ模倣困難な経営資源が、物理的な店舗網や人的な専門性だけでなく、企業が蓄積してきた「独自の取引データベース」であるという事実だ。
AI技術が査定、価格設定、在庫管理といった中核業務を担う時代において、そのAIの性能を決定づけるのは、学習元となるデータの質と量に他ならない。ゲオホールディングスやコメ兵ホールディングスのような大手企業が保有する、数百万、数千万件に及ぶ過去の取引記録(「何を」「いくらで仕入れ」「どのような状態で」「いつ、どこで、いくらで売れたか」)は、新規参入者が決して再現不可能な、極めて希少かつ模倣困難な資産である。
この独自のデータを活用して優れたAIモデルを構築できれば、より精度の高い査定(安く仕入れる)と需要予測(高く売る)が可能となり、収益性が向上する。その利益をさらなるデータ収集とAI開発に再投資することで、競合との差は雪だるま式に拡大していく。この正のフィードバックループこそが、AI時代の持続的競争優位の源泉となる。したがって、企業は自社の取引データを単なる過去の記録としてではなく、最も戦略的な資産として位置づけ、その価値を最大化するための組織能力(データサイエンティストやAIエンジニアの確保・育成)を構築することが急務である。
人材動向
業界の変革に伴い、求められる人材のスキルセットも大きく変化している。
- 需要が高まるスキルセット:
- 従来型: 査定士(バイヤー)、店舗運営スタッフ。
- 新規: EC運営人材(撮影、採寸、原稿作成)、データサイエンティスト(価格最適化、需要予測)、AIエンジニア、デジタルマーケター(特に買取顧客獲得のためのWeb集客担当)。
- 査定士(バイヤー)の役割変容: 属人的な「目利き」の価値は、AI査定システムの普及により相対的に低下する。今後の査定士には、AIでは判断が難しい超高額品や真贋判定が困難な希少品を扱う「専門家」としての役割、あるいは顧客との対面コミュニケーションを通じて買取成立率を高める「交渉・クロージング能力」がより一層求められるようになる。
- 賃金相場と人材獲得競争:
- 査定士の給与体系は、固定給に加えて買取実績に応じたインセンティブが設定されることが一般的である。キャリアパスとしては、店長やエリアマネージャーといったマネジメント職、あるいは特定商材の専門性を極めるスペシャリスト職などが存在する 65。モデル年収例として、入社4年目の店長で550万円、入社9年目の課長で650万円といった水準の企業も見られる 67。
- 特に、データサイエンティストやAIエンジニアといったDX人材は、IT業界をはじめとする他業界との獲得競争が極めて激しい。「魅力的な処遇が提示できない」ことが人材確保の大きな課題となっており、業界全体で専門人材の獲得・育成が急務である 68。
労働生産性
リユース業界の労働生産性には、依然として多くの改善の余地が残されている。
- 生産性のボトルネック:
- 査定業務の属人化: 査定士のスキルレベルによって査定時間や精度にばらつきが生じ、組織全体の生産性を不安定にしている。
- EC出品業務: 商品の撮影、採寸、状態確認、説明文作成といった一連の作業は、手作業が多く、ECの売上規模拡大における最大のボトルネックとなっている。
- 店舗オペレーション: 膨大な一点物商品の品出し、陳列、在庫管理、店舗間移動といった物理的な作業は、多くの人手を要する。
- 効率化のポテンシャル: これらのボトルネックは、AI技術の導入によって解消される可能性が非常に高い。AIによる査定支援は業務の標準化と高速化を促し、AI画像認識を用いた自動採寸や商品説明文の自動生成は、EC出品業務の工数を劇的に削減することが期待される。
第8章:AIの影響とインパクト
AI(人工知能)は、リユース業界のバリューチェーン全体に破壊的なインパクトをもたらし、競争のルールを根本から書き換える最大のゲームチェンジャーである。
AIによる「査定・真贋鑑定」の変革
従来、熟練した人間の「目利き」に依存してきた査定・真贋鑑定の領域は、AIによって最も劇的な変革を遂げつつある。
- 真贋鑑定AI: AI画像認識技術を活用し、ブランド品のロゴのフォント、縫製のピッチ、金具の形状、刻印の深さといった微細な特徴点を、数百万点に及ぶ正規品と模倣品のデータベースと照合することで、瞬時に真贋を判定する。ブランド品リユース大手のコメ兵が導入する「AI真贋システム」は99%以上の精度を謳い、鑑定にかかる時間を従来の3分の1に短縮したと報告されている 69。また、フェイクバスターズに代表される真贋鑑定に特化したサービスは、スニーカーや高級時計、アパレル、トレーディングカードへと鑑定対象を急速に拡大しており、業界のインフラとなりつつある 71。
- 価格査定AI: 自社の過去の膨大な販売・買取データに加え、C2Cプラットフォーム上の取引価格、事業者向けオークションの落札相場といった外部市場のデータをリアルタイムでクローリング・分析する。これにより、商品の状態、付属品の有無、季節性、最新のトレンドといった多様な変数を考慮した上で、利益を最大化する最適買取価格と最適販売価格を自動で算出する 72。
- 属人化の打破と業務の標準化: AIは、一部のベテラン査定士が持つ「暗黙知」であった査定ノウハウを、データに基づいた「形式知」へと転換させる。これにより、経験の浅い新人スタッフでも、AIのアシストを受けることで一定水準以上の査定業務を遂行できるようになる。これは、教育コストの大幅な削減と、店舗や担当者による査定価格のばらつきの解消、すなわちサービス品質の標準化に直結する 70。人間の査定士は、AIの判断を最終確認したり、AIでは判定が困難な超高額品や特殊なケースに集中したり、あるいは顧客とのコミュニケーションに注力するなど、より付加価値の高い役割を担うことになる。
AIによる「オペレーション・マーケティング」の変革
AIのインパクトは査定業務に留まらず、バックヤード業務からマーケティングに至るまで、オペレーションのあらゆる側面に及ぶ。
- 需要予測と在庫最適配置: AIは、店舗別、カテゴリ別、さらにはSKU(最小管理単位)別の過去の販売データを分析し、天候、曜日、地域のイベントといった外部要因も加味して、将来の需要を高精度で予測する 77。この予測に基づき、「どの商品をどの店舗に配置すれば最も早く売れるか」「店舗在庫のうち、どの商品をECサイトに出品すべきか」といった在庫の最適配置を自動で判断・指示する。これにより、販売機会の損失を最小化すると同時に、在庫回転率を向上させ、キャッシュフローを改善する 79。
- EC出品業務の自動化: リユースECにおける最大のボトルネックである「ささげ業務(撮影・採寸・原稿作成)」は、AIによる自動化が最も期待される領域である。最新の技術では、商品画像をAIが解析し、①商品のカテゴリを自動で分類、②画像から寸法を自動で採寸、③キズや汚れといった状態を自動で検出し説明文に反映、④商品の特徴に基づいた魅力的な商品説明文を自動で生成する、といったプロセスの一気通貫での自動化が進んでいる 80。これにより、EC出品にかかる時間と人件費を劇的に削減できる。
- 顧客対応・マーケティング: AIチャットボットを導入することで、買取に関する基本的な問い合わせや査定依頼の受付を24時間365日自動で対応することが可能になる。また、顧客の過去の購買履歴やサイト上の閲覧行動をAIが分析し、個々の顧客の嗜好に合わせた中古品を推薦(パーソナライズド・リコメンデーション)することで、購買転換率の向上が期待できる 80。
AIがもたらす競争優位の変化
AIの導入は、リユース業界の競争構造を「勝者総取り(Winner-Takes-All)」へと変貌させる可能性を秘めている。
AIモデルの性能、特に査定や需要予測の精度は、学習に用いるデータの「質」と「量」に完全に依存する。ゲオホールディングスやコメ兵ホールディングスといった、長年にわたり数千万点以上の取引データを蓄積してきた大手企業は、他社が到底持ち得ない巨大で質の高い教師データを持っている。
この独自のデータを活用することで、彼らは他社よりも高性能なAIを開発することが可能となる。高性能なAIは、より正確な査定(より安く、適切な価格で仕入れる)と、より的確な価格設定(より高く、早く売る)を実現し、企業の収益性を向上させる。そして、その向上した収益を、さらなるAI開発やデータ蓄積(例えば、M&Aによる他社データの獲得)に再投資することができる。この「データ → AI → 収益 → データ」という正のフィードバックループが回り始めると、データを持つ企業と持たざる企業の差は指数関数的に拡大し、最終的には「データ富者」が市場を独占する構造が生まれる可能性がある。
この構造変化は、中小事業者にとって深刻な脅威である。単独で大手に対抗するAIを開発することは、データ量と資金力の両面から極めて困難である。したがって、今後の戦略として、高精度なAI査定・真贋鑑定サービスをSaaS形式で提供するサードパーティ企業(例:AIデータ社の「AI孔明」72、フェイクバスターズ 71など)と積極的に連携し、テクノロジーの恩恵を享受することが、生き残りのための必須条件となるだろう。
第9章:主要トレンドと未来予測
リユース業界は、AIのインパクトに加え、一次流通との関係性やチャネル戦略の変化といった大きなトレンドに直面している。
リコマース(Recommerce)の本格化
- 定義: リコマースとは、製品を製造・販売するメーカーや小売業者(一次流通)自身が、自社製品の買取や再販(下取りプログラム、認定中古品販売など)を手掛けるビジネスモデルを指す 83。*CPO(Certified Pre-Owned)*とは、メーカー自身が品質を保証する認定中古品のことで、その代表例である。Appleの認定整備済製品や、アウトドアブランドのスノーピーク、アパレルブランドの無印良品などが先進的な事例として挙げられる 83。
- リユース専業事業者への影響: この動きは、リユース専業事業者にとって「脅威」と「機会」の両側面を持つ。
- 脅威: 一次流通企業が自ら買取チャネルを持つことは、リユース事業者の仕入れ競争がさらに激化することを意味する。特に、特定ブランドの専門店にとっては、仕入れの源流を直接押さえられることになり、深刻な脅威となり得る。
- 機会: 一方で、多くの一次流通企業は、中古品の査定、値付け、商品化、在庫管理、再販といったリユース事業特有のオペレーション・ノウハウを持っていない。リユース事業者が長年培ってきたこれらのケイパビリティは、一次流通企業にとって非常に魅力的である。したがって、一次流通企業の公式パートナーとして買取・再販業務を請け負うことで、新たな収益源を確保し、質の高い商品を安定的に仕入れるという協業の機会が生まれる。
オンラインとオフラインの融合(OMO)
- 定義: *OMO(Online Merges with Offline)*とは、Webサイトやスマートフォンアプリといったオンラインチャネルと、実店舗であるオフラインチャネルの垣根を取り払い、顧客データを一元化することで、顧客一人ひとりに対して最適化された一貫性のある購買体験を提供する戦略である 57。
- 具体例:
- ECサイトで注文した商品を、最寄りの店舗で試着・受け取りができる(クリック&コレクト)。
- スマートフォンのアプリで店舗の在庫状況をリアルタイムに確認し、取り置きを依頼できる。
- 店舗で査定を受けた商品の情報をアプリで管理し、後日好きなタイミングで売却を決定できる。
- コメ兵グループのK-ブランドオフは、店舗とECのポイント連携やお取り寄せ機能を強化するOMO戦略により、売上を20%向上させたと報告している 58。
- 戦略的意味合い: OMOは、顧客の利便性を最大化するための鍵となる戦略である。店舗はもはや単に商品を売買する場所ではなく、ECと連携した物流拠点であり、ブランドの世界観を伝え、顧客との信頼関係を深める「体験の場」へとその役割を変化させていく必要がある。
専門特化と高付加価値化
- 背景: メルカリに代表されるC2Cプラットフォームは、日常的な衣類や雑貨といった、低~中価格帯の汎用品の取引において圧倒的な強みを持つ。この領域でB2C事業者が価格や品揃えで競合することは非効率である。
- 戦略: この状況を受け、多くのB2C事業者はC2Cとの直接的な消耗戦を避け、自社の強みが活きる領域へと戦略的にシフトしている。具体的には、以下の二つの方向性が挙げられる。
- 高価格帯への特化: 高級ブランド品、宝飾品、高級時計、美術品など、購入・売却の双方で「専門的な知識」と「真贋を見極める信頼性」が決定的に重要となる領域。
- 特定カテゴリへの特化: スニーカー、トレーディングカード、ヴィンテージ古着、楽器、アニメグッズなど、特定の趣味やライフスタイルに深く関連し、熱心なファンコミュニティが存在する領域。
これらの領域では、価格だけでなく「専門性」と「信頼性」が付加価値となり、高い利益率を確保することが可能になる 48。
海外市場への展開
- 背景: 日本で流通している中古品は、総じて状態が良く、品質が高いと国際的に評価されている。特に、日本のブランド品、アニメ・漫画関連グッズ、ホビー商材などは、アジアを中心とした海外市場で非常に高い人気を誇る 18。
- 動向: この旺盛な海外需要を取り込むため、大手リユース企業の海外展開が加速している。ゲオホールディングスが運営する「セカンドストリート」は、アメリカ、台湾、マレーシア、タイへ積極的に出店し、海外店舗数は100店舗を突破した 86。ブックオフグループホールディングスも、「BOOKOFF USA」やマレーシアで「Jalan Jalan Japan」を展開し、成功を収めている 89。戦略としては、越境ECプラットフォームを活用したオンライン販売と、現地でのリアル店舗展開が両輪となる 90。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
業界をリードする主要企業およびディスラプターの戦略、強み・弱み、DX/AIへの取り組みを比較分析する。
| 企業名 | ビジネスモデル | 主力商材 | 強み | 弱み | DX/AIへの取り組み | 仕入れ戦略 | 直近の業績(売上/利益成長率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲオHD(セカンドストリート) | 総合リユース | 衣料・服飾雑貨、家具・家電 | 圧倒的な店舗網(国内880店超)、規模の経済、海外展開 | 総合ゆえの専門性の希薄化、低~中価格帯でのC2Cとの競合 | OMO(お取り寄せ)、在庫管理システム | 店舗買取中心、海外での買取も強化 | 2025.3期: 売上4,277億円(△1.4%)、営業利益112億円(△33.1%) 27 |
| ハードオフコーポレーション | 専門・総合リユース | AV機器、楽器、PC、生活雑貨 | 商材別屋号による専門性、強力なFC網、高いブランド認知度 | 直営比率が低く、戦略の浸透に時間がかかる可能性 | – | 店舗買取中心 | 2025.3期: 売上335億円(+11.4%)、営業利益32億円(+14.8%)。29期連続増収 92 |
| トレジャーファクトリー | 総合リユース | 家具・家電、アパレル | 関東圏でのドミナント戦略、独自サービス(トレファク引越) | 全国的な知名度は限定的 | 基幹システムの自社開発 | 店舗・出張買取(引越連携) | 2025.2期: 売上422億円(+22.5%)、営業利益40億円(+20.5%)。過去最高益 94 |
| コメ兵ホールディングス | 専門リユース | ブランド品、宝飾品、時計 | 高価格帯での圧倒的な専門性と信頼性、強力な鑑定士チーム | ブランド品相場変動の影響を受けやすい | AI真贋鑑定システム、OMO戦略 | 店舗・宅配買取、業者間オークション | 2025.3期: 売上1,590億円(+33.1%)、営業利益62億円(△17.1%) 24 |
| ブックオフグループHD | 専門・総合リユース | 本・ソフト、トレカ・ホビー、アパレル | 高いブランド認知度、トレカ・ホビーへのシフト成功、海外事業 | 祖業である書籍市場の縮小 | – | 店舗買取中心 | 2025.5期: 売上1,192億円(+6.8%)、経常利益39億円(+13.2%)。過去最高益 95 |
| BuySell Technologies | オンライン・非店舗型 | 着物、骨董品、ブランド品 | 出張・宅配買取特化、シニア層へのマーケティング力、データドリブン経営 | 店舗接点の欠如、広告宣伝費への依存 | 買取販売統合プラットフォーム「Cosmos」 | Web集客による出張・宅配買取 | 2025.12期2Q: 売上246億円(+48.3%)、営業利益24億円(+39.8%) 97 |
| マーケットエンタープライズ | オンライン・非店舗型 | 多岐(農機具、楽器、家電等) | Webマーケティング力、多数の専門買取サイト運営、高い在庫回転率 | 買取単価が比較的低い傾向 | 買取プラットフォーム「おいくら」 | Web集客による宅配・出張買取 | 2025.6期3Q: 売上178億円(+34.0%)、営業利益4.7億円(+344.9%) 99 |
| メルカリ | C2Cプラットフォーム | 全般 | 圧倒的なユーザー基盤、優れたUI/UX、ブランド力 | 偽造品リスク、個人間トラブル、出品・発送の手間 | AIによる出品簡便化、レコメンド機能 | -(個人が出品) | – |
プレイヤー別戦略概要
- 総合リユース(ゲオHD、ハードオフ、トレジャーファクトリー): これらの企業は、広範な店舗網を基盤とした「規模」と「利便性」を追求している。特に業界最大手のゲオHD(セカンドストリート)は、国内での圧倒的な地位を固めつつ、成長の活路を海外に求めている 86。トレジャーファクトリーは、引越と買取を組み合わせるなど、ユニークなサービス開発で差別化を図る 100。
- 専門リユース(コメ兵HD、ブックオフHD): 特定領域での「専門性」と「信頼性」を深掘りする戦略をとる。コメ兵は、AI真贋鑑定などテクノロジーへの投資を積極的に行い、高価格帯市場でのリーダーシップを強化している 70。ブックオフは、縮小する書籍市場から、成長著しいトレカ・ホビー領域へとうまく事業の軸足を移し、過去最高益を達成した 96。
- オンライン・非店舗型(BuySell、マーケットエンタープライズ): これらの企業は、物理的な店舗を持たず、デジタル技術を駆使して効率性を極める「DX先行」モデルである。BuySellは、テレビCMなどを活用したシニア層へのアプローチと、データに基づいたオペレーションに強みを持つ 5。マーケットエンタープライズは、卓越したWebマーケティング能力で多数の専門買取サイトから集客し、業界最高水準の在庫回転率を誇る 28。
- ディスラプター(メルカリ): C2Cの巨人であるメルカリは、B2C事業者にとって最大の競合であると同時に、市場全体のパイを拡大した功労者でもある。近年は、B2C事業者が出店する「メルカリShops」や、真贋鑑定サービスとの連携など、B2Cとの「競争」から「共創」へと関係性をシフトさせる動きも見せている 5。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの分析を統合し、リユース・リサイクル業界で勝ち抜くための戦略的な示唆と具体的な推奨事項を導出する。
今後3~5年の勝敗を分ける決定的な要因
- 優良在庫の安定確保能力: C2Cプラットフォームやリコマースに参入する一次流通企業との熾烈な仕入れ競争を勝ち抜くため、店舗買取だけでなく、利便性の高いオンライン買取チャネルや法人提携など、多様かつ効率的な買取網を構築できるかが企業の生命線を握る。
- AI活用によるオペレーション効率: 査定、真贋鑑定、在庫管理、EC出品といったバリューチェーンのあらゆるプロセスをAIによって最適化・自動化し、属人性を排して圧倒的なコスト競争力と高い利益率を実現する能力。これは、もはや選択肢ではなく必須要件となる。
- C2Cにはない「信頼」の構築とブランド化: 真贋鑑定、品質保証、専門知識に基づくコンサルテーション、充実したアフターサービスといった「信頼」を、単なる安心材料ではなく、明確な付加価値を持つ「サービス」として提供し、ブランド化する能力。これにより、価格競争からの脱却が可能となる。
自社が捉えるべき機会と備えるべき脅威
- 機会(Opportunities):
- C2Cからの顧客シフト: C2Cの出品・取引プロセスに「手間」や「リスク」を感じるユーザー層が、利便性と信頼性を求めてB2Cチャネルへ移行する潮流を捉える。
- AI技術による生産性革命: AIを導入することで、従来は不可能だったレベルでの業務効率化と、データに基づいた新たなサービス創出が可能になる。
- リコマース市場での協業: 一次流通企業がリユース事業に参入する動きを脅威と捉えるだけでなく、自社の専門ノウハウを提供するパートナーとなることで、新たな事業機会を創出する。
- グローバル市場の開拓: 品質の高い日本の中古品に対する旺盛な海外需要を、越境ECや現地出店を通じて取り込む。
- 脅威(Threats):
- 仕入れ先の枯渇: C2Cプラットフォームによる個人在庫の継続的な吸収。
- 一次流通企業の市場侵食: メーカー自身が認定中古品事業を本格化させることによる、仕入れと販売両面での競争激化。
- AI活用の格差拡大: AI開発の鍵となる「データ」を独占する大手が、後発企業に対して圧倒的なコスト優位・精度優位を確立し、市場の寡占化が進むリスク。
戦略的オプションの提示と評価
| 戦略オプション | 概要 | メリット | デメリット/リスク | 成功の鍵 |
|---|---|---|---|---|
| A: 総合リユース×OMO強化 | 既存の広範な店舗網を活かし、OMO戦略で顧客利便性を追求。幅広い商材で規模を拡大し、マスマーケットでのシェアを維持・拡大する。 | ・既存資産(店舗網)の有効活用 ・幅広い顧客層へのリーチ ・規模の経済性 | ・低利益率体質に陥りやすい ・低~中価格帯でのC2Cとの直接競合が激しい | ・店舗オペレーションの徹底的な効率化 ・シームレスなEC連携システムの構築 |
| B: 専門特化×高付加価値化 | 高価格帯・特定カテゴリ(ブランド品、時計、トレカ等)に経営資源を集中させ、専門性と信頼性(真贋鑑定)で圧倒的な差別化を図る。 | ・高い利益率の確保 ・価格競争からの脱却 ・強固なブランド構築 | ・対象市場規模が限定的 ・高度な専門人材(鑑定士、バイヤー)の確保・育成が必須 | ・最先端の真贋鑑定技術(AI含む)への投資 ・専門家コミュニティの形成とネットワーク |
| C: オンライン買取プラットフォーム化 | 店舗を持たず、オンライン完結型の買取サービス(宅配・出張)に特化。WebマーケティングとAI査定を駆使して全国から効率的に仕入れる。 | ・店舗関連コストが不要で損益分岐点が低い ・地理的制約なく全国から仕入れ可能 | ・Web上での激しい集客競争 ・現物を確認できないことによる査定リスク | ・優れたUI/UXによる高い申込完了率 ・高精度なAI査定モデルと物流の効率化 |
| D: M&Aによる非連続的成長 | 専門分野に強みを持つ小規模事業者や、独自のAI技術を持つITベンチャーを買収することで、事業領域や技術力を短期間で獲得する。 | ・新規事業・技術への迅速な参入 ・新たなノウハウや人材の獲得 | ・PMI(買収後の統合プロセス)の失敗リスク ・高値掴みによる財務的負担 | ・明確なM&A戦略と対象企業の精緻な評価(デューデリジェンス)能力 |
最終戦略提言:「AIパワード・スペシャリティ・リテイラー」への変革
提言:
中長期的に持続可能な高収益事業を構築するため、戦略オプションB「専門特化×高付加価値化」を主軸戦略として採用し、その実行プロセスをAI技術で徹底的に強化する「AIパワード・スペシャリティ・リテイラー」への変革を提言する。
具体的には、市場成長率と利益率が共に高く、かつC2Cが参入しにくい「信頼性」が問われる専門領域、すなわち「ブランド品」「高級時計」「スニーカー」「トレーディングカード」などに経営資源を集中させる。そして、バリューチェーンのあらゆる段階でAIを活用し、オペレーション効率と顧客体験を極限まで高めることで、模倣困難な競争優位を確立する。
実行に向けたアクションプラン概要:
- Phase 1:基盤構築(初年度)
- 主要KPI: AI真贋鑑定システムの導入完了および精度99%達成、オンライン買取申込プロセスのUI/UX改善による申込完了率20%向上。
- アクションプラン:
- 最先端のAI真贋鑑定技術を持つベンダーとの戦略的提携、または自社開発チームの組成。
- 買取Webサイトおよびアプリの全面リニューアルプロジェクトの開始。
- データサイエンティスト、AIエンジニア、UI/UXデザイナーといったDX専門人材の採用を最優先で強化。
- Phase 2:サービス展開と効率化(2~3年目)
- 主要KPI: 対象とする専門領域における買取シェアNo.1の獲得、EC出品プロセスの50%自動化達成。
- アクションプラン:
- 専門領域に特化したデジタルマーケティング投資を倍増させ、ターゲット顧客層への認知を拡大。
- AIによる商品説明文自動生成、画像からの自動採寸・キズ検出システムの導入。
- 既存店舗の一部を、専門商材の買取・相談カウンターおよびEC商品のショールーム機能を備えた拠点としてリニューアル。
- Phase 3:エコシステム構築(4~5年目)
- 主要KPI: 一次流通メーカーとの認定中古品(CPO)パートナーシップ契約を3社以上締結、海外向け越境EC売上比率15%達成。
- アクションプラン:
- Phase 1, 2で培った高度な鑑定・再販ノウハウをパッケージ化し、一次流通メーカーに対してCPO事業の共同運営を提案。
- 多言語対応の越境ECプラットフォームを構築し、海外市場への本格的な販売を開始。
第12章:付録(Appendix)
参考文献・引用データ・参考ウェブサイト
- リユース経済新聞「リユース業界の市場規模推計」各年版
- 環境省「令和6年度 リユース市場規模調査 報告書」等
- 株式会社ゲオホールディングス IR資料
- コメ兵ホールディングス株式会社 IR資料
- 株式会社ブックオフグループホールディングス IR資料
- 株式会社BuySell Technologies IR資料
- 株式会社マーケットエンタープライズ IR資料
- 本文中に引用した各種調査レポート、ニュース記事一覧
引用文献
- リユース業界の市場規模推計2024(2023年版) – リユース経済新聞, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_10109.php
- II.リユース市場規模調査等 – 環境省, https://www.env.go.jp/content/000214349.pdf
- 【2025年版】リユースEC市場と大手4社の動向を解説 – ebisumart, https://ebisumart.com/blog/reuse-ec/
- リユース業界の市場規模推計2023(2022年版), https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_8811.php
- リユース業界の市場規模は4兆円に拡大する?最新動向と将来性2024 – SI Web Shopping, https://siws.dgbt.jp/blog/reuse-market-trends
- リユース市場2030年に4兆円規模、本紙推計, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_8561.php
- 2030年に4兆円市場?! リユース業界の最新動向とブックオフの成長戦略【前編】, https://recruit.bookoff.co.jp/blog/1742/
- 物価高騰でリユースの利用が増加、50%が「リユース品の購入」が増加、36%が「不用品の売却」が増加 ー家計の不足は平均5.6万円/月 | BEENOS株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000532.000035599.html
- リユース業界の市場規模推計2022(2021年版), https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_7557.php
- リユース等を取り巻く社会動向と これまでの環境省の取組, https://www.env.go.jp/content/000266392.pdf
- リユース業界の市場規模推計2025(2024年版) – リユース経済新聞, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_11719.php
- 中古ブランド品・宝飾品売上ランキング2024(2023年度) – リユース経済新聞, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_5752.php
- 中古家具・中古家電売上ランキング2024(2023年度) – リユース経済新聞, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_5818.php
- 【本・CD・ゲーム等】中古メディア売上ランキング2024(2023年度) – リユース経済新聞, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_9726.php
- リユース企業 成長率ランキング2024(2023年度版), https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_5998.php
- リユース産業のダイナミズム ~メルカリ参入後の市場の変化~ – 高知工科大学, https://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/pdf/2017/03/14/a1180492.pdf
- リユース業界の未来が見える! 環境省の「リユース促進のロードマップ」をのぞいてみた, https://recruit.bookoff.co.jp/blog/2112/
- リユース・中古の市場規模が拡大傾向へ! その理由や今後の課題を解説 | 大塚商会のERPナビ, https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/category/apparel/sp/solving-problems/archive/230927-01.html
- 2024年度「国内Z世代意識・購買行動調査」 | デロイト トーマツ グループ – Deloitte, https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/consumer-products/research/generationz-behavior-survey.html
- ファッションリユース市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, http://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3584
- 2019年度「フリマアプリ利用者と非利用者の消費行動」に関する意識調査 | 株式会社メルカリ, https://about.mercari.com/press/news/articles/20190425_consumersurvey/
- リユース市場とは?動向と将来性を専門紙が解説(2025年版), https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_5804.php
- 買取専門店が儲からない理由とその解決策をお教えいたします – ソレウル, https://soreuru.jp/column/notprofitable/
- IR(株主・投資家情報)|株式会社コメ兵ホールディングス, https://komehyohds.com/ir/
- 決算説明会 – IR(株主・投資家情報) – コメ兵ホールディングス, https://komehyohds.com/ir/event/presentation.html
- 決算説明資料 | 株式会社ゲオホールディングス, https://www.geonet.co.jp/ir/library/presentation/
- 決算説明資料 – ゲオホールディングス, https://www.geonet.co.jp/geo_wp/wp-content/uploads/2025/05/2681_20250509_presentation_4Q_J_Sebu09.pdf
- 【IR広告】マーケットエンタープライズ〈3135〉個人投資家向けIR説明会 – 楽天証券, https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/marketenterprise/
- リユース業界を取り巻く環境関連法の法的環境の整理 (Ver.1.0) – 環境省, https://www.env.go.jp/content/900532866.pdf
- eKYCとは?オンライン本人確認の導入方法や導入メリットなどを解説 – 三井住友銀行, https://www.smbc.co.jp/hojin/magazine/planning/about-ekyc.html
- ソフマップ社長が語る、買取アプリ「ラクウル」のオンライン本人確認/eKYC導入の決め手と未来, https://biz.trustdock.io/column/sofmap-reusetech-conf
- リユースビジネスを行う際は要注意!家電リサイクル法により事業者に課せられる義務とは?|Selloop | 二次流通で、顧客とのつながりをつくる。 – note, https://note.com/jolly_beetle845/n/n60f36959f2d8
- いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル! – 環境省, https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tvrecycle.html
- インボイス制度が古物商に与える影響とは?特例も解説 – マネーフォワード クラウド, https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/49492/
- 2023年のインボイス制度についてのお客様への影響 | 金・プラチナ・ダイヤ・宝石高額買取なら実績No.1のリファスタ, https://kinkaimasu.jp/system/invoice/
- 【Z世代トレンド】400人調査で判明!消費行動のカギは「自分軸」と「信頼感」, https://prx.dentsuprc.co.jp/blog/generation_z_research
- 【フリマアプリあるある大公開】全年代で圧倒的に認知されているのは「メルカリ」と判明!フリマ出品で尻込みしてしまうこと、失敗してしまうことは”箱”にあり…!? | 株式会社アースダンボールのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000047392.html
- 【フリマアプリの不安に関するアンケート調査】フリマアプリ「個人間の取引」に対して72.2%のユーザーが不安を感じると回答 最大の不安は「返品トラブルのリスク」という結果に | VELVETT.PTE.LTD.のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000128267.html
- UI/UXの進化を25年間見てきたからこそ伝えたい、今が最高のタイミングという話 – note, https://note.com/koheitorigoe7/n/nbdcab629aa24
- eKYCとは?オンライン本人確認のメリットやよくある誤解、選定ポイント、事例、最新トレンド等を徹底解説! – TRUSTDOCK, https://biz.trustdock.io/column/ekyc
- RFIDでサプライチェーンをまたぐ医薬品トレーサビリティを確保するデモシステムを構築 – サトー, https://www.sato.co.jp/about/news/2022/release/20220518_01.html
- リサイクル素材の出自を解き明かす「RePLAYER®︎ ブロックチェーンプラットフォーム」 – 三井化学, https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/soso/archive/column/recycle/2023-0628-01
- トレーサビリティの基礎からブロックチェーン活用まで!食品・医療分野の注目技術を徹底解説, https://blog.rflocus.com/traceability/
- 令和6年2月16日 よくあるご質問 問1 模倣品の水際取締りが強化されたとのことですが、 – 税関, https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/20221001faq.pdf
- 我が国におけるリユースの現状と今後の方向性(案) – 環境省, https://www.env.go.jp/content/900532858.pdf
- サーキュラーエコノミーで実現する資源の循環と新たなビジネスモデル – 大阪ガス, https://ene.osakagas.co.jp/media/column/column_15.html
- リユース品・中古品に関する調査(2024年) | リサーチ・市場調査 …, https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20240911reuse
- リユース事業をゼロから始める方法!市場動向と成功事例を徹底解説, https://corp.ei-o.com/blog/start-reuse-business/
- リユース品市場における二次流通業者と消費販売者の取引特性 – researchmap, https://researchmap.jp/h-nabuchi/published_papers/50086858/attachment_file.pdf
- 買取専門店を開業する方法とは?手順や成功のポイントをご紹介! | RECORE POS, https://recore-pos.com/column_post/purchase-store-opening/
- 出張買取が人気の理由|フリマアプリやリサイクルショップとの違いを徹底解説, https://xn--ihqw4leua816gvvy.jp/2024/12/24/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%81%8C%E4%BA%BA%E6%B0%97%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1%EF%BD%9C%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%84%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF/
- 80%以上が宅配買取に満足。宅配買取のメリットがわかるアンケート結果 | バイセル公式, https://buysell-kaitori.com/column/feature-survey-delivery/
- バリューチェーン(価値連鎖) | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI), https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/value_chain.html
- バリューチェーンとは?企業価値の源泉を特定する考え方を解説 | [ファンダナビ]Funda Navi, https://navi.funda.jp/article/value-chain
- 買取システムならBuyForc、完全自動の買取リユースシステム – 買取システムBuyForce, https://www.buy-force.jp/%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/
- 買取システムBuyForce|企業向け総合買取・効率化ソリューション」 – 買取buyforce 専用システム, https://www.buy-force.jp/
- OMO型店舗とは?メリットと具体例、成功のためのポイントを解説 | LISKUL, https://liskul.com/omo-store-109071
- リユース事業を展開するK-ブランドオフがW2 Unifiedを導入、 EC×リアル店舗の相乗効果で生み出す新たな顧客体験を実現, https://www.w2solution.co.jp/example/kbrandoff/
- 買取サービスに関する実態調査報告書 令和7年4月 30 日 消費者庁表示対策課, https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms201_250430_02.pdf
- ゲオ、「中古品売買に関する意識調査」を実施 | 株式会社ゲオホールディングス, https://www.geonet.co.jp/news/28085/
- 拡大する個人間の中古品消費市場 – Research Focus, https://www.jri.co.jp/file/report/researchfocus/pdf/10345.pdf
- 【47都道府県別 リユース利用実態調査】エリアによって異なる利用実態が明らかに! – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000141539.html
- VRIO分析とは?やり方やメリットを具体的な事例で解説 – Lucid Software, https://lucid.co/ja/blog/how-to-use-vrio-framework
- VRIO分析とは 4つ視点から強みを明らかにする分析フレームワークを解説 – 大和総研, https://www.dir.co.jp/world/entry/vrio
- 【2025年最新版】ブランド品の鑑定士に必要な資格とは?年収や将来性も徹底解説! – エステメ, https://estime.co.jp/column/brand-appraiser-qualification/
- 買取業界の将来性とは?今後伸びる仕事か徹底分析!|株式会社Tieel 採用広報 – note, https://note.com/jolly_snipe4099/n/n9170188fd4ff
- 鑑定士(査定・買取)/未経験歓迎 – 株式会社エコリングの求人情報 – doda, https://doda.jp/DodaFront/View/EndJobDetail/j_id__3006498062/
- DX動向2024-深刻化するDXを推進する人材不足と課題, https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/discussion-paper/f55m8k00000039kf-att/dx-talent-shortage.pdf
- 日本のリユース品「信頼できる」 訪日客から熱視線…注目浴びるワケは“偽物”を短時間で見抜くAI技術【news23】|TBS NEWS DIG – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=op_mvIq_uSU
- AIでブランド品の真贋をチェック 細かい印刷の違いなど見極める ブランド品リユース大手「コメ兵」 | 愛知のニュース, https://news.tv-aichi.co.jp/single.php?id=6198
- 国内シェアNo.1のAI真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」、落とし物リユース事業における真贋鑑定を開始。findと連携し、落とし物の循環型モデルを強化 | IVA株式会社のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000053083.html
- AIデータ リユース向けにAIソリューション, https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_11806.php
- AIデータがリユース業界のDXを推進―「AI孔明」で査定の標準化と経営分析を支援, https://brandreusenews.jp/posts/wzJizPFL
- ウリドキ、AIで異常査定価格を自動検出する新システムを導入, https://uridoki.co.jp/news/press/2025_0512_2802/
- テクノロジーでリユース市場は加速する!査定・回収での技術革新事例まとめ|Selloop – note, https://note.com/jolly_beetle845/n/n9716d1202837
- リユース領域における最先端技術の研究開発組織「BuySell Research」を本格始動 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000018121.html
- 在庫管理にもAI?在庫管理にAIを活用するメリットとポイント – ZAICO, https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/ai-for-inventory-management/
- AIを在庫管理に活用すると現場はどう変わる?メリットや事例を紹介 – エルライン, https://lline-group.co.jp/magazine/ai-inventory-management/
- AIによる在庫最適化で業務効率UP!在庫管理における4つの導入事例, https://wa2.ai/ai-news/zaiko-kanri-ai-dounyu-jirei-mondaiten
- 【2025年最新】ECサイト運営における生成AI活用術5選!導入メリットやプロンプトを紹介!, https://weel.co.jp/media/generate-ai-ec/
- 【2025年版】生成AIで差をつけるECサイト運営の秘訣 – Ecbeing, https://www.ecbeing.net/contents/detail/s/483
- 生成AIヒーローが変えるEコマースの未来: 自動出品で時短と効率化を実現 – note, https://note.com/housememo/n/nf10e3243ca48
- リコマースとは?注目の理由やブランドの取り組み事例を解説 – コマースピック, https://www.commercepick.com/archives/51795
- 【認定中古品とは】メーカー担当者が押さえるべきポイントを解説 – オーダー!, https://order-us.jp/article-certified-used-item/
- なぜ海外で日本のリユース品は人気を集めるのか?個人や企業の販売方法も解説, https://wasabi-inc.biz/column/reuse_overseas/
- ゲオ傘下のセカンドストリートが海外で急成長。100店突破、台湾やアメリカで急伸の店舗戦略 | Business Insider Japan, https://www.businessinsider.jp/article/295740/
- セカンドストリート世界1,000店舗達成!世界に広がるセカストの魅力とは? – talk about 2ndSTREET, https://www.2ndstreet.jp/talkabout/shop/global1000stores/index.html
- 世界的なリユースショップチェーンを目指して、海外出店を強化セカンドストリート 海外100店舗を突破 | 株式会社ゲオホールディングス, https://www.geonet.co.jp/news/46672/
- 数字で見るリユース業界とブックオフ – BOOK-OFF Group 新卒採用サイト, https://freshers.bookoff.co.jp/blog/344/
- リユース業界の市場規模と最新トレンドを解説!今後の成長要因とは?, https://corp.ei-o.com/blog/reuse-market-size/
- 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結), https://assets.money.st-note.com/documents/securities/2681/010120250509536681.pdf
- 決算説明資料, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250526/20250523564268.pdf
- 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結), https://finance.stockweather.co.jp/contents/dispPDF.aspx?disclosure=20250512540077
- 株式会社トレジャー・ファクトリー, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250409/20250409511355.pdf
- ブックオフグループホールディングス(9278)2025年5月期通期決算説明動画 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Z2hQq-Kbcmo
- ブックオフグループホールディングス[9278] 2025年5月期 決算説明会 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=F6igXNVULG0
- バイセル、堅調な既存事業とM&A戦略がけん引し連結売上高67.2%増、営業利益100.1%増 通期計画を営業利益85億円へ上方修正【2025年12月期 第2四半期決算】 | 株式会社BuySell Technologiesのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000018121.html
- 2025年12月期 第2四半期 決算説明資料, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250814/20250813541370.pdf
- [IRTV 3135] Market Enterprise/Sales and gross profit both reach record highs, and steady progress… – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=KPrSm1pyg6Q
- 中期経営計画 – トレジャーファクトリー, https://www.treasurefactory.co.jp/ir/pdf/Mid-term_version-2024.02-2026.02.pdf