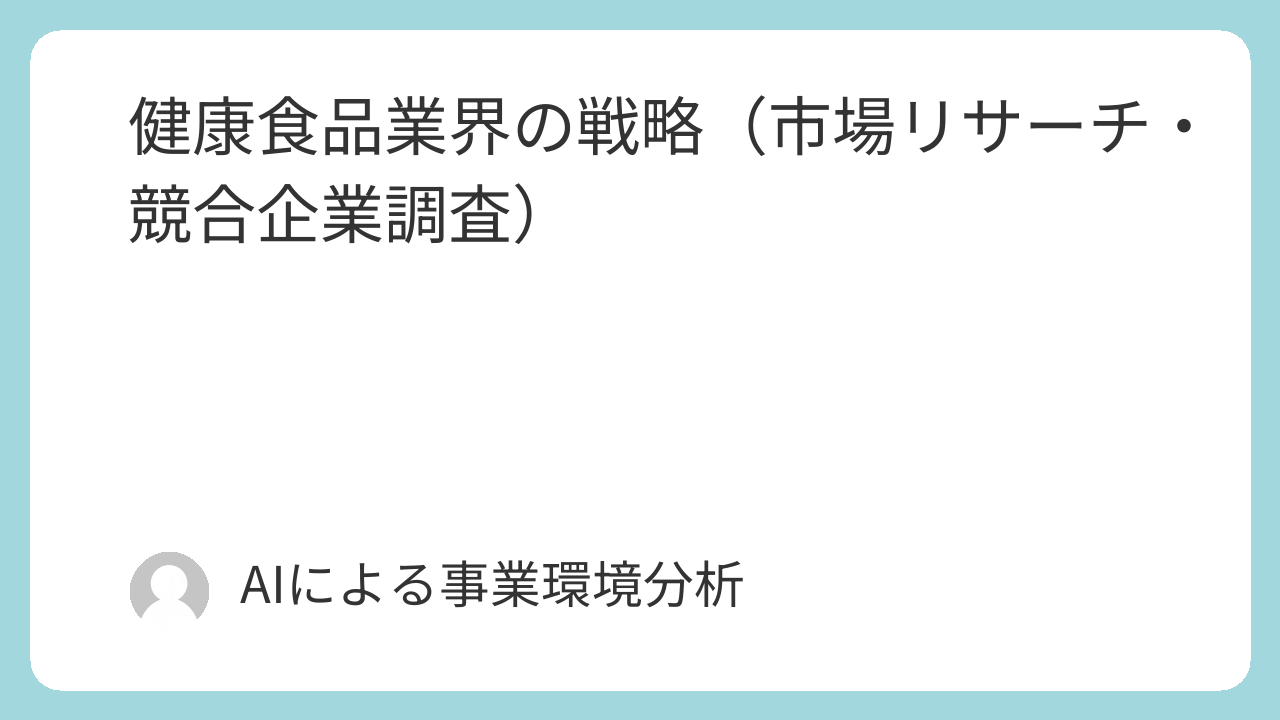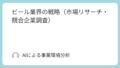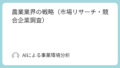エビデンスとAIが駆動する「予防医療」エコシステム:健康食品業界の次世代戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、日本の健康食品(サプリメント)業界において持続可能な成長戦略を策定することを目的とした、包括的な市場分析および戦略提言である。調査対象は、ビタミン・ミネラル等の基礎栄養サプリメント、機能性表示食品、特定保健用食品(トクホ)に加え、それらに関連するOEM/ODM(受託製造)、原料供給、D2Cプラットフォーム市場を含む、業界のバリューチェーン全体を網羅する。
最も重要な結論
日本の健康食品市場は、2024年の紅麹関連問題に端を発する一時的な市場縮小と信頼性の揺らぎに直面している。しかし、高齢化の進展と「治療から予防へ」という不可逆的なヘルスケア意識のパラダイムシフトを背景に、市場の中長期的成長基盤は揺るぎない。
本質的な変化は、競争の主戦場が、単なる「商品(モノ)」の販売から、科学的エビデンスとAIによるパーソナライズ化を核とした「ソリューション」の提供へと完全に移行している点にある。この構造変化は、業界に新たな成長機会をもたらす一方で、適応できない企業にとっては、製品のコモディティ化と熾烈な価格競争に埋没し、市場からの退出を余儀なくされる深刻な脅威となる。今後の勝敗を分けるのは、エビデンス構築力、データ活用・パーソナライズ化技術、そして顧客との関係構築力という3つの能力を有機的に結合させ、高速で学習・改善サイクルを回せる組織能力の有無である。
主要な戦略的推奨事項
本分析に基づき、取るべき事業戦略として、以下の4点を提言する。
- 事業ドメインの再定義:「データ駆動型パーソナル・ウェルネス・ソリューション事業」への転換
従来の「サプリメント製造販売業」という自己認識を捨て、顧客一人ひとりの健康課題にデータと科学的根拠をもって寄り添い、継続的な改善を支援するソリューションプロバイダーへと事業ドメインを再定義する。これは、製品提供に留まらず、診断、アドバイス、コミュニティを含む統合的な顧客体験の設計を意味する。 - R&D投資の戦略的集中:特定領域における「エビデンスNo.1」の確立
全方位的な製品開発から脱却し、睡眠、メンタルヘルス、フェムテック、エイジテックなど、市場成長性が高く、かつ自社の技術的強みを活かして独自の高レベルな科学的エビデンス(ヒト臨床試験データ等)を構築可能な特定領域に研究開発リソースを集中投下する。これにより、模倣困難な競争優位性と高いブランド価値を確立する。 - D2Cモデルの高度化とOMO連携による顧客接点の最適化
顧客データを直接収集・活用できるD2C(Direct to Consumer)を事業の中核に据え、AIを活用したCRM(顧客関係管理)を高度化し、LTV(顧客生涯価値)の最大化を図る。同時に、D2Cの弱点である信頼性やリーチの限界を補うため、ドラッグストアやクリニック、調剤薬局と連携したOMO(Online Merges with Offline)戦略を推進し、専門家によるカウンセリングや製品推奨といったオフラインの接点を戦略的に活用する。 - AIケイパビリティの全社的獲得:異業種アライアンスの積極推進
バリューチェーン全体、特に研究開発(新規素材探索、臨床試験最適化)、マーケティング(パーソナライズ広告、コンプライアンス自動チェック)、顧客体験(AI健康相談)にAIを導入するため、データサイエンティストやAIエンジニア等の専門人材の獲得・育成を最優先課題とする。同時に、自社単独での開発に固執せず、IT、バイオテック、デジタルヘルス分野のスタートアップや大手企業との戦略的アライアンスやM&Aを積極的に模索し、スピード感をもって最先端技術を取り込む。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本の健康食品・サプリメント市場規模の推移と今後の予測
日本の健康食品・サプリメント市場は、長期的な成長トレンドの中、短期的な調整局面に突入している。調査会社により推計値は若干異なるものの、その方向性についての見解は一致している。
富士経済によると、国内サプリメント市場は2023年に拡大したものの、2024年には前年比1.4%減の1兆606億円に縮小する見込みである 1。同様に、矢野経済研究所は2023年度の健康食品市場を9,050億2,000万円と推計し、2024年度は同1.2%減の8,945億1,000万円と予測している 3。
この短期的な縮小の最大の要因は、2024年3月に発覚した小林製薬の「紅麹サプリ」問題である。この問題は、対象製品カテゴリー(コレステロール対策)に留まらず、健康食品全般に対する消費者の安全性への懸念と信頼の揺らぎを引き起こし、顧客離脱や消費マインドの低下につながった 1。
しかし、マクロな視点で見れば、市場の成長を支える根源的なドライバーは依然として強力である。高齢化の進展に伴う健康寿命への関心の高まりや、セルフメディケーション意識の浸透は不可逆的な社会トレンドであり、市場の基盤を支えている。このため、短期的な調整を経た後、市場は再び成長軌道に復帰すると予測されている。矢野経済研究所は、市場は緩やかな回復基調を辿り、2029年度には再び9,000億円規模に達すると予測している 3。
戦略的意味合い(So What?): 現在の市場縮小は、構造的な衰退ではなく、安全性と信頼性という業界の根幹が問われる「調整局面」である。この局面は、信頼性の低いプレイヤーが淘汰され、エビデンスと品質管理体制を強化してきた企業にとっては、むしろ市場シェアを拡大する好機となり得る。短期的な売上減に動揺することなく、顧客の信頼回復と、次なる成長に向けた事業構造改革に投資することが賢明である。
紅麹問題は、消費者の製品選別眼を格段に厳しくした。これにより、市場の二極化が加速する可能性が高い。一つは、製薬会社系企業に代表される、長年の実績に裏打ちされた高い信頼性を持つブランドへの需要集中である。もう一つは、機能性表示食品の中でも、質の高い科学的エビデンス(特にヒト臨床試験の結果)を分かりやすく提示している製品への選好である。消費者は、漠然としたイメージや安価さだけでは製品を選ばなくなり、「誰が、どのような根拠で、安全性を保証しているのか」を厳しく問うようになる。この変化に対応できない、エビデンスが曖昧な「いわゆる健康食品」は、その存在価値を失い、市場から淘汰されていくだろう。
市場セグメンテーション分析
市場を複数の切り口で分析すると、成長領域と縮小領域が明確に浮かび上がる。
制度区分別
市場の構造変化を最も象徴しているのが、制度区分別の市場規模の変動である。
- 機能性表示食品: 2015年の制度開始以来、市場の成長を牽引する最大のエンジンとなっている。富士経済によれば、2023年の市場規模は前年比19.3%増の6,865億円に達し、2024年も成長を維持し7,350億円に拡大すると予測されている 6。特に、サプリメント形状の機能性表示食品は、健康食品市場全体の23.0%を占めるまでに成長しており、その存在感を増している 7。
- 特定保健用食品(トクホ): かつて保健機能食品市場の主役であったトクホは、機能性表示食品への需要流出により、市場の縮小が続いている。日本健康・栄養食品協会の調査では、2020年度の市場規模は前年度から13.6%の大幅なマイナスとなった 8。富士経済も、2023年、2024年ともに市場縮小が続くと予測している 6。これは、トクホが許可取得までに時間とコストを要するのに対し、機能性表示食品の方が多様なヘルスクレームを表示できる柔軟性を持つためである。
- 栄養機能食品・その他一般食品: ビタミン・ミネラル等の基礎栄養素を補給する栄養機能食品や、法的な機能性表示を持たない「いわゆる健康食品」は、明確なエビデンスを持つ機能性表示食品との競争において、厳しい状況に置かれている。
機能性訴求別
消費者の健康課題を反映し、特定の機能性訴求市場が急成長している。
- 三大成長領域: 「脂肪・コレステロール値改善」「睡眠サポート」「ストレス緩和」が市場を牽引する三大領域である 6。
- 脂肪対策: 生活習慣病予防やダイエットへの関心の高さから、市場の約3割を占める最大のセグメントを形成。大手飲料メーカーによる機能性表示食品の新商品投入も活発である 6。
- 睡眠・ストレス対策: コロナ禍を契機に健康意識が変化し、睡眠の質やメンタルヘルスへの関心が爆発的に高まった。「Yakult1000」の大ヒットが市場を象徴しており、GABAや乳酸菌などを関与成分とする新商品が相次いで投入されている 6。
販売チャネル別
顧客との接点である販売チャネルも、大きな変革期にある。
- 通販チャネル(D2C/ECモール): これまで市場成長を牽引してきたが、近年は新規参入の激化や、薬機法・景表法、アフィリエイト広告等の規制強化により、新規顧客獲得効率が低下し、成長が鈍化する傾向にある 2。しかし、食品D2C市場全体としては、2020年度に前年度比58.1%増の340億円規模に達するなど、依然として重要なチャネルである 11。
- 店頭チャネル(ドラッグストア、CVS等): 新型コロナウイルスの5類移行に伴う人流回復やインバウンド需要の復調により、売上が回復基調にある 2。特にドラッグストアは、専門家(薬剤師・登録販売者)によるカウンセリング機能も担っており、信頼性を重視する消費者にとって重要な購入拠点となっている。
戦略的意味合い(So What?): 経営資源を投下すべき成長領域は、「機能性表示食品」制度を活用した「睡眠」「ストレス」「脂肪対策」の3分野に集中することが合理的である。チャネル戦略においては、D2Cによる顧客データ蓄積とLTV向上を追求しつつ、ドラッグストア等のリアル店舗との連携を通じて信頼性を補完し、幅広い顧客層にリーチするOMO(Online Merges with Offline)戦略の構築が不可欠となる。
業界の主要KPIベンチマーク分析
| KPI | ベンチマーク / 動向 | 戦略的意味合い |
|---|---|---|
| 主要メーカー売上高 | トップはサントリーウエルネス(推定約1,000億円)。DHC(約529億円)、世田谷自然食品(約300億円)が続く 13。 | 業界は一部の勝ち組企業による寡占化が進んでいる。スケールメリットとブランド力が競争の重要な要素であることを示唆。 |
| 営業利益率 | 健康食品はリピート性が高く、一般の食品に比べて利益率が高い傾向にある 15。 | 高い利益率は、研究開発やマーケティングへの再投資を可能にする。持続的な成長のためには、この利益率を維持・向上させる付加価値創造が不可欠。 |
| 機能性表示食品の届出・撤回 | 届出受理件数は増加の一途を辿るが、2025年3月末時点で撤回件数は累計2,708件に上り、届出総数(撤回含む)の約3割を占める 16。 | 「届出受理 ≠ 事業成功」の現実を浮き彫りにしている。制度活用はスタートラインに過ぎず、その後のマーケティング・販売戦略の巧拙が成否を分ける。 |
| チャネル別成長率 | D2Cチャネルは過去に急成長したが、近年は競争激化で鈍化。一方、店頭チャネルが復調 2。 | 単一チャネルへの依存はリスクが高い。顧客接点を最大化するオムニチャネル戦略、特にオンラインとオフラインを融合させたOMO戦略が重要性を増す。 |
| D2C関連KPI(CPA/LTV) | 事業の健全性は の関係性で測られる 17。BASE FOODの月次顧客継続率93.2%は高い水準 18。 | 新規顧客獲得コスト(CPA)の上昇が課題となる中、既存顧客の継続率を高め、LTVを最大化するCRM戦略の重要性がこれまで以上に高まっている。 |
届出撤回件数の多さは、特に重要な示唆を含んでいる。機能性表示食品制度が始まった当初は、「機能性表示」というラベル自体が強力な差別化要因となり、先行者利益を享受できた。しかし、届出件数が9,000件を超え 16、市場に類似製品が溢れる現在、その優位性は薄れている。消費者は単に「〇〇の機能があります」と表示されているだけでは購入せず、他の製品と比較し、ブランドの信頼性や価格、口コミなどを総合的に判断する。結果として、多額の投資をしてエビデンスを揃え、届出を完了させても、計画通りに売れずに「販売見込みなし」として撤回に至るケースが後を絶たない 16。これは、科学的根拠の構築という「製品開発(モノづくり)」の発想だけでは不十分であり、それをいかに顧客価値に転換し、市場に届けるかという「事業開発(コトづくり)」の視点が不可欠であることを物語っている。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
健康食品業界を取り巻くマクロ環境は、複数の要因が複雑に絡み合い、事業機会とリスクの両方を生み出している。PESTLEフレームワークを用いてこれらの要因を体系的に分析する。
政治(Politics)
政府の政策は、健康食品業界にとって強力な追い風と規制強化という逆風の両側面を持つ。最大の追い風は、国民医療費の抑制を目的としたセルフメディケーション推進政策である 19。政府は、軽度な身体の不調は自分で手当てすることを推奨しており、その一環としてスイッチOTC医薬品の拡充と並行し、科学的根拠に基づく保健機能食品の活用を後押ししている。
この政策の中核を担ってきたのが機能性表示食品制度である。しかし、2024年の紅麹問題は、この制度の信頼性を根底から揺るがした。これを受け、消費者庁や厚生労働省は、届出審査の厳格化、製造工程におけるGMP(適正製造規範)の義務化検討、健康被害情報の報告義務化など、事後チェック体制の抜本的な強化に乗り出している 21。
戦略的意味合い(So What?): 政府のセルフメディケーション推進という大方針は変わらないものの、規制強化は確実なトレンドである。これにより、薬事・品質保証部門の重要性が飛躍的に高まる。コンプライアンス体制の不備は、事業停止命令や課徴金といった直接的なダメージだけでなく、企業のレピュテーションを毀損し、ブランド価値を永続的に傷つける最大のリスクとなる。規制対応を単なるコストではなく、顧客からの信頼を勝ち取るための投資と位置づけ、盤石な体制を構築することが不可欠である。
経済(Economy)
グローバル経済の動向は、コスト構造と消費者の購買行動の両面から業界に影響を与える。健康食品の原材料、特に機能性関与成分やビタミン類は、その多くを海外からの輸入に依存している 22。そのため、原材料価格の世界的な高騰や、近年の円安進行は、製造コストを直接的に押し上げる要因となる 23。
一方、消費者サイドでは、インフレーションによる実質的な可処分所得の減少が、健康への投資意欲に影響を与え始めている。消費者は支出に対してより慎重になり、製品の価格弾力性が高まる可能性がある。つまり、価格に見合う価値を明確に感じられなければ、より安価な代替品にスイッチしたり、購入そのものを見送ったりする傾向が強まる。
戦略的意味合い(So What?): サプライチェーンの強靭化とコスト管理能力が、収益性を維持する上での生命線となる。重要原料については、調達先の多様化、長期契約、国内生産への切り替えなどを検討する必要がある。価格戦略においては、単なる値上げは顧客離反を招くリスクが高い。価格を維持・向上させるためには、科学的エビデンス、パーソナライズ化、手厚い顧客サポートといった、価格以上の付加価値を明確に提示し、顧客の納得感を醸成するコミュニケーションが求められる。
社会(Society)
日本の社会構造の変化は、健康食品市場にとって最も根源的かつ強力な成長ドライバーである。高齢化率の上昇と、それに伴う「健康寿命」への関心の高まりは、市場の需要基盤を形成している 26。人々は単に長生きするだけでなく、生涯を通じて活動的で質の高い生活(QOL)を送ることを望んでおり、そのための予防医療やセルフケアへの投資を惜しまない。
ライフスタイルの多様化も新たなニーズを生んでいる。ストレス社会や睡眠不足、食生活の乱れといった現代的な課題は、メンタルヘルスケアや睡眠の質向上、栄養バランス改善を目的とした製品への需要を喚起している。特に若年層においては、美容や健康維持の観点から「腸活」への関心が高く、新たな市場トレンドとなっている 29。
また、健康に関する情報源としてSNSの役割が増大している。これは、製品の認知度を飛躍的に高める機会であると同時に、誤情報や偽情報が拡散しやすく、企業のブランドイメージを損なうリスクもはらんでいる 27。
戦略的意味合い(So What?): 顧客のニーズは、特定の疾患の治療から、より広範なQOLの維持・向上へとシフトしている。ターゲットとする顧客セグメント(例:アクティブシニア、働く女性、Z世代)が抱える具体的なライフスタイル上の課題を深く理解し、それに応えるソリューションを提供することが重要になる。また、SNS時代においては、企業自らが信頼性の高い情報を積極的に発信するオウンドメディア戦略や、専門家と連携した情報発信が、顧客との信頼関係を築く上で不可欠である。
技術(Technology)
テクノロジーの進化、特にバイオテクノロジーとデジタル技術の融合は、業界に破壊的な変化をもたらす最大の要因である。
- バイオインフォマティクス: ゲノム解析や腸内フローラ解析といった技術が、研究室レベルから一般消費者向けサービスへと急速に普及し、低コスト化が進んでいる 30。これにより、個人の遺伝的体質や腸内環境といった、これまでブラックボックスだった生体情報を科学的に把握することが可能になった。
- デジタルヘルス: スマートウォッチやスマートリングなどのウェアラブルデバイスが普及し、活動量、睡眠の質、心拍数といったライフログデータを24時間365日、リアルタイムで取得できるようになった 34。
- 製造技術: 成分の吸収率や体内動態を制御するDDS(ドラッグデリバリーシステム)技術の応用や、品質管理を高度化するGMP(適正製造規範)準拠工場のスマート化が進んでいる。
戦略的意味合い(So What?): これらの技術は、サプリメント事業を「マス向けの製品販売」から「個人に最適化されたソリューション提供」へと変革させる基盤技術である。個人の生体データ(ゲノム、腸内フローラ)とライフログデータ(ウェアラブル)を統合的に解析し、その人に最適な成分と量のサプリメントを、最適なタイミングで提供する「超パーソナライズ化」が現実のものとなりつつある。このデータ駆動型アプローチを導入できるか否かが、未来の競争優位性を決定づける。
これまでサプリメントの効果は、個人の主観的な「体感」に大きく依存しており、それが継続利用の障壁となることも少なくなかった。しかし、テクノロジーはこの課題を解決する可能性を秘めている。例えば、睡眠改善サプリを摂取する顧客がウェアラブルデバイスを装着していれば、摂取前後の睡眠スコアや深い睡眠の時間の変化を客観的なデータとして「可視化」できる。腸活サプリであれば、定期的な腸内フローラ検査によって善玉菌の割合の変化を数値で示すことができる。このように、客観的データによって効果をフィードバックする仕組みは、顧客の製品への信頼を高め、継続利用への強力な動機付けとなる。これは、単に製品を売るのではなく、顧客の健康改善の旅路に寄り添うパートナーとしての役割を担うことを意味し、LTV(顧客生涯価値)の飛躍的な向上に直結する。
法規制(Legal)
健康食品業界は、消費者の健康に直接関わるため、厳格な法規制の下に置かれている。特にマーケティング活動においては、以下の法律が大きな制約となる。
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律): 健康食品は医薬品ではないため、「がんが治る」「糖尿病を予防する」といった、病気の診断、治療、予防を目的とする効能効果の標榜が厳しく禁止されている 40。これに違反した場合、未承認医薬品の広告とみなされ、厳しい罰則の対象となる。
- 景品表示法: 「これを飲むだけで痩せる」といった、製品の効果について、客観的な根拠なく、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる優良誤認表示が禁止されている 21。消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を事業者に求めることができ、根拠が示せない場合は措置命令や課徴金の対象となる。2021年からは薬機法にも課徴金制度が導入され、違反事業者への金銭的ペナルティが強化されている 43。
- 特定商取引法: 特にD2Cで主流のサブスクリプション・モデルにおいて、消費者を保護するための規制が強化されている。2022年6月1日に施行された改正法では、事業者は申込みの最終確認画面において、契約期間、支払総額、解約条件などを消費者が明確に認識できる形で表示することが義務付けられた 44。
戦略的意味合い(So What?): 法規制は事業活動における絶対的な制約条件である。コンプライアンスを遵守することは、リスク回避だけでなく、企業の社会的信頼を構築する上での大前提となる。マーケティング部門と法務・薬事部門の緊密な連携が不可欠であり、クリエイティビティとコンプライアンスを両立させる高度な専門性が求められる。「攻め」のマーケティングを実現するためには、まず「守り」の体制を盤石にすることが必要である。
環境(Environment)
サステナビリティへの配慮は、もはや企業の任意活動(CSR)ではなく、ブランド価値と消費者の購買意思決定を左右する重要な経営課題となっている。
- サステナブルな原料調達: パーム油におけるRSPO認証、海洋資源におけるMSC認証、紙製品におけるFSC認証のように、環境や人権に配慮して生産されたことを示す第三者認証原料の利用がグローバル基準となりつつある。大手食品メーカー各社は、サプライチェーン全体でのトレーサビリティ確保とサステナブル調達目標を掲げ、取り組みを強化している 50。
- 環境配慮型パッケージ: プラスチック使用量削減に向けた、リサイクル素材の利用、バイオマスプラスチックへの切り替え、容器の軽量化などが進められている。
- フードロス問題: AIによる需要予測の精度向上などを通じて、製造から販売に至る過程での廃棄ロス削減への取り組みも重要視されている。
戦略的意味合い(So What?): サステナビリティへの取り組みは、コストではなく、未来の成長への投資である。特に、健康や自然由来といったイメージが重要な健康食品業界において、環境や社会に配慮しない企業姿勢は、消費者の厳しい批判にさらされ、ブランドイメージを大きく損なうリスクがある。サプライチェーンの透明性を確保し、サステナビリティへの取り組みを積極的に情報開示することが、企業の信頼性を高め、意識の高い消費者を惹きつける要因となる。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
マイケル・ポーターの五つの力(Five Forces)フレームワークを用いて、健康食品業界の収益構造と競争の力学を分析する。業界の収益性は、これら五つの力の相互作用によって決定される。
供給者の交渉力
分析: 供給者の交渉力は、扱う原料によって大きく異なり、全体としては「中〜強」と評価できる。
汎用的なビタミンやミネラルといったコモディティ原料の供給者は多数存在し、価格競争に陥りやすいため、その交渉力は弱い。しかし、競争の主戦場が機能性へとシフトする中で、独自の機能性関与成分を持つ原料メーカーの力は著しく増大している。例えば、特定の菌株(例:乳酸菌、ビフィズス菌)や、独自に開発・抽出した植物エキスなど、特許や豊富な臨床試験データによって保護された排他的な原料を持つサプライヤーは、サプリメントメーカーに対して強い価格交渉力を持つ 55。これらの原料を確保できなければ、製品の差別化が困難になるため、サプリメントメーカーは高価格を受け入れざるを得ない場合がある。
また、製造の多くを担う大手OEM/ODMメーカーは、規模の経済や高度な製造技術(GMP準拠など)、薬事申請ノウハウを背景に一定の交渉力を持つ 56。しかし、委託側であるサプリメントメーカーも、複数のOEM/ODMメーカーを比較検討することが可能であるため、その力は一方的なものではない 57。
戦略的意味合い(So What?): 製品の差別化と安定供給を実現するためには、強力な原料メーカーとの関係構築が極めて重要である。単なる買い手としてではなく、共同研究開発や原料の独占供給契約といった、より深く踏み込んだ戦略的パートナーシップを構築することが、模倣困難な競争優位を築くための鍵となる 55。
買い手の交渉力
分析: 買い手、すなわち最終消費者の交渉力は「強い」と評価できる。
最大の要因は、情報の非対称性の解消である。インターネット、SNS、比較サイトの普及により、消費者は製品の成分、機能性に関するエビデンス、価格、使用者による口コミといった情報を、購入前に容易に入手し、比較検討できるようになった。これにより、企業側の情報優位性は崩れ、消費者はより賢明な購買決定を下す力を得た。
特にD2C(Direct to Consumer)モデルが主流の通販チャネルでは、消費者は数クリックでサブスクリプションを解約でき、スイッチングコストは極めて低い。ある製品に満足できなければ、すぐに競合製品に乗り換えることが可能である。
さらに、紅麹問題以降、消費者の健康リテラシーと安全性に対する要求水準はかつてないほど高まっている。価格やブランドイメージだけでなく、「どのような科学的根拠があるのか」「安全性はどのように担保されているのか」といった本質的な価値を厳しく評価する傾向が強まっている。
戦略的意味合い(So What?): 価格競争に陥らないためには、価格以外の価値で顧客を引きつける必要がある。具体的には、①科学的根拠の透明性が高く、分かりやすい情報開示、②GMP準拠工場での製造など、徹底した品質管理による安全性の担保、③パーソナライズされた提案や手厚い相談体制といった優れた顧客体験(CX)の提供、を通じて顧客からの「信頼」を勝ち取ることが不可欠である。これらの取り組みは、顧客ロイヤルティを高め、実質的なスイッチングコストを引き上げる効果を持つ。
新規参入の脅威
分析: 新規参入の脅威は「中」程度であるが、参入者の属性によって脅威のレベルは異なる。
D2Cモデルの普及とデジタルマーケティング手法の確立により、理論上は小資本のスタートアップでも、特定のニッチな課題(例:特定の美容の悩み、アスリート向けの栄養補給)に特化したブランドを立ち上げ、市場に参入することは比較的容易になった。
しかし、市場の主戦場である機能性表示食品分野で本格的に競争するためには、科学的エビデンスの構築(特にヒト臨床試験)に多額の研究開発投資と長い時間が必要となる。これが実質的な参入障壁として機能している。
一方で、異業種からの参入は大きな脅威である。
- 製薬会社: 医薬品開発で培った高い研究開発能力、厳格な品質管理体制、そして消費者からの絶大な「信頼」という無形資産を武器に、エビデンスベースの高品質な製品を投入してきている。
- 大手食品・飲料メーカー: 既存の強力なブランド力、広範な販売網、豊富なマーケティング予算を活かして、市場に参入している 58。
- 化粧品会社: D2C事業のノウハウや美容領域での顧客基盤を活かし、インナービューティーの観点から市場に参入している。
- IT企業: ヘルスケアアプリやデータ解析プラットフォームを起点に、パーソナライズサービス領域への参入を窺っている。
戦略的意味合い(So What?): 既存事業者は、新規参入者が容易に模倣できない障壁を築く必要がある。それは、単一の製品機能だけでなく、長年にわたって築き上げてきたブランドへの信頼、大規模な顧客データベース、そしてそのデータを活用した顧客との深い関係性(エンゲージメント)といった複合的な強みである。
代替品の脅威
分析: 代替品の脅威は「強い」と評価できる。
サプリメントにとっての最大の代替品は、特定の製品ではなく、「バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠」という根本的な生活習慣の改善そのものである。消費者が健康的なライフスタイルを確立できれば、サプリメントへの依存度は低下する。
また、より手軽な代替品も多数存在する。例えば、整腸作用を期待する場合、サプリメントではなく、機能性表示のヨーグルトや乳酸菌飲料を選ぶ消費者は多い。同様に、脂肪吸収を抑える効果は、サプリメントだけでなく、特定保健用食品のお茶でも得られる。このように、飲料や一般食品の形態をとる機能性表示食品は、強力な代替品となっている。
さらに広義には、フィットネスジム、パーソナルトレーニング、オンライン栄養指導、睡眠改善アプリといった、製品ではない「健康関連サービス」も代替品と見なすことができる。
戦略的意味合い(So What?): この強い代替品の脅威は、視点を変えれば最大の事業機会となる。自社を単なる「サプリメント販売会社」と定義するのではなく、「顧客のウェルネス実現を支援するソリューションプロバイダー」と再定義することが求められる。具体的には、代替品である食事指導や運動プログラム、睡眠アドバイスなどを自社のサービスとして取り込み、サプリメントと組み合わせた統合的なソリューションとして提供する。これにより、顧客を自社エコシステム内に囲い込み、代替品への流出を防ぐと同時に、新たな価値と収益源を創造することが可能になる。
業界内の競争
分析: 業界内の競争は「非常に激しい」。
市場には多様なバックグラウンドを持つプレイヤーがひしめき合い、多軸的な競争が繰り広げられている。
- 大手老舗メーカー(例:サントリーウエルネス、DHC): 長年かけて築いたブランド力と大規模な顧客基盤を強みとする。
- 製薬系企業(例:大塚製薬、小林製薬): 科学的根拠に基づく研究開発力と医療・健康領域での信頼性を強みとする。
- D2C新興企業(例:FUJIMI): 特定の顧客セグメントに深く刺さるコンセプトと、SNSなどを駆使したデジタルマーケティング力を強みとする。
機能性表示食品の届出件数の増加は、市場を活性化させた一方で、同質的な機能性を謳う製品の乱立を招いた。「睡眠の質向上」や「ストレス緩和」といった人気カテゴリーでは、多数の製品が同じような成分(GABA、L-テアニン等)で競合しており、価格競争に陥る兆候も見られる。
戦略的意味合い(So What?): 既存の競争軸から抜け出し、新たな戦場で戦うことが求められる。それは、価格や成分の数で競う消耗戦ではなく、「特定の顧客セグメントが抱える、まだ満たされていない深い課題を、誰よりも深く理解し、最も効果的なソリューションを提供する」という顧客中心のアプローチである。例えば、「更年期に悩む40代女性の睡眠の質」や「リモートワークによる運動不足とストレスに悩む30代男性」といった、より解像度の高いターゲット設定を行い、その課題解決に特化した製品・サービスを開発することで、競争の激しいレッドオーシャンから抜け出し、独自のポジションを築くことが可能となる。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析
健康食品業界のサプライチェーンは、「原料調達 → 製造 → 物流 → 販売・顧客」という流れで構成されるが、特に「製造」工程における外部依存度の高さが特徴である。
構造と課題:
- 原料調達: 機能性関与成分の探索・確保から始まる。独自性の高い成分は製品差別化の源泉となるが、その多くは海外からの輸入に依存しており、価格高騰、為替変動、地政学リスクといった外部環境の変化に脆弱である 22。また、消費者のサステナビリティ意識の高まりを受け、原料のトレーサビリティ確保と環境・人権に配慮した調達が求められている 50。
- 製造: 多くのブランド企業は自社工場を持たず、製造をOEM/ODMメーカーに委託している。これは、巨額の設備投資を回避し、多品種少量生産に柔軟に対応できるメリットがある。しかし、この依存構造は以下のようなジレンマを内包する 60。
- 品質管理のリスク: 最終製品の品質は、委託先であるOEMメーカーの製造管理・品質管理体制に大きく依存する。委託先の管理が不十分な場合、自社ブランドの信頼を揺るがす品質問題に直結する。
- 技術・ノウハウの空洞化: 製造を外部に丸投げすることで、自社内に製造技術や生産ノウハウが蓄積されず、長期的な製品開発能力の低下を招く恐れがある。
- 差別化の困難: 人気のあるOEMメーカーは、複数のブランドから同様の製品製造を受託している場合がある。これにより、市場に類似製品が溢れ、ブランド独自の差別化が困難になる可能性がある 62。
- 物流: 特にD2Cモデルにおいては、顧客に直接製品を届ける「ラストワンマイル」の重要性が高い。迅速かつ確実な配送はもちろん、不在時の対応や梱包の質といった細やかなサービスが顧客満足度に影響を与える。
戦略的意味合い(So What?): サプライチェーンは、もはや単なるコストセンターではなく、企業の競争力を左右する戦略的領域である。重要原料については、調達先の複数化や国内サプライヤーの育成、長期契約などを通じて供給網の強靭化(レジリエンス)を図る必要がある。OEM/ODMパートナーに対しては、単なる発注者・受注者という関係を超え、品質基準や製造プロセスに関する情報を密に共有し、改善を共に進める戦略的パートナーシップを構築することが求められる。品質管理体制の定期的な監査や、主要な製造工程におけるブラックボックス化の排除が不可欠である。
バリューチェーン分析
業界の構造変化に伴い、企業が付加価値を生み出す源泉(バリューソース)は、従来の「製造」や「マス販売」から、以下の3つの領域へと明確にシフトしている。
- 研究開発(R&D):
価値の根源は、質の高い科学的エビデンスの構築能力にある。これには、独自の機能性素材の探索・発見、作用機序の解明、そして最終製品を用いたヒト臨床試験(特にランダム化比較試験:RCT)の実施能力が含まれる。質の高いエビデンスは、機能性表示食品としての届出を可能にするだけでなく、製品の信頼性を担保し、価格競争から脱却するための強力な武器となる。この領域への投資を怠る企業は、コモディティ化の波に飲まれることになる。 - マーケティング・ブランディング:
価値創造の核心的課題は、厳格な法規制(薬機法・景品表示法)を遵守しつつ、いかにして製品のベネフィットを顧客に魅力的に伝えるかという点にある。これは、「エビデンスとマーケティングのジレンマ」とも言える。成功している企業は、直接的な効能効果を謳うのではなく、科学的根拠を背景としたストーリーテリングや、顧客のライフスタイルに寄り添うコンテンツマーケティング(オウンドメディア、SNS、インフルエンサー活用)を駆使している。ヤクルト1000の「ストレス緩和・睡眠の質向上」や、iMUSEの「免疫ケア」といった成功事例は、社会的なニーズを捉え、科学的根拠に基づいた分かりやすいメッセージを発信することで、巨大な市場を創出した典型例である 63。 - 顧客関係管理(CRM):
特にD2Cモデルにおいて、事業の収益性を決定づける最重要機能である。価値創造のポイントは、新規顧客獲得コスト(CPA)を抑制し、顧客生涯価値(LTV)を最大化することにある。これを実現するためには、顧客データを収集・分析し、顧客一人ひとりの属性や購買ステージ、悩みに応じて、パーソナライズされたコミュニケーション(メール、LINE、アプリ通知等)を展開する能力が求められる。アップセルやクロスセルの提案、継続利用を促すためのエンゲージメント施策(コミュニティ運営、限定コンテンツ提供など)がLTV向上に直結する 65。
これらの3つの機能は、もはや独立して存在するものではない。D2Cチャネルを通じて得られた膨大な顧客データ(CRM)は、顧客が次に何を求めているのか、既存製品にどのような不満を持っているのかを明らかにする。このインサイトを研究開発部門(R&D)にフィードバックすることで、次の製品開発の成功確率を高めることができる。そして、その新製品の価値は、再びデータに基づいてパーソナライズされたメッセージ(マーケティング)を通じて、最も響くであろう顧客セグメントに届けられる。このように、CRMがR&Dの起点となり、R&Dの成果がマーケティングの武器となるという、データ駆動型の価値創造サイクルを構築し、高速で回転させることが、持続的な競争優位の源泉となる。これは、従来の分断されたバリューチェーンから、顧客を中心に据えた統合的なバリューサイクルへの転換を意味する。
第6章:顧客需要の特性分析
持続可能な成長戦略を策定するためには、市場を構成する顧客を深く理解し、そのインサイトに基づいて価値提案を設計することが不可欠である。
主要な顧客セグメント
健康食品の顧客は、単一の塊ではなく、多様なニーズを持つ複数のセグメントから構成される。効果的な戦略立案のためには、従来の年齢・性別といったデモグラフィック変数に加え、より本質的な変数で市場を切り分ける必要がある。
- 悩み別セグメンテーション:
消費者の購買行動は、解決したい「健康上の悩み(ペイン)」によって直接的に動機づけられる。主要な悩みとしては、「疲労感」「睡眠の質の低下」「精神的ストレス」「体型・内臓脂肪」「肌の悩み(美容)」「関節の不調(ロコモティブシンドローム対策)」「認知機能の維持」などが挙げられる 6。近年の特徴として、日本能率協会総合研究所の調査によれば、若年層を中心に「姿勢の悪さ」を気にする割合が急増しており、新たなニーズとして注目される 29。 - 年齢・ライフステージ別セグメンテーション:
- シニア層: 健康寿命の延伸が最大の関心事であり、ロコモ・サルコペニア対策、認知機能維持、骨の健康、血圧・血糖値管理といった加齢に伴う課題へのニーズが根強い 26。
- ミレニアル・Z世代: ライフパフォーマンスの向上に関心が高く、日々のストレス緩和、睡眠の質向上、集中力維持、美容(肌・髪)などを目的とする。また、SNSでの情報収集に積極的で、製品のコンセプトやブランドの世界観への共感を重視する傾向がある。
- フェムテック関連: 女性特有のライフステージにおける悩みに特化したセグメント。月経前症候群(PMS)、妊活、産後ケア、更年期障害といった課題に対応する製品・サービス市場が急速に拡大している。日本のフェムテック市場は2022年時点で約695億円規模に達しており、今後の成長が期待される 66。
- 健康リテラシー別セグメンテーション:
- ヘルスコンシャス層: 健康への関心が非常に高く、主体的に情報を収集・吟味する層。製品選択において、科学的根拠(特にヒト臨床試験の有無や質)、成分の由来や品質、製造管理体制(GMP準拠など)を重視する。価格が高くても、納得できる価値があれば購入を厭わない。今後のパーソナライズ市場を牽引する主要ターゲットである。
- ライト層: なんとなく健康が気になるが、情報収集にはあまり時間をかけない層。製品選択においては、価格の手頃さ、購入のしやすさ(近所のドラッグストアで買えるか)、口コミや評判、ブランドの知名度などを重視する。機能性表示よりも、分かりやすいパッケージやキャッチコピーに影響されやすい。
顧客のKBF(Key Buying Factor:購買決定要因)
顧客が最終的に製品を購入する際に重視する要因は、セグメントによって優先順位が異なるものの、以下の要素が重要となる。
- 科学的根拠(エビデンス): 特にヘルスコンシャス層にとって最も重要な要因。機能性表示食品であることは最低条件であり、どのような臨床試験で、どのような結果が出ているのか、といった情報の分かりやすさが求められる。
- 安全性・品質: 全てのセグメントに共通する大前提。紅麹問題以降、その重要性はさらに高まった。GMP認定工場での製造、原材料の原産国表示、アレルギー情報の明確化などが信頼につながる。
- ブランドの信頼性: 長年の販売実績を持つ老舗ブランドや、製薬会社系のブランドが持つ「安心感」は、強力なKBFとなる。情報が氾濫する中で、信頼できるブランドを選ぶというショートカットが働きやすい。
- 効果の体感: 科学的根拠と並び、リピート購入を決定づける重要な要因。摂取後に何らかのポジティブな変化を感じられるかどうかが、顧客満足度に直結する。
- 価格: 特にライト層にとっては重要な要因。サブスクリプションモデルにおいては、月々の支払額が継続のハードルとなる場合がある。
- 利便性(飲みやすさ・続けやすさ): 錠剤の大きさ、1日の摂取粒数、味や匂い、パッケージの形状など、日々の摂取におけるストレスの少なさも継続利用を左右する。
顧客の情報収集プロセス
消費者は、複数の情報チャネルを組み合わせて購買意思決定を行っている。
- オンライン: SNS(Instagram, X, YouTube)、Webメディア(比較サイト、専門家ブログ)、インフルエンサーや著名人のレビュー、ECサイトの商品レビュー。特に若年層では、ビジュアルで直感的に理解できるSNSが主要な情報源となっている。
- オフライン: ドラッグストアや薬局の店頭(POP、薬剤師・登録販売者からの推奨)、テレビCMや健康情報番組、友人・家族からの口コミ。特に中高年層や、専門家のアドバイスを重視する層にとっては、オフラインチャネルの影響力が依然として大きい。
戦略的意味合い(So What?): 企業は、ターゲット顧客が主に利用するチャネルを特定し、それぞれのチャネル特性に合わせた情報発信戦略を構築する必要がある。オンラインでは信頼性の高いコンテンツ(専門家監修など)で認知を獲得し、オフラインでは店頭での推奨を得るための専門家向け情報提供(学術情報の提供など)を強化するといった、デジタルとリアルを連携させた複合的なアプローチが求められる。
D2C(サブスクリプション)モデルの継続・解約要因
D2Cモデルの収益性は、顧客にいかに長く継続してもらうか(LTVの最大化)にかかっている。
- 継続要因(LTV向上要因):
- 効果の体感・可視化: 製品の効果を実感できることが最大の継続理由。ウェアラブルデバイスのデータ連携などで効果を客観的に可視化できれば、さらに強力な動機付けとなる。
- 摂取の習慣化支援: アプリによる摂取リマインダー、飲み忘れ防止のための配送サイクル調整機能、ユーザー同士が励まし合うコミュニティの提供などが、習慣化をサポートする。
- パーソナライズされた関係性: 顧客データに基づき、「〇〇様のお悩みには、こちらの製品もおすすめです」といった個別のアプローチを行うことで、「自分を理解してくれている」という特別感を醸成する。
- ロイヤルティプログラム: 継続期間に応じた割引率の向上、限定商品の提供、誕生日プレゼントといった特典が、継続へのインセンティブとなる 65。
- 解約要因(Churn要因):
- 効果が実感できない: 最も多い解約理由。期待した効果が得られないと、支払いを続ける価値を見出せなくなる。
- 価格への不満: 競合製品や代替手段と比較して、価格が高いと感じられる場合。
- 在庫の余剰: 飲み忘れが続き、製品が溜まってしまうことで、一時停止や解約につながる。
- ネガティブな体験: 配送の遅延、問い合わせ対応の不備、ウェブサイトの使いにくさなど、製品以外の顧客体験の悪化。
戦略的意味合い(So What?): D2C事業者は、製品を届けて終わりではなく、顧客が製品を正しく摂取し、効果を実感し、健康的な生活習慣を確立するまでの一連のジャーニーをサポートする視点が不可欠である。解約の兆候(アプリの利用頻度低下、サイトへのアクセス減少など)をデータで早期に検知し、解約に至る前に先回りしてサポート(利用方法の再案内、カウンセリングの提案など)を行うプロアクティブなCRMが、Churn率を低下させ、LTVを最大化する鍵となる。
第7章:業界の内部環境分析
外部環境の変化に対応し、競争優位を築くためには、企業が保有する内部の経営資源(リソース)と組織能力(ケイパビリティ)を客観的に評価することが不可欠である。
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
VRIOフレームワークは、経営資源やケイパビリティが持続的な競争優位(Sustainable Competitive Advantage)の源泉となりうるかを評価する手法である。それは、価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Inimitability)、組織(Organization)の4つの問いで構成される。
健康食品業界において、持続的な競争優位の源泉となりうる経営資源・ケイパビリティは以下の通りである。
- 独自の機能性関与成分と関連特許・臨床データ群
- [V]: 高い付加価値を生み、消費者の購買意欲を刺激する(価値あり)。
- [R]: 他社が保有していない独自成分である(希少性あり)。
- [I]: 特許で法的に保護され、また、質の高い臨床データを再現するには多額の投資と時間が必要なため(模倣困難)。
- [O]: この資源を製品開発、マーケティングに活用する組織体制が整っている場合、持続的な競争優位となる。キリンの「プラズマ乳酸菌」などが典型例である。
- 長年かけて築き上げたブランドの信頼性
- [V]: 安全性への関心が高い市場において、消費者の不安を払拭し、選択を後押しする絶大な価値を持つ(価値あり)。
- [R]: 長年の実績に裏打ちされた信頼は、一部の大手・老舗企業のみが持つ(希少性あり)。
- [I]: 信頼は一朝一夕には構築できず、広告宣伝だけでは獲得できない。地道な品質管理と顧客との誠実なコミュニケーションの積み重ねが必要であり(模倣困難)。
- [O]: 組織全体で品質と顧客満足を最優先する文化が浸透している場合、持続的な競争優位となる。大塚製薬などの製薬会社系ブランドがこの資源を持つ。
- 大規模な優良顧客データベースと高度なCRMノウハウ
- [V]: 既存顧客へのクロスセルやアップセル、LTV向上を通じて安定的な収益基盤となる(価値あり)。
- [R]: D2Cの黎明期から事業を展開し、データを蓄積・活用してきた一部の先進企業のみが保有する(希少性あり)。
- [I]: データベースの構築自体は可能だが、データの質、量、そしてそれを顧客インサイトに転換し、パーソナライズ施策に結びつける運用ノウハウの蓄積には時間がかかり、単純な模倣は困難(模倣困難)。
- [O]: データサイエンティストやCRMマーケターが在籍し、データ分析から施策実行までを迅速に行う組織体制が整っている場合、持続的な競争優位となる。ファンケルがデータ統合基盤「FIT」を核に高度なパーソナライズを実現している例が挙げられる 70。
- 薬事・法務部門の高度なコンプライアンス対応能力
- [V]: 規制違反による事業リスクを最小化し、事業の継続性を担保する(価値あり)。
- [R]: 複雑で変化の速い法規制を深く理解し、かつマーケティング部門と連携して「攻め」の表現を模索できる専門人材は希少(希少性あり)。
- [I]: 専門知識と経験の蓄積が必要であり、外部コンサルタントの活用だけでは代替できない組織能力である(模倣困難)。
- [O]: 経営層がコンプライアンスの重要性を理解し、法務・薬事部門に十分な権限とリソースを与えている場合、持続的な競争優位となる。
人材動向
競争環境の変化は、企業に求められる人材像を根本的に変えつつある。
- 求められる人材像のシフト:
従来のマスマーケティングを担う営業職やマーケターの重要性は維持しつつも、それ以上に以下の専門人材の需要が急増している 71。- 研究開発職: 薬学、農学、栄養学、生命科学などの博士号を持つ、機能性素材の探索や作用機序の解明、臨床試験の設計・実行ができる高度な専門人材。
- 薬事・品質保証の専門家: 薬機法、景品表示法、食品表示法などに精通し、製品開発から広告表現まで、全てのプロセスでコンプライアンスを担保できる人材。
- データサイエンティスト: 顧客の購買データ、ウェブ行動ログ、さらにはゲノムや腸内フローラといった生体データを統計的に解析し、事業に資するインサイトを抽出できる人材。
- D2Cデジタルマーケター: SEO、SNS広告、CRMツールなどを駆使し、CPAを抑えながら新規顧客を獲得し、LTVを最大化させるグロースハック能力を持つ人材。
- 人材獲得競争の激化:
特にデータサイエンティストのようなデジタル人材は、IT業界、コンサルティング業界、金融業界など、あらゆる産業で需要が高く、業界を越えた熾烈な人材獲得競争が繰り広げられている。求人ボックスの統計によれば、データサイエンティストの平均年収は約629万円から647万円、スキルや経験によっては1,000万円を超えることも珍しくない 75。これは、従来の食品業界の給与水準を大きく上回る可能性がある。
戦略的意味合い(So What?): 企業は、自社の人材ポートフォリオを戦略的に見直し、未来の競争に必要な専門人材の獲得・育成計画を策定・実行しなければならない。競争力のある報酬パッケージの提示はもちろんのこと、企業のビジョンへの共感、挑戦的な仕事内容、成長機会、柔軟な働き方といった非金銭的な魅力を含んだEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)を構築し、優秀な人材を惹きつけ、リテンションすることが死活問題となる。
労働生産性
事業の収益性を評価する上で、主要な投資領域における生産性(ROI)の評価が重要となる。
- R&D投資(特に臨床試験)のROI:
ヒト臨床試験には、数千万円から数億円単位の多額の投資が必要となる。そのROIを評価する際には、単にその試験結果を用いて開発された製品単体の売上・利益を見るだけでは不十分である。①そのエビデンスがもたらすブランド価値全体の向上への貢献、②開発された技術や知見が他の製品へ横展開できる可能性、③強力なエビデンスによる参入障壁の構築効果といった、長期的・多面的な視点から総合的に評価する必要がある。 - D2CにおけるマーケティングROI:
D2C事業のマーケティングROIは、 という指標でシンプルかつ厳密に評価される。この比率をいかにして3倍以上に保つか(一般的にが健全性の目安とされる)が、事業の成長と収益性を左右する。AIを活用した広告ターゲティングの高度化によるCPAの低減や、CRM施策の精緻化によるLTVの向上が、生産性向上のための主要なレバーとなる。
第8章:主要トレンドと未来予測
健康食品業界は、テクノロジーの進化と社会ニーズの深化によって、新たな成長フェーズへと移行しつつある。今後5年から10年の業界地図を塗り替える可能性のある主要なメガトレンドを以下に詳述する。
パーソナライズ化の本格化:診断ベースの科学的アプローチへ
これまでもWebアンケートなどに基づいた簡易なパーソナライズは存在したが、今後はより科学的・客観的なデータに基づいた「超パーソナライズ化」が本格化する。
- トレンド: 尿、血液、唾液などを用いた生体検査、低価格化が進むゲノム(遺伝子)検査 77、そして健康状態との関連が次々と明らかになっている腸内フローラ(マイクロバイオーム)解析 30といった、個人の生体データを直接分析するサービスが拡大している。これらの診断結果に基づき、一人ひとりの体質や健康状態に最適化されたサプリメントを提供するビジネスモデルが主流となる。
- 市場規模: 富士経済によると、パーソナライズフード市場は2024年に105億円(前年比47.9%増)と、まだ市場全体に占める割合は小さいものの、極めて高い成長率を示している 80。
- 未来予測: 将来的には、これらの静的な生体データ(ゲノムなど)と、ウェアラブルデバイスから得られる動的なライフログデータ(睡眠、活動量など)をAIが統合解析し、リアルタイムでその日の体調に合わせたサプリメントの配合や摂取タイミングを推奨する、より高度なサービスへと進化する。これにより、サプリメントは「万人に向けた製品」から「個人のための動的なソリューション」へとその本質を変える。
フェムテックとエイジテック:特定セグメントの課題解決市場の拡大
マス市場から、特定のデモグラフィック(人口動態)が抱える固有の健康課題に深く寄り添う市場へと細分化・深化が進んでいる。
- フェムテック(Femtech): 女性(Female)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。月経、妊活・不妊、妊娠・産後ケア、更年期といった、女性特有のライフステージに伴う健康課題をテクノロジーで解決する製品・サービスを指す。サプリメントもこの領域で重要な役割を担う。矢野経済研究所によると、日本のフェムケア&フェムテック市場は2022年に約695億円に達し、成長を続けている 67。
- エイジテック(Agetech): 高齢者(Age)とテクノロジーを組み合わせた造語。高齢者のQOL(生活の質)向上を目指し、自立支援、健康維持、社会的孤立の解消などを支援する。健康食品領域では、加齢による筋力低下(サルコペニア)や運動機能低下(ロコモティブシンドローム)、認知機能の維持といった課題に対応する製品が中心となる。
- 未来予測: これらの市場は、単に製品を提供するだけでなく、専門家によるオンラインカウンセリング、ユーザー同士のコミュニティ、関連情報メディアなどを組み合わせたエコシステム型ビジネスへと発展する可能性が高い。特定の課題を持つ顧客とのエンゲージメントが深いため、高いLTVが期待できる。
スリープテックとメンタルヘルス:現代社会の普遍的課題への対応
睡眠の質の低下と精神的ストレスは、年齢や性別を問わず、現代社会に生きる多くの人々が抱える普遍的な課題であり、巨大な市場を形成している。
- スリープテック(Sleeptech): 睡眠(Sleep)とテクノロジーを組み合わせ、睡眠状態を可視化し、改善を支援する製品・サービス。ウェアラブルデバイスによる睡眠トラッキングが一般的になり、そのデータに基づいたソリューションへの需要が高まっている。矢野経済研究所の予測では、国内スリープテック市場は2023年の95億円から、2027年には160億円へと拡大する見込みである 81。
- メンタルヘルスケア食品: ストレス緩和、リラックス、記憶力・集中力の維持などを訴求する食品市場も急成長している。富士経済は、メンタル・脳機能ケア食品市場が2023年の実績から2030年には61.1%増の5,698億円に達すると予測している 83。GABAやL-テアニン、乳酸菌などを関与成分とする機能性表示食品が市場を牽引している 6。
- 未来予測: スリープテックで取得した個人の睡眠データと、メンタルヘルスに関する問診データをAIが解析し、その日の状態に最適なサプリメントやアロマ、音楽、食事メニューなどを統合的にレコメンドするパーソナライズド・ウェルネス・プラットフォームが登場するだろう。
チャネルの融合:D2Cとリアル店舗の連携(OMO)
販売チャネルは、オンラインとオフラインが分断された状態から、顧客体験を軸にシームレスに融合するOMO(Online Merges with Offline)へと進化する。
- トレンド: D2Cブランドが、オンラインでの顧客接点の限界を補い、ブランド体験や信頼性を向上させる目的で、ポップアップストアや常設店をオープンする動きが活発化している。逆に、ドラッグストアなどのリアル店舗も、オンラインでの顧客データ活用やECサイトへの送客を強化している。ファンケルは、ECと店舗の会員IDを統合したOMOアプリを導入し、チャネルを横断する顧客のLTVが特に高いことをデータで証明し、相互送客を強化している 70。
- 未来予測: 今後は、クリニックや調剤薬局が、サプリメントの新たなOMO拠点として重要性を増す。オンラインでゲノム検査や血液検査を受け、その結果を基に医師や薬剤師といった専門家がオフラインでカウンセリングを行い、パーソナライズされたサプリメントを推奨・販売する、といった医療連携モデルが普及する。これにより、サプリメントは「自己判断で選ぶもの」から「専門家と共に選ぶもの」へと位置づけが変わり、信頼性と付加価値が飛躍的に向上する。
第9章:AIの影響とインパクト(特別章)
人工知能(AI)は、健康食品業界の個別の業務プロセスを効率化するツールに留まらない。それは、バリューチェーン全体をデータで垂直統合し、ビジネスモデルそのものを「マス生産・マスマーケティング」から「個人最適化ソリューション」へと根底から変革する、破壊的かつ創造的な力である。AIの導入と活用能力が、未来の企業の生死を分けると言っても過言ではない。
AIは、研究開発(R&D)から製造、マーケティング、そして最終的な顧客体験(CX)まで、バリューチェーンのあらゆる段階に浸透し、それぞれを高度化する。しかし、その真のインパクトは、これらのプロセスがAIを介してデータで繋がり、一つの連続的なループを形成することにある。例えば、AIが顧客のライフログデータから未来の健康リスクを予測し(CX)、そのリスクを低減するための最適な成分配合をAIがシミュレーションし(R&D)、その個人向け製品の製造指示をAIが自動で行い(製造)、摂取後の生体データの変化をAIがモニタリングして、次の処方や生活習慣アドバイスに反映させる(CX)。この高速学習サイクルこそが、AIが駆動する次世代のパーソナル・ウェルネス・ソリューション事業の核心である。
研究開発(R&D)
- 新規機能性素材の探索: 創薬分野で先行しているように、AIは膨大な数の学術論文、特許情報、化合物データベースを解析し、人間では見つけ出すことが困難な、新たな機能性を持つ素材候補や、既存成分の相乗効果をもたらす組み合わせを高速で探索する 84。これにより、R&Dの初期段階における時間とコストを劇的に削減し、イノベーションの成功確率を高める。
- 臨床試験デザインの最適化と効率化: AIは、過去の臨床試験データや電子カルテデータなどを解析し、試験の成功確率が最も高くなるような被験者群の特性(年齢、性別、遺伝的背景など)を特定する 85。また、最適な試験期間や評価項目をシミュレーションすることで、臨床試験全体のデザインを最適化し、開発期間の短縮とコスト削減に貢献する 86。
- 処方(成分配合)の最適化シミュレーション: 個人のゲノム情報、健康診断結果、ライフスタイルといったデータに基づき、その人にとって最も効果的で、かつ副作用リスクの少ない成分の組み合わせと配合量を、AIがシミュレーションによって導き出す。
製造・サプライチェーン
- 需要予測の高度化と在庫最適化: AIは、過去の販売実績(POSデータ)だけでなく、天候、季節、SNSのトレンド、イベント情報、競合の販促活動といった多様な外部データをリアルタイムで取り込み、高精度な需要予測を行う 89。これにより、欠品による販売機会の損失と、過剰在庫による廃棄ロス(フードロス)という二律背反の課題を同時に解決し、サプライチェーン全体の効率を最大化する 92。
- スマートファクトリーにおける品質管理の自動化: GMP準拠工場において、画像認識AIが製造ライン上の製品(錠剤やカプセル)を監視し、形状不良や異物混入をリアルタイムで検知・排除する。これにより、品質管理の精度と効率が飛躍的に向上し、人的ミスを削減する。キユーピーは、AIを活用した原料検査装置を開発し、処理能力を2倍に向上させている 94。
マーケティング・販売
- 超パーソナライズド・レコメンデーション: AIは、顧客一人ひとりの購買履歴、ウェブサイト上の行動(閲覧ページ、滞在時間)、アプリの利用状況、さらには連携された健康データ(睡眠スコアなど)を統合的に分析し、その顧客が今まさに必要としているであろう商品や健康情報を、最適なタイミングとチャネル(メール、LINE、プッシュ通知など)で推奨する 97。
- デジタル広告の自動最適化: AIは、広告キャンペーンの成果をリアルタイムで分析し、ターゲットオーディエンス、広告クリエイティブ(画像、キャッチコピー)、配信時間、入札価格などを自動で最適化する。これにより、広告費用対効果(ROAS)を最大化し、CPAを低減させる。
- 薬機法・景品表示法チェックの自動化: AI(特に自然言語処理技術)を活用した広告表現の自動校閲ツールが多数登場している 99。これらのツールは、広告文やLP(ランディングページ)のテキストを解析し、薬機法や景品表示法に抵触するリスクのある表現を瞬時に検出し、代替表現を提案する。これにより、コンプライアンス遵守とマーケティングのスピードを両立させることが可能になる。
顧客体験(CX)
- AIチャットボットによる24時間健康・栄養相談: AIチャットボットが、顧客からの食事や栄養に関する質問に24時間365日対応する。個人の健康目標やアレルギー情報などを記憶し、「今日の夕食は何を食べたら良いか」「このサプリメントはいつ飲むのが効果的か」といった具体的な質問に対して、パーソナライズされた回答を即座に提供する 104。
- ウェアラブルデータと連携したプロアクティブな介入: ウェアラブルデバイスが検知したデータ(例:睡眠の質の低下、ストレスレベルの上昇)をトリガーとして、AIが「今夜はリラックス効果のあるサプリメントの摂取をおすすめします」といった、先回りのアドバイスや摂取リマインドを自動で送信する。これにより、顧客が不調を自覚する前からの予防的アプローチが可能となる。
- 食事画像解析による栄養指導: 顧客がスマートフォンのカメラで食事の写真を撮るだけで、AIが画像解析を行い、メニューを特定し、カロリーや栄養素を自動で算出する。そのデータに基づき、「タンパク質が不足していますね。次の食事では鶏肉や大豆製品を取り入れましょう」といった具体的な栄養指導を行う。
| バリューチェーン | AI活用事例 | 期待されるインパクト |
|---|---|---|
| 研究開発 (R&D) | 論文・特許データ解析による新規機能性素材の探索 | 開発期間の短縮、イノベーションの加速、R&Dコストの削減 |
| 臨床試験デザインの最適化、被験者リクルーティングの効率化 | 開発成功確率の向上、臨床試験コストの削減 | |
| 製造・SCM | 需要予測の高度化による生産・在庫計画の最適化 | 廃棄ロス(フードロス)の削減、欠品による機会損失の防止 |
| 画像認識AIによる製造ラインでの品質管理自動化 | 品質向上、人件費削減、ヒューマンエラーの防止 | |
| マーケティング | 顧客データ分析に基づくパーソナライズド・レコメンデーション | CVR(転換率)の向上、アップセル・クロスセルの促進 |
| 広告表現の薬機法・景品表示法コンプライアンス自動チェック | 法規制違反リスクの低減、マーケティング施策の迅速化 | |
| 顧客体験 (CX) | AIチャットボットによる24時間の健康・栄養相談 | 顧客満足度の向上、問い合わせ対応コストの削減 |
| ウェアラブルデータ連携によるプロアクティブな健康アドバイス | 顧客エンゲージメントの深化、製品の継続利用率(LTV)向上 |
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
健康食品市場は、異なる出自と強みを持つ多様なプレイヤーが競合する複雑な戦場である。ここでは、主要なプレイヤーを類型化し、それぞれの戦略、強み・弱み、そして業界のメガトレンドであるD2C/パーソナライズ化への取り組みを比較分析する。
大手食品・飲料系:サントリーウエルネス、アサヒグループ食品、味の素など
- 強み:
- 圧倒的なブランド力と信頼性: 長年にわたり消費者向け製品を提供してきたことによる、高い知名度と安心感。
- 豊富な資金力と研究開発基盤: 長期的な視点での大規模な研究開発投資が可能。
- 広範な販売網と顧客基盤: スーパーやコンビニなどの既存チャネルと、長年の通販事業で培った大規模な顧客データベース。
- 弱み:
- 巨大組織ゆえの意思決定の遅さ: 新興企業に比べて、市場の速い変化への対応が遅れる可能性がある。
- 既存事業とのカニバリゼーション: 新規の健康食品が、既存の飲料や食品事業と競合する可能性。
- 戦略・取り組み:
- 製品(モノ)の提供に留まらず、顧客の健康的なライフスタイル全体をサポートする「ソリューション」提供への転換を志向している。
- サントリーウエルネスは、健康行動アプリ「Comado」を開発・提供。フィットネス動画や健康情報コンテンツを通じて顧客との日常的な接点を増やし、エンゲージメントを深化させている。アプリ利用状況に応じてプッシュ通知やコンテンツを出し分けるなど、パーソナライズ施策にも着手しており、顧客を「ヘルス」から「ウエルネス」(身体的・精神的・社会的に良好な状態)へと導く伴走者となることを目指している 109。
製薬会社系:大塚製薬、小林製薬、武田コンシューマーヘルスケアなど
- 強み:
- 科学的根拠(エビデンス)への絶対的な強み: 医薬品開発で培われた厳格な研究開発プロセスと、質の高い臨床試験を実施する能力。
- 消費者からの絶大な信頼: 「製薬会社が作っている」という事実が、何よりの品質保証となる。紅麹問題以降、この強みはさらに際立っている。
- 医療機関とのネットワーク: 医師や薬剤師といった専門家からの推奨を得やすい。
- 弱み:
- マーケティングの柔軟性: 医薬品のプロモーションに慣れているため、規制の厳しい健康食品領域での消費者向けマーケティングに課題を抱える場合がある。
- 価格: 高い品質と研究開発コストを反映し、価格が高めに設定されがちである。
- 戦略・取り組み:
- 大塚製薬は、「ニュートラシューティカルズ(Nutraceuticals)」という独自の事業コンセプトを掲げ、科学的根拠に基づいた独創的な製品開発を推進している。水分補給、栄養、女性の健康、大豆(Soylution)といった領域で、既存の市場にない新たな価値を創造することを目指している 113。研究開発への継続的な大規模投資がその戦略を支えている。
化粧品・化学系:ファンケル、富士フイルムなど
- 強み:
- D2C事業の長い歴史とノウハウ: 通販チャネルでの顧客との直接的な関係構築に長けている。
- 膨大な顧客データと高度なCRM: 長年のD2C事業で蓄積した顧客データを活用した、精緻なパーソナライズマーケティング能力。
- 美容領域での専門性: インナービューティー(体の内側からの美)という文脈で、化粧品とサプリメントのシナジーを創出しやすい。
- 弱み:
- ブランドイメージの偏り: 「美容」のイメージが強いため、シニア男性など、他の顧客セグメントへのアプローチに課題が生じる可能性がある。
- 戦略・取り組み:
- ファンケルは、データ活用を競争優位の核に据えている。2021年に刷新したデータ統合基盤「FIT」を活用し、顧客の悩みや行動を深く分析。そのインサイトに基づき、MA(マーケティングオートメーション)による160以上の自動レコメンド施策や、休眠顧客へのパーソナライズドDMなどを展開している。また、ECと店舗のデータを統合したOMOアプリを軸に、チャネル横断でのLTV最大化に成功している 70。
D2C新興企業:(特定の急成長企業:FUJIMI、VITANOTEなど)
- 強み:
- デジタルネイティブな発想と実行力: 顧客課題の発見から製品開発、マーケティングまで、デジタルを前提とした迅速なPDCAサイクル。
- 特定の顧客課題への特化: マス市場ではなく、特定のペルソナが抱える深い悩みに特化することで、熱狂的なファンを獲得。
- ユニークなビジネスモデル: 診断サービスとサブスクリプションを組み合わせた、新しい顧客体験の提供。
- 弱み:
- ブランド認知度と信頼性の低さ: 大手に比べて知名度が低く、信頼性を獲得するまでに時間がかかる。
- 資金力と研究開発能力の限界: 大規模な臨床試験など、エビデンスレベルを高度化するための投資に限界がある。
- 戦略・取り組み:
- パーソナライズ化を事業の核に据え、大手との差別化を図っている。
- FUJIMIは、オンラインの肌診断を起点に、2,000億通り以上の組み合わせから個人に最適なサプリメントやプロテインを提案するビジネスモデルを構築。診断という「体験」を提供することで、飽和したサプリメント市場に新たな価値を創造した 120。
- VITANOTEは、郵送型の尿検査キットを用いて、体内の栄養素の過不足を科学的に分析。その客観的なデータに基づき、mg単位で栄養素を配合したフルパーソナライズサプリメントを提供する、より高度な科学的アプローチを実践している 97。
| プレイヤー類型 | 強み | 弱み | D2C/パーソナライズ化への取り組み |
|---|---|---|---|
| 大手食品・飲料系 | ブランド力、資金力、顧客基盤 | 組織の硬直性、意思決定の遅さ | 製品販売から健康習慣サポートへの「ソリューション」転換を志向(例:健康アプリ「Comado」) |
| 製薬会社系 | 科学的根拠(R&D力)、信頼性 | 消費者向けマーケティングの柔軟性 | 「ニュートラシューティカルズ」コンセプトに基づく、エビデンスドリブンな製品開発をグローバルに展開 |
| 化粧品・化学系 | D2Cノウハウ、顧客データ、CRM | ブランドイメージの偏り(美容中心) | データ統合基盤を核とした高度なパーソナライズ戦略とOMO連携によるLTV最大化(例:ファンケル「FIT」) |
| D2C新興企業 | デジタルマーケティング力、スピード | ブランド認知度、資金力、R&D力 | 診断サービス(Web診断、尿検査等)とサブスクリプションを組み合わせたパーソナライズモデルが事業の核 |
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、日本の健康食品市場で持続的な成長を遂げるための戦略的な意味合いを導き出し、具体的な推奨事項を提言する。
今後5~10年で、勝者と敗者を分ける決定的な要因
今後の健康食品業界における勝者と敗者を分けるのは、エビデンス構築力、マーケティング力、パーソナライズ化技術といった個別の能力の優劣ではない。それらを有機的に結合させ、顧客価値へと転換する「統合的な事業システム」を構築できるか否かである。決定的な要因は、以下の3つの能力を高いレベルで融合させ、高速で学習・改善サイクルを回せる組織能力に集約される。
- 科学的信頼性の構築能力(Evidence Engine):
質の高いヒト臨床試験に裏打ちされた、独自性の高い科学的エビデンスを継続的に創出する力。これは、製品の付加価値と信頼性の根幹であり、価格競争から脱却するための絶対条件である。 - データ駆動型パーソナライズ能力(Data & AI Engine):
D2Cチャネルやウェアラブルデバイス、各種検査を通じて得られる多様な顧客データを統合・解析し、AIを活用して一人ひとりに最適化された製品・情報・サービスを提供する力。これにより、顧客エンゲージメントとLTVを最大化する。 - 規制下での顧客エンゲージメント能力(Engagement Engine):
薬機法・景表法といった厳しい規制を遵守しつつ、科学的な事実を顧客に分かりやすく伝え、共感を呼び、長期的な信頼関係を構築する力。製品の機能的価値だけでなく、ブランドが提供する情緒的価値や世界観が問われる。
これら3つのエンジンが連動しない事業は、必ず行き詰まる。エビデンスなきマーケティングは信頼を失い、データなきパーソナライズは自己満足に終わり、エンゲージメントなき製品は容易に代替される。勝者は、これら三位一体のシステムを構築し、顧客中心の価値創造サイクルを最も速く回した企業となる。
捉えるべき機会と備えるべき脅威
本分析から導出される、主要な機会(Opportunities)と脅威(Threats)は以下の通りである。
- 機会(Opportunities):
- 高成長セグメントへの集中: 睡眠、メンタルヘルス、フェムテック、エイジテックといった、明確な顧客課題が存在し、高い成長が見込まれる市場への参入・深耕。
- 「ソリューション」への事業転換: サプリメント単体ではなく、診断サービス、食事・運動プログラム、専門家によるカウンセリングなどを組み合わせた統合ソリューションを提供することによる、新たな価値創造と顧客の囲い込み。
- AI活用によるバリューチェーン革新: R&Dの効率化から、超パーソナライズドマーケティング、顧客体験の向上まで、AIを戦略的に活用することによる、全社的な生産性向上と競争優位性の確立。
- 信頼性への回帰: 紅麹問題後の市場において、高い品質管理体制と透明性の高い情報開示を徹底することで、他社との差別化を図り、「信頼できるブランド」としてのポジションを確立する好機。
- 脅威(Threats):
- 異業種からの強力な新規参入: 製薬、大手食品、ITといった、豊富なリソースと異なる強みを持つプレイヤーの参入による、既存の競争ルールの破壊。
- 規制強化とコンプライアンスリスク: 機能性表示食品制度の見直しや広告表示規制の厳格化に伴う、事業運営コストの増大と法的リスクの高まり。
- 安全性問題による業界全体の信頼失墜: 一社の不祥事が、業界全体のイメージを悪化させ、市場全体の縮小につながるレピュテーションリスク。
- テクノロジーへの適応遅延: ゲノム解析、AI、デジタルヘルスといった破壊的技術への対応が遅れることで、競合から取り残され、時代遅れとなるリスク。
戦略的オプションの提示と評価
上記の分析を踏まえ、取りうる主要な戦略的オプションを3つ提示し、それぞれのメリット・デメリットを評価する。
| 戦略オプション | 内容 | メリット | デメリット | 成功確率 |
|---|---|---|---|---|
| A: 総合ウェルネス・プラットフォーマー戦略 | 全方位の製品ラインナップに加え、アプリ、診断、各種健康サービスを統合したプラットフォームを構築。M&Aやアライアンスを多用。 | ・広範な顧客層をカバーし、巨大な市場シェアを狙える。 ・データ収集の規模が大きく、ネットワーク効果を期待できる。 | ・莫大な投資が必要。 ・経営資源が分散し、各領域で専門企業に劣後する「器用貧乏」に陥るリスク。 ・組織の複雑化。 | 中 |
| B: 特定領域特化型スペシャリスト戦略 | 「睡眠」「認知機能」など、自社の強みを活かせる特定領域に経営資源を集中。その領域でNo.1のエビデンスとソリューションを構築。 | ・深い専門性により高い付加価値と顧客ロイヤルティを築ける。 ・リソース集中による高い投資効率。 ・「〇〇といえばこのブランド」という強力な認知を確立できる。 | ・特定市場の成長が鈍化した場合のリスク。 ・事業ポートフォリオの多様性が低い。 | 高 |
| C: B2B2C(原料・ソリューション提供)戦略 | 自社で最終製品を販売するだけでなく、開発した独自素材やパーソナライズ・ソリューション(診断エンジン等)を他社(健康食品メーカー、クリニック等)に提供。 | ・R&D投資を多角的に収益化できる。 ・自社での大規模なマーケティング投資を抑制できる。 ・業界内での影響力を高められる。 | ・最終顧客との接点が希薄になり、ブランド構築が困難。 ・パートナー企業の戦略に収益が左右される。 | 中 |
最終提言:特定領域特化型スペシャリスト戦略の推進
提言: この競争の激しい市場で生き残り、高収益な成長を遂げるために、オプションB:「特定領域特化型スペシャリスト戦略」を中核戦略として採用することを強く推奨する。
論拠:
競争が激化し、顧客ニーズが多様化・深化する成熟市場においては、全方位を狙う「総合メーカー」戦略は経営資源を分散させ、どの領域でも中途半端なポジションに終わるリスクが極めて高い。また、B2B2C戦略は収益源の多様化には有効だが、企業の根幹であるべき最終顧客との関係構築とブランド資産の蓄積を疎かにする危険性がある。
したがって、最も勝算が高いのは、自社のコアコンピタンス(既存の技術シーズやブランド資産)を最大限に活かせる一つまたは少数の特定領域を選び抜き、そこにR&D、マーケティング、人材といった全ての経営資源を集中投下することである。その領域において、「エビデンスの質と量」「ソリューションの深さ」「顧客からの信頼」の全てで競合を圧倒するNo.1ポジションを確立する。これにより、価格競争から脱却し、高い収益性と持続的な成長を実現する強固な事業基盤を築くことができる。
実行に向けたアクションプランの概要
Phase 1: 基盤構築フェーズ(初年度)
- 集中領域の決定: 市場の魅力度(成長性、収益性)と自社の適合度(技術的強み、ブランド親和性)を評価し、ターゲットとする特定領域(例:「40代女性の更年期に伴う睡眠課題」)を1〜2つに絞り込む。
- R&D体制の再構築: 決定した領域に特化した研究開発チームを組成。最高レベルのエビデンス構築(大規模RCTの計画など)に着手。
- インサイト深掘り: ターゲット顧客のペルソナとカスタマージャーニーを徹底的に分析し、未充足ニーズを特定。
- KPI: 集中領域の決定、R&D計画の策定完了。
Phase 2: 事業立ち上げフェーズ(2〜3年目)
- 基幹製品の上市: 集中領域において、最高レベルのエビデンスを持つフラッグシップ製品を開発し、市場に投入。
- D2Cチャネルの構築: 製品販売と顧客データ収集の拠点として、D2Cサイトを立ち上げ。初期顧客獲得のためのデジタルマーケティングを展開。
- ソリューションの初期提供: 製品提供に加え、専門家によるコラムや簡易診断ツールなど、関連する情報・サービスを提供開始。
- KPI: D2C会員数、新規顧客獲得単価(CPA)、初期リピート率。
Phase 3: エコシステム拡大フェーズ(4〜5年目)
- パーソナライズ・サービスの展開: 蓄積した顧客データを活用し、よりパーソナライズされた製品(配合調整など)やアドバイスを提供。
- テクノロジー連携: ウェアラブルデバイスや検査キットとの連携を開始し、効果の可視化とプロアクティブな介入を実現。
- OMO戦略の展開: ターゲット顧客との親和性が高いリアルチャネル(例:婦人科クリニック、調剤薬局、フィットネスジム)との提携を開始し、専門家による推奨やカウンセリングの場を設ける。
- KPI: 顧客生涯価値(LTV)、解約率(Churn Rate)、ネット・プロモーター・スコア(NPS)、OMOチャネル経由の売上。
このアクションプランを通じて、単なるサプリメントメーカーから、特定領域におけるリーディング・ソリューションプロバイダーへと変貌を遂げ、持続的な成長を実現することができるだろう。
第12章:付録
引用文献
- 国内サプリ市場、10年ぶり縮小か 富士経済調べ、24年「顧客離脱・消費マインド低下」, https://wellness-news.co.jp/posts/20241031-5/
- サプリメントの国内市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24100
- 2024年度の健康食品市場は1.2%減の8945億円、紅麹問題が響く。2029年度には9000億円規模に再拡大へ | ネットショップ担当者フォーラム, https://netshop.impress.co.jp/node/13759
- 【矢野経済研究所プレスリリース】健康食品市場に関する調査を実施(2025年)~2024年度の健康 … – エキサイト, https://www.excite.co.jp/news/article/Dreamnews_0000317480/
- 健康食品市場に関する調査を実施(2025年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3760
- 機能性表示食品、特定保健用食品などの国内市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24019&la=ja
- 美容と健康を支える機能性表示食品サプリメント、健康食品の中で初めての2割超え、矢野経済研究所が明らかに | ヒフコNEWS, https://biyouhifuko.com/news/japan/6113/
- 変調したトクホ市場 日健栄協調べ 20年度 – 健康産業界の総合専門紙・健康産業流通新聞, https://www.him-news.com/news/view/5210
- 2022年 乳酸菌関連商品の市場分析調査―「免疫力向上」「ストレス緩和」「睡眠サポート」商品が伸長、 機能性の多様化が進む, https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220210566
- 健康志向食品(明らか食品、ドリンク類)の国内市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=22132&view_type=2
- 食品D2Cサービス市場は340億円、58%増の見込み【2020年度】, https://netshop.impress.co.jp/node/8659
- 矢野経済研究所 20年食品D2C市場、約340億円(前年度比58.1%増) | Healthcare News, https://www.this.ne.jp/news/6436/
- AIが予測する健康食品メーカー 業界|2030年市場規模推移と主要企業ランキング – xenoBrain, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/health-food
- 【2024年最新】健康食品ECの売上高ランキング – リピスト | EC/D2Cサイト構築システム, https://rpst.jp/blog/marketing_analysis/15109/
- 健康食品ECを成功させるマーケティング戦略7選|市場動向・成功事例など, https://ecmarketing.co.jp/contents/archives/3642_nya
- 機能性表示食品届出の動向|ウェルネスフード・ワールド第119回 …, https://global-nutrition.co.jp/blog/2025-04-21/
- D2Cサブスクの成功事例7選|失敗しないための共通点と始め方をプロが徹底解説, https://stock-sun.com/column/how-to-success-d2c-subscription/
- 260%成長を遂げたD2Cの代表格「ベースフード」がIPO -創業の背景や資金調達、重視するメトリクスを解説- – Yoii Fuel, https://yoii.jp/posts/d2c-basefood
- セルフメディケーション~薬と健康食品~, https://www.kenpo.gr.jp/kracie/contents/hoken/dayori/pdf/244.pdf?1760486400051
- 【第2回】セルフケアの中で保健機能食品を利用するために, https://hfnet.nibn.go.jp/column/detail4693/
- 【広告表現付き!】健康食品広告の薬機法、景表法等の法律ルール …, https://www.89ji.com/lab/healthy-food/healthfood_advertising.html
- サプリメント(健康食品)製造の費用を理解しよう!原価率をおさえて高収益のサプリをつくるには, https://sapuri-standard.co.jp/blog/understanding-the-cost-of-making-supplements/
- Ⅲ 我が国の食料供給への影響 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_zyukyu_doko_m/pdf/syokuryo_jyukyu_1506no4.pdf
- 円安が食品輸出に与える影響やメリットとは?販路拡大のポイントも紹介 – JFEX, https://www.jfex.jp/hub/ja-jp/blog/article10.html
- 【10月からの値上げ】その原因とは? – 植物性原料 リンクフード株式会社|プロテイン・プラントベース・食物繊維, https://www.link-food.com/archives/3833
- 【2025年最新】健康食品ECで成功する秘訣:市場動向から次世代戦略まで徹底解説, https://odem.toyoshinyaku.co.jp/article/detail237/
- 健康食品市場の半世紀, https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n2504jo1.pdf
- 日本における健康食品の成長性, https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202402/202402p.pdf
- 健康ニーズ基本調査2024 | 生活者調査レポート・リサーチデータ …, https://www.jmar.biz/report2/health2024/
- 2025年サプリメント市場のトレンド予測!消費者が求める – Wellness Life, https://wellnesslife.co.jp/column/supplementmarket_trends2025/
- 日本腸活サプリメント市場規模 2033年 – IMARC Group, https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-gut-health-supplements-market
- 2030年まで年平均成長率20%で411億米ドルに達する腸内細菌叢市場の成長予測, https://presswalker.jp/press/62600
- ゲノム解析関連サービス・装置の国内市場を調査 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=23111&view_type=2&la=en
- デジタルヘルスケアで自分にも地球にも優しく – ロスゼロ, https://losszero.jp/blogs/column/col_406
- ヘルスケア事業はデータから生まれる その理由とは? – TIS株式会社, https://www.tis.jp/special/healthcare_data/blog_ps_003/
- a-14 : 食・栄養素のパーソナライズ技術 | 未来コンセプトペディア | D4DR株式会社, https://www.d4dr.jp/fcpedia/a/a-14/
- PHRサービス進化中。食事、運動、睡眠…スマホ記録で健康管理, https://journal.meti.go.jp/p/29192/
- TechDoctor(テックドクター)|デジタルバイオマーカーを開発しデータによる遠隔サポート医療を実現, https://www.technology-doctor.com/
- ウェアラブルデバイスを活用した「食品ヒト試験サポート …, https://www.technology-doctor.com/news/20251014
- 薬機法と健康食品とは?表現範囲やNG表現・言い換え例について解説 – デジタルアイデンティティ, https://digitalidentity.co.jp/blog/pmd-act/foodstuff.html
- 【2025年最新】薬機法改正のポイント!広告・パッケージの規制とペナルティー完全ガイド, https://outsense.jp/eco7/
- 1 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 制 定 平成 25 年 12 月 24 日 – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms214_221205_01.pdf
- 【2021年8月施行】薬機法改正で何が変わった?広告表現で気をつけたいこと – 【公式】Sienca, https://sienca.jp/blog/advertising/charge-of-pmd-act/
- D2Cビジネスを開始したい!|BtoBとの違いや法律上のポイントを解説, https://ec-lawyer.com/609/
- 特定商取引法の改正でEC事業者が注意すべきポイントとは? – FID, https://marketing.f-i-d.jp/blogs/revision-of-the-specified-commercial-transactions-law/
- 5分でわかる改正特商法! 定期購入やサブスクなど通販(D2C)事業 …, https://netshop.impress.co.jp/node/9750
- 特定商取引法改正によるサブスク規制導入と申込み画面表示規制の強化 – クラウドサイン, https://www.cloudsign.jp/media/20210422-tokusyouhou2021kaisei/
- 全てのEC事業者様へのお知らせ – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/assets/consumer_transaction_cms101_220628_15.pdf
- ECやサブスク事業者は必読!特定商取引法の規制とクーリングオフ制度を弁護士が解説, https://it-bengosi.com/website-law/tokusho-saishin/
- 持続可能な調達への取り組み-サステナビリティ – ハウス食品グループ本社, https://housefoods-group.com/sustainability/otorihikisaki/index.html
- 持続可能な調達 – サステナビリティレポート – セブン‐イレブン, https://sustainability.sej.co.jp/esgp/environment/sustainabilityprocurement/
- 持続可能な原材料調達の推進 | 森永製菓グループのサステナビリティ, https://www.morinaga.co.jp/company/sustainability/valuechain/procurement.html
- 持続可能な調達 | 日清食品グループ, https://www.nissin.com/jp/company/sustainability/environment/procurement/
- サステナブル調達 サントリーグループのサステナビリティ サントリー, https://www.suntory.co.jp/company/csr/soc_procurement/
- 健康食品・サプリの原料メーカーおすすめ6選一覧 | OEMウォーク, https://oem.uocc.co.jp/archives/855
- 食品OEM徹底解説:定義から市場動向、主要企業、収益性(粗利率)分析まで – note, https://note.com/grino_yu/n/n37a543223d31
- 食品OEMの費用相場はどのくらい?見積もりの確認・交渉ポイントも紹介 – ドリンク ジャパン, https://www.drinkjapan.jp/ja-jp/blog/article_063.html
- 【2025年最新】健康食品・サプリメント業界のM&A・売却・買収事例30選, https://masouken.com/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AEM&A
- 健康食品・サプリメント業界のM&A・売却・買収!業界動向・相場 …, https://masouken.com/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AEM&A
- 健康食品・サプリメントの製造におけるOEMとODM:違いと選択の …, https://sunao-seiyaku.com/manufacturing-and-sales/difference-between-oem-and-odm/
- サプリメント(健康食品)のODMとは何か?メリット・デメリット、依頼する際の流れを解説 – 備前化成, https://www.bizen-c.co.jp/blog/odm.html
- OEMとは?コスメ・スキンケア・健康食品の成功事例と注意点 – ecforce, https://ec-force.com/blog/product_no33
- 健康食品・サプリメントのマーケティング成功事例14選, https://yakujihou-marketing.net/archives/4991
- 健康食品マーケティングを成功させる戦略と最新事例まとめ | 通販支援ノート – ニッセンLINX, https://www.nissen.biz/support/successful_strategies_for_marketing_health_foods/
- 【成功事例5選】健康食品のD2Cマーケティングで成功するポイントと注意点 – W2, https://www.w2solution.co.jp/useful_info_ec/d2c-healthy-food/
- 経済産業省のフェムテック推進について, https://tjad.takarajimasha.tkj.jp/detail/post_pdf/19346/
- 日本と世界のフェムテックの市場規模|おすすめアイテムも紹介! – PIARY(ピアリー), https://www.piary.jp/femtech/articles/a0096/
- スマートウォッチやスマートリングなど
ウェアラブル/ヘルスケア機器、システム・サービスの国内市場を調査 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24040 - フェムテックの規模とシェア|予測レポート 2025-2034 – Global Market Insights, https://www.gminsights.com/ja/industry-analysis/femtech-market
- 急伸長する「ファンケルのEC」マーケティング戦略とは …, https://ecact.jp/fancl-ec-marketing/
- 食品業界の就活で押さえておくべき業界知識|アピールのコツも伝授, https://careerpark-agent.jp/column/29798
- 食品業界に興味がある学生必見!就活の動向、選考対策、求められる人材像, https://job.career-tasu.jp/guide/study/041/
- 求める人物像, https://www.i-note.jp/housefoods/recruit/recruitment/personality.html
- 求める人材像|日本栄養食品 |札幌・食品卸売総合商社|学校給食・病院・高齢者施設, https://www.nes-co.jp/recruit/desire/
- データサイエンティストの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ) – 求人ボックス, https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6
- データサイエンティストの年収ってどれくらい?高年収の理由、未経験からでも高年収を狙えるのか解説 – キカガク, https://www.kikagaku.co.jp/career-blog/data-scientist-salary/
- 日本の遺伝子検査市場は2033年までに21億4720万 … – アットプレス, https://www.atpress.ne.jp/news/5151051
- 日本の遺伝子検査市場は2033年までに21億4720万米ドル規模に成長、年平均成長率10.17%で推移 | NEWSCAST, https://newscast.jp/news/5151051
- 日本におけるDNA検査市場規模、2033年までの動向 – IMARC Group, https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-dna-testing-market
- H・Bフーズ(サプリメントや健康志向食品)の国内市場を総括 …, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25041
- スリープテック市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3750
- 2027年のスリープテック市場規模は160億円へ – note, https://note.com/yri_lifescience/n/n83bc770fac08
- メンタル・脳機能ケア食品市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24068
- 人工知能を使用して食生活の向上を! 世界各国の最新AI事情 – AGRI JOURNAL, https://agrijournal.jp/renewableenergy/54450/
- 製薬・創薬業界のAI活用事例18選!約45%開発コスト削減の理由は? | AI Front Trend, https://ai-front-trend.jp/pharmaceutical-ai/
- 【製薬業界のAI活用事例10選】創薬から臨床開発、患者支援、サプライチェーン, https://www.bit2byte.co.jp/blog/1360
- 医療業界に広がる AI|製薬業界での活用例と導入のヒントを紹介 – インターフェックス, https://www.interphex.jp/hub/ja-jp/blog/article_064.html
- 製薬業界のAI活用事例17選!創薬・研究の効率化・自動化を実現【2025年最新版】 – AI Market, https://ai-market.jp/industry/ai-medical-medicine/
- 食品業界のAI活用|需要予測から在庫管理までの最適化事例 – newji, https://newji.ai/supplier/manufacturing-industry/ai-applications-in-the-food-industry-optimization-case-studies-from-demand-forecasting-to-inventory-management/
- AIの需要予測で食品ロス削減へ 需給最適化プラットフォーム – NEC Corporation, https://jpn.nec.com/vci/optimization/index.html
- 食品業界のAI活用方法を、事例8点を交えてご紹介 – MatrixFlow, https://www.matrixflow.net/case-study/78/
- 在庫管理のキホン AIによる需要予測で実現する在庫最適化|ビジネスブログ – ソフトバンク, https://www.softbank.jp/business/content/blog/202312/inventory-control
- AIによる在庫最適化で業務効率UP!在庫管理における4つの導入事例, https://wa2.ai/ai-news/zaiko-kanri-ai-dounyu-jirei-mondaiten
- 【AI導入事例】食品工場の製造ラインにて原材料の不良品検知にAIを活用(キユーピー株式会社) | DOORS DX – ブレインパッド, https://www.brainpad.co.jp/doors/contents/02_ai_case_study_kewpie/
- AIを活用した原料検査装置をグループに展開 | ニュースリリース | キユーピー, https://www.kewpie.com/newsrelease/2019/1152/
- キユーピー、AI活用に成功した4つのワケ。食品の原料検査の事例から考える – Ledge.ai, https://ledge.ai/articles/kewpie-inspection
- サプリメント・健康食品D2Cの成功事例11選!成功の秘訣も紹介 – Shopi Lab(ショピラボ), https://shopi-lab.com/know-how/17742/
- パーソナライズの時代 個別化栄養学で企業が挑む新たなマーケティング戦略 – Wellness Life, https://wellnesslife.co.jp/column/personalized/
- アフィリエイト広告に役立つ薬機法・広告表現チェックツール13選 – デジマ部 – 株式会社シード, https://www.seedinc.jp/column/affiliate/ad-compliance-checker/
- 薬機法チェックを生成AIで効率化 広告違反リスクの可視化と改善提案 – AlgoMagazine, https://magazine.algomatic.jp/streamlining-pharmaceutical-affairs-law-checks-with-generative-ai-visualization-of-advertising-violation-risks
- 広告表現チェックツールを徹底比較!口コミや料金を紹介, https://www.shopowner-support.net/customer_attraction_information/online/affiliate/advertising-expression/
- 薬機法チェックツールおすすめ11選まとめ! | Dr.開業ナビ | AI時代のクリニック経営・集患戦略の完全ガイド – 株式会社Medrock, https://medrock.co.jp/navi/yakkiho-checktool/
- 薬機法チェックツールの比較10選。違いや選び方は? | アスピック, https://www.aspicjapan.org/asu/article/32175
- 「カロミル」にてChat GPTを活用した「AI食事相談チャット(β)」がスタート – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000018894.html
- AIが栄養管理!食生活の改善を提案する人工知能の仕組みとは? – AIsmiley, https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-the-mechanism-of-artificial-intelligence-that-proposes-improvement-of-eating-habits/
- AIダイエット術!ChatGPTをダイエットコーチにして-10kgになった事例まとめ! | WEEL, https://weel.co.jp/media/innovator/chatgpt-diet/
- 生成AIを活用した栄養指導業務の効率化|古澤久志 – note, https://note.com/hwww/n/n23ac28d667df
- 生成AIで管理栄養士の職場環境向上!悩み解決への第一歩 – チャプロAI, https://chapro.jp/account/17949/article/2285
- ユーザーを深く理解し、アプリ利用の習慣化につなげる施策を発想 …, https://cxclip.karte.io/friends/story/comado/
- サントリーウエルネス株式会社様 | 事例&ナレッジ | ドコモマーケティングソリューション, https://ssw.web.docomo.ne.jp/marketing/article/20200811/
- 本格展開1年で60万以上のDL達成! 顧客向け健康行動促進アプリ「Comado」の挑戦 【3人のキーパーソンが語るサントリーウエルネスの理念と戦略 <第2回>】 – ECのミカタ, https://ecnomikata.com/original_news/45927/
- 人生100年時代にサントリーウエルネスが挑むマーケティング―1400人と対話し顧客の多様性を捉える (1/3) – MarkeZine(マーケジン), https://markezine.jp/article/detail/45003
- ニュートラシューティカルズ関連事業|大塚製薬, https://www.otsuka.co.jp/nutraceutical/
- 【大塚製薬の魅力】転職・就活で知っておくべき社風と研究開発の最前線 – note, https://note.com/tisobro/n/n3e6223289fe0
- 大塚ホールディングス株式会社の会社概要・業績・中期経営計画を解説, https://www.provej.jp/column/st/otsuka-holdings/
- 第4 次中期経営計画(2024 年~2028 年度)の策定について, https://www.otsuka.com/jp/ir/management/pdf/plan01.pdf
- Kirin Investor Day 2020 「ファンケルの成長戦略」, https://pdf.irpocket.com/C2503/vTQq/q03S/SLhm.pdf
- 通販システムと研究力で市場を開拓するファンケルのポテンシャル – ECzine, https://eczine.jp/article/detail/12013
- 「一時の売上よりお客様の利益」ファンケルの長期的ブランド戦略とは – MarkeZine(マーケジン), https://markezine.jp/article/detail/44177
- 6つのD2C国内事例。ブランド成長のキーワードは「モノづくり …, https://ec-force.com/blog/d2c_no42
- パーソナライズ商品の成功事例15選|D2Cビジネスのポイントやツールも紹介 – ヨミトル, https://shindancloud.com/trend/1477
- 体調管理・栄養改善ならVITANOTE(ビタノート), https://vitanote.jp/
- DeepResearch追加指示.txt
- サプリメント国内市場2.3%増の1兆651億円【富士経済】 – ヘルスケアワークスデザイン, https://hoitto-hc.com/2113/
- サプリメントと健康志向食品の国内市場(H・Bフーズ市場)を総括
予防意識の高まりで活況を呈する | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=23052&view_type=2 - 2025年版 健康食品の市場実態と展望 ~市場調査編~ 矢野経済研究所 – イプロス ものづくり, https://mono.ipros.com/product/detail/2000354944/
- 2025年版 健康食品の市場実態と展望 ~市場調査編 – ヤノデータバンク(YDB), https://www.ydb.jp/market_reports/C66122300
- 健康食品業界の動向 – 〜「健康」をキーワードに成長する市場の戦略方向性, https://www.smbc.co.jp/hojin/report/investigationlecture/resources/pdf/3_00_CRSDReport080.pdf
- 第1章 全国・九州地域における機能性食品の現状と課題, https://www.kyushu.meti.go.jp/report/2003/200324_1_1.pdf
- 2018年 健康と食 ~機能性表示食品制度とヘスルケアフーズ市場に関して – アグリウェブ, https://www.agriweb.jp/column/439.html
- 健康食品とは?~区分と市場と機能性表示制度~ | 株式会社オルトメディコ, https://www.orthomedico.jp/column/221129-2.html
- 機能性表示食品の24年市場規模 富士経済 – ウェルネスデイリーニュース, https://wellness-news.co.jp/posts/250304-4/
- 減り続ける届出件数、撤回新たに41件 【機能性表示食品届出DB更新】新規は既存中心に16件, https://wellness-news.co.jp/posts/20241010-4/
- 健康寿命延伸への貢献 | サステナビリティ – キユーピー, https://www.kewpie.com/sustainability/dietary-lifestyle/health/
- 薬機法における健康食品と化粧品の広告規制について | ベンチャースタートアップ弁護士の部屋, https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/basic-law-of-the-company/yakkiho-cosmetics.php
- 【食品業界】海外のサステナブルな取り組み事例や動向を紹介 – サステナビリティ ハブ, https://www.sustainability-hub.jp/column/food-abroard/
- 急成長するパーソナライズサプリ市場|成功事例とパーソナライズ手法を解説 – ヨミトル, https://shindancloud.com/trend/1661/
- 【事例紹介】パーソナライズサプリメントで成功したD2Cブランド12選 | 記事を探す – ハンソクエスト, https://hansokuest.jp/article/detail/58
- 【2025年最新】D2Cブランドの成功事例18選|近年の傾向や共通する特徴を徹底解説します!, https://www.future-shop.jp/magazine/d2c-brand-casestudy
- 日本のパーソナライズD2Cブランド15選!データを駆使し、使い続けるほどに精度向上で快適な顧客体験に – SMMLab, https://smmlab.jp/article/d2c-personalized-brands/
- POCT市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3628
- 2024年版 遺伝子検査・解析に関する市場動向調査 – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C66105100
- 富士経済 ゲノム解析関連サービス・装置の国内市場を調査 – LINK-J, https://www.link-j.org/bulletinboard/post-6946.html
- 健康食品業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説 – CINC Capital, https://cinc-capital.co.jp/column/industry/health-food-ma
- 健康食品OEMの会社11社 注目ランキング【2025年】| Metoree, https://metoree.com/categories/9545/
- 青汁 OEM商品開発-市場シェア拡大!消費者ニーズに応える差別化戦略とは?, https://odem.toyoshinyaku.co.jp/article/detail244/
- 日本の購買行動調査―購買行動から読み解く生活者の類型 | PwC Japanグループ, https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/consumer-insights-survey2025.html
- 健康意識と食品消費行動に関する消費者アンケート調査を実施(2022年) – 矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3064
- 売上拡大のチャンス!異業種からでもOEMを活用すればサプリ市場に参入可能。 – SUNAO製薬, https://sunao-seiyaku.com/manufacturing-and-sales/new-entrant-in-supplement-sales/
- 異業種からの新規 飲食店・食品販売事業 立ち上げ支援事例 – フードコンサルタント 岩田都, https://www.shokusaigetu.com/sinkitatiage/
- 事例 02 | 健康食品のOEM/ODM【アピ株式会社】, https://api-odm.com/case02
- VRIO分析とは何か? バーニー教授が考案、「企業内」の経営資源の強みと弱みを知る, https://www.sbbit.jp/article/cont1/30339
- VRIO分析とは?基礎からメリット、手順、活用事例までを解説 | 記事一覧 | 法人のお客さま, https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/18231/
- データサイエンティストの年収はいくら?仕事内容も解説 – コエテコ, https://coeteco.jp/articles/10736
- データサイエンティストの平均年収を紹介! 今後の展望も解説します, https://freelance-hub.jp/column/detail/211/
- D2Cとは?ブランド戦略からメリット、事例までわかりやすく解説!, https://siki.ntp-k.co.jp/column/detail21/
- シンセカイテクノロジーズ、トリコ社の「FUJIMI パーソナライズプロテイン」にてDiscordとLINEオープンチャットを活用したユーザーコミュニティ構築・運営支援を実施 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000115234.html
- データだけで顧客は見えない―パーソナライズビューティケア「FUJIMI」に学ぶ顧客インサイトの捉え方 (1/3) – MarkeZine(マーケジン), https://markezine.jp/article/detail/45509
- VitaNote FOR / パーソナライズサプリ VitaNote FORの公式商品情報 – アットコスメ, https://www.cosme.net/products/10224060/
- 尿検査して作るパーソナライズサプリメント VitaNote FOR Base Supplement(ビタノート・フォー・ベースサプリメント), https://vitanote.jp/service/vitanote-for-base-supplement
- サービス – 株式会社ユカシカド, https://www.yukashikado.co.jp/service/
- 世界初、AIが全ての市販食品の健康への影響を判定「FoodScore」 – 共同通信PRワイヤー, https://kyodonewsprwire.jp/release/202101260183
- 全世代のウェルビーイングを実現するエイジテック | PwC Japanグループ, https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/agetech.html
- フェムケア&フェムテック(消費財・サービス)市場に関する調査を実施(2024年), https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3666
- 睡眠ビジネス市場がいま注目される理由とは? | エステプロ・ラボ, https://www.esthepro-labo.com/column/inner-beauty/sleepbusiness2410/
- スリープテックとは?睡眠の質を上げる方法・睡眠の重要性・市場規模・サービス例を紹介, https://spaceshipearth.jp/sleeptech/
- 脳の健康補助食品市場規模、シェア|レポート[2032] – Fortune Business Insights, https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E8%84%B3%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%B8%82%E5%A0%B4-107767
- 国内消費者におけるメンタルヘルスに関する調査 | デロイト トーマツ グループ – Deloitte, https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/consumer-products/research/mental-health-survey.html