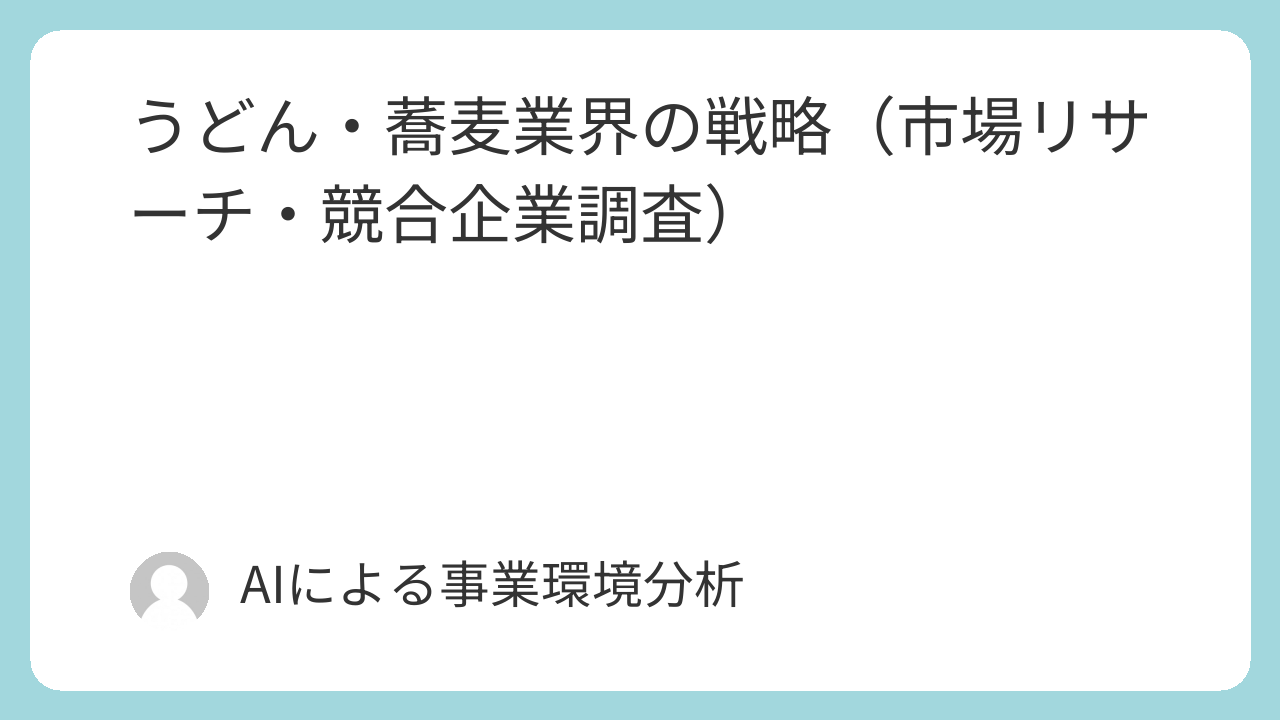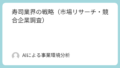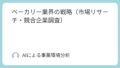伝統と革新の岐路:AIと効率化が再定義する「うどん・蕎麦」業界の持続的成長戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、日本の外食産業において成熟市場と見なされる「うどん屋・蕎麦屋」業界における新たな事業戦略(新規参入、既存事業の変革、M&Aなど)の策定を目的とする。現在、当業界は①原材料費・エネルギーコストの高騰、②深刻な人手不足と人件費の上昇、③消費者のニーズの二極化、④デジタル化・自動化の遅れという、複合的かつ構造的な課題に直面している。これらの課題を乗り越え、持続的な成長を達成するための戦略的選択肢を、データに基づき網羅的に分析・提言する。
調査範囲は、セルフ式うどん・蕎麦チェーン(例:丸亀製麺、はなまるうどん)、フルサービス型の専門店(老舗、手打ち)、立ち食いそば・うどん店、そして近年急速に存在感を増しているデリバリー・テイクアウト(中食)市場、さらには冷凍麺や乾麺などの内食市場までを包括的に対象とする。
最も重要な結論
本調査分析から導き出された最も重要な結論は以下の通りである。
- 市場の二極化と「中価格帯」の空洞化: うどん・蕎麦市場は、「低価格・効率追求型」と「高付加価値・体験型」へと明確に二極化が進行している。コスト上昇圧力と、消費者の「安さ・速さ」または「本物志向・体験価値」へのニーズの先鋭化により、両者の中間に位置する特徴の曖昧なプレイヤーは競争優位を失い、淘汰される「ミドルマーケットの空洞化」が不可逆的に加速している。
- テクノロジー導入が勝敗を分ける戦略的武器へ: AIによる需要予測や調理・配膳ロボットの活用は、もはや単なるコスト削減策ではない。これらは、業界特有の労働集約的なビジネスモデルを根底から覆し、収益性とスケーラビリティを両立させるための戦略的武器である。特に、飲食店の経営を長年圧迫してきたFLコスト(食材費+人件費)の構造的課題を解決する鍵となる。
- 「職人技」の価値の再定義と工業化: 伝統的な手打ち技術や秘伝の出汁は、高付加価値戦略の核となる一方で、その属人性が成長の最大のボトルネックとなっている。今後は、熟練技術をセンサーやカメラでデータ化し、AIを活用したトレーニングや品質管理に応用することで、「職人技の工業化」を実現できる企業が、品質を維持しながらスケールメリットを享受し、持続的な競争優位を築く。
主要な推奨事項
上記の結論に基づき、当業界で成功を収めるために、以下の4つの戦略的行動を推奨する。
- 戦略的ポジショニングの明確化: 自社の経営資源と強みを踏まえ、「徹底的な効率化によるコストリーダーシップ」か、「独自の体験価値提供による差別化」のいずれかの戦略に資源を集中投下する。中途半端なポジショニングは最も危険である。
- DXへの積極投資によるオペレーション変革: AI需要予測を全社的に導入し、食品ロスと機会損失を最小化する。同時に、調理・配膳ロボットを積極的に活用して労働集約型モデルから脱却し、FLコスト比率を構造的に改善する。
- 高付加価値セグメントへの戦略的参入: 国産そば粉や希少な出汁原料、インバウンド観光客を惹きつける体験価値(例:そば打ち体験併設店舗)を組み合わせた、高単価・高利益率の新規ブランドを立ち上げる、もしくは既存ブランドをリポジショニングする。
- M&Aによる成長加速: 後継者不足に悩む地域の優良個人店(ブランド力、独自の技術を持つ)を戦略的に買収する。獲得した無形資産に、自社の資本力とマネジメントシステムを注入し、再生・多店舗展開を図ることで、非連続的な成長を実現する。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本のうどん・蕎麦市場規模の推移と今後の予測
日本のうどん・蕎麦市場は、外食、中食、内食の各領域で異なる動向を示しており、消費者の食生活の変化を映し出している。
外食市場:
日本フードサービス協会の推計によると、外食における「そば・うどん店」の市場規模は、2019年に1兆3,144億円に達していた。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、2020年には前年比73%の水準まで大幅に縮小した 1。その後、社会経済活動の正常化に伴い市場は回復基調に転じ、2022年には前年比16.0%増を記録している 2。矢野経済研究所の調査では、2023年度の国内主要外食市場規模がコロナ禍前を上回る水準まで回復したと報告されており、うどん・蕎麦業態も同様の回復トレンドにあると推察される 4。しかし、長期的な人口減少や他業態との競争激化を考慮すると、今後の外食市場の成長は緩やか、もしくは横ばいで推移すると予測される。
中食・内食市場:
一方で、中食・内食市場は顕著な成長を遂げている。日本惣菜協会によると、スーパーやコンビニで販売される調理麺(チルド麺)市場は成長が著しく、2024年には1兆863億円(前年比7.8%増)に達する見込みである。この市場は過去10年間で約2倍に拡大しており、消費者のライフスタイルの変化を捉えて力強く成長している 5。
同様に、冷凍麺市場も拡大している。特に冷凍うどんは、技術革新による品質向上を背景に、家庭用・業務用ともに需要が伸長している 7。グローバル市場においても、冷凍うどん市場は2024年に18億9,000万米ドル規模と評価され、2030年にかけて年平均成長率(CAGR)7.36%での成長が予測されている 8。
これらのデータは、食の主戦場が伝統的な「外食」から、利便性と品質を両立した「中食・内食」へと構造的にシフトしていることを示唆している。高齢化や単身世帯の増加 9、女性の社会進出といった社会構造の変化が、調理の手間を省きたいというニーズを高め、高品質な調理麺や冷凍麺市場の成長を後押ししている。したがって、外食事業者は店内飲食の価値向上に取り組むと同時に、この成長する中食・内食市場にいかにリーチするかという視点を持つことが、今後の成長戦略において不可欠となる。
市場セグメンテーション分析
うどん・蕎麦市場は、業態、立地、価格帯によって多様なセグメントに分類される。
- 業態別:
- セルフ式チェーン: 丸亀製麺やはなまるうどんに代表される業態。手軽さと価格、トッピングの自由度が支持され、市場の主要プレイヤーとなっている。
- フルサービス専門店: 地域の老舗や手打ちを売りにする個人経営店が中心。品質、職人技、店舗の雰囲気を価値の源泉とする。厚生労働省の調査によれば、全国のそば・うどん店の事業所数29,137カ所のうち、従業者規模「1~4人」が52.6%を占めており、小規模な専門店が多数を占める構造となっている 11。
- 立ち食い: ゆで太郎、富士そば、小諸そばなど、主に駅ナカやオフィス街で「速さ」と「安さ」を求めるビジネスマン層の需要を捉えている。
- デリバリー・テイクアウト専門店: コロナ禍以降に増加した業態。中食需要の受け皿として機能している。
- 立地別:
厚生労働省の調査によると、立地は「商業及び住宅地区」が全体の71%強を占め、地域住民の日常的な利用が中心であることがわかる。その他、「工場・オフィス街」「郊外の幹線道路沿い」「駅舎内・駅前」など、ターゲット顧客層に応じた多様な立地で展開されている 12。 - 価格帯別:
価格帯による二極化が鮮明である。厚生労働省の調査では、「そば専門店」の平均食事単価が1,165.4円であるのに対し、「立ち食いそば・うどん店」は260.0円(※原文ママ、恐らく誤記で500円前後の意図と推察)と低い水準にあり、高価格帯と低価格帯に需要が分かれていることがデータで裏付けられている 11。
主要な市場成長ドライバーと阻害要因
市場成長ドライバー:
- 健康志向の高まり: そばに含まれるルチンなどの栄養素への関心や、グルテンフリー食品としての十割そばの価値が見直されている 13。また、減塩つゆや、野菜・海藻・きのこ類、肉・卵といったタンパク質源をトッピングすることで栄養バランスを整えたいという需要も顕在化している 14。
- インバウンド需要の回復: 観光庁の調査によると、訪日外国人観光客が訪日前に最も期待していることは「日本食を食べること」(69.7%)であり、その消費額は飲食費と食関連の買い物代を合わせて約1.4兆円に上る 17。特にそばは、「ざるそば」や「天ぷらそば」を中心に人気が高く、大きな成長機会となっている 18。
- 中食・デリバリー需要の定着: 前述の通り、調理麺や冷凍麺市場の拡大は、うどん・蕎麦という食カテゴリー全体の市場規模を押し上げる強力なドライバーとなっている。
市場阻害要因:
- 人口減少と他業態との競争激化: 日本の総人口減少というマクロトレンドに加え、ラーメン、パスタ、牛丼といった強力な競合との間で顧客の奪い合いが常に発生している 20。
- 原材料・エネルギーコストの高騰: 小麦粉、そば粉、出汁原料、食用油、光熱費といったあらゆるコストが上昇しており、飲食店の利益構造を著しく圧迫している 1。
- 事業所数の減少と二極化の進行: 市場規模全体は微増または横ばい傾向にあるものの、総務省の統計では「そば・うどん店」の事業所数は平成18年から28年にかけて約14.7%減少している 11。これは、一部の勝ち組(大手チェーンなど)が市場シェアを拡大する一方で、多数の個人経営店が競争に敗れ廃業に追い込まれている「弱肉強食」のサバイバル市場であることを示唆している 22。
業界の主要KPIベンチマーク分析
うどん・蕎麦業界における戦略を策定する上で、業態ごとの収益構造を理解することは極めて重要である。各業態の主要KPIを比較分析することで、それぞれのビジネスモデルの特性と課題が明確になる。
| 指標 | セルフ式チェーン | フルサービス専門店 | 立ち食い店 | 業界平均/目安 | データソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均客単価 | 500~800円 (推定) | 1,165.4円 | 500円前後 (推定) | 956.7円 | 11 |
| 原価率 | 25~30% | 30~35% | 30%前後 | 29~36.9% | 23 |
| FLコスト比率 | 50~55% (推定) | 60%前後 | 55~60% (推定) | 50~60% | 23 |
| 営業利益率 | 10%前後 (推定) | 5%前後 | 5%前後 | 6% | 23 |
- FLコスト: 食材費(Food Cost)と人件費(Labor Cost)の合計。飲食店の経営における最重要管理指標の一つ。売上高に占める比率で管理され、一般的に50~60%が目安とされる 23。
この表から、各業態のビジネスモデルの違いが読み取れる。
- セルフ式チェーンは、低い客単価を効率的なオペレーションによる低いFLコスト比率と高い回転率でカバーし、比較的高い営業利益率を目指すモデルである。
- フルサービス専門店は、高い客単価を設定できるものの、こだわりの食材による原価率の上昇や、手厚い接客に伴う人件費の増加により、FLコスト比率は高くなる傾向にある。結果として営業利益率はセルフ式に劣る可能性がある。
- 立ち食い店は、低い客単価と比較的高い原価率を、極限まで効率化したオペレーション(省スペース、少人数)による人件費抑制と、圧倒的な回転率で補うビジネスモデルである。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
うどん・蕎麦業界を取り巻くマクロ環境は、政治、経済、社会、技術、法規制、環境の各側面から多大な影響を受けている。これらの要因をPESTLEフレームワークで分析する。
政治(Politics)
- 農産物の輸入政策: うどんの主原料である小麦は、その多くを輸入に依存しており、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」に基づき政府が輸入を管理している 26。政府が製粉会社などに売り渡す価格(政府売渡価格)が、国内の小麦粉価格の基準となるため、政府の価格決定は業界のコスト構造に直接的な影響を与える。直近では価格が引き下げられたものの、依然として高水準で推移しており、経営の圧迫要因となっている 27。
- 国産農産物の振興策: 政府は食料自給率向上の観点から、国産農産物の生産を支援している。特にそばは、水田からの転作作物として「水田活用の直接支払交付金」の対象となったり、「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」によって生産コストと販売価格の差額が補填されたりしており、国産そば粉の安定供給に寄与している 30。
- 食品表示法: 消費者の食の安全・安心への関心の高まりを受け、食品表示に関する規制は厳格化している。特にそばは、重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があるため、「特定原材料」として表示が義務付けられている8品目の一つである 33。アレルゲンのコンタミネーション(意図しない混入)防止など、店舗運営における厳格な管理が求められる。
経済(Economy)
- 原材料価格とエネルギー価格の高騰: 近年、世界的な需給バランスの変動、地政学的リスク、円安の進行により、小麦やそばの実といった穀物価格が高騰している 35。出汁に不可欠な鰹節や昆布も、不漁や気候変動による生育環境の悪化で価格が上昇 37。さらに、電気・ガスといったエネルギー価格の上昇も加わり、製造から店舗運営に至るまで、あらゆる段階でコストが増加している 1。
- 人件費の上昇: 全国的な最低賃金の引き上げは、パート・アルバイト比率が高い労働集約型のうどん・蕎麦業界にとって、人件費の継続的な上昇圧力となっている 39。
- 消費者の可処分所得と節約志向: 物価高が続く一方で賃金の伸びは緩やかであり、消費者の可処分所得は圧迫されている。これにより、外食に対する節約志向が強まっている。帝国データバンクの調査でも、多くの外食企業が値上げに踏み切るものの、その後の客足の鈍化を懸念しており、コスト上昇分を価格へ完全に転嫁することが難しい状況がうかがえる 42。
社会(Society)
- 人口動態と食生活の変化: 高齢化と単身世帯の増加という構造的な変化は、「調理や後片付けが面倒」と感じる層を拡大させ、外食や中食(惣菜、弁当など)への需要を根本的に下支えしている 9。手軽に食事を済ませたいというニーズは、うどん・蕎麦業態にとって追い風となる。
- 健康志向の深化: 消費者の健康への関心は、「漠然と体に良いものを」という段階から、「減塩」「低糖質」「グルテンフリー」といった具体的なニーズへと深化・細分化している 43。そばに含まれる健康成分(ルチンなど)や、十割そばがグルテンフリーである点などが、新たな付加価値として注目されている 13。
- インバウンド観光客の和食への関心: 訪日外国人観光客にとって「日本食を食べること」は、観光の主要な目的の一つである 17。特にそばは、寿司やラーメンと並び、本格的な和食体験として高い関心を集めている 18。
- SNSによる「映え」消費: InstagramやTikTokといったSNSの普及は、消費者の飲食店選びに大きな影響を与えている。見た目にインパクトのある「デカ盛り天ぷら」や、カラフルな「創作うどん」など、写真や動画映えするメニューが若年層を中心に人気を集め、来店動機となっている 45。
技術(Technology)
- 食品加工技術の進化: 冷凍麺やチルド麺、および専用つゆの品質は、技術革新により飛躍的に向上した 47。これにより、店舗で提供される味に近いクオリティが家庭でも手軽に楽しめるようになり、強力な代替品として中食・内食市場の拡大を牽引している。
- 店舗オペレーションのデジタル化: 省人化と顧客利便性向上を目的としたデジタル技術の導入が加速している。リクルートの2024年の調査では、消費者のスマートフォンで注文するセルフオーダーシステムの利用経験率が57.1%に達し、2021年の26.0%から倍増した 49。キャッシュレス対応の券売機やモバイルオーダーの普及も進んでいる。
- 調理・配膳の自動化: 人手不足への対応策として、調理ロボット(麺茹で機、天ぷら自動揚げ機など)や配膳ロボットの導入事例が出始めている。これらは、作業効率の向上と品質の標準化に貢献するポテンシャルを秘めている。
- デリバリープラットフォームとの連携: Uber Eatsなどのデリバリープラットフォームとの連携は、新たな販売チャネルとして定着した。
法規制(Legal)
- 食品衛生管理基準(HACCP): 2021年6月より、原則としてすべての食品等事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が完全義務化された。これにより、衛生管理計画の策定、実行、記録、検証が求められ、管理コストが増加している 51。
- 労働基準法: 「働き方改革関連法」の施行により、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化が導入された。これにより、勤怠管理の厳格化が求められ、労務管理コストが増大している 53。
- インボイス制度: 2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、特に免税事業者との取引が多い小規模事業者にとって、仕入税額控除の観点から大きな影響を及ぼしている。仕入先の見直しや、経理業務の煩雑化といった課題が生じている 55。
環境(Environment)
- 食品ロス削減への取り組み: 食品ロスは、経営コストの観点だけでなく、企業の社会的責任としても重要課題となっている。AIを活用した需要予測による仕込み量の最適化や、食べ残しの持ち帰りを推奨する「mottECO(モッテコ)」といった取り組みへの関心が高まっている 57。
- 持続可能な食材調達: 海洋資源の枯渇が懸念される中、持続可能な漁業で獲られた水産物の証であるMSC認証や、環境と社会に配慮した養殖業の証であるASC認証を取得した食材(例:天ぷら用のエビ、出汁用の鰹)への注目が集まっている 59。
- プラスチック製テイクアウト容器の規制: 2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」により、使い捨てプラスチック製品の削減が求められている。これにより、テイクアウト用の容器を紙製やリユース可能な素材へ切り替える動きが加速している 61。
これらのマクロ環境要因は、単独ではなく複合的に作用し、うどん・蕎麦業界の構造を大きく変えようとしている。経済的な圧力(原材料費・人件費の高騰)は、すべての事業者の利益を圧迫する。この圧力に対して、事業者は「コストを吸収するためにテクノロジーを活用し徹底的に効率化する」か、「コスト上昇分を価格に転嫁するために社会的な要請(健康、環境)に応え付加価値を高める」という二つの戦略的方向に進まざるを得ない。法規制(労働基準法、HACCP)は非効率な経営を許さず、政治的な動き(国産振興策)や社会・環境トレンドは高付加価値戦略を後押しする。結果として、これらPESTLEの各要因が、中途半半端な戦略を取る企業を市場から排除し、業界構造を「低価格・効率追求型」と「高付加価値・体験型」の両極へと不可逆的に再編しているのである。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
ポーターのFive Forcesフレームワークを用いて、うどん・蕎麦業界の収益性に影響を与える5つの競争要因を分析し、業界の構造的な魅力を評価する。
供給者の交渉力:中〜高
供給者の交渉力は、原材料の種類によって異なるが、総じて中程度から高いレベルにある。
- 製粉会社: 小麦粉市場は、日清製粉(シェア約40%)、日本製粉、昭和産業の大手3社による寡占状態であり、市場全体の9割のシェアを握っている 63。この高い市場集中度により、製粉会社は価格設定において強い交渉力を持つ。うどん店にとって小麦粉は代替の難しい基幹食材であり、供給者の価格戦略を受け入れざるを得ない構造となっている。
- 国産そば粉生産者: 国産そば粉は、その希少性と高い品質から、こだわりの蕎麦屋にとっては不可欠な原材料である。しかし、生産は天候に左右されやすく、また、より収益性の高い作物(小麦、大豆など)への転作も進んでおり、供給は不安定である 66。これにより、特に高品質な国産そば粉の生産者は強い交渉力を持つ。
- 出汁・つゆメーカー: 業務用市場においても、ヤマキ、キッコーマン、味の素といった大手メーカーが存在感を示している 67。独自の製造技術やブランド力を持つこれらのメーカーは、価格競争に巻き込まれにくく、比較的強い交渉力を維持している。
買い手の交渉力:高
買い手である消費者の交渉力は非常に高い。
- 価格敏感性: 経済の先行き不透明感や物価高を背景に、消費者の節約志向は根強い。特に日常食としての利用が多い当業界では、価格は購買決定における重要な要素である。外食企業の値上げが客離れにつながるケースも報告されており、消費者は価格に対して非常に敏感である 42。
- 低いスイッチングコスト: 消費者にとって、うどん・蕎麦から他の食事への切り替えコストは皆無に等しい。ラーメン、パスタ、牛丼、ハンバーガーといった多種多様な外食オプションが存在する 20。さらに、近年品質が著しく向上したコンビニエンスストアやスーパーマーケットの中食(調理麺、冷凍麺)も強力な競合であり、消費者はその日の気分や状況に応じて容易に選択肢を切り替えることができる。
新規参入の脅威:業態により異なる(セルフ式は低、専門店は中)
新規参入の障壁は、どの市場セグメントを狙うかによって大きく異なる。
- セルフ式チェーン市場: この市場は、丸亀製麺とはなまるうどんという二大巨頭による寡占化が進んでいる 69。大手は、スケールメリットを活かした食材の大量調達によるコスト競争力、全国的なブランド認知度、確立された店舗開発・運営ノウハウといった強固な参入障壁を築いている。過去には異業種からの参入もあったが、多店舗展開に失敗し撤退した事例もあり、新規参入の脅威は低い 70。
- 個人経営の専門店: 独立開業には、居抜き物件を活用した場合でも800万円~1,500万円程度の初期投資が必要となる 71。加えて、蕎麦打ちの技術習得には「木鉢三年」と言われるように、最低でも3年以上の修行期間が必要とされ、これが人的な参入障壁となる 74。これらの投資や時間的コストを考慮すると、参入障壁は中程度と言える。
代替品の脅威:高
代替品の脅威は極めて高い。
- 他業態の外食: 前述の通り、消費者の胃袋を奪い合う競合は、同業のうどん・蕎麦屋だけではない。ラーメン、パスタ、カレー、定食、ファストフードなど、あらゆる外食業態が代替品となりうる。
- 中食・内食: 特に脅威度が高いのが、コンビニやスーパーで手軽に購入できる中食・内食製品である。冷凍麺技術の進化により、家庭でも専門店に遜色ないレベルのうどんが楽しめるようになった 47。調理麺市場も1兆円を超える巨大市場に成長しており 5、「安さ」「手軽さ」を求める顧客層にとっては、外食の強力な代替品となっている。
業界内の競争:高
業界内の競争は非常に激しい。
- 大手チェーン間の競争: セルフうどん市場では、トリドールホールディングス傘下の「丸亀製麺」と、吉野家ホールディングス傘下の「はなまるうどん」が、店舗数、売上、マーケティング戦略において激しい競争を繰り広げている 69。立ち食いそば市場においても、「ゆで太郎」「富士そば」「小諸そば」などが首都圏を中心に熾烈なシェア争いを展開している 77。
- チェーン店 vs 個人店の競争: 効率的なオペレーションと価格競争力で勝負するチェーン店と、独自の味やこだわりの空間で差別化を図る個人店との間で、顧客の奪い合いが生じている。事業所数の減少傾向は、この競争において多くの個人店が苦戦を強いられている現実を示唆している 11。
以上の分析から、うどん・蕎麦業界は、バリューチェーンの上流(供給者)からのコスト圧力と、下流(買い手・代替品)からの価格抑制圧力に挟まれた、収益を上げにくい「サンドイッチ構造」にあることがわかる。供給者は寡占化や希少性を背景に強い交渉力を持ち、原材料費の上昇圧力が常に存在する。一方で、買い手は価格に敏感で、かつ魅力的な代替品が豊富にあるため、コスト上昇分を販売価格へ容易に転嫁することができない。この構造的な収益圧迫から脱却するためには、大規模調達によるコスト削減、テクノロジー活用による徹底的な生産性向上、あるいはブランドや体験価値といった価格以外の価値を創造し、顧客のスイッチングコストを高める戦略が不可欠となる。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析
うどん・蕎麦業界のサプライチェーンは、主要原材料の調達から店舗での提供まで、複数の段階を経て構成されている。各段階にはそれぞれ特有のリスクと課題が存在する。
主要原材料の調達ルートと価格変動リスク
- 小麦: うどんの主原料である小麦は、その大半を輸入に依存している。政府が米国、カナダ、オーストラリアなどから一元的に輸入し、製粉会社へ売り渡す仕組みが取られている 26。そのため、国際市況や為替レートの変動が政府売渡価格に反映され、それが直接的に小麦粉の仕入れ価格に影響を及ぼす。近年の地政学的リスクや円安は、価格の不安定性を高める大きな要因となっている 28。国産小麦も一部で使用されているが、生産量は限られている 80。
- そばの実: そばの実は、国産品と輸入品(主に中国、米国、ロシア)が併用されている 19。国産品は北海道を筆頭に各地で生産されているが、天候不順による作柄変動が大きく、供給が不安定な側面を持つ 66。輸入品はかつて安価な代替品と位置づけられていたが、近年は国際的な需要増や生産国の状況により価格が高騰し、国産品との価格差が縮小している 36。これにより、特に輸入品に依存してきた低価格帯の業態は、コスト構造の見直しを迫られている。
- 出汁原料: 和食の要である出汁の原料(鰹節、昆布、いりこ等)は、主に国内で調達される。しかし、鰹の漁獲量減少や、地球温暖化に伴う海水温上昇による昆布の生育不良など、資源の持続可能性に関する課題が深刻化している 37。これにより、品質の高い原料の確保が困難になり、価格も上昇傾向にある。調達の安定性確保が、今後の大きな経営課題となる。
製粉から店舗配送までのフロー
- 製粉: 調達された小麦やそばの実は、製粉会社によって小麦粉やそば粉に加工される。この段階は、日清製粉などの大手製粉メーカーが市場を寡占している 64。
- 製麺: 製麺プロセスは、業態によって大きく異なる。
- 自家製麺: 丸亀製麺のように、店舗内に製麺機を設置し、その場で麺を製造する方式。出来立ての品質を提供できる反面、設備投資や専門知識を持つ人材が必要となる。
- 外部調達: 製麺所から生麺や茹で麺、冷凍麺を仕入れる方式。多くの個人店や一部チェーンで採用されており、初期投資を抑え、オペレーションを簡素化できる。
- 店舗配送:
- セントラルキッチン(CK)経由: 大手チェーンでは、CKで出汁や天ぷらなどの具材を一括調理・加工し、各店舗へ効率的に配送するモデルが採用されることが多い。品質の均一化と店舗作業の負荷軽減に繋がるが、大規模な設備投資が必要となる。
- 直接配送: 各店舗が製麺所や卸売業者から直接食材の配送を受ける方式。小規模な事業者に多く見られる。
バリューチェーン分析
うどん・蕎麦業界における価値創造のプロセス(バリューチェーン)は、業態の戦略によってその焦点が大きく異なる。
価値の源泉(コア・コンピタンス)
- セルフ式チェーン: 価値の源泉は、徹底的に効率化されたオペレーションにある。「注文から提供までのスピード」「手頃な価格」「天ぷらなどを自由に選べるカスタマイズ性」が、顧客にとっての主要な価値となっている。丸亀製麺は、この効率性に加え、「全店自家製麺」という非効率な工程をあえて見せることで、「手づくり・できたて感」という体験価値を創出し、他社との差別化に成功している 81。
- フルサービス専門店: こちらの価値の源泉は、効率とは逆の「非効率」の中にある。「国産の希少なそば粉を使った手打ち麺」「職人が手間暇かけて引く秘伝の出汁」「季節の食材を使った天ぷら」「落ち着いた店内空間と心のこもったおもてなし」など、模倣が困難な品質と体験そのものがコア・コンピタンスとなる。
- 立ち食い店: 価値は「圧倒的なスピード」と「利便性の高い立地(駅ナカなど)」に集約される。多忙なビジネスマンの時間を節約すること自体が、提供価値となっている。
各プロセスにおけるコスト構造と利益創出ポイント
- 調達: 大手チェーンは、スケールメリットを活かした一括大量購入により、調達コストを抑制する。
- 製麺・調理: 自家製麺は品質向上に貢献するが、設備投資と人件費(職人)を要する。CKの活用や、調理ロボット(自動麺茹で機、天ぷらフライヤー等)の導入は、この工程のコストを削減し、品質を標準化するための重要な利益創出ポイントとなる。
- 接客・販売: 人件費が最も発生しやすいこのプロセスにおいて、セルフサービス方式の導入、券売機やモバイルオーダーシステムの活用は、コスト構造を劇的に改善する。これにより創出された人員を、より付加価値の高い調理や顧客対応に再配置することが可能になる。
この業界で成功を収めるには、バリューチェーン上に存在する「非効率」を戦略的にマネジメントする視点が不可欠である。業界には、①職人技に代表される「価値を生む非効率」と、②配膳や会計などの単純作業に起因する「コストを生む非効率」の二種類が存在する。高付加価値戦略を採る企業は、①をブランドの核として磨き上げ、②をテクノロジーで徹底的に排除することで、創出したリソースを①に再投資する。一方、コストリーダーシップ戦略を採る企業は、①ですらも工業化・標準化の対象とし、バリューチェーン全体からあらゆる非効率を排除することで、究極のコスト競争力を追求する。自社の戦略に基づき、どの非効率を維持し、どの非効率を排除すべきかを明確に定義することが、持続的な競争優位の構築に繋がるのである。
第6章:顧客需要の特性分析
うどん・蕎麦市場は、多様な顧客セグメントと利用シーンによって構成されており、それぞれが異なる購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)を持っている。これらの需要特性を深く理解することが、効果的なマーケティング戦略と商品開発の基盤となる。
主要な顧客セグメントとKBF(Key Buying Factor)
- ビジネスマン(ランチ利用):
- ニーズ・課題: 限られた昼休み時間内に、手頃な価格で満足感のある食事を素早く済ませたい。
- KBF: 「スピード」「価格」「ボリューム」「立地の利便性(オフィス街、駅ナカ)」。このセグメントは、立ち食いそば店やセルフ式うどんチェーンの主要なターゲット層である。
- ファミリー層(週末・休日利用):
- ニーズ・課題: 子供から高齢者まで、家族全員が楽しめる食事の場を求めている。駐車場の有無や、子供がいても気兼ねなく過ごせる空間が重要。
- KBF: 「座席の広さ・くつろげる空間」「メニューの多様性(子供向けメニュー、セットメニュー)」「コストパフォーマンス」「駐車場の有無」。ロードサイドに店舗を構えるセルフ式チェーンや、「和食麺処サガミ」のような和食ファミリーレストランがこの需要に応えている。
- 高齢者層:
- ニーズ・課題: あっさりとした消化の良い食事を、落ち着いた環境で楽しみたい。健康への配慮も重要な要素。
- KBF: 「あっさりした味付け(薄味の出汁など)」「健康への配慮(減塩、柔らかい麺)」「落ち着いた雰囲気」「バリアフリーなどのアクセスの良さ」。フルサービス型の専門店や地域の老舗が強い支持を得ているセグメント。
- インバウンド観光客:
- ニーズ・課題: 日本ならではの本格的な食文化を体験したい。言葉の壁や注文方法への不安がある。
- KBF: 「日本らしい体験(手打ちの実演など)」「本物感(国産素材、伝統的な製法)」「分かりやすさ(多言語メニュー、写真付きメニュー、券売機)」。観光庁の調査でも「日本食を食べること」への期待は極めて高い 17。そばは特に人気があり、「ざるそば」の喉越しや「天ぷらそば」の組み合わせが好評である 18。一方で、「富士そば」のような手軽なチェーン店も、ローカルな雰囲気を味わえるとして人気を集めている 83。
- Z世代・若年層:
- ニーズ・課題: 食事をSNSで共有することを楽しみたい。トレンドに敏感で、新しい体験や話題性を求めている。コストパフォーマンスも重視する。
- KBF: 「SNS映え(見た目のインパクト、動画映え)」「話題性・限定感」「カスタマイズ性(豊富なトッピング)」「コストパフォーマンス」。丸亀製麺が発売した「シェイクうどん」は、テイクアウトの手軽さと振って混ぜるというエンターテイメント性を両立させ、SNS上で大きな話題となり、この層の心を的確に捉えた成功事例と言える 84。
利用シーン分析
顧客は、様々な生活シーンにおいてうどん・蕎麦を選択している。
- 日常のランチ: 最も主要な利用シーン。オフィス街や商業地において、スピードと価格が最優先される。
- 飲んだ後のシメ: 繁華街に立地する立ち食い店や、富士そばのような24時間営業のチェーン店が、深夜帯のこの特殊な需要を捉えている。
- 週末の家族での外食: 食事そのものだけでなく、家族団らんの時間という付加価値が求められる。
- 観光地での食体験: その土地ならではの食材を使った郷土うどん・蕎麦や、そば打ち体験など、非日常的な価値提供が重要となる。
健康志向への具体的な需要と成功事例
健康志向は、単なるトレンドではなく、幅広い世代に浸透した確固たる需要となっている。
- 具体的な需要:
- 減塩・糖質オフ: 高血圧や糖尿病への懸念から、減塩つゆや糖質を抑えた麺への需要が存在する。市場には、こんにゃくを使った低糖質麺なども登場している 44。
- グルテンフリー: 小麦アレルギーを持つ人や、健康上の理由でグルテンを避ける人にとって、そば粉100%の「十割そば」は魅力的な選択肢である 13。
- 栄養バランスの補完: うどん・蕎麦が炭水化物中心の食事であることから、不足しがちな栄養素を補いたいというニーズが強い。わかめ、きのこ類(食物繊維)、卵、肉、豆腐(タンパク質)といったトッピングは、手軽に栄養バランスを改善できるため、非常に人気が高い 14。サラダうどんなどもこの需要に応える商品である。
- 成功事例:
個別の商品の具体的なヒットデータは限定的だが、多くのチェーン店が「野菜たっぷり」や「肉増し」といったメニューを定番化させていること自体が、この需要の大きさを物語っている。例えば、わかめうどんや肉うどん、とろろそばといったメニューは、単なる味のバリエーションではなく、「食物繊維をプラスする」「タンパク質を補う」といった健康上のベネフィットを消費者に提供している。
これらの分析から、顧客は単に「うどん・蕎麦」というプロダクトを消費しているのではなく、「特定のシーンにおける最適な食事ソリューション」を求めていることがわかる。例えば、「時間のないビジネスマンのランチ問題を最速で解決するソリューション」として立ち食いそばがあり、「週末の家族の食事体験を豊かにするソリューション」として和食レストランのうどんセットがある。したがって、成功する戦略は、ターゲットとする顧客セグメントとその利用シーン(顧客が片付けたい用事=ジョブ)を明確に定義し、そのジョブを最も効果的に解決する価値(スピード、体験、健康など)を設計することから始まるのである。
第7章:業界の内部環境分析
業界の持続的な競争優位の源泉を特定するため、VRIOフレームワークを用いて経営資源を分析し、人材動向や労働生産性といった内部環境の実態を明らかにする。
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
VRIOは、企業の経営資源やケイパビリティが「価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Inimitability)」「組織(Organization)」の4つの観点から競争優位に繋がるかを評価するフレームワークである。
- 価値(Value):
- 強力なブランド: 「〇〇屋のそばが食べたい」と顧客に指名される老舗の屋号や、「丸亀製麺」のような全国的なブランド認知度は、集客力を高め、価格競争を緩和する価値を持つ。
- 超一等地の立地: 交通量の多い駅前やロードサイドといった優れた立地は、安定した顧客フローを確保し、売上を創出する上で極めて価値が高い。
- 独自のレシピ・技術: 他社が真似できない秘伝の出汁レシピや、独自の食感を生み出す製麺技術は、製品を差別化し、顧客ロイヤルティを高める価値の源泉である。
- 希少性(Rarity):
- 老舗としての歴史的ブランド: 数十年、百年以上にわたって築き上げられた暖簾や評判は、新規参入者が短期間で獲得できるものではなく、非常に希少な資源である。
- 熟練した職人の存在: 高度な製麺技術や天ぷらを揚げる技術を持つ職人は、育成に長い年月を要する。特に後継者不足が深刻化する現在、その存在は極めて希少性が高い。
- 模倣困難性(Inimitability):
- 独自のオペレーションシステム: 丸亀製麺が展開する「全店舗での店内製麺」と効率的なセルフサービスを組み合わせたビジネスモデルは、単に製麺機を導入するだけでは模倣できない。その背後には、高度な店舗開発能力、標準化された教育システム、強力なサプライチェーン管理が一体となった複雑な組織能力が存在し、他社が容易に模倣することを困難にしている 81。
- 店舗の文化・雰囲気: 老舗が持つ独特の空気感や、長年の常連客との間に築かれた関係性といった無形の資産は、物理的にコピーすることが不可能な、極めて模倣困難性の高い経営資源である。
- 組織(Organization):
上記の価値があり、希少で、模倣困難な経営資源も、それを活用するための組織体制がなければ競争優位には繋がらない。例えば、希少な職人を確保・育成し、その技術を「麺職人制度」のような形で組織的に展開する仕組みがあって初めて、職人技は個人のスキルを超えた組織の強みとなる 81。丸亀製麺は、データサイエンスを活用してマーケティング戦略を策定し、それを全社的に実行する組織能力を持つことで、持続的な成長を実現している 84。
人材動向
- 職人の需要と供給ギャップ、後継者問題:
フルサービス型の専門店では、麺打ち、茹で、天ぷら揚げといった工程を担う職人が品質の核となる。しかし、職人の高齢化と若者の職人離れにより、後継者不足は業界全体の深刻な課題となっている。これが、M&Aによる事業承継が増加する一因ともなっている 21。 - ホール・キッチンスタッフの需給と賃金トレンド:
パート・アルバイトを中心とするホール・キッチンスタッフの確保も、少子高齢化による労働人口の減少で年々困難になっている。特に飲食業は他業種との人材獲得競争が激しく、外国人労働者への依存度が高い状況にある 87。全国的な最低賃金の継続的な引き上げは、人件費を構造的に押し上げ、経営を圧迫している 39。
労働生産性
- 人時売上高(MH)のベンチマーク:
人時売上高(従業員1人が1時間あたりに生み出す売上高)は、労働生産性を測る重要な指標である。一般的な飲食店の平均値は3,000円~4,000円、5,000円以上が優良店の目安とされる 88。業態による差は大きく、セルフサービス業態はフルサービス業態に比べて高い傾向にある。 - 生産性向上の定量的効果:
セルフサービス化、券売機の導入、食洗機の活用は、ホール業務や洗い場業務に必要な人員を削減し、人時売上高を直接的に向上させる。例えば、配膳ロボットの導入により、スタッフ1名分の労働力を代替し、人件費を1割程度削減した事例も報告されている 90。 - FLコスト比率の悪化傾向と対策:
食材費(F)と人件費(L)の双方が高騰しているため、多くの飲食店でFLコスト比率が悪化傾向にある。飲食店の経営における適正水準は50~60%とされており、これを超える状態が続けば赤字経営に陥る 23。この課題に対し、各社は省人化技術の導入による人件費抑制や、メニュー価格への転嫁といった対策を進めているが、価格転嫁は客離れのリスクを伴うため、生産性の向上がより本質的な解決策となる。
以上の内部環境分析から、当業界の最大の経営資源が「人」であると同時に、それが最大の経営リスクにもなっているという構造的なジレンマが浮かび上がる。VRIO分析で示された競争優位の源泉、すなわち「職人技」や「おもてなし」は、すべて人的資本に深く根差している。しかし、その「人」の確保は困難を極め、コストは上昇し続けている。この矛盾は、人的資本への過度な依存がビジネスモデルの脆弱性に直結することを示している。このリスクをヘッジし、持続的成長を遂げるためには、「人への依存を減らす(省人化・自動化)」と「人の価値を最大化する(技術のデータ化による継承、単純作業から解放された従業員による高付加価値な接客)」という、両面からの戦略的アプローチが不可欠である。
第8章:主要トレンドと未来予測
うどん・蕎麦業界は、外部環境の変化と内部の課題に対応する形で、いくつかの明確なトレンドに沿って未来が形成されていくと予測される。
業態の二極化の加速
今後、業界構造は「低価格・効率追求型」と「高付加価値・体験型」への二極化がさらに加速し、両者の中間に位置する特徴の曖昧なプレイヤーは淘汰される「バーベル構造」がより鮮明になる。
- 低価格・効率追求型: このセグメントは、徹底したコスト削減と高い利便性を武器に、日常食としての需要を確実に取り込む。セルフサービス、立ち食い業態が中心となる。AIによる需要予測や調理ロボットといったテクノロジーの導入が競争の鍵を握り、さらなる効率化と低価格化を推し進める。
- 高付加価値・体験型: こちらは、食事を単なる栄養摂取ではなく、一つの体験として捉える消費者のニーズに応える。国産・有機栽培のそば粉、希少な出汁原料、職人の手打ち実演、日本文化を感じさせる店舗空間、心のこもった接客などが価値の源泉となる。インバウンド観光客や特別な食事の機会を求める国内顧客が主なターゲットとなる。
成長の機会は両極に存在するが、求められる経営資源やケイパビリティは全く異なる。そのため、自社の強みと市場機会を照らし合わせ、どちらの極で戦うかを明確に選択することが、生き残りのための絶対条件となる 22。
デリバリー・テイクアウト市場の定着と進化
コロナ禍を契機に定着したデリバリー・テイクアウト需要は、今後も市場の重要な一部を占め続ける。この市場での競争は、新たな段階に入る。
- 技術開発: 「麺が伸びる」といううどん・蕎麦の根本的な課題を解決する技術開発が競争の焦点となる。麺の改良(例:老化を遅らせる配合)や、麺とつゆをセパレートし、食べる直前に合わせる専用容器の開発などが進む。
- メニュー開発: デリバリー専用のメニュー開発も重要になる。汁気の少ない「まぜそば」や「ぶっかけうどん」、あるいは冷めても美味しさが損なわれにくい天ぷらや丼ものとのセットメニューなどが強化される。
- 収益モデル: デリバリープラットフォームへの手数料が収益を圧迫するため、自社アプリによる注文受付やテイクアウトへの誘導を強化し、利益率を高める取り組みが不可欠となる。
海外展開の可能性
国内市場が成熟する中、海外市場は重要な成長フロンティアとなる。
- うどん業態: 丸亀製麺の成功は、うどん業態の海外展開ポテンシャルの高さを証明した。成功の鍵は、単にうどんを提供するだけでなく、「店内自家製麺」というライブ感あふれる体験価値をセットで提供したこと、そして現地の食文化や嗜好に合わせたメニューのローカライズを徹底したことにある 91。このモデルは、他のうどんチェーンにとっても重要なベンチマークとなる。
- そば業態: そばの海外展開は、うどんに比べてハードルが高い側面がある。そばアレルギーへの対応や、繊細な出汁文化への理解をどう促進するかが課題となる 92。しかし、一方で「グルテンフリー」という世界的な健康トレンドは大きな追い風である 13。日本食としてのブランドイメージと健康価値を前面に打ち出すことで、新たな市場を切り拓く可能性がある。
M&Aによる業界再編
後継者不足と経営者の高齢化は、特に個人経営の専門店において深刻な問題である。この構造的な課題は、業界再編を促す大きな原動力となる。
- 資本力のある大手チェーンや異業種の企業が、事業承継に悩む地域の優良店をM&Aのターゲットとする動きが加速する 21。これにより、買い手は短期間で「ブランド」「伝統のレシピ」「熟練の職人技術」「顧客基盤」といった無形の資産を獲得できる。
- 買収後は、買い手の持つマーケティングノウハウ、システム、資金力を注入して経営を近代化し、多店舗展開を目指す「再生・成長モデル」が一般化するだろう。
サステナビリティへの対応強化
企業の社会的責任(CSR)やESG経営への関心の高まりは、飲食業界にも大きな影響を与える。
- 食材調達: 国産食材、特に生産量が限られる国産そば粉への回帰は、食の安全・安心やトレーサビリティを重視する消費者への強力なアピールとなる。また、鰹などの水産資源については、MSC認証やASC認証といった持続可能性を証明する認証を取得した原料への切り替えが進む 59。
- 環境負荷の低減: AIによる需要予測を活用した食品ロス削減は、コスト削減と環境貢献を両立する取り組みとして、業界のスタンダードになる 93。また、出汁を取った後の昆布や鰹節を再利用した商品(佃煮など)の開発や、テイクアウト容器の脱プラスチック化も、企業の環境姿勢を示す上で重要となる。
第9章:AIの影響とテクノロジー活用の未来
AIをはじめとするテクノロジーは、うどん・蕎麦業界が直面するコスト上昇、人手不足、品質維持といった根深い課題を解決し、ビジネスモデルそのものを変革する最も強力なドライバーである。テクノロジーは、単なる効率化ツールにとどまらず、企業が選択した戦略(コストリーダーシップか、高付加価値か)を競合が追随不可能なレベルまで先鋭化させる「戦略的増幅器(Strategic Amplifier)」として機能する。
オペレーション効率化
- AIによる需要予測:
過去のPOSデータ、曜日、天候、周辺のイベント情報、さらにはSNSのトレンドといった膨大なデータをAIが統合的に分析し、将来の来店客数やメニュー別の出数を高精度で予測する。これにより、以下のような効果が期待できる。- 食品ロスと機会損失の削減: 勘と経験に頼った過剰な仕込みによる廃棄(食品ロス)と、品切れによる販売機会の損失を同時に最小化する。回転寿司チェーンのスシローやリンガーハットでは、AI需要予測の導入により食品ロスを20%~50%削減したという事例が報告されている 93。
- 発注・在庫管理の自動化: 予測された需要に基づき、必要な食材(特に鮮度が命の天ぷら種など)を最適なタイミングで自動発注する。これにより、在庫を圧縮し、キャッシュフローを改善すると同時に、発注業務にかかる従業員の負担を大幅に軽減する。
- 最適人員配置(シフト管理): 来客予測に基づき、時間帯ごとに必要な人員を算出し、最適なシフトを自動で作成する。これにより、人員の過不足をなくし、人件費の無駄を排除しながら、サービスレベルを維持することが可能になる 96。
調理の自動化・標準化
- 調理ロボットの導入:
これまで職人技が必要とされたり、単純作業であったりした調理工程をロボットが代替する。- 麺茹で・盛り付け: コネクテッドロボティクス社などが開発するそば調理ロボットは、複数の茹で釜を管理し、正確な茹で時間で麺を上げ、冷水で締め、盛り付けるまでの一連の作業を自動化する 97。
- 天ぷら・炒め物: TechMagic社の「I-Robo」のような調理ロボットは、天ぷらを自動で揚げたり、炒め物や焼きうどんといったメニューを調理したりすることが可能である 98。
- ROI(投資対効果): 調理ロボットの導入コストは、単機能のもので100万円~500万円、多機能なシステムでは数千万円に及ぶ場合もある 100。しかし、24時間稼働可能で、人件費(採用・教育コスト含む)を大幅に削減できるため、長期的に見れば高い投資対効果が期待できる。
- AIによる品質の標準化:
センサー技術とAIを組み合わせることで、これまで職人の感覚に頼っていた品質管理をデータに基づいて行う。例えば、出汁の塩分濃度、糖度、旨味成分をリアルタイムで監視し、常に一定の味を保つように自動調整する。また、AIがカメラ映像を解析し、麺の茹で加減や天ぷらの揚げ色を判断し、最適なタイミングをオペレーターに指示することも可能になる。これにより、店舗や調理担当者による品質のブレをなくし、ブランド全体の信頼性を高めることができる。
「職人技」のデータ化と継承
テクノロジーは、属人性の高い「職人技」を形式知化し、組織の資産として継承・スケールさせることを可能にする。
- 暗黙知の形式知化: 熟練職人の動きをモーションキャプチャ技術で記録したり、麺をこねる際の手の圧力や生地の水分量をセンサーで計測したりすることで、「こね」「のし」「切り」といった各工程の暗黙知をデジタルデータに変換する。
- AIトレーニングシステムへの応用: データ化された「匠の技」を基に、若手従業員向けのトレーニングシステムを構築する。例えば、VR(仮想現実)ゴーグルを装着し、熟練職人の動きを仮想空間でトレースしながら学ぶことで、従来よりも短期間で効率的に技術を習得させることが可能になる。これは、深刻な後継者不足問題に対する画期的な解決策となりうる。
マーケティングと顧客体験
- AIによる口コミ・SNS分析:
食べログやGoogleマップ、X(旧Twitter)などに投稿される膨大な量の口コミや投稿をAIが自然言語処理技術を用いて分析する。「味は良いが、接客が悪い」「〇〇というメニューがSNSで話題になっている」といった顧客の生の声を、定性的かつ定量的に把握できる 101。これにより、自社および競合の強み・弱みを客観的に特定し、メニュー開発やサービス改善に活かすことができる。 - パーソナライズド・マーケティング:
POSデータや公式アプリの利用履歴、会員情報などをAIが分析し、顧客一人ひとりの利用頻度や好みのメニュー、アレルギー情報などを把握する。その上で、「最近ご無沙汰しているお客様に再来店を促すクーポン」や「いつも天ぷらを注文するお客様に新商品の天ぷらをおすすめする」など、個々の顧客に最適化されたマーケティング施策を自動で実行する 104。 - 顧客体験の向上と省人化の両立:
タッチパネル式のセルフオーダーシステムや配膳ロボットは、ホールスタッフの人件費を削減するだけでなく、顧客体験の質を向上させる側面も持つ。顧客は店員を呼ぶ気兼ねなく自分のペースで注文でき、ロボットによる配膳はエンターテイメント性も提供する 90。単純作業をテクノロジーに任せることで、従業員は空いた時間を使って、より人間的な温かみのある接客(おすすめの説明、顧客との会話など)に集中でき、結果として顧客満足度を高めることにも繋がる。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
うどん・蕎麦業界の競争環境を理解するため、主要なプレイヤーを抽出し、その戦略、強み・弱み、財務状況、そしてDX/AIや海外展開への取り組みを比較分析する。
| 企業名(ブランド) | 業態 | 戦略・強み | 弱み・課題 | 財務状況(売上/利益) | DX/AI投資・海外展開 | データソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリドールHD(丸亀製麺) | セルフうどん | ・「店内製麺」によるライブ感と出来立ての「感動体験(KANDO)」の提供 ・データサイエンスを駆使したマーケティングと商品開発(例:シェイクうどん) ・圧倒的な店舗開発力と高いブランド認知度 | ・高付加価値路線による客単価の上昇と、それに伴う低価格志向の顧客層との乖離 ・店内製麺・調理にこだわる故のFLコスト管理の難易度 | ・26年3月期1Qは増収増益で過去最高益を更新 ・売上営業利益率は前年同期の5.3%から11.5%へ急改善し、高い収益性を示す | ・DX投資に極めて積極的。AI需要予測や顧客データ分析(MMM×KSF分析)を導入し、マーケティングROIを最大化 ・海外展開の成功モデル。200店舗以上を展開し、今後も加速 | 81 |
| 吉野家HD(はなまるうどん) | セルフうどん | ・親会社である吉野家グループの強固な調達力とブランド力 ・「うどんのファストフード」としての効率性と標準化されたオペレーション ・牛丼などご飯ものメニューの提供による顧客層の拡大 | ・丸亀製麺と比較した際の「体験価値」や「専門性」といったブランドイメージの弱さ ・低価格競争からの脱却と収益性向上が課題 | ・コロナ禍から回復し、24年2月期は過去最高のセグメント利益を達成 ・中期経営計画では2029年度に売上480億円、利益42億円を目指す | ・中期経営計画において、DX活用による省人化を推進する方針を明記 ・海外展開は限定的 | 76 |
| ゆで太郎システム | 立ち食いそば | ・「三たて(挽きたて、打ちたて、茹たて)」を掲げ、店内製麺による品質を訴求 ・フランチャイズ(FC)モデルによるスピーディーな店舗網拡大(年間10-15店舗ペース) ・独立支援制度による優秀な人材の確保と定着 | ・店舗網が首都圏に集中しており、他地域への展開が課題 ・立ち食いそばの枠を超えたブランドイメージの向上が必要 | ・非上場。2024年6月期の売上高は101億円と、立ち食い業態ではトップクラスの規模を誇る | ・FCモデルのため、全社的なDX投資の推進には課題も ・海外展開は未実施 | 112 |
| ダイタングループ(富士そば) | 立ち食いそば | ・都心の駅前一等地に集中した卓越した立地戦略 ・24時間営業による多様な利用シーンへの対応 ・カツ丼やカレーなど、そば以外の豊富なメニュー構成 ・海外メディアでも紹介され、インバウンドからの高い認知度 | ・創業家による経営体制からの組織的な変革 ・過去に指摘された労働環境問題のイメージ払拭と、現代的な労務管理体制の構築 | ・非上場 | ・台湾などへの海外出店実績あり。インバウンド需要の取り込みに積極的 | 83 |
| サガミホールディングス | フルサービス | ・「和食麺処サガミ」として、うどん・蕎麦を軸に、手羽先など幅広い和食メニューを提供 ・中京圏を地盤とした強固な顧客基盤 ・ファミリー層から高齢者層まで、幅広い客層に対応可能 | ・セルフ式業態や他の中価格帯ファミリーレストランとの競争 ・若年層の取り込みとブランドイメージの刷新 | ・(要IR資料分析) | ・(要IR資料分析) |
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、うどん・蕎麦業界で成功を収めるための戦略的な意味合いを導き出し、取るべき具体的な行動を提言する。
今後3~5年で、勝者と敗者を分ける決定的要因
今後3~5年において、うどん・蕎麦業界の勝者と敗者を分ける要因は、以下の3点に集約される。
- 戦略的明確性(Strategic Clarity):
市場の二極化が不可逆的に進む中、「低価格・効率」を徹底的に追求するコストリーダーか、「高付加価値・体験」で独自性を打ち出す差別化リーダーか、自社の戦うべき土俵を明確に定義し、経営資源をそこに集中投下できるかどうかが最も重要となる。両方を中途半端に追い求める「二兎を追う者」は、双方の専門プレイヤーとの競争に敗れ、市場から退出を余儀なくされる。 - テクノロジー活用能力(Technological Capability):
AIやロボティクスを、単なるコスト削減ツールとしてではなく、ビジネスモデル変革の核として経営戦略に組み込めるかどうかが勝敗を分ける。特に、勘と経験に依存してきた需要予測、発注、シフト管理をデータドリブンに変革し、FLコスト構造を根本から改善できる企業が圧倒的な競争優位を築く。テクノロジー投資の遅れは、競争劣位に直結する。 - 人材戦略の革新(Human Capital Innovation):
労働集約型ビジネスの宿命である「人」への依存を、リスクから強みへと転換できるかが問われる。具体的には、①属人的な職人技をデータ化・システム化し、組織として技術を継承・スケールさせる仕組みを構築できるか、そして②単純作業をテクノロジーに代替させ、創出された時間で従業員が人間ならではの「おもてなし」や「創造的な業務」に集中できる組織文化を醸成できるか、という二つの側面が鍵となる。
機会(Opportunity)と脅威(Threat)の整理
この市場で成功するためには、以下の機会を捉え、脅威に備える必要がある。
- 捉えるべき機会(Opportunity):
- 高付加価値・体験型市場の成長: 健康志向、本物志向の消費者をターゲットとした、高単価・高利益率市場には大きな成長余地がある。
- インバウンド需要の本格回復: 「本物の日本食」を求める訪日客は、高価格帯のメニューに対しても支払意欲が高い、極めて魅力的な顧客セグメントである。
- M&Aによる非連続的成長: 後継者不足に悩む地方の優良個人店は、ブランド、技術、顧客基盤を短期間で獲得できる絶好のM&Aターゲットである。
- 生産性の飛躍的向上: DX(デジタルトランスフォーメーション)への積極投資により、業界の構造的な低収益性から脱却し、高い利益率を実現する機会がある。
- 備えるべき脅威(Threat):
- コスト上昇の常態化: 原材料費、人件費、エネルギーコストの上昇は一過性のものではなく、今後も継続する構造的な脅威である。
- 競争領域の拡大: 競合は同業者だけではない。品質が向上したコンビニ・スーパーの中食製品が、日常食の領域で市場を侵食し続ける。
- テクノロジー格差の固定化: 先行してテクノロジー投資を行う大手企業との生産性・コスト競争力の差が拡大し、追いつくことが困難になるリスク。
- 消費者の飽き: 標準化されたチェーン店の味やサービスに対して、消費者が新鮮さを失い、より個性的でユニークな食体験を求めるようになる。
戦略的オプションの提示と評価
上記の分析に基づき、考えられる戦略的オプションを複数提示し、評価する。
| 戦略オプション | 概要 | メリット | デメリット | 成功確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 【新規参入】高付加価値特化型そばブランドの立ち上げ | 国産・単一産地のそば粉、希少な出汁原料、職人による手打ち、体験コンテンツ(そば打ち教室など)を組み合わせた高価格帯(客単価3,000円~)ブランドを主要都市や観光地で展開。 | ・高い利益率が期待できる ・インバウンドや富裕層を取り込める ・既存の低価格チェーンとの競争を回避できる | ・ブランド構築に時間とマーケティング費用を要する ・高度な技術を持つ職人の確保・育成が最大のボトルネックとなる ・多店舗展開の難易度が高い | 中 |
| 2. 【既存事業変革】AI/DXによる徹底的なローコストオペレーションの構築 | 既存のうどん・蕎麦事業(または新規に立ち上げるセルフ業態)に対し、AI需要予測、調理・配膳ロボット、完全キャッシュレスなどを包括的に導入し、業界最高水準の生産性を実現する。 | ・FLコスト比率を劇的に改善し、収益構造を根本から変革できる ・コストリーダーシップを確立し、価格競争において優位に立てる | ・多額の初期投資が必要 ・既存のオペレーションと組織文化の変革には、現場からの強い抵抗が予想される | 高 (ただし、強力なリーダーシップと実行力が伴えば) |
| 3. 【M&A】後継者不足の地方優良店の買収と再生 | 後継者不在で事業承継に悩む、地域で高い評価を得ている老舗・人気店を複数買収。買収後、本部が経理・労務・マーケティング・DXを支援し、職人は調理に専念できる体制を構築する。 | ・短期間でブランド、レシピ、技術、顧客基盤を獲得できる ・買収による成長ポテンシャルが高い ・社会的な課題(事業承継)の解決にも貢献できる | ・買収後の統合(PMI)プロセスが複雑で難易度が高い ・キーパーソンである職人の離反リスクがある ・複数の個人店を束ねるマネジメント体制の構築が必要 | 中~高 |
最終提言:ハイブリッド成長戦略
これまでの分析を総合的に判断し、最も持続的かつ大きなリターンが期待できる戦略として、「M&Aによる高付加価値ブランドの獲得」と「DXによる既存事業の収益性改善」を両輪で進めるハイブリッド戦略を提言する。
この戦略は、M&Aによって高付加価値市場への参入障壁(ブランド、技術)を乗り越えつつ、同時にDXによって既存事業または買収事業の収益基盤を強化することで、成長性と収益性を両立させるものである。
実行に向けた具体的なアクションプラン
- Phase 1:基盤構築フェーズ(Year 1)
- M&A: 後継者不在の地方の有名そば店(独自のブランド価値、模倣困難な技術を持つ)をターゲットリストアップし、デューデリジェンスを経て、1〜2件の買収を実行する。
- KPI: 買収完了件数、買収後のキーパーソン(職人)のリテンション率。
- DX: 既存事業(または買収した店舗)の中からパイロット店舗を選定し、AI需要予測システムと配膳ロボットを試験導入する。導入前後のFLコスト比率、食品ロス率、人時売上高を測定し、ROIを厳密に評価する。
- KPI: パイロット店舗におけるFLコスト比率の改善率(目標:5ポイント削減)、食品ロス削減率(目標:30%削減)。
- M&A: 後継者不在の地方の有名そば店(独自のブランド価値、模倣困難な技術を持つ)をターゲットリストアップし、デューデリジェンスを経て、1〜2件の買収を実行する。
- Phase 2:展開・スケールフェーズ(Year 2-3)
- M&A: 買収した店舗の経営(仕入れ、経理、労務管理)を本部主導で標準化・システム化する。職人技をデータ化し、若手への技術継承プログラムを構築する。成功モデルを確立後、2号店、3号店を出店し、多店舗展開モデルの有効性を検証する。
- KPI: 買収店舗の売上成長率(目標:年率15%)、営業利益率(目標:10%達成)。
- DX: パイロット導入で効果が実証されたテクノロジー(AI需要予測など)を、全社(全ブランド)的に展開する。
- KPI: 全社平均FLコスト比率、全社平均人時売上高。
- M&A: 買収した店舗の経営(仕入れ、経理、労務管理)を本部主導で標準化・システム化する。職人技をデータ化し、若手への技術継承プログラムを構築する。成功モデルを確立後、2号店、3号店を出店し、多店舗展開モデルの有効性を検証する。
- 必要リソース:
- 組織: M&A専門チーム、PMI(買収後統合)担当チーム、DX推進専門部署、データサイエンティスト。
- 資金: M&A実行資金、DXシステム導入・開発投資資金。
このハイブリッド戦略を実行することで、伝統的な職人技という無形資産と、最先端のテクノロジーという競争優位を両手にし、成熟市場であるうどん・蕎麦業界において、新たな成長曲線を描くことが可能となる。
第12章:付録
引用文献
- 生産性向上に向けた 取組みのヒント – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/001297207.pdf
- 【令和 4 年】 Ⅰ.外食産業の市場規模, http://anan-zaidan.or.jp/data/2024-1-1.pdf
- 外食産業市場規模、2年連続で前年比2ケタ増もコロナ禍前には至らず | ごはん彩々ニュース(GOHAN SAISAI NEWS), https://gohansaisai.news/news/article-7837/
- 外食市場に関する調査を実施(2024年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3642
- 全国麺類特集:調理麺概況=24年は1兆0863億円 10年間で市場は2 …, https://news.nissyoku.co.jp/news/fukushima20250513045708113
- 全国麺類特集:調理麺概況=市場は初の1兆円超え 19年から5年で47%増 – 日本食糧新聞, https://news.nissyoku.co.jp/news/fukushima20240509031127147
- 2023年冷凍めん生産食数は20億2426万食(前年比101%)、工場出荷額で市販用23.7%増, https://frozenfoodpress.com/2024/04/09/reitomen-2023-reitomenkyokai/
- 冷凍うどん市場 | 市場規模 分析 予測 2025-2030年 【市場調査レポート】, https://www.gii.co.jp/report/ires1718409-frozen-udon-market-by-product-varieties-packaging.html
- 単身者の中食・外食に関する意識調査|生活科学 – 日清オイリオグループ, https://www.nisshin-oillio.com/report/report/20180312.html
- 中食市場の現状と今後の動向 – ひょうご経済研究所, https://heri.or.jp/hyokei/166/3_166.pdf
- 飲食店営業 (そば・うどん店)の | 実態と経営改善の方策 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640921.pdf
- そば・うどん店の実態と 経営改善の方策 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001547705.pdf
- 【2024年最新】インバウンドに人気の食べ物15選!集客におすすめのメニューを解説 | hibana, https://biz-hibana.com/inbound-3/
- うどんのカロリーまとめ|太りにくい食べ方や簡単レシピも紹介 – ふるなび, https://furunavi.jp/discovery/knowledge_food/202310-udon/
- 栄養が偏りがちな〈素うどん〉栄養バランスよく食べるには?管理栄養士おすすめのトッピング&食べ方 | ヨガジャーナルオンライン, https://yogajournal.jp/21530
- ダイエット中にうどんはダメ?ダイエット向きの食べ方やレシピを紹介 – からだにいいこと, https://www.karakoto.com/67730/
- 訪日外国人旅行者の「食」への関心 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/attach/pdf/suishin_kenkyu-16.pdf
- 世界が認める日本のそば、外国人に嫌われているNo.1は?外国人に聞いてみた! – LIVE JAPAN, https://livejapan.com/ja/article-a0001788/
- 外国人観光客が喜ぶ日本食の魅力を伝える英語#5 「蕎麦」 – note, https://note.com/naomi_minamoto/n/n3d7b2eb74e07
- もっと利益を出したい店主のためのうどん・そば店の勝ち残り策:第一章 | 大和製作所, https://www.yamatomfg.com/info/udon-soba-strategy-1-reality/
- うどん・そば屋業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説, https://cinc-capital.co.jp/column/industry/ma-udon
- 実は拡大し続けている、うどん・そば市場!!―もっと利益を出したい店主のためのうどん・そば店の勝ち残り策:第二章 | 大和製作所, https://www.yamatomfg.com/info/udon-soba-strategy-2-udon-soba-expand/
- うどん屋の開業後の年収の目安は?相場や成功例、そば屋、ラーメン屋との比較, https://biz.moneyforward.com/restaurant/basic/2267/
- 【原価率と売上】飲食店運営の経費を把握して、支出を抑えて利益率を増やす!, https://lab.ipad-solution.com/cost-price/
- FLコスト管理 – みんなの飲食店開業, https://insyokukaigyo.com/guide/cost_management/
- 麦類の輸入手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る – ジェトロ, https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010880.html
- 輸入小麦 政府売渡価格 4.6%引き下げ 4月から 農水省 2025年3月13日 – JAcom, https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2025/03/250313-80159.php
- 令和5年4月期の輸入小麦の政府売渡価格について – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/mugi_zyukyuu/attach/pdf/index-20.pdf
- 令和5年4月期の輸入小麦の政府売渡価格について, https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/boeki/attach/pdf/230314-1.pdf
- 5 支援事業等 (1)水田活用の直接支払交付金等, https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/mr-924.pdf
- 経営所得安定対策について – 米原市, https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/nousei/nougyo/113.html
- 令和 6年度 経営所得安定対策等のあらまし, https://www.zennoh.or.jp/am/product/rice/pdf/r6aramashi.pdf
- アレルギー表示基準 | 産直の東都生協 | TOHTO CO-OP, https://www.tohto-coop.or.jp/sanchoku/anshin/allergy/
- 【解説】加工食品のアレルギー表示の読み方|食物アレルギーの子どものための 食事の基礎知識, https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/allergy/recipe/knowledge/processfood.html
- 2022.4.4 そば粉の輸入原料(玄ソバ)事情について |鈴木文明(すずきふみあき) – note, https://note.com/suzuki2020/n/n6e04073a30e8
- 「外国(中国)産玄そばの輸入状況と国内取引価格の動向」 – 江戸ソバリエ協会, https://www.edosobalier-kyokai.jp/pdf/202206kojima_sobaimport.pdf
- 【ラーメン業態の皆様へ】出汁原価価格高騰を助けたい!!!関東食糧が代替商品をご提案させていただきます!価格高騰シリーズ第3弾! | BS, https://kanto-syokuryo.info/bs/dasi20250415/
- 和食の命「だし」がピンチ! かつおぶしの値上げ相次ぐ – レタスクラブ, https://www.lettuceclub.net/news/article/120833/
- 2025年「最低賃金改定」に飲食店経営者の本音は? 約16%が「経営継続が危うい」と回答, https://www.inshokuten.com/foodist/article/8085/
- 2025年10月、東京都最低賃金1226円へ―飲食・給食・弁当業界に迫る影響 – note, https://note.com/clear_donkey3200/n/na77e5eeb8a40
- 2025年(令和7年)東京都最低賃金は1226円へ!10月3日適用, https://taxlabor.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91/
- 主要外食100社 「今年も」値上げ 4割 前年から16社減少 値上げ後の客足「鈍化」影響も, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000760.000043465.html
- 慢性腎臓病患者と小麦アレルギー人のための “減塩グルテンフリー米粉ラーメン” の開発に成功。米粉のつるつるラーメン「あかり」。 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000135707.html
- 【楽天市場】低糖質 ラーメン(健康志向減塩・無塩)の通販, https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E4%BD%8E%E7%B3%96%E8%B3%AA+%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3/-/tg1013845/
- 【事例】カフェメニューでプラスの売上づくり!SNSでの拡散で認知度もアップ – ぐるなびPRO, https://pro.gnavi.co.jp/magazine/t_res/cat_6/a_3868/
- 飲食店向けインスタ映え写真に対応したメニューの取り組み方 – FOOD-IN(フーディン), https://food-in.jp/entry/smartphone-shooting-008
- 第1回 冷凍めんの歴史を紐解く | 飲食店の経営環境を変える ~冷凍食品によるイノベーション Vol.1冷凍めん編 | 特集 | 外食産業の活性化を支援するサイト – 外食ドットビズ, https://gaisyoku.biz/article/reitoumen/400/
- 10月10日は冷凍めんの日!冷凍めんにはどんな種類がある? | なべやき屋キンレイ, https://www.kinrei.com/fan/news/column/201709/24110000.php
- 外食店利用時の注文ツールの利用実態・意向調査 | ホットペッパーグルメ外食総研「すべての人に, https://www.hotpepper.jp/ggs/research/article/column/20240722
- 外食店での利用経験率、セルフオーダー(自身のスマホ利用)57.1%、テイクアウト時のモバイルオーダー(事前注文や決済)48.8%。セルフオーダーが2021年調査(26.0%)と比べて急増 | 株式会社リクルート, https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/0722_14591.html
- 飲食店におけるHACCPとは?罰則や手引書を使った導入方法、役立つツールも紹介 – カミナシ, https://kaminashi.jp/media/haccp-restaurant
- HACCP義務化への飲食店の対応は?わかりやすい解説と対応Q&Aまとめ – フーズチャネル, https://foods-ch.infomart.co.jp/anzen/law/1625540541853
- 【2021年最新】労働基準法改正が勤怠管理にもたらす影響とは – OBC, https://www.obc.co.jp/360/list/post49
- 働き方改革にともなう法改正対応とFoodingJournal, https://foodingjournal.com/guide/work-style-reform
- インボイス制度が飲食店に与える影響とは?必要な対応と今からできる準備について解説 – Freee, https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_restaurant/
- インボイス制度が飲食店に与える影響は?必要な準備などを徹底解説, https://tax-startup.jp/feature/tax/19711/
- 事業者向け情報 | 食品ロスポータルサイト, https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/busi.html
- 特集「今日からできる食品ロス削減運動」 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2310/spe1_03.html
- MSC認証シーフードレストラン「BLUE」が世田谷にオープン – Marine Stewardship Council, https://www.msc.org/jp/what-you-can-do/media-centre/press-releases/msc%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3-blue-%E3%81%8C%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3
- 持続可能な漁業、養殖業の実現に向けて 「サステナブル・シーフード」を国内16施設で採用, https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/230927_ORIXGJ.html
- テイクアウトを、もっとエコに – リユース容器システムが創る、選ばれ続ける店づくりとビジネス価値の向上, https://kom-system.co.jp/reusable-container-eco-system/
- プラ循環法に対応、飲食店のためのプラスチック削減策8つ – table source, https://www.table-source.jp/column/plasticscycle-restaurant-8ideas/
- 【製粉業界徹底研究ガイド】概要と主要企業を一挙大公開! – 就活の未来, https://shukatsu-mirai.com/archives/57275
- 製粉業界研究 の解説 | バリュートレンド 長期投資家のためのIR情報, https://e-actionlearning.jp/guide/526
- 日清製粉株式会社採用情報, https://www.nisshin-recruit.com/seifun/hq/
- ソバ栽培の現状と課題。日本の生産状況、世界のソバ事情。, https://www.kaku-ichi.co.jp/media/crop/buckwheat-cultivation
- 白だし市場シェアNo.1「ヤマキ割烹白だし®500ml」が13年連続で伸長し過去最高売上に!~ アンバサダー・山崎育三郎さん出演のTVCMを4月13日(土)より放映 ~ | ニュースリリース, https://www.yamaki.co.jp/news_release/detail/2024_4_12_1/
- 【就活生必見】調味料の業界研究|事業構造・将来性・働き方など徹底解説, https://job-q.me/articles/13126
- 店舗数は2倍、売上高は4倍…いつの間に「丸亀製麺1強独走」になったのか? 丸亀・はなまる 「セルフうどん」2強の競争の歴史 – 東洋経済オンライン, https://toyokeizai.net/articles/-/900721?display=b
- 経営のプロも「ビジネスになるか!」と一喝してたのに…なぜ「セルフうどん」は全国を制覇? 丸亀製麺・はなまるうどんの歴史から読み解く – 東洋経済オンライン, https://toyokeizai.net/articles/-/900726?display=b
- うどん屋を開業するには?必要な資格や資金なども解説 – ビジネスaumo, https://business.aumo.jp/column/udon-open
- そば・うどん店開業の資金調達 | 飲食店開業マップ – テンポスドットコム, https://www.tenpos.com/kaigyo/openmap/soba-udon/soba-udon-business_plan/soba-udon-fundraising/
- 脱サラしてうどん屋を開業!必要資金や準備を徹底解説, https://www.fc-hikaku.net/dokuritsu_kaigyo/2833
- そば職人になるには?仕事内容や向いてる人も解説!, https://www.best-shingaku.net/s-matome/culinary/c002924.php
- 蕎麦職人ってどうやってなるの? 一人前になるまでの期間は約3年半 – 求人飲食店ドットコム, https://job.inshokuten.com/foodistMagazine/career/career_development/detail/34
- 丸亀製麺とはなまるうどん、どこで差が付いたのか 振り向けば「資さん」も……三つ巴の乱戦に?, https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2505/31/news013.html
- そば屋の人気チェーン店ランキングTOP10!みんながよく行くお店は? – マカロニ, https://macaro-ni.jp/116054
- 【そばチェーン】人気ランキングTOP15! 第1位は2年連続「ゆで太郎」に決定!【2021年最新投票結果】(1/4) – ねとらぼ, https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/287080/
- 最高にうまいと思う「そばチェーン」ランキングTOP29! 第1位は「富士そば」【2025年最新調査結果】(3/3) | チェーン店 ねとらぼリサーチ:3ページ目 – ITmedia, https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/3484769/3/
- 製粉業界の現状 製粉業は、粒のままでは利用できない小麦から小麦粉を製造し – ニップン, https://www.nippn.co.jp/ir/announcement/presentation/pdf/2023-5.pdf
- 【企業分析】株式会社丸亀製麵 – CareerAnchors, https://food.careerladder.jp/marugame/
- 優秀賞 – 日本サービス大賞, https://service-award.jp/result_case03/spring06.html
- 「富士そば」に外国人が殺到する理由は?人気メニュー・海外進出・今後の展開も解説 | 訪日ラボ, https://honichi.com/news/2020/05/29/inboundxfujisoba/
- 勝率を高めるマーケティング戦略の裏側 丸亀製麺式データサイエンス活用法【マーケティングアジェンダ2024 イベントレポート】 | 株式会社サイカ, https://xica.net/xicaron/eventreport_marketingagenda2024/
- 株式会社丸亀製麺 | マーケティング成功事例 – サイカ, https://xica.net/client-interview/marugame-seimen/
- 【2025年版】外食・飲食業界のM&A・事業承継の動向と実態, https://ma.sharemall.co.jp/columns/restaurant-industry-ma
- 外国人労働者の雇用状況に関する分析, https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2020/documents/235.pdf
- 飲食店経営者が意識すべき人時売上高の目安・労働分配率とは?人件費率を30%に抑えるだけじゃダメ!? – 店舗物件探し, https://www.inshokuten.com/foodist/article/4468/
- 飲食店経営の基本!人時売上高の重要性と上げる方法を解説 – HIRAKEL, https://www.stand-3.com/column/business-column/11284/
- 【都道府県別】配膳ロボット導入店舗48選!ロボットの導入効果も紹介 – DFA Robotics, https://dfarobotics.com/topics/0wcgld56sz/
- 丸亀製麺はなぜうどん業界でトップになれたのか? – Flier(フライヤー), https://www.flierinc.com/interview/interview110
- グローバル市場での勝ち方―大和ラーメン学校開設以来17年の積み重ねによるラーメン店店主も知らない課題解決:第五章 | 大和製作所, https://www.yamatomfg.com/info/problem-solving-5-global-market/
- フードロスよ、さようなら!食品ロスを削減する需要予測AIの活用事例まとめ – AIsmiley, https://aismiley.co.jp/ai_news/case-study-of-demand-forecasting-ai-to-reduce-food-waste/
- 飲食業界のこれからの新常識! 売上予測にAIを活用して食品ロス対策を – ガルフネット, https://www.gulfnet.co.jp/knowhow/59/
- 飲食店におけるAIの活用事例15選!売上UPやロス・人件費削減など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/restaurant-ai-cases/
- 来店来客数予測AI-Hawk-飲食店での需要予測導入事例| データによるロジカルツールで最強チームに – 株式会社ROX, https://www.rox-jp.com/example1
- 「惣菜盛り付けロボット」を共同開発/キユーピー、TechMagic – Robot Digest, https://www.robot-digest.com/contents/?id=1635301051-856205
- 外食産業の人手不足解消を目指す「調理ロボット」日米5社のスタートアップを紹介, https://www.atx-research.co.jp/contents/2024/04/14/cooking-robot
- I-Robo 2 | TECHMAGIC株式会社, https://techmagic.co.jp/i-robo2/
- 調理ロボットとは? 導入のメリットや 活用事例、おすすめのメーカーを解説 – JET-Robotics, https://jet-mfg.com/category/service-robots/restaurant-robot/cooking-robot/
- 【飲食店向けAIサービス10選】集客・接客・口コミ対応を自動化できる最新ツールまとめ(2025年最新版) | 飲食店集客情報メディア「リライト マガジン」, https://relight-consulting.com/magazine/ai-tools-for-restaurants/
- 店舗向けAIサービス「口コミコム」、日本最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」と公式連携開始, https://lab.kutikomi.com/news/restaurant/kutikomicomxtabelog/
- クチコミートが「食べログ連携」に対応|MEO分析の精度をさらに向上, https://blog.jarea.jp/seo/kuchikomeet-for-googlebussinessprofile/tabelog-integration
- AI・DXがスーパーマーケットを激変!最新テクノロジー事例をまとめて紹介 – 株式会社折兼, https://www.orikane.co.jp/orikanelab/34767/
- 飲食店におけるAI活用事例7選とChatGPTの活用術を紹介 | 飲食店集客.com, https://niigata-seo.com/restaurant/ai/
- 飲食店向け配膳ロボット導入で人手不足解消!回転率アップ! – 日本リテイルシステム株式会社, https://www.alljrs.co.jp/solution/hotel/haizenrobot/
- トリドールホールディングス(3397) 東証プライム 決算 | マーケット情報 | 松井証券, https://finance.matsui.co.jp/stock/3397/settlement/index
- (株)トリドールホールディングス【3397】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3397.T/financials
- 株主・投資家情報 | 株式会社トリドールホールディングス, https://www.toridoll.com/ir/library/
- 統合報告書 | IRライブラリ | 株主・投資家情報 | 株式会社吉野家 …, https://www.yoshinoya-holdings.com/ir/library/corporate_reports/
- IRストレージ「株式会社吉野家ホールディングス」のIR情報 – CCReB GATEWAY, https://ccreb-gateway.jp/company-information/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%89%E9%87%8E%E5%AE%B6%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9/?security_code=98610×=2025&listed=0&industrys=%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%A5%AD%E7%A8%AE&document_code=20
- 会社概要 – ゆで太郎, https://yudetaro.jp/company_outline/
- 株式会社ゆで太郎システムの企業情報 | インターンシップ・新卒採用情報からES・面接対策まで掲載!キャリタス就活, https://job.career-tasu.jp/corp/00091758/detail-uc/
- 株式会社ゆで太郎システム – ひとごと|優良企業のヒトづくり|hitogoto, https://hitogoto.jp/personel/yudetaro/
- 丹道夫の人生観|名代 富士そば(ダイタングループ), https://fujisoba.co.jp/company/president/
- 名代富士そば – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E4%BB%A3%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E3%81%9D%E3%81%B0
- 丹道夫 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E9%81%93%E5%A4%AB
- 生麺類業界を取り巻く環境、 直面する諸課題と取組み 平成28年3月23日 全国製麺協同, https://zenmenren.or.jp/about/pdf/160620.pdf
- 2024年版 惣 菜 白 書 拡大編集版 -ダイジェスト版- – 日本惣菜協会, https://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/wp-content/uploads/hpb-media/hakusho_2024digest.pdf
- 4-4 めん製造業の状況, https://kankyo.shokusan.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/r3-syokuloss-rpt_05.pdf
- 令和6年度 電子商取引に関する市場調査 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf
- 1.4%)となり、ここ数年では低落傾向となっている。(図表1) – 全国製麺協同組合連合会, https://zenmenren.or.jp/about/current_status_h16.html
- 生(餃子、焼売、雲呑、春巻)を製造する事業所の団体として、昭和35年9月に当会の前身である任意組織の全国製麺組合連合会が設立され, https://www.zenmenren.or.jp/about/active.html
- 生めん類業界の動向(平成21年版) – 全国製麺協同組合連合会, https://zenmenren.or.jp/about/current_status_h21.html
- うどん・そば市場が過去最大の市場規模に, https://menkaigyou.com/wp/%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93%E3%83%BB%E3%81%9D%E3%81%B0%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%8C%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%81%AB
- ソバ市場の規模とシェア、予測レポート2025-2034 – Global Market Insights, https://www.gminsights.com/ja/industry-analysis/buckwheat-market
- #613 そば・うどん店市場規模の推移 | 木下製粉株式会社, https://www.flour.co.jp/news/article/613/
- 冷凍麺 の市場ランキング | ウレコン, https://urecon.jp/categories/%E9%A3%9F%E5%93%81/%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E9%A3%9F%E5%93%81/%E5%86%B7%E5%87%8D%E9%A3%9F%E5%93%81/%E5%86%B7%E5%87%8D%E9%BA%BA/110723
- テーブルマークの冷凍麺※1が世界売上No.1としてギネス世界記録™︎に認定 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000075782.html
- 冷凍めんの製品革新と市場の展開 – 日本大学, https://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~imozuru/img/file10918.pdf
- チルド麺 値上げ響き需要停滞 価値訴求が浮上のカギ – 食品新聞, https://shokuhin.net/61706/2022/09/12/topnews/
- 冷凍麺・チルド麺の世界市場:2031年までの予測 – グローバルインフォメーション, https://www.gii.co.jp/report/qyr1771248-global-frozen-chilled-noodles-market-insights.html
- 生麺・冷凍麺特集2025 – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/special/1221055
- チルド麺市場 焼そば拡大 コメ代替など再評価 – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/news/kubo20250801041944889
- 外食産業の国内市場は2025年に35兆7116億円の見込 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25077
- 2024年版 外食産業マーケティング総覧 | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, https://www.yano.co.jp/market_reports/C66109300
- 外食主要カテゴリーの2030年市場を予測 | プレスリリース | 富士経済グループ, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=23139
- 富士経済、「2030年 外食市場将来予測と業態ビジネス変化」の調査 – マイライフニュース, https://www.mylifenews.net/drink-food/39891/
- 令和5年度の外食市場は+6.5%の31兆円強、矢野経済調べ, https://gohansaisai.news/news/article-10313/
- うどん麺市場の調査では、業界の成長見通しと2025年から2032年までの年平均成長率(C, https://pando.life/article/2428698
- 10年後を見据えた飲食店の課題 そば・うどん=目指そう“業態特化” – 日本食糧新聞・電子版, https://news.nissyoku.co.jp/restaurant/grs-142-0013
- 日本のパスタ・麺類市場規模・シェア分析・成長予測および調査報告書 2025~2035年, https://www.dreamnews.jp/press/0000332946/
- 今、外国人に「立ち食いそば」が大人気!その意外な理由とは? – 日本宿泊業支援協会, https://hotelsupport.jp/column/hospitality/064/
- 権八 GONPACHI|和食レストラン, https://gonpachi.jp/
- うどんのカロリー徹底解説!健康とダイエットに役立つ選び方・食べ方ガイド, https://hashizumen.shop/blogs/noodle-note/udon_guide
- 7月2日は「うどんの日」! うどんで美味しく「腸活」するコツ – こころ躍る、からだ喜ぶ JIDL, https://magazine.japan-ishokudougen.jp/n/n331a577c35ed
- うどんの栄養価を学ぶ:健康的なメリットとおすすめの具・副菜レシピ – そば処 更科, https://sobadokoro-sarashina.com/blog/20230823-4617/
- 2025年、飲食店の原価高騰が止まらない——食品値上げラッシュと経営戦略の再設計, https://gf-support.com/media/news/250425
- 冷凍食品の進化と歴史について, http://kannoseimenjo.com/dishes/2299/
- HACCP(ハサップ) – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
- インボイス制度と飲食店のレシートおよび領収書の関係について税理士が解説, https://some-rize.jp/blog/invoice/invoice_inshokuten/
- 海のおいしい魚を守るため「サステナブル・シーフード」を食べよう! | 日本財団ジャーナル, https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2025/109953/social_good
- 地球環境にやさしいテイクアウト容器を使うメリットとは | 山﨑株式会社, https://yamasaki.jp/archives/2122
- そば・うどん店 | 市場調査データ | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト], https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/restaurant/cons-soba-udon.html
- 小麦価格 | 1977-2025 データ | 2026-2027 予測, https://jp.tradingeconomics.com/commodity/wheat
- 業務用そば粉をお探しの方へ|そば粉・信州そば粉の製造販売 創業120年 蔵の粉屋 大西製粉, https://www.konaya.jp/pro/wholesale.html
- そば粉専門店のそば粉を通販で。信州の本格石臼挽そば粉屋 倉科製粉所, https://sobakoya.com/item-list?categoryId=77633
- そば粉比率 低い格安立ち食いに対し大手チェーンは品質向上 – NEWSポストセブン, https://www.news-postseven.com/archives/20140727_265599.html?DETAIL
- 大手企業の導入事例にみる配膳ロボット活用のポイントとは – NECプラットフォームズ, https://www.necplatforms.co.jp/solution/food/column/column67.html
- ロボットが調理する時代が到来!?恵比寿に「Magic Noodle 香味麺房」がオープン。自動調理ロボットの開発を行うTechMagic直営のスパイスヌードル専門店 – フードスタジアム, https://food-stadium.com/headline/32630/
- そば屋は初期投資額が高い?そば職人・最上はるかさんに真相を直撃! – カルク, https://www.calq.jp/column/feature/2016-10-07/
- うどん県からは,なぜ,うどん屋チェーンが出ないのか?, https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/6719/files/AN00038281_86_417_426.pdf
- 丸亀製麺とはなまるうどんを比較 どっちのメニューがお得? – マネーポストWEB, https://www.moneypost.jp/183252
- J.D. パワーによる顧客満足度調査で18年連続No.1を受賞 | ニュース一覧, https://www.ctc.co.jp/news/2023/20231018/
- おかげさまでリコージャパンはお客様満足度No.1, https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan/cs/jdpower
- 【J.D. パワー2025 年法人向け通販サービス顧客満足度調査 】オフィス部門「Amazon Business」, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000358.000042677.html
- 外食市場調査(2025年7月度) | ホットペッパーグルメ外食総研「すべての人に、食で笑顔を。」, https://www.hotpepper.jp/ggs/research/article/marketing/202507
- 【2025年4月】外食市場3040億円!ファスト需要増と価格意識の高まりを読む, https://fs-ring.jp/news_trend/1279/
- 外食市場の最新動向と「飲みたい街ランキング2025」を発表!無料オンラインセミナー開催 – 食団連, https://shokudanren.jp/partner/activies/g5Joo80e
- 2025年1月の外食市場動向!飲食店が取るべき最新戦略とは, https://fs-ring.jp/news_trend/1211/
- 外国人に人気の日本食とは?人気の理由や苦手な料理も解説! – リゾLAB(リゾラボ), https://www.resort-lab.com/n/n1becda5391f6
- 観光客の「コト消費」のメインは日本食! 人気の理由&国別の日本食に対する姿勢を徹底解説します! – Guidable, https://guidable.co.jp/marketing/contents/post-606/
- 欧米豪の訪日客が好む「日本食」体験と傾向 – 世界最大級の英語訪日メディア – ジャパンガイド, https://japan-guide.co.jp/blog/japanese-food-and-experiences-preferred-by-overseas-visitors-to-japan/
- インバウンド需要における「食」への期待 – Research Focus, https://www.jri.co.jp/file/report/researchfocus/pdf/15255.pdf
- 需要拡大に向けた主要農水産物サプライチェーンに おける課題と取り組むべき方向 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/attach/pdf/170731_30kyokyu4.pdf
- 全国蕎麦製粉協同組合-蕎麦粉・蕎麦の実・手打ち蕎麦-, http://www.sobako.or.jp/
- サイカ、トリドールホールディングスと丸亀製麺が推進する「心的資本経営」の支援において外食業界初の分析メソッドを共同で開発 「従業員の幸せ」と「お客様の感動」が事業成果に与える影響を明らかに – サステナビリティアクション, https://sustainability-action.jp/1768/
- 蕎麦の原価とは?知っておきたい費用の内訳 | ブログ – そば処 更科, https://sobadokoro-sarashina.com/blog/20241008-26378/
- 生そば専門店 – フードビジネス.com|船井総研の経営コンサルティング, https://food-business.funaisoken.co.jp/biz_eat_out/biz_eat_out_solution/soba/
- 【そば屋の売上アップ術】原価率を抑えて利益を最大化!人気の低コストメニュー5選, https://www.tenpos.com/foodmedia/newstrend/33543/
- 蕎麦屋・うどん屋の原価率・利益率の平均値は?経営分析に役立つ指標5つを解説!, https://satoscpa.com/column/keieishihyo-soba-udon
- 株主・投資家情報 | 株式会社吉野家ホールディングス, https://www.yoshinoya-holdings.com/ir/
- 株式会社ゆで太郎システム(東京都品川区 / 未上場) – ナレッジエンジン, https://baseconnect.in/companies/e4f5f0f7-4472-4d12-90b0-137359665526
- 株式会社ゆで太郎システム の企業情報 – 社長名鑑, https://shachomeikan.jp/corporations/22438
- ゆで太郎 – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%86%E3%81%A7%E5%A4%AA%E9%83%8E
- 業界毎特集記事-ダイタンホールディングス株式会社 代表取締役 丹 有樹 – 社長名鑑, https://shachomeikan.jp/industry_article/4604
- 「名代 富士そば」の成長を支える“情と理”の経営哲学 – PHPオンライン, https://shuchi.php.co.jp/article/7209
- 飲食店の平均的な売上はいくら?1日・1ヶ月・年間の期間ごとの目安と計算方法を解説, https://www.tenant-p.jp/TenantPlaza3/column/16-kyoto-uriage.jsp
- 製造業の人時生産性向上のポイントは?業種別平均値、計算式も解説 – 現場改善ラボ – tebiki, https://tebiki.jp/genba/useful/man-hour-productivity
- 人時売上高の目安とは?飲食店における人員数の決め方と計算方法 – canaeru(カナエル), https://canaeru.usen.com/opening/zyunbi441.html
- 【導入事例】はなまるうどんがCRM施策をモニプラに全面移管、顧客データのマーケティング活用を開始 | アライドアーキテクツ株式会社, https://www.aainc.co.jp/news-release/2016/01268.html
- 細麺が切り拓く、麺ビジネスの新しい未来 – 大和製作所, https://www.yamatomfg.com/info/rocky-fuji-mail-archive/turn-problems-into-advantages-noodle-business/
- みんな大好き “麺”ビギナーズ | おいしさを支える研究と技術 | 食と健康Lab | 太陽化学株式会社, https://www.taiyokagaku.com/lab/taste/12/
- 世界が認める日本のラーメン、うどん、蕎麦だけど外国人に嫌われているNo.1は?外国人に聞いてみた!, https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-tokyo_train_station/article-a0001895/
- M&A調査レポート 飲食業界の事業承継に関する実態調査実施 – M&Aキャピタルパートナーズ, https://www.ma-cp.com/about-ma/survey/027/
- 在庫管理をAIに任せてフードロス削減!実践店舗の成功事例 – 飲食AIナビ, https://inshokuai.jp/ai-operation-dashboard-guide/
- AIとDXが飲食店・外食産業を変える!事例をまとめて紹介 – 株式会社折兼, https://www.orikane.co.jp/orikanelab/35101/
- 飲食店の食品ロス削減法|AI活用の具体例と成功事例 – Hakky Handbook, https://book.st-hakky.com/industry/reducing-food-waste-in-restaurants-with-ai
- 飲食業界でのAI活用事例!人手不足解消・売上を予測する方法とは? – MatrixFlow, https://www.matrixflow.net/case-study/64/
- 飲食店×AI活用事例10選!前年比120%に売上向上した理由は? | AI Front Trend, https://ai-front-trend.jp/ai-restaurants/
- ぐるなび、生成AIを活用した飲食店検索アプリ「UMAME!」β版をリリース 会話や画像から店を提案, https://markezine.jp/article/detail/48098
- AIレビュー・口コミ管理システム15選!評判・料金・導入パターンを徹底解説 – バクヤスAI 記事代行, https://bakuyasu.techsuite.co.jp/34864/
- AIにお任せ!飲食店の口コミ返信を自動化するツール5選【2025年最新版】, https://inshokuai.jp/ai-review-reply-tools/
- アナログ接客がファンを作る|小さなお店の事例 – 飲食AIナビ, https://inshokuai.jp/analog-service-fan-strategy/
- 飲食店のLINE公式アカウントの集客活用方法:成功事例と合わせて紹介 | Mico(ミコ), https://mico-inc.com/blog/line-restaurant/
- 配膳ロボットとは?おすすめロボット・事例・特徴をわかりやすく解説 – AI総合研究所, https://www.ai-souken.com/article/what-is-serving-robot
- 配膳ロボットの時給はいくら? 導入価格と人件費を比較した費用対効果を解説 – JET-Robotics, https://jet-mfg.com/contents/serving-robot-hourly-wage/
- 配膳ロボット導入で得られる3つのメリットと2025年最新市場動向【人手不足・コスト削減・衛生対策】, https://www.hawksvision.co.jp/robot-maintenance/rubots-three-merits/
- 配膳ロボットの主要機種を比較!メリット、注意点、選定ポイントは?, https://012cloud.jp/article/serving-robot
- 配膳ロボットの価格相場は?時給・人件費と比較した費用対効果や主な機能を紹介, https://www.foodtechjapan.jp/hub/ja-jp/blog/article_073.html
- 配膳ロボットとは? おすすめのメーカーや導入のメリット、選び方を解説 – JET-Robotics, https://jet-mfg.com/category/service-robots/restaurant-robot/serving-robot/