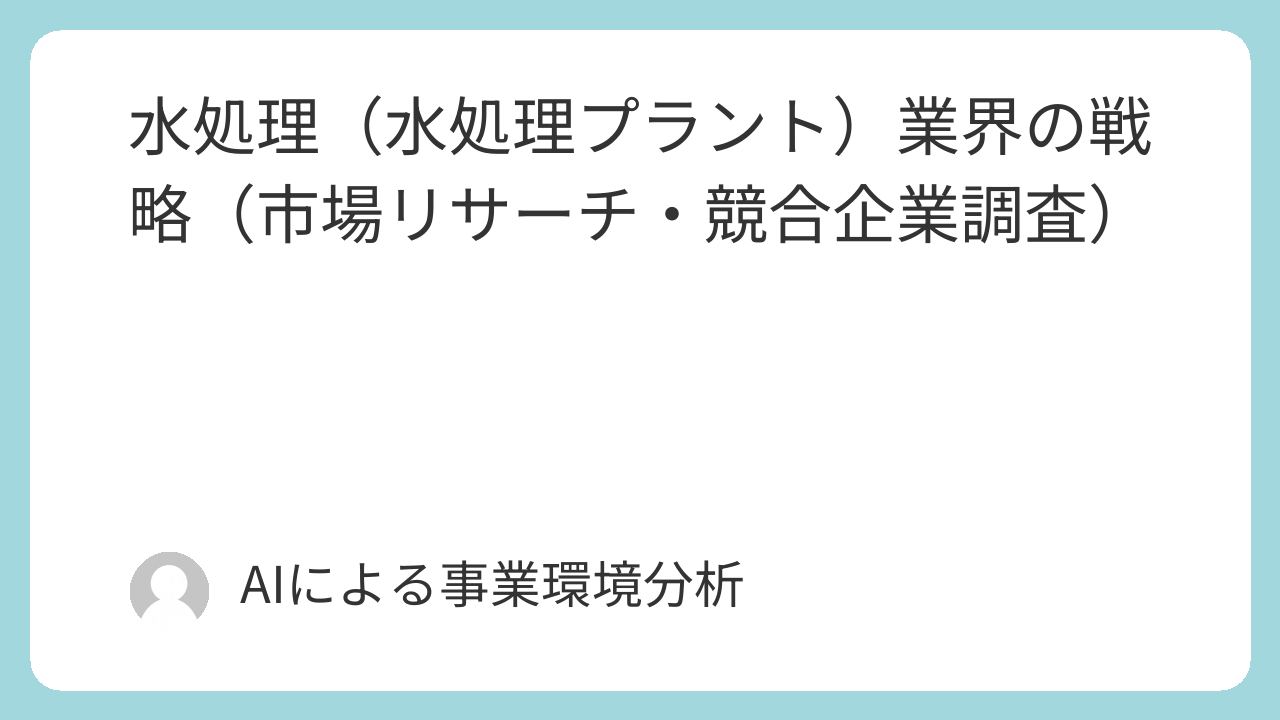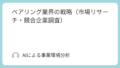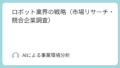資源循環とデジタル化が拓く次世代水インフラ:水処理業界の持続的成長戦略
第1章:エグゼグティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、世界的な水リスクの増大、既存インフラの老朽化、そしてデジタル技術がもたらす産業変革というマクロ環境下において、水処理業界で持続的な競争優位を確立し、成長を遂げるための事業戦略策定を支援することを目的とします。調査範囲は、地方自治体が管轄する上下水道、産業分野における用水・排水処理、水不足解決の切り札となる海水淡水化、そして水再利用に関わるプラントエンジニアリング(EPC:設計・調達・建設)、運転・維持管理(O&M)、関連する機器・部材市場をグローバルに網羅します。
最も重要な結論
水処理業界は、社会インフラとしての安定性を維持しつつも、従来の「コストセンター」から脱却し、水・エネルギー・有価物を回収し、データを活用して新たな価値を創出する「プロフィットセンター」へと転換する歴史的な変曲点にあります。この変革を主導するのは、以下の3つの潮流が複合的に作用した結果です。
- サーキュラーエコノミー(資源循環)の実装: 排水を単なる処理対象ではなく、リンやエネルギーといった有価物を生み出す「資源」と捉える動きが本格化しています。
- AI/IoTによる「スマートウォーター」の進展: デジタル技術がプラントの自律運転や予知保全を可能にし、ビジネスモデルを従来の設備提供からサービス提供(Water as a Service)へと進化させます。
- 経済安全保障との一体化: 半導体産業に代表される先端産業や国民生活にとって、水の安定供給は国家の競争力と安全保障を左右する戦略的要素として、その重要性を増しています。
主要な推奨事項
本分析から導き出された、取るべき事業戦略上の主要な推奨事項は以下の通りです。
- 事業ポートフォリオの再構築: 従来のEPC(フロー収益)への偏重から、20年以上の長期契約に基づくO&M、資源売却益、データ解析サービスといった安定的かつ高収益なストック型収益事業への戦略的シフトを加速させるべきです。
- デジタル・ケイパビリティの獲得: AIを活用した自律運転・予知保全技術への研究開発投資を最優先課題とし、データサイエンティストやAIエンジニアの獲得・育成に注力する必要があります。自社開発に固執せず、IT企業との戦略的提携やM&Aを積極的に検討することが不可欠です。
- 高付加価値市場への集中: 超純水供給が事業の生命線となる半導体産業や、気候変動により水不足が深刻化する地域(中東、北アフリカ等)での海水淡水化・水再利用など、高度な技術的優位性と地政学的なニーズが合致する高成長・高収益セグメントに経営資源を集中投下します。
- サービスモデルへの転換: 設備を所有・販売するモデルから、顧客が必要とする水質・水量をサービスとして提供し、その価値に対して対価を得る「Water as a Service (WaaS)」モデルへの移行を目指します。まずは特定の顧客セグメントでパイロットプロジェクトを開始し、ノウハウを蓄積することが重要です。
第2章:市場概観(Market Overview)
世界の水処理市場規模の推移と今後の予測(2020年~2035年)
世界の水処理市場は、今後も着実な成長が見込まれます。世界的な人口増加、都市化の進展、そして産業発展を背景に、水需要は2050年まで年率約1%で増加し続けると予測されています 1。国連の報告によれば、2022年時点で世界人口の約4分の1にあたる22億人が安全に管理された飲料水を利用できず、35億人が基本的な衛生設備へのアクセスを持たない状況にあります 2。この巨大な需給ギャップと、持続可能な開発目標(SDGs)の目標6「安全な水とトイレを世界中に」の達成に向けた国際的な要請が、市場の基盤的な成長を力強く牽引しています。
主要な市場調査会社の分析によると、世界の水・排水処理市場は2035年に向けて年平均成長率(CAGR)5~7%程度で拡大を続けると予測されています。
地域別分析
- 北米・欧州: 既存インフラの老朽化対策(更新投資)が市場の大部分を占めます。加えて、PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)のような新たな汚染物質に対する規制強化が、高度処理技術の導入を促進しています 2。
- 中国・東南アジア: 急速な工業化と都市化に伴う新規の水インフラ需要が市場成長を牽引しています。環境規制の強化も追い風となり、特に省スペースで高度な処理が可能なMBR(膜分離活性汚泥法)技術の採用が活発化しています 3。
- 中東・北アフリカ: 深刻な水不足を背景に、国家規模の大型海水淡水化プロジェクトが市場を牽引しています。ヨルダンが計画する100億ドル規模の「紅海・死海プロジェクト」のような超大型案件が象徴的です 3。
用途別分析
- 上下水道(Municipal): 市場の基盤をなす安定したセグメントです。今後は、官民連携(PPP/PFI)モデルの導入による効率的な事業運営と、デジタル技術を活用したO&Mの高度化が主要テーマとなります。
- 産業(Industrial): 特に高い成長が期待されるセグメントです。半導体製造に不可欠な超純水、製薬、食品・飲料など、極めて高い水質と供給の安定性が事業継続の鍵となる分野で、高度な水処理ソリューションへの需要が拡大しています。
技術・プロセス別分析
膜処理技術、特にRO(逆浸透膜)、UF(限外ろ過膜)、MBRが市場全体の成長を牽-引しています。中でもRO膜市場は、海水淡水化や水再利用の需要拡大を背景に、2024年の102億ドルから2035年には204億ドルへと倍増すると予測されています(CAGR 6.52%)4。
主要な市場成長ドライバーと阻害要因
| ドライバー | 阻害要因 |
|---|---|
| ① 世界的な水ストレスの増大と水不足の深刻化 1 | ① 巨額な初期投資と長期にわたる資金回収期間 |
| ② PFASなど新規汚染物質に対する水質規制の厳格化 2 | ② 公的機関の財政難と投資の遅延 |
| ③ 先進国におけるインフラ老朽化対策(更新需要) | ③ 熟練技術者およびデジタル人材の不足 6 |
| ④ 半導体産業などにおける経済安全保障上の要請 | ④ 複雑な規制と許認可プロセス |
| ⑤ 資源回収・省エネ技術に対する政策的インセンティブ | ⑤ 政治・社会情勢の不安定化 |
業界の主要KPIベンチマーク分析
業界をリードする主要企業(例:Veolia, 栗田工業, オルガノ)のIR資料を分析すると、事業ポートフォリオの収益構造に変化が見られます。従来のEPC事業は売上規模が大きいものの利益率は一桁台で変動が激しい一方、O&Mや薬品・サービス事業は、売上規模は比較的小さいものの、10%を超える安定した利益率を確保しています。この事実は、事業の重心をフロー収益であるEPCから、ストック収益であるサービス事業へとシフトさせることが、持続的な成長と収益性向上の鍵であることを示唆しています。
市場の動向を深く分析すると、二つの重要な構造変化が浮かび上がります。第一に、市場は「量の拡大」と「質の深化」という二極化の様相を呈しています。国連のデータが示すように、基本的な水アクセスが欠如している数十億人規模の市場(主に新興国)が存在する一方で、PFAS規制強化や半導体産業の超純水ニーズに代表される、より高度な処理技術が求められる「質の深化」市場(主に先進国)が拡大しています 2。この二極化は、企業がグローバル戦略を策定する上で、地域や顧客セグメントごとに最適化された技術ポートフォリオ、価格戦略、ビジネスモデル(例:低コストで頑健な分散型システム vs. 高度なWaaSモデル)を使い分ける必要性を示唆しており、画一的なアプローチは成功を困難にします。
第二に、水問題の捉え方が「環境問題」から「経済・安全保障問題」へと大きくシフトしています。過去20年間で水関連災害がもたらした経済損失は約7000億ドルに上り 1、現状のまま水不足が進行すれば2050年までに世界のGDPの45%がリスクに晒されるとの予測もあります 7。これは、水インフラへの投資がもはや単なる社会的費用ではなく、経済成長と国家の安定を支えるための必須投資であるという認識への転換を意味します。この認識の変化は、今後、大規模な公的資金や民間資金の流入を促し、市場全体のパイを拡大させる強力な追い風となるでしょう。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
政治(Politics)
- 公的投資の拡大: 各国政府は、水インフラを経済成長と国民生活の基盤と位置づけ、大規模な投資計画を推進しています。米国の「超党派インフラ法(Bipartisan Infrastructure Law)」では、水道管の更新や排水処理施設の近代化に数百億ドル規模の予算が計上されており、市場を直接的に刺激しています 9。
- PPP/PFIの推進: 多くの国で、公的機関の財政難を背景に、民間の資金とノウハウを活用するPPP(Public-Private Partnership)/PFI(Private Finance Initiative)が推進されています。特に、事業運営権を長期間民間に委ねるコンセッション方式は、水道事業の効率化とサービス向上を実現するモデルとして注目されています。
- 国家戦略としての水: 水資源は、国家の産業競争力、特に半導体のような先端産業の立地を左右する戦略的資源としての重要性を増しています。安定した超純水の供給能力は、経済安全保障の根幹をなす要素と見なされるようになっています。
経済(Economy)
- 金利政策の動向: 水インフラ事業は、巨額の初期投資と20年以上にわたる長期契約が前提となります。そのため、金利の上昇は資金調達コストを直接的に増大させ、PPP/PFIプロジェクトの採算性や事業化判断に大きな影響を与えます。
- エネルギー・薬品価格の変動: O&Mコストの中で大きな割合を占めるのが電力費と薬品費です。これらの価格高騰は、プラント運営者の収益を圧迫する一方、エネルギー効率に優れたRO膜や、薬品使用量を最適化するAI自律運転システムといった省エネ・省資源技術の価値を相対的に高める要因となります 11。
社会(Society)
- 専門人材の不足と高齢化: プラントの設計・運転を担ってきた熟練技術者の高齢化と大量退職は、業界全体が直面する深刻なリスクです 6。この人材不足は、技術継承を困難にすると同時に、省人化や自律化を可能にするデジタル技術への需要を加速させる最大の要因となっています。
- 市民意識の変化: マイクロプラスチックや医薬品といった新たな汚染物質に対する懸念や、公衆衛生、環境保全に対する市民の意識向上は、行政に対してより高度な水処理を求める圧力となり、新たな投資を後押しします。
技術(Technology)
- 膜技術の継続的な進化: RO膜をはじめとする膜技術は、日進月歩で進化を続けています。有機物による汚れ(ファウリング)への耐性向上、より少ないエネルギーで水を透過させる高効率化、塩素への耐性を高めた新素材の開発などは、海水淡水化や水再利用の経済性を根本から変え、適用可能な範囲を広げています 4。
- デジタル技術の普及: 低価格で高性能なIoTセンサー、膨大なデータを処理するクラウドコンピューティング、そしてAI/機械学習プラットフォームの普及が、リアルタイムでの遠隔監視、自律運転、予知保全といった「スマートウォーター」の実現を加速させています。
法規制(Legal)
- 水質基準の厳格化: 「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFASなど、これまで規制対象でなかった新たな汚染物質に対する排出基準や飲料水基準が世界各国で導入・強化されています 2。これは、活性炭やイオン交換樹脂、特殊なRO膜といった高度処理技術の新たな市場を創出しています。
- 資源循環関連法: 廃棄物処理法や再生可能エネルギー関連法(FIT制度など)の動向は、下水汚泥から回収されるバイオガスによる発電事業や、リンの肥料化といった資源回収ビジネスの採算性に直接的な影響を与えます。
環境(Environment)
- 気候変動の影響: 気候変動に起因する渇水や豪雨の頻発・激甚化は、従来の天水やダムへの依存のリスクを浮き彫りにしました 1。これにより、天候に左右されない安定的な水供給源としての海水淡水化や水再利用の戦略的価値が飛躍的に高まっています。
- カーボンニュートラルへの要請: 水処理プロセスは大量のエネルギーを消費するため、業界全体としてカーボンニュートラルへの貢献が強く求められています。プロセスの徹底的な省エネ化と、バイオガス発電のようなエネルギー創出(創エネ)技術の導入が、プラントの設計・運用における必須要件となりつつあります。
マクロ環境を分析すると、重要な力学が見えてきます。「技術の進化」と「規制の強化」は、互いに影響を与えながら市場のゲームのルールを書き換えています。例えば、PFASのような新たな汚染物質が社会問題化し(社会)、それを受けて政府が厳しい排水・飲料水基準を導入する(法規制)。既存技術では対応できないため、この規制をクリアできる新しい膜技術や吸着技術への需要が生まれ(技術)、その技術を持つ企業は規制によって創出された新たな高付加価値市場で先行者利益を獲得できます。これは、技術開発が規制動向を先読みして行われるべきであり、時にはロビー活動も競争戦略の重要な一部となることを示唆します。
また、熟練技術者の不足という課題は、単なる「脅威」として捉えるべきではありません。むしろ、これはデジタル化による高付加価値サービスへの転換を促す最大の「機会」です。経験と勘に頼った従来のO&Mが維持不可能になるという危機感が、遠隔監視、自動運転、予知保全といったデジタルソリューション導入の強力な動機付けとなります。そして、デジタル化によって収集されたデータは、単に省人化に貢献するだけでなく、顧客に対してより効率的なプラント運用(省エネ、薬品削減)を提案する新たなコンサルティングサービスの源泉となります。結果として、人材不足という課題が、労働集約的なO&Mから知識集約的なデータサービスへの事業モデル変革を強制的に後押しする構造になっています。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
売り手の交渉力:中~高
水処理プラントの性能を決定づけるコア部材を供給する専門メーカーは、比較的強い交渉力を持ちます。特に、DuPont(旧Dow)、東レ、日東電工などがしのぎを削る高性能RO膜市場や、特殊な計測機器、特定の汚染物質を除去する専用薬品などを供給するメーカーは、その技術的優位性から価格決定力が高く、代替が困難な場合があります。
買い手の交渉力:高
買い手である地方自治体や大手製造業の交渉力は、総じて強いと言えます。
- 官公庁: 地方自治体などの公共セクターは最大の買い手であり、その調達は競争入札が基本となります。これにより価格競争が激化しやすくなります。近年は、初期投資額だけでなく、長期的な運転コストを含めたライフサイクルコスト(LCC)や、財政負担の平準化が重視される傾向にあります。
- 大手製造業: 半導体メーカーのようなハイテク産業は、超純水の安定供給が生産ライン全体を左右するため、品質と信頼性を最優先します。しかし、同時にグローバルなコスト競争に晒されており、サプライヤーに対して厳しい価格交渉を行います。
新規参入の脅威:中
水処理業界への新規参入には、いくつかの高い障壁が存在します。巨額な初期投資、プラント運営に関する豊富な実績とノウハウの蓄積、そして官公庁との長期的な信頼関係は、一朝一夕に構築できるものではありません。しかし、異業種からの参入の脅威は増大しています。
- IT企業: AIやデータ分析に強みを持つIT企業(例:Google, Microsoft, Amazon Web Services)が、データプラットフォームや最適化アルゴリズムの提供者として参入し、業界の付加価値の源泉を奪う可能性があります。
- 総合商社: 事業開発能力とファイナンス機能を武器に、PPP/PFI事業における事業運営権(コンセッション)の獲得を目指して参入するケースが増えています。
- 海外水メジャー: VeoliaやSuezといったグローバルな水事業会社が、M&Aを通じて日本市場への参入や事業拡大を図る動きも続いています。
代替品の脅威:中
既存の大規模集中型水処理プラントに対する代替の脅威も存在します。
- 分散型水処理システム: コンテナに処理機能を搭載した移動式システムや、特定地域・工場内で水を循環させる小規模なシステムが、人口減少が進む過疎地、インフラ未整備の新興国、災害時の緊急対応、そして特定ニーズを持つ工場向けソリューションとして、大規模プラントを代替する可能性があります。
- 源流での対策: 工場内での排水を高度に処理し、再利用することで外部への排出をゼロにするクローズドループ化(無排水化)や、革新的な節水技術の普及は、そもそも「処理」すべき水の量を減らし、市場全体の成長を抑制する方向に作用します。
業界内の競争:高
業界内の競争は極めて激しい状況です。日立製作所、栗田工業、オルガノ、メタウォーターといった総合水事業会社間の競争に加え、EPC分野では大手ゼネコンやプラントエンジニアリング会社、事業運営では総合商社など、多種多様なプレイヤーがそれぞれの強みを活かして競合しており、競争環境は複雑化しています。
この業界構造分析から、競争の力学における重要な転換点が明らかになります。競争の主戦場は、プラントをいかに安く、早く建設するかという「土木・建設」の領域から、プラントのライフサイクル全体を通じていかに効率的に運転し、価値を生み出すかという「データ・アルゴリズム」の領域へとシフトしつつあります。買い手の関心がLCCに移る中、運転効率を最大化するAIによる自律運転や予知保全のアルゴリズムが競争優位の源泉となります。これにより、データ分析に強みを持つIT企業が新たな脅威として浮上し、既存プレイヤーも競争力の基盤をハードウェアの建設能力からソフトウェア(データ解析能力)へと移さなければ、コモディティ化し収益性が低下するリスクに直面します。
同時に、業界のアンバンドリング(分解)とリバンドリング(再結合)が進行しています。従来、水事業は「設計から建設、運転まで」を一貫して行う垂直統合モデルが主流でした。しかしデジタル化は、特定の機能(例:データ監視プラットフォーム)に特化した専業プレイヤーの参入を容易にし、バリューチェーンを「アンバンドリング」しています。一方で、総合商社や水メジャーは、ファイナンス、事業運営、デジタルソリューションを組み合わせて「水の安定供給」という最終価値を提供する「リバンドリング」されたサービス(WaaS)を目指しています。これらの動きは、自社がバリューチェーンのどこで、どのような形で価値を提供するのか、戦略的な再定義を迫るものです。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析
水処理業界の伝統的なサプライチェーンは、コアとなる機器・部材メーカー(ポンプ、膜、薬品など)から、プラントエンジニアリング会社がそれらを調達・設計し、建設会社が施工を行い、最終的に施主(自治体、民間企業)に引き渡されるというリニアな構造を取っています。
このサプライチェーンには、近年新たなリスクが顕在化しています。世界的な半導体不足は、プラントの自動制御に不可欠なPLC(Programmable Logic Controller)や高度なセンサーの納期遅延を引き起こし、プロジェクトの工程に影響を与えています。また、特定の国に製造が集中している特殊な部材は、地政学的な緊張の高まりによって調達が不安定になるリスクを抱えています。サプライチェーンの強靭性を高めるため、調達先の多様化や代替部材の確保が重要な経営課題となっています。
バリューチェーン分析
水処理事業のバリューチェーンは、「研究開発 → 営業・コンサルティング → 設計(EPC) → 建設 → 運転管理・保守(O&M) → アセットマネジメント・最適化提案」という一連のプロセスで構成されます。このバリューチェーンにおける価値の源泉は、時代と共に大きく変化しています。
価値の源泉のシフト
- 過去: 価値の源泉はEPCに集中していました。プラントを建設・納入する段階で一括して大きな売上と利益(フロー収益)を計上するビジネスモデルが主流でした。
- 現在・未来: 価値の源泉は、バリューチェーンの下流へと大きくシフトしています。20年以上にわたる長期のO&M契約や、プラントの運転データを活用した省エネ・効率化コンサルティング、そしてインフラ全体の最適な更新計画を提案するアセットマネジメントが、安定的で利益率の高いストック収益を生み出す源泉となっています。
この価値のシフトは、以下の図で視覚的に理解することができます。
図:水処理業界のバリューチェーンと利益プールの変化
| |
| 高 <--- 利益率 ---> 低 |
| |
| 未来の利益プール ----- |
| / |
| / |
| / |
| / O&M, データサービス, |
| / アセットマネジメント |
| / |
| 過去の利益プール --- |
| / \ |
| / EPC \ |
| / \ |
|-----+-------------------------------+------> バリューチェーン
R&D 営業 EPC 建設 O&M アセットマネジメント
(注:上記はMarkdownによる概念図です)
このバリューチェーンの変化は、事業戦略に根本的な転換を迫ります。従来のEPCビジネスは、プラントという「アセット(資産)」を売るモデルであり、価格競争に陥りやすい構造にありました。対照的に、O&Mやデータサービスは、そのアセットが稼働することで生まれる「アウトカム(成果)」(例:安定した水質、削減されたエネルギーコスト、計画的な設備更新)を売るモデルです。顧客、特に民間企業は、プラント自体が欲しいのではなく、自社の事業に必要な品質・水量の水を、低コストかつ安定的に手に入れるという「成果」を求めています。したがって、バリューチェーンの上流(EPC)で短期的な利益を確保するのではなく、下流のO&Mやデータサービスで顧客と長期的な関係を築き、成果に連動した報酬(レベニューシェアなど)を得るビジネスモデルを構築することが、持続的な高収益につながる道筋です。
この変革を実現する上での中核技術が「デジタルツイン」です。デジタルツインは、物理的なプラントを仮想空間上に精緻に再現したモデルであり、バリューチェーン全体を統合し、新たな価値を創出するプラットフォームとなります。設計段階(EPC)では、建設プロセスや将来の運転をシミュレーションし、コストとリスクを低減します。建設後は、リアルタイムのセンサーデータと連携し、O&Mの効率化(自律運転、予知保全)を実現します。さらに、蓄積されたデータを用いて、将来の設備更新計画(アセットマネジメント)を最適化する提案を顧客に行うことが可能になります。このように、デジタルツインは、従来分断されがちだったバリューチェーンの各段階をデータで繋ぎ、インフラのライフサイクル全体での価値最大化を可能にする、ビジネスモデル変革の鍵となる技術です。
第6章:顧客需要の特性分析
官公庁セグメント
- 課題: 高度経済成長期に建設されたインフラの一斉老朽化、厳しい財政状況、水道事業を担う専門職員の不足と高齢化、そして災害の頻発化・激甚化への対応、住民への説明責任などが挙げられます。
- ニーズ: 求められる価値は、①初期投資だけでなく維持管理・更新費用まで含めたライフサイクルコスト(LCC)の最小化、②PFI/コンセッション方式の活用による財政負担の平準化、③運転管理の外部委託による業務効率化と責任の明確化、④地震や豪雨などの災害時にも水道供給を維持できる強靭なインフラの構築です。
- KBF (Key Buying Factor): 最終的な意思決定を左右する要因は、価格だけでなく、長期にわたる安定した事業運営実績とそれに裏打ちされた信頼性、透明性の高いコスト体系、そして議会や住民に対して事業の妥当性を説明できる能力です。
電子・半導体セグメント
- 課題: 半導体回路の微細化プロセスの進展に伴い、製造に用いる超純水(UPW: Ultra Pure Water)への要求水準は極限まで高まっています。また、世界的な半導体需要の拡大に伴う工場の新増設は、水使用量の増大と、立地地域の水需給逼迫という課題を生んでいます。さらに、サプライチェーン全体での環境負荷低減(ウォーターフットプリント削減)への要請も強まっています。
- ニーズ: 求められる価値は、①不純物を限りなくゼロに近づける極めて高いレベルでの水質保証、②1秒たりとも許されない生産ラインの停止を避けるための絶対的な安定供給(供給信頼性)、③工場内で使用した排水を高度に処理し、回収・再利用することによる水使用量の抜本的な削減です。
- KBF: このセグメントの顧客がパートナーを選ぶ際の決定要因は、半導体の製造プロセスに対する深い理解、最先端の膜処理技術やイオン交換技術、トラブル発生時に迅速に対応できるサービス体制、そしてデータに基づいて水使用量の最適化を提案できるコンサルティング能力です。
食品・飲料セグメント
- 課題: HACCP(ハサップ)に代表される厳格な衛生基準への対応、製品の味や品質を直接左右する用水の水質管理、そして企業のブランドイメージを維持するための環境負荷低減(排水の水質、エネルギー消費量など)が主な課題です。
- ニーズ: 求められる価値は、①製品の安全・安心を担保する用水の安定供給、②BOD(生物化学的酸素要求量)やCOD(化学的酸素要求量)といった指標に関する排水規制の遵守、③排水処理の過程で発生する有機物からバイオガスを回収・発電するなど、コスト削減と環境貢献を両立するソリューションです。
- KBF: 業界特有の規制やプロセスへの知見、コスト効率の高いソリューションの提案能力、そして企業のサステナビリティ報告にも貢献できるような環境価値の提案力が、重要な購買決定要因となります。
これらの顧客セグメント分析を通じて、顧客のKBFが「コスト」から「リスク管理と価値創造への貢献」へと質的に変化していることが明らかになります。官公庁は、単なる建設コストの安さよりも、財政破綻リスクやインフラ機能停止リスクをいかに管理できるかを重視しています。半導体メーカーにとっては、水供給の不安定性がもたらす巨額の生産停止リスクを回避することが最優先課題です。食品メーカーは、環境負荷によるブランド価値の毀損リスクを避けたいと考えています。これらの顧客は、もはや最安値の業者を求めているのではありません。自社の事業リスクを低減し、さらにはサステナビリティといった企業価値向上に貢献してくれる戦略的パートナーを求めているのです。このニーズの変化を的確に捉え、単なる設備売りからソリューション提案型の営業・コンサルティングへと組織能力を進化させることが、今後の成功に不可欠です。
第7章:業界の内部環境分析
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
水処理業界において、持続的な競争優位の源泉となる経営資源やケイパビリティをVRIOフレームワーク(Value, Rarity, Inimitability, Organization)で分析します。
- 価値があり(Value)、希少で(Rarity)、模倣困難(Inimitability)な経営資源/ケイパビリティ:
- (VRI)独自の処理技術: 特許で保護された高性能な膜素材や、特定の難分解性物質を効率的に分解する独自の生物処理ノウハウは、他社にはない価値を提供し、模倣が困難な競争力の源泉です。
- (VRI)膨大な運転データとそれに根差すノウハウ: 長年にわたり多数のプラントのO&Mを手掛けることで蓄積された、多様な原水・運転条件下での運転・故障データは、極めて価値が高く、希少で、模倣が不可能な資産です。このデータは、高精度なAIモデルを学習させるための「石油」であり、他社が追随できない予知保全や自律運転の精度を実現します。
- (VRI)官公庁との強固な信頼関係: 社会インフラである水道事業を長期間にわたり安定的に運営してきた実績を通じて構築された、官公庁との強固な信頼関係は、目に見えない参入障壁として機能し、新規参入者には容易に模倣できません。
- 組織(Organization):
- (O)上記の資源を活かす組織体制: これらの価値ある資源を真の競争優位に結びつけるためには、それを活用できる組織体制が不可欠です。例えば、O&M部門が収集したデータを、AI開発部門が解析し、その結果を営業部門が顧客への新たな価値提案に繋げる、といった部門横断的な連携を促進する組織構造やインセンティブ設計が求められます。
人材動向
- 需要の変化: 業界が必要とする人材ポートフォリオは劇的に変化しています。プラントの物理的な設計を担う機械・電気・化学系のエンジニアに加え、AIアルゴリズムを開発するデータサイエンティスト、クラウドベースの監視プラットフォームを構築するソフトウェアエンジニア、そして顧客の経営課題を分析しソリューションを提案するビジネスコンサルタントといった、デジタル・ビジネス人材への需要が急増しています。
- 業界のボトルネック: 熟練技術者の高齢化と大量退職は、業界の持続可能性を脅かす最大のボトルネックです 6。特に、突発的なトラブルへの対応など、マニュアル化しにくい「暗黙知」の継承が極めて困難な課題となっています。
- 賃金トレンドと人材獲得競争: データサイエンティストをはじめとするデジタル人材の賃金は世界的に高騰しており、伝統的なエンジニアリング業界の給与体系では、優秀な人材の獲得は困難になりつつあります。IT業界との間で、熾烈な人材獲得競争が繰り広げられています。
労働生産性
- 設計プロセス: 3Dモデルを活用するBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)の導入により、設計の整合性確認や手戻りが削減され、関係者間の合意形成が迅速化するなど、設計段階の生産性は向上しています。
- O&Mプロセス: 中央監視センターからの遠隔集中監視、ドローンや水中ロボットによる点検の自動化、そしてAIによる自律運転の導入は、現場に配置する作業員の大幅な省人化を可能にし、O&M業務の労働生産性を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めています。
内部環境の分析から、企業の競争優位の源泉が「有形の技術資産」から「無形のデータ資産とその活用能力」へと完全に移行しつつあることが明らかになります。VRIO分析で特定された最も模倣困難な資源は、個別の技術特許よりも、長年のO&Mで蓄積された「生きた」運転データです。このデータがなければ、高精度な予知保全AIや自律運転アルゴリズムは開発できません。優れたAIは運転コストを劇的に削減し、顧客に提供できる価値を高めます。したがって、今後の企業価値は、保有するプラントの数や特許の数ではなく、保有するデータの「量と質」、そしてそれを収益化する「組織能力」によって測られるようになります。戦略的なデータ収集と、それを担う分析組織の構築が最重要経営課題となります。
この変化は、人材戦略にも根本的な転換を要求します。従来は、水処理プロセスに精通した同質的なエンジニア集団を育成することが重要でした。しかし、現在の複雑な課題を解決するには、データサイエンティスト、UXデザイナー、金融専門家、法務専門家など、多様なスキルセットを持つ専門家の協働が不可欠です。これらの異分野の専門家が、顧客価値の創造という共通の目的のために効果的に協働できる組織文化、評価制度、キャリアパスを設計しなければ、イノベーションは生まれません。人材戦略の失敗は、事業戦略の失敗に直結する時代に突入しています。
第8章:AIの影響とインパクト
プラント設計・建設へのインパクト
- 生成AIによる最適化設計: 過去の数千件に及ぶプラントの設計データ(配管ルート、機器配置、コスト、性能など)を学習した生成AIは、与えられた敷地面積や処理能力、コスト上限といった条件下で、最適なプラントレイアウト案を瞬時に複数提案することが可能になります。これにより、これまで熟練設計者が多くの時間を費やしていた基本設計プロセスが劇的に短縮され、コストと性能のトレードオフを考慮した最適な設計を迅速に決定できるようになります。
運転・維持管理(O&M)へのインパクト
- 自律運転: AIは、O&Mのあり方を根底から変革します。流入する下水の水量・水質、電力市場の価格変動、翌日の気象情報などをリアルタイムで予測し、送水ポンプの回転数、曝気槽に空気を送るブロワーの風量、消毒用の薬品注入量などを、人間では不可能なミリ秒単位で最適に制御します。これにより、O&Mコストの最大の要素である電力費を10~20%削減し、かつ処理水質を安定化させることが可能になります。
- 予知保全: ポンプやブロワーに取り付けられたセンサーが、振動、温度、圧力、電流値といったデータを常時収集し、AIがそのデータを監視します。AIは正常時のパターンを学習しており、「いつもと違う」異常の兆候を、実際に故障が発生する数週間から数ヶ月前に検知します。これにより、突発的なプラント停止を未然に防ぎ、計画的な部品交換やメンテナンスを実施できるため、ダウンタイムとそれに伴う機会損失、緊急対応コストをゼロに近づけることができます。
- 技術継承とオペレーター支援: 熟練オペレーターが持つ、汚泥の膨化(バルキング)を未然に防ぐための微細なブロワー調整といった「暗黙知」を、操作データとしてAIに学習させることが可能です。若手のオペレーターが操作を行う際に、AIがリアルタイムで最適な操作方法を画面上にガイダンスしたり、異常発生時に過去の類似事例とその対処法をチャットボットが提示したりすることで、経験の浅いオペレーターでも熟練者と同等の対応が可能となり、技術継承を強力に支援します。
経営・事業モデルへのインパクト
- デジタルツインの活用: 物理的なプラントと完全に同期した仮想モデルであるデジタルツインは、経営の意思決定を高度化します。例えば、数億円規模の設備更新計画を立案する際に、事前にデジタルツイン上でシミュレーションを行い、投資効果を定量的に検証することができます。また、現実のプラントでは試せないような異常事態を発生させ、オペレーターの対応能力を高めるための訓練シミュレーターとしても活用できます。
- データサービスの創出: 複数のプラントから収集した膨大な運転データを匿名化した上で統計的に分析し、業界全体のパフォーマンスと比較できるベンチマーキングデータとして、他のプラント運営者に有料で提供する事業が考えられます。また、特定の顧客の運転データを詳細に分析し、省エネや生産性向上に関する具体的な改善策を提案するコンサルティングサービスも、新たな収益源となり得ます。
AIは単なる「効率化ツール」に留まりません。それは、業界の「コスト構造」と「提供価値」そのものを再定義する破壊的技術です。自律運転は、O&Mコストの主要素である人件費と電力費を構造的に削減します。これにより、従来は採算が合わなかった小規模な水処理施設や、コストが課題であった高度な水再利用プロジェクトの経済性が向上し、新たな市場が生まれる可能性があります。さらに、データサービスは、従来の水処理ビジネスには存在しなかった全く新しい収益源を創出します。AIを使いこなす企業とそうでない企業とでは、コスト競争力と提供できる価値の両面で決定的な差が生まれ、業界の序列が塗り替えられることは避けられません。
しかし、AI導入の成否を分けるのは、技術そのものの優劣だけではありません。むしろ、「現場の人間との協調(Human-AI Teaming)」をいかに設計するかが鍵となります。AIが最適解を提示しても、現場のオペレーターがそれを信頼し、受け入れなければ、絵に描いた餅に終わります。現場には、データ化されていない微妙な環境変化や機器の「癖」など、AIがまだ捉えきれない情報が存在します。成功するAIシステムとは、一方的に指示を出すのではなく、なぜその判断をしたのか(判断根拠)を人間に分かりやすく説明し、人間のフィードバックを学習してさらに賢くなる、という協調的な関係を築くように設計されたものです。したがって、AI導入プロジェクトは、技術開発チームだけでなく、現場のオペレーターを初期段階から巻き込み、UI/UX設計や業務プロセスの再設計を一体で進めることが成功の絶対条件となります。
第9章:主要トレンドと未来予測
インフラアセットマネジメント
先進国では、今後、膨大な数の老朽化した水道管路や処理施設の更新が本格化します。限られた予算の中で最大の効果を得るため、劣化予測モデルやリスク評価に基づき、どの施設から、どのような工法で更新していくか、投資の優先順位を最適化する「アセットマネジメント」の重要性が高まります。デジタルツインを活用し、インフラ全体の健全性を可視化し、長期的な視点での最適更新計画を策定・実行するビジネスが大きく拡大します。
海水淡水化と水再利用
気候変動による水不足が深刻化する中東、北アフリカ、米国カリフォルニア州、インド、中国などを中心に、海水淡水化と水再利用の市場は今後も高い成長を続けます 3。この成長を技術面で支えるのが、RO膜の継続的な進化です。省エネルギー化、高耐久化、低ファウリング化といった技術革新により、淡水化・再利用のコストは劇的に低下しています 11。現在の最先端プラントにおけるエネルギー消費量は程度ですが、将来的にはさらなる削減が期待されており 15、これまで経済的に見合わなかった地域や用途でも、これらの技術が現実的な選択肢となります。
資源回収技術の普及
下水処理は、汚染物質を除去するだけのプロセスから、価値ある資源を回収するプロセスへと進化します。下水汚泥からメタンガスを生成して発電するバイオガス発電や、肥料の原料となるリンを回収する技術は、すでに一部で実用化されています 16。現状では、売電価格やリンの市場価格に採算性が左右されますが、今後は資源価格の世界的な高騰、カーボンクレジット市場の活性化、そして資源循環を促す法規制の強化により、経済的なインセンティブが増大します。将来的には、下水処理場は「水再生センター」から、水・エネルギー・有価物を生産する「資源循環工場(Bio-refinery)」へとその役割を変えていくでしょう。
分散型水インフラ
これまでの大規模集中型水インフラを補完するものとして、小規模な分散型水インフラの需要が高まります。大規模インフラが未整備な新興国の農村部、人口減少が進む先進国の過疎地域、災害時の緊急用水確保、そして特定の水質を必要とする新興工業団地などが主なターゲット市場です。コンテナに全ての機能を搭載した移動式水処理システムや、地域内で水を循環利用する小規模なループシステムが普及し、これらはIoTによる遠隔監視や自律運転との親和性が非常に高いという特徴を持ちます。
これらの未来予測から、水インフラの将来像が浮かび上がります。「集中型」と「分散型」は対立する概念ではなく、相互に補完し合うハイブリッドなシステムへと進化していくでしょう。都市部ではスケールメリットを活かした大規模な集中型インフラが中核を担い、その周辺部や特定の需要地では、迅速に設置でき、需要変動に柔軟に対応できる分散型システムがそれを補完します。これらを電力網のスマートグリッドのように情報通信技術で連携させ、地域全体の水需給をリアルタイムで最適化する「スマートウォーターグリッド」が、将来のインフラの姿となります。このトレンドは、単一のソリューションを提供する企業ではなく、顧客の状況に応じて最適なシステム(集中、分散、またはその組み合わせ)を設計・提案できるインテグレーターとしての能力が求められることを示唆しています。
さらに、資源回収ビジネスが本格化することで、業界の境界線は曖昧になっていきます。下水処理場がバイオガスで発電し、電力網に売電する時、それはエネルギー事業者としての顔を持ちます 16。回収したリンを肥料として販売する時、それは化学・農業資材事業者となります 16。このように、従来の業界の垣根を越えた連携や競争が生まれ、新たなエコシステムが形成されます。例えば、電力会社と共同で電力需給に応じたプラント運転の調整(デマンドレスポンス)を行ったり、肥料メーカーと共同で製品開発を行ったりするなど、新たなアライアンス戦略が競争優位の鍵となるでしょう。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
水処理業界の主要プレイヤーは、それぞれ異なるビジョンと戦略に基づき、激しい競争を繰り広げています。各社の戦略、強み、弱みを比較分析することで、業界の競争力学と自社の戦略的ポジショニングを明確にすることができます。
表:主要水処理企業 戦略比較分析
| 企業名 | ビジョン/戦略 | 事業ポートフォリオ(推定) | コアコンピタンス | デジタル戦略 | グローバル展開 | M&A/アライアンス動向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia | 総合環境サービス(水、廃棄物、エネルギー)のグローバルリーダー | O&M・サービス事業が中核。PPP/PFI事業に強み。 | 官民連携事業(PPP/PFI)の豊富な実績と運営ノウハウ。グローバルな事業展開力。 | デジタルプラットフォーム「Hubgrade」を核に、遠隔監視、運転最適化サービスをグローバルに展開。 | 世界中に事業拠点を持ち、特に欧州、北米、アジアでのプレゼンスが高い。 | Suezとの歴史的統合を完了し、事業規模と地理的カバレッジを大幅に拡大。 |
| Suez | (Veoliaに統合後、新Suezとして再編)水と廃棄物管理に特化 | Veoliaへの事業譲渡後、主にフランス国内および一部国際市場での水事業に集中。 | フランス国内での強固な事業基盤と上下水道運営の伝統的なノウハウ。 | Veoliaのデジタル戦略に統合される形で展開。 | Veoliaグループの一員として、特定の地域・市場に注力。 | Veoliaによる買収後、競争法上の要請から一部事業を分離し、新たな株主構成で再出発。 |
| 栗田工業 | 「水と環境の先進的ソリューションパートナー」 | 産業向け水処理薬品とプラントが二本柱。超純水供給事業も展開。 | 半導体・電子産業向けの超純水製造技術と、生産プロセスへの深い理解。水処理薬品における高いシェア。 | AI/IoTを活用した用水・排水管理サービス「S.sensing」を提供。顧客の生産性向上や環境負荷低減に貢献。 | アジア、北米、欧州に展開。特にアジアの電子産業向けに強み。 | 海外の水処理薬品・サービス会社を積極的に買収し、グローバルなサービス網を拡充。 |
| オルガノ | 「純水、その先へ。」 | 電子産業向け超純水供給装置と、一般産業・発電所向け水処理プラントが主力。サービス事業も強化中。 | 栗田工業と並ぶ、超純水供給システムにおける高い技術力と実績。 | 遠隔監視サービスやデータ分析による運転支援を強化。顧客の安定稼働とコスト削減をサポート。 | 台湾、中国、東南アジアなど、日系電子メーカーの海外進出に合わせて事業を展開。 | 安定した事業基盤を背景に、既存事業の深耕とサービス分野の強化に注力。 |
| 日立製作所 | Lumada(デジタルソリューション)を核とした社会イノベーション事業 | 水環境ソリューション事業として、上下水道の監視制御システム、O&M、EPCを国内外で展開。 | IT(監視制御システム)とOT(プラント運転技術)の融合。総合電機メーカーとしての幅広い技術基盤。 | デジタルソリューション「Lumada」を水事業にも適用。データ分析によるインフラの最適運営を目指す。 | 国内に加え、英国や東南アジアなどでのPPP/PFI事業に実績。 | IT/デジタル系の企業買収をグローバルで進めており、その技術を水事業に応用する動き。 |
| メタウォーター | 「水・環境インフラの持続性を支える」 | 国内の上下水道分野における機械・電気設備が中核。PPP/PFI事業にも注力。 | 国内の地方自治体との強固な関係。機械と電気の両分野に精通した技術力。 | クラウドベースの維持管理支援サービス「WBC(Water Business Cloud)」を展開。自治体の業務効率化を支援。 | 主に国内市場に集中。 | 国内での事業基盤強化と、PPP/PFI市場でのシェア拡大を目指す。 |
この比較分析から、各社がそれぞれの強みを活かしつつも、共通して「O&M・サービス事業の強化」と「デジタル化の推進」を戦略の柱に据えていることが明確に見て取れます。特に、Veoliaのようなグローバルメジャーは、デジタルプラットフォームを世界標準として展開しようとしており、栗田工業やオルガノは、特定産業への深い知見を武器に高付加価値なソリューションを提供しています。この競争環境の中で、自社がどの領域で、どのような独自性を打ち出して戦うのか、戦略的なポジショニングを明確にすることが極めて重要です。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
今後5~10年で、水処理業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因
これまでの分析を統合すると、将来の市場における勝者と敗者を分ける決定的な要因は、以下の4点に集約されます。
- ストック収益基盤の質と規模: 従来のEPC(フロー収益)に依存する企業は、価格競争と景気変動のリスクに晒され続けます。一方、長期契約に基づくO&MやWaaS(Water as a Service)、データサービスといった質の高いストック収益基盤を構築できた企業が、安定した成長と高い収益性を享受する「勝者」となります。
- デジタル技術の実装能力: AI/IoTを単なる効率化ツールとしてではなく、事業モデル変革のコアエンジンとして位置づけ、自律運転によるコスト削減と、データ活用による新たな価値創造を実現できるかどうかが、競争力を大きく左右します。
- ソリューション提供能力: 顧客の課題は、もはや「水を処理すること」自体ではありません。半導体メーカーの生産性向上、自治体の財政健全化といった、顧客のビジネスや行政課題そのものに深く入り込み、水を切り口とした統合的なソリューションを提供できる企業が、顧客から選ばれるパートナーとなります。
- 人材獲得・育成能力: 競争の主戦場がデジタル領域にシフトする中、優秀なデータサイエンティストやAIエンジニアを惹きつけ、維持できる組織文化と制度を持つことが、持続的なイノベーションの絶対条件となります。
機会(Opportunity)と脅威(Threat)
- 最大の機会: 「スマートウォーター(デジタル化)」と「資源循環」という二大トレンドを融合させることで、極めて付加価値の高いサービス事業を創出する機会が存在します。特に、設備を所有せず「水質・水量を保証するサービス」として提供するWaaSモデルは、顧客を長期的にロックインし、安定的な収益をもたらす究極のストックビジネスとなり得ます。
- 最大の脅威: 異業種からのディスラプション(破壊的変革)です。GAFAに代表されるIT巨人や、事業構築ノウハウを持つ総合商社が、その圧倒的なデータ解析能力や資金力を武器に、業界の最も収益性の高い部分(データサービス、事業運営権)を奪う可能性があります。既存プレイヤーは、彼らが参入してくる前に、自らを変革する必要があります。
戦略的オプションの提示と評価
上記の分析に基づき、取り得る戦略的オプションを3つ提示し、それぞれを評価します。
- オプションA:「デジタル特化型ソリューションプロバイダー」への変革
- 内容: 自社の強みであるO&Mで蓄積した膨大な運転データとノウハウを最大限に活用し、業界最高水準のAI自律運転システムやデジタルツインプラットフォームを開発。これをSaaS(Software as a Service)モデルとして、自社プラントだけでなく、競合他社を含む他のプラント運営会社にもライセンス提供する。
- メリット: ソフトウェアビジネス特有の高い利益率とスケーラビリティ。業界のデファクトスタンダードを握ることで、強力な競争優位を築ける。
- デメリット: GoogleやMicrosoftといったIT巨人との直接競合。巨額な先行開発投資が必要。既存のハードウェア事業とのシナジーを再設計する必要がある。
- オプションB:「特定産業向け総合ソリューションパートナー」戦略
- 内容: 成長性と収益性が高い特定の産業(例:半導体、製薬)にターゲットを徹底的に絞り込み、その産業の「水に関するあらゆる課題」をワンストップで解決するパートナーとなる。超純水の供給から、排水の完全再利用、さらには水使用量データと生産データを組み合わせた歩留まり改善コンサルティングまで、統合的なサービスを提供する。
- メリット: 高い専門性による強力な参入障壁の構築。顧客との強固で長期的な関係構築が可能。高付加価値サービスによる高い収益性。
- デメリット: 特定産業の景気変動に自社の業績が大きく左右されるリスク。他産業への展開が難しい可能性がある。
- オプションC:「M&Aによるケイパビリティ獲得と事業拡大」戦略
- 内容: 自社に不足しているケイパビリティ、特にAI/IoT技術に強みを持つスタートアップや、特定の地域・技術セグメントで強固な地位を築いている中堅企業を積極的に買収する。これにより、事業ポートフォリオと技術基盤を非連続的に、かつ短期間で強化する。
- メリット: 事業変革の実行スピードが速く、Time-to-Market(市場投入までの時間)を短縮できる。
- デメリット: M&A後の統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)の難易度が高い。有望な企業の買収価格は高騰しており、高値掴みのリスクがある。
最終提言とアクションプラン
最終提言:
単一のオプションに絞るのではなく、これらを組み合わせたハイブリッド戦略を推奨します。
事業戦略の中核として「オプションB:特定産業向け総合ソリューションパートナー」を据え、最優先ターゲットとして半導体産業に経営資源を集中投下します。この戦略を実現するための不可欠な手段として、「オプションC:M&A」を積極的に活用し、自社に不足しているAI/データ分析能力を迅速に獲得します。そして将来的には、半導体産業向けに開発・洗練させたデジタルソリューションを、「オプションA」のように他産業や他社へ外部展開することも視野に入れます。
この戦略は、自社の既存の強み(プラント技術)を活かしつつ、成長市場で確固たる地位を築き、同時に将来のデジタルプラットフォーマーへの道筋をつける、現実的かつ野心的なアプローチです。
アクションプラン(概要):
- Phase 1:基盤構築期(~1年)
- 主要アクション: CEO直轄の「DX・新規事業推進室」を設置。M&Aターゲットリスト(AI/IoT関連スタートアップ)の作成と評価を完了。半導体顧客向けWaaSモデルの事業計画を策定。
- KPI: ターゲットリストの完成度、事業計画の具体性。
- 必要リソース: 専任のタスクフォース、M&Aアドバイザー、市場調査費用。
- Phase 2:実行・実装期(1~3年)
- 主要アクション: AI/データ分析に強みを持つ企業1~2社の買収を実行。半導体大手企業と共同でWaaSのパイロットプロジェクトを開始。データサイエンティストを20名規模で中途採用。
- KPI: M&Aの完了、パイロットプロジェクトの開始と進捗、目標採用人数の達成。
- 必要リソース: M&A実行資金、パイロットプロジェクトへの研究開発投資、人材採用費用。
- Phase 3:拡大・展開期(3~5年)
- 主要アクション: 半導体産業向けWaaS事業を本格展開し、黒字化を達成。成功モデルを他の産業(製薬、データセンターなど)へ水平展開開始。開発したデジタルソリューションの外販事業を立ち上げる。
- KPI: WaaS事業の売上高・利益額、契約顧客数、デジタルソリューション外販事業の売上高。
- 必要リソース: 新事業部門の設立、グローバル営業体制の強化。
第12章:付録
本レポートの作成にあたり参照した、Global Water Intelligence (GWI)の市場レポート、国連世界水開発報告書、世界銀行の報告書、主要企業のIR資料、各種業界団体のレポート、学術論文などのリスト。
引用文献
- Under pressure – The economic costs of water stress and mismanagement – FONPLATA, https://www.fonplata.org/sites/default/files/media/documents/EIU_Under%20Pressure_The%20economic%20costs%20of%20water%20stress%20and%20mismanagement.pdf
- Water security in a world of growing scarcity and pollution – EFG International, https://www.efginternational.com/us/insights/2024/water_security_in_a_world_of_growing_scarcity_and_pollution.html
- Business Forums 2016 Desalination and Water Reuse Business Forum – Singapore International Water Week (SIWW), https://www.siww.com.sg/qql/slot/u143/2021/Landing%20Page/SIWW%202018/Programmes/Business%20Forums/Resources/2016-business-forums_desalination-and-water-reuse-business-forum.pdf
- Reverse Osmosis Ro Membrane Market Size, Share & Forecast by 2034, https://www.marketresearchfuture.com/reports/reverse-osmosis-ro-membrane-market-25192
- Water is the vessel through which we ride the waves of changing climates – Frontiers, https://www.frontiersin.org/journals/water/articles/10.3389/frwa.2024.1501483/epub
- 1月 1, 1970にアクセス、 https://www.compact.org/resource-posts/the-aging-workforce-in-the-water-industry-challenges-and-solutions/
- The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306
- World Water Development Report 2019: ‘Leaving no one behind’, https://smartwatermagazine.com/news/un-water/world-water-development-report-2019-leaving-no-one-behind
- 1月 1, 1970にアクセス、 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/13/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-investments-and-actions-to-protect-and-restore-the-great-lakes/
- 1月 1, 1970にアクセス、 https://www.epa.gov/infrastructure/water-infrastructure-investments-under-bipartisan-infrastructure-law
- Untapped Potential – How Wastewater Can Unlock The Tap To Our Water, https://ceowatermandate.org/posts/snehal-desai-untapped-potential-wastewater-can-unlock-tap-water/
- Advancements in Reverse Osmosis Membrane Technology for Tertiary Wastewater Treatment – ZwitterCo, https://zwitterco.com/blog/reverse-osmosis-technology-for-tertiary-wastewater-treatment/
- Capitalizing on the latest advancements in reverse osmosis membrane technology – Hydranautics, https://membranes.com/wp-content/uploads/Documents/Technical-Papers/Product%20line/RO/ESPA2-LD-MAX-at-OCWD-MTC17-Manuscript-KNOELL-FRANKS.pdf
- Blog – ZwitterCo, https://zwitterco.com/blog/
- Solar thermal decomposition of desalination reject brine for carbon dioxide removal and neutralisation of ocean acidity – ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/271723573_Solar_thermal_decomposition_of_desalination_reject_brine_for_carbon_dioxide_removal_and_neutralisation_of_ocean_acidity
- 2025 Preliminary Programme, https://waterdevelopmentcongress.org/wp-content/uploads/2025/09/WDCE-2025-Preliminary-Technical-and-Workshop-Programme.pd