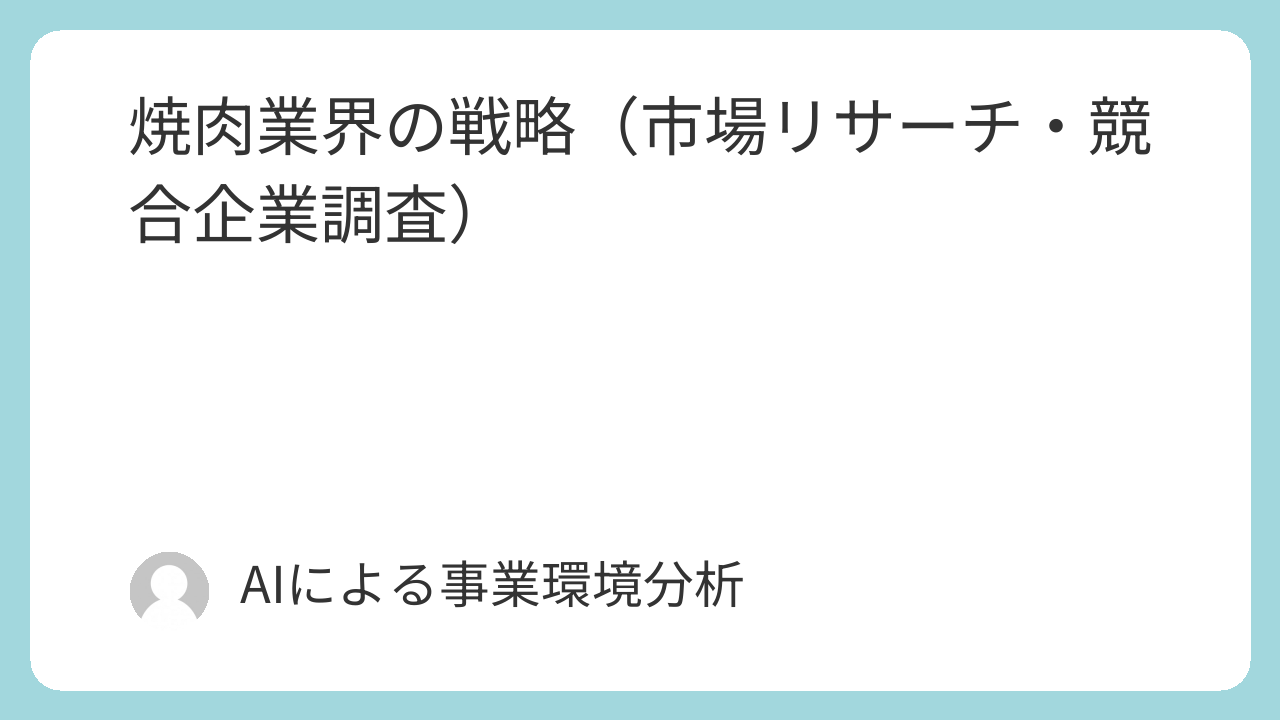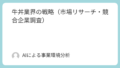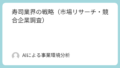岐路に立つ焼肉業界:コスト高騰と人手不足を克服し、「体験価値」で持続的成長を実現するDX・SCM戦略
- 第1章:エグゼクティブサマリー
- 第2章:市場概観(Market Overview)
- 第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
- 第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
- 第5章:サプライチェーン分析
- 第6章:バリューチェーン分析
- 第7章:顧客需要の特性分析(Customer Demands)
- 第8章:業界の内部環境分析(Internal Environment Analysis)
- 第9章:AIとテクノロジー活用のインパクト分析
- 第10章:主要トレンドと未来予測
- 第11章:主要プレイヤーの戦略分析
- 第12章:戦略的インプリケーションと推奨事項
- 第13章:付録(Appendix)
第1章:エグゼクティブサマリー
1.1. 岐路に立つ業界の現状
日本の焼肉業界は、今まさに歴史的な岐路に立たされている。新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う人流回復と急回復するインバウンド需要は力強い追い風となる一方、原材料費・物流費・人件費の「トリプルコスト高騰」と深刻な人手不足という未曾有の逆風が同時に吹き荒れている。市場全体としては回復基調にあるにもかかわらず、帝国データバンクによれば2024年の倒産件数は過去最多を更新するペースで推移しており 1、大手チェーンの成長と中小事業者の淘汰という二極化が鮮明になっている。この複雑な事業環境は、従来の経営モデルの限界を露呈させ、抜本的な事業戦略の見直しを全プレイヤーに迫るものである。
1.2. 分析から得られた主要インサイト
本レポートでは、この複雑な環境を多角的に分析した結果、焼肉業界の未来を左右する3つのメガトレンドを特定した。第一に、消費者の嗜好が「ハレの日」の特別な体験を求める高付加価値志向と、「日常使い」のコストパフォーマンスを重視する志向へと明確に二極化していること。第二に、円安による輸入牛肉の高騰と国内和牛の価格軟化という逆転現象が発生し、サプライチェーン・マネジメント(SCM)がコスト管理だけでなく、新たな価値創造の源泉へと変貌していること。第三に、デジタルトランスフォーメーション(DX)が単なる省人化ツールに留まらず、オペレーションモデルを根底から変革し、人的資本をより付加価値の高い業務へ再配置する戦略的ドライバーとなっていることである。これらの分析が示す核心は、「コスト削減」と「付加価値向上」は二者択一のトレードオフではなく、DXとSCM革新を両輪とすることで両立が可能であるという点にある。
1.3. 戦略的推奨事項の要旨
上記の分析に基づき、焼肉業界の事業者が持続的成長を実現するため、本レポートは以下の3つを柱とする戦略を提言する。
- 「体験価値」に基づく業態ポートフォリオの再構築: ターゲット顧客セグメントを明確化し、「高級体験特化型」「エンタメ・ファミリー型(プレミアム・マス)」「超効率特化型」のいずれかの価値提供に経営資源を集中させる。
- データドリブンなSCMによるコスト構造改革: 国内産牛肉の活用による新たな価値提案、需要予測に基づく発注最適化、調達ルートの複線化により、コスト変動に対する耐性を強化し、収益構造を抜本的に改善する。
- 「省人化」と「人財価値最大化」を両立するDX戦略: 配膳ロボットやモバイルオーダーを標準装備とし、単純作業を自動化する。これにより創出された人的リソースを、顧客とのコミュニケーションやアップセル提案といった、人間にしかできない高付加価値なサービス提供へと再配置する。
本レポートは、これらの戦略的選択肢を定量・定性データに基づき詳細に分析し、経営層が次なる一手となる事業戦略を策定するための羅針盤となることを目的とする。
第2章:市場概観(Market Overview)
2.1. 市場規模と成長性
焼肉業態を含む外食産業は、コロナ禍の打撃から力強い回復を見せている。日本フードサービス協会(JF)によると、2023年の外食産業全体の市場規模は前年比14.1%増の約24兆円規模に回復した 3。焼肉業態もこの回復基調を捉え、特にファミリーレストラン型焼肉は急速に需要を取り戻し、2023年には売上高、店舗数ともにコロナ禍前の2019年の水準を上回った 6。直近のデータでも、2025年8月の焼肉業態の売上高は前年同月比6.5%増となるなど、底堅い需要が継続していることが確認できる 7。
焼肉業態単独の市場規模については、推計値に幅が見られる。5,000億円超とする調査 8 から、年商約1兆2,000億円、店舗数約22,000軒とする推計まで存在する 9。いずれにせよ、外食産業の中で大きな存在感を持ち、今後も堅調な推移が予測される巨大市場であることは間違いない。
2.2. 業界の収益性と課題:K字回復の実態
市場全体の回復という明るい側面とは裏腹に、業界内部では深刻な淘汰が進行している。帝国データバンクの調査によれば、2024年の焼肉店の倒産件数(負債1,000万円以上)は過去最多だった前年に並ぶペースで推移しており、9月までに39件と前年同期の2倍以上に急増している 1。
この倒産の背景には、歴史的な円安を起因とする輸入牛肉価格の高騰(4年前から平均1.7倍) 1、人手不足による人件費の上昇、そして電気・ガス代といったエネルギーコストの増加がある。これらのコスト急騰分をメニュー価格へ十分に転嫁できず、利益が消失する「消耗戦」に耐えきれなくなった中小・零細事業者が市場からの退出を余儀なくされている 1。
市場全体の売上は回復しているにもかかわらず、倒産件数が過去最多を記録するという一見矛盾した状況は、焼肉業界が典型的な「K字回復」の局面にあることを示している。すなわち、強固な資本力、スケールメリットを活かした調達力、そしてブランド力を持つ大手チェーンが成長を続ける一方で、価格競争力やブランド力に劣る中小・個人経営店が淘汰されるという二極化が急速に進んでいるのである。この構造変化は、事業者が「規模によるコストリーダーシップ」か「高度な差別化による高付加価値」のいずれかの戦略を選択せざるを得ない状況を生み出している。
| 指標 | 数値・動向 | 主な情報源 |
|---|---|---|
| 市場規模(推計) | 年商 約5,000億円〜1兆2,000億円 | 8 |
| 成長率(焼肉業態売上高) | 2025年8月:前年同月比 +6.5% | 7 |
| 店舗数(推計) | 約22,000軒 | 9 |
| 倒産件数 | 2024年は過去最多ペースで推移、前年比倍増 | 1 |
2.3. 業態別の動向
顧客ニーズの多様化を背景に、焼肉業態は細分化・専門化が進んでいる。コロナ禍からの回復を牽引したのは、ファミリー層をターゲットとしたファミリーレストラン型焼肉であった 6。同時に、「一人焼肉」やテイクアウト・デリバリーといった新たな利用シーンも市場に定着した 12。
コンサルティングファームの船井総合研究所は、現在の市場で好調な焼肉業態として以下の5つを挙げている 13。
- 郊外型おひとり様焼肉業態: 「焼肉ライク」に代表される、個食ニーズに対応した高回転率モデル。
- 大衆焼肉酒場業態: 食事と飲酒を組み合わせ、日常使いの需要を捉えるモデル。
- 特急レーン焼肉業態: 回転寿司のシステムを応用し、エンターテインメント性と省人化を両立するモデル。
- 高単価 焼肉食べ放題業態: 「焼肉きんぐ」のように、品質と体験価値を高めた食べ放題モデル。
- 中単価和牛焼肉単品業態: 国産和牛を手頃な価格で提供し、品質志向の顧客を掴むモデル。
これらの業態の隆盛は、消費者が単に「肉を焼いて食べる」だけでなく、利用シーンや目的に応じて多様な「体験価値」を求めていることの証左である。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
3.1. Political(政治的要因)
- 貿易協定(TPP等)の影響: TPP(環太平洋パートナーシップ)協定の発効により、牛肉の関税率は現行の38.5%から16年間かけて段階的に9%まで引き下げられる計画である 14。これは長期的には輸入牛肉の調達コストを押し下げる要因となり得るが、短期的には為替レートの変動が価格に与える影響の方がはるかに大きい。
- 食品衛生法の改正(HACCPの義務化): 2021年6月1日から、飲食店を含む全ての食品等事業者に対し、HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理が完全義務化された 18。これにより、衛生管理計画の策定、実施、記録、保存が法的に必須となった。遵守できない場合、営業許可の更新が認められないリスクがあり、特に管理体制が脆弱な中小事業者にとっては、新たなコンプライアンスコストとなっている 21。
3.2. Economic(経済的要因)
- コストプッシュ・インフレ: 歴史的な円安の進行により、輸入牛肉の価格は2020年比で平均1.7倍にまで高騰している 1。これに加えて、電気・ガス代などのエネルギー価格、物流費も上昇しており、飲食店のコスト構造を根底から揺るがしている。
- 人件費の上昇: 全国的な最低賃金の引き上げと、飲食業界の構造的な人手不足が相まって、人件費は継続的な上昇圧力に晒されている 1。
- 消費行動の二極化: 物価高騰を背景に消費者の節約志向が強まる一方で、記念日などの「ハレの日」には、価格が高くても品質の高い食事や特別な体験を求める傾向も依然として根強い 6。この結果、高価格帯と低価格帯の業態は支持を集める一方、明確な特徴を打ち出せない中間価格帯の店舗が最も厳しい競争環境に置かれている。
3.3. Social(社会的要因)
- ライフスタイルの変化と個食化: 単身世帯の増加やライフスタイルの多様化を背景に、「一人焼肉」に代表される個食(ソロ活)の需要が定着している 12。これにより、従来のグループ利用を前提とした店舗設計やメニュー構成の見直しが求められている。
- 健康志向の高まり: メディア等で肉の健康効果が広く認知され、特に脂肪の少ない赤身肉や、タンパク質が豊富な部位への関心が高まっている 9。一方で、アンケート調査では、年齢が上がるにつれて「昔ほど肉が食べられなくなった」という声も見られ、高齢層向けのメニュー開発も課題となっている 6。
- Z世代の飲食店選択行動: 10代〜20代のZ世代は、従来のグルメサイトよりもInstagramやTikTokといったビジュアル重視のSNSを情報源とする傾向が極めて強い 24。彼らは点数評価よりも、投稿される写真や動画から伝わる「店の雰囲気」や、インフルエンサーなどによる「リアルな体験レビュー」を信頼する 26。インパクトのある盛り付け(「フォトジェ肉」)など、SNSでの共有を誘発するような視覚的な魅力が、若年層の集客において不可欠な要素となっている 9。
3.4. Technological(技術的要因)
- 省人化・自動化技術の普及: 人手不足を背景に、配膳ロボット、モバイルオーダーシステム、セルフレジといった省人化技術の導入が急速に進んでいる。これらのテクノロジーは、単なるコスト削減策に留まらず、店舗オペレーションの効率を飛躍的に向上させ、生産性向上の鍵となっている(詳細は第9章で詳述)。
- データ活用の進展: POSデータや予約データなどを活用した需要予測、顧客分析、メニュー開発の精度が向上している。データに基づいた意思決定が、競争優位性を左右する時代に突入している。
3.5. Legal(法的要因)
- 労働関連法規の厳格化: 労働基準法に基づき、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)、休憩時間、有給休暇の付与義務の遵守が厳しく求められている 28。長時間労働が常態化しやすい飲食業界において、これらのコンプライアンスは重要な経営課題である。
- 最低賃金の上昇: 各都道府県で定められる最低賃金は年々引き上げられる傾向にあり、人件費を押し上げる直接的な要因となっている 30。
3.6. Environmental(環境的要因)
- サステナビリティへの要請: SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりを受け、フードロス削減への取り組みが社会的に強く求められている。特に食べ放題業態においては、食材の廃棄をいかに抑制するかがブランドイメージにも影響する。
- 代替プロテインの台頭: 環境負荷の低減やアニマルウェルフェアの観点から、植物由来の代替肉市場が世界的に拡大している。現時点では焼肉業態での導入は限定的だが、将来的には新たなメニューの選択肢として、また企業の環境姿勢を示す手段として重要性を増す可能性がある。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
マイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いて、焼肉業界の収益性に影響を与える5つの競争要因を評価する。
4.1. 業界内の競争(Rivalry Among Existing Competitors) – 【脅威度:高】
焼肉業界内の競争は極めて激しい。市場には「牛角」や「焼肉きんぐ」といった大手ナショナルチェーンから、地域密着型の個人経営店まで、無数のプレイヤーがひしめき合っている 12。特に、原材料費高騰の局面において、低価格帯の店舗間での消耗戦が激化しており、コストを価格に転嫁できない事業者が淘汰されるという厳しい現実がある 1。さらに、食べ放題、高級専門店、一人焼肉、大衆酒場型など、業態の多様化が進展しており、それぞれのセグメント内での顧客獲得競争も熾烈を極めている。
4.2. 新規参入の脅威(Threat of New Entrants) – 【脅威度:中】
飲食店の中でも、焼肉店は排煙・換気設備の導入など、比較的高額な初期投資を要する。しかし、参入障壁が決定的に高いわけではなく、コロナ禍においても異業種からの参入が相次いだ 12。ただし、既存の大手チェーンは、スケールメリットを活かした強力な仕入れ力と、テレビCMなどによる高いブランド認知度という強固な参入障壁を築いている。そのため、新規参入者が市場で確固たる地位を築くのは容易ではない。
4.3. 代替品の脅威(Threat of Substitute Products or Services) – 【脅威度:中】
外食における代替品の脅威は常に存在する。寿司、イタリアン、中華料理など、他のあらゆる外食業態が焼肉の代替選択肢となりうる。また、家庭で楽しむ焼肉(中食)や、スーパーマーケットで購入した食材を持ち寄るバーベキューも強力な代替体験である。特にコロナ禍を経て、手ぶらで楽しめるグランピング施設やバーベキュー場の需要は多様化・定着しており 12、外食としての焼肉店の需要を一部侵食している。
4.4. 買い手の交渉力(Bargaining Power of Buyers) – 【脅威度:高】
消費者は極めて強い交渉力を持っている。無数の焼肉店が存在するため、店舗間のスイッチングコストはほぼゼロに近い。SNSやグルメサイトの普及により、消費者は価格、品質、雰囲気、口コミといった情報を容易に比較検討できる。さらに、消費者の嗜好が「高付加価値」と「コストパフォーマンス」に二極化しているため 6、どちらのニーズにも応えられない中途半端な価値提案しかできない店舗は、顧客から選ばれにくくなっている。
4.5. 供給者の交渉力(Bargaining Power of Suppliers) – 【脅威度:高】
供給者の交渉力は、扱う食肉の種類によって構造が大きく異なる。この二元的な構造を理解することが、戦略上極めて重要である。
- 輸入牛肉の供給者: 海外のパッカー(食肉処理加工業者)や商社は、極めて強い交渉力を持つ。世界的な需要の増加と円安の進行が価格を直接押し上げており、輸入牛肉に依存する低価格帯チェーンの収益性を著しく圧迫している 1。これらのチェーンにとって、供給者の力は経営を左右する最大の脅威の一つである。
- 国産和牛の供給者: 対照的に、国産和牛の供給者(生産農家や卸売業者)の交渉力は、現在相対的に弱まっている。国内の生産頭数の増加により供給が需要を上回り、枝肉卸売価格が下落傾向にあるためである 32。これは、中〜高価格帯の店舗にとって、品質の高い和牛を有利な条件で調達する戦略的な好機となり得る。
このように、供給者の交渉力は一様ではなく、どのサプライチェーンに依存するかによって、企業が受ける影響は全く異なる。自社の業態と調達戦略が、この二極化した供給者パワーのどちらに晒されているかを正確に把握することが不可欠である。
第5章:サプライチェーン分析
5.1. 調達環境の激変:輸入牛肉と国産和牛の価格逆転現象
現在の焼肉業界のサプライチェーンは、地殻変動ともいえる大きな変化に直面している。その核心は、主要な原材料である輸入牛肉と国産和牛の価格動向が完全に逆行している点にある。
- 輸入牛肉の歴史的高騰: 円安と旺盛な海外需要を主因として、米国産や豪州産の牛肉輸入価格は急騰を続けている。帝国データバンクの分析によると、主要部位であるロイン・かた・ばらの輸入原価は、2020年と比較して平均で1.7倍、7割以上の上昇を記録した 1。このコストショックは、特に輸入肉への依存度が高い食べ放題や低価格チェーンの経営基盤を直撃している。
- 国産和牛の価格軟化: その一方で、国内の和牛市場は異なる様相を呈している。生産者の努力により和牛の出荷頭数は増加傾向にあり、供給が安定している 33。この結果、需給バランスが緩み、和牛の枝肉卸売価格は軟調に推移している。農林水産省のデータによれば、2024年7月の和牛相場(去勢A5)は、コロナ禍で需要が落ち込んだ2020年同月の価格さえも下回る水準となった 32。
この輸入牛肉と国産和牛の価格動向のデカップリング(分離)は、一時的ではあるものの、極めて重要な戦略的機会を生み出している。従来は「高価」であった国産和牛が相対的に割安になることで、メニュー構成を見直す余地が生まれる。例えば、メニューにおける国産牛(交雑種(F1)も価格が安定している 33)の比率を高めることで、輸入肉のコスト高騰リスクをヘッジしつつ、顧客に対しては「国産」という付加価値を訴求することが可能になる。これは、輸入肉に依存する競合他社に対して、コスト構造と提供価値の両面で優位性を築く「戦略的ソーシング・アービトラージ」の好機と言える。
5.2. 調達戦略の多様化とリスクヘッジ
こうした環境変化に対応するため、各社は調達戦略の多様化を進めている。
- 一頭買い: 牛一頭を丸ごと買い付けることで、スケールメリットにより単価を抑え、市場に出回りにくい希少部位を提供できるというメリットがある 34。これは店の大きな魅力となり得る。しかし、ロースやカルビといった人気部位だけでなく、需要の少ない部位も全て使い切る必要があり、高度な加工技術とメニュー開発力がなければ大量のフードロスを発生させるリスクを伴う 35。
- 生産者との直接契約: 卸売業者などの中間流通を排し、生産者(牧場)と直接契約を結ぶことで、中間マージンを削減し、価格と供給の安定化を図る手法。また、生産者の顔が見えることでトレーサビリティが確保され、食の安全・安心を顧客にアピールするマーケティング上の利点も大きい。
- 調達先の多角化: 米国産牛肉への依存度を下げ、豪州産や他の産地の牛肉の比率を高めることで、特定国の天候不順や政治・経済情勢に起因する供給リスクを分散する。
- 代替肉の導入検討: 現時点では主流ではないが、サステナビリティや多様な食文化への対応という観点から、植物由来の代替肉をメニューの一部として導入する動きも将来的には考えられる。これは新たな顧客層の開拓に繋がる可能性を秘めている。
5.3. 歩留まり改善とフードロス削減
調達した原材料をいかに無駄なく製品に変えるか(歩留まりの向上)は、利益率を左右する重要な要素である。特に一頭買いを行う場合、枝肉から骨や余分な脂肪を取り除き、各部位を商品として切り分けるカット技術が歩留まりを大きく左右する。残ったスジ肉や端材をスープや煮込み料理、ランチメニューなどに活用し、食材を使い切るメニュー開発力が求められる。
また、食べ放題業態においては、顧客の過剰な取りすぎによる食べ残しが大きな課題であった。しかし、「焼肉きんぐ」などが採用するタッチパネル式のテーブルオーダーバイキングは、ビュッフェ形式と比べて顧客が必要な分だけを注文するため、フードロスの削減に絶大な効果を発揮している 37。
第6章:バリューチェーン分析
企業の事業活動を機能ごとに分類し、どの部分で付加価値が生み出されているかを分析する。
6.1. 購買・物流
- 課題: 前章で述べた原材料費の高騰に加え、物流業界の「2024年問題」に象徴されるドライバー不足とそれに伴う物流コストの上昇が、安定的な食材供給の大きな足かせとなっている。
- 戦略的対応: 大手チェーンでは、セントラルキッチンやプロセスセンターを設置し、食材の一括仕入れ・一次加工・各店舗への配送を行うことで、物流の効率化と規模の経済を追求している。叙々苑がHACCPの理念に基づき設立した自社食品工場「叙々苑フードファクトリー」は、全店の仕入れと加工を一括して行い、品質の標準化と効率化を両立する先進事例である 38。
6.2. オペレーション(店舗運営)
- 課題: 深刻な人手不足と、肉のカット技術や盛り付けといった属人的なスキルへの依存が、店舗運営の安定性と品質維持のボトルネックとなっている。
- 戦略的対応: モバイルオーダーや配膳ロボットの導入による省人化は、もはや不可欠な選択肢となっている 39。これにより、オーダーテイクや配膳といった単純作業を自動化し、生産性を向上させる。同時に、タレやスープなどの重要食材をセントラルキッチンで一括製造し、店舗での調理工程を可能な限り標準化・マニュアル化することで、従業員のスキルレベルに依存しない安定した品質を実現している。
6.3. マーケティング・販売
- 課題: 多様な顧客セグメント(ファミリー、Z世代、インバウンド等)に対し、それぞれに響く効果的なアプローチが求められる。
- 戦略的対応: Z世代に対しては、InstagramやTikTokを活用したビジュアル訴求が極めて有効である 24。インバウンド観光客向けには、多言語メニューの整備や海外の予約サイトとの連携が重要となる。また、物語コーポレーションがコロナ禍で広告費を3倍に増やし、「焼肉きんぐ」のブランド認知度を飛躍的に高めた事例は、大胆なマスマーケティングが依然として有効であることを示している 42。
6.4. サービス
- 課題: 省人化・効率化を進める中で、いかにして顧客満足度を維持・向上させるかというジレンマ。
- 戦略的対応: 成功している事業者は、テクノロジーと人的サービスを対立するものとしてではなく、相乗効果を生むものとして捉えている。具体的には、モバイルオーダーや配膳ロボットの導入によって単純作業から解放された従業員が、より付加価値の高い接客サービスに集中する「ヒューマン・テック シナジーモデル」を構築している。その代表例が「焼肉きんぐ」の「焼肉ポリス」である 44。彼らは店内を巡回し、網交換や肉の美味しい焼き方のアドバイスといった「おせっかい」なサービスを提供することで、食事の楽しさという体験価値を劇的に向上させている。テクノロジーによる効率化が、人間による温かみのあるサービスの質を高めるための時間を創出するという、この好循環こそが、現代の焼肉店におけるサービスモデルの最適解の一つである。
第7章:顧客需要の特性分析(Customer Demands)
7.1. 利用動機と頻度
焼肉店の利用動機は、大きく二つのパターンに分類される。消費者アンケート調査によると、最も多い利用頻度は「年に数回程度」(56.7%)であり、誕生日や記念日、家族での会食といった「ハレの日」の特別な機会に利用する層がマジョリティを形成している 6。一方で、「月に1回程度以上」利用する高頻度ユーザーも全体の約2割を占めており 6、ランチや普段の夕食といった「日常使い」の需要も市場にしっかりと根付いている。
7.2. 店舗選択の決定要因(KBF: Key Buying Factor)
顧客が焼肉店を選ぶ際に何を重視するかを分析すると、明確な傾向が見られる。J-Net21が実施した1,000人規模のアンケート調査によれば、店舗選択の最重要項目は「料理のおいしさ、メニューの豊富さ」であった 6。これに「低価格、お得感」と「家や職場からの距離(立地の利便性)」が続く。この結果は、顧客が「品質価値」を最優先する層と、「利便性・コスト価値」を重視する層に大別されることを示唆している。
興味深いことに、「大手チェーンのブランド力や安心感」を重視する回答者の割合は、他の項目に比べて比較的低い 6。これは、消費者が単なるブランド名で店舗を選ぶのではなく、そのブランドが提供する具体的な価値(味、価格、体験)をシビアに評価していることを意味する。
7.3. セグメント別分析
- ハレの日利用層(高付加価値志向): このセグメントは、価格よりも肉の品質(例:A5ランク和牛)、希少部位の有無、洗練された店の雰囲気、質の高い接客サービスを重視する。特に女性は男性と比較して、1回あたりの利用金額が高い傾向が見られる 6。
- 日常使い利用層(コストパフォーマンス重視): ランチや仕事帰りの夕食などで利用するこのセグメントは、手頃な価格、満足できるボリューム、そして提供スピードを重視する。アンケートでは、男性、特に30代から40代の働き盛りの世代でこの傾向が強いことが示されている 6。
- インバウンド観光客: 多くの訪日外国人にとって、「日本食を体験すること」は旅行の主要な目的の一つである 45。中でも日本の和牛は、その圧倒的な「柔らかさ」と美しい「霜降り(marbling)」が高く評価されており、焼肉は和牛の魅力をダイレクトに楽しめる食体験として絶大な人気を誇る 46。彼らは価格が高くても、本物の和牛を求める傾向が非常に強い。
- Z世代: この世代は、店舗探しにおいてInstagramやTikTokなどのSNSに大きく依存している 24。彼らが重視するのは、料理や店内の「写真映え」「動画映え」であり、友人との共有が可能な体験である 9。グルメサイトの点数評価よりも、インフルエンサーや友人が投稿したビジュアル情報から伝わる「リアルな雰囲気」を信頼する傾向がある 24。
7.4. 今後の利用意向
今後の利用意向に関する調査では、回答者全体の83.0%が「利用したい(「ぜひ利用したい」51.2% +「どちらかと言えば利用したい」31.8%)」と回答しており、焼肉業態に対する需要は今後も極めて底堅いことが示されている 6。この高い需要を背景に、各事業者が多様化する顧客ニーズにいかに的確に応えていくかが、今後の成長の鍵となる。
第8章:業界の内部環境分析(Internal Environment Analysis)
8.1. コスト構造:高FLコスト業態の宿命
焼肉店は、飲食業の中でも特にコスト構造に特徴がある業態である。その最大の特徴は、食材原価(Food Cost)が極めて高いことにある。
- FLコスト比率: FLコストとは、売上高に占める食材費(F)と人件費(Labor Cost)の合計比率を指す、飲食店の収益性を測る最重要指標である。焼肉店のFLコスト比率の業界平均は60%を超え、他の業態に比べて高い水準にある 51。一般的な目安としては、食材費(F)が38〜42%、人件費(L)が18〜22%程度とされている 52。
- 収益性への影響: このようにFコストが構造的に高いため、焼肉店の利益創出は、Lコストである人件費をいかに効率的にコントロールするかに大きく依存する。現在の原材料費高騰は、この脆弱なコスト構造を直撃している。しかし、見方を変えれば、この構造はDX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性向上の効果が、利益に対してより大きく貢献することを意味する。例えば、人件費を10%削減できた場合、その利益インパクトはFコストが低い業態(例:喫茶店)よりも相対的に大きくなる。したがって、焼肉業界にとってDX投資は、単なる「あれば望ましい」ものではなく、収益性を確保し生き残るための「不可欠な」戦略的要素であると言える。
8.2. 人材とスキル:「伝統的ノハウ」の継承問題
焼肉店の競争力を支える重要な要素の一つが、職人的なスキルである。
- 肉の目利き: 仕入れる枝肉や部位の品質を見極める能力。
- カット技術: 同じ部位からでも、筋の入り方や肉質を見極め、最も美味しく食べられるように切り出す技術。歩留まりを最大化し、フードロスを最小化する上でも不可欠。
- タレの開発: 肉の味を最大限に引き出す、店独自のタレ。これは他店が容易に模倣できない、競争優位の源泉となる。
これらのスキルは、長年の経験を通じて培われる属人的なノウハウであり、マニュアル化や短期的な育成が極めて難しい。熟練した職人の高齢化や離職は、店の品質を直接的に低下させ、ブランド価値を毀損する重大な経営リスクとなる。大手チェーンでは、セントラルキッチンでの一次加工の徹底や、詳細な調理マニュアルを整備することで、この属人性の問題を克服し、品質の平準化を図っている。
8.3. VRIO分析(業界レベル)
業界が持つ資源や能力が持続的な競争優位に繋がるかを分析する。
- Value(価値): 高品質な食肉と、それを楽しむための空間・サービスを提供し、顧客に「ハレの日」の特別な体験や日常の活力を与える能力は、経済的な価値を持つ。
- Rarity(希少性): 特定の生産者との独占的な仕入れルート、長年受け継がれてきた秘伝のタレのレシピ、他の追随を許さない卓越した職人のカット技術などは、希少な経営資源である。
- Imitability(模倣困難性): 叙々苑が長年かけて築き上げてきた「高級焼肉店」としてのブランドイメージや、「焼肉きんぐ」が確立した「エンターテインメントとしての食べ放題」というサービスモデルは、単にメニューや価格を真似るだけでは模倣が困難である。
- Organization(組織): 上記のような価値ある希少な資源を、組織として有効に活用し、継続的に利益を生み出す仕組み(例:人材育成システム、品質管理体制、データに基づいた出店戦略)を構築できている企業が、業界内で持続的な競争優位を確立している。
第9章:AIとテクノロジー活用のインパクト分析
9.1. 省人化・生産性向上への貢献
AIとテクノロジー、特にロボティクスの活用は、焼肉業界が直面する深刻な人手不足問題に対する最も有効な解決策の一つである。
- 配膳・下げ膳ロボット: 導入した店舗では、ホールスタッフの歩行距離が大幅に削減され、熱い皿や重い食器を運ぶといった身体的負担が劇的に軽減される 41。一度に人の約4倍の量を運搬できるため 54、料理提供のスピードアップや、食後のテーブル片付け(バッシング)の迅速化に繋がり、結果として店舗の座席回転率向上に寄与する 41。実際にロボットと働くスタッフの満足度は約9割と非常に高く、その最大の理由として「配膳・下げ膳業務の負担が減った」ことが挙げられている 55。
- モバイルオーダー/タッチパネル: 顧客自身のスマートフォンやテーブル上の端末で注文が完結するため、従来ホールスタッフが行っていたオーダーテイク業務が不要となる。これにより、ホール人員の最適化が可能になるだけでなく、注文の聞き間違いといったヒューマンエラーを撲滅し、非接触という現代的なニーズにも応えることができる 56。
9.2. コスト構造(FLコスト)への影響
これらのテクノロジー導入は、店舗のコスト構造、特に人件費(Lコスト)に直接的なインパクトを与える。あるラーメン店では、配膳ロボットの導入により、来客数が少なくなる深夜帯のアルバイト従業員を3名から1名に削減できたという事例も報告されている 54。ロボットの導入には初期投資や月額利用料が発生するが、継続的に発生する人件費や求人・教育コストと比較すれば、長期的にはコスト削減効果が期待できる。飲食店の生産性指標である「人時売上高」(従業員1人が1時間あたりに生み出す売上高)を向上させる上で、テクノロジー活用は不可欠な施策となっている 57。
9.3. 顧客体験(CX)への影響
テクノロジーの導入は、顧客体験(Customer Experience)にも多大な影響を及ぼす。
- ポジティブな影響: 注文から料理提供までの待ち時間が短縮され、ストレスのない食事体験が実現する。また、猫型ロボットに代表されるように、ロボット自体が持つエンターテインメント性は、特にファミリー層の子供たちに喜ばれ、来店の動機にもなり得る 39。最も重要なのは、配膳などの単純作業から解放されたスタッフが、おもてなしやメニューのおすすめといった、より付加価値の高い接客に集中できるようになることで、全体のサービス品質が向上する点である 55。
- ネガティブなリスク: 一方で、過度な自動化はスタッフと顧客のコミュニケーション機会を奪い、サービスが「無機質」だと感じられるリスクも存在する 39。また、ロボットでは対応できない個別のアレルギー対応や、イレギュラーな要望への対応が遅れる可能性も考慮する必要がある。
これらの分析から導き出されるのは、テクノロジーが業界を単に「ハイテク/ロータッチ(低接触)」と「ローテク/ハイタッチ(高接触)」に二極化させるのではない、という事実である。むしろ、「焼肉きんぐ」に代表されるように、テクノロジーは「プレミアム・マス」という新たな市場カテゴリーの創出を可能にしている。このモデルは、バックヤードや物流ではテクノロジーを駆使してマス市場レベルの効率性を達成し、それによって節約された人的資源を、フロントエンドでのプレミアムな高付加価値サービスに再配分する。このビジネスモデルは、従来の高級店(スケールが難しく高コスト)とも、従来の低価格店(コスト削減に追われサービスに投資できない)とも異なる、極めて強力な競争優位性を構築するものである。
第10章:主要トレンドと未来予測
これまでの分析を踏まえ、焼肉業界の今後の主要トレンドと未来像を予測する。
10.1. 業態の専門化と細分化の加速
消費者のニーズが多様化・専門化する流れは、今後さらに加速する。「一人焼肉」「大衆焼肉酒場」「ホルモン専門店」「希少部位専門店」など、特定の顧客セグメントや利用シーンに特化した業態がますます増加するだろう。あらゆる客層を狙う総合型の焼肉店は、よほど強力なブランド力や立地優位性がない限り、専門業態との競争の中で埋没していくリスクが高まる。
10.2. 大手チェーンによる寡占化の進行
本レポートで指摘した「K字回復」の構図は、今後より鮮明になる。資本力、調達力、ブランド力、そしてDX投資余力に勝る大手チェーンへの市場シェア集中は不可逆的なトレンドである 12。コスト高騰と人手不足に対応できない中小事業者の淘汰は継続し、業界再編が進むと予測される。
10.3. DXの「標準装備」化
現在、競争優位の源泉となっているモバイルオーダーや配膳ロボットは、数年後には業界の「標準装備」へとコモディティ化していくだろう。次の競争軸は、これらのツールを通じて収集された膨大な顧客データ(注文履歴、来店頻度など)をいかに活用するかに移る。AIを用いた需要予測によるフードロス削減、顧客一人ひとりに最適化されたクーポンを配信するCRM(顧客関係管理)施策などが、新たな差別化のポイントとなる。
10.4. サプライチェーンの垂直統合と多様化
価格変動リスクのヘッジと品質管理の徹底を目指し、大手プレイヤーによるサプライチェーンへの関与が深まる。叙々苑の自社工場(フードファクトリー)のように 38、自社で食肉加工センターを保有・運営する動きや、特定の生産者グループとの連携を強化し、川上へと遡る垂直統合の動きが活発化する可能性がある。同時に、調達先を特定の国に依存せず、多角化する動きも進むだろう。
第11章:主要プレイヤーの戦略分析
業界を牽引する主要プレイヤーの戦略を分析し、競争環境を明らかにする。
11.1. 物語コーポレーション(焼肉きんぐ):体験価値創造型食べ放題の王者
- ビジネスモデル: 顧客が着席したままタッチパネルで注文できる「テーブルオーダーバイキング」形式を採用。ビュッフェ形式の煩わしさを解消し、落ち着いた食事体験を提供する 43。さらに、「焼肉ポリス」と呼ばれるスタッフが最高の焼き加減を伝授するなど、食事をエンターテインメント化することで、特にファミリー層から圧倒的な支持を集めている 44。
- 業績: 増収増益を継続しており、2025年6月期は売上高1,239億円(前期比15.6%増)、営業利益92億円(同13.1%増)を達成 59。既存店売上高も好調を維持している 59。コロナ禍で競合が広告を控える中、テレビCMに積極投資し、ブランド認知度を飛躍的に高めた戦略が奏功した 42。
- 強み: 顧客体験を細部まで設計し、マニュアル化して全店で実行する卓越した組織力。タッチパネルのUI/UXを工夫し、顧客満足度と原価コントロールを両立させる緻密な戦略 37。54.3%という高い自己資本比率に支えられた強固な財務基盤を背景に、積極的な新規出店・既存店改装投資を継続している 43。
11.2. コロワイド(牛角):規模とブランド力を活かす最大手
- ビジネスモデル: 国内最大級の店舗網を誇る焼肉チェーンのパイオニア。アラカルトメニューを中心に、食べ放題コースも提供し、若者からファミリーまで幅広い客層をターゲットとする。フランチャイズ(FC)システムを積極的に活用し、迅速な店舗網拡大を実現した。
- 業績・課題: 親会社コロワイドのレインズインターナショナルセグメント(牛角等を運営)の2025年3月期売上収益は923億円 63。グループ全体の業績は増収基調にあるものの、近年は利益面で伸び悩む傾向も指摘されている 64。店舗数においては、2023年7月の571店舗から2025年7月には497店舗へと減少傾向にあり 65、ブランド力の再活性化が経営課題となっている。
- 戦略: 近年は、フードコートに特化した新業態「牛角焼肉食堂」の出店を加速させており、新たな成長ドライバーとして期待されている 63。また、若者や学生をターゲットにした手頃な価格の食べ放題プランを強化し、客層の維持・拡大を図っている 67。
11.3. 叙々苑:揺るぎない高級ブランド
- ビジネスモデル: 「高級であるより、一流でありたい」という哲学のもと、最高品質の和牛と、ホテルマンのようなきめ細やかなおもてなしを提供 68。客単価はディナーで1万円を超え 69、接待や記念日といった特別なシーンでの利用に特化している。
- 業績: 2025年3月期の売上高は318億円 68。景気変動の影響を受けにくい富裕層や法人需要を確実に捉え、安定した収益を確保している。
- 強み: 長年の歴史の中で築き上げた、他社の追随を許さない圧倒的なブランドイメージ。HACCPに対応した自社食品工場「叙々苑フードファクトリー」を保有し、仕入れから加工までを一元管理することで、高い品質を維持している 38。従業員に占める正社員比率が高く、質の高いサービスを支える強固な組織体制も特徴である 71。
11.4. 焼肉ライク:一人焼肉市場の開拓者
- ビジネスモデル: 「焼肉のファストフード」をコンセプトに、これまで手薄だった「一人焼肉」市場を開拓。一人一台の無煙ロースターを備えたカウンター席、注文から最短3分で提供するスピード、1,000円前後から楽しめるセットメニュー構成により、圧倒的な高回転率を実現している 72。
- 運営: 「牛角」創業者である西山知義氏が率いるダイニングイノベーショングループ傘下で、FC展開を主体に急成長を遂げた 72。
- 強み: 「個食化」という社会のメガトレンドを的確に捉えた、極めて明確なコンセプト。モバイルオーダーやセルフレジなどのテクノロジーを徹底活用した効率的なオペレーション。20坪程度の小規模な物件でも出店可能なフォーマットは、都市部での迅速な店舗展開を可能にしている。
| 項目 | 物語コーポレーション (焼肉きんぐ) | コロワイド (牛角) | 叙々苑 | 焼肉ライク |
|---|---|---|---|---|
| ターゲット | ファミリー層 | 幅広い層(若者、グループ) | 富裕層、法人、記念日利用 | 単身者、クイックランチ/ディナー |
| 価値提案 | 楽しさ、エンタメ性、満足感 | 手軽さ、定番の安心感 | 最高品質、一流のサービス、ステータス | 速さ、安さ、気軽さ(一人で) |
| 価格帯 | 中価格帯(食べ放題 3,000円台〜) | 中価格帯(客単価 3,000〜4,000円) | 高価格帯(客単価 10,000円〜) | 低価格帯(客単価 1,000〜2,000円) |
| コアコンピタンス | 体験価値の設計・実行力、マーケティング力 | ブランド認知度、大規模な店舗網 | 圧倒的なブランド力、品質管理能力 | コンセプトの独自性、高回転オペレーション |
| SCM戦略 | スケールメリットを活かした調達 | グループ共通の調達プラットフォーム | 自社工場による垂直統合、高品質和牛の調達 | 効率・コスト重視の輸入肉調達 |
| DXレベル | 高(タッチパネル、データ分析) | 中(モバイルオーダー導入中) | 低(伝統的サービス重視) | 高(モバイルオーダー、セルフレジ) |
| 近年の業績 | 高成長(増収増益) | 横ばい/微減(店舗数減少) | 安定 | 急成長(店舗数拡大) |
第12章:戦略的インプリケーションと推奨事項
12.1. 分析から導かれる戦略的示唆(So What?)
本レポートの分析全体を通じて、焼肉業界で事業戦略を策定する上で考慮すべき、以下の3つの戦略的示唆が導き出される。
- 示唆1:中間市場の消滅と戦略の純化: K字回復が示す通り、「安くてそこそこ美味しい」といった中途半端なポジショニングの事業者は、コスト高騰と競争激化の波に飲まれ淘汰されている。今後の市場で生き残るためには、戦略を純化させ、①圧倒的な規模とDXによる「コストリーダーシップ」を追求するか、②他社が模倣困難な独自の「差別化(体験価値)」を創造するかのいずれかに経営資源を振り切る必要がある。
- 示唆2:サプライチェーンの戦略的活用: サプライチェーンはもはや単なるコストセンターではない。輸入牛肉と国産和牛の価格逆転現象は、調達ポートフォリオの見直しを通じて、コスト構造を改善しつつ「国産」という新たな付加価値を顧客に提供する絶好の機会である。SCMは守りのコスト管理から、攻めの価値創造へとその役割を変えつつある。
- 示唆3:DXの真の目的は「人的資本の価値最大化」: DX投資の最終目的は、単なるコスト削減や省人化ではない。配膳ロボットやモバイルオーダーで単純作業を自動化し、それによって創出された従業員の時間を、顧客とのコミュニケーション、おもてなし、アップセル提案といった「人間にしかできない高付加価値業務」へ再配置することにある。DXは、人的資本の価値を最大化するための戦略的投資と捉えるべきである。
12.2. 3つの戦略的推奨事項
上記の示唆に基づき、焼肉事業者が検討すべき3つの戦略的選択肢を提示する。自社の経営資源や目指す方向性に応じて、これらのオプションを組み合わせ、あるいは一つの方向に特化することが求められる。
推奨1:体験価値に基づくセグメント戦略の明確化
- Option A: プレミアム・エクスペリエンス戦略 (叙々苑モデル): インバウンド富裕層や国内の記念日利用といった高単価市場に特化する。A5ランクのブランド和牛や希少部位の品揃えを強化し、肉のカットや提供方法に職人技を活かす。プライバシーが確保された個室空間を充実させ、顧客一人ひとりに寄り添うパーソナルな接客を徹底する。この戦略の成否は、高品質な国産和牛の安定的な調達ルートを確保できるかにかかっている。
- Option B: プレミアム・マス/エンターテインメント戦略 (焼肉きんぐモデル): ファミリー層を中核ターゲットとし、食事の「楽しさ」という体験価値を追求する。DXを徹底してオペレーション効率を高めつつ、「焼肉ポリス」のような人間味のあるサービスを組み合わせることで、効率と体験価値を両立させる。サプライチェーンにおいては、品質とコストのバランスに優れた食材(例:国産F1牛、特定の穀物肥育輸入牛)を安定的に調達する能力が競争力の源泉となる。
- Option C: ハイパー・エフィシエンシー戦略 (焼肉ライクモデル): 単身者や「安く、早く」食事を済ませたいというニーズに特化する。モバイルオーダー、完全キャッシュレス、配膳・下げ膳の自動化など、テクノロジーを極限まで活用し、徹底した省人化と効率化を図る。これにより捻出されたコストを価格に還元し、圧倒的なコストパフォーマンスで差別化する。サプライチェーンでは、価格変動が比較的少なく、安定供給が可能な輸入牛肉の調達ルートを複数確保することが重要課題となる。
推奨2:データドリブンSCMによるコスト構造改革
- 国産牛活用の戦略的転換: 国産和牛の卸売価格が軟調な現在の市場環境を最大限に活用し、メニューにおける国産牛(交雑種含む)の使用比率を引き上げることを検討する。これを単なる原価対策に留めず、「日本の生産者を応援」「本物の和牛を手頃な価格で」といったストーリーと共にマーケティングに展開し、ブランド価値向上に繋げる。
- 需要予測と発注の最適化: POSデータや予約データ、さらには天候データなどをAIで分析し、日別・時間帯別の来客数とメニュー別出数を高精度で予測するシステムを導入する。これにより、過剰在庫や品切れを防ぎ、発注精度を向上させる。特に歩留まり管理をデジタル化・徹底することで、フードロスを最小化する。
- 調達リスクの分散: 単一の国や特定のサプライヤーへの依存を避け、複数の仕入れ先を確保する(マルチプルソーシング)。これにより、価格交渉力を高めると同時に、地政学的リスクや天候不順による供給不安といった不測の事態に備える。
推強3:「省人化」と「人財価値最大化」を両立するDX・HR戦略
- オペレーションモデルの再設計: 配膳ロボットとモバイルオーダーを「標準装備」と位置づけ、ホールオペレーションをゼロベースで再設計する。単純作業から解放された従業員の役割を「オペレーター」から「エクスペリエンス・アンバサダー」へと再定義し、顧客とのコミュニケーション、メニューの魅力の伝達、快適な空間の維持といった、顧客満足度に直結する業務にリソースを集中投下する。
- 伝統技術の形式知化と継承: 熟練職人が持つ肉のカット技術や目利きのノウハウを、動画マニュアルやVRトレーニングといったデジタルツールを用いて形式知化する。これにより、経験の浅い従業員でも短期間で一定レベルのスキルを習得できる教育システムを構築し、伝統技術の継承と全社的な品質の平準化を両立させる。
- データに基づく人事管理: 「人時売上高」を店舗運営における最重要KPI(重要業績評価指標)として設定・管理する。データに基づき、繁閑に応じた最適な人員配置とシフト管理を徹底することで、労働生産性を最大化する。
| 戦略オプション | ターゲット市場 | 必要なコアコンピタンス | 投資レベル | コスト高耐性 | 収益性ポテンシャル |
|---|---|---|---|---|---|
| A: プレミアム体験 | 富裕層、インバウンド、記念日 | ブランド構築力、高品質な調達力、高度な接客スキル | 高 | 高 | 高 |
| B: プレミアム・マス | ファミリー層、グループ | 体験価値の企画・実行力、マーケティング力、効率的オペレーション | 中〜高 | 中 | 高 |
| C: 超効率化 | 単身者、コスト重視層 | DX推進力、低コストオペレーション構築力、都市部での物件開発力 | 中 | 低 | 中 |
第13章:付録(Appendix)
13.1. 関連統計データ集
- 外食産業市場規模の推移(2019年〜2023年)
- 2019年: 26兆2,834億円(コロナ前基準)
- 2020年: 18兆2,005億円(前年比30.7%減) 75
- 2021年: (データ欠損)
- 2022年: 20兆970億円(前年比18.0%増) 76
- 2023年: 約24兆円規模(前年比14.1%増) 3
- 牛肉価格の動向
- 輸入牛肉(ロイン・かた・ばら平均原価): 2020年比で平均1.7倍に上昇 1
- 国産和牛(枝肉卸売価格、去勢A5): 2024年7月時点で2,377円/kg、2020年7月の2,413円/kgを下回る水準 32
- 飲食サービス業の有効求人倍率
- 全職業平均の有効求人倍率が1.2〜1.3倍で推移する中、飲食業(飲食物調理の職業)の有効求人倍率は約2.8〜2.9倍と、極めて高い水準で推移しており、深刻な人手不足を示している 77。
13.2. 主要企業IRデータサマリー
- 物語コーポレーション(2025年6月期 通期)
- 売上高: 1,239億2,100万円 (前期比15.6%増)
- 営業利益: 92億4,200万円 (前期比13.1%増)
- 自己資本比率: 54.3%
- 情報源: 59
- コロワイド(2025年3月期 通期)
- 売上収益: 2,691億円
- セグメント別売上収益(レインズインターナショナル): 923億8,400万円
- 親会社所有者帰属当期利益: 12億4,900万円 (前期比57.0%減)
- 情報源: 63
13.3. 用語解説
- FLコスト: Food and Labor costの略。売上高に占める食材費と人件費の合計額の割合。飲食店の収益性を測る上で最も重要な経営指標の一つ。焼肉店は一般的にこの比率が高い業態とされる。
- HACCP(ハサップ): Hazard Analysis and Critical Control Pointの略。食品の製造・加工工程で発生するおそれのある危害をあらかじめ分析し、特に重要な管理点を定めて継続的に監視・記録することで、製品の安全性を確保する衛生管理の手法。2021年6月から日本の全ての食品等事業者に導入が義務化された。
- VRIO(ヴリオ): 企業の経営資源(リソース)が競争優位性を持つかどうかを分析するためのフレームワーク。Value(経済的価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織)の4つの要素で評価する。
- 歩留まり(ぶどまり): 投入した原材料の総量に対して、実際に製品として完成したものの割合。食肉加工においては、枝肉から骨やスジ、余分な脂肪などを除去した後に残る、可食部分の肉の重量比率を指す。歩留まりが高いほど、原材料を効率的に使用できていることを意味する。
- 一頭買い(いっとうがい): 牛を部位ごとではなく、一頭丸ごと買い付ける仕入れ方法。希少部位を確保でき、交渉次第で単価を抑えられる可能性があるが、全ての部位を使い切る高度な技術と販売計画が必要となる。
引用文献
- 「焼肉店」の倒産 前年から倍増 輸入牛肉に加え野菜の高騰も打撃 帝国データバンク – JAcom, https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2024/10/241003-76817.php
- 「焼肉店」の倒産動向(2024年度、速報) – 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250401_yakiniku24fy/
- 23年外食市場、24兆円規模に回復 2年連続で大幅プラス コロナ前水準には届かず, https://news.nissyoku.co.jp/news/yokotah20240927055211215
- 外食業界の動向と展望|株式会社 帝国データバンク[TDB], https://www.tdb.co.jp/report/industry/u01-gaisyoku/
- 日本フードサービス協会、2023年暦年の外食市場動向調査結果を発表 – サッポロビール, https://www.sapporobeer.jp/hanjo/gyokai/topics/post4927.html
- 焼肉店(2025年版) | 市場調査データ | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト], https://j-net21.smrj.go.jp/startup/research/restaurant/cons-yakiniku2.html
- 日本フードサービス協会/8月の外食売上8.4%増、お盆帰省需要が好調 | 流通ニュース, https://www.ryutsuu.biz/sales/r092514.html
- 焼肉新業態紹介サイト – 創業27年 全国110店舗以上を展開する焼肉屋さかいプロデュース, https://fckamei.yakiniku.jp/
- 企画に使えるデータ・事実 成長市場を探せ 焼肉店(2020年版) – J-marketing.net produced by JMR生活総合研究所, https://www.jmrlsi.co.jp/trend/data/06-dist/06-07.html
- 帝国データバンク、「焼肉店」の倒産発生状況について調査・分析を実施 – サッポロビール, https://www.sapporobeer.jp/hanjo/gyokai/topics/post6100.html
- 焼き肉店の倒産“過去最多” 去年同時期の2倍以上に「すべてのコストが上がっている」 小規模な店では厳しい価格競争に耐えきれず… – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=hCp-IK_1Bcc
- 日本の焼肉について(パート3) 外食産業としての焼肉とバーベキュー場の現在と今後 – note, https://note.com/huge_macaw9770/n/n5d56692bb120
- 今、船井総研が推奨している5つの好調な焼肉業態とは? | フードビジネス.com, https://food-business.funaisoken.co.jp/biz_eat_out/biz_eat_out_solution/public_yakiniku/12541/
- TPPによって米国と日本の食料部門に 生まれるチャンス – USDA Japan, https://www.usdajapan.org/wpusda/wp-content/uploads/2016/05/TPP-for-website-Japanese.pdf
- TPP協定交渉の合意内容について (畜産関係品目), https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_hosin/attach/pdf/index-325.pdf
- 1.農林水産分野, https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2015/pdf/161122_tpp_bunyabetsu01.pdf
- 農林水産分野のTPP関連法案 – 参議院, https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20160415033.pdf
- HACCPが義務化されました|広島市公式ウェブサイト, https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shokuhin-eisei/1026715/1014212.html
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/01_00019.html
- HACCP(ハサップ) – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
- 飲食店におけるHACCPとは?罰則や手引書を使った導入方法、役立つツールも紹介 – カミナシ, https://kaminashi.jp/media/haccp-restaurant
- HACCP(ハサップ)義務化とは?違反した際の罰則や導入事例を解説, https://www.harecord.com/article/2/
- 焼肉市場 19年1月も好調、売上高は3.9%増と26カ月連続で前年上回る/JF・外食産業市場動向調査 | 食品産業新聞社ニュースWEB, https://www.ssnp.co.jp/meat/259220/
- Z世代の飲食店選びはSNSが主流に! グルメサイト離れと「リアル重視」の実態 – 「舌肥」は, https://www.shitakoe.com/7250910213
- 【年代別】令和時代の飲食店の探し方は?【グルメサイト vs Googleマップ vs SNS】 | ショップス, https://www.shopship.jp/blog/find-restaurants/
- Z世代の飲食店探しはSNSで完結?Instagramの視覚訴求と保存性がZ世代に圧倒的人気!【StorePro調査】 – マナミナ, https://manamina.valuesccg.com/articles/4476
- Z世代は食べログどころか口コミも見ていない!?Z世代はどうやって飲食店を選ぶ? – note, https://note.com/azresearch/n/nfac5e769323c
- 飲食店の労務管理で重要なポイントとは?基礎知識や効率化する方法を紹介 | ITトレンド, https://it-trend.jp/labor_management_system/article/481-0040
- 労働基準法, https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/hatarakikata_qa_all_191108ok.pdf
- 人手不足解消の鍵は労基法にあり!飲食店が守るべきポイント解説!飲食店経営者が知っておくべき労働基準法とは?, https://gf-support.com/property/features/20250130u
- 飲食店の人件費について|時給に法的な最低額があるって知ってた? – ぶけなび, https://bukenavi.jp/kanto/opening/knowhow/synthesis8/44
- 牛肉の販売情勢, https://wagyukoushien.com/2025/wp-content/uploads/2024/11/%E3%80%90%E5%86%8D%E9%80%81%E3%80%91%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99%E2%91%A1%E7%89%9B%E8%82%89%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%83%85%E5%8B%A2.pdf
- 牛枝肉卸売価格 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/tikusan/attach/pdf/241023-23.pdf
- 山形牛一頭買いの焼肉店だからこそ楽しめる部位の違い、そして作りたての生冷麺を堪能してきた話, https://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/tamaoki/5044
- 【牛肉一頭買いしてます!ドヤッ!】←これの何が凄いのか肉屋が語る動画 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=nkUNTgMtV8Y
- 焼肉屋でよく見る「一頭買い」の意味って何? – 谷牧場, http://tanibokujou.com/wp2/blog/%E7%84%BC%E8%82%89%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%82%88%E3%81%8F%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%8C%E4%B8%80%E9%A0%AD%E8%B2%B7%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%EF%BC%9F/
- なぜ「焼肉きんぐ」は好調なのか? 数字が語る驚きの秘密, https://financial-note.com/yakiniku/
- 株式会社叙々苑 | 沖縄の新卒向け就活総合サイトりゅうナビ 2026年, https://www.ryunavi.com/2026/company/423
- 飲食店の配膳ロボットとは?機能や導入のメリット・デメリットを解説, https://www.foodtechjapan.jp/hub/ja-jp/blog/article_026.html
- 今、大注目の『配膳ロボット』 飲食店の『人手不足克服』を考える。 – 株式会社USEN, https://usen.com/column/robot/problem-solving-with-robots.html
- 配膳ロボット6つのメリットとは?導入の“効果”をご紹介します – ROBOTI(ロボティ), https://robot.i-goods.co.jp/column/502/
- 「物語コーポレーション」が高成長する理由を社長に直撃! アナリスト注目の“業界トップの成長力”に加えて認知度も上昇、値上げも好感されて株価は上昇へ!|ダイヤモンドZAi最新記事, https://diamond.jp/zai/articles/-/1016927
- 「焼肉きんぐ」が快進撃を続ける理由:物語コーポレーションの決算書から読み解く成長の秘密, https://financial-note.com/yakiniku-king/
- 倒産急増の焼肉業界で「焼肉きんぐ」が”一人勝ち”の理由とは?”食べ放題”だけじゃない魅力を現地レポと幹部取材で深掘り!都心出店の真意も聞いた | 外食 | 東洋経済オンライン, https://toyokeizai.net/articles/-/907155?display=b
- 2022年からのインバウンドを考える – アセンティア・ホールディングス(AssentiaHoldings), https://www.assentia-hd.com/news_and_pressrelease/20220524/
- 令和6年度輸出環境整備推進委託事業(農林水産業・ 食品関連産業におけるインバウンド需要と消費実態の分 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/attach/pdf/160328_shokub-17.pdf
- なぜインバウンド外国人は「日本の焼肉」が大好きなのか…肉YouTuberが「和牛の食べ方も輸出すべき」と言う理由 海外には「薄切り肉」がほとんどない (3ページ目) – プレジデントオンライン, https://president.jp/articles/-/80753?page=3
- なぜインバウンド外国人は「日本の焼肉」が大好きなのか…肉YouTuberが「和牛の食べ方も輸出すべき」と言う理由【北海道 民泊 管理】, https://weliz-co.jp/blog/detail/20240430104804/
- 和牛は海外でも大人気!インバウンド需要の高さや人気な料理を紹介! | 肉のながおか|北九州で厳選したステーキとワインを堪能, https://niku-nagaoka.com/articles/wagyu_foreigncountry/
- 外国人観光客を虜にする和牛の魅力:インバウンドSEO成功事例と実践テクニック, https://beauty-web-hunter-blog.com/inbound-wagyu-beef/
- 【飲食店】人件費率の目標の設定方法とは?業態別の平均からFLコストで解説 – ニュートン, https://hr-newton.leap-it.jp/column/personnel-costs/
- FLコスト・FL比率がパッと分かる!行列店オーナーが図解します, https://www.unchi-co.com/kaigyoblog/insyoku/flcost.html
- 飲食店経営にはFLコストが重要!目安や業態ごとの適正値を解説, https://clock-kitchen.com/columns/3540
- 配膳ロボット導入のメリット8選|注意点や導入までの流れも徹底解説 – DFA Robotics, https://dfarobotics.com/topics/merit/
- 飲食店】配膳ロボットと一緒に働いてみて、約9割が「満足している」と回答 導入での変化 第2位「他の業務に時間を使えるようになった」、第1位は? | 株式会社DFA Roboticsのプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000028572.html
- 【図解】なぜ、コロナ禍でも「焼肉きんぐ」は儲かるのか? – note, https://note.com/solati/n/n054e58853e5b
- 注目すべき経営指標「人時売上高」とは?飲食店の生産性を上げる方法 | フードビジネス.com, https://food-business.funaisoken.co.jp/biz_eat_out/biz_eat_out_consulting/eat_evaluation/eat_evaluation_column/9869/
- 飲食店経営の基本!人時売上高の重要性と上げる方法を解説 – HIRAKEL, https://www.stand-3.com/column/business-column/11284/
- 【決算説明会】「物語コーポレーション」/ 2025年6月期決算説明会 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=JNo_oXaW8OU
- (株)物語コーポレーション【3097】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3097.T
- (株)物語コーポレーション【3097】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3097.T/financials
- 【焼肉チェーン売り上げ1位】焼肉きんぐのマーケティング戦略 – note, https://note.com/mild_magpie4856/n/n1453f69d6e40
- コロワイド、2025年3月期(2024年4月~2025年3月)の連結業績を発表 – 外食ドットビズ, https://gaisyoku.biz/news/32627/
- (株)コロワイド【7616】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/7616.T
- 【2024年版】焼肉チェーンの店舗数ランキング, https://www.nipponsoft.co.jp/blog/analysis/chain-yakiniku2024/
- 【2025年版】焼肉チェーンの店舗数ランキング – 日本ソフト販売, https://www.nipponsoft.co.jp/blog/analysis/chain-yakiniku2025/
- インフォメーション 2025年 | 株式会社コロワイド, https://www.colowide.co.jp/information/
- (株)叙々苑の会社概要 | マイナビ2027, https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp95311/outline.html
- 怖がらずに一歩を踏み出す 叙々苑 創業者 新井泰道氏 – FOODLABO, http://ss-foodlabo.com/quotation/quotation_detail.php?id=109
- 叙々苑(ランチ) – 東京グルメレポート, https://www.biglive.jp/images/gourmet-report16.pdf
- 株式会社叙々苑 | GOODSTORY – ストーリーがつむぐ、人と企業の出会い, https://www.goodstory.jp/companies/jojoen/
- 世界一の焼肉ファストフードを目指す! – 飲食店コンサルタント -株式会社田中コンサルティング事務所, https://www.tanaka-consulting.jp/column/column043.html
- ダイニングイノベーショングループ、グローバル500店舗突破&「焼肉ライク」オーストラリア初進出, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000446.000034691.html
- ダイニングイノベーション – Wikipedia, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
- 2020年外食産業市場規模は18兆2005億円 前年比30.7%減 日本フードサービス協会発表, https://news.nissyoku.co.jp/news/kinbara20211223113757635
- 【令和 4 年】 Ⅰ.外食産業の市場規模, http://anan-zaidan.or.jp/data/2024-1-1.pdf
- マイナビキャリアリサーチLab 飲食業レポート(2023年11月), https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-insyokugyo.pdf
- マイナビキャリアリサーチLab 飲食業レポート(2024年2月), https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/02/2024-2-insyokugyo.pdf
- 飲食店の人手不足の実態!原因と解決策を詳しく解説 – カゴメ, https://www.kagome.co.jp/foodservice/column/01/
- 【求人倍率2.86倍】飲食業の求人応募が集まらない原因と解決策|コスト20%減も可能?!, https://guidablejobs.jp/contents/how-to-recruit/10194/
- コロワイド【25年3月期決算】、増収だが、減損で利益半減。「大戸屋」12%増の反面、「牛角」など7%減。 – フードリンクニュース, https://www.foodrink.co.jp/sp/detail.php?blog_id=4&entry_id=16089