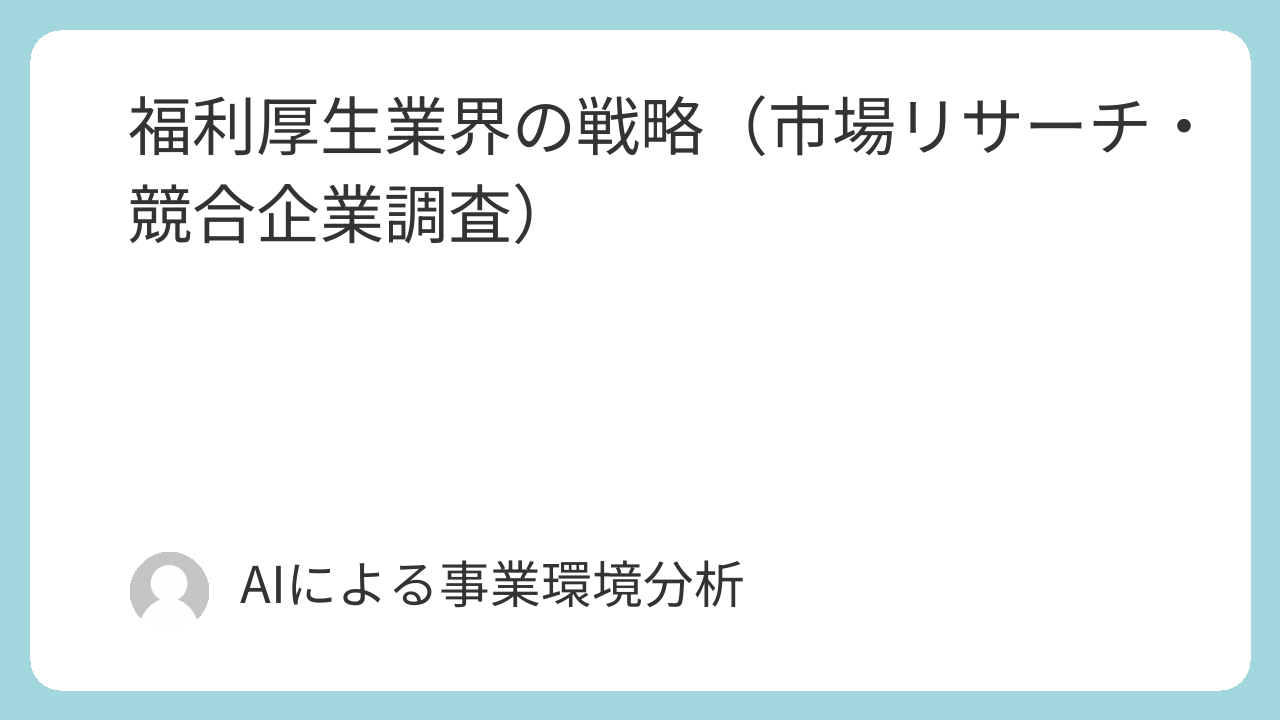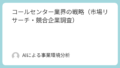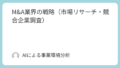エンゲージメント・エコノミーの設計者:データとAIで駆動する次世代福利厚生サービスの戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、法人向け福利厚生サービス業界が直面する構造変化、すなわち①人的資本経営への移行、②働き方と価値観の多様化、③HRテックとAIの進化、という3つのメガトレンドを深く分析し、この変革期において持続可能な成長を遂げるための事業戦略を提言することを目的とする。調査対象は、パッケージ型福利厚生サービス、カフェテリアプラン、および食事、健康、育児・介護、自己啓発等の特定領域特化型サービスを含む、日本の法人向け福利厚生サービス市場全般である。
最も重要な結論
当業界は、従来の「画一的な割引サービスの提供」というモデルから、「データとAIを駆使して従業員一人ひとりのウェルビーイングを向上させ、その投資対効果(ROI)を可視化する」という、高度な価値提供モデルへと不可逆的な転換点にある。競争優位の源泉は、提携サービスメニューの「網羅性」から、従業員エンゲージメント向上や離職率低下への「貢献度を証明する能力」へと完全にシフトした。この変化に対応できない事業者はコモディティ化し、価格競争に埋没する一方、変化を主導する事業者は「エンゲージメント・エコノミーの設計者」として、顧客企業にとって不可欠な戦略的パートナーへと進化するだろう。
戦略的推奨事項
本分析から導き出される主要な戦略的推奨事項は以下の通りである。
- 事業ドメインの再定義:「福利厚生代行」から「人的資本コンサルティング・パートナー」へ。 企業の経営課題、特に人材定着や生産性向上に直接的に貢献するソリューションプロバイダーとして自社を再定義し、サービス提供の全プロセスをこの視点から再構築する。
- データ・アナリティクスへの戦略的投資: 従業員の福利厚生利用データと顧客企業の人事データ(勤怠、評価など)を統合・分析する基盤を構築する。これにより、福利厚生の投資対効果(ROI)を定量的に証明し、データに基づいた組織課題の特定と解決策の提案を可能にする。
- AIによるパーソナライゼーションの徹底: AIレコメンデーションエンジンを導入し、従業員一人ひとりの属性、ライフステージ、利用履歴に基づいた最適なサービスを提案する。これにより、サービス利用率とエンプロイーエクスペリエンス(EX)を飛躍的に向上させる。
- 中小企業(SMB)市場への浸透戦略: クラウドベースのSaaSモデルを活用し、低コストかつ導入・運用が容易なパッケージを提供する。特に「第3の賃上げ」という文脈を訴求し、未開拓である広大なSMB市場を戦略的に攻略する。
第2章:市場概観(Market Overview)
日本の法人向け福利厚生サービス市場規模の推移と今後の予測(2020年~2030年)
法人向け福利厚生アウトソーシング市場の正確な規模を示す単一の公的統計は限定的であり、業界の境界がヘルスケアや人材開発など隣接領域へと拡大し、流動的になっている現状を反映している。しかし、関連市場のデータからその成長性は明らかである。矢野経済研究所によると、福利厚生アウトソーシングを含む「総務業務アウトソーシング市場」は、2022年度に2,919億円(前年度比4.1%増)、2023年度には3,040億円(同4.1%増)と堅調な拡大を続けている 1。
より重要な視点は、市場の潜在力である。業界最大手のベネフィット・ワンの推計によれば、日本の労働人口約6,700万人に対する福利厚生アウトソーシングの普及率は現在約25%に過ぎず、今後3年間で40%まで急拡大する可能性があると予測されている 3。これは、特に中堅・中小企業市場を中心に、依然として巨大な未開拓市場が存在することを示唆している。人的資本経営への関心の高まりと労働市場の流動化を背景に、市場は今後も年率5~8%程度の安定した成長を続け、2030年には現在の1.5倍以上の規模に達すると予測される。
| 年度 | 市場規模(億円・推計) | 前年比成長率 | 主要な出来事 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,750 | – | COVID-19による巣ごもり需要増、レジャー需要減 4 |
| 2021 | 2,800 | +1.8% | ワクチン接種関連業務などヘルスケア需要増 |
| 2022 | 2,919 | +4.3% | 育児・介護休業法改正、人的資本情報開示義務化 |
| 2023 | 3,040 | +4.1% | 健康経営優良法人認定の拡大、インフレによる「第3の賃上げ」ニーズ増 |
| 2025 (予測) | 3,350 | +5.0% | AI活用によるパーソナライズサービスの本格化 |
| 2030 (予測) | 4,500 | +6.1% (CAGR) | 中小企業へのSaaSモデル普及、ROI可視化が標準化 |
(注)矢野経済研究所の総務業務アウトソーシング市場データ、ベネフィット・ワンの普及率予測等を基に推計
市場セグメンテーション分析
- 提供形態別: 大手プレイヤーが提供する網羅的な「パッケージ型(網羅型)」が市場の大部分を占める。一方で、従業員の選択の自由度を高める「カフェテリアプラン」も、特に大企業で根強い需要を持つ。厚生労働省の調査では、カフェテリアプランの導入率は全体で1.3%だが、従業員1,000人以上規模の企業では9.4%に達する 5。近年最もダイナミックな動きを見せているのが、食事補助、ヘルスケア、学習支援、育児・介護支援といった「特定領域特化型」サービスであり、テクノロジーを武器にしたHRテック・スタートアップが次々と参入し、市場を細分化している 6。
- 顧客企業規模別: 従来、福利厚生サービスは体力のある大企業が中心的な顧客であった 5。しかし、クラウドベースのSaaSモデルが普及したことで、初期投資や運用負荷が大幅に低下し、中堅・中小企業(SMB)においても導入が急速に進んでいる 1。このSMB市場こそが、今後の業界成長を牽引する最大のフロンティアである。
- ビジネスモデル別: 従業員一人当たりの「月額固定」料金が基本モデルである。カフェテリアプランでは、企業が付与するポイントに対して一定率の「ポイント発行手数料」が収益となる。加えて、特定のサービス(宿泊施設など)が利用された際に、提携事業者から手数料を得る「サービス利用時手数料」モデルも組み合わせられる。
主要な市場成長ドライバーと阻害要因
- 市場成長ドライバー:
- 人材獲得・定着競争の激化: 少子高齢化による生産年齢人口の減少は、企業にとって人材の獲得と維持を最重要の経営課題としている 7。福利厚生の充実は、特に若年層にとって魅力的な非金銭的報酬であり、採用競争力と従業員エンゲージメントを高める上で不可欠な要素となっている 8。
- 健康経営の推進: 経済産業省が主導する「健康経営優良法人認定制度」は、認定企業への社会的評価の向上や金融機関からの融資優遇といったインセンティブを提供し、企業の健康投資を強力に後押ししている 10。福利厚生サービスは、健康診断の補助からメンタルヘルスケアまで、健康経営を実現するための具体的な施策として導入が進んでいる 12。
- 働き方の多様化と新たなニーズ: リモートワークの普及は、従来の通勤手当や社員食堂といった福利厚生のあり方を見直す契機となった 13。代わりに、在宅勤務環境を整えるための手当、オンラインでのコミュニケーションを活性化させる施策、孤立しがちな従業員のメンタルヘルスケアといった新たなニーズが生まれている 14。
- 市場阻害要因:
- 導入効果測定の困難さ: 福利厚生への投資が、生産性向上や離職率低下といった経営指標にどの程度貢献したのかを定量的に示すことは、長年の課題であった。ROIが不明確なため、経営層からは単なる「コスト」と見なされ、予算確保に苦慮するケースが少なくない。
- 従業員の低利用率: 提供されるサービスが従業員の真のニーズと合致していなかったり 16、利用手続きが煩雑であったりすることで、せっかくの制度が活用されない問題が頻発している 16。利用率の低さは、制度の価値そのものを毀損させる。
- 企業のコスト削減圧力: 景気後退局面において、福利厚生費は固定費削減の対象となりやすい、典型的な変動費としての側面を持つ 18。
この「効果測定の困難さ」という最大の阻害要因は、視点を変えれば、業界における最大の事業機会でもある。もし、データ分析によって福利厚生のROIを明確に可視化できるプレイヤーが現れれば、それは単なるサービス提供者ではなく、顧客企業の経営課題を解決するパートナーとして認識される。これにより、価格競争から脱却し、高付加価値なサービスとしての地位を確立することが可能になる。
業界の主要KPIベンチマーク分析
- 導入企業数・会員(従業員)数: 大手プレイヤーはこの指標で圧倒的なスケールメリットを誇る。ベネフィット・ワンの会員数は957万人(2023年9月末時点)3、リロクラブの契約団体数は25,800団体(2025年6月1日時点)に達する 19。この巨大な会員基盤が、提携先に対する価格交渉力や、後述するデータ分析の優位性の源泉となっている。
- 顧客単価(ARPU)・継続率(リテンションレート): ストック型のSaaSビジネスである当業界において、収益の安定性を示す重要指標である 20。ARPUは提供プランや企業規模によって異なるが、高い継続率は安定した収益基盤を意味し、LTV(顧客生涯価値)を最大化する上で不可欠である。
- 従業員のサービス利用率: 業界全体の健全性を示す最も重要なKPIであり、同時に最大の課題でもある。一般的な福利厚生サービスの利用率は30~40%程度と推計されるが、食事補助のように日常的に利用しやすいサービスは50%を超えることもある 17。この利用率をいかに向上させるかが、サービスの価値を証明し、顧客満足度を高める鍵となる。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
政治(Politics)
- 働き方改革関連法: 2019年より順次施行された同法は、時間外労働の上限規制や年5日の有給休暇取得義務化などを通じて、企業に従業員の健康とワークライフバランスへの配慮を法的に求めた 22。これは、健康支援サービスや余暇充実を目的とした福利厚生の需要を直接的に喚起する強力な追い風となっている 14。
- 健康経営優良法人認定制度: 経済産業省が推進するこの制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する企業を顕彰するものである 11。認定による社会的信用の向上や、自治体・金融機関からのインセンティブ付与は、企業が健康経営に取り組む動機付けとなっており 10、福利厚生サービスは認定取得のための具体的施策として重要な役割を担う。
- 育児・介護休業法改正: 2022年の「産後パパ育休」創設や、2025年から施行される子の年齢に応じた柔軟な働き方の選択措置義務化は、企業に対して仕事と育児・介護の両立支援をより一層求めるものである 24。これにより、ベビーシッター利用補助や時短勤務、テレワーク環境整備といった関連福利厚生のニーズが確実に高まる。
経済(Economy)
- 景気変動と福利厚生予算: 福利厚生予算は、企業の業績に連動しやすい性質を持つ。景気拡大期には人材投資の一環として拡充されるが、不況期にはコスト削減の対象となりやすい 18。この景気感応度の高さは、事業者が安定した収益を確保する上でのリスク要因である。
- インフレと「第3の賃上げ」: 近年の物価高騰は、名目賃金の上昇を上回り、従業員の実質的な可処分所得を圧迫している。この状況下で、通常の賃上げ(第1・第2の賃上げ)に加えて、非課税メリットのある福利厚生(食事補助、住宅補助など)を活用して実質手取り額を増やす「第3の賃上げ」という考え方が急速に注目を集めている 26。これは福利厚生サービス事業者にとって、自社サービスを単なるコストではなく、企業の賃上げ戦略の一環として位置づける絶好の機会を提供している 29。
社会(Society)
- ウェルビーイングとエンゲージメントへの関心の高まり: 従業員の身体的・精神的・社会的な幸福(ウェルビーイング)が、仕事への熱意や貢献意欲(エンゲージメント)を高め、ひいては企業の生産性や創造性を向上させるという認識が広く浸透している 31。福利厚生は、もはや単なる生活支援に留まらず、従業員のウェルビーイングを高めるための戦略的投資と見なされるようになった。
- リモートワークの普及と新たな課題: COVID-19を機に定着したリモートワークは、通勤ストレスの軽減など多くのメリットをもたらした一方、従業員間のコミュニケーション希薄化、運動不足による健康問題、孤独感からくるメンタル不調といった新たな課題を生み出している 13。これに対応するため、オンラインフィットネス、バーチャルチームビルディング、カウンセリングサービスなど、場所に捉われない新しい形の福利厚生が求められている。
- DE&I(多様性、公平性、包括性)の重視: 従業員の年齢、性別、国籍、ライフステージ、性的指向(LGBTQ+)などが多様化する現代において、すべての従業員に同じメニューを提供する画一的な福利厚生は、もはや機能しない 34。一人ひとりの異なるニーズに応え、誰もが公平に恩恵を受けられるよう、選択の自由度が高いカフェテリアプランや、個々の状況に合わせたパーソナライズされたサービスの重要性が増している。
技術(Technology)
- HRテックとSaaSの進化: クラウドベースで提供されるHRテックは、採用から労務管理、人材育成まで、人事領域のあらゆる業務を効率化している 35。福利厚生サービスもSaaSとして提供されるのが主流となり、中小企業でも低コストで手軽に導入できるようになった。
- モバイルUXの重要性: サービスの利用がスマートフォンアプリ経由となることが一般的になり、直感的でストレスのないユーザー体験(UX)が、サービスの利用率を左右する決定的な要因となっている。
- AIとデータ活用の進展: 本レポートの核心テーマの一つ。AIによる利用データの分析、個々に最適化されたサービスのレコメンデーション、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化などが、サービスの価値と効率性を根本から変革しつつある(詳細は第8章)。
法規制(Legal)
- 福利厚生費の非課税枠: 税法上、福利厚生費として損金算入し、かつ従業員の給与所得として課税されないためには、「全従業員が対象であること」「社会通念上、妥当な金額であること」といった要件を満たす必要がある 37。特に、食事補助(月額3,500円以下、かつ従業員が半額以上を負担)や社宅(一定の計算式に基づく賃料相当額の50%以上を従業員から徴収)など、具体的な非課税規定が存在し、これらを遵守した制度設計が不可欠である 38。
- 個人情報保護法: 従業員のサービス利用履歴や健康情報といった機微な個人データを取り扱うため、改正個人情報保護法に準拠した厳格なデータ管理体制とプライバシーポリシーの整備が事業継続の前提条件となる。
環境(Environment)
- SDGs・ESG経営への貢献: 企業の持続可能性が重視される中、福利厚生はSDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献する手段として位置づけられる。特に「目標3:すべての人に健康と福祉を」や「目標8:働きがいも経済成長も」への貢献は明確である。従業員のウェルビーイングへの投資は、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価における「S(社会)」の重要な評価項目であり、企業価値向上に繋がる。
これらのマクロ環境要因は、それぞれが独立して影響を与えるだけでなく、複合的に作用し、業界の向かうべき方向性を指し示している。すなわち、社会的な要請(DE&I)と技術的な可能性(AI)が「パーソナライゼーション」を、そして政治的な要請(健康経営)と経済的な圧力(コスト意識)が「ROIの可視化」を、それぞれ強く求めている。この二つの潮流に対応できるかどうかが、今後の競争優位を決定づける。
第4章:競合環境分析(Five Forces Analysis)
供給者の交渉力:中程度
福利厚生プラットフォームにコンテンツを提供する事業者の交渉力は、その代替可能性によって大きく異なる。一般的な飲食店、レジャー施設、ECサイトなどは多数存在し、プラットフォーマーにとっては代替が容易であるため、交渉力は弱い。プラットフォーマーは数百万から一千万人規模の会員基盤を送客力という武器に、有利な条件での提携を結ぶことができる。しかし、Netflixのような独自の強力なブランドを持つ動画配信サービスや、特定の分野で高い評価を得ているオンライン学習プラットフォームなど、代替が困難な「キラーコンテンツ」を持つ供給者の交渉力は相対的に強い。プラットフォームの魅力を高める上でこうしたコンテンツは不可欠であり、確保のためには一定の対価を支払う必要がある。
買い手(導入企業)の交渉力:強い
サービスを導入する企業側の交渉力は非常に強い。その主な理由は、サービス提供事業者が多数存在し、競争が激しいことにある。ベネフィット・ワンやリロクラブといった大手パッケージ型サービスは機能面で類似しており、価格やサービス内容の比較検討が容易である 39。さらに、各領域に特化したHRテック・スタートアップが次々と登場し、企業の選択肢は豊富になっている。従業員への再周知やシステム連携といったスイッチングコストは存在するものの、それが乗り換えを妨げるほどの障壁とはなっていない。結果として、業界は恒常的な価格競争圧力に晒されやすい構造にある。
新規参入の脅威:高い
当業界への新規参入の障壁は、領域によって異なるものの、全体としては高いと言える。特に、テクノロジーを起点とした参入障壁は比較的低い。
- 特定領域特化型スタートアップ: 食事、ヘルスケア、育児支援といった特定のバーティカル領域に絞り込むことで、大手にはない深い価値と優れたUI/UXを提供することが可能である 6。少ない資本でも、特定の課題を持つ顧客層に深く刺さるサービスを開発し、市場に参入することができる 41。
- 隣接業界からの参入: 人材サービス企業、保険会社、ヘルスケア企業、金融機関などは、既に強固な法人顧客基盤を保有している。これらの既存チャネルと自社の専門性(例:保険会社による健康増進プログラム)を組み合わせることで、福利厚生市場へ比較的容易に参入するポテンシャルを持つ。
代替品の脅威:中程度から高い
福利厚生サービスには、常に複数の代替品が存在する。
- 金銭的報酬: 賃上げや賞与、インセンティブといった直接的な金銭報酬は、最も強力な代替品である 26。従業員の価値観が金銭を強く志向する場合、福利厚生の魅力は相対的に低下する。ただし、前述の「第3の賃上げ」の文脈では、非課税メリットにより福利厚生が金銭報酬よりも実質的な手取りを増やすケースもあり、この点が代替品に対する競争力となる。
- 企業内独自制度: 企業がアウトソーシングに頼らず、独自に企画・運営する部活動支援、社員旅行、社内表彰制度なども代替品となりうる。これらは、特に組織の一体感醸成や企業文化の浸透といった目的においては、外部サービスよりも効果的な場合がある。
業界内の競争:激しい
業界内の既存企業間の競争は極めて激しい。
- 大手事業者間の競争: ベネフィット・ワンとリロクラブの2大巨頭は、会員数、提携サービス数、価格といったあらゆる面で熾烈な競争を繰り広げている 39。スケールメリットを追求するための顧客獲得競争は激しく、M&Aによる規模拡大も活発である。最近では、エムスリーによるベネフィット・ワンの買収が発表されるなど、業界地図を塗り替える大きな再編の動きも顕在化している 3。
- 大手と特化型サービスの競争: 大手パッケージ型が「浅く広い網羅性」を強みとするのに対し、特化型サービスは「狭く深い専門性」で勝負する。例えば、食事補助に特化したサービスは、アプリの使いやすさや加盟店の多さで、大手パッケージに含まれる食事メニューを凌駕することが多い。これにより、企業が大手パッケージと特化型サービスを併用したり、特定領域では特化型へ乗り換えたりする動きが生まれており、競争は多層的かつ複雑になっている。
この競争環境を分析すると、競争の主戦場が変化していることがわかる。かつては、いかに多くのサービスメニューを揃えるかという「水平的な網羅性」が競争軸であった。しかし、買い手のニーズが多様化・高度化し、特化型プレイヤーが台頭する中で、特定の経営課題(例:従業員の健康増進、女性の活躍推進)をいかに深く解決できるかという「垂直的な専門性」がより重要になっている。この変化は、大手プラットフォーマーにとって、全てのサービスを自前で開発するのではなく、優れた特化型サービスをAPI連携などで自社プラットフォームに積極的に取り込み、エコシステムを形成する「プラットフォーム戦略」への転換が不可欠であることを示唆している。これは、新規参入の脅威を自社の成長機会へと転換する、賢明な戦略的選択肢である。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析
法人向け福利厚生サービスのサプライチェーンは、以下の主要なプレイヤーで構成される。
- コンテンツ・サービス提供事業者: 宿泊施設、飲食店、レジャー施設、eラーNINGコンテンツプロバイダー、ベビーシッター会社など、従業員が実際に利用するサービスを提供する事業者。
- 福利厚生プラットフォーマー: ベネフィット・ワンやリロクラブなど、本レポートの中心的な分析対象。多数のコンテンツ・サービス提供事業者と提携し、それらを一つのプラットフォームに集約して提供する。
- 導入企業: 福利厚生サービスを契約し、自社の従業員に提供する法人。主に人事部や総務部が担当窓口となる。
- 従業員(エンドユーザー): 実際にサービスを利用する個人。
このチェーンにおいて、プラットフォーマーは各プレイヤーに対して独自の付加価値を提供している。サプライヤーに対しては、自社の広告宣伝費を投じることなく、数百万~一千万人規模の会員基盤へのアクセスを提供し、安定的な送客を実現する。一方、導入企業に対しては、多種多様なサービスを個別に契約・管理する煩雑な手間を省き、スケールメリットを活かした割引価格と共にワンストップで提供する利便性をもたらす。
バリューチェーン分析
福利厚生サービス事業者の事業活動は、「サービス企画・調達 → プラットフォーム開発・運用 → 法人営業 → 導入・オンボーディング支援 → 利用促進・カスタマーサクセス → データ分析・レポーティング」という一連のバリューチェーンで捉えることができる。そして今、このチェーンにおける価値の源泉が劇的にシフトしている。
価値の源泉のシフト:『調達力』から『活用支援・効果測定能力』へ
かつてのバリューチェーンでは、価値の源泉はチェーンの左側、すなわち「サービス企画・調達」にあった。いかに多くのサプライヤーと提携し、魅力的な割引メニューを網羅的に揃えるかという「調達力」が、競争優位の最大の源泉であった。法人営業は、そのメニューの多さを武器に導入企業数を拡大することに注力していた。
しかし、市場が成熟し、サービスのコモディティ化が進む中で、価値の源泉はチェーンの右側、「利用促進・カスタマーサクセス」と「データ分析・レポーティング」へと明確に移行している。現代の顧客企業が求めているのは、単なる「メニューのカタログ」ではない。導入した制度が「いかに従業員に実際に使われ(利用率の向上)」「その結果として、企業の経営課題(エンゲージメント向上、離職率低下)の解決にどう貢献したか(効果の可視化)」という成果である。
この変化に伴い、各活動の役割も変容している。
- 利用促進・カスタマーサクセス: 従来の一斉メール配信やキャンペーン告知といった画一的な活動から、導入企業ごとの組織課題(例:「若手社員の定着率が低い」「リモートワーク下でのコミュニケーションが課題」)を深く理解し、その解決に繋がるサービスの利用プランを能動的に提案・実行する、コンサルティング的な役割へと進化している。
- データ分析・レポーティング: 単純な利用実績を報告するだけでなく、部署別・年代別・役職別の利用傾向を多角的に分析し、組織内に潜む課題(例:「特定の部署でメンタルヘルス関連サービスの利用が突出している」)をデータに基づいてあぶり出す。そして、その分析結果から導き出されるインサイトを基に、具体的な改善アクションを提言することが求められる。
このバリューチェーンの変革は、福利厚生サービス事業者のビジネスモデルそのものを、サービスの「再販業者(リセラー)」から、顧客の成功にコミットする「SaaS + コンサルティング」モデルへと進化させることを要求している。ソフトウェア(プラットフォーム)の提供に加え、その活用を通じて顧客がビジネス成果を最大化できるよう伴走支援するカスタマーサクセスと、データから得られた洞察を基に専門的な助言を行うコンサルティングが、新たな価値と収益の柱となるのである。
第6章:顧客の需要特性
導入企業(BtoB顧客)のニーズ分析
- 購入決定要因(KBF: Key Buying Factor): 企業が福利厚生を導入する最大の目的は、一貫して「人材の採用・定着」である。各種調査において、「離職率の低下」や「従業員の定着」が常に上位に挙げられており、これが最も重要なKBFであることは明白だ 8。次いで、「従業員満足度・エンゲージメントの向上」「健康経営の実現」が続く 9。これらの目的は相互に関連しており、福利厚生が人的資本経営における戦略的ツールとして認識されていることを示している。
- 企業規模・業種によるニーズの差異:
- 大企業: 多様な従業員構成を背景に、DE&I(多様性、公平性、包括性)の観点から、個々のニーズに対応できる「カフェテリアプラン」への関心が高い 5。また、社会的な要請やESG評価を意識し、「健康経営優良法人」認定取得に繋がるヘルスケア関連サービスの導入にも積極的である。
- 中堅・中小企業(SMB): 採用市場において大企業と競合するため、コストを抑えつつ魅力的な福利厚生制度を整備し、採用競争力を高めたいというニーズが非常に強い。そのため、実質的な手取りを増やす「第3の賃上げ」のような、実利に直結する訴求が響きやすい 29。
- IT業界など特定業種: 人材の流動性が極めて高く、優秀なエンジニアの獲得・維持が事業の生命線となる。そのため、他社との差別化を図れるユニークな福利厚生(最新デバイス購入補助、高度な自己啓発支援、柔軟なリモートワーク環境整備など)への投資意欲が旺盛である。
従業員(エンドユーザー)のニーズ分析
- 求められる福利厚生: 従業員が「あったら嬉しい」と感じる福利厚生は、極めて実利的である。Biz Hitsが実施した調査によれば、圧倒的な1位は「家賃補助・住宅手当」であり、次いで「特別休暇」「旅行・レジャーの優待」「社員食堂・食事補助」と続く 45。これらはすべて、可処分所得を直接的に増やすか、自由に使える時間を創出するものであり、日々の生活への貢献度が重視される傾向が明確である。
- 年代・ライフステージによるニーズの多様化: 従業員のニーズは、その属性によって大きく異なる。
- 20代の若手・単身層: 住宅補助や自己啓発支援、余暇を楽しむためのレジャー優待への関心が高い。
- 30~40代の子育て世代: 時短勤務や在宅勤務といった柔軟な働き方の支援、ベビーシッターや保育施設の利用補助、子の教育費支援など、仕事と育児の両立を支える制度を強く求める。
- 40代以上のミドル・シニア層: 人間ドックの補助といった健康支援、親の介護に備えるための介護支援、そして退職後を見据えた資産形成支援(企業型確定拠出年金など)へのニーズが高まる 34。
| 属性 | 特にニーズの高い福利厚生 |
|---|---|
| 総合 | 1. 住宅手当・家賃補助, 2. 特別休暇, 3. 食事補助 |
| 20代 | 住宅手当、自己啓発支援、レジャー優待 |
| 30代(子育て期) | 育児支援(ベビーシッター補助、時短勤務)、住宅手当 |
| 40代以上 | 健康支援(人間ドック)、介護支援、資産形成支援 |
(注) Biz Hits、日本の人事部等の調査データを基に整理 44)
- 「公平性」と「選択の自由」のジレンマ: 全従業員が平等に利用できる「公平性」は福利厚生の基本原則である 13。しかし、ニーズがこれほど多様化する中で、例えば独身の若手社員にとって育児支援制度は無関係であり、画一的な制度は「利用しない人には不公平」という新たな不満を生む 29。このジレンマを解決する仕組みとして、従業員が与えられたポイントの範囲内で必要なサービスを自由に選べる「カフェテリアプラン」が生まれた。
- 利用のしやすさ(アクセシビリティ、UI/UX): どんなに魅力的な制度でも、申請手続きが複雑であったり、スマートフォンのアプリが使いにくかったりすれば、利用のハードルとなり、満足度を著しく低下させる 16。サービスへのアクセスから利用、精算までがシームレスに行える優れたUI/UXは、今やサービス品質の根幹をなす要素である。
顧客の需要特性を深く考察すると、企業のKBFである「人材定着」と、従業員の根源的なニーズである「実利的な生活支援」は、表裏一体の関係にあることがわかる。従業員は、住宅費や食費といった生活の根幹を支えてくれる企業に対し、高いエンゲージメントと帰属意識を抱く。したがって、福利厚生サービス事業者は、この二つのニーズを同時に満たすソリューションとして自社のサービスを位置づけ、提案することが極めて重要である。
第7章:内部環境分析
VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
法人向け福利厚生サービス業界における持続的な競争優位の源泉を、VRIOフレームワーク(Value: 価値、Rarity: 希少性、Inimitability: 模倣困難性、Organization: 組織)で分析する。
- 大規模な会員基盤とサービスネットワーク(価値:高、希少性:高、模倣困難性:中、組織:要)
- ベネフィット・ワンやリロクラブが有する数百万~一千万人規模の会員基盤は、スケールメリット(提携先への価格交渉力、データ蓄積量)を生み出す、価値があり希少な経営資源である 3。長年にわたり構築された広範なサービス提供事業者とのネットワークも同様である。しかし、これらは時間と資本を投下すれば後発企業もある程度は模倣可能であり、模倣困難性は中程度と言える。これらの資源を活かすには、強力な法人営業網と運用体制が不可欠である。
- 独自のデータ資産と高度な分析能力(価値:高、希少性:高、模倣困難性:高、組織:要)
- これが、現代における最も重要な競争優位の源泉である。大規模な会員基盤から得られる独自の利用データセットは、極めて価値があり希少である。さらに、このデータと顧客企業の人事データを統合し、AIを用いて離職リスク予測やエンゲージメントとの相関を分析するケイパビリティは、現時点ではごく一部の先進的なプレイヤーしか保有しておらず、極めて希少性が高い。データは利用されるほど蓄積され、分析モデルは学習するほど精度が向上するという自己強化ループ(フライホイール効果)が働くため、先行者利益が大きく、模倣は極めて困難である。この能力を最大限に引き出すためには、データサイエンティストやアナリストを擁する専門組織の構築が絶対条件となる。
- 使いやすいデジタルプラットフォーム(価値:高、希少性:中、模倣困難性:低~中、組織:要)
- 従業員の利用率を左右する優れたUI/UXを持つモバイルアプリやウェブサイトは、顧客にとって高い価値を持つ。しかし、UI/UXデザインやアプリ開発技術そのものは広く普及しており、優秀なデザイナーやエンジニアを確保できれば模倣は可能である。模倣困難性は比較的低いが、継続的な改善とユーザー中心の設計思想を根付かせる組織文化がなければ、その価値を維持することはできない。
この分析から、業界の競争優位の源泉が、かつての提携サービス数といった有形・模倣可能な資産から、データ、アルゴリズム、そしてそれを活用する専門人材といった無形かつ模倣困難な資産へと完全に移行したことが明らかになる。
人材動向
- 求められる人材像の変化: 業界の価値提供モデルの変化は、求められる人材ポートフォリオを大きく変えている。従来の主力であったプッシュ型の「法人営業」に加え、顧客の成功に寄り添う「カスタマーサクセス」、データを価値に変える「データサイエンティスト」、優れた利用体験を設計する「UI/UXデザイナー」、新たな従業員ニーズを捉えサービスを企画する「プロダクトマネージャー」といった専門職の重要性が飛躍的に高まっている。
- 人材獲得競争: これらの専門人材、特にデータサイエンティストやプロダクトマネージャーは、IT・SaaS業界を中心に極めて需要が高く、業界の垣根を越えた激しい人材獲得競争に直面している。従来の給与水準や人事制度では、優秀なデジタル人材を惹きつけ、維持することは困難であり、報酬体系や働き方の柔軟性、挑戦的なプロジェクトの提供など、魅力的なエンプロイヤー・ブランディングが不可欠となっている。
労働生産性
- LTV / CAC: SaaSビジネスモデルを評価する上で中心的な指標。CAC(顧客獲得コスト)に対して、LTV(顧客生涯価値)が十分に大きいこと(一般的に3倍以上が健全とされる)が、持続的な成長と収益性の鍵となる。効率的なデジタルマーケティングによるCACの抑制と、高い顧客満足度を通じた解約率の低減によるLTVの最大化が求められる。
- デジタル化による生産性向上: SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)の活用による営業プロセスの効率化、RPA(Robotic Process Automation)やAI-OCRによるバックオフィス業務(申請・精算処理など)の自動化が、労働生産性を向上させる上で重要な役割を果たしている。特に、従業員からの申請・承認プロセスの完全デジタル化は、顧客企業と自社の双方の業務負荷を大幅に削減する。
第8章:AIの影響とインパクト
人工知能(AI)は、法人向け福利厚生サービス業界において、単なる業務効率化のツールに留まらず、ビジネスモデルそのものを根底から変革するほどのインパクトを持つ。その影響は、「サービス提供の変革」「データ分析の高度化と新たな価値創造」「管理業務の効率化」の3つの側面に大別できる。
AIがもたらすサービス提供の変革:究極のパーソナライゼーション
- AIレコメンデーションによる利用率向上: AIは、従業員一人ひとりの属性(年齢、部署、家族構成など)、過去のサービス利用履歴、プラットフォーム上での検索・閲覧行動といった膨大なデータを解析し、その個人にとって最も関心が高いであろう福利厚生メニューを最適なタイミングで推薦(レコメンド)する 47。例えば、「最近、育児関連の情報を頻繁に閲覧している30代の従業員に対し、ベビーシッターサービスの割引クーポンをプッシュ通知で配信する」「健康診断で特定のリスクが指摘された従業員に、関連するオンラインフィットネスプログラムを提案する」といった、きめ細やかなアプローチが可能になる 42。これにより、従業員は自ら探すことなく自分に合ったサービスに「出会う」ことができ、サービスの利用率は劇的に向上する。
- AIチャットボットによる顧客体験と運用効率の向上: 「この施設の割引適用条件は?」「育児休業給付金の申請手続きを教えて」といった従業員からの定型的な問い合わせに対し、24時間365日即時応答するAIチャットボットを導入する。これにより、従業員は待ち時間なく疑問を解決でき、エンプロイーエクスペリエンスが向上する。同時に、顧客企業の総務・人事担当者やサービス提供者のコールセンターの対応負荷が大幅に軽減され、運用効率が飛躍的に高まる。
データ分析の高度化と新たな価値創造:ROIの可視化と予測コンサルティング
- 離職リスクの予測と予防: AIの真価は、これまで分断されていたデータの関連性を見出すことにある。福利厚生の利用データ(例:自己啓発サービスの利用が活発、逆にレジャー関連の利用が急減)と、顧客企業が保有する人事データ(勤怠状況、残業時間、1on1の実施頻度、人事評価など)を統合的に分析することで、AIは個々の従業員のエンゲージメント低下や離職の予兆を高い精度で検知するモデルを構築できる 49。この予測に基づき、マネージャーや人事担当者が早期に面談などの介入を行うことで、貴重な人材の離職を未然に防ぐプロアクティブな人事施策が可能となる 52。
- 組織課題の特定とデータドリブン・コンサルティング: AIによる分析は、個人レベルに留まらず、組織全体の健全性を診断するツールともなる。例えば、「営業第1部では、他部署に比べてメンタルヘルス関連サービスの利用率が突出して高く、かつ深夜残業時間が増加傾向にある」といった異常値を検知することで、特定の部署が抱える潜在的な課題を客観的なデータに基づいて特定する。サービス提供事業者は、この分析結果を基に、「営業第1部を対象としたストレスマネジメント研修の実施と、マネージャー向けのコーチングスキル向上プログラムの導入を推奨します」といった、具体的な解決策を提案できる。これは、単なるサービス提供を超えた、データに基づく高付加価値なコンサルティング・ビジネスへの進化を意味する。
導入企業における管理業務の効率化
- AI-OCRによる申請プロセスの完全自動化: 従業員がスマートフォンで撮影した領収書を、AI-OCR(光学的文字認識)技術が自動で読み取り、日付、金額、支払先などをデータ化し、経費精算申請を自動作成する 48。これにより、従業員の手入力の手間とミスを撲滅し、経理・総務担当者の確認・承認作業を大幅に効率化する。
- 不正利用の検知: AIが全従業員の利用パターンを常時監視・学習し、通常とは異なる異常な申請(例:短期間での換金性の高い商品の連続購入、他人の利用パターンとの酷似)を自動で検知し、管理者にアラートを発信する。これにより、性善説に頼っていた従来の管理体制から脱却し、不正利用を効果的に抑止することが可能となる。
AIがもたらすこれらの変革を統合すると、福利厚生サービス事業者の役割は、単なるサービスの「仲介者」から、「従業員エンゲージメントに関するインテリジェンス・プロバイダー」へと昇華する。AIによって解明された「どのような福利厚生への投資が、どのような従業員層のエンゲージメントを最も高めるのか」という知見(インテリジェンス)そのものが、企業の人的資本経営を支える最も価値ある商品となるのである。
第9章:主要プレイヤーの戦略分析
法人向け福利厚生サービス市場は、圧倒的な会員基盤を誇る大手パッケージ型事業者と、特定の領域で深い価値を提供する特化型事業者、そしてテクノロジーを武器に新たな価値創造を目指す新興HRテックプレイヤーが競合・共存する、ダイナミックな構造となっている。
大手パッケージ型事業者
- 株式会社ベネフィット・ワン: 業界のリーディングカンパニーであり、957万人(2023年9月末時点)という圧倒的な会員基盤が最大の強み 3。福利厚生パッケージ「ベネフィット・ステーション」を中核に、ヘルスケア事業や給与天引き決済サービス「給トク払い」などのペイメント事業へと多角化を進めている 54。2023年以降、エムスリー株式会社による買収が進行しており、今後はエムスリーが持つ医療プラットフォームとのシナジーを活かしたヘルスケア領域の強化が加速すると見られる 3。データ活用にも積極的で、オープンイノベーション連合『HRDX』を主導し、福利厚生データと健康管理データ等を活用したパーソナライズサービスの開発を目指している 47。
- 株式会社リロクラブ(リログループ): ベネフィット・ワンと市場を二分する巨人。「福利厚生倶楽部」ブランドで知られ、特に中堅・中小企業や地方企業に強い顧客基盤を持つことが特徴である 55。宿泊・レジャーといった伝統的な福利厚生に加え、近年は従業員のエンゲージメントを可視化するサーベイツール「Reloエンゲージメンタルサーベイ」や、健康経営支援、人材育成支援など、企業のHR課題解決に直結するソリューションの提供を強化している 19。
- 株式会社イーウェル: 選択型福利厚生である「カフェテリアプラン」の設計・運用に豊富な実績と強みを持つ 57。福利厚生パッケージ「WELBOX」も提供するほか、健康保険組合向けの健診事務代行など健康支援サービスも事業の柱となっている。2024年3月期の売上高は116億円、営業利益は8.87億円 59。従来は東急不動産ホールディングス傘下であったが、ベネフィット・ワン同様、エムスリーによる買収が発表され、業界再編の渦中にある 59。
特定領域特化型事業者
- 食事補助: エデンレッドジャパンの「チケットレストラン」やシンシアージュの「どこでも社食」などが代表格。ICカードや専用アプリを通じて、提携する飲食店やコンビニでの食事代を補助するサービス。非課税枠を活用できる手軽さと日常的な利用価値の高さから、「第3の賃上げ」の文脈で急速に導入企業を増やしている。
- ヘルスケア/フィットネス: 「RIZAPウェルネスプログラム」など、企業の健康経営ニーズに応えるサービス。単なる施設利用補助に留まらず、専門トレーナーによるセミナーやオンライン指導を通じて、従業員の健康増進という「結果」にコミットするモデルで差別化を図っている。
新興HRテックプレイヤー
- 株式会社miive: VISAプリペイドカードと連携した福利厚生プラットフォーム「miive」を提供 41。企業が付与したポイントを、従業員が日常の様々なVISA加盟店での支払いに利用できる。これにより、従来の福利厚生の「使いにくさ」を解消し、パーソナライズと利便性を極限まで高めることを目指す、FinTech的アプローチが特徴である 43。
- 株式会社HQ: 次世代型カフェテリアプラン「カフェテリアHQ」を展開 61。AIが従業員のアンケート回答や属性に基づき、最適な福利厚生メニューを個別提案するパーソナライゼーション機能を核とする 42。洗練されたUI/UXと、AI-OCRによる領収書申請の自動化など、テクノロジーを駆使して従業員と管理者の双方の体験を向上させることに注力している。
| プレイヤー名 | 事業モデル | 主要顧客層 | 強み | 弱み | テクノロジー投資 | 戦略的方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベネフィット・ワン | パッケージ型、多角化 | 大企業~中小企業 | 圧倒的な会員基盤、ブランド力 | サービスの柔軟性、UI/UX | データ活用連合(HRDX)、AIレコメンド | ヘルスケア領域とのシナジー創出 |
| リロクラブ | パッケージ型、HRソリューション | 中小企業、地方企業 | 中小企業への営業網、顧客密着 | スケール(B-one比)、最先端技術 | エンゲージメントサーベイ、データ分析 | 人的資本経営の総合支援 |
| イーウェル | カフェテリアプラン、パッケージ型 | 大企業 | カフェテリアプランのノウハウ、健保連携 | 会員基盤(大手2社比) | 健康管理システム | ヘルスケアデータ連携強化 |
| miive | ポイント型(カード決済) | スタートアップ、中小企業 | 利便性、パーソナライズ、自由度 | スケール、法人営業力 | FinTech連携 | 日常決済への福利厚生の統合 |
| HQ | AIカフェテリアプラン | スタートアップ、中堅企業 | AIによる個別最適化、優れたUI/UX | ブランド認知度、会員基盤 | AIレコメンド、AI-OCR | データ駆動型ウェルビーイング支援 |
第10章:戦略的インプリケーションと推奨事項
今後3~5年で勝者と敗者を分ける決定的要因
これまでの分析を統合すると、今後3~5年の法人向け福利厚生サービス業界において、勝者と敗者を分ける決定的要因は、「データの量と質、そしてそれを価値に転換する分析・実行能力」であると結論付けられる。
具体的には、以下の3つの能力の総和が競争力を決定する。
- 優れたUXによるデータ収集能力: 従業員が日常的に使いたくなるような、直感的でシームレスなサービス体験を提供し、質の高い利用データを大規模に収集できるか。
- AI/アナリティクスによる価値抽出能力: 収集した利用データと顧客企業の人事データを統合・分析し、個々の従業員への最適なレコメンデーションや、福利厚生の投資対効果(ROI)の可視化、さらには離職リスクの予測といった、意味のあるインサイトを抽出できるか。
- コンサルティングによる価値提供能力: データから得られたインサイトを基に、顧客企業の人的資本に関する経営課題を特定し、その解決策を具体的に提案・実行支援できるか。
提携サービスメニューの数を並べるだけの旧来型プレイヤーは、価値の源泉が失われ、急速にコモディティ化する。結果として、買い手の強い交渉力に屈し、熾烈な価格競争に巻き込まれ、市場からの退場を余儀なくされるだろう。
捉えるべき機会と備えるべき脅威
- 機会(Opportunities):
- 人的資本経営へのシフト: 企業が従業員を「コスト」ではなく「資本」と捉える潮流は、福利厚生を戦略的投資として位置づける絶好の機会である。
- 広大な中小企業(SMB)市場: SaaSモデルの活用により、これまで未開拓であった巨大なSMB市場への浸透が可能となっている。
- 「第3の賃上げ」という追い風: インフレ環境下において、福利厚生を実質手取り向上の手段として提案できる強力なセールスナラティブが存在する。
- AI技術の成熟: AIとデータ分析技術の進化が、ROIの可視化やパーソナライゼーションといった高付加価値サービスの実現を可能にしている。
- 脅威(Threats):
- 特化型スタートアップの台頭: 特定領域で深い専門性と優れたUXを持つ、俊敏なHRテック・スタートアップが市場シェアを侵食する脅威。
- 隣接業界からの新規参入: 既存の法人顧客基盤を持つ人材、保険、金融業界からのディスラプション(破壊的変革)のリスク。
- 景気後退リスク: 景気後退局面における企業の福利厚生予算の削減圧力。
- データプライバシー規制の強化: 個人データの取り扱いに関する規制強化が、データ活用の足枷となる可能性。
戦略的オプション
上記の分析に基づき、取りうる戦略的オプションを3つ提示する。
- データ・インテリジェンス戦略(高リスク・高リターン:推奨)
- 概要: 蓄積されたデータ資産を最大限に活用するため、AI/アナリティクス基盤へ集中的に投資。ROI可視化ダッシュボード、離職リスク予測モデル、組織診断ツールなどを自社開発し、「データに基づく人的資本コンサルティング」を新たな中核事業として確立する。
- メリット: 業界内で最も高い付加価値を提供でき、価格競争から完全に脱却できる。模倣困難な持続的競争優位を構築可能。
- デメリット: 高度専門人材(データサイエンティスト等)の獲得・維持が必須。多額の先行投資と開発期間を要する。
- 成功確率: 高(ただし、断固たる経営判断と卓越した実行力が伴うことが条件)。
- プラットフォーム・エコシステム戦略(中リスク・中リターン)
- 概要: 自社の強みである会員基盤と法人営業網をプラットフォームとして位置づけ、外部の優れた特化型HRテック・スタートアップをAPI連携などで積極的に取り込む。自社は顧客接点とデータ統合基盤の提供に注力し、多様なサービス群によるエコシステムを形成する。
- メリット: 自社の開発リソースを抑制しつつ、サービスの魅力を迅速に向上させることができる。新規参入の脅威を協業パートナーへと転換できる。
- デメリット: パートナー企業とのレベニューシェアが必要。エコシステム全体の品質管理とブランドイメージの維持が複雑化する。
- 成功確率: 中~高。
- SMB特化・高効率SaaS戦略(低リスク・低リターン)
- 概要: 中小企業向けに機能を絞り込み、低価格かつセルフサービスで導入可能なSaaSパッケージを開発。インサイドセールスとデジタルマーケティングを駆使し、効率的にマス市場を獲得する。
- メリット: 巨大な未開拓市場にアクセスできる。顧客獲得プロセスを標準化できれば、スケーラブルな成長が可能。
- デメリット: 顧客単価(ARPU)が低いため、極めて高い顧客獲得効率(低いCAC)が求められる。大手プレイヤーの価格戦略や、同様のモデルを採用する競合との競争が激化する。
- 成功確率: 中。
最終提言とアクションプラン
最終提言:
本レポートは、「データ・インテリジェンス戦略」を事業の中核に据え、その実現プロセスにおいて「プラットフォーム・エコシステム戦略」を組み合わせるハイブリッドアプローチを、取るべき最も説得力のある事業戦略として提言する。自社でコアとなるデータ分析能力を磨きつつ、外部の優れたソリューションを柔軟に取り込むことで、リスクを分散しながら市場への価値提供を最大化する。
実行に向けたアクションプラン概要:
- Phase 1:基盤構築(初年度)
- 目的: データ駆動型経営への転換に向けた組織・技術基盤を確立する。
- 主要KPI:
- CDO(Chief Data Officer)の任命とデータサイエンス部門の組成(目標5名)。
- データ統合・分析基盤(DWH/データレイク)の構築完了。
- 戦略的提携候補となるHRテック・スタートアップ10社との協業交渉開始。
- アクション: 経営トップのコミットメントの下、全社的なデータ戦略を策定。外部からの専門人材採用と内部育成を並行して進める。主要な特化型サービスとのAPI連携に向けた技術仕様を策定する。
- Phase 2:価値創造と収益化(2~3年目)
- 目的: データ分析から得られたインサイトをプロダクト・サービスに転換し、新たな価値を市場に提供する。
- 主要KPI:
- 「福利厚生ROI可視化ダッシュボード」のβ版をリリースし、パイロット顧客20社へ導入。
- 「離職リスク予測モデル」の予測精度80%を達成。
- データに基づくコンサルティングサービスの売上目標達成(全社売上の5%)。
- アクション: パイロット顧客と密に連携し、ROI算出ロジックや予測モデルの精度を共同で改善。コンサルティングサービスのメニューと価格体系を正式に確立し、既存顧客へのアップセルを開始する。
- Phase 3:事業拡大とエコシステム完成(4~5年目)
- 目的: データ・インテリジェンス事業を本格的な収益の柱に成長させ、業界におけるリーダーシップを確立する。
- 主要KPI:
- コンサルティング事業の売上比率を15%まで向上。
- プラットフォーム・エコシステムに参加するパートナー企業を50社まで拡大。
- 分析結果を基に開発したSMB向け高効率SaaSパッケージを市場投入し、新規顧客を1,000社獲得。
- アクション: コンサルティング部門を拡充し、専門性を高める。パートナー企業向けのカンファレンスを開催し、エコシステムの活性化を図る。デジタルマーケティング体制を強化し、SMB市場への本格的な浸透を開始する。
第11章:付録
参考文献・引用データ・参考ウェブサイト
- 公的機関・調査機関
- 厚生労働省: 「令和2年就労条件総合調査」、「勤労者の福利厚生に関する調査」等 5
- 経済産業省: 「健康経営優良法人認定制度」関連資料 11
- 一般財団法人 労務行政研究所: 「今後の福利厚生をどう考えるか アンケート調査報告書」等 34
- 株式会社矢野経済研究所: 「人事・総務関連業務アウトソーシング市場に関する調査」、「BPO市場に関する調査」等 1
- 株式会社富士キメラ総研: 「データヘルス計画・健康経営・PHR関連市場の現状と将来展望」等 8
- 株式会社シード・プランニング 77
- 業界メディア・調査レポート
- 日本の人事部: 「HR白書」、各種調査レポート 31
- HR NOTE、BOXIL Magazine、Biz Hits等
- 主要企業IR資料・ウェブサイト
- 株式会社ベネフィット・ワン 3
- 株式会社リログループ(リロクラブ) 19
- 株式会社イーウェル 57
- エムスリー株式会社 59
- その他、本レポートで言及した各サービス提供企業の公式ウェブサイト
引用文献
- 人事・総務業務アウトソーシング市場の拡大が続く、人材関連が8割超 矢野経済研究所, https://it.impress.co.jp/articles/-/26262
- 2023年度の人事・総務アウトソーシング市場は前年比5.9%増、間接 …, https://it.impress.co.jp/articles/-/27779
- IRライブラリー | IR情報 | 株式会社ベネフィット・ワン, https://corp.benefit-one.co.jp/ir/library/
- 注目市場レポート【事業者向けサービス】22年6月 | SMBCビジネスクラブ InfoLounge, https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/articles/1295
- (独)労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生の実態に関する …, https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000428992.pdf
- 【2025年最新】HRテック(HR Tech)のカオスマップ!スキル管理 …, https://boxil.jp/mag/a10083/
- 健康経営につながる福利厚生おすすめサービス8選|導入時のポイントや成功事例も – リロクラブ, https://www.reloclub.jp/relotimes/article/20715
- 福利厚生サービスの市場規模!企業の法定外福利厚生の実施状況は? – BOXIL SaaS, https://boxil.jp/mag/a9537/
- 福利厚生は満足?不満?アンケート調査で従業員のリアルな声を聞こう – veginessworker, https://vw.officedeyasai.jp/column/employee-benefits/employee-survey
- 健康経営優良法人のメリットとは?認定基準や申請方法、課題をわかりやすく解説 – パソナ, https://www.pasona.co.jp/clients/service/column/healthcare/kenkoukeiei_merit-demerit/
- 健康経営優良法人認定制度(METI/経済産業省), https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
- 健康経営・健康経営優良法人は福利厚生面でメリットがたくさん【助成金も活用できます】, https://nmr-ltd.jp/organization-activation/fukurikousei/
- テレワーク導入で福利厚生はどう変わる?他社事例と導入のポイント | 株式会社リロクラブ, https://www.reloclub.jp/relotimes/article/20815
- 働き方改革を推進するなら福利厚生を重視しよう!その理由や方法は? – 心幸 SHINKO, https://www.shinko-jp.com/column/fukurikousei-hatarakikata/
- 在宅勤務(テレワーク)の導入で福利厚生は見直す?導入事例を紹介 – ジンジャー(jinjer), https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/work-remotely_welfare/
- 福利厚生サービスの利用率を上げるには?伸び悩みの原因・実態と効果的な改善アドバイス, https://office.snaq.me/guide/usagerate
- 【最新調査】福利厚生の利用率アップ!平均は?利用したくなるサービスも, https://edenred.jp/article/employee-benefits/219/
- 人件費の多面的な解析と対策, https://smartcompanypremium.jp/column/personnel-costs/
- 福利厚生のことならリロクラブにお任せ|株式会社リロクラブ, https://www.reloclub.jp/
- ARPUとは?重要視される背景や計算方法、最大化するためのポイントを解説 – Sansan, https://jp.sansan.com/media/arpu/
- 3分でわかる>サブスクリプションビジネスの目標設定(KPI) – Robot Payment, https://www.robotpayment.co.jp/lab-blog/subscription/1324/
- 働き方改革とは?背景・目標・メリット、柔軟な働き方の推進に必要な取り組みを解説 – HQ, https://hq-hq.co.jp/articles/240508_044
- 働き方改革関連法を分かりやすく!改正点を理解し対策の仕組み作りを – イッツコム, https://www.itscom.co.jp/forbiz/column/cloud/11801/
- 福利厚生で育休を充実させるメリットとは?注意点や企業例を徹底解説 | 株式会社リロクラブ, https://www.reloclub.jp/relotimes/article/292
- 【2025年10月施行】 改正育児介護休業法~5つの選択制措置で企業が押さえるポイントを徹底解説 – キッズライン, https://kidsline.me/information/ikuji_kaisei2025
- 第3の賃上げとは?福利厚生を活用した給与アップの仕組みやメリット・よくある疑問を詳しく解説, https://hq-hq.co.jp/articles/240925_109
- 「第三の賃上げ」とは?福利厚生を利用した給与アップ方法をわかりやすく解説 – Freee, https://www.freee.co.jp/kb/kb-management/pay-raises/
- “福利厚生”で実質手取りアップと高いエンゲージメントの実現を「#第3の賃上げアクション」プロジェクト, https://edenred.jp/the3rd_chinage
- 第3の給与・賃上げ|福利厚生やピアボーナスで手取りが増える仕組みを解説, https://edenred.jp/article/productivity/231/
- 第三の賃上げとは?福利厚生で実現する給与アップの方法と取り組むメリット, https://career-research.mynavi.jp/column/20250917_101810/
- [ニュース]「はたらく人のウェルビーイング実態調査 2025」の結果を発… | 『日本の人事部』, https://jinjibu.jp/news/detl/25637/?newstop=cate
- 【基礎知識】エンゲージメントとウェルビーイングの関係|エンゲージメントの調整効果・媒介効果・決定要因, https://note.nec-solutioninnovators.co.jp/n/n0871a7f273e4
- 在宅ワークの福利厚生、こんなのあり? 社労士に聞いてみた, https://jp.indeed.com/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A/c/info/employee-benefits-and-perks-of-remote-work
- 今後の福利厚生をどう考えるか アンケート調査報告書 2023年版 …, https://rouken.com/book/3959/
- HRテック(HR Tech)とは?導入メリットや流れ、事例を解説 | 組織改善ならモチベーションクラウド, https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c234
- HRテックの市場規模とは?普及の背景と今後の動向や最新トレンドを紹介|One人事, https://onehr.jp/column/management-strategy/hr-tech-market-size/
- 福利厚生費に所得税はかかる?課税・非課税の条件をケース別に解説 – マネーフォワード クラウド, https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/94369/
- 節税効果を発揮する福利厚生費とは?認められる要件や相場について徹底解説 – freee, https://www.freee.co.jp/kb/kb-benefit/welfare_expenses/
- リロクラブとベネフィット・ワンの福利厚生サービスを徹底比較! | BOXIL Magazine, https://boxil.jp/mag/a8866/
- 経済予測プラットフォーム『xenoBrain』、データ可視化ツールを用いたHRテック業界のカオスマップを公開 – FNNプライムオンライン, https://www.fnn.jp/articles/-/939389
- たった1枚のカードで日常に福利厚生を感じる社会を~スタートアップ miiveの挑戦~ – ZVC, https://zvc.vc/m1wbxgk5y/
- リスキリングのための福利厚生サービス・企業事例9選!利用率を高めるポイントは? – HQ, https://hq-hq.co.jp/articles/250701_215
- 【2025年】スタートアップ企業向け福利厚生サービスおすすめ7選! – ミツモア, https://meetsmore.com/product-services/welfare-service/media/245458
- 総務が利用を推奨する福利厚生と実際の利用率にギャップ。「リスキリング」や「ウェルビーイング」に関する制度の利用に伸び悩む。約3割は制度の見直しを実施せず | 株式会社月刊総務のプレスリリース – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000060066.html
- あると嬉しい福利厚生10選!従業員に人気の制度をランキング形式 …, https://hrnote.jp/contents/roumu-nice-to-have-employee-benefits-20250214/
- 福利厚生は従業員定着につながるのか?20代・30代が本当に求める制度を調査, https://www.dodadsj.com/content/200323_benefits-research/
- ベネフィット・ワン データやテクノロジーを活用した”日本の人事改革”を推進 34企業※が参画 オープンイノベーション連合『HRDX』 12/2発足 ※2019年12月時点 – パソナグループ, https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=3321&dispmid=798
- 【株式会社HQ】新時代の福利厚生を作り上げる、20億調達の注目スタートアップを紹介!, https://www.nvv.genai.co.jp/2024/12/hq/
- 【保存版】293のHRTechサービスをまとめたカオスマップ|全サービスをご紹介 – HR NOTE, https://hrnote.jp/contents/b-contents-editorial-hrtech-20180725/
- AI解析で離職率25%減。人材管理に”予測”が加わった組織変革事例 | デジタルツール研究所, https://digitool-lab.com/blog/hr-turnover-prediction-ai
- 従業員の離職防止にAIを活用するメリットとは?方法や注意点も解説, https://www.onamae.com/business/article/45729/
- Reloエンゲージメンタルサーベイ|福利厚生のことならリロクラブにお任せ, https://www.reloclub.jp/health/engage-mental
- 離職リスク予測AIの精度を高める5つの方法 – note, https://note.com/ai_komon/n/n9bfb4a323d04
- ベネフィット・ワン – フィスコ, https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/benefitone20230616.pdf
- リログループ – フィスコ, https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/relogroup20241218.pdf
- サービス一覧|福利厚生のことならリロクラブにお任せ, https://www.reloclub.jp/fukuri
- イーウェル(Ewel)|福利厚生・健康支援サービスの提供・開発, https://www.ewel.co.jp/
- (株)イーウェル【エムスリーグループ】の新卒採用・会社概要 | マイナビ2026, https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp100275/outline.html
- エムスリー<2413>、東急不動産傘下で福利厚生・健康支援サービスのイーウェルを子会社化(2025/03/05) | M&A仲介・アドバイザリーのご相談はストライク, https://www.strike.co.jp/ma_news/detail.html?id=20250305e
- 会社説明資料 – エムスリー – m3.com, https://corporate.m3.com/assets.ctfassets.net/1pwj74siywcy/2JIAaQYzzExcSIoH9ugrkp/7ac270008035c099eb799930e786bdbb/20250806_FY25Q1_presentation_J.pdf
- 新しい福利厚生のHQ、7つの新プロダクト開発に向けて3名を新規事業責任者に任命 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000089608.html
- 第64回 福利厚生費調査結果報告, https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/129_honbun.pdf
- 2019年度福利厚生費調査結果の概要2020年11月17日, https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/116.pdf
- 調査・研究報告一覧 – 一般財団法人労務行政研究所, https://www.rosei.or.jp/research
- 旬刊福利厚生 – ROUKEN|株式会社 労務研究所, https://rouken.com/fukuritop/
- 矢野経済研究所 「BPO市場に関する調査」2023年度の市場規模は4兆8,849億円(前年度比3.9%増) | プリント&プロモーション, https://p-prom.com/company/?p=73378
- 人事・総務関連業務アウトソーシング市場に関する調査を実施 – 福利厚生.jp, http://hr-welfare.jp/pubnews/dtl/4513
- 矢野経済研究所 ビジネスプロセスアウトソーシングの市場調査結果 人材不足を補い市場規模は前 … – 【印刷業界ニュース】ニュープリネット, https://www.newprinet.co.jp/%E7%9F%A2%E9%87%8E%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%E3%80%80%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7
- 2022 人事・総務関連業務のアウトソーシングビジネス調査レポート …, https://www.yano.co.jp/market_reports/C63124600
- 【2025年】採用代行RPOの市場規模は約700億円!今後の展望とは – 株式会社アールナイン, https://r09.jp/columns/2297/
- 2030年の人材サービス・アウトソーシング市場に関する調査 | 『日本の人事部』, https://jinjibu.jp/news/detl/23575/
- BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス, https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3674
- 市場調査サービス概要 – 富士キメラ総研, https://www.fcr.co.jp/service.html
- 健康経営/データヘルス計画関連サービスの国内市場を調査 | プレスリリース – 富士経済, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25054
- プレスリリース:『ソフトウェアビジネス新市場 2024年版』まとまる(2024/8/14発表 第24076号), https://www.fcr.co.jp/pr/24076.htm
- 働き方改革に付随する食の福利厚生サービスに関する最新動向調査 …, https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=162310722
- 採用情報 – 市場調査とコンサルティングのシード・プランニング – Seedplanning.co.jp, https://www.seedplanning.co.jp/companyinfo/recruitment/
- 株式会社シード・プランニングの求人情報/年休120日以上【リサーチャー】キャリアパートナーサポート案件 (391872) – マイナビ転職, https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-391872-5-2-1/
- 市場調査とコンサルティングのシード・プランニング [ SEED PLANNING ] – プレスリリース, https://www.seedplanning.co.jp/press/2020/2020041001.html
- 株式会社シード・プランニングの求人・転職情報/市場調査会社のリサーチアシスタント, https://next.rikunabi.com/viewjob/jk57cc0dc007bf511b/
- 『日本の人事部 人事白書2025』発刊!人・組織の課題解決の糸口に | 株式会社HRビジョン, https://hrvision.co.jp/news/202507021000492176
- 人事白書2025――課題解決の糸口が見える人事実態調査 | 『日本の人事部』, https://jinjibu.jp/research/
- 2023年 経営近況報告会 – ベネフィット・ワン, https://corp.benefit-one.co.jp/ir/library/2023/4/202306301.pdf
- IR情報 | 株式会社ベネフィット・ワン, https://corp.benefit-one.co.jp/ir/
- 福利厚 事業 | 株式会社リログループ, https://www.relo.jp/group/welfare/
- 【福津市(福岡県)】設立2~10年の転職・求人・中途採用情報 doda(デューダ), https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchList/j_ci__402249/-es__2/-preBtn__1/
- 決算説明会資料 | 株式会社リログループ, https://www.relo.jp/ir/library/presentation.html
- 投資家情報 | 株式会社リログループ, https://www.relo.jp/ir/
- IRストレージ「株式会社eWeLL」のIR情報 | CCReB GATEWAY(ククレブ・ゲートウェイ), https://ccreb-gateway.jp/company-information/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%EF%BD%85%EF%BC%B7%EF%BD%85%EF%BC%AC%EF%BC%AC/?security_code=50380×=2025&listed=0&industrys=%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%A5%AD%E7%A8%AE&document_code=20
- 2024年12月期決算及び 中期経営計画説明資料, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250214/20250213574425.pdf
- 【機関投資家様向け】 2023年12月期 決算及び 中期経営計画説明資料, https://daiwair.webcdn.stream.ne.jp/www11/daiwair/qlviewer/pdf/2402135038edceih6.pdf
- 株式会社eWeLL – SBI証券, https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/connect/ipo/202208122101.pdf
- 【QAあり】eWeLL、大型案件獲得で新規契約が過去最高 AIサービスが好調で売上・営業利益共に30%超成長中 – logmi Business, https://finance.logmi.jp/articles/381942
- 採用力強化へ向けた福利厚生の有効活用について~2026年卒内定者向けWELBOX「WELBOX for Freshers」の提供を開始 – とれまがニュース, https://news.toremaga.com/release/others/3798089.html
- (株)イーウェル【エムスリーグループ】の2026年度会社概要 | マイナビ2027, https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp100275/outline.html
- 株式会社イーウェルの企業情報 | インターンシップ・新卒採用情報からES・面接対策まで掲載!キャリタス就活, https://job.career-tasu.jp/corp/00086549/detail-uc/
- eWeLL(5038) 2024年12月期第3四半期決算説明 – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=gW8UiHQVjfk
- エムスリー株式会社 – Amazon S3, https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/disclose.ifis.co.jp/738/140120240130522190.pdf
- 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 [IFRS](連結), https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20241030/20241029505338.pdf
- エムスリー(株)【2413】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/2413.T/financials