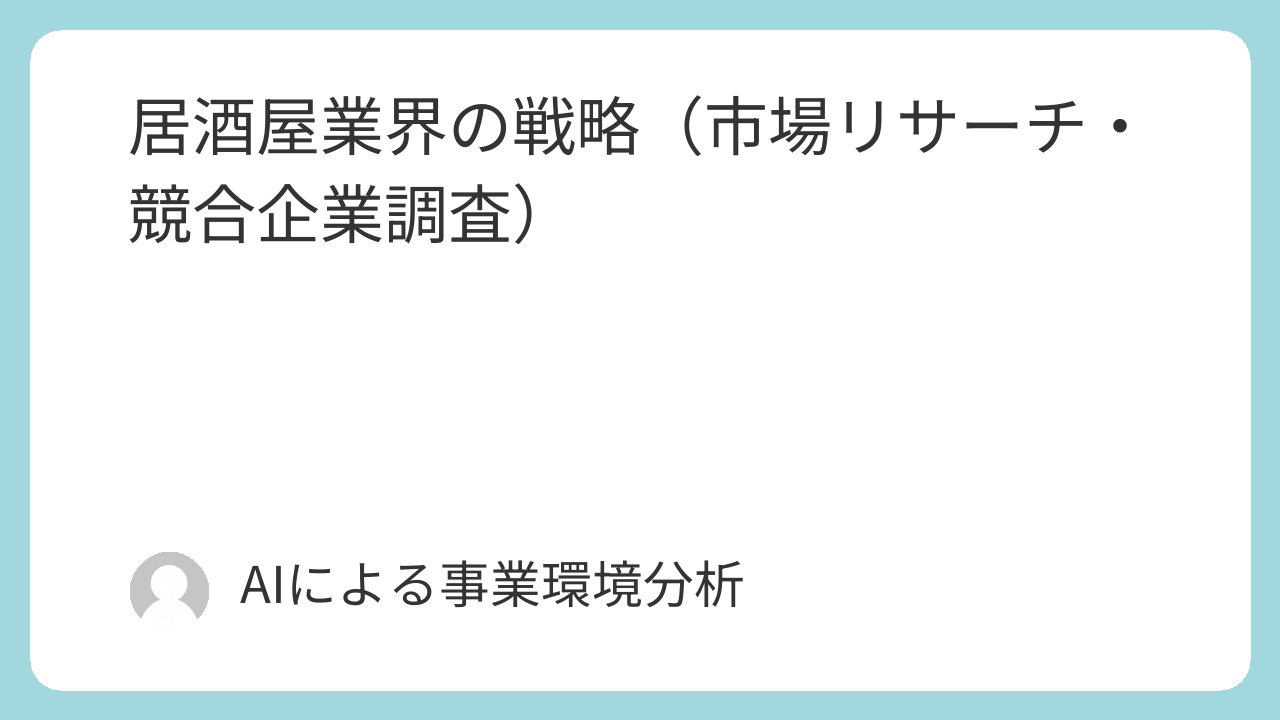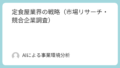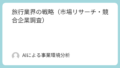ポスト・パンデミックの岐路:体験価値とDXで再定義する居酒屋業界の成長戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートは、ポストコロナ時代の居酒屋業界が直面する構造的課題、すなわち消費行動の不可逆的な変化、深刻な人手不足とそれに伴う人件費・原材料費の高騰、そして「中食・宅飲み」といった代替市場との競争激化という三重苦を深く分析し、持続可能な成長を実現するための事業戦略を提言することを目的とする。調査対象は、総合居酒屋、専門居酒屋(焼鳥、海鮮等)、バル・ネオ大衆酒場など、アルコール提供を主とする業態全般である。
居酒屋市場はコロナ禍から回復過程にあるものの、パンデミック前の市場規模には回帰しない構造変化に直面している。単に「安く飲める場」としての提供価値は薄れ、市場は①専門性・高品質を追求する「目的来店型」と、②コミュニティや体験価値を重視する「情緒的価値型」へと明確に二極化している。この変化に対応できない従来型の総合居酒屋は淘汰の道を辿る可能性が高い。今後の勝敗を分ける決定的要因は、「独自の体験価値の創出」と「デジタルトランスフォーメーション(DX)による徹底した生産性革命」を両立できるか否かにかかっている。
本分析から導き出された事業戦略上の主要な推奨事項は以下の通りである。
- 業態ポートフォリオの再構築: 収益性が低く、差別化が困難な従来型総合居酒屋から戦略的に撤退し、浮いた経営資源を「専門特化型」や「ネオ大衆酒場」といった高付加価値・高収益性が見込める成長セグメントへ集中投下する。
- DXの全面的推進による収益構造改革: モバイルオーダーや配膳ロボットの導入により省人化を進め、業界の構造的課題であるFLコスト(食材費・人件費)を抑制する。それによって捻出された人的リソースを、マニュアル化できない「体験価値の向上」に再配分する。同時に、CRM(顧客関係管理)やAI(人工知能)を活用したパーソナライズド・マーケティングを推進し、顧客ロイヤルティと生涯価値(LTV)を最大化する。
- 「中食・小売」への事業領域拡大: 実店舗をブランドの世界観を発信する「メディア」兼「体験の場」と再定義し、店舗で人気のメニューをECサイトで販売(D2C: Direct to Consumer)したり、小売向けに商品化したりすることで、店舗の売上に依存しない新たな収益源を確立する。
第2章:市場概観(Market Overview)
市場規模の推移と予測
日本の居酒屋・パブ・ビアホール市場は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより壊滅的な打撃を受けた。2021年には市場規模がコロナ禍以前(2019年)の3割程度まで落ち込んだとみられている 1。その後、行動制限の緩和に伴い回復基調にはあるものの、その道のりは険しい。NPD Japanの調査によれば、2022年の居酒屋・バーの市場規模は9,253億円と前年比で74.3%増と大幅に回復したが、2019年比では依然として51.5%減であり、市場は半減したままである 2。日本フードサービス協会のデータもこの傾向を裏付けており、2022年の「居酒屋・ビヤホール等」の市場規模は6,636億円(前年比48.0%増)となったが、他の外食業態と比較して回復ペースは鈍い 3。経済産業省も、外食産業の中で特にパブレストランや居酒屋の回復の遅れを指摘している 4。
今後の市場予測については、見方が分かれるものの、楽観的なシナリオは描きにくい。富士経済は、飲酒スタイルの変化などを理由に、2030年時点でも市場はコロナ禍以前の規模を大幅に下回ると予測している 1。一方で、AIによる市場予測を行うxenoBrainは、2030年に向けて8,264億円まで微増すると予測するが、これはバー業態の縮小を居酒屋・パブ業態の微増が補う形であり、急成長を見込んでいるわけではない 6。
これらのデータが示す戦略的意味合い(So What?)は、居酒屋市場が不可逆的な構造変化に直面しており、市場全体のパイは縮小均衡に向かう可能性が高いということである。したがって、今後の成長戦略は、市場全体の成長に乗るのではなく、縮小する市場の中で競合からシェアを奪い、より高い利益率を確保する戦略でなければならない。
| 年 | 市場規模(億円) | 前年比 | 2019年比 | 主要因・備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | (推定) 19,078 | – | 100% | コロナ禍前 | NPD Japan 2 |
| 2021 | (推定) 5,308 | – | 27.8% | コロナ禍による市場の底 | 富士経済 1 |
| 2022 | 9,253 | +74.3% | 48.5% | 行動制限緩和による回復 | NPD Japan 2 |
| 2023 | (見込) – | – | – | 5類移行による回復加速 | 富士経済 1 |
| 2030 | (予測) 8,264 | – | 43.3% | 構造変化後の市場規模 | xenoBrain 6 |
市場セグメンテーション分析
市場全体が停滞する中で、セグメント별로는成長と衰退の二極化が鮮明になっている。
- 業態別: 従来型の総合居酒屋が苦戦を強いられる一方、食事を主目的とした「専門店型居酒屋」(例:やきとり、串カツ、海鮮)は回復が進むと予測されている 1。さらに顕著な成長セグメントとして「ネオ大衆酒場」が挙げられる。これは、昭和レトロな雰囲気を現代的に再解釈した業態であり、SNS映えする内装やメニューが若者層を惹きつけている。中には23坪で月商1,400万円、坪月商50万円超といった驚異的な収益性を叩き出す店舗も出現している 7。
- 地域別: 市場の回復は都心部から先行している。店舗の商圏は立地によって大きく異なり、都心部では半径500m程度の徒歩圏が中心であるのに対し、郊外では半径3km程度の自動車利用圏(車で10分圏内)となる 9。このため、郊外店は「わざわざ車で行きたい」と思わせる強い専門性や独自のコンセプトが成功の必須条件となる。
- 客単価別: 自宅で安価に楽しめる「宅飲み」との差別化意識から、外食としての居酒屋は「機会食」としての位置づけが強まり、客単価は上昇傾向にある。ある調査では、飲酒を伴う外食の1回あたり支払額が過去10年で最も高い水準に達した 11。利用シーンも、大人数の宴会から少人数利用へとシフトし、一人当たりの単価が5,000円から9,999円といった比較的高価格帯の利用が増加している 2。
市場成長ドライバーと阻害要因
- 成長ドライバー:
- インバウンド需要の回復: 政府の観光立国推進政策と円安を背景に、訪日外国人観光客は急増している。2024年には訪日客の飲食費が1兆7千億円に達し、外食市場全体の5%以上を占める巨大な成長ドライバーとなっている 4。特に日本のローカルな食文化を体験できる居酒屋は人気が高く、インバウンド集客の成功が売上回復の鍵を握る事例も多い 12。
- 阻害要因:
- 飲み会文化の変化: 企業のコンプライアンス意識向上や働き方の多様化により、かつてのような大規模な企業宴会は激減した。社会人への調査では64.5%が「飲みニケーションは不要」と回答しており、この傾向は若手からベテランまで年代による大きな差は見られない 14。
- 若者のアルコール離れ: 20代の約半数は日常的に飲酒せず、健康志向などからあえて飲まない「ソーバーキュリアス」と呼ばれる層も20代の4分の1にのぼるとの調査結果もある 16。この社会的トレンドは、ノンアルコール・微アルコール飲料市場の急拡大を後押ししている 17。
- 可処分所得の伸び悩みと節約志向: 物価高騰に実質賃金の上昇が追いついておらず、消費者の節約志向は根強い。これは外食の頻度や単価を抑制する圧力として働く 4。
業界の主要KPIベンチマーク分析
- FLコスト比率: 飲食店の収益性を測る上で最も重要な指標の一つ。食材費(Food)と人件費(Labor)の合計額が売上高に占める割合を示す。一般的に60%以下が健全な経営の目安とされるが、近年のコスト高騰により、この比率のコントロールは極めて重要な経営課題となっている。
- 坪当たり売上高: 店舗の収益効率を示す指標。前述の通り、ネオ大衆酒場の成功事例では坪月商34万円 7 や50万円超 8 といった高い数値を記録しており、業態のコンセプトと立地戦略によって収益性に大きな差が生じている。
- 平均客単価と平均来店頻度: 来店頻度の全体的な低下傾向を、一回当たりの客単価上昇でカバーするビジネスモデルへの転換が求められている 2。店舗選択の理由も「価格の安さ」から「食べ物のおいしさ」や「いつも行くから」といった付加価値へと重点がシフトしており、リピーターの育成がこれまで以上に重要となっている 2。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
政治(Politics)
居酒屋業界は、政府の政策や規制から直接的な影響を受ける。強力な追い風となっているのが、政府のインバウンド観光政策である。「観光立国」の実現に向けた各種施策は訪日客を増加させ、特に観光地や都心部の店舗にとって大きな売上ドライバーとなっている 5。一方で、2020年4月に全面施行された改正健康増進法(受動喫煙防止法)は、事業者に大きな影響を与えた。原則屋内禁煙となったことで、非喫煙者やファミリー層といった新たな顧客層の取り込み機会が生まれたが、同時に喫煙客の離反リスクも生じさせた。喫煙室の設置など、分煙対策の巧拙が客層拡大の鍵を握っている 20。また、パンデミック時に経験した酒類提供制限や深夜営業に関する規制は、事業継続計画(BCP)における政治的リスクを業界全体に強く認識させた。
経済(Economy)
現在、業界が直面する最大の課題は経済環境の激変である。原材料費、エネルギー価格、物流費のトリプル高騰は、利益構造を根底から揺るがしている 5。特に、トラックドライバーの労働時間規制強化に起因する物流の「2024年問題」は、食材の安定供給を脅かし、仕入れコストを構造的に押し上げる要因となっている 23。これに対応するための価格転嫁は不可避だが、消費者の根強い節約志向とのジレンマに直面している 5。
さらに、全国的な最低賃金の上昇は、労働集約的な居酒屋業界の人件費(Lコスト)を直接的に増加させる。生産性向上が賃金上昇に追いつかなければ、経営を直撃する深刻な問題となる 25。為替レートの変動も無視できない。現在の円安は、インバウンド消費を促進するプラスの効果がある一方で、輸入食材の仕入れコストを増大させるマイナスの側面も併せ持つ。
社会(Society)
社会・文化的な変化は、居酒屋の存在意義そのものを問い直している。人口動態の変化、特に高齢化と単身世帯の増加は、「一人飲み」や「サク飲み」といった小規模・短時間利用の需要を喚起している 2。
最も大きな構造変化は、アルコール消費文化の変容である。いわゆる「若者のアルコール離れ」はデータ上も明らかであり、飲酒を前提としないコミュニケーションが若者世代の主流となりつつある 16。これにより、食事メインの利用シーンへの対応や、急拡大するノンアルコール・微アルコール飲料市場の取り込みが必須となっている 14。
また、健康志向の高まりも重要なトレンドであり、糖質オフや低カロリーといった健康を意識したメニュー開発が、新たな顧客層を開拓する鍵となりうる 6。
そして、店舗選択の意思決定プロセスにおいて、SNS(特にInstagramやTikTok)の影響力は絶大である。「映え」るメニューや内装は、広告費をかけずとも情報が拡散される強力な集客ツールであり、ネオ大衆酒場の成功はこの文脈で理解できる 12。
技術(Technology)
テクノロジーは、業界が抱える課題を解決し、新たな価値を創造する上で最も重要な変数となっている。
店舗運営のDXは、人手不足とコスト高騰への直接的な対抗策として急速に普及している。顧客自身のスマートフォンで注文するモバイルオーダー、セルフレジ、料理を運ぶ配膳ロボット、自動洗浄機などの導入は、省人化を実現するだけでなく、非接触という新たな顧客ニーズにも応える 5。
集客・CRMのDXも進化している。かつてのようなグルメサイトへの過度な依存から脱却し、自社アプリやSNS、Googleマップ(MEO対策)などを活用して、顧客とダイレクトな関係を構築する動きが活発化している 13。これにより、手数料を削減しつつ、顧客データを蓄積・活用したリピート促進が可能となる。
法規制(Legal)
事業運営は各種法規制の遵守が前提となる。労働基準法における労働時間管理や残業規制の厳格化は、長時間労働が常態化しがちだった業界のオペレーション変革を促している。また、食品衛生法に基づくHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の完全義務化は、食の安全に対する社会的な要求水準を高め、対応できない事業者の淘汰要因となり得る。その他、メニュー表示に関する景品表示法なども遵守が必要である。
環境(Environment)
環境への配慮は、企業の社会的責任(CSR)としてだけでなく、ブランド価値を高める要素として重要性を増している。食品ロス削減への取り組みは、SDGsへの関心の高まりを背景に、消費者の店舗選択に影響を与える可能性がある。需要予測に基づく計画的な仕入れや、宴会時の食べ残しを減らす「30・10運動」の推奨などが具体的なアクションとして挙げられる 35。また、サステナブルな食材調達も注目されている。例えば、持続可能な漁業で獲られた水産物の証であるMSC認証や、責任ある養殖水産物の証であるASC認証を取得したシーフードを積極的に採用する動きは、環境意識の高い顧客層に強くアピールする 38。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
マイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いることで、居酒屋業界の収益性がなぜ構造的に低くなりやすいのか、そして競争の力学がどのように変化しているのかを明らかにできる。
新規参入の脅威
脅威の度合い:高い
居酒屋業界への参入障壁は極めて低い。開業に必要な資格は、1日の講習で取得可能な「食品衛生責任者」程度であり、特別な調理技術がなくても比較的容易に開業できる 41。このため、個人経営の小規模店舗が次々と市場に参入し、常に過当競争状態が続いている 34。また、レストランチェーンや小売業がアルコール提供や惣菜販売を強化するなど、異業種からの参入も絶えない。この低い参入障壁は、既存事業者に対して常に価格とサービスのプレッシャーを与え続ける構造となっている。したがって、既存店はブランド力や常連客との強固な関係性といった、新規参入者が容易に模倣できない無形の資産を構築し、差別化を図る必要がある。
代替品の脅威
脅威の度合い:非常に高い
居酒屋業界は、多様かつ強力な代替品・サービスの脅威に常に晒されている。
- 中食・デリバリー: Uber Eatsや出前館といったフードデリバリーサービスの普及により、消費者は自宅にいながら専門店の料理を手軽に楽しめるようになった。
- 宅飲み: 小売店で販売される酒類や惣菜の品質向上と価格の安さから、「宅飲み」は最も強力な代替品と言える。特にコロナ禍を経て、その利便性と経済性が消費者に広く浸透し、外飲みの機会を奪う最大の要因となっている 43。
- 他の外食業態: 居酒屋が「食事」の機能を強化するにつれて、レストラン、ファミリーレストラン、カフェなども直接的な競合となる。
これらの代替品は「コスト」「利便性」「プライバシー」といった点で居酒屋よりも優れた価値を提供する場合が多い。この事実は、居酒屋が「店でしか味わえないライブ感のある雰囲気」「プロによる心のこもった接客」「顧客同士が交流できるコミュニティ機能」といった、代替品では決して提供できない独自の体験価値を徹底的に磨き込む必要があることを示唆している。
買い手(顧客)の交渉力
脅威の度合い:非常に高い
顧客は極めて強い交渉力を持っている。都市部では無数の飲食店がひしめき合っており、顧客にとって店舗を乗り換える際のスイッチングコストはほぼゼロに近い。さらに、グルメサイトの普及は、顧客が店舗の評価や価格を容易に比較できるようにした。サイト上の口コミや評価、クーポンの存在は顧客の価格感度を高め、店舗を激しい価格競争へと誘導する 44。グルメサイトへの集客依存は、高額な広告料や送客手数料を通じて利益を圧迫するリスクもはらんでいる 44。この強い買い手の交渉力に対抗するためには、価格以外の魅力、すなわち独自のメニュー、居心地の良い空間、店員との良好な関係性などを通じて顧客ロイヤルティを構築し、リピーターを確保する戦略が不可欠である。
売り手(サプライヤー)の交渉力
脅威の度合い:中〜高い
複数のサプライヤーが業界の収益性に影響力を持っている。
- 食材・飲料メーカー: 特定の食材を扱う専門卸や、市場を寡占する大手ビールメーカーは価格交渉において優位な立場にある。近年の世界的な原材料費高騰局面では、その価格転嫁圧力が経営を直撃している 46。
- 不動産オーナー: 都心の一等地など好立地の物件オーナーは非常に強い交渉力を持ち、家賃は経営における最大の固定費の一つとなる。
- 人材: 深刻な人手不足を背景に、労働者(売り手)の交渉力は著しく高まっている。賃金上昇圧力は今後も継続することが予想される。
- グルメサイト運営企業: 多くの店舗が集客を依存しているため、プラットフォームとしてのグルメサイトは強い交渉力を持つ。
これらの強い売り手からのコスト上昇圧力を吸収するためには、①顧客への適切な価格転嫁、②産地直送など仕入れルートの多様化・短縮化による中間マージンの削減、③DXによるオペレーション効率化を通じたコスト削減、といった多角的な打ち手が必須となる。
業界内の競争
脅威の度合い:非常に激しい
低い参入障壁と高い代替品の脅威の結果として、業界内の競争は極めて激しい。大手チェーン間では、スケールメリットを活かした価格競争や、駅前一等地を巡る立地競争が繰り広げられる。一方で、独自性の高いコンセプトで勝負する個人経営店や中堅チェーンも無数に存在し、大手チェーンの標準化されたサービスとは異なる価値を提供している 34。
重要なのは、競争の主軸が変化している点である。単純な価格競争は、利益なき消耗戦に陥りやすい。現在の競争の主戦場は、いかにユニークな「体験価値」(専門性、雰囲気、エンターテインメント性)を提供できるかという点に明確にシフトしている。SNSで若者から絶大な支持を集めるネオ大衆酒場の隆盛は、この競争軸のシフトを象徴する現象である 48。この環境下では、競合と同じ土俵で戦うのではなく、独自のコンセプトを確立し、特定の顧客セグメントから熱狂的に支持される「ニッチトップ」を目指す戦略が有効となる。
第5章:サプライチェーンとバリューチェーン分析
サプライチェーン分析
居酒屋のサプライチェーンは、食材や飲料が生産者から店舗に届くまでの複雑な流れで構成されている。
- 調達ルート: 一般的に、食材(生鮮品、加工品)や飲料(酒類、ソフトドリンク)は、「生産者 → 卸売市場/食品商社 → 卸売業者 → 店舗」という多段階のルートを辿る 49。この構造は、各段階でマージンが発生し、最終的な仕入れコストを押し上げる要因となっている。
- 物流の「2024年問題」: 2024年4月から適用されたトラックドライバーの時間外労働上限規制は、物流業界全体に深刻な影響を及ぼしている。飲食店にとっては、①配送コストのさらなる上昇、②遠隔地からの食材の納品リードタイム長期化(鮮度低下リスク)、③配送頻度の減少や最低発注ロットの引き上げといったサービス条件の変更、といった形で経営を圧迫する 23。これにより、計画的な発注と高度な在庫管理がこれまで以上に重要となる。
- サプライチェーンの変革: このような課題に対応するため、サプライチェーンの透明化や短縮化が新たな価値を生み出している。例えば、生産者と直接契約する「産地直送」は、中間マージンを削減しコストを抑えるだけでなく、新鮮で高品質な食材の安定確保を可能にする。さらに、「〇〇県の漁港から直送」といったストーリーは、メニューの付加価値を高め、顧客に対する強力なアピールポイントとなる。
バリューチェーン分析
居酒屋ビジネスの価値創造プロセスをバリューチェーンの観点から分析すると、価値の源泉がどこにシフトしているかが明らかになる。バリューチェーンは主に以下の活動で構成される。
- メニュー開発・企画: 顧客ニーズやトレンドを捉え、店のコンセプトを体現するメニューを創造する活動。
- 食材調達: 品質、コスト、安定供給を考慮し、最適なサプライヤーから食材や飲料を仕入れる活動。
- 店舗開発・立地選定: ターゲット顧客にリーチできる最適な場所を選び、コンセプトに合った空間を設計・構築する活動。
- 調理・加工: 仕入れた食材をレシピに基づき調理し、最終的な商品(料理・ドリンク)を製造する活動。
- 接客・空間演出: 顧客を迎え入れ、注文を取り、料理を提供し、快適な時間と空間を演出する活動。
- マーケティング・集客: 店舗の存在を認知させ、来店を促進するための広告宣伝や販促活動。
伝統的な居酒屋では、価値の源泉は主に「④調理・加工」における料理の味や、「③立地」の利便性にあった。しかし、外部環境の変化により、この構造は大きく変化している。宅飲みや中食で美味しいものが手軽に食べられるようになった今、「調理」だけで差別化を図ることは困難になっている。
ポスト・パンデミック時代における価値の源泉は、「⑤接客・空間演出」へと明確にシフトしている。つまり、単に料理を提供するだけでなく、「そこでしか味わえない体験の演出」こそが、顧客が対価を支払う最大の理由となっている。これには、スタッフのホスピタリティ溢れる接客、SNSで共有したくなるような魅力的な内装、ライブ感のあるオープンキッチン、常連客とのコミュニケーションなどが含まれる。
また、テイクアウトやデリバリーへの対応は、既存のバリューチェーンに変革を迫る。店舗での飲食(イートイン)とは異なる容器の選定、配達に適したメニュー開発(冷めても美味しい、汁漏れしない等)、デリバリープラットフォームとの連携といった新たな活動がバリューチェーンに組み込まれる必要がある。
第6章:顧客需要の特性分析
居酒屋業界で成功するためには、多様化する顧客セグメントを深く理解し、それぞれのニーズや購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)に合わせた価値を提供することが不可欠である。
主要な顧客セグメント
顧客は、利用シーン、世代、志向性によって複数のセグメントに分類できる。
- 利用シーン別:
- 企業宴会: かつては主要な収益源だったが、飲み会文化の変化により需要は大幅に減少。個室や飲み放題プランへのニーズは依然として存在するが、頻度・規模ともに縮小傾向にある。
- 友人・知人との会食: 現在の居酒屋利用の中心。気兼ねなく話せる雰囲気、シェアしやすいメニュー、コストパフォーマンスがKBFとなる。
- デート: おしゃれな雰囲気、質の高い料理とドリンク、プライバシーが保たれる空間が重視される。
- 一人飲み: カウンター席の充実、ハーフサイズメニューの提供、店主や他の客との適度な距離感が求められる。単身世帯の増加に伴い、重要なセグメントとなっている。
- 家族での食事: 禁煙環境、子供向けメニューの有無、座敷席などがKBFとなる。食事処としての機能が求められる。
- 世代別:
- Z世代(1990年代後半~2010年代序盤生まれ): デジタルネイティブであり、SNSでの「映え」を重視。コストパフォーマンスに敏感だが、共感できるストーリーやユニークな体験には対価を支払う。アルコール離れの傾向が強く、ノンアルコールドリンクの充実度が店舗選択に影響する 52。
- ミレニアル世代(1980年代前半~1990年代中盤生まれ): 品質や本物志向が強く、食に対する知識も豊富。個室や落ち着いた雰囲気を好み、健康志向も高い。
- X世代(1960年代中盤~1980年頃生まれ): 従来の居酒屋文化に最も馴染みがある世代。なじみの店や質の高いサービスを評価する傾向がある。
- シニア層: 健康志向が強く、あっさりしたメニューや少量多品種の料理を好む。昼間の利用や早めの時間帯での利用も多い。
- 志向別:
- コスパ重視: とにかく安く飲みたい、食べたいという層。大手低価格チェーンの主要ターゲット。
- 専門性・品質重視: 特定の料理(例:熟成魚、地鶏)や酒(例:日本酒、クラフトビール)にこだわり、高くても質の良いものを求める層。専門店型居酒屋のターゲット。
- 雰囲気・体験重視: 料理の味だけでなく、店の内装、接客、他の客層を含めた全体の「体験」を重視する層。ネオ大衆酒場やコンセプト系居酒屋に惹かれる。
- 健康志向: 低糖質、低カロリー、オーガニック食材など、健康に配慮したメニューを求める層。
Z世代・ミレニアル世代の価値観
特に今後の市場の核となるZ世代やミレニアル世代は、従来の居酒屋の価値観とは異なるものを求めている。彼らにとって居酒屋は、単に酔うための場所ではなく、「SNSで共有・共感できるコンテンツ」であり、「日常から解放される非日常的な空間」であり、「同じ価値観を持つ仲間と繋がるコミュニティ」である 43。調査によれば、Z世代の大学生は居酒屋・バー(26%)よりもカラオケ(70%)や宅飲み(38%)を夜の遊びとして利用しており、その選択理由は「安さ」「時間の自由度」「友達と深く話せる」ことである 43。このことは、居酒屋がこれらの代替品と「対話価値」や「コスト」で競争していることを示唆している。
リピーター顧客と集客チャネル
新規顧客の獲得コストが高騰する中、既存顧客をリピーター化し、そのLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を高めることが収益安定の鍵となる。LTVを高める要因は、ポイントカードやクーポンといった金銭的インセンティブだけでなく、店員との良好な関係、居心地の良さ、メニューの定期的な更新といった情緒的な満足度が大きく影響する。
集客チャネルも変化している。かつてはグルメサイトが支配的だったが、現在はGoogleマップ(MEO)やInstagram、TikTokといったSNSの重要性が飛躍的に高まっている。特に若年層は、グルメサイトの点数よりも、SNSで見つけた「リアルな」写真や動画、インフルエンサーの投稿を信頼する傾向が強い。予約行動も、電話からグルメサイト経由のネット予約、さらには店の公式SNSアカウントへのDM(ダイレクトメッセージ)予約へと多様化している。
第7章:業界の内部環境分析
VRIO分析
VRIOフレームワーク(Value: 価値、Rarity: 希少性、Inimitability: 模倣困難性、Organization: 組織)を用いて、居酒屋業界における持続的な競争優位の源泉となる経営資源やケイパビリティを分析する。
- 持続的な競争優位の源泉となりうる資源・ケイパビリティ:
- 強力なブランド力: 長年にわたって築かれた信頼と独自のポジショニング(例:「鳥貴族」の全品均一価格という分かりやすいブランド)は、価値があり(Value)、希少で(Rarity)、短期間での模倣は極めて困難(Inimitability)である。これを活用できる組織(Organization)があれば、持続的競争優位となる。
- 熟練した職人技術と独自の仕入れルート: 特定ジャンルにおける卓越した職人技や、生産者との強固な関係に基づく独自の仕入れ網は、他社が容易に真似できない価値の源泉である(Value, Rarity, Inimitability)。しかし、その技術や関係性が特定の個人に依存している場合、組織的な継承が課題となり、持続性が脅かされる(Organizationの課題) 55。
- ロイヤリティの高い常連客コミュニティ: 店主と顧客、あるいは顧客同士の間に生まれる強固な繋がりや、その店ならではの「空気感」は、極めて模倣困難な無形資産である(Inimitability)。これは「情緒的価値型」居酒屋の核心であり、代替品や競合に対する強力な防壁となる。
- 一時的な競争優位に留まる資源:
- 超一等地の立地: 希少ではあるが(Rarity)、高い賃料が収益を圧迫する。また、オンラインでの店舗検索が一般化した現在、立地の絶対的な優位性は相対的に低下している。
- 標準化されたオペレーション: 大手チェーンの強みであったが、効率性だけではコモディティ化を招き、価格競争に陥りやすい。模倣も比較的容易である。
人材動向
業界の内部環境における最大のアキレス腱は、人材に関する問題である。
- 深刻な人手不足: 厚生労働省の職業安定業務統計によると、飲食サービス関連職種の有効求人倍率は極めて高い水準で推移している。特に「飲食物調理従事者」は2.57倍、「接客・給仕職業従事者」は2.00倍と、全職業平均(約1.2〜1.3倍)を大幅に上回っており、人材獲得競争が極めて激しいことを示している 57。これは一過性ではない構造的な問題であり、短期的な解決は困難である。
- 賃金相場の上昇: 激しい人材獲得競争と政府主導の最低賃金引き上げを受け、アルバイト・パートスタッフの時給をはじめとする賃金相場は上昇トレンドが続いている。これは人件費(Lコスト)を直接的に圧迫し、収益性を悪化させる主要因となっている 25。
- 採用・定着(リテンション)戦略: 賃金水準の向上だけでは人材確保は難しい。働きがい、スキルアップの機会、良好な人間関係、柔軟なシフト制度といった非金銭的な魅力を提供することが、人材の採用と定着において不可欠となっている。
- 職人の育成と技術継承問題: 専門性の高い業態では、ベテラン職人の高齢化と若手育成の遅れが深刻な経営課題となっている。調理技術にはマニュアル化が難しい「暗黙知」が多く含まれており、その継承が事業の継続性を左右するボトルネックとなっている 55。
労働生産性
- 指標と現状: 飲食店の労働生産性を測る主要なKPI(重要業績評価指標)は「人時売上高」であり、「売上高 ÷ 総労働時間」で算出される。これは従業員一人が1時間あたりにどれだけの売上を生み出したかを示す指標である。一般的な飲食店の平均は3,000円〜4,000円、5,000円以上が優良店の一つの目安とされる 64。日本の外食産業全体の労働生産性は、チップ制度の違いなどを考慮しても、欧米諸国と比較して低い水準にあると指摘されている 68。
- 生産性向上のジレンマ: コスト削減のために単純に人員を削減すると、料理の提供遅延やサービスの質の低下を招き、結果として顧客満足度を損なうリスクがある 64。生産性の向上と顧客体験の維持・向上をいかに両立させるかが、業界全体の大きな課題である。
- テクノロジーによる改善ポテンシャル: モバイルオーダーや配膳ロボットといった省人化テクノロジーは、注文受付や配膳といった単純作業を自動化する。これにより、従業員はより付加価値の高い業務(丁寧な接客、おすすめの提案、顧客とのコミュニケーションなど)に集中することが可能となり、生産性と顧客満足度の両方を向上させるポテンシャルを秘めている 5。
| 職業分類 | 有効求人倍率 | 業界への示唆 (So What?) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 飲食物調理従事者 | 2.57倍 | 専門スキルを持つ調理人材の獲得は極めて困難。調理工程の簡略化や調理ロボット導入が急務。 | 厚生労働省 57 |
| 接客・給仕職業従事者 | 2.00倍 | ホールスタッフの確保も非常に厳しい。モバイルオーダーや配膳ロボットによる省人化が不可欠。 | 厚生労働省 57 |
| 介護サービス職業従事者 | 3.59倍 | (参考) 他の労働集約型サービス業との人材獲得競争の激しさを示唆。 | 厚生労働省 57 |
| 全職業計(参考) | (約1.2-1.3倍) | 飲食業の人手不足の深刻さが際立つ。 | 厚生労働省 58 |
第8章:AI(人工知能)がもたらす影響とインパクト
AI(人工知能)は、単なる店舗オペレーションの効率化ツールに留まらず、需要予測からマーケティング、メニュー開発に至るまで、居酒屋ビジネスのバリューチェーン全体を根底から変革するポテンシャルを秘めている。AIは、経験と勘に依存してきた旧来の経営を、データに基づいた科学的な意思決定へと転換させるゲームチェンジャーである。
需要予測と発注最適化
- インパクト: 過去の売上データ(POS)、天候、曜日、近隣のイベント情報、SNSのトレンドといった膨大な変数をAIが統合的に分析し、日別・時間帯別の来客数やメニュー別の出数を高精度で予測する 69。この予測に基づき、最適な食材の発注量を自動で算出するシステムも実用化されている。
- 導入事例:
- スシロー: レーン上の寿司皿に付けたICタグから得られる膨大な販売データとAIを組み合わせた需要予測システムを導入。これにより、顧客が求めるネタを最適なタイミングでレーンに流し、食品ロスを約50%削減するという劇的な成果を上げた 70。
- サイゼリヤ: 来店予測AIを導入し、売上予測の誤差を25%改善。これにより、人員配置の最適化や食材発注の精度向上を実現している 72。
- 戦略的意味合い (So What?): 高精度な需要予測は、過剰発注による食品ロス(原価率の悪化)と、過小発注による品切れ(機会損失)という、二律背反の課題を同時に解決する。これは、原材料費が高騰する現代において、利益を確保するための極めて強力な武器となる。
マーケティングとCRM
- インパクト: AIは、顧客の属性、過去の注文履歴、来店頻度、利用金額といったCRM(顧客関係管理)データを深層学習する。これにより、顧客一人ひとりに対して最適化されたクーポンやおすすめメニューを、適切なタイミングで自動提案する「パーソナライズド・マーケティング」が実現可能となる 73。
- 導入事例:
- スターバックス: AIを活用した顧客データ分析により、個々の顧客の嗜好に合わせた新商品の推奨やプロモーションを展開し、リピート率の向上に成功している 69。
- 国内の大手飲食チェーンでも、自社アプリのログデータなどをAIで分析し、マーケティング施策のPDCAサイクルを高速化する取り組みが進んでいる 77。
- 戦略的意味合い (So What?): 全員に同じ情報を提供する画一的なマスマーケティングから、顧客一人ひとりとのエンゲージメントを深めるOne-to-Oneマーケティングへの移行を加速させる。これにより、顧客ロイヤルティとLTV(顧客生涯価値)を劇的に向上させることが可能になる。
メニュー開発
- インパクト: SNS上の口コミ、最新の食のトレンド、競合店のメニュー、さらには原価情報や栄養バランスといった多様なデータをAIが分析し、ヒットの可能性が高い新メニューのコンセプトやレシピを提案する。
- ダイナミック・プライシング: AIが需要(混雑状況、時間帯、曜日など)をリアルタイムで分析し、メニュー価格を変動させる。例えば、客足の鈍いアイドルタイムには価格を下げて集客を促し、需要が集中するピークタイムには価格を上げることで収益を最大化する。テイクアウト専門店での導入事例も存在する 77。
- 戦略的意味合い (So What?): 従来、料理長の経験と勘に頼りがちだったメニュー開発を、データドリブンな科学的プロセスへと変革し、開発の成功確率を高める。ダイナミック・プライシングは、固定価格制では取りこぼしていた収益機会を最大化する、全く新しい収益モデルとなる可能性を秘めている。
オペレーション効率化
- インパクト: AI技術は、店舗運営の様々な場面で省人化・自動化を推進し、深刻な人手不足への直接的な解決策となる。
- 導入事例:
- 予約・問い合わせ対応: AIチャットボットやAI音声認識システムが24時間365日、予約電話やウェブサイトからの問い合わせに自動で対応する。鳥貴族では、対話型AI「AIレセプション」を導入し、AIスタッフ「さゆり」が予約応対を行うことで、電話応答率の向上とネット予約4.5倍増を達成した 72。
- 調理ロボット: 炒め物、揚げ物、麺茹でといった定型的な調理作業をAI搭載のロボットが自動で行う。これにより、調理品質の安定化、提供スピードの向上、そして調理スタッフの省人化に貢献する 69。
- 配膳・下げ膳ロボット: 高度なAIセンサーを搭載した配膳ロボットが、障害物を避けながら安全かつ効率的に料理を運ぶ。すかいらーくグループや焼肉きんぐなどで導入が進み、ホールスタッフの歩行距離を大幅に削減し、負担軽減と客席回転率の向上に寄与している 69。
- 戦略的意味合い (So What?): AIによるオペレーションの自動化は、人手不足の解消と人件費削減に直結する。これにより、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い「人間ならではの接客」に集中できる。結果として、生産性と顧客満足度の両立という、業界の長年の課題を解決する道筋が見えてくる。
第9章:主要トレンドと未来予測
居酒屋業界は、外部環境の変化と内部の課題に対応するため、様々な新しいトレンドを生み出している。これらのトレンドは、業界の未来を形作る重要な要素である。
- 専門化と「ネオ大衆」:
消費者の嗜好が多様化し、専門性が求められるようになった結果、特定の食材やメニュー(例:餃子、焼売、海鮮、鶏料理)に特化した「専門居酒屋」が増加している。総合居酒屋が提供する「何でもある」安心感よりも、専門店が提供する「ここでしか食べられない」という付加価値が支持されている。同時に、昭和の大衆酒場の持つノスタルジックな雰囲気を、現代的な清潔感とデザイン性で再解釈した「ネオ大衆酒場」が若者層を中心に爆発的な人気を博している 29。SNS映えするカラフルなドリンクやユニークな内装が特徴で、単なる飲食の場を超えたエンターテインメント空間として機能している。 - ノンアル・微アル市場の拡大:
「若者のアルコール離れ」や健康志向の高まりを受け、「飲まない/飲めない」層の存在感が急速に増している。これに対応するため、クラフトコーラや自家製レモネード、ノンアルコールカクテル(モクテル)など、こだわりのノンアルコールドリンクの品揃えが店舗の競争力を左右する重要な要素となっている 14。また、アルコールを飲まない顧客も楽しめるよう、「食事メイン」のメニュー構成を強化する動きも活発化している。このトレンドは、従来の「酒場」の定義を拡張し、より幅広い客層を取り込む機会を創出している。 - ゴーストレストラン/間借り営業:
コロナ禍でデリバリー需要が急増したことを背景に、客席を持たずデリバリー専門で料理を提供する「ゴーストレストラン(バーチャルレストラン)」という業態が注目されている。既存の居酒屋が、キッチンのアイドルタイム(例:昼間の営業時間外)を活用し、デリバリー専用の別ブランド(例:唐揚げ専門店、丼もの専門店)を運営するケースが増えている。これは、既存の厨房設備と人材を有効活用し、低投資で新たな収益源を生み出す効率的なビジネスモデルである。同様に、夜のみ営業のバーが昼間にカレー店に場所を貸すといった「間借り営業」も、不動産コストを抑えたい新規開業者と、空き時間を収益化したい店舗オーナーの双方にメリットをもたらす。 - D2Cと小売化:
店舗のブランド力と人気メニューを、外食の枠を超えて展開する動きが加速している。これは、店舗で人気の看板メニュー(例:もつ煮、餃子、特製ドレッシング)を冷凍食品やレトルト商品として商品化し、自社のECサイトで直接消費者に販売(D2C)したり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店で販売したりするビジネスモデルである 85。この「小売化」は、店舗の商圏という物理的な制約を超えて全国の顧客にアプローチできるため、大きな成長ポテンシャルを秘めている。店舗は、商品を販売する場であると同時に、ブランドの世界観を伝え、ファンを育成する「ショールーム」としての役割を担うことになる。 - サステナビビリティ:
SDGs(持続可能な開発目標)への社会的な関心の高まりは、飲食店の経営にも影響を与えている。食品ロス削減への取り組みは、コスト削減に直結するだけでなく、企業の環境配慮姿勢を示す上で重要である 35。また、地元の食材を積極的に使用する「地産地消」や、MSC/ASC認証のような環境認証を取得したサステナブルな食材の調達は、食の安全・安心を重視し、社会貢献に関心を持つ顧客層からの支持を集め、ブランド価値の向上に繋がる 38。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
居酒屋業界の主要な上場企業は、それぞれ異なる戦略で厳しい市場環境に対応している。ここでは代表的な企業の動向を比較分析する。
- 鳥貴族ホールディングス (証券コード: 3193):
- 事業戦略: 「焼鳥屋 鳥貴族」の単一業態に経営資源を集中し、国産食材の使用と全品均一価格という分かりやすいコンセプトで強力なブランドを構築。ターゲット顧客層は、品質とコストパフォーマンスを重視する若者からファミリー層まで幅広い。
- 強み: 高いブランド認知度と、均一価格による明朗会計の安心感。食材調達から加工、物流までを自社グループで担う製販一貫体制によるコスト競争力。
- コスト高騰への対応: 徹底したコスト管理と生産性向上に加え、2022年に価格改定を実施。エネルギーコストの一服感もあり、2024年7月期第2四半期では大幅な増益を達成している 89。
- 成長戦略: 国内での着実な出店に加え、米国・台湾への海外進出を本格化させ、新たな成長軸を模索している 89。
- ワタミ (証券コード: 7522):
- 事業戦略: 「和民」「ミライザカ」などの外食事業に加え、「ワタミの宅食」で展開する中食事業、農業、環境事業など、多角的な事業ポートフォリオを持つ。
- 強み: 多角化によるリスク分散。特に「宅食事業」は高齢化社会の進展を背景に安定した収益基盤となっている。農業から加工、提供までを手掛ける6次産業モデルも特徴。
- DXへの投資: 最新の決算資料では具体的なDX投資戦略の記載は限定的だが、過去には中期経営計画を策定している 91。
- 成長戦略: 外食事業の収益性改善を進めつつ、宅食事業や海外事業の拡大に注力。近年ではM&Aにも積極的で、米国の寿司加工・卸売事業を買収するなど、サプライチェーン強化と海外展開を加速させている 92。
- コロワイド (証券コード: 7616):
- 事業戦略: M&Aを積極的に活用し、多様な業態を買収・再生することで事業規模を拡大する「プラットフォーマー」戦略。傘下には「甘太郎」「牛角」「かっぱ寿司」「大戸屋」など、居酒屋から焼肉、寿司、定食まで幅広いブランドを持つ。
- 強み: 多様な業態ポートフォリオによるリスク分散と、グループ全体の規模を活かした食材の共同調達(MD機能)によるコスト競争力。
- コスト高騰への対応: グループ全体の調達力を活かした仕入れ交渉や、各ブランドでの価格改定で対応。
- 成長戦略: M&Aを成長の核と位置づけ、近年ではオセアニアのステーキレストランチェーンを買収するなど、海外展開を加速。これにより、海外での事業基盤獲得と、グループ全体の牛肉調達力強化というシナジーを狙っている 92。
- モンテローザ (非上場):
- 事業戦略: 「白木屋」「魚民」「笑笑」など、多様なブランドを直営で全国展開。マスマーケットをターゲットとした総合居酒屋チェーンの代表格。
- 強み: 全国をカバーする店舗網と、多業態展開による幅広い顧客層へのリーチ。
- 近年の動向: コロナ禍で不採算店舗の整理を進める一方、近年は既存店舗の設備更新を伴うリニューアルに注力。特に基幹ブランド「白木屋」のリニューアルでは、従来の「お酒を飲む場」から「時間を楽しむ空間」へとコンセプトを転換し、女性グループやファミリー層の取り込みを図っている 94。
- DDホールディングス (証券コード: 3073):
- 事業戦略: 「わらやき屋」「アリスのファンタジーレストラン」など、独自のコンセプトを持つ個性的な専門業態を多数展開。飲食事業のほか、ダーツ・ビリヤードなどのアミューズメント事業も手掛ける。
- 強み: 高い業態開発力と、特定のエリアに集中出店するドミナント戦略による効率性。
- DXへの投資: Google Cloudとの協業によるDX化ビジョンを掲げ、「業務システム最適配置」「LTV最大化」「グループ経営力の強化」などを推進している 95。
- 成長戦略: 新中期経営計画では「ブランドカンパニー」への進化を掲げ、顧客生涯価値(LTV)の最大化を目指す。外食領域以外での事業セグメント創出やストックビジネスの拡充も視野に入れている 96。
- SFPホールディングス (証券コード: 3198):
- 事業戦略: 24時間営業の海鮮居酒屋「磯丸水産」と、鶏料理専門の「鳥良商店」を二大主力業態とする。
- 強み: 「磯丸水産」の持つ、新鮮な魚介とライブ感のある浜焼きという強力なコンセプトと、24時間営業による幅広い需要の取り込み。
- 成長戦略: 主力業態のブラッシュアップと着実な出店に加え、昭和レトロ感のある大衆酒場「五の五」など、新たな業態開発にも力を入れている 97。
- ヨシックスホールディングス (証券コード: 3221):
- 事業戦略: 本格的な職人が握る寿司を手頃な価格で提供する「や台ずし」を主力業態とし、郊外や地方都市を中心にドミナント展開。
- 強み: 「寿司居酒屋」という明確なコンセプトと、徹底したコスト管理による高いコストパフォーマンス。専門職人(寿司職人)の育成システム。
- 財務状況: 自己資本比率が78.4%(2026年3月期1Q時点)と非常に高く、健全な財務基盤を持つ 98。
- 成長戦略: 主力業態「や台ずし」の継続的な出店による成長を目指す。直近の四半期では増収減益となったが、通期では増収増益を見込んでいる 98。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、居酒屋業界が取るべき戦略的な方向性を提言する。
勝者と敗者を分ける決定的要因
今後3年から5年の間に、居酒屋業界の勝者と敗者を分ける要因は、以下の4点に集約される。
- 明確な価値提案の有無: 「安ければ良い」という時代は終焉した。市場が「高品質・専門性」を求める層と、「体験・コミュニティ」を求める層に二極化する中、自社がどちらの価値を提供するのかを明確に定義し、それを体現する強力なブランドを確立できた企業が勝者となる。特徴のない従来型の総合居酒屋は、価値が陳腐化し、価格競争に埋没して敗者となる。
- DXによる生産性革命の断行: 深刻な人手不足とコスト高騰は、もはや根性論や従来のQSC(品質・サービス・清潔さ)改善だけでは乗り越えられない。モバイルオーダー、配膳ロボット、需要予測AIなどのテクノロジーを駆使してFLコストを構造的に抑制し、高い利益率を維持できる企業が生き残る。経験と勘に頼ったアナログ経営を続ける企業は、高コスト構造に耐えきれず淘汰される。
- データ活用能力: 顧客データを単なる売上記録ではなく、経営の意思決定を左右する「資産」として捉え、収集・分析し、LTV最大化に向けた施策を迅速に実行できるかどうかが問われる。データドリブンなマーケティングや店舗運営を実現した企業が顧客の心を掴み、そうでない企業は取り残される。
- 事業ドメインの多角化: 外食という単一事業への依存は、パンデミックのような外的ショックに対して極めて脆弱である。店舗をブランドの発信基地と位置づけ、中食(デリバリー)や小売(D2C、商品開発)など、複数の収益源を持つ事業ポートフォリオを構築できた企業が、持続的な成長を遂げる勝者となる。
機会(Opportunity)と脅威(Threat)
- 捉えるべき機会 (Opportunity):
- インバウンド需要の本格回復: 増加する訪日客は、日本の食文化体験に高い意欲を持っており、大きな売上増が見込める。
- 新市場の拡大: 健康志向やノンアルコール需要の高まりは、新たなメニューや業態開発のチャンスである。
- DXによる生産性革命: テクノロジー投資により、コスト構造を抜本的に改善し、収益性を高める好機である。
- D2Cモデルによる新収益源: 店舗ブランドを活用し、商圏の制約を超えた全国規模でのビジネス展開が可能になる。
- 備えるべき脅威 (Threat):
- 構造的なコスト上昇: 人手不足による人件費高騰と、原材料費・エネルギー価格の上昇は今後も継続する。
- 代替市場との競争激化: 利便性と経済性で勝る「宅飲み」「中食」市場は、今後も外食の需要を侵食し続ける。
- 飲み会文化の衰退: 企業宴会などの団体需要は、コロナ禍以前の水準には戻らない。
戦略的オプションの評価
上記の分析に基づき、考えられる戦略的オプションを評価する。
| 戦略オプション | メリット | デメリット | 成功確率 |
|---|---|---|---|
| A. 事業拡大(新業態開発・多店舗展開) | 成長セグメント(専門業態、ネオ大衆酒場)への進出による売上拡大。 | 高い初期投資、人材確保の困難さ、コンセプト模倣のリスク。 | 中 |
| B. 事業転換(中食・小売への進出) | 新たな収益源の確保、商圏の制約を超えた顧客接点の創出、店舗資産の有効活用。 | 異なるノウハウ(食品製造、EC、マーケティング)が必要、既存の小売大手との競争。 | 中 |
| C. DX推進による既存事業の徹底効率化 | FLコストの削減による収益性改善、生産性向上、データドリブン経営への転換。 | 初期投資が必要、システム導入だけでなく業務プロセスと組織文化の変革が必須。 | 高 |
| D. M&A・アライアンス | 新業態や技術、人材の迅速な獲得。スケールメリットによるコスト削減 92。異業種連携による新価値創造 101。 | 高額な買収費用、PMI(買収後統合)の失敗リスク、企業文化の衝突。 | ケースバイケース |
最終提言:ハイブリッド戦略「リブランディング × DX × 事業ドメイン拡大」
単一の戦略では、複雑化した市場環境に対応できない。そこで、既存事業を「体験価値」と「DX」で磨き上げ、そこで確立したブランド力と収益力を基盤に、「中食・小売」へと事業ドメインを拡大するハイブリッド戦略を提言する。これは、防御(効率化)と攻撃(成長)を両立させ、持続的な成長を実現するための現実的なロードマップである。
実行に向けた具体的なアクションプラン
Phase 1: 基盤改革 (Year 1-2)
- アクション:
- ポートフォリオ改革: 不採算な総合居酒屋業態の整理・縮小を実行。
- リブランディング: 成長領域である「専門特化業態」または「ネオ大衆酒場」へのリブランディングと集中投資を行う。
- DX基盤導入: 全社的にモバイルオーダー、CRMシステム、需要予測AIを導入し、オペレーションの標準化とデータ収集基盤を構築する。
- 主要KPI: FLコスト比率(目標: 58%以下)、人時売上高(目標: 5,000円)、リブランディング店舗の坪当たり売上高。
- 必要リソース: DX投資予算、ブランドマネージャー、データサイエンティスト。
Phase 2: 収益拡大 (Year 2-3)
- アクション:
- 成功モデルの水平展開: Phase 1で成功したリブランディング店舗のモデルを多店舗展開する。
- データ活用本格化: 蓄積したCRMデータを活用し、パーソナライズド・マーケティング(顧客별クーポン、おすすめメニュー提案)を本格化する。
- インバウンド強化: 多言語メニュー、キャッシュレス決済の完全対応、海外向けSNSでの情報発信を強化する。
- 主要KPI: 既存店売上高成長率、リピート率、インバウンド顧客比率。
- 必要リソース: マーケティング予算、店舗開発チーム。
Phase 3: ドメイン拡大 (Year 3-5)
- アクション:
- D2C事業開始: 店舗で確立した看板メニューを商品化し、自社ECサイトでのD2C販売を開始する。
- 小売事業への進出: スーパーやコンビニエンスストア向けのプライベートブランド(PB)商品開発を推進する。
- M&Aの活用: 必要に応じて、食品製造会社やEC運営に強みを持つ企業をM&Aのターゲットとし、事業拡大を加速させる。
- 主要KPI: 非外食事業の売上比率(目標: 15%以上)、ECサイト売上高、新規顧客獲得数。
- 必要リソース: 商品開発チーム、EC運営チーム、M&A専門チーム。
この段階的かつ連動したアプローチこそが、居酒屋業界が直面する構造的課題を乗り越え、ポスト・パンデミック時代における真の勝者となるための道筋である。
第12章:付録
参考文献・引用データリスト
- 政府統計・業界団体
- 経済産業省「外食産業の動向」 4
- 日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」 3
- 農林水産省「食品ロス削減関連資料」 35
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」 57
- 消費者庁「食品ロス関連資料」 37
- 調査会社レポート
- 富士経済 1
- NPD Japan (現Circana) 2
- xenoBrain 6
- 企業IR資料
- 鳥貴族ホールディングス 89
- ワタミ 91
- コロワイド 93
- DDホールディングス 95
- SFPホールディングス 97
- ヨシックスホールディングス 98
- その他引用ウェブサイト・記事
- 7 – 51 – 122 – 52 – 125
- 3 – 127
引用文献
- 外食主要カテゴリーの2030年市場を予測 | プレスリリース | 富士 …, https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=23139
- <外食・中食 調査レポート>2022年計の居酒屋の市場規模は9253億 …, https://www.npdjapan.com/press-releases/pr_20230322/
- 日本フードサービス協会、令和4年の外食産業市場規模推計値を公表 – サッポロビール, https://www.sapporobeer.jp/hanjo/gyokai/topics/post5428.html
- コロナ禍に苦しんだ外食産業、今後の期待は賃上げとインバウンドか, https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20250313hitokoto.html
- 【2025年】外食産業の今|消費動向から支援制度まで徹底解説, https://www.cherpa.co.jp/column/estaurant-industry/
- AIが予測する居酒屋・パブ業界 業界|2030年市場規模推移と主要 …, https://service.xenobrain.jp/forecastresults/market-size/izakaya-pub
- ネオ大衆ホルモン酒場が熱い!!「肉力屋」ライセンス展開拡大中 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000019548.html
- なぜ月商1400万円売れるのか!? ネオ大衆酒場『つむぎ堂』のメニューを大解剖, https://www.inshokuten.com/foodist/article/6917/lead/
- 飲食店の商圏範囲は半径500m!郊外店と都心店の違いも解説します – エリマケ!, https://www.mapmarketing.co.jp/mm-blog/area-marketing/innshokuten-shoken/
- 飲食店はどこに出すべき?商圏調査の基本と都心・郊外の違いも解説, https://biz.moneyforward.com/restaurant/basic/3403/
- 居酒屋 | 業種別開業ガイド | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト], https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/restaurant/food09.html
- インバウンドで飲食店業界の売上は上がったのか?差別化を図って繁盛させよう!, https://www.tenpos.com/foodmedia/knowledge/35140/
- インバウンドに人気のお店のマル秘テクニックとは|東芝テックCVC, https://note.com/ttec_cvc/n/n8bdbdf53b80c
- 飲みニケーションはついに過去の文化に?!2025年の最新飲酒トレンドと厚労省“新ガイドライン”から見る飲食店の生き残り戦略 – gf-support.com, https://gf-support.com/media/news/20241212u
- “飲みニケーション”は時代遅れ? 年代問わず6割超が「いらない」と …, https://www.hrpro.co.jp/trend_news.php?news_no=3377
- さらに進んだ若者のアルコール離れ-20代の4分の1は、あえて飲まない「ソーバーキュリアス」, https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63562?site=nli
- ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査 サントリー …, https://www.suntory.co.jp/news/article/14881.html
- ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査 サントリー ノンアルコール飲料レポート2025 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001370.000042435.html
- 居酒屋・バーのインバウンド対策|訪日外国人に選ばれる集客戦略と実践方法 – マケスク, https://media.meo-taisaku.com/inbound/izakaya_bar_inbound_measures/
- 受動喫煙防止法規制で飲食店の禁煙化による経営への影響 – 国立保健医療科学院, https://www.niph.go.jp/journal/data/69-2/202069020005.pdf
- 居酒屋を喫煙可にするには?必要な条件や活用できる助成金などを解説, https://www.qleanair.jp/guide/law/3384/
- 飲食店の分煙対策「経営的なメリットとデメリット」 – サニクリーン, https://www.sanikleen.co.jp/biz/seisou/detail/3163.html
- 飲食業における物流の課題とは?2024年問題の影響と対策を解説 | マネーフォワード クラウド, https://biz.moneyforward.com/restaurant/basic/2511/
- 物流がピンチ!物流の2024年問題が飲食業界へもたらす影響と対策 – canaeru, https://canaeru.usen.com/diy/purchase/p1185/
- 2025年度の最低賃金改定について独自調査。飲食店での人件費高騰への具体的な対策は?, https://www.inshokuten.com/foodist/article/8061/
- 15%が、経営継続が危ういと回答~飲食店の2025最低賃金調査~ | 株式会社シンクロ・フード, https://www.synchro-food.co.jp/news/press/6733
- 最低賃金1,500円時代、飲食店経営はどう変わる?成功へのヒントと戦略, https://fs-ring.jp/news_trend/1127/
- 「若者の酒離れ」はコロナ禍で進んだのか メーカーは「アルコール飲む人も飲めない人も」取り込みたい – J-CAST ニュース, https://www.j-cast.com/2023/11/15473066.html?p=all
- 今トレンドのネオ居酒屋!キーワードは「ニュートロ」 | テンポスフードメディア, https://www.tenpos.com/foodmedia/newstrend/3078/
- ネオ居酒屋とは その特徴や人気の理由を解説, https://sharedine.me/media/know-how/neo-izakaya
- 店舗DX導入エピソード 事例.009 – 株式会社USEN, https://usen.com/dx/interview/p09/
- 飲食DX成功事例6選!小規模飲食店がDXに取り組むメリットとは – 飲食店デジタル経営大学, https://food-dx.com/article/dx
- 飲食店のDX成功事例12選!取り組むメリットや集客力アップにつながるツール – コボット, https://kobot.jp/kobot_lab/attracting-customers/dx-cases-in-restaurants/
- 居酒屋開業に必要な資金の目安は?資金調達の方法や成功するためのポイントも解説!, https://canaeru.usen.com/diy/opening/p1065/
- 飲食店等の 食品ロス削減のための 好事例集 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/170516-38.pdf
- 2024年9月27日(金)「居酒屋で目指すべきSDGsって?」|おおたま – note, https://note.com/masayoshi_ota/n/n423a3c371b3b
- 食品ロス削減の取組事例集 – 消費者庁, https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/case/assets/case_200319_0002.pdf
- サステナビリティは“おかず”のひとつ 老舗本格和食店「きじま」の揺るがぬ理念と挑戦 – ELEMINIST, https://eleminist.com/article/842
- 選ぶことが環境保全。今「サステナブル・シーフード」が食べられるお店はココ, https://magazine.tabelog.com/articles/152321
- 飲食チェーン店が挑戦する、持続可能なレストラン/~食の明日のために~vol.14, https://magazine.hitosara.com/article/1848/
- こんな人は飲食店開業、やめたほうがいい。飲食店開業のリスク – テンポスドットコム, https://www.tenpos.com/foodmedia/management/11242/
- 飲食店経営が難しい理由は?経営を成功させるためのノウハウも解説, https://foodservice.nisshin-oillio.com/library/2023-011/
- 【Z世代のホンネ調査】飲み会はもう古い? 次に来る大学生の夜遊びは「パブゲーム」昭和・平成世代が知らない夜遊びの最新事情とは – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000033607.html
- 飲食店がグルメサイトを利用するメリット・デメリット – ロカオプメディア, https://locaop.jp/media/web-attracting-customers/gourmet_site/
- グルメサイト離れの実態調査と2021年からの飲食店集客のカタチ – レストランスター, https://res-star.com/archives/column/gourmet-site
- ファイブフォース分析とは?やり方から業界別事例まで解説 | InsideSales Magazine, https://sora1.jp/blog/fiveforces-analysis/
- マクドナルドの成功を読み解く:5フォース分析による徹底解説 | マーケティング戦略部, https://yushutsulabo.com/mcdonalds-5-forces-analysis/
- 違和感が魅力? 大手も参入する「ネオ大衆酒場」の人気の理由 – 政経電論, https://seikeidenron.jp/articles/23267
- 第2章-3 業務用開拓で 販路を拡大する, https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kasseika/keieiKaizenManual_2.pdf
- 酒類業界とは?業界の定義や構造、主要プレイヤーの動向を徹底解説 – 法人営業ハック|新人から中堅社員まで必見 – BIZMAPS, https://biz-maps.com/media/?p=11364
- 2024年問題とは?飲食業界への影響と対策を紹介 | インバウンドプラス | INBOUND PLUS, http://inboundplus.jp/wp/feature/99090/
- Z世代にとって飲み会は、多様な楽しみ方で参加する食事会! – 日本インフォメーション, https://www.n-info.co.jp/report/0051
- 【Z世代のホンネ調査】大学生がよく飲むお酒No1はレモンサワー!レモンサワーが若者に選ばれる意外な心理とは? – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000033607.html
- Z世代の飲み会と気配り意識――コロナ禍で芽生えた飲み会の“マス目”意識 – AdverTimes, https://www.advertimes.com/20250415/article494507/
- 職人技継承の問題点と解決策。代役はロボット? | リンクウィズ株式会社, https://linkwiz.co.jp/topics/column/craftsmanship_20200907/
- 技術継承とは?問題点や具体的な解決策や事例を紹介 |現場と人 – カミナシ, https://kaminashi.jp/media/technology-inheritance
- 【2024年11月】職種別の有効求人倍率と採用市場の動向を解説 – エン転職, https://saiyo.employment.en-japan.com/blog/jobs-to-applicants-ratio-by-job-type
- 一般職業紹介状況(令和7年8月分)について – 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64026.html
- 有効求人倍率とは?意味・計算方法・職種別の最新データや推移を解説 – マイナビ転職, https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/77/
- ベテランの技術を受け継ぐ「技術継承」。その中で起こる課題と解決策とは? | Platio(プラティオ), https://plat.io/ja/posts/task-skillfolklore
- 技術継承・技能継承はなぜ進まない?原因と起こりやすい業界、方法をご紹介 | コラム – スキルナビ, https://www.101s.co.jp/column/technology-inheritance/
- 製造業における技術継承の課題とは|若手の育成への取り組み | Koto Online, https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/archives/619
- 技術伝承の課題は大きく4つ。若手育成に役立つ継承のコツとマニュアル | 株式会社フォトロン, https://www.photron.co.jp/column/skillfolklore_task/
- 飲食店経営者が意識すべき人時売上高の目安・労働分配率とは?人件費率を30%に抑えるだけじゃダメ!? – 店舗物件探し, https://www.inshokuten.com/foodist/article/4468/
- 飲食店経営の基本!人時売上高の重要性と上げる方法を解説 – HIRAKEL, https://www.stand-3.com/column/business-column/11284/
- 飲食店スタッフの生産性に関する基礎知識。正しく数値を把握して業務効率化を!, https://www.inshokuten.com/foodist/article/5434/
- 人時売上高の目安とは?飲食店における人員数の決め方と計算方法 – canaeru(カナエル), https://canaeru.usen.com/opening/zyunbi441.html
- 外食・中食産業を含むサービス産業生産性に関する欧米との比較について, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/bestpractice-13.pdf
- 飲食店×AI活用事例10選!前年比120%に売上向上した理由は? | AI Front Trend, https://ai-front-trend.jp/ai-restaurants/
- 外食産業×AI:成功事例から学ぶ需要予測と食品ロス削減の秘密 – SUN’s blog – 株式会社サン, https://www.kk-sun.co.jp/blog/2025/02/25/%E5%A4%96%E9%A3%9F%E7%94%A3%E6%A5%ADxai%EF%BC%9A%E6%88%90%E5%8A%9F%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%81%A8%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD/
- マーケティング分野におけるAI活用事例15選【2023年最新版】 – 株式会社マクロセンド, https://macro-send.com/blog/ai-marketing
- 飲食店におけるAIの活用事例15選!売上UPやロス・人件費削減など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/restaurant-ai-cases/
- 飲食業に最適なCRMソフトウェア – Salesforce, https://www.salesforce.com/jp/retail/restaurant-software/
- EMOROCO(エモロコ)|感情を理解するパーソナライズドCRM, https://crm.emoroco.com/
- 飲食店の集客方法やお店に呼ぶアイデアを紹介!オンライン集客もあわせて解説 – JFEX, https://www.jfex.jp/hub/ja-jp/blog/article05.html
- 飲食業界における2025年のAIトレンド | クチトル, https://kuchitoru.com/blog/ai-trends-2025
- 飲食業界でのAI活用事例!人手不足解消・売上を予測する方法とは? – MatrixFlow, https://www.matrixflow.net/case-study/64/
- 今後の飲食店業界が変化する!?調理ロボット導入で飲食店はどのように変わるのか?, https://www.tenpos.com/foodmedia/knowledge/34630/
- 飲食店はAIでどう変わる?メリットや活用できるシステム、事例を紹介, https://www.bemotion.co.jp/ondemand/column-list/restaurant-ai/
- 配膳ロボットの価格相場は?時給・人件費と比較した費用対効果や主な機能を紹介, https://www.foodtechjapan.jp/hub/ja-jp/blog/article_073.html
- 飲食店における配膳ロボットとは?導入メリット・デメリットまで解説 | マネーフォワード クラウド, https://biz.moneyforward.com/restaurant/basic/1789/
- ネオ大衆酒場とは?大衆酒場との違いや人気のメニューを解説 | マネーフォワード クラウド, https://biz.moneyforward.com/restaurant/basic/956/
- 「いま居酒屋業態を席巻する「ネオ大衆酒場」ってどんな店? その特徴と人気の理由」, https://www.tenpodesign.com/magazine/article/43
- 「ネオ大衆酒場」とは? 従来の大衆酒場との違いやその魅力について解説します!, https://style.iichiko.co.jp/trend/20230818/0249/
- 食品D2Cで注目されているブランドの事例15選!食品D2Cの特徴やメリットも紹介, https://shop-pro.jp/yomyom-colorme/83285
- 【2022年最新】食品系D2Cブランドの成功事例13選を紹介 – AnyMind Group, https://anymindgroup.com/ja/blog/e-commerce/food
- D2Cとは?成功事例から学ぶお酒×D2C成功のポイント – お酒トレンド研究所, https://om.seam-inc.com/d2c/
- 食品D2Cの成功事例20選!競争で勝ち残るための7つのポイントを解説, https://corekara.co.jp/contents/sales-up/food_d2c/
- 2024年7月期 第2四半期決算説明会, https://daiwair.webcdn.stream.ne.jp/www11/daiwair/qlviewer/pdf/2403123193nc8nia4r7q.pdf
- 2025年7月期 決算説明会, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250917/20250917558798.pdf
- 決算説明会資料 | IRライブラリー | 株主・投資家情報 | ワタミ株式会社, https://www.watami.co.jp/ir/library/present.html
- 飲食業界のM&A動向!注意点と事例・案件例を解説【2025年最新】, https://mastory.jp/%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AEma
- (株)コロワイド【7616】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/7616.T/financials
- モンテローザが全国で「白木屋」リニューアルを加速 再構築 …, https://syougyoushisetsu.com/news/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%81%8C%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%A7%E3%80%8C%E7%99%BD%E6%9C%A8%E5%B1%8B%E3%80%8D%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%92/
- DDグループ、上期は増収増益、通期予想を上方修正 飲食セグメント成長や販管費削減が貢献、2024年を上回る計画 – logmi Business, https://finance.logmi.jp/articles/380395
- DD グループ – 株式会社フィスコ, https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/dd-holdings20230623.pdf
- IR情報 | SFPホールディングス, https://www.sfpdining.jp/ir/
- (株)ヨシックスホールディングス【3221】:決算情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3221.T/financials
- ヨシックスホールディングス(3221) 東証プライム 決算 | マーケット情報 – 株式市況 – 松井証券, https://finance.matsui.co.jp/stock/3221/settlement/index
- 飲食店業界のM&Aと事業承継の動向・2025年最新, https://www.nihon-ma.co.jp/sector/restaurant.php
- 食品業界の異業種コラボが熱い!提携するメリットや企業の事例を紹介 – ショクビズ!, https://shokubiz.com/5495/
- 2024年のフード・ビジネス「飲食店、飲食サービス業」の上昇により、3年連続の上昇, https://journal.meti.go.jp/p/40808/
- 第1章 食品製造業をめぐる市場経済動向 – 農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_doutai/attach/pdf/doutai_top-145.pdf
- 日本フードサービス協会/8月の外食売上8.4%増、お盆帰省需要が好調 | 流通ニュース, https://www.ryutsuu.biz/sales/r092514.html
- 厚生労働省提出資料, https://www5.cao.go.jp/keizai1/koyoukaigou/20200702/20200702siryo2.pdf
- 2023年7月期 決算説明会, https://daiwair.webcdn.stream.ne.jp/www11/daiwair/qlviewer/pdf/2309203193vkyk8x1.pdf
- https://www.watami.co.jp/assets/pdf/ir/202503.pdf
- https://www.yossix.co.jp/ir/library
- コロワイド(7616) : 決算・業績進捗情報|株予報Pro, https://kabuyoho.jp/sp/report?bcode=7616
- コロワイド (7616) : 決算情報・業績 [COLOWIDE] – みんかぶ, https://minkabu.jp/stock/7616/settlement
- DDホールディングス—連結中期経営計画策定、2026年2月期に連結売上高400億円を目標 | 企業情報FISCO, https://web.fisco.jp/platform/selected-news/00108000/0009350020230421037
- SFPホールディングス(株)【3198】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3198.T
- SFPホールディングス (3198) : 株価/予想・目標株価 [SFP Holdings Co.,] – みんかぶ, https://minkabu.jp/stock/3198
- https://www.sfpdining.jp/ir/library/presentation/
- IRライブラリー | IR情報 | SFPホールディングス, https://www.sfpdining.jp/ir/library/
- (株)ヨシックスホールディングス【3221】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス, https://finance.yahoo.co.jp/quote/3221.T
- [書き起こし]ヨシックスホールディングス(3221) IRセミナー・質疑応答 2024.5.25開催 – note, https://note.com/kabuberry_/n/n5e97be83f2e0
- ヨシックスホールディングス 開示資料 – Strainer, https://strainer.jp/companies/00686/filings?page=2
- IRストレージ 「株式会社ヨシックスホールディングス」のプレスリリース「2026年3月期 第1四半期決算説明資料」開示日時:2025/08/08 15:30:00 | CCReB GATEWAY(ククレブ・ゲートウェイ), https://ccreb-gateway.jp/ir-storage-detail?id=1118163
- ヨシックスホールディングス【3221】のIR資料 – キタイシホン, https://kitaishihon.com/company/3221/ir-library
- 日本の労働生産性の動向2023」を公表|外食トピックス – サッポロビール, https://www.sapporobeer.jp/hanjo/gyokai/topics/post4772.html
- グラフでみる加工食品の 生産・販売、外食等の指標, https://www.fmric.or.jp/stat/bukka/bukka2409.pdf
- 社長メッセージ | (株)モンテローザ, https://www.monteroza.co.jp/company/message/
- 【新事実!】モンテローザの業績回復が著しい件 – M&A Online, https://maonline.jp/articles/monteroza_20180831?page=2
- 飲食店のM&A動向は?実施メリット・デメリットや事例9選を紹介 – fundbook, https://fundbook.co.jp/column/industries-ma/restaurant/
- 決算説明会資料 | IR資料室 – 日清製粉グループ, https://www.nisshin.com/ir/reference/presentation/
- https://www.inshokuten.com/foodist/article/8061/