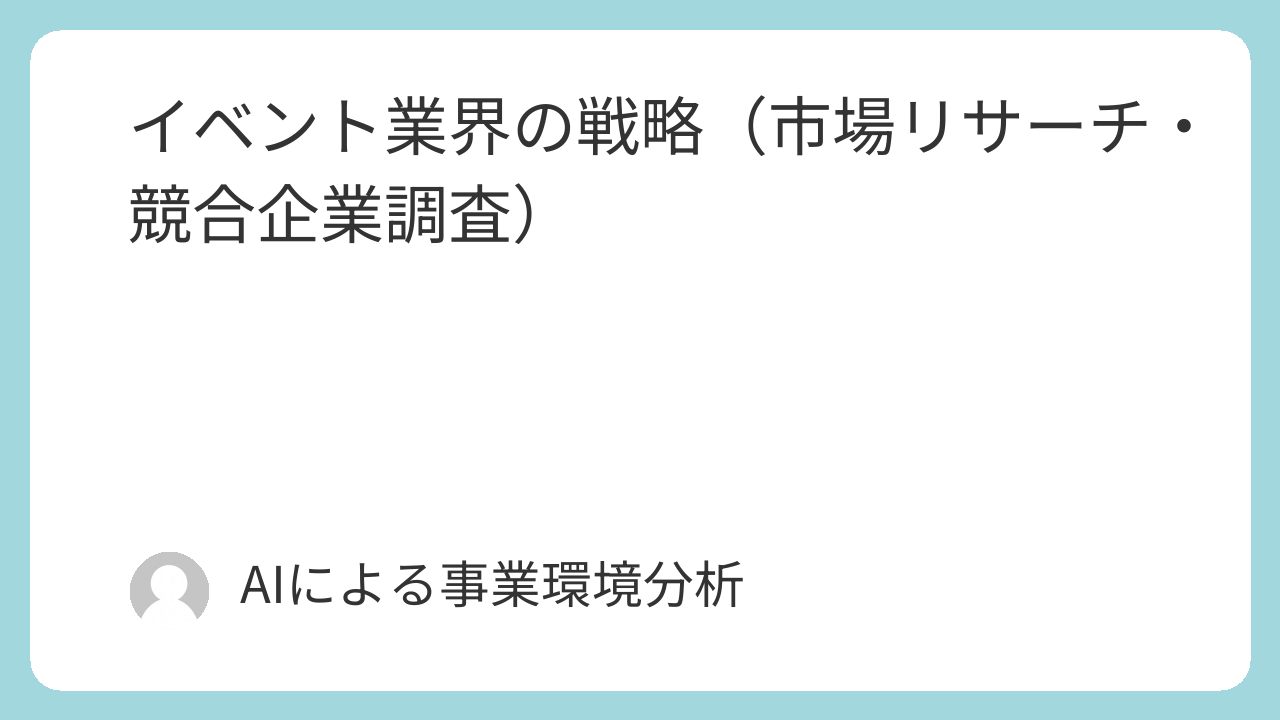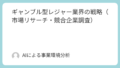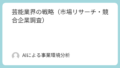体験の未来:データとAIが再定義するイベント業界の次世代戦略
第1章:エグゼクティブサマリー
本レポートの目的と調査範囲
本レポートは、パンデミックによる強制的なデジタルトランスフォーメーション(DX)を経て、構造変化の岐路に立つ日本のイベント業界における持続可能な成長戦略の策定を目的とする。調査対象は、MICE(会議、インセンティブ旅行、コンベンション、展示会)、企業イベント(プロモーション、カンファレンス)、ライブ・エンターテインメント、スポーツイベント、eスポーツイベント、および関連する企画・運営、会場、設営、テクノロジー提供ビジネスを包括する。分析の核心として、①リアルイベントへの揺り戻しとオンライン/ハイブリッドの融合(フィジタル化)、②「集客」から「没入型体験」と「コミュニティ形成」への価値移行、③イベントテックとデータ活用によるROI(投資対効果)の可視化、そして④生成AIによるオペレーション革命という、4つのメガトレンドが業界に与える複合的な影響を深く掘り下げる。
最も重要な結論:ビジネスモデルの岐路と新たな収益機会
イベント業界は、単なる「集客代行業」から「データ駆動型の体験創造業」へと、不可逆的なビジネスモデルの転換を遂げている。パンデミックを経て市場規模は回復軌道にあるが、その内実は大きく変容した 1。今後の勝者と敗者を分ける決定的な要因は、リアルの持つ「熱量」を維持しつつ、デジタル技術を駆使して「パーソナライゼーション」「ROIの可視化」「運営の効率化」を高度に実現できるか否かである。
従来の労働集約的な運営モデルは、人件費・資材費の高騰と深刻な人材不足により限界を迎えつつある 3。この構造的課題を解決し、新たな収益機会を創出する鍵は、AIの全面的活用にある。AIは、企画、マーケティング、運営、分析といったバリューチェーンの全工程を革新し、業界の生産性とコスト構造を根本から変えるポテンシャルを秘めている。価値の源泉は、イベントという「点」の成功から、イベント前後を通じて顧客エンゲージメントを維持する「線」のコミュニティ運営、そしてそこで得られる膨大な行動データを分析・活用し、新たな価値を提供する「面」のデータソリューションへと移行している。
主要な推奨事項
本分析に基づき、持続的成長を達成するために取るべき事業戦略上の主要な推奨事項を以下に4点提言する。
- 事業ポートフォリオの再定義と資源集中
「没入型体験のプロデュース(BtoC/BtoB体験価値の深化)」と「データドリブン・ソリューション(BtoB向けROI最大化支援)」の2領域を事業の核と再定義し、経営資源を集中投下する。従来の画一的なイベント運営から脱却し、専門性と付加価値の高い領域で競争優位を確立する。 - AIファーストへの組織・業務プロセス変革
企画立案から事後分析に至る全バリューチェーンにおいて、AIの活用を前提とした業務プロセスを再設計する。「AIプランナー」「体験デザイナー」「データアナリスト」といった次世代人材の育成・獲得を急務とし、組織全体でAIリテラシーを向上させ、生産性を抜本的に改善する。 - データアセットの収益化モデル構築
イベントを通じて収集される参加者の行動データ(ブース滞在時間、セッション参加率、ネットワーキング動向など)を分析・商品化する。スポンサー向けに高度なROIレポーティングサービスを提供するほか、データを活用したパーソナライズド体験の提供を新たな収益の柱として確立する。 - 戦略的アライアンスによるケイパビリティ獲得
自社に不足するケイパビリティを迅速に獲得するため、AI、データ分析、VR/AR等の専門技術を持つテクノロジー企業とのM&Aまたは資本業務提携を積極的に実行する。特に、イベントテック・プラットフォーマーとの連携は、データ基盤の強化と市場での影響力拡大に不可欠である。
第2章:市場概観(Market Overview)
2.1. 市場規模の推移と予測
日本のイベント業界は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる甚大な影響から力強い回復を遂げ、新たな成長フェーズへと移行している。
日本の市場動向
日本イベント産業振興協会(JACE)の推計によると、2020年に急減したイベント関連産業規模は、その後V字回復を見せている。2023年には2兆6,337億円(前年比126.6%)に達し、コロナ禍前である2019年の水準とほぼ同等まで回復した 2。さらに2024年には、リアルイベントへの回帰が加速したことに加え、大阪・関西万博に関連する売上の一部計上、そしてコロナ禍で普及したオンラインイベントによる参加者層の拡大効果が重なり、2019年比で約1.1倍となる2兆8,535億円(前年比108.3%)へと成長した 1。この成長は、単なるリアルへの揺り戻しではなく、イベント管理システム(SaaS)の普及によってイベント主催のハードルが下がったことなど、質的な構造変化を伴うものである点が重要である。
世界の市場動向
グローバル市場も同様に力強い成長が予測されている。ある調査では、世界のイベント産業市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率(CAGR)13.5%で成長し、この期間に1兆671億米ドルの増分価値を生み出すと予測されている 5。企業イベントの増加やソーシャルネットワーキングの普及が主な牽引役とされている 5。別の予測では、2024年時点で1.4兆ドル規模の市場が、2035年には2.5兆ドルから2.9兆ドルに達する可能性も示唆されている 6。
| 年次 | 日本市場規模(億円) | 世界市場規模(10億米ドル) | 成長ドライバーの要点 |
|---|---|---|---|
| 2020 | (2019年比で大幅減) | – | パンデミックによるリアルイベント中止・延期 |
| 2021 | (回復基調) | – | オンライン・ハイブリッドへの移行 |
| 2022 | 20,803 2 | – | リアルイベントの段階的再開 |
| 2023 | 26,337 2 | 39.4 (展示会) 7 | リアル回帰の本格化、コロナ禍前水準へ回復 |
| 2024 | 28,535 1 | 1,121.9 (MICE) 8 | 万博効果、オンライン層の維持、リアル需要の深化 |
| 2025(予測) | 成長継続 | 1,226.0 (MICE) 8 | CAGR 10.39% (MICE, 25-32年) 8 |
| 2029(予測) | 成長継続 | – | CAGR 13.5% (全体, 24-29年) 5 |
注:世界市場規模は調査機関や対象セグメントにより値が異なるため、参考値を記載。
2.2. セグメント別分析
市場の成長は、セグメントごとに異なるダイナミクスを示している。
- MICE: ビジネス観光の回復と国際的な交流の再活性化を背景に、安定した成長が見込まれる。世界市場は2024年に1兆1,219億ドルと評価され、2032年までに2兆4,491億ドルへ、CAGR 10.39%で成長すると予測されている 8。
- ライブ・エンターテインメント: 体験価値への強い需要を背景に、市場はコロナ禍前を上回る活況を呈している。日本の市場規模は2023年に過去最高の6,857億円を記録 9。2024年も、大規模なアリーナ・スタジアム公演の増加とチケット単価の上昇が牽引し、動員数は過去最多の約6,000万人、市場規模は6,000億円を超える高水準を維持している 10。特に海外アーティストの公演はチケット平均単価が14,402円と高く、市場全体の単価上昇に寄与している 10。
- スポーツイベント: 観戦体験の価値が再評価され、市場は着実に回復している。日本のスタジアム観戦市場は2023年に5,191億円(前年比+35.6%)に達した 11。世界市場もテクノロジー導入による体験向上を追い風に、2031年には5,008億ドル規模への成長が予測されている(CAGR 10.5%) 12。
- eスポーツ: 新たな巨大イベント領域として急成長している。日本の市場規模は2023年に前年比117%の146.8億円に達し、2025年には200億円に迫る勢いである 13。市場の内訳を見ると、「イベント運営」が37.6%を占める主要セグメントとなっており、専門的な運営ノウハウを持つ事業者にとって大きな事業機会が存在する 13。
市場全体の回復・成長の裏側では、その中身が「大規模・高単価なリアル体験」と「スケーラブルなデジタル/ハイブリッド」へと二極化している。ライブ・エンタメ市場におけるアリーナ公演の活況と高単価化は、消費者が非日常的で付加価値の高い「プレミアム体験」には対価を支払うことを示している 10。一方で、NTTドコモのような大手IT企業がVRイベントプラットフォーム(HIKKY)に巨額出資する動きは、デジタル領域での規模とリーチを追求する戦略が加速していることを物語っている 14。この両極の中間に位置する、特徴の乏しい従来型の中小規模イベントは、上下からの圧力により淘汰されるリスクが高まっている。
2.3. 市場成長ドライバーと阻害要因
市場成長ドライバー
- 企業のマーケティング予算の回復: 企業の好調な収益を背景に、2024年の日本の総広告費は過去最高を更新した 15。中でも「イベント・展示・映像他」を含むプロモーションメディア広告費は4,269億円(前年比111.0%)と大幅に増加しており、企業がリアルな顧客接点への投資意欲を回復させていることがわかる 15。
- リアル回帰と体験価値(コト消費)への欲求: パンデミックによる行動制限の反動で、人々はリアルな場での交流や体験に強い価値を見出している。特にZ世代は、モノの所有よりも体験を重視する「コト消費」の傾向が強く、「推し活」や没入型体験への支出を惜しまない層として、市場の重要な牽引役となっている 16。
- テクノロジーの進化と普及: イベントテック(イベント管理SaaS、マッチングアプリ、行動分析ツール)の普及が、運営効率化とデータに基づいた意思決定を可能にしている 18。また、AI、VR/ARといった先端技術が、これまでにない没入感のある体験価値を創出し、新たな需要を喚起している 19。
市場阻害要因
- 人材不足と人件費高騰: イベント業界は、長時間労働や休日勤務の多さ、他業界比で低い給与水準といった労働環境の問題から、慢性的な人材不足に直面している 3。特に設営・撤収を担う若手人材の確保は年々困難になっており、これが成長の足枷となっている 3。
- 資材・会場費の高騰: 世界的なインフレは、イベント制作に必要な資材費、輸送費、そして会場費の高騰を招いている 21。これらのコスト増は利益率を直接的に圧迫し、主催者や企画会社にとって大きな経営課題となっている。
- 安全・セキュリティ要件の高度化: 大規模イベントにおける安全基準の遵守(消防法、雑踏警備)や、テロ・犯罪対策の重要性が増しており、これらに対応するためのコストが増加傾向にある 22。
2.4. 業界のビジネスモデルと主要KPI
イベント業界は、多様なプレイヤーが相互に関係し合う複雑なエコシステムを形成している。
- 主催者(オーガナイザー): イベントの企画主体。自社開催(企業)や、興行として開催(プロモーター)。
- 企画・運営会社: 主催者から委託を受け、企画、制作、運営を担う。広告代理店系(電通、博報堂など)と、専門会社(丹青社、乃村工藝社など)に大別される。
- 会場(ベニュー)提供者: 東京ビッグサイト、幕張メッセなどの大規模施設から、ホテル、ユニークベニューまで様々。施設の稼働率が主要KPI。
- イベントテック(Eventech)ベンダー: EventHub、Sansan(EventRegist)など、イベント管理や参加者エンゲージメント向上を支援するSaaSプラットフォームを提供。
業界の主要KPIは、イベントの目的によって異なるが、一般的に以下のものが重視される。
- BtoBイベント: リード獲得数、商談化率、リード獲得単価(CPL)、そして最終的なROI。
- BtoCイベント: 集客数、チケット売上、顧客満足度、SNSでのエンゲージメント数。
- 全般: イベント当たりの収益、利益率、スポンサー単価・満足度。
近年、特にBtoBイベントにおいては、スポンサー(買い手)が他のデジタルマーケティング施策との比較を厳密に行うため、データに基づいたROIの可視化が最重要KPIとなっている。
第3章:外部環境分析(PESTLE Analysis)
イベント業界は、自社でコントロール不可能なマクロ環境の変化から大きな影響を受ける。PESTLEフレームワークを用いて、主要な外部環境要因を分析する。
政治(Politics)
- MICE推進政策: 日本政府および各自治体は、観光立国推進の一環としてMICE誘致に積極的である 24。1994年の「コンベンション法」制定以降、施設整備が進められ、近年では横浜市や京都市などがDMO(観光地域づくり法人)を核とした戦略的な誘致活動を展開している 25。これらの支援策(補助金、広報協力など)は、国際会議や大規模展示会の開催にとって強力な追い風となる。
- 大規模国際イベントの誘致: 大阪・関西万博や過去のオリンピック、G7サミットといった国家的な大規模イベントは、インフラ整備を促進し、関連するイベント需要を短期的に創出する。しかし、その反動による需要の落ち込みや、リソースの集中による他イベントへの影響も考慮する必要がある。
- 安全保障・入国管理政策: 国際情勢の緊迫化に伴うテロ対策の強化や、新たな感染症の発生による入国管理の厳格化は、国際的なイベントの開催における最大のリスク要因である。これらの政策変更は、海外からの参加者数やイベントの開催可否に直接的な影響を及ぼす。
経済(Economy)
- 景気変動と広告宣伝費: イベント予算、特に企業のプロモーションイベントは、景気動向と密接に連動する企業の広告宣伝費に大きく左右される。2024年は、企業の好調な収益を背景に日本の総広告費が過去最高を更新し、イベント市場にはポジティブな影響を与えている 15。
- コストプッシュ・インフレ: 原材料価格やエネルギー価格の上昇に伴う資材費、輸送費、会場の光熱費の高騰は、イベントの制作コストを直接押し上げている 21。また、労働市場の逼迫による人件費の上昇も重なり、業界全体の利益率を圧迫する大きな要因となっている 4。
- 為替レートの変動: 円安は、海外からの参加者を誘致するインバウンドMICEにとっては参加コストの低下につながり、追い風となる。一方で、海外の著名なアーティストや講演者の招聘費用、海外製機材の輸入コストを増大させ、アウトバウンドのインセンティブ旅行には逆風となる。
社会(Society)
- 価値観の変化と体験重視(コト消費): パンデミックを経て、人々はリアルな場での「集い」や「体験」の価値を再認識している。特にZ世代を中心とした若年層では、モノを所有する「モノ消費」から、体験や経験に価値を見出す「コト消費」へのシフトが顕著である 16。フェスやライブ、没入型アート展など、非日常的な体験を提供するイベントへの需要は極めて高い。
- 「推し活」文化の浸透: アイドルやアニメキャラクターなど、特定の対象を熱狂的に応援する「推し活」は、巨大な消費市場を形成している。関連イベントのチケットやグッズへの支出意欲は非常に高く、イベントの集客と収益を支える強力なドライバーとなっている 17。
- サステナビリティ・SDGsへの意識の高まり: 環境への配慮(カーボンフットプリント削減、廃棄物ゼロ)、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)といったサステナビリティへの取り組みが、イベント開催における必須要件となりつつある 28。これらの取り組みは、企業の社会的責任(CSR)としてだけでなく、参加者やスポンサーからの評価を高め、ブランド価値を向上させる重要な要素となっている 30。
当初、規制対応やコスト増と見なされがちだったサ-ステナビリティへの要求は、その意味合いを大きく変えている。環境(Environment)要因としてのCO2排出や廃棄物問題への対応は、確かにコスト増の圧力である 28。しかし、社会(Society)要因として、SDGsへの意識が高い若年層は、サステナブルな取り組みを行う企業やイベントを積極的に支持する傾向にある 28。さらに、サステナビリティをテーマとしたイベント自体が、関連企業間の連携や新規事業開拓といった「新たなビジネスチャンス」を生み出すことも指摘されている 28。これらの点を統合すると、サステナビリティは単なる環境規制対応という「守り」の側面だけでなく、新たな顧客価値を創造し、企業のブランドイメージを向上させる「攻め」の戦略的投資へと進化している。
技術(Technology)
- イベントテックの進化: イベントの企画・集客・運営・分析を支援するテクノロジー(イベントテック)が急速に進化・普及している。参加者管理システム、オンライン配信プラットフォーム、行動分析ツール、AIを活用したマッチングアプリなどが統合され、データに基づいた効率的なイベント運営を可能にしている 19。
- 没入型・体験型技術(VR/AR/MR): 仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、複合現実(MR)といったXR技術や、プロジェクションマッピング、センサー技術は、参加者に五感を刺激する「没入型体験」を提供する。これにより、イベントの付加価値が飛躍的に向上している 19。
- 通信インフラの高度化: 5G/6Gといった次世代通信技術の普及は、高品質な映像のリアルタイム配信や、遅延のないインタラクティブな体験を可能にし、ハイブリッドイベントの質を向上させる基盤となる。
- 生成AIの台頭: 生成AIは、企画書の自動生成、マーケティング用コピーや画像の作成、パーソナライズされたコミュニケーション、データ分析の自動化など、イベントのバリューチェーン全体に破壊的な変化をもたらすゲームチェンジャーである。
法規制(Legal)
- 安全基準と主催者責任: 大規模な集客を伴うイベントでは、消防法や建築基準法、雑踏警備に関する条例など、厳格な安全基準の遵守が求められる 22。事故発生時の主催者の安全配慮義務は極めて重く、リスク管理体制の構築が不可欠である 22。
- 個人情報保護法: イベントの事前登録や会場での行動追跡によって収集される参加者の個人データは、個人情報保護法に則って厳格に管理・運用する必要がある。データ活用の前提として、適切な同意取得とセキュリティ対策が必須となる。
- 景品表示法: プロモーションイベントにおける景品や特典の提供は、景品表示法の規制対象となる。誇大な表示や有利誤認を招く表現は厳しく禁じられており、コンプライアンス遵守が求められる。
環境(Environment)
- カーボンフットプリントへの対応: イベント開催に伴う参加者・機材の移動、会場での大量の電力消費は、多大なCO2を排出する。これに対し、カーボンフットプリントを算定・公開し、再生可能エネルギーの利用やカーボンオフセットを導入する動きが広がっている。「CO₂ゼロMICE®」のようなソリューションも登場している 28。
- 廃棄物問題への取り組み: イベントの設営・撤去時に発生する大量の廃棄物は、業界の長年の課題である 29。リサイクル可能な資材の採用、デジタル化によるペーパーレス推進、ノベルティグッズの見直しなど、廃棄物削減(リデュース、リユース、リサイクル)への取り組みが強く求められている。
第4章:業界構造と競争環境の分析(Five Forces Analysis)
イベント業界の収益構造と競争の力学を、マイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いて解き明かす。
供給者の交渉力:中〜高
イベントの価値を決定づける重要な要素を供給するプレイヤーは、強い交渉力を持つ。
- 交渉力が高い供給者:
- キラーコンテンツ(アーティスト、IP、著名講演者): 集客の成否を左右する世界的に有名なアーティスト、人気IP(知的財産)、あるいは業界の第一人者である基調講演者は、代替が不可能であり、極めて強い交渉力を持つ。彼らの出演料はイベント予算の大部分を占めることも少なくない。
- 唯一無二の会場(大規模アリーナ、国際会議場、ユニークベニュー): 東京ドームや東京ビッグサイト、あるいは歴史的建造物などのユニークベニューは、その規模やブランド力において代替が困難である。特に需要が集中する時期には、会場側が価格設定や利用条件において優位な立場に立つ。
- 交渉力が中程度の供給者:
- 専門技術・機材会社: 高度な専門性が求められる音響、照明、映像、特殊効果、大規模設営などを担う企業は、イベントの品質を保証する上で不可欠な存在である。しかし、同業の専門会社も複数存在するため、競争原理が働き、交渉力は中程度に留まる。
- システムベンダー: イベントテックを提供するベンダーは、そのプラットフォームへの依存度が高まるにつれて交渉力を増すが、一方で新規参入も多く、スイッチングコストが極端に高くない限り、交渉力は限定的である。
買い手の交渉力:高
イベントの対価を支払う買い手(スポンサー企業や一般参加者)は、総じて強い交渉力を持っている。
- BtoB(スポンサー/出展企業):
- ROIの厳格な要求: 企業のマーケティング担当者は、イベントへの投資を、デジタル広告、コンテンツマーケティング、セールスプロモーションといった他の多様な施策と比較検討する。そのため、出展や協賛の効果(リード獲得数、商談化率、ブランド認知度向上など)をデータに基づいて明確に証明できなければ、予算を獲得することは難しい。ROIの可視化は、買い手の交渉力を背景とした絶対的な要求となっている。
- BtoC(一般参加者):
- 価格感度と時間の奪い合い: チケット価格に対する消費者の目は厳しい。特に、YouTubeやSNSで無料の高品質なコンテンツが溢れる現代において、イベントに参加することは金銭的コストだけでなく、貴重な「可処分時間」を投資する行為である。他のエンターテインメントとの時間の奪い合いは熾烈を極めている。
- 例外: ただし、熱狂的なファンを持つアーティストのライブや、「推し」に関連するイベントなど、強い愛着や所属欲求を喚起するコンテンツに対しては、高額なチケットや関連グッズでも購入する傾向があり、このセグメントにおいては買い手の価格交渉力は弱まる。
新規参入の脅威:中〜高
伝統的なイベント業界の垣根は、テクノロジーと異業種の参入によって低くなりつつある。
- イベントテック・スタートアップ: 参加者マッチング、オンライン配信、データ分析といった特定の課題を解決するSaaSモデルのスタートアップが次々と登場している。彼らは少ない初期投資で特定のバリューチェーンに切り込み、既存事業者の領域を侵食する。
- 大手ITプラットフォーマー: Metaが提供するVRイベント空間「Horizon Worlds」や、Zoomが強化するイベント機能のように、巨大なユーザー基盤と最先端技術を持つグローバルIT企業が本格参入した場合、業界地図を塗り替える破壊的な脅威となり得る。
- 異業種からの参入: JTBやH.I.S.といった大手旅行会社が、旅行手配のノウハウを活かしてMICE事業を強化している 32。また、メディア企業が自社コンテンツを核にイベントを主催するなど、既存の顧客基盤やブランド力を持つ異業種からの参入は今後も続くと考えられる。
代替品の脅威:高
イベントが提供する価値(情報収集、ネットワーキング、体験)は、多様な代替品との競争に晒されている。
- オンラインコミュニケーションツール: Zoom、Microsoft Teams、Google Meetといったツールは、特に情報伝達を主目的とするセミナー、社内会議、小規模な勉強会などの代替品として完全に定着した。移動コストや時間的制約がないオンラインの利便性は、多くのリアルイベントにとって恒久的な脅威である。
- メタバースプラットフォーム: アバターを介して交流するメタバース空間でのイベントは、物理的な制約を超えた新たな体験を提供する可能性を秘めており、特にゲームやエンターテインメント分野での代替品となり得る。
- デジタルマーケティング施策全般: 企業がリード獲得やブランディングを目指す際、イベントは常にWeb広告、SEO、SNSマーケティング、ウェビナーといった他のデジタル施策と比較される。これらは効果測定が容易で、ターゲットを絞りやすいという利点があり、イベントの予算を奪い合う強力な代替品である。
- 常設の体験施設: テーマパーク、ブランドの旗艦店、ショールーム、科学館などは、継続的に没入型の体験を提供しており、単発のプロモーションイベントの代替となり得る。
業界内の競争:激しい
イベント業界は、多種多様なプレイヤーがひしめき合い、競争が非常に激しい。
- プレイヤーの多様性と競争構造:
- 大手広告代理店系(電通、博報堂など): 巨大な顧客基盤、総合的な企画力、メディアとの連携を武器に、大規模な国家イベントや企業の大型プロモーション案件で強みを発揮する。
- 大手専門会社(丹青社、乃村工藝社など): 展示会の空間デザインや設営・施工における高い専門性と実績を誇る。
- 外資系(Live Nation, Informa, RXなど): グローバルなネットワークと標準化された運営ノウハウを活かし、国際的な展示会や大規模コンサート市場で大きなシェアを持つ。
- 中小の専門制作会社: 特定の領域(例:音楽ライブ、学術会議)に特化し、機動力とコスト競争力で差別化を図る。
- 差別化要因の変化: 従来は、安全な運営遂行能力や人脈といった「実行力」が競争力の源泉であった。しかし、コモディティ化が進む中で、単なる運営能力だけでは差別化が困難になり、価格競争に陥りやすい構造となっている 3。
この競争環境において、競争の軸そのものが変化し始めている。個別のイベントを滞りなく成功させる「実行力」の競争から、参加者とスポンサーのデータを一元的に管理し、継続的なエンゲージメントを創出する「プラットフォーム」の支配力を巡る競争へとシフトしている。新規参入の脅威であるイベントテック企業やITプラットフォーマーの強みは、まさにこの技術基盤にある。また、ROIの証明を求めるスポンサー(買い手)の要求に応えるには、プラットフォーム上で参加者の行動データを収集・分析する能力が不可欠となる。これは、データを基盤とするデジタルマーケティング(代替品)に対抗するための必須条件でもある。結果として、データを制し、顧客との継続的な関係性を構築できるプラットフォームを持つプレイヤーが、業界のハブとして収益構造上有利なポジションを築く可能性が高い。
第5章:バリューチェーンとサプライチェーン分析
5.1. バリューチェーン分析:価値の源泉のシフト
イベントビジネスのバリューチェーンは、一連の活動を通じて付加価値を創出するプロセスとして分解できる。その価値の源泉は、大きな転換期を迎えている。
イベントビジネスの典型的なバリューチェーン
- 企画・コンセプト策定: 市場調査、ターゲット設定、イベントの目的・テーマ決定。
- 営業・スポンサー獲得: 企画書作成、スポンサー・出展企業への営業、予算確保。
- コンテンツ制作・調達: 講演者・アーティストの招聘、セッション・展示コンテンツの制作。
- マーケティング・集客: プレスリリース、広告、SNSプロモーション、チケット販売。
- 会場・設営: 会場選定・契約、空間デザイン、ブース・ステージの設営、機材手配。
- 当日運営・演出: 受付、誘導、進行管理、音響・照明・映像演出、安全管理。
- 事後分析・フォローアップ: アンケート実施、データ分析、リードフォロー、報告書作成。
価値の源泉はどこへシフトしているか?
かつて、イベントの価値は「安全でスムーズな運営」や「豪華なステージ演出、著名な登壇者」といった、当日の物理的な体験に大きく依存していた。これらは現在も重要な基盤であるが、競争優位を生み出す価値の源泉は、より無形でデータドリブンな要素へと明確にシフトしている。
- 「集める」から「繋げる」へ: 価値の源泉は、単に多くの人を集めること(集客)から、参加者同士、あるいは参加者と出展者の間に意味のある繋がり(ネットワーキング)を創出することへと移行している。AIを活用したマッチングシステムや、共通の興味関心に基づくコミュニティ形成支援は、この新たな価値創造の中核を担う。
- 「画一的」から「パーソナライズ」へ: 全員に同じコンテンツを提供するのではなく、収集した個々の参加者の興味関心データに基づき、パーソナライズされた体験(推奨セッション、ネットワーキング相手の紹介など)を提供することが付加価値となる。これにより、参加者一人ひとりの満足度とエンゲージメントが最大化される。
- 「感覚的」から「データに基づく証明」へ: イベントの成功を、来場者数や漠然とした満足度といった感覚的な指標で語る時代は終わった。価値の源泉は、収集した行動データを分析し、スポンサーに対して投資対効果(ROI)を客観的な数値で証明することにある。どのブースにターゲット顧客が何分滞在し、いくつの商談が生まれたかを可視化することが、スポンサー予算を獲得するための絶対条件となっている。
このシフトは、バリューチェーンの後半、特に「当日運営」と「事後分析」のプロセスで収集されるデータが、次のイベントの「企画」や「営業」の質を決定づけるという、循環的な価値創造モデルへの転換を意味している。
5.2. サプライチェーン分析:コスト圧力と新たな協業形態
イベントは、多岐にわたる専門業者やフリーランスとの連携によって成り立つ、複雑なサプライチェーンの上に構築されている。
イベントを構成するサプライチェーン
- 会場: 国際展示場、カンファレンスセンター、ホテル、アリーナ、ユニークベニュー
- ハードウェア:
- 設営・装飾: 施工会社、デザイン会社、木工・システム部材業者
- 機材: 音響(PA)、照明、映像(LEDビジョン、プロジェクター)の専門会社
- ソフトウェア・コンテンツ:
- ITシステム: イベント管理プラットフォーム、チケット販売システム、配信システム
- コンテンツ: 映像制作会社、グラフィックデザイナー、コピーライター
- ヒューマンリソース:
- 運営スタッフ: ディレクター、AD、受付、誘導、警備、通訳
- ケータリング: 飲食提供会社
サプライチェーンへの圧力
- 人件費・資材費の高騰: 建設業界や物流業界とも連動し、設営・撤去に関わる人件費や、木材・金属といった資材費が高騰している 34。これはイベント制作の原価を直接的に押し上げ、利益を圧迫する最大の要因の一つである。
- 人材不足と属人化: 業界の労働環境の問題から、特に現場を支える若手スタッフや技術専門職の確保が困難になっている 3。これにより、一部のベテランにノウハウが偏る「属人化」が進行し、サプライチェーンの脆弱性を高めている。
フリーランス・パートナーとの連携(ギグエコノミー)
イベント業界では、プロジェクト単位で専門スキルを持つフリーランス(個人事業主)との連携が不可欠である。イベントディレクター、プロデューサー、テクニカルディレクター、デザイナーなど、多くの専門職がフリーランスとして活動している 35。
- 活用実態: 企業は、正社員だけでは賄えない専門性や、プロジェクトの繁閑に合わせた柔軟な人員配置を実現するために、フリーランスを積極的に活用している。フリーランスのディレクターは、日当制(首都圏で1日4〜5万円程度)で業務を請け負うことが多い 36。
- 重要性と課題: 彼らは業界の重要な人的資本であり、質の高いイベントを実現するためのキーパーソンである。一方で、企業側には、優秀なフリーランスとの継続的な関係構築や、彼らのスキル・稼働状況を効率的に管理する仕組みが求められる。また、フリーランス自身も、安定した案件獲得のためのネットワーク構築やプラットフォーム活用が課題となっている 35。
第6章:顧客需要の特性分析(Customer Demands)
イベントの成功は、ターゲットとなる顧客セグメントのニーズと、その購買決定要因(KBF: Key Buying Factor)を深く理解し、的確に応えることにかかっている。パンデミックを経て、これらのニーズとKBFは大きく変化した。
6.1. BtoB顧客(主催者・出展企業)
- ニーズ(Needs)の変化:
- リードの「量」から「質」へ: かつては名刺の獲得枚数が重視されたが、現在は自社のターゲット顧客に合致した質の高いリード(MQL: Marketing Qualified Lead)の獲得が最優先事項となっている。
- 商談創出とパイプライン貢献: 単なる情報提供の場ではなく、具体的な商談機会を創出し、営業パイプラインに直接貢献することが求められる。
- ROIの徹底的な可視化: イベントへの投資が、他のマーケティング施策と比較してどれだけの成果(売上貢献)をもたらしたのか、データで明確に説明できることが必須となった。
- ブランディングとエンゲージメント: 新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との関係を強化し、ブランドへのロイヤリティを高める場としての役割も重視される。
- KBF(Key Buying Factor)の変化:
- 集客力 → ターゲット適合性: 単純な来場者数よりも、自社のターゲット顧客層がどれだけ来場するかが重要な判断基準となる。
- 会場の豪華さ → 商談マッチングの精度: 豪華なブースデザインよりも、AIなどを活用して確度の高い見込み客と効率的にマッチングできる機能がKBFとなっている。
- コストパフォーマンス: 投下した費用(出展料、設営費など)に対して、どれだけの質の高いリードや商談を獲得できるかという費用対効果が厳しく評価される。
- データ提供の質と量: イベント後に提供される来場者データや行動分析レポートの質(どのブースに誰が訪れたか、など)が、次回の出展を決定する上で極めて重要なKBFとなる。
6.2. BtoB顧客(参加者)
- ニーズ(Needs)の変化:
- 網羅的な情報収集 → 効率的な課題解決: 漠然と情報を集めるのではなく、自社が抱える具体的なビジネス課題を解決するためのヒントやソリューションを、短時間で効率的に見つけたいというニーズが高まっている。
- 名刺交換 → 質の高いネットワーキング: 数多くの名刺を交換することよりも、自社と同様の課題を持つ同業者や、有益な知見を持つ専門家と深く議論できる、質の高いネットワーキング機会を求めている。
- KBF(Key Buying Factor)の変化:
- コンテンツの質(登壇者・テーマ): 著名な登壇者であることに加え、自らの業務に直結する実践的で先進的なテーマのセッションが提供されるかどうかが参加の決め手となる。
- 参加者の質: どのようなレベル・役職の参加者が集まるのか。質の高いネットワーキングを期待できるコミュニティかどうかが重視される。
- 効率的なネットワーキング機能: 事前に他の参加者のプロフィールを閲覧でき、興味のある相手にアポイントを申請できるマッチングアプリなどの機能は、参加価値を大きく左右するKBFである。
- 時間的投資対効果: 貴重な業務時間を割いて参加する価値があるか。オンラインでの情報収集と比較して、リアル参加ならではのメリット(深い議論、偶然の出会い)が得られるかどうかが問われる。
6.3. BtoC顧客(参加者)
- ニーズ(Needs)の変化:
- 鑑賞 → 没入・参加: コンテンツを一方的に受け取る(鑑賞する)だけでなく、自らが物語の一部になるような「没入感」や、演出に参加できる「インタラクティブ性」を求める傾向が強まっている。
- 感動・一体感の共有: 同じ空間で同じ体験を共有することによる感動や一体感は、リアルイベントならではの根源的なニーズであり、パンデミックを経てその価値はむしろ高まっている。
- コミュニティへの所属感: イベントへの参加を通じて、同じ趣味や価値観を持つ人々と繋がり、コミュニティに所属しているという感覚を得たいというニーズ。「推し活」文化はこれを象徴している 17。
- 利便性とシームレスな体験: チケットの購入、入場、会場内での決済、情報取得といった一連の体験が、スマートフォンアプリなどでストレスなくシームレスに行えることへの要求が高まっている。
- KBF(Key Buying Factor)の変化:
- コンテンツ(アーティスト、IP): 参加を決定する最も強力な要因は、出演するアーティストや、テーマとなるIP(アニメ、ゲームなど)そのものである。
- 体験の質(演出、没入感): プロジェクションマッピングや特殊効果、インタラクティブな仕掛けなど、五感を刺激し、非日常的な世界に没入できる演出の質がKBFとなる 37。
- 会場の快適性・安全性: 音響の質、視界の良さ、混雑の緩和、清潔なトイレ、そして何よりも安全対策が徹底されていることが、満足度を左右する基本的なKBFである。
- チケット価格と付加価値: 価格そのものに加え、限定グッズや特別な体験(ミート&グリートなど)といった付加価値とのバランスが購買決定に影響する。
第7章:AIがイベント業界に与える影響とインパクト(特別章)
生成AIをはじめとするAI技術は、労働集約型であったイベント業界のバリューチェーン全体に破壊的変化をもたらし、生産性を飛躍させ、新たな事業機会を創出する最大のゲームチェンジャーである。
7.1. 企画・制作プロセスにおける革命
従来、人間の経験と勘に大きく依存していた企画・制作プロセスは、AIによってデータドリブンかつ高速なプロセスへと変貌する。
- 市場トレンド分析とテーマ提案: AIがSNSの投稿、ニュース記事、過去のイベントデータなどを大規模に分析し、次に流行する可能性のあるテーマや、ターゲット層に響くコンセプトの切り口を複数提案する。これにより、企画の成功確率を高め、ブレインストーミングの時間を大幅に短縮できる 39。
- 企画書・広報文案の自動生成: イベントの目的やターゲット、キーコンセプトといった要件を入力するだけで、生成AI(ChatGPTなど)が構成の整った企画書、魅力的なキャッチコピー、プレスリリース、SNS投稿文のドラフトを数分で作成する 40。企画者はゼロから作成する手間から解放され、より戦略的な内容の精査に集中できる。
- ビジュアルコンテンツの高速プロトタイピング: 画像生成AI(Midjourney, Stable Diffusionなど)を活用し、イベントのキービジュアルやブースデザイン、ステージ演出のイメージを瞬時に複数パターン生成する 41。これにより、クライアントとの合意形成を迅速化し、デザインの試行錯誤にかかるコストと時間を劇的に削減できる。
7.2. マーケティング・集客プロセスの高度化
AIは、マーケティング活動を「マス」から「個」へと進化させ、集客の効率と効果を最大化する。
- 精密なターゲティングとセグメンテーション: AIがCRMデータや過去の参加者データ、Web行動履歴を分析し、イベントテーマに最も関心を持つであろう潜在顧客セグメントを自動で抽出する。これにより、広告配信の無駄をなくし、コンバージョン率を高める。
- パーソナライズド・コミュニケーションの自動化: 抽出されたセグメントや個人の属性・興味関心に合わせて、メールの件名や本文、広告のクリエイティブ(画像・コピー)をAIが自動で最適化し、配信する 42。これにより、開封率やクリック率を大幅に向上させることが可能となる。
- 24時間365日の問い合わせ対応: AIチャットボットがWebサイトやSNSに常駐し、イベントに関する参加者からの頻繁な質問(日時、場所、アクセス方法など)に24時間体制で自動応答する 44。これにより、運営スタッフの問い合わせ対応業務の負担を大幅に軽減する。
7.3. 運営・体験プロセスの革新
イベント当日の運営は、AIによるリアルタイム予測と最適化によって、よりスムーズで安全、かつパーソナライズされたものになる。
- リアルタイム混雑予測と人員配置の最適化: 会場に設置されたカメラやセンサーのデータをAIがリアルタイムで分析し、特定のエリア(受付、人気ブース、トイレなど)の混雑状況を予測。予測に基づき、来場者に迂回を促したり、警備・案内スタッフを最適に再配置したりすることで、ストレスと危険を未然に防ぐ。
- 多言語対応のバリアフリー化: AIを活用したリアルタイム自動翻訳・字幕生成システムにより、海外からの参加者も言語の壁を感じることなくセッションに参加できる。
- AIコンシェルジュによる体験向上: AIアバターが会場案内を行ったり、参加者のプロフィールや行動履歴に基づいて、ネットワーキングに最適な相手や、次に見るべきおすすめのセッションをレコメンドしたりする。
- スムーズで安全な入場管理: AI顔認証システムを導入することで、チケットやQRコードを提示することなく、ウォークスルーでのスムーズな入場(非接触)を実現し、受付の混雑を解消すると同時に、セキュリティを向上させる。
7.4. 事後分析とROI可視化の深化
イベントの効果測定は、AIによってこれまで不可能だったレベルまで精緻化・自動化され、明確なROIとして提示される。
- 定性データの定量分析: AIが、アンケートの自由記述欄やSNS上の投稿(テキスト、画像)を分析し、イベントに対する参加者の感情(ポジティブ、ネガティブ)や具体的な意見を自動で集計・分類する(感情分析)。これにより、従来は見過ごされがちだった定性的なフィードバックを大規模に可視化できる。
- 統合データ分析によるROIの算出: セッションの参加率、各ブースの滞在時間、商談成立数、アンケート結果、SNSでの反響といった、分断されていた様々なデータをAIが統合的に分析。イベント全体の成果を多角的に評価し、スポンサーが最も重視するKGI/KPI達成度やROIを、客観的データに基づいたダッシュボードで提示する 46。
| バリューチェーンの工程 | AI活用による変革 | 具体的なソリューション・技術例 |
|---|---|---|
| 企画・制作 | 経験と勘からデータ駆動型の高速立案へ | 市場トレンド分析AI、ChatGPT(企画書・コピー生成)、Midjourney(ビジュアル生成) |
| マーケティング・集客 | マスアプローチから超パーソナライズドへ | AI搭載MAツール(HubSpot)、AIによる広告クリエイティブ最適化、AIチャットボット |
| 運営・体験 | 事後対応からリアルタイム予測・最適化へ | 混雑予測AI、リアルタイム自動翻訳、AI顔認証システム、AIコンシェルジュ |
| 事後分析・ROI | 手動集計から統合的な自動分析・可視化へ | 感情分析AI、統合データ分析プラットフォーム、AIによるROI算出レポート |
7.5. 業界構造へのインパクト
AIの浸透は、個々の業務効率化に留まらず、業界の構造そのものを変革する。
- 求められる人材像のシフト: イベントプランナーやマーケターの役割は、手配や調整といったオペレーション業務から、AIを使いこなし、データからインサイトを読み解き、より創造的な体験を設計する「戦略家」「体験デザイナー」へと変化する。AIに代替されるスキルと、AIを使いこなすスキルとの間で、人材価値の二極化が進行する。
- 生産性の飛躍的向上とコスト構造の変化: ルーティンワークや単純作業の自動化により、業界全体の労働生産性は劇的に向上する可能性がある。これにより、長時間労働といった業界の構造的課題が解決に向かうと同時に、人件費中心だったコスト構造が、AIツール利用料などのIT投資へとシフトしていく。
- 新たなプレイヤーの台頭: イベント業界特有の課題を解決する、特化型AIソリューションを提供する新たなベンダーが次々と出現し、業界のエコシステムに新たなレイヤーを加える。
第8章:業界の内部環境分析(Internal Environment Analysis)
8.1. VRIO分析:持続的な競争優位の源泉
イベント業界において、持続的な競争優位(Sustainable Competitive Advantage)を築くための経営資源やケイパビリティは何か。VRIOフレームワーク(Value: 経済的価値、Rarity: 希少性、Imitability: 模倣困難性、Organization: 組織)を用いて分析する 48。
| 経営資源/ケイパビリティ | V: 価値 | R: 希少性 | I: 模倣困難性 | O: 組織 | 競争上の意味合い |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界的に有名なイベントブランド (例: サマーソニック, 東京ゲームショウ) | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 |
| 大規模会場の長期運営権 (例: 東京ビッグサイト) | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 |
| トップクラスの企画・演出チーム | Yes | Yes | No/Yes | Yes | 一時的〜持続的競争優位 |
| 大手スポンサーとの強固なリレーション | Yes | Yes | No/Yes | Yes | 一時的〜持続的競争優位 |
| 独自のイベントテック・プラットフォーム | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 |
| 豊富な参加者行動データと分析能力 | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 |
| 一般的なイベント運営ノウハウ | Yes | No | No | Yes | 競争均衡 |
- 持続的競争優位の源泉:
- 強力なイベントブランドやIP: 長年にわたる実績と投資によって築かれたブランドは、高い集客力とスポンサーからの信頼をもたらし、他社が容易に模倣することはできない。
- 物理的資産の独占: 東京ビッグサイトのような大規模会場の運営権は物理的に希少であり、新規参入者にとって極めて高い参入障壁となる。
- テクノロジーとデータ: 独自に開発されたイベントテック・プラットフォームや、それを通じて蓄積された膨大な参加者の行動データ、そしてそれを分析・活用する能力は、ネットワーク効果と学習効果により、後発企業が追いつくことが困難な模倣困難性の高い資源となる。
- 一時的な競争優位に留まる可能性のあるもの:
- 人的資本: カリスマ的なプロデューサーやトップクラスのクリエイティブチームは希少で価値があるが、人材の引き抜きや独立のリスクが常に伴う。組織としてノウハウを形式知化し、文化として定着させなければ、持続的な優位とはなりにくい。
- 顧客リレーション: 大手スポンサーとの長年の関係は価値があるが、担当者の異動や、より高いROIを提示する競合の出現によって失われる可能性がある。関係性をデータ基盤で補強し、組織的に管理することが重要である。
- 競争優位の源泉にならないもの:
- 一般的な運営ノウハウ: 安全管理やロジスティクスといった基本的な運営能力は、事業継続の必須条件(Valueはある)だが、多くの企業が保有しており希少性(Rarity)がないため、これだけで競争に勝つことはできない。
8.2. 人材動向:求められるスキルの変革
業界の変革に伴い、求められる人材像も大きくシフトしている。
- 求められる人材像のシフト:
- From: 従来の「運営マンパワー」「設営・調整役」。体力と経験則に頼り、決められたことを正確に実行する能力が重視された。
- To: 「デジタルマーケター」「データアナリスト」「体験デザイナー」「AI活用プランナー」。データを読み解き戦略を立て、テクノロジーを駆使して新たな体験を創造し、AIツールを使いこなして生産性を向上させる能力が求められる。
- 専門人材の需給ギャップ:
- イベントプロデューサーやテクニカルディレクターといった従来の中核人材に加え、上記のデジタル系専門人材の需要が急増している。しかし、イベント業界の業務知識とデジタルスキルの両方を兼ね備えた人材は極めて少なく、IT業界や広告業界との間で激しい人材獲得競争が生じている。この需給ギャップが、業界全体のDXを遅らせる要因の一つとなっている。
- フリーランス(個人事業主)の活用:
- 業界では、専門スキルを持つフリーランスの活用が常態化している 35。彼らはプロジェクトの繁閑に合わせた柔軟なリソース調整を可能にする重要な存在である。企業にとっては、優秀なフリーランスとのネットワークを構築し、継続的に協業できる関係性を築くことが、プロジェクトの品質を担保する上で不可欠となっている。
8.3. 従業員の賃金相場とトレンド
- 業界の賃金レベル: イベント業界(企画、制作、運営)の平均年収は、300万円〜400万円が相場とされ、日本の平均給与水準と比較して高いとは言えない 50。特に若手はアシスタント業務が中心となり、長時間労働に見合わない報酬水準が人材定着の課題となっている 3。
- 大手と中小の格差: 大手広告代理店系のイベント会社では年収1,000万円以上を目指すことも可能である一方、中小の制作会社では300万〜450万円程度が一般的と、企業規模による格差が大きい 51。
- 専門人材の賃金高騰: データアナリストやAIエンジニアといったデジタル・データ系の専門人材の賃金は、業界を問わず高騰している。イベント業界がこれらの人材を獲得するためには、IT業界やコンサルティング業界と同水準の報酬体系を提示する必要があり、従来の賃金構造の見直しが迫られている。SansanのようなIT企業では、イベント関連職でも年収763万円〜1015万円といった高水準の報酬が提示される例もある 52。
8.4. 労働生産性
- 「労働集約型」の実態: イベント業界は、プロジェクトごとの繁閑差が激しく、繁忙期には長時間労働が常態化しやすい「労働集約型」の産業構造を持つ 3。多くの業務がマニュアル化されにくく、個人の経験や調整能力に依存する部分が大きいため、労働生産性(例:従業員一人当たり売上高)は他業界に比べて低い傾向にある。
- テクノロジー導入による生産性向上の可能性: イベントテックやAIの導入は、この構造的課題を解決する鍵となる。
- 業務自動化: 問い合わせ対応、メール配信、データ集計といった定型業務を自動化することで、従業員はより付加価値の高いクリエイティブな業務に集中できる 43。
- 情報共有の効率化: クラウドベースのプロジェクト管理ツールは、社内外の多数の関係者との情報共有を円滑にし、コミュニケーションコストを削減する。
- データに基づく迅速な意思決定: 従来は会議を重ねて決定していた企画内容やマーケティング戦略を、データ分析に基づいて迅速に決定できるようになる。
これらのテクノロジー活用が、従業員一人当たりの売上高やプロジェクト当たりの利益率といった生産性指標を向上させるポテンシャルは極めて大きい。
第9章:主要トレンドと未来予測
これまでの分析を踏まえ、今後5〜10年のイベント業界を形作る主要なトレンドと、その帰結としての未来像を予測する。
9.1. サステナブル・イベントの標準化
サステナビリティは、もはや特別な取り組みではなく、イベント開催の「標準仕様(デフォルト)」となる。
- 環境負荷の可視化と削減義務: イベント開催に伴うカーボンフットプリント(CO2排出量)の測定と報告が、スポンサーや自治体から求められるようになる。廃棄物ゼロ(ゼロウェイスト)を目指した運営計画や、リサイクル・アップサイクル可能な資材の使用が標準的な調達基準となる 28。
- 認証制度とサプライチェーン全体での取り組み: サステナブル・イベントに関する国際認証(ISO 20121など)の取得が、企業の信頼性を示す指標として重要になる。また、自社だけでなく、設営会社やケータリング業者といったサプライチェーン全体での環境・社会配慮が求められるようになる。
- 地域社会への貢献: イベントの経済効果を地域に還元するだけでなく、地域の文化振興や社会課題解決に貢献するプログラムを組み込むことが、開催意義を高める上で不可欠となる。
9.2. 「没入型(Immersive)」と「インタラクティブ」の極致
テクノロジーの進化は、参加者の体験をより深く、能動的なものへと進化させる。
- 五感を刺激する体験設計: VR/AR/MR、プロジェクションマッピング、触覚技術、立体音響、さらには香りなどを組み合わせ、参加者を完全に物語の世界に没入させる体験型コンテンツが主流となる 37。PCMAの調査でも、参加者の64%が「没入型体験」を最も重要な experiential element と回答している 54。
- 参加者主導のストーリー展開: 参加者の選択や行動によって、イベントの展開や結末が変化するインタラクティブな設計が一般化する。これにより、参加者は単なる観客ではなく、物語の主人公としての当事者意識を持つことになる。
9.3. イベントの「常時接続(Always-On)」化
イベントの価値は、開催期間中だけのものから、年間を通じた継続的なエンゲージメントへと拡張される。
- 「点」から「線」へのビジネスモデル転換: 単発のイベント開催(点)で関係が途切れるのではなく、イベントをきっかけに形成されたコミュニティをオンラインプラットフォーム上で維持・育成し(線)、年間を通じて情報交換やネットワーキングが行われる場を提供するビジネスモデルへ移行する 55。
- コミュニティが新たな収益源に: この「常時接続」コミュニティは、限定コンテンツの提供やサブスクリプションモデル、あるいは年間を通じたスポンサーシップなど、イベント本体とは別の新たな収益源となる。
9.4. eスポーツとメタバース:新たなフロンティア
デジタルネイティブ世代を惹きつける新たな領域が、大規模イベント市場として確立される。
- eスポーツ市場の拡大: eスポーツは、若年層を中心に巨大なファンベースを持つ一大エンターテインメントとして成長を続ける。プロリーグの大会は、数万人規模のアリーナを満員にする大規模イベントとなり、放映権やスポンサーシップを含めた市場規模はさらに拡大する 13。
- メタバースイベントの可能性と課題: メタバース空間におけるバーチャルイベントは、物理的な制約を超えたグローバルな参加と、現実では不可能な演出を可能にするポテンシャルを持つ。しかし、現状では高品質な体験を提供するためのデバイス(VR HMDなど)の普及率や、セキュリティ、法整備などが課題として残る 58。当面は、リアルイベントを補完するハイブリッド型での活用が中心となるだろう。
9.5. M&Aと業界再編の加速
テクノロジーとデータの重要性が高まる中、業界の垣根を越えたM&Aが活発化し、競争地図が塗り替えられる。
- テクノロジー企業によるイベント会社の買収: AI、データ分析、VR/ARなどの技術を持つ企業が、リアルな顧客接点とコンテンツを持つイベント会社を買収し、自社技術の応用先を確保する動きが加速する。NTTドコモによるVRイベント企業HIKKYへの出資はその一例である 14。
- イベント会社によるテクノロジー企業の買収: 逆に、大手イベント会社が、自社のDXを加速させるために、専門性を持つイベントテック・スタートアップを買収する動きも活発化する。
- 業界内での合従連衡: 厳しい競争環境と後継者問題などを背景に、専門領域の異なるイベント会社同士が合併し、総合力を高める動きも増えるだろう。
第10章:主要プレイヤーの戦略分析
日本のイベント業界における主要プレイヤーをカテゴリー別に分類し、各社の戦略、強み・弱み、テクノロジーへの投資状況を比較分析する。
10.1. 大手広告代理店系
- プレイヤー: 電通グループ(電通ライブなど)、博報堂DYグループ(博報堂プロダクツなど)
- 戦略: ナショナルクライアントとの強固な関係を基盤に、マーケティング戦略全体の一部としてイベントを位置づけ、企画からメディア展開までをワンストップで提供する「統合ソリューション」を志向。
- 強み:
- 圧倒的な顧客基盤と営業力。
- テレビCMなど他メディアと連動させた大規模なプロモーション展開能力。
- 国家的・国際的な大型イベント(オリンピック、万博など)の豊富な実績とノウハウ。
- 弱み:
- 組織が巨大であるため、意思決定のスピードやコスト面で中小の専門会社に劣る場合がある。
- 従来のマスマーケティング発想が強く、データ活用やパーソナライゼーションといったデジタルトランスフォーメーションへの対応が課題となる可能性がある。
- テクノロジー投資: 電通ライブは、新しいビジネスを創出する「ビジネスクリエーションユニット」を設立し、独自のベニューマッチングプラットフォーム「VENUE LINK」を開発するなど、自社発のテクノロジー開発にも注力している 60。
10.2. 大手専門会社(企画・設営)
- プレイヤー: 丹青社、乃村工藝社、TSP太陽、フロンティアインターナショナル
- 戦略: 「空間創造」のプロフェッショナルとして、展示会、商業施設、文化施設などのデザイン・施工における高い専門性を核に事業を展開。近年は、デジタル技術を融合させた体験価値の向上や、サステナビリティへの対応を強化。
- 強み:
- 長年の経験に裏打ちされた、高品質な空間デザイン、設営・施工能力。
- 博物館や企業ショールームなど、常設展示で培ったコンテンツ制作力。
- TSP太陽は、防災・防疫ソリューションを事業の柱の一つとし、社会課題解決型のビジネスモデルを構築している 61。
- 弱み:
- 事業が設営・施工に偏重している場合、デジタルマーケティングやデータ分析といった領域のケイパビリティが不足する可能性がある。
- テクノロジー投資: フロンティアインターナショナルは、「エクスペリエンス・トランスフォーメーション」を掲げ、デジタルマーケティングを強化し、「リアル×デジタル」のO2Oフレームを推進している 63。
10.3. 外資系・グローバル
- プレイヤー: Live Nation, Informa, RX (Reed Exhibitions)
- 戦略: グローバルなネットワークとブランド力を活かし、世界標準のフォーマットで大規模な国際展示会や音楽ツアーを各国で展開。M&Aを積極的に活用し、各地域での事業基盤を拡大する。
- 強み:
- 世界中の出展企業や参加者を動員できるグローバルなネットワークとデータベース。
- Live Nationは、傘下のTicketmasterの膨大な顧客データを活用したデジタルマーケティングに強みを持つ 65。
- RX Japanは、「資産運用 EXPO」や「Femtech Tokyo」など、時代のニーズを先読みした新規展示会の立ち上げ能力に長けている 67。
- 弱み:
- グローバルで標準化されたフォーマットが、日本の独自の商習慣や文化に必ずしも適合しない場合がある。
- テクノロジー投資: Live Nationはマーケティング予算の80%をデジタルに投下し、ビッグデータ分析を駆使している 65。RX Japanもサイバーエージェントと組み、Webマーケティング戦略の改革やAIを活用したクリエイティブ制作に取り組んでいる 68。
10.4. MICE・会場運営
- プレイヤー: 東京ビッグサイト、幕張メッセ、パシフィコ横浜、コングレ
- 戦略: MICE誘致のハブとして、施設のハード面(規模、設備)の魅力を高めると同時に、主催者を支援するソフト面のサービスを強化。サステナビリティやDXへの対応を推進し、施設の付加価値を高める。
- 強み:
- 代替の難しい大規模な物理的資産を保有。
- 長年の運営で蓄積されたMICE誘致・開催ノウハウ。
- 弱み:
- 施設の稼働率が景気や大規模イベントの有無に大きく左右される。
- 自らがコンテンツを企画する能力は、企画会社に比べて限定的。
- テクノロジー投資: パシフィコ横浜は、施設利用申込のDX化やローカル5Gの実証実験、サステナビリティ対応(CO2排出量実質ゼロ化)などを積極的に推進している 69。コングレは、日本で初めてISO20121(イベントサステナビリティ)認証を取得し、「サステナブルMICE」を強力に推進している 71。
10.5. イベントテック・プラットフォーマー
- プレイヤー: EventHub, Sansan (EventRegist), ぴあ, イープラス
- 戦略: イベントの企画から事後分析までを一元管理できるSaaSプラットフォームを提供し、業界のDXを支援。データ活用を軸に、リード獲得や商談創出といった顧客のビジネス成果に貢献することを目指す。
- 強み:
- テクノロジー開発力と、スケーラブルなビジネスモデル。
- EventHubは、ウェビナーからリアル展示会まで対応する統合プラットフォームとして、商談化率向上などの実績を上げている 72。
- Sansanは、名刺管理サービスとの連携を活かし、オンライン名刺を活用したスムーズなイベント参加登録「Smart Entry」などを提供 74。
- ぴあは、チケット販売を核に、コンテンツ制作、メディア、アリーナ運営(ぴあアリーナMM)までを手掛ける垂直統合モデルを構築している 75。
- 弱み:
- プラットフォームの提供が主であり、個別のイベントの深い企画・演出ノウハウは持たない場合が多い。
- テクノロジー投資: AI、データ分析、MAツールとの連携などが投資の中心。事業そのものがテクノロジーであるため、継続的なR&Dが生命線となる。
10.6. 異業種参入
- プレイヤー: 旅行会社(JTB, H.I.S.)、IT企業
- 戦略: 自社の既存事業(旅行手配、ITソリューション)とのシナジーを追求。旅行会社はMICE参加者の交通・宿泊手配までをワンストップで提供することで付加価値を生み出す。
- 強み:
- JTB、H.I.S.は、国内外の広範なネットワークと、ロジスティクス手配における圧倒的なノウハウを持つ 32。
- 弱み:
- イベント専門の企画・演出力や、最新のイベントテックに関する知見が不足している可能性がある。
第11章:戦略的インプリケーションと推奨事項
これまでの包括的な分析を統合し、取るべき具体的な事業戦略を提言する。
11.1. 勝者と敗者を分ける決定的な要因
今後5〜10年で、イベント業界の勝者と敗者を分ける決定的な要因は、以下の3つの能力に集約される。
- データ・ケイパビリティ: イベントを通じて得られる膨大な行動データを収集・分析し、それを「パーソナライズされた体験の提供」と「スポンサーへのROI証明」に繋げられるか。データを制する者が、顧客と予算を制する。
- AIアダプティブ能力: 生成AIをはじめとするAI技術を、単なる効率化ツールとしてではなく、ビジネスモデルの中核に据え、企画から運営までの全プロセスを再構築できるか。AIを使いこなす組織文化と人材を育成できる企業が、圧倒的な生産性と競争力を手にする。
- 体験創造力: テクノロジーがコモディティ化する中で、最終的に差別化の源泉となるのは、テクノロジーを駆使して、人の心を動かす唯一無二の「没入型体験」や、持続的な「コミュニティ」を創造できるかという、人間ならではのクリエイティビティと構想力である。
これら3つの能力を統合し、「データ駆動型の体験創造企業」へと変革できた企業が勝者となり、従来の労働集約的な運営モデルに固執する企業は敗者として市場から淘汰されるだろう。
11.2. 機会(Opportunity)と脅威(Threat)
- 捉えるべき機会(Opportunity):
- BtoBデータソリューション市場: ROI可視化への強いニーズを捉え、単なるイベント運営代行から、データ分析に基づくマーケティング・コンサルティングサービスへと事業を進化させる。
- 高付加価値な体験市場: 「コト消費」「推し活」需要を背景に、VR/ARなどの技術を活用した没入型エンターテインメントや、熱量の高いコミュニティを核としたプレミアムイベント市場を開拓する。
- AIによる生産性革命: AIを全社的に導入し、抜本的なコスト削減と業務効率化を実現することで、価格競争力を高め、捻出したリソースを新たな価値創造へ再投資する。
- 備えるべき脅威(Threat):
- テクノロジー・プラットフォーマーによるディスラプション: イベントテック企業や大手ITプラットフォーマーが、データと技術力で業界の主導権を握り、従来の企画・運営会社が下請け化するリスク。
- 人材の陳腐化と流出: デジタルスキルやデータ分析能力を持たない既存人材のスキルが陳腐化し、市場価値を失うリスク。同時に、希少なデジタル人材はIT業界など他業界との獲得競争に敗れ、流出が続くリスク。
- コスト構造の悪化: 人件費や資材費の高騰が継続し、テクノロジーへの投資も重なることで、利益率が構造的に低下するリスク。
11.3. 戦略的オプションの提示と評価
取り得る主要な戦略的オプションを3つ提示し、それぞれのメリット・デメリット、成功確率を評価する。
| 戦略的オプション | メリット | デメリット | 成功確率(評価) |
|---|---|---|---|
| A: 総合フルサービスモデルの維持・強化 | ・既存の顧客基盤とブランド力を維持できる ・あらゆるニーズに対応できるため、大型案件を獲得しやすい | ・経営資源が分散し、専門性が希薄化する ・各分野のスペシャリスト(特にテック企業)との競争で劣後する ・組織変革のスピードが遅くなりがち | 低 |
| B: 特定分野特化型スペシャリストへの転換 | ・特定領域(例: AI×BtoBテックイベント, eスポーツ)で圧倒的な専門性とブランドを確立できる ・高い利益率を確保しやすい ・経営資源を集中投下できる | ・市場がニッチな場合、成長に限界がある ・市場環境の変化に脆弱な可能性がある ・総合的な提案を求める大手クライアントを失うリスク | 中〜高 |
| C: テック企業とのM&A/アライアンスによる事業変革 | ・自社にない技術力・データ基盤を迅速に獲得できる ・「体験創造力×テクノロジー」のシナジーを創出できる ・新たなビジネスモデルを構築し、業界のゲームチェンジャーとなり得る | ・M&A後の組織文化の統合(PMI)が難しい ・買収には多額の資金が必要 ・アライアンスの場合、主導権を相手に握られるリスク | 高 |
評価の結果、現状維持の「総合フルサービスモデル」は、リソースの分散と競争の激化により、長期的にはジリ貧となる可能性が高い。一方で、「特定分野特化」と「M&A/アライアンス」は、いずれも高い成長ポテンシャルを持つが、業界全体の構造変化に対応し、ゲームチェンジャーとなるためには、オプションBとCを組み合わせたハイブリッド戦略が最も有効であると結論づける。
11.4. 最終戦略提言とアクションプラン
提言:『データ駆動型体験創造企業』への変革を、AI活用と戦略的M&Aによって加速せよ
戦略の核心:
自社の強みである「企画・演出力」を活かせる「BtoB向け高付加価値イベント」と「BtoC向け没入型エンターテインメント」の2領域に事業を特化(オプションB)。そして、その実行基盤として不可欠な「データ分析・AI活用能力」を、イベントテック企業のM&Aによって獲得する(オプションC)。この両輪によって、単なるイベント会社から脱却し、業界をリードする「データ駆動型体験創造企業」へと変革を遂げる。
アクションプラン概要:
- Phase 1: 基盤構築(初年度)
- KPI: AI導入による企画・マーケティング業務の工数30%削減、M&Aターゲットリストの策定完了。
- アクション:
- 全社的なAIリテラシー向上研修の実施。
- 企画・マーケティング部門への生成AIツールの導入と活用プロセスの標準化。
- M&A専門チームを組成し、買収候補となるイベントテック企業(データ分析、AIマッチング等に強み)のロングリスト・ショートリストを作成、初期接触を開始。
- 不採算・非注力領域のイベント事業からの段階的撤退計画を策定。
- Phase 2: 統合と事業モデル転換(2〜3年目)
- KPI: M&Aの実行、統合データプラットフォームの構築完了、データソリューション事業の売上構成比5%達成。
- アクション:
- イベントテック企業のM&Aを実行し、PMI(経営統合プロセス)を開始。
- 買収した企業の技術基盤と自社のイベント運営データを統合し、全社的なデータプラットフォームを構築。
- スポンサー向け「ROI可視化ダッシュボード」を新サービスとして提供開始。
- VR/AR技術を持つ企業との協業による、没入型エンタメコンテンツのパイロットプロジェクトを実施。
- Phase 3: 成長の加速(4〜5年目)
- KPI: データソリューション事業の売上構成比15%達成、没入型エンタメ事業の黒字化。
- アクション:
- データプラットフォームを外部にも提供するPaaS(Platform as a Service)事業の検討を開始。
- 成功した没入型エンタメコンテンツを自社IPとしてシリーズ化、グローバル展開を視野に入れる。
- AIによる需要予測に基づいた、新たなイベントブランドの立ち上げ。
AI導入ロードマップ:
- Year 1: 生成AIの導入(企画書、コピー、画像生成)、AIチャットボット(問い合わせ対応)。
- Year 2: AI搭載MAツールの本格導入(パーソナライズドマーケティング)、AIマッチングシステムの導入。
- Year 3-5: 統合データプラットフォーム上でのAI分析機能の強化(需要予測、ROI自動算出)、運営最適化AI(混雑予測など)の導入。
この戦略を実行することで、短期的な生産性向上とコスト削減を実現しつつ、中長期的にはデータとテクノロジーを収益の柱とする、持続可能な成長モデルを確立することができる。
第12章:付録
引用文献
- 2024 年 イベント産業規模推計 – 日本イベント産業振興協会, https://www.jace.or.jp/news/20250619/
- 2023 年 イベント産業規模推計, https://www.jace.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/a60d0f86738a0b8326aa54569ba64391.pdf
- イベント業界はやばいって本当?現場のリアルと続ける理由を解説 – 職人BASE, https://shokunin-base.com/blog/dk18-event-career-tips-20250828/
- 【2025年最新】イベント開催費用の相場とは?内訳や費用削減のアイディアを紹介, https://cloud-pass.info/event-holding-cost/
- 市場調査レポート: 世界のイベント産業市場、2025~2029年, https://www.gii.co.jp/report/infi1626791-global-events-industry-market.html
- 2025年のイベントマーケティング:知っておきたい40の重要統計データ – Thunderbit, https://thunderbit.com/ja/blog/event-marketing-statistics
- 展示会市場規模とシェア、統計レポート 2024-2032 – Global Market Insights, https://www.gminsights.com/ja/industry-analysis/exhibition-market
- マウスの市場規模、シェア、成長|業界レポート[2032], https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/mice%E5%B8%82%E5%A0%B4-108653
- 国内ライブエンタメ市場過去最高の6857億円、音楽フェスも過去最大, http://animationbusiness.info/archives/15962
- 2024年のライブ・エンタメ市場は過去最多の動員数6,000万人 市場 …, https://www.musicman.co.jp/business/667254
- 【速報】 2023 年スポーツマーケティング基礎調査, https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/10/news_release_231030_01.pdf
- 年平均成長率10.5%で拡大【市場規模・シェア・トレンド分析】 – NEWSCAST, https://newscast.jp/news/3068591
- eスポーツの市場と推移 | 一般社団法人日本eスポーツ協会 …, https://jesu.or.jp/contents/about-market/
- イベント会社のM&A動向と売却事例、売却価格相場を詳しく解説 …, https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-9455
- 2024年日本の総広告費は7兆6730億円、4年連続で成長【電通調べ …, https://www.massmedian.net/news/view/1120
- 【おでかけ&グルメ】Z世代に人気の体験型施設|コト消費とSNSがキーワード!話題の“イマーシブ”もピックアップ – 株式会社トランス, https://www.trans.co.jp/column/trend/generation_z_experiential_facility/
- 【Z世代は何を考えて消費活動をするのか?】若者たちの消費傾向を …, https://gtoe.info/post_zblog/z%E4%B8%96%E4%BB%A3%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E6%B6%88%E8%B2%BB%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/
- Event Management Software Market Size & Share Analysis – Industry Research Report – Growth Trends 2030 – Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/event-management-software-market
- 15 年に注目すべきイベント業界の 2025 の新しいトレンド – Time.ly, https://time.ly/ja/blog/%E5%BF%85%E8%A6%8B%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89/
- イベント業界とは?市場規模や職種、課題と将来性について解説, https://eventlife.ikusa.jp/column/20250530191
- PCMA Survey: Ongoing Challenges in a Robust Meetings Market, https://www.prevuemeetings.com/news/pcma-survey-ongoing-challenges-in-a-robust-meetings-market/
- 【安全基準とは?】イベント用語辞典 – ビジプリ, https://visipri.com/event-dictionary/1478-SafetyStandards.php
- 展示会搬入搬出等安全ガイドライン, https://www.nittenkyo.ne.jp/media/works/items/1726/download
- MICEとは | MICE の推進 | インバウンド回復戦略 | 観光政策・制度 | 観光庁 – 国土交通省, https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/mice/micetoha.html
- MICE誘致 – 行政情報ポータル, https://ai-government-portal.com/mice%E8%AA%98%E8%87%B4/
- 持続可能な観光立国の実現に向け、経団連が提言を公表 | 訪日ラボ, https://honichi.com/news/2025/10/23/keidanren/
- コロナからの大逆転~テーマパークの動向~|その他の研究・分析レポート – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20251024hitokoto.html
- サステナビリティイベントとは?開催のためのポイントや注意点を …, https://event.jtbcom.co.jp/topics/post-2842/
- サステナブルなイベントを開催する方法は?環境への配慮が重要! – 株式会社トーガシ, https://www.tohgashi.co.jp/magazine/sustainable_event/
- 世界のイベント産業市場 2031年の市場規模2.3兆米ドル、年平均成長率(CAGR)6.4%の成長予測 – PressWalker, https://presswalker.jp/press/66802
- 自然災害時のイベント開催中止の判断と周知方法について – 田辺市, https://www.city.tanabe.lg.jp/jinken/sizensaigai.html
- MICE – コンサルティング・調査 – JTB総合研究所, https://www.tourism.jp/consulting/sector/mice/
- 企業イベント・社内イベント 成功事例やアイデアを紹介|HIS, https://www.his-j.com/corp/businessevent/
- 【TOPPAN物流DXセミナー】物流課題を解決へ導く!データ主導のサプライチェーン最適化と補助金活用による現場効率化, https://solution.toppan.co.jp/seminar/detail/logiseminar_250820.html
- イベントディレクターの年収は高い?仕事内容や収入をあげる方法もご紹介 – 職人BASE, https://shokunin-base.com/blog/event-director-annual-income-20240422/
- イベント業でフリーランスは食えるのか?年収や日々の業務内容を解説【フリーのディレクター】, https://event-academy.com/articles/free_director
- イマーシブとは?エンタメ業界注目の没入・体験型イベントの事例を紹介 – トランス, https://www.trans.co.jp/column/oshikatsu/immersive/
- イマーシブ(没入体験)イベントの演出事例:深い価値体験づくり, https://www.seiko-giken.jp/mist-production/blog/examples-of-immersiveproduction
- イベント業界の生成AI活用法|集客効果30%増の実例 – note, https://note.com/ai_komon/n/n0278b89b6901
- 生成AIの活用事例14選!生成AIの導入を成功させるポイントやおすすめツールも紹介 – freeconsultant.jp for Business – みらいワークス, https://mirai-works.co.jp/business-pro/business-column/generative-ai-case-study
- 生成AIの面白い活用事例12選!ビジネスからエンタメ、ゲーム、公共サービスまで, https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/ai-usage-examples-interesting/
- AI活用のマーケティングツール16選!選び方や注意点も解説 – GMO TECH, https://gmotech.jp/semlabo/webmarketing/blog/ai-marketingtool/
- MAツールにAIは必要か?その可能性と限界を考える – ブログ, https://www.saaske.com/blog/sales/ma-tool-ai/
- AIマーケティングツールのおすすめ10選!導入メリットやポイント、役立つツールを紹介 – Braze, https://www.braze.com/ja/resources/articles/10-leading-ai-marketing-tools-to-save-time-and-money-and-increase-revenue
- マーケティングでのAI活用術とメリット、効率化ツール例を紹介 – bizboost, https://blog.bizboost.co.jp/ai-in-marketing-benefits-tools
- 広告業界における生成AIの活用事例15選!制作時間短縮やROI向上など | ニューラルオプト, https://neural-opt.com/ad-generative-ai-cases/
- AIのROIに関する課題を解決するのは容易ではない | PwC Japanグループ, https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/dataanalytics/artificial-intelligence-roi.html
- VRIO分析とは?VRIO分析の考え方や具体的な事例をわかりやすく解説 – bizboost, https://blog.bizboost.co.jp/what-is-vrio-analysis-and-how-it-works
- VRIO分析とは?やり方や具体例、メリット・デメリットをわかりやすく解説 – sonar ATS, https://sonar-ats.jp/column/other-4008/
- イベントプランナーの年収、給料、給与は!? – 東京コミュニケーションアート専門学校, https://www.tca.ac.jp/job/entertainment/eventplanner/salary.html
- イベントプランナーの実態に迫る!年収・給料・働き方を徹底解説 …, https://www.kotora.jp/c/66550/
- イベントプロデューサー / Sansan株式会社 – Talentio, https://open.talentio.com/r/1/c/sansan/pages/76655
- イベント現場のスタッフ労務管理とは?重量なポイントを解説 …, https://pro-cas.jp/column/20250415-01/
- Trends Report 2025: Will Event Tech Costs Fuel Low-Tech Options? – PCMA, https://www.pcma.org/trends-report-2025-will-event-tech-costs-fuel-low-tech-options/
- コミュニティマーケティングの成功事例メリット・デメリットや …, https://www.dnp.co.jp/biz/column/detail/20172063_4969.html
- 第5章 自立的・継続的に事業を 進めるためのビジネスモデル, https://www.chisou.go.jp/sousei/about/ccrc/daigo.pdf
- 世界で、日本で急成長している「eスポーツ」ってなんだ? | Discover DNP, https://www.dnp.co.jp/media/detail/20168780_1563.html
- メタバースを活用したイベントの事例9選!開催メリットや課題・対策も解説 – Cultive(カルティブ), https://sp-cultive.com/blog/article-137/
- 広がるメタバースのビジネス活用 期待と課題を探る – NTT技術ジャーナル, https://journal.ntt.co.jp/article/21685
- 株式会社電通ライブ-未来をもっと面白く『マスナビ』, https://www.massnavi.com/company/20015149.html
- SDGsにおける事業戦略|TSP太陽株式会社, https://www.tsp-taiyo.co.jp/company/sustainable/business/
- サステイナブル|TSP太陽株式会社, https://www.tsp-taiyo.co.jp/company/sustainable/
- フロンティアインターナショナルが事業計画及び成長可能性に関する事項(2024年7月)を発表, https://altvega.com/frontieri-bg-20240731/
- 株式会社フロンティアインターナショナルの会社情報 | M&Aクラウド, https://macloud.jp/companies/20284
- ライブ・ネイションCEOが語る、ライブ市場で勝つ戦略「マーケティングの80%はオンラインに投下した」 | Musicman, https://www.musicman.co.jp/column/20851
- LiveNation-世界最強の音楽イベント会社は、なぜ強いのか? – note, https://note.com/wackiix/n/n660f575684b5
- OUR VALUE|RX Japan 2026 Recruitment, https://www.rxjapan.jp/recruiting/value
- 展示会業界のリーディングカンパニー RX Japan社とともに歩むWebマーケティング戦略の改革、常駐による密なコミュニケーションでCPA目標対比120%を実現 | WORKS | サイバーエージェント インターネット広告事業「CyberAgent AD.AGENCY」, https://www.cyberagent-adagency.com/works/810/
- 臨港パーク関連施設 – 年間事業計画書 – 横浜市, https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/kaku-katsuyou/kowan/default20230201.files/rinpa_r6_keikaku.pdf
- P F I ・コンセッション方式導入に係る啓発資料, https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001874876.pdf
- Untitled – 株式会社コングレ, https://www.congre.com/assets/PDF/Congres_SustainabilityReport_2024view.pdf
- 【EventHub活用事例】ウェビナー開催数4倍、商談化率1.2倍を実現したREHATCH株式会社のウェビナー戦略を支援 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000031178.html
- EventHubがREHATCH社の成功事例ウェビナーを開催、ファネル戦略で受注を最大化 – trends, https://trends.codecamp.jp/blogs/media/news1128
- Sansanのイベントテック事業がもたらすシナジー効果 運営・管理・登録・参加の「新常識」とは?, https://logmi.jp/brandtopics/323394
- 事業紹介|ぴあ株式会社, https://corporate.pia.jp/business/
- DeepResearch追加指示.txt
- 経済産業省 特定サービス産業動態統計調査の終了(オンライン回答は2月末日まで)について, https://www.e-survey.go.jp/survey_Infomation/1740
- 特定サービス産業動態統計調査 – 経済産業省, https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/index.html
- Global Exhibition Industry Statistics – UFI.org, https://www.ufi.org/industry-resources/research/global-reports/global-exhibition-industry-statistics/
- UFI releases a new set of global exhibition industry statistics – UFI.org, https://www.ufi.org/mediarelease/ufi-releases-a-new-set-of-global-exhibition-industry-statistics/
- Global Exhibition Industry Statistics (May 2025) – UFI.org, https://www.ufi.org/archive-research/global-exhibition-industry-statistics-may-2025/
- MICE産業の市場規模、トップシェア、2033年までの成長動向予測 – Straits Research, https://straitsresearch.com/jp/report/mice-industry-market
- MICE市場規模、シェア、主要トレンド、2032年 – consumergoodsindustryのブログ – ムラゴン, https://consumergoodsindustry.muragon.com/entry/163.html
- PEST分析とは?目的ややり方・フレームワークを事例つきで解説 – Salesforce, https://www.salesforce.com/jp/blog/jp-pest-analysis/
- PEST分析の基本と実践!テンプレートを使った具体例と成功のコツを解説, https://ferret-one.com/blog/pest
- 「日本の広告費」の媒体別の推移グラフまとめ【2024年版】 – メディアレーダー, https://media-radar.jp/contents/meditsubu/ad_cost/
- EdgeTech+ 2025 | 生成AIで進化する開発現場。ものづくりは『AIと創る』新時代へ, https://www.jasa.or.jp/expo/
- 5F(ファイブフォース)分析とは? | ダイレクトマーケティングラボ | リコー, https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/g00035/
- ファイブフォース分析を解説: 競争要因からビジネス戦略を立てる方法 – Asana, https://asana.com/ja/resources/porters-five-forces
- ファイブフォース(5F)分析とは?業界別の事例を交えて徹底解説! – 仕組み化ブログ, https://libru-blog.com/strategy/framework-5f/
- イベント産業を取り巻く社会動向とリスクマネジメント – 東京海上ディーアール株式会社, https://www.tokio-dr.jp/publication/report/riskmanagement/pdf/pdf-riskmanagement-114.pdf
- バリューチェーンとは?分析方法・サプライチェーンとの違い・事例などをわかりやすく紹介, https://prtimes.jp/magazine/value-chain/
- 【2025年最新】バリューチェーンとは?構成要素やサプライチェーンとの違い、分析方法を徹底解説, https://www.koukoku.jp/service/suketto/marketer/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%88%A6%E7%95%A5/%E3%80%902025%E5%B9%B4%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%80%91%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%A7%8B%E6%88%90%E8%A6%81%E7%B4%A0%E3%82%84/
- バリューチェーンとは?分析のステップやメリット、業界別の先行事例をわかりやすく解説, https://monstar-lab.com/dx/about/about-value-chain/
- 【事例3選】フリーランス×地方創生 | Otanomi(オタノミ), https://o-tanomi.jp/specials/127
- KBF/KSFとは?ビジネス成功のカギを見つけよう! | ダイレクトマーケティングラボ | リコー, https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/g00057/
- KBF(購買決定要因)とは?決め方やKSFとの違い、Web 広告での活用方法, https://www.kwm.co.jp/blog/kbf/
- 電通、プロモーション領域強化に向け新会社の設立と事業再編 ― 体験価値創造ビジネスとデジタル起点型プロモーションで成長戦略を加速へ ― – News(ニュース) – 電通ウェブサイト, https://www.dentsu.co.jp/news/release/2016/1014-009064.html
- Integrated Report – 2024 – 博報堂DYホールディングス, https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/assets/pdf/csr/2024/csr2024.pdf
- 株式会社丹青社, https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240425/20240417572071.pdf
- 【丹青社ニュースレター2024.3】中期経営計画策定 社長インタビュー – 共同通信PRワイヤー, https://kyodonewsprwire.jp/release/202403057533
- 丹青社【9743】のリスク・方針 – キタイシホン, https://kitaishihon.com/company/9743/management-strategy
- 乃村工藝社/コロナにより大型案件の完工が減少 – ログミーFinance, https://finance.logmi.jp/articles/376288
- 新中期経営計画発表会をプロデュース – 株式会社タノシナル, https://tanoshinal.com/works/1909/
- 「日本のライブ・エンターテイメント産業の進化と可能性」レポート – GEM Standard, https://www.gem-standard.com/columns/1022
- インフォーマ マーケッツ ジャパン(株)と横浜市が 「海洋都市横浜の実現に関する連携協定, https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/seisaku/2024/1010_Informakyotei.files/0011_20241009.pdf
- InformaTechのデジタルビジネスとの戦略的統合を通じて、B2Bデータおよび市場アクセスにおける規模とリーダーシップの地位を拡大します。TechTargetの株主は、1株あたり約11.79ドルの現金を受け取り – ウィブル証券, https://www.webull.co.jp/news-detail/10041139136720896
- インフォーママーケッツジャパンの企業情報 | CFN(CareerForum.Net), https://careerforum.net/ja/event/tks/companylist_626/5316/company_detail/
- 使命を実現するためのビジネスモデル|RX Japan 2026 Recruitment, https://www.rxjapan.jp/recruiting/business_02
- 7. 東京ビッグサイトの計画の目的及び内容, https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/docs/7_%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%85%E5%AE%B91.pdf
- 一般事業主行動計画|会社概要 – 東京ビッグサイト, https://www.bigsight.jp/visitor/company/about/actionplan.html
- 株式会社EventHub 様 – セレブリックス, https://www.eigyoh.com/case/51
- 活動分析 | ユーザー向け活用ナビサイト【Sansan Innovation Navi】, https://sin.sansan.com/map/sales-analysis/
- 狙うのは“ビジネスイベントに来ない層” Sansanが見出したブルーオーシャンなビジネスイベントの形, https://markezine.jp/article/detail/45755
- SDGsイベント事例7選!基礎知識と実施メリットの解説! – GLOBAL PRODUCE, https://www.global-produce.jp/gpjournal/sustainability/sdgs-event/
- 世界のM&A 業界別動向:2024年の見通し | PwC Japanグループ, https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/dealsinsights/deals-trends2024.html
- 【公式】TLT株式会社, https://tlt.company/
- 心に響かせ、記憶に刻む。Meetings & Events – JTB法人サービス, https://www.jtbbwt.com/meetings-and-events/
- 公社等外郭団体の改革方針(案) 団体名 (株)幕張メッセ 所管所属名 商工労働部経済政策課, https://www.pref.chiba.lg.jp/gyoukaku/shingikai/gyouseikaikaku/2011/documents/siryou4-2-20.pdf
- 資料2 – 千葉県, https://www.pref.chiba.lg.jp/gyoukaku/shingikai/gyouseikaikaku/2009/6-gaiyou/documents/siryou2.pdf
- 健康経営 | 働き方・働く環境 – 株式会社コングレ, https://www.congre.com/recruit/work-style/health/
- 成長戦略|財務・業績情報 – ぴあ株式会社, https://corporate.pia.jp/ir/individual/strategy/
- ビジョン – 株式会社イープラス, https://corp.eplus.jp/vision/index.html
- OUR SERVICE 事業紹介 – 株式会社イープラス, https://corp.eplus.jp/service/index.html
- 海外企業のインセンティブ旅行を日本へ!可能性と誘致のポイント|JCD NOW!, https://www.jtbcom.co.jp/article/chiiki/1311.html
- 特集1 “MICE“とは何か 守屋 邦彦 – 観光文化, https://www.jtb.or.jp/tourism-culture/bunka262/262-01/
- H.I.S.のデジタルマーケティング戦略に学べ!競合他社の中で生き残るためのSNS活用術, https://fungry.co.jp/cnaps/blog/his-degital-marketing-strategy/
- HIS、MICE事業の強化でイベント系5社と業務提携、訪日の報奨旅行も積極展開へ, https://www.travelvoice.jp/20190402-128736
- イベント・マネージャーのためのAIスタートアップ:イベント主催を簡素化する方法, https://eventory.jp/news/event-dx/
- 自動化とAIによってキャンペーン作成を効率化する – HubSpot, https://www.hubspot.jp/use-case/maximize-efficiency-ai-automation
- 2025年、イベント運営を円滑にするAIツール9選 – ClickUp, https://clickup.com/ja/blog/105987/ai-tools-for-event-management
- 業務効率を改善する生成AIツール紹介50選 – (株)LIFE PEPPER, https://www.lifepepper.co.jp/other/incluseiseiai/
- イベント企画に最適なAIツール10選(2025年XNUMX月) – Unite.AI, https://www.unite.ai/ja/best-ai-tools-for-event-planning/
- 生成AIで変わる業務効率化|法人向け|ソフトバンク, https://www.softbank.jp/biz/solutions/generative-ai/work-efficiency/
- 【2025年最新】AI業務効率化の完全ガイド|大手企業5社の成功事例から学ぶ失敗しない導入の3ステップ – 事業内容, https://service.aainc.co.jp/sherpa-ai/article/ai-business-efficiency-guide
- 【業界別】AIの活用事例21選|導入するメリット・デメリットも解説 – Salesforce, https://www.salesforce.com/jp/blog/jp-ai-casestudy/
- Appier (エイピア) 主催「エージェント型AI」イベントレポート:ROI向上を追求する!最新AIマーケティングソリューション公開 – PR TIMES, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000025921.html